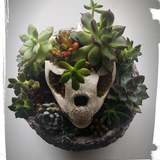悪は存在しないのレビュー・感想・評価
全78件中、1~20件目を表示
侵入者≒「他者」の受容と拒絶
石橋英子さんから濱口監督へライブパフォーマンス用映像の制作依頼がきっかけでつくられた本作。映像イメージの使用のみを想定してか、1ショットでのカメラワークや劇が実験/挑戦的で面白くて凄い。1ショットでの長回しは『親密さ』での明けの散歩シーンなどで印象的だが、強度がさらに強まっている。学童からの車の移動のショットとか、巧と花の山を歩くショットとか、巧と高橋の薪を割るショットとか凄すぎでしょ!!!本当にみているだけであっと驚かされる。役の練度がそのままカメラに撮られーつまり準備が凄いー、それをみるだけで十分面白いと思えるんです。
さて、本作は自然と人間の二項対立による濱口監督のエコロジー論が語られるのかと勝手に予測していたが全然違った。どのように〈私〉は侵入者≒「他者」を拒絶し、受け入れられるのかが主題系をなしているように思われる。菊池葉月さんや渋谷采郁さんがキャスティングされていることもあり、『ハッピーアワー』の主題系がリフレインされている印象だ。
その他者とは、まず主人公の巧らが生活する長野県・水挽町にグランピングを建設しようしている高橋と黛だ。二人は地域住民に対して説明会を開き、事業の推進を目指して説明をする。しかしその説明は、事業の正当化と利益のためであることが透けてみえて、地域住民の生活を考慮していない杜撰なものだ。地域住民は反発する。巧も計画の見直しを求める。しかしこの町も開拓地であり、地域住民も元はよそ者≒他者だ。もちろんこの計画に賛成の住民もいる。それなら解決は他者の拒絶ではない。拒絶と受容のバランスが問題なのだ。
バランスを失うと崩れる。崩れる運動の描写が『ハッピーアワー』でもされていることを指摘するのは蛇足であるが、高橋と黛はバランスを崩さないために、巧や水挽町の生活を知ろうとする。
他者の理解だ。巧の生活の一部となっている薪割りを高橋はしてみる。峰村夫妻が切り盛りしているうどん屋でご飯を食べてみる。うどんに使われる湧き水を汲んでみる。山に分け入ってみる。
高橋と黛は他者をさらに理解したように思える。それならば理解したものを東京に持ち帰って、グランピングの計画は改善されていくに違いない。地域住民も計画に納得して、「ハッピーアワー」が訪れる。
と、ならないのが本作の特異点である。濱口監督と石橋英子さんの二人が好きな映画がファスビンダーであることはパンフレットをみて知ったのだが、本作にはファスビンダー同様に不条理さがつきまとっている。
そんな数日の出来事で他者は理解できないし、グランピングの計画は社長とコンサル事業者といったさらなる他者によって問題は複雑であり、解決は困難だーさらに社会経済的な時間の有限さもあるー。〈私〉と他者が言葉を交わし合い、反省し合い、啓蒙されたら万事解決になるわけではない。理性的コミュニケーションの限界。徹底的な本読みによって、〈声〉を重視する濱口監督の作家性とは思えない展開だ。
さらに他者とは、〈私〉以外の誰かであると共に〈私〉の中にも他者性として存在するのではないか。そんな他者性の発露が巧にとって花の失踪事件だろう。
この事件は巧が迎えを忘れることが一つの原因ではあるが、彼の意志を超えた偶発的な出来事である。高橋も黛も原因には全く関係ない。しかし事件は起こってしまう。
花はみつかる。住民の必死な捜索が全く無意味で、巧が勝手にみつけたこともまた不条理極まりないのだがそれでもみつかる。しかし花はバランスを崩して死んでいるように思える。さらにそこから高橋への殺意と暴力に転化するのは全く理解不能だ。Quoi??? でもそれが他者性なんだと思う。巧は事件以前は殺意なんて全くなかったはずだ。けれど殺意は顕れた。行動に移された。他者とはそれだけ理解不能で不気味なものだ。
ではどのように〈私〉は侵入者≒「他者」を拒絶し、受け入れられるのか。その問いの答えは霧の靄へと姿を消す。グランピングの建設が進められるのかも分からない。花の死が事件か事故なのかも分からない。彼らの結末がどうなるのかも分からない。そもそもラストシーンは、物語世界で本当に起こったことかも分からない。全てが「判断不可能性」に開かれていて、悪の存在も判断がつかない。
つまりは私たち観賞者に問いが突きつけられているのだ。映されたイメージは何なのかと。「悪は存在しない」。このタイトルは結局のところ何なのだろう。思考が循環する。不気味な何かが私の中に澱んでいるのだけは分かる。
会話劇がものすごく面白い。
レビュー書き始める前にミニシアターで拝見
したので日にちは適当。
結構、苦手な人も多い様子。
私といえば、集会や車内の会話が
面白かったです。
それぞれの視点から見たときに
皆それぞれ、事情や考えがあり。
自分では何ともできない状況がある、
そこに悪なんていない。
それがわかりやすい、日常の会話劇が
面白いと見てたらあっという間にエンディング。
あのエンディングは好き嫌いわかれる
だろうな、と思いました。
色々考えられるけど、主人公は鹿に娘が
殺されることを容認したわけじゃなく。
娘を助けるためにあの男性が鹿を殺して
しまうのを防いだのだと感じてました。
何故なら鹿はあくまで身を守ろうと
してるだけだから。
主人公はあくまで物語全体を
通して自然とともにいる、
偏らないけど自然に抗う事は違うと感じ
てる印象だったので個人的に
伏線のように感じました。
今までが日常の人々の会話劇だったから
油断してました。
主人公の精神自体は自然に寄り添ってる、
倒すべき悪はいないから
運悪く手負の鹿にあった娘を
助けるために手を出そうとはしなかったし、
娘を助けなかったように見える
主人公も言ってみたら悪ではない。
色々と思考の迷宮に迷い込む映画で
良い映画だと思いました。
最後はどういうことなのかしら
水の美味しい田舎の村にグランピングの施設を建てたいという芸能事務所が現れる。その時点でマユツバの事業計画。舐めてかかっていた住民にコンテパンにされる。
この住民説明会は結構見応えあった。
後半に向けて芸能事務所の担当が、このグランピングの運営に興味を持ち始める。その発言がなんとも薄っぺらな感じなのだ。通り道にグランピングができて柵を作られてしまったら鹿はどこに行けばいいのか、どこか他の所へ行ってもらいましょう。そういえ問題か??
クライマックスが1番難解だ。鹿は誰に撃たれたのか、娘はなぜ鹿に近づいていったのか、止めに行こうとした男を締め殺す必要があったのか、娘を抱いてどこに行くのか。
不思議な世界の中で,終わってみると確かに悪はいなかったなぁ。
わからないですね
あのコンサルタント会社の人が怖いなぁ、と感じました。
生業である仕事先のことをあんなに適当に考えているのだろうか、と。もちろん依頼主の社長も悪いですが、コイツにええように踊らされていく予感。手に入れた補助金から支払い、当然のごとく事業は失敗の憂き目に遭うでしょう。
完璧を求めてはいけない、って⁉️
それで金貰うの❓
現実もこんなんでしょうか。
汲んでいた水をうどん屋さんで使うのですね。
陸ワサビでうどんや素麺食べたいな。
子鹿の死骸は生々しい。
鳥の羽根🪶の利用法を知りました。
[説明会]ええ加減過ぎて腹立ちます。😤
読まなくていいです、ムカっとしますから。
浄化槽の規模、→検討する、毎日5人分濾過されず流される。
浄化槽の位置、井戸の汚染→公共施設、専門家に相談している、
清い水でうどん屋経営→汚染水となれば、死活問題、
この土地の人にとって水は大事、位置の変更必ず→
貴重なご意見、、社長の決裁を仰ぐ、
専門ではなくコンサルタント会社に教えてもらっている。
なぜ社長やコンサルタント会社が来ないか?
この土地に金が落ちる、→共存共栄、
ここは住宅地、ホテルみたい、焚き火が怖い→24時間体制じゃない、←絶対24hの管理体制必要、
問題はバランスだ。
水は低いところに流れる、から、
上の方であったことが下に流れる、
上に住む人には義務がある、わかって欲しい、
とてもよくわかる説明。
巧さん、薪割りうまい。
うどん食べて水汲み体験、までは良かったですが。
花ちゃん帰らない、一人で歩くシーンがよくあり、
駿河のオッチャンにもあまり行くな、と言われていたのに。
父親巧はなぜ忘れるのでしょうか?
普通なら、迎えに行く時間だ、と所用を切り上げるでしょうに。
黛のケガは何を表し、巧は高橋をどうしたのでしょう?
花ちゃんの体が見つかるまで手負いのシカと対峙のシーン
シカ🫎にやられたのでしょうか。
“悪”は存在しない、の”悪”はやはり人間でしょうか。
入って来た人間には自然の制裁があり、存在できないからでしょうか。たとえ花ちゃんであっても。
『悪は存在しない』は自分の中で存在し続けていく
濱口竜介はつくづくアートの監督だ。
その評価を決定的にした『ドライブ・マイ・カー』も難解と言われたが、まだ物語性や巧みな構成や最後はポジティブなメッセージも感じられた。
しかし、本作はどうだ。難題を突き出し、問い、明確な答えは描かない。見た人に委ね、見た人それぞれの解釈。
自分の解釈が当たっているのか、見当外れなのかすら分からない。
それも含め、試されているのだろう。いや、信じられているのだろう。
見た人一人一人が何かを見つけてくれる。絶賛でも酷評でも。
はっきりと意見は分かれる。ダメな人にはとことん合わず、好きな人はその深淵に誘われていく。開幕、森林木々の中に奥深く入り込んで行くかのように。
私も入りは迷ったが、気付いたら引き込まれていた。
長野県山奥の集落・水挽町。
豊かな自然と澄んだ雪解け水が自慢のこの高原地方は今、東京からのアクセスも良く、観光客も増えている。
この地で娘・花と暮らす巧は、自然と調和した慎ましい生活を送っていた。
序盤はこの父娘や住人たちの日々の営み。
薪割り、水汲み…。巧は寡黙ながら実直に日々の仕事をする。
花は元気に森の中を駆ける。
住人たちの交流。長年暮らす年長者の知恵、教え。
質素ながらも穏やかな町と暮らし…が今、大きな局面を向かえている。
巧の家の近くで、キャンプとホテルを備えた“グランピング”のオープン計画が上がる。
計画した企業による住民説明会が開かれる。
企業側は利便性と町の更なる活性化に繋がると自信満々に話すが、コロナの煽りで経営難に陥った芸能事務所が補助金と別企業からの提案で楽観的に推し進めた計画。
自然水が汚染される事、ホテルの管理体制やキャンプの火の問題など住民から不満疑問が続出。ずさん過ぎる計画に怒りの声も。
担当の高橋と黛は田舎人を簡単に言いくるめる事が出来るとタカを括っていたが、鋭い視点や意見、地元愛に完全にKO。
水は上から下へ。上でやった事は必ず下に影響する。…この区長の言葉は響いた。
社長や推進してきた企業を招いて改めて説明会を開く事に。高橋と黛はそう会社に伝えるが、社長も企業も条件は受け入れず、変わらず楽観的意見。
地元住民たちはバカじゃない。いい加減な計画、口だけの上役、それに振り回される自分たち。その愚かさに気付く。
最初はヤな連中と思った高橋と黛だが、彼らにも徐々に感情移入。再び水挽町へ向かう車内での会話が平社員の苦労が感じられ、何か気に入った。
二人は再び水挽町へ。会社の(バカみたいな)名案故。
町の便利屋のような仕事をしている巧にホテルの管理人を。どうせ暇だろう。←こんな言い方をする会社側にイラッと。
善は急げ。あまり気乗りしない二人。
巧の元を訪れ、薪割り中。薪割りをしてみる高橋。
管理人の話を伝えるが、暇ではないと鈍い反応。
巧にはもう一つ、気に掛けている事が。グランピングが建つ辺りはちょうど鹿の通り道。
鹿は滅多に人を襲わない。グランピングが出来、人も増えたらそこを通らなくなるだろう。
なら、鹿は何処に行く…?
花が行方不明に。住民総出で探す。
巧は思い当たる所を。高橋と黛も協力。
黛が怪我。巧の家で休ませ、巧と高橋で。
開けた平野。そこに、花が…。目の前に、鹿が…。
巧は驚きの行動を。そのままこれまた驚きの終幕になる…。
どう解釈したらいいか分からないラスト。
突然巧が高橋を羽交締めにして殺す。負傷した花を抱き抱えて森の何処へ。
巧は死に場所を求めていたのか…?
どんなに反対してもグランピングは建つ。そうなったら自分には居場所は無い。
鹿は何処に行く…? これは、自分なのだ。
そして私たちなのだ。我々は何処へ行く…?
居場所を無くした動物たち、破壊された自然。その悲しみ、怒り、憎しみは必ず人間に降り掛かる。
上の方の汚れが必ず下の方へ流れるように。自然の摂理。
巧=自然の高橋=人間への突然襲った災い。
災いの後は静寂が訪れる。無に帰すように…。
タイトルの“悪は存在しない”。
確かに本作には“悪”は存在しない。巧の行動も、住民たちの反発も、高橋や黛の言動も、会社側だって悪意は無い。
悪は存在しないが、愚かでもの哀しいだけなのだ。
…なんて解釈してみたが、全く自信ナシ。見当違いも甚だしいだろう。
3日ほど前に見たのだが、なかなか考えまとまらず。
やっと何とかまとまったのだが、そもそもこんな解釈でいいのか…?
今もふとした時に思い出す。多分これからも、印象残るラストと考えさせられる作品として、自分の中で存在し続けるだろう。
恐るべし、濱口竜介!
何故あのラストシーンだったのか。
悪は存在しないというタイトルから単純な善と悪の二項対立ではないよというのは何となくイメージしていた。途中までは当初のイメージ通りというか、違和感なくストーリーが進んでいた。
ただ、最後のシーンとそれまでの展開の結びつきが未だに自分の中で噛み砕いて整理できていない。
悪意のない人が何故あのような仕打ちを受けたのか。1つ思うのは最後羽交い締めにするシーンに繋がる直前に手負いの鹿を見ていた。鹿は臆病だが、手負いの鹿だったら逃げられないから立ち向かうために人を襲うと映画の中で説明があった。
もしかしたら彼は、手負い鹿と自分を重ねてしまったのかもしれない。人は不合理な行動や間違いをしてしまうことはある。万人が理解出来て分かりやすい悪なんて存在しない。
シカに取り憑かれたヒゲ男
結論からいうと1980~90年代であったら、まあまあな映画という感じでした。ホン・サンス監督作品のほぼ全てよりはマシってくらい。
衝撃のラスト!といいますが単純に明確な結末から逃げているように思えました。根底にキリスト教が屹立するブレッソン映画のようにはいかないのは、織り込み済みなのだとは思いますが。石橋英子の持ち出し企画と知ったうえで元も子もない話をしますと、あのラストシーンに情緒的なBGMは不要。あれは本当に非常にダサいです。
まず、今やアニメ・漫画の分野で例えば前時代的なメロドラマであったとしても自分たちなりの倫理観を問い詰めつつ覚悟を持って明確な結論を示す時代にあっては、この映画に関して言えばトータルの力量が足りてないように見えました(観察者目線のカメラワーク、映像処理、アングル・レイアウトも監督本人が狙っているだろう以上に実に古典的)。
申し訳ございませんが、時代遅れのスノビズムを感じずにはいられませんでした。
また、「地方山間部」「シングルファザー」「芸能事務所による政府からの補助金目当てのグランピング建設計画」という舞台・題材の比較的安易に感じるセレクトが、あくまで明日の食事に困らないような都市生活者≒ブルジョア目線であり、町長のいう「水は上から下へ」論は、よもや自己言及ならば悪趣味です。悪趣味といえば、父親が娘の帰宅時間を二度も忘れてるのは、あれは意図的でしょう。銃声と前後して思い出すのも意図的。娘をあえて危険な状態に晒している。「悪」も存在しないかもしれませんが同時に親子の「愛」も存在しない、他人と意思疎通も難しいが何故かポーズだけは上手い、まあまあサイコパスな(シカに取り憑かれた?)父親の話といったところでしょう。
普通の物語にはしたくないし、あわよくば映画史に名を残したいという鼻息と姿勢は垣間見せつつ、説明セリフを極力排すが作劇をスムーズに進めるべく、意図的に登場人物はステロタイプ化されているというアンバランスさは、あの懐かしき平成初期にあまたあった自主制作映画を思わせます。
あえてテーマを単純に読み解くならば、「社会道徳」<「個人倫理」<「自然の摂理」ということなのでしょうか。
便利な背景と小道具、雰囲気作りに成り下がっている森の樹木だって生きている。今度は、シカが樹木にヤられる続編でもあるのかな?って、ほら、くだらないでしょう?
しかし、「作劇」としては面白くなる可能性が多々あっただけに非常に残念でした。監督は「作劇」ではなく「芸術」をとったのでしょう。この「芸術」がどういうわけか世界的に認められたわけですから、次回作は思いっきりお金を使って「芸術」が出来るであろう幸運は大変喜ばしいことだとは思います。
この映画に「悪」は存在しないかもしれないが、送り手の「悪趣味」と受け手の「嫌悪感」は確実に存在しました。
最後に大きなお世話だとは思いますが、作品タイトルをストレートに「グランピング建設予定地殺人(未遂)事件」とか「シカに取り憑かれたヒゲ男」とかにすれば、見方も変わるし分かりやすいし宣伝もしやすいしで、良いことづくめだったのでは?
有名な役者さんは出てこない
『ドライブ・マイ・カー』の濱口竜介監督の作品。
ヴェネツィア国際映画祭で銀獅子賞(審査員賞)を受賞したんですよね。
映画の内容はというと、前半は長野県の自然の描写が多く、移動しながら木々を移す映像が多々あった。
正直、何も起こらない序盤は眠かった。
すると、田舎町にグランピング施設建設の話が持ち上がる。
有名な役者さんは出てこない。
それは好印象。
理由はなんのイメージも持たずに見れるし、テレビに出てない良い役者はたくさんいると思うし。
演技をしていない淡々と話す感じが現実に近くて良い。
棒というか、現実世界は役者じゃなければ、こんな話し方だと思うし。
映像描写は好きな感じ。
低予算映画の邦画のくくりでいうと、昨年見た『J005311』みたいにめっちゃ良いとは感じなかった。
共感しなかったということ。
今見ると『J005311』はココで熱くレビューしています。。
良かったら見てみて!
それと子役の女の子の顔がめっちゃ大人びていた。
そこが体に対してアンバランスで違和感を感じた。
そしていろいろあって、衝撃のラスト。
衝撃というか理解できなかった。
見る人が判断するという事なんだろうけど?が多いラスト。
特にあのチョークスリーパーは理解できなかった。
私は彼は死ななかったんじゃないかと思う。
最後に立ち上がったし。。
ここにグランピング施設を作ったら災いが起きるという事、
それを娘の死とともに人間の行いへの報いとして死で表したのだろうと私は考えた。
あくまで私のこじつけである。
昨年見た『怪物』のラストぐらいだと、こじつけなくても理解できたが、ここまでくると中々自分の中で消化できない。
悪は、グランピング施設を作ろうとしてる会社であり、金儲けを考える社長だろう。
でもタイトルは『悪は存在しない』だし。。
考えさせますねー。
起承転結しないというか、昔のフランス映画のようなラスト。。
ハリウッド系ばかり見てると、見慣れないエンディングだと思う。
単純なハッピーエンドじゃないエンディング。。
芸術性が高い映画という事なんだろうと思うけど。。
『ドライブ・マイ・カー』は特に違和感なく見れてた。
カンヌやアカデミー賞を取ったんで、自由に映画を撮りたかったのかなと思う。
単純な娯楽作品ではないので、ある程度の覚悟は必要かも。
木立のエンドロール
Evil Does Not Exist
長尺に描かれる辺境の日々の作業。そこに音楽はないが、頭に生活を植え付けられるよう。
(同様に)対比して、業者たちの人物像も長尺でしっかり描かれる。その後で背景が不明瞭なままなのは、むしろ住人たちの方だ。
車の後方映像、蕎麦屋の水汲み、それらは伏線回収として使われるだけ、本当に大切なのは幼稚園のお迎えの刻限。
失踪する命。お互いが権利を主張して、乾いた馴れ合いで腹を探り合っている間に。上流のやり取りが下流の足元を掬うように。
自然のことなら、既にもう皆が喰い合うようにして生きている。
失ったものに対して、その報復を受ける。そこに善悪は存在しない。
ベネチアで銀獅子賞ってことはゲージュツ映画かな?そしてあの結末。
OPで延々と見上げた森の映像を見せられた挙句に
主人公のおっさん、なんか台詞凄い棒読みですが大丈夫?
いきなり不安な幕開けの後は薪割りの長回しで
嫌な予感しかしないゲージュツ映画の匂いプンプン。
今度は特に状況説明なしに川で水を汲み車まで運ぶだけのシーン。
TVだったらこの時点でチャンネル変えてます。
前置きが長くてイライラさせる演出。
後に水汲みは蕎麦屋の拘りの水と判明しますがやはり不親切。
説明的台詞の多い邦画に慣れてしまった自分も悪いが。
さて一番の山場(?)グランピング施設開発業者の説明会。
このシーンが結構良くて監督の演出が入っていないのか
マジもん会議のライブ中継観ているみたいな感じ。
開発業者の男女2人の車内でのどうでも良い会話も妙なリアル感。
その後主人公のおっさんの娘が森で行方不明になり村人総出で
探す訳ですがここから結末が謎展開。開発業者のおっさんと
2人で探していたのに主人公が何の脈絡もなしにフルボッコ攻撃。
倒れたおっさん一度は起き上がるがまた倒れTHE END。
あれ?特に恨みないよね。それに色々問題解決していませんが?
観客に委ねる系のが苦手の人にはちょっとアレですが
意識高い映画ファンにはウケが良さそうなゲージュツ映画でした。
再見したらジワジワくるかもしれんが一週間限定だったので残念。
悪とくくる安易さ
自然を開拓して暮らしを営んできた町民と、利益優先のグランピング場建設を計画する都会人の明快な対立の中で、極めて理性的に振る舞う主人公。
町民と交渉しながらも、現状の生活に嫌気が差していた都会人一行は、主人公との交流を経て、田舎町での暮らしに感化されていく。
娘が行方不明となり、主人公の中に眠る独善的な思惑が、"自然"に実現する条件が整ったとき、それが実行されるお話。
ー
衝撃のラストについて個人的な感想。
異様なまでに娘の迎えの時間を忘れる、
娘の甘えより、環境を守る誓いのお絵描きを優先するといったあたりから、
主人公は妻なき今、心の底では娘を愛せていなかったのではないか?
と思いました。
自然の摂理によって起きた事故として、
娘を救わなかった目撃者を消し、
遭難の二次災害が起きてしまった悲劇として、
町民に語り継がれるように実行された。
娘が生還するか、都会の男が生還するか、
もしくは両者とも死ぬか。
それは自然の摂理に委ねた。
そんな独善的な行動の条件が整う瞬間を、
主人公は心のどこかで待ち続けていたのではないか。
そんな主人公の思惑がチラ見えしたときの、
ゾッっと感が忘れられない。
そこには主人公の抱える"弱さ"や"狡猾さ"、
自然を知り尽くした"賢さ"や"畏敬の念"もあるかもしれない。
それを単なる"悪意"とくくってしまうのは、
安易なのかもしれないと思いました。
最後はなんだったのだろうか
音楽良かった
棒読みのセリフの感じはとてもいい
最後のシーン
「鹿が人間を襲うのは手負の時」という前振りがあったので、あの鹿が花を襲った、ということ?
北欧の映画っぽい演出とストーリー
均衡(バランス)崩壊の行き着く先は!?
追加上映にて観賞。何となく「楽園」の佐藤浩市の話に似ているなと思いました。
ある芸能事務所が山の中にグランピングの施設を建てる計画を立てていることで住民と対立し、均衡が破れることによって起きる話ですね。
後半に巧の娘である花が行方不明になり、事態は急変します。巧は建設側の高橋という男と一緒に花を捜すことになります。
ラストに巧たちは、2頭の親子鹿の前に立っている花を発見しますが、おそらくこれは巧の見ている幻覚なのではないかと思います。
現実は花が倒れていて、鹿に襲われて死亡しているのではないかと思います。このラストの前に鹿の狩猟による銃声があり、撃たれた小鹿は死亡し、苛立っている親鹿が花を襲ったのかなと感じます。
つまり、あの親子鹿は巧親子を表しており、混乱した巧は高橋をスリーパー・ホールドにかけてしまったのかなと思います。
冒頭と最後に木々を見上げた風景が流れますが、人間が倒れないとその風景は見られませんので、やはり花の死を暗示しているのかなと思いました。
個人的な推測による感想になりましたが、劇中で真実を出していないため、いろいろな考察ができる面白い映画になったと思います。
追記 ラストシーンは、「だるまさんが転んだ」のシーンと同じ静止シーンになっています。小技が上手すぎです。
大自然の背景なのに、希望が見出せない明日を描いている
やっと先日「悪は存在しない」を観たわ。
皆さんは、
野生の鹿、イノシシ、猿、狐、狸、アライグマ、ハクビシン etc
遭ったこと在る?
猿ぐらいかなスグに逃げていかないのは。他は必死に逃げていく。
猿は人間と同じで状況を確認してから逃げる。
野生の鹿と遭遇して一度追いかけた事あるけど、もの凄い早さで走る。
ライフルで狙って撃つにも とても難しいだろうと感じたな。
それが野生の鹿である。
この映画ラストで 野生の鹿が出てきて、体にライフルで撃たれた跡があった。
巧の娘(花)の前に居るのだが 一目見てこれは嘘であると分かった。
脚本に沿った演出だからワザワザ用意しているのだろうけど、実際なら長時間そこに居ることは無いだろうし スグに去って行く。
況してや熊じゃ在るまいし 背丈の小さな娘を襲う理由も無い。
無理な展開流れで 何とか野生の鹿に襲われた事にしたいのであろうが
返って不自然さを残す羽目に感じる。
同時に、野生の鹿を刺激しないように? または 娘と鹿との対峙を邪魔しないように? 一緒に娘を探してくれて同行している高橋の首を背後から絞めて 口から泡を吹かせて気を失わせている。
この行為が最も理解しがたい。
巧の妻は理由不明だが亡くなっている。一人娘を育てているのだが心が病んでいる想定なのだろう。最後は親子二人で無理心中~ って展開なのだが 全く頂けないよ。ここに至るまでの説明が弱いと思う。
心中する場合 いつでも死ねる。場所もある。
なのに 何故高橋の居るときに、薫も居るときにするのか。
それは 自分達の最後を見届けて欲しい狙いなのかもだが
人の子の親(しかも残された子の親)が考える事では無いな。
残念だけど この流れは 0点だわ。
賞獲向けに仕込んだ罠に感じるけど、もっと素直に心の流れは描いた方が高評価と感じるよ。今作のセリフ調は大分良かったと感じた。前作の”ドライブ・マイ・カー”は酷かったもんね。
一番良かったのは、グランピング説明会での区長の話。
あの住人代表者でかつ年配者としての目線の話が一番心に刺さり、上手く表現説明出来ていたと感じます。
心ある言葉とは あの様な事を言うのだと思った次第です。
監督の更なる次回作に期待しております。
もっと多くの人に観てもらいたい
寝ても覚めてもやドライブマイカーを彷彿させるような演技で、濱口監督ならではの演出でとても魅力的でした。
最初のシーンや車を出発させるシーン、木々の間にぴったり人を配置してるシーンがとても印象的でどのように撮影が行われたのだろうと気になりました。
音楽も画にとても合っていて、リズムがぴったりで楽しく観ることができました。
この画や音の美しさをもっと多くの人に観てもらいたい!!
すべては、バランス
星5をつけたの久々か…
いや、たしかに終盤は「まさかここでエンドロールくる?きちゃったらどうしよう??」と慌てたところでほんとにエンドロールが来てしまい、一周回って気持ちよかった。それも終わり方のあまりの潔さに好感を持ったのと濱口竜介監督のテイストがそもそも私は好きだからというのが大きい。「なんだこりゃ」という人がいるのもわかる。でも好きなのだ。上手く理由が説明できない、自分にとっては久々にゾクッとするような美しい作品に出会えたなと。
見終わってすぐ他の人の考察読んじゃったけど。その人の考察がすごすぎて全て納得した。
まずこの作品は序盤からかなり人を選ぶと思う。かなり冗長な長回しが続く。私も思わずスクリーンを見ながら「今晩の夕飯何にしよう」と意識を飛ばすほどだ。でも嫌な感じがしないのは、映像美と石橋英子の贅沢な音楽のおかげ。私、ハッキリ言うと映画の中で「音楽」をかなり重視しているので、この音楽だけでも既に高得点…
濱口竜介監督の作品そこまで沢山見てるわけではないけど、緩急の付け方が心地よい。作品のテンポそのものが音楽のようだなと思う。私はその「バランス」がとても好きだ。そして終盤にかけて「バランス」が傾いていく、不穏に…
でもまさかここまでとは。面食らった。
花ちゃんの存在感もすごい。出番は決して多くないのに彼女の存在が作品テーマの根幹である気がする。
自然も人間も傷ついているのだ、ということだと思う。印象的なのは枝に付いた血。でもその前にもシカの死骸など直接的なイメージが出てくるし、奥さんの存在も既に他界しているだろうから、生よりも死を纏った映画だと思えた。だから最後の巧さんの行動も唐突であって唐突ではなかった。ずっと死は側にあった。
でも彼の行動に悪意はなかった、殺意もなかっただろう。最後首を絞められた彼は生き残った描写もあったし、死の淵に行ったのはあの親子だった。まさかグランピング施設建設からこんなテーマに飛ぶなんて思わなかったしもっともっと重くてしんどいテーマだった。でも途方もなく美しい映画だった。
難しい
映画館で見るのは監督作品はドライブマイカーに次いで二作目
後の作品はcsにて
前作とは違い 著名な俳優は出て無い
森の空を映す映像から始まる
監督は余り演技経験の無い人を上手く
していくのに長けた人かも
最後のアレは何を現すのかな
悪の存在は過程にある。そして、我々、地球人への警告?。
映画館で6月16日に観賞した。村人の問題意識の強さや的を得た論理的な批判的思考能力の高さには敬服した。「美味しい」「かわいい」「おもしろい」などの理由がつけられない語彙の連発に嫌気がさして嫌厭していたが、この映画によって、私の、特に最近の日本映画に対する認識が高まった。
この監督の作品を初めて観たが、この映画を観たいなあと思わなかった。日本語のクラスで学習者の二人が観てきてネタバレなしで他の学習者や私の質問に答えてくれた。予告編を見ただけで映画について意見を言い合ったり想像力も使って話しあうので外国語学習にぴったりだと思う。コンテンツから語学を学ぶことは学習動機をあげるし....
私はリニアと関連させて水の枯渇化や大自然破壊がテーマで「開発と自然保護のバランスや調和」がテーマだと思っていた。観賞後気づいたが、テーマは少しその方向である。クラスで学習者にリニア中央新幹線|JR東海のホームぺージと信濃毎日新聞に掲載されていた水の枯渇化の記事も入れて、送ったら、
ある学習者が:
新しいリニアにワクワクしてきたのですが、今は少し考え方が変わりました。谷崎潤一郎のアイデア(陰翳礼讃)を考えて、このニュース記事を読んだ後、リニアのJR広告へのリンクをクリックしました。そして自分の反応に驚きました。電車のイメージから、何か怪物を連想してしまったのです。谷崎の言葉を考えると、こんな速い電車が本当に必要なのか、と。(学習者のそのままのコメント)
以下はあくまでも私見で、この映画を一度だけ映画館で観てレビューを書いている。
テーマは バランスだと思う。大きなテーマは 悪は存在しないが、バランスが壊れる過程で悪は存在する。だから注意せよと「その過程に」警告を発していると思う。この英語題の表示の仕方で私はそう感じた。
Evil exists
Evil does exist
Evil does not exist
バランスを崩した(崩された)時に諸々の問題が発生する。例えば、主人公タクミ(大美賀均)の娘ハナ(西川玲)との親子関係。お母さんが生きていて?三人家族だった時は、この三人でバランスが取れていたかもしれない。母親の死で、このバランスが、壊れる前にどこかで気づきが生まれると、このような断絶的な父娘関係にならずにすんで、人間関係に変わっていったと思う。優秀そうでアスペルガー気味で人間社会で機能が果たしにくい主人公タクミ(何でも屋)と娘とのバランスを取っていたのがお母さんの存在だったと思う。娘は遊んでくれる友達もいなければ、(遊ぼうとしない様だ)愛情の表し方の知らない父親は自分の世界に入り込んでしまっている。娘との会話は木々についてで、学校であったことを聞くわけでもないし、甘えさせてもあげない。ハナは母親から受けた戯れたりする愛情をタクミはハナに与えることができないのではないかと思う。家庭での情緒教育や子供の心を育てるのは自然とのふれあいだけで人間との触れ合いが希少。これはネット社会のなかで育っている子供達にも言える。「歌を忘れたカナリヤ」になるなと、監督が警告しているのではないか?区長に鳥の羽をあげて喜ばれたのが彼女が受けた褒め言葉でもあり、注意をされた言葉でもある。「一人でいくな」と区長に言われた開拓を始めた土地に一人で羽集めに出かける。ハナはタクミのように、自然の恵みを持ち合わせていてサバイバルスキルがあるように見えるが、自然環境オタクの弱点はこのような人間性のバランスを持ち合わせていないからハナには機械のように接するだけ。例えば、実例だが、子供のころ情緒や感情の教育を受けていない人は人間の感情と現実とのバランスが悪い。しかしこれは悪ではない。この人が悪に染まるとしたら、他の要因が過程にあるはずだ。
人間は自然の中で、人間は自然とともに共存する。動物もそうである。そのバランスを壊すのは自然破壊や生態系を崩すことである。ここではグランピング(生まれて初めてこの言葉を聞いた)の会社の計画だ。森林生態系を崩していく(もちろん、水域生態系,土壌生態系)人間中心の自然の摂理を無視する行動や活動であり、ここではタクミは自然界の摂理を理解してバランスの乱れを恐れている。タケミも村の人々も自然環境の大切さを十分理解している。森林生態系を崩していくことは悪のようだが、誰かやどこかがこの恩恵を被っている。グランピングの成果から癒しが与えられる人も出てくるだろう。それに、経済も活性化するし多面的に見れば、悪ではないと思うし善悪の問題ではないと思う。悪が生まれるのはその過程の中に存在する行為であると思う。監督はその過程に警告を与えてるのだ。
最後のシーンもバランスが崩れた(崩した)いい例だと思う。
「野生の鹿は人を攻撃しない。 怖がりだから。 しかし、例外はある。 銃に当たって逃げる余力がなければ、人を攻撃することもできる」とタクミは言う。
タクミは鹿という自然の生態系の賜物に娘がどう対応するか確かめたかったように思えてならない。娘は父親のように帽子を脱いで尊敬の念を表している。それは自然の創造物の賜物である野生の動物と人間、ハナとの対峙である。娘と野生との突如の対峙を見守りたかったと思う。見たかったのかもしれない。ハナにはその野生と融合する素質があると思っていたとも思う。また、鹿とハナを見つけた瞬間、タクミにはハナを救い出す方法が考えられなかったとも思う。しかし、プレイモードの高橋啓介(小坂竜士)が叫び声を上げ、ハナと鹿のバランスを崩したと思う。それを(正当)防衛しようとしたのが、タクミであったと思う。
「ハッ」と気づいた時は娘は傷ついて倒れていた。タケミが「ハッ」と気づく時はいつも手遅れだ。
極論かもしれないが、娘を使うことで自然の賜物と人間である娘がバランスをとれたことが証拠になると思ったのではないか(不幸にも、そうは問屋がおろさなかったが)。娘が救われ、そのバランスを見たかったから、オレンジジャケットを身につけている高橋啓介の叫びを抑えた。でも、当てが外れた。またこの叫びに加え自然環境とアンバランスなジャケットの色はより鹿を獰猛にさせたのではないか。高橋啓介の自然の賜物に傍若無人なもの知らない態度が悪をもたらす結果になるが、高橋は自分の態度がバランスを崩したと気づいていないのだ。
地球は、社会はバランスを失っている。でも、それに気づいている人々はどのくらいるだろうか。リニア開発、アマゾン森林破壊、地球温暖化、次から次へ起こる戦争などなど数をあげたらキリがない。
SNS, そして、AI環境が人間の心の病気により拍車をかける。また、その心を失ないかけている人間が、不安定な状態で人間を育てる。 アンバランスになる訳である。
村の人はバカじゃありませんよという黛(渋谷采郁)の言葉がひかる。
我々の社会でAIの一億総白痴化はもうすぐそこにまできている
でも、私たちはバカじゃない
人間性を失いつつあるこの社会へ、地球への警告を監督が示していると思う。
我々が、人間として、または地球人として、批判的思考や問題意識をもって行動することが悪を存在させない一つの方法であると言っていると思える。
問題意識と批判的思考能力の強い村人のように自然と人間の調和を意識化に入れた啓蒙的思想を強めよと監督は我々にメッセージを与えていると思う。
似非自然主義
自然の中に溶け込むようにして暮らす親子を描きたかったのでしょうが、日夜山の中で暮らしているという設定にも関わらず、父娘ともども新品でピカピカの服を着ている時点で急速に冷めてしまいました。娘なんて眉まで綺麗に整えてますよね?全体的に山の中で暮らす父子家庭っぽさが皆無でした。傷ついた鹿に自分達を重ね合わせるようなエンディングへとつなげるのであれば、もう少し泥臭い生活感をにじませるべきではないでしょうか。本作ののテーマであるはずの人と自然との共生って、森の中を歩くシーンと、水汲み、薪割りぐらいにしか描かれていませんよね。
またグランピングに関する説明会のありようにも、違和感しか覚えません。説明された内容で行政が開発許可を出したのだとすれば、住民が責めるべきは許可権者である行政でしょう。合併浄化槽の位置や容量に問題があるのだとすれば、それで良しとした行政が悪いのは言うまでもありません。さらにそんな欠陥事業に補助金まで交付するというのであれば、どう考えても悪は行政側にあるわけです。ところが本作に登場する住民達はただひたすらに事業者のみを糾弾し、批判し続けます。ルールに則って開発を進めようとする事業者が悪しざまに言われる所以はありませんよね。この町に住む住民の中には、物事の道理を理解している人間は一人もいないのでしょうか。
他にも様々引っ掛かる部分ばかりが目立ち、個人的にはさっぱり楽しめませんでした。職業「便利屋」でお金には困っていないと言いつつ、具体的な仕事内容は水汲みぐらいしか描かれないし。その割にピカピカの新車のSUVを乗り回しているし。水汲みってずいぶん儲かる仕事なんですね。そこは使い古したジムニーとか軽トラで良かったんじゃないですかね?田舎暮らしや自然との付き合い方、行政の仕組みについてよく知らない人達が、頭の中に思い浮かんだそれっぽいイメージをよく調べもせずにただ並べて作り上げた映画、という印象です。エンターテインメントである以上フィクションが前提になるのは当然ですが、最低限のリアリティーは担保して欲しかったと思います。
全78件中、1~20件目を表示