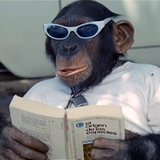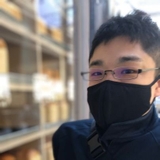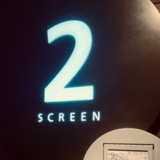悪は存在しないのレビュー・感想・評価
全174件中、121~140件目を表示
映画的なショック
森の中の移動ショットが素晴らしい。山の霊性、人の関係性、夢の中、いずれも説明的でなく絵でしっかりと描き出しており、しかもとても美しい。
薪割り、水汲みなどをロングで長回しするショットも良い。永遠に見続けたいと願うほど魅力的。長回しの中、高橋が見事に薪を割る瞬間がこの映画のひとつのクライマックスになっている。
監督が得意な会話劇も素晴らしい。無駄なカット割りをせず、すべて引きのショットでドキュメンタリータッチに描いた説明会シーン、車中で芸能事務所のふたりがお互いのことを話すシーン、いずれも精緻。
話されている内容はドラマチックでも何でもないし撮影もいたってクールだが、だんだんと感情が高揚し胸が熱くなってくる。これぞ濱口映画。
ラストのつるべ落としはネタバレになるので書けないが、とても映画的なショックが与えられる。
濱口組といってもいいような人たちと、演技経験のない主役を組み合わせたキャスティングも見事。
そもそもMVとして始まった企画なのに、音楽が映像のクオリティーに追いついていないのが残念。
森の中の父娘
悪とは
スマホのある時代に生まれたことを強く悔やんだ。
最初の森の長回し。
すごくその森のことが気になったし
物語に入り込むには十分だった。
男の棒読み感に
ああ、大学サークルの延長か、OBか、と思った
がっかりした。
女の子もベルギー映画に出てくるような、
2人共にバランスの悪さを感じた。
チープさ。
荒いカメラワーク、
暗くて絵が見えないカット
チカチカする長回し
けれどそれでいて
むしろ身近に感じられるという作用。
途中からはもう男のような存在が欲しく、花が羨ましかった。あんな存在が欲しい。
私はずっと子供なのだと思った。しっかりしてなければいけない、子供。
男の包容力を感じてからは
少し良いなと、思うようになった。
あの生活、あの落ち着き。良いなと思った。
羨ましいなと思う良いなと、これって良いな、の気づく良いな、だ。
東京から来たプロダクションの2人、
最初は背景に過ぎなかったが
女の意志を感じ、そして車の会話劇は名シーンだ。もうすんごい多幸感。こういう映画を見ていたいし、作りたいし、でたい。かと言ったら
もしかしたら作りたいが一番強い。
そこからはどの登場人物も愛おしかった。
それはすごいよなあ。
最初意識的に引き込まれていなくても
掴んで離せない何かはあって
最終的に持っていかれる。
わたくしはこういう関わり方をしたい。
こういう環境にいたい。
有機体のような恐ろしさ
自我の気化 人の希釈
僕の期待が高過ぎた、期待してる部分が監督の描きたいことと違っていた...
僕の期待が高過ぎた、期待してる部分が監督の描きたいことと違っていた(偶然と想像は年間ベスト、寝ても覚めてもは生涯ワースト)という鑑賞態度の不義理さでスコアはこんなものになるけど、とんでもない作品なのは間違いない。
グランピングの説明会のピリピリした会話劇が本当に面白かった。安直に『都会vs田舎』『革新vs安寧』に留めることなく、住民の中にも『自然側からすると我々は部外者である』という認識を持ったキャラクターが出てくるからこそ、ラストの衝撃の展開が「ただ単に突飛にしたかっただけではない」という説得力を持たせている。実際説明会する側がみんな乗り気なのか、前向きなのかもわからないしな。どうしてもこのタイミングで観ると、静岡のリニア問題を想起させる。
濱口監督の素晴らしい「車シーン」は今回も健在。何となく車の空気を重くしないようにふわっとしたトークからプライベートな話に入っていく自然さ。
自分は『誰の視点に立つかによって見方が変わるので絶対悪は存在しない』と解釈した。
音楽があまり好みじゃなくて、ぶつ切り演出もくどいなと思っちゃったところはある。前半の内容が必要なのは承知の上で、説明会までのシーンが長いなというのもある。
裸の王様
どんな話
ドライブマイカーの様な心地良さと偶然と想像の様な企み
2024年劇場鑑賞32本目 佳作 59点
濱口竜介監督の昨今の躍進から、注目せざるおえない作品
んんん、当方2018年くらいから意識して劇場に足を運んで、レビューを残し映画文化に触れて目も肥えてきた方だと自負していましたが、その日常が7年目になっても今作の様な奥ゆかしい味わいのある作風に理解が追いつかない作品との出会いが時折あり、ドライブマイカーなんかは玄人に比べれば半分も楽しめていないと思うけど、それでもその年の年間10位くらいに位置付ける程には楽しめた記憶で、反対に偶然と想像は年間ワーストクラスと堪能できるか否かがまだ定まりきっていない感覚ですが、今作はどちらかというと後者よりの味わいでした
タイトルや物語として伝えたいことというのは、要は侵略や継続を望む多様な人間もそこに本来住んでいた動物や木々などの自然含め、誰かの正義は誰かにとっての悪なのかもしれないけど、共通として残る残したいのは温かさであり愛なんだよね、ってことなんだと思う、抽象的な表現ですが
主人公が確か技術さんかなんかなんでしたよね、演技の力の抜け具合やハツラツとしていない発声、よそ者であったり達観している様は、会議の場でも客観的な立場からの物言いであったり、淡々と営みに励んでいるのが、妙な怖さにも見えた
確か東京から来た男女の一方の彼の簡単なやつっぷりがまさしく滑稽で、仕事しかりいい年して自分を貫く軸の無さが伺える
配信くんのかな、ドライブマイカーは結構時間かかったし、上映館も都内渋谷下北沢のみと渋っていたため観れてない人も多いだろうから、また理解を深めたいですね
他者を理解すると言う事。表象だけの理解では、物事の本質に触れる事は...
視点を変えるとジャンルも変わる映画
偏見ではあるけど、田舎町の住民と芸能事務所の人間は、なんとも相性が悪い。
特に社長とコンサルは危険分子でしかない。
自然と人間がバランスを取りながら暮らしているところに、ウェーイなヤツらが来るかと想像すると、住民のざわつきも致し方ない。説明会のシーンは、開発側と住民の怒りや不安、苛立ちなど、垣間見える感情が人間臭くて見応えがあった。
高橋と黛は、自然に触れ、人に触れ、気づきはあったものの、ねぇ。
ラストは"なんで⁈"ってなる急展開。
町の人たちは知っているのか否か、初めての事なのか、それともいつもの事なのか。
いろいろ想像してみると、木々や風の音、銃声や水の流れなんかも、急に不気味にも感じられる、音と映像の説得力たるや。
世にも奇妙なっぽいエンディングで結構好き。
もう一度観たら、また違う何かが見えるかな?
問題提起型の作品です、明確な結末は画かれていません。
いい意味で眠くなる映像詩
意味深
ドキュメンタリー映画のよう
自然と人と。俳優がはまってくる不思議
物語の事前知識なく鑑賞。
最初は長回しの自然との共生が描かれ、昨今の話が進む作品に慣れている人には合わないだろうなと思いながら、リラックスしながら観る。
気になったのは、カメラワーク。
山葵、車の後部、鹿の死体、ちょっと離れた木陰からの視点など、いい意味で映画であることを感じることができる。
そのうち、だんだんと社会性の要素が描かれるとともに、最初は違和感があった俳優陣が住民として妙にハマってくる。
やりとりにも随所に濱口監督らしいユーモアがあり、劇場内で笑いが起こり、とても心地良い。
タイトルからわかるように、両面の人々から状況が描かれる展開は目新しさはないが、そこに自然がうまく入ってくることで、考えさせられる作品となっていた。
そして、キーとなっていた音楽。おどろおどろしいもの、ポップなもの、自然の中での非日常感を増してくれていたとともに、音楽と映像だけでも楽しめた。
全174件中、121~140件目を表示