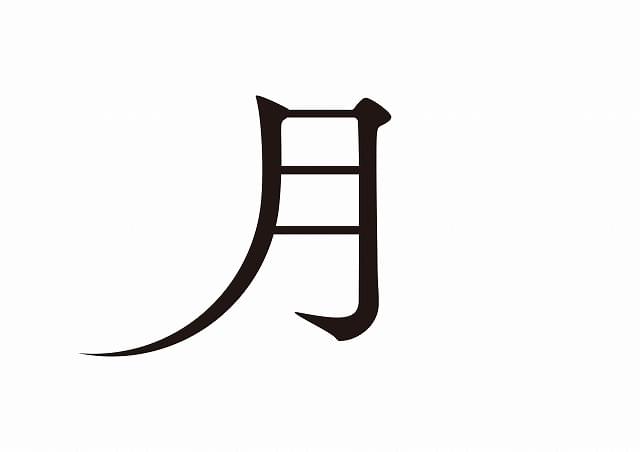月 : 特集
【顔を背けてはならない大問題作】実際の障がい者施設
の殺傷事件を題材に描き、1秒毎に深刻な衝撃与える…
社会が隠蔽する闇は日常のそばにある テレビやニュース
では観られぬ“問題提起”にあなたはどう向き合うか?

10月13日から公開される「月」。辺見庸氏の同名小説をもとに、「舟を編む」の石井裕也監督が宮沢りえを主演に迎え、実際に起きた障がい者殺傷事件をモチーフに描いたヒューマンドラマだ。
その物語は、今を生きている私たちが、見て見ぬふりをしてきた事実を白日の下に晒す。そして1秒毎に深刻な衝撃を与え、観る者の価値観をもんどり打って転覆せしめるのである。

映画冒頭にはこんな文言が表示される。「言葉を使えない一部の障害者は<声>を上げることができない。ゆえに障害者施設では、深刻な<問題>が隠蔽されるケースがある(原文ママ)」。
原作者はもちろん、石井監督をはじめとするスタッフ・キャスト陣は、多くのメディアが踏み込めない領域に果敢に切り込んだ。覚悟をもって叫ぶその問題提起は、絶望の向こう側にある“真の希望”をも浮き彫りにする――。
この記事では、「月」の特筆すべき力強さと意義を詳細に伝える。ぜひ注目してほしい本作だが、あなたは真正面から向き合えるだろうか。
かつてここまで鑑賞後に“言葉を失う”作品はあったか
映画ファンは、この大問題作から顔を背けてはならない

本作を「どういう作品なのか?」「なぜ問題作なのか?」「観るとどうなるのか?」の3つにわけて解説していこう。
[どういう作品なのか?]深い森の奥にある重度障がい者施設。堂島洋子は、ここで新しく働くことになった。

元有名作家の堂島洋子(宮沢りえ)は、夫(オダギリジョー)と2人で慎ましく暮らしながら、森の奥深くにある重度障がい者施設で働きはじめる。そこで彼女は、作家志望の陽子(二階堂ふみ)や、絵の好きな青年さとくん(磯村勇斗)といった同僚たち、そして光の届かない部屋でベッドに横たわったまま動かない、きーちゃんと呼ばれる入所者と出会う。
洋子は自分と生年月日が同じきーちゃんのことを、どこか他人だと思えず親身に接するようになる。その一方で他の職員による入所者へのひどい扱いや、暴力を目の当たりにする。さとくんも理不尽な状況に憤り、徐々にその独特な価値観や正義感、使命感を増幅させていき……。

配給はスターサンズ(「あゝ、荒野」「愛しのアイリーン」「潤一」「新聞記者」「宮本から君へ」「MOTHER マザー」「ヤクザと家族 The Family」「パンケーキを毒見する」「空白」「ヴィレッジ」など)が手掛け、プロデューサーは日本映画界の異端児である故・河村光庸氏。観る者を強く刺激する“渾身作”を、またも世に放ってきた。
[なぜ問題作なのか?]テレビやニュースでは観られない、深刻なタブーを描破する

冒頭でも述べたが、本作は実際に起きた障がい者施設での殺傷事件をモチーフにしている。さらに言えば障がい者施設での暴力など、社会が、そして人々が見て見ぬふりをし、隠蔽してきた事実をも題材にする。
障がい者施設での事件はなぜ起きたのか? その描写の解像度たるや、全編通じて筆舌に尽くしがたいものがあり、テレビやニュースではおそらくここまでは触れられないだろう部分にまで、「月」は突き進んでいく。
もちろん、本作は優生思想や暴力を容認する物語ではない。そして観た人すべてを喜ばせる映画でもない。得てして暗い気分に沈んでしまうかもしれない。しかし、私たちはこの映画の問題提起を受け止める必要がある。だからこそ本作は、映画comユーザーへ強く紹介したい、まさに必見作なのだ。
[観るとどうなるのか?]胸ぐらをつかまれたような衝撃に襲われ、言葉に詰まり、そして…

マスコミ試写に来場した人々(つまりプロの映画ライターや記者や映画人たち)に感想を聞くと、皆一様に「鑑賞直後はすぐには感想が出てこない」と口をそろえる。言葉を生業にする人々から、これほど言葉を奪う作品は非常に稀だ。
そのなかでも絞り出されたものにフォーカスしてみよう。「身動きもできないまま観終わった」と圧倒された声があった。「今、何も答えが出ない」という衝撃の声もあった。「とにかく観てよかった」と意義を感じた声。「日本映画界でこの作品を完成させた覚悟」と称賛する声。「絶対に公開すべき」と背中を推す声。声、声、声……。
あなたは鑑賞後、どんな言葉を紡ぐだろうか。
【レビュー】1秒1秒が胸をえぐる…天才・石井裕也監督
が届ける結末を体感した時、真の希望が見えてくる――

では、実際に本作を鑑賞した映画.com編集部は、何を感じたのか。やはり鑑賞直後は言葉を失ったが、受け取ったものはなんとしても言葉にすべきだと強く感じる。だから精一杯ここに記していく。もうしばし、「月」という映画の旅にお付き合いいただこう。
※ネタバレなしで記述
●注目してほしいのは、後半に訪れる画期的な“対話”シーン
本音と建前が白日のもとに晒され、観客にそっと、何かが手渡される

まさに1秒1秒が胸をえぐるような映画体験だった。磯村勇斗演じるさとくんと、宮沢りえ扮する洋子。月あかりの差し込む施設の一室で、2人が正面きって対話するシークエンスがある。ここをぜひ映画館で観てほしい。
鏡合わせとなった2人の本音と建前が漏れ出ていく。洋子はさとくんに話しかけていたつもりが、やがて洋子自身への対話に変貌していく。月は太陽の光を反射して輝き、そしてどこまでも追いかけてくる。彼女らの言葉がお仕着せの綺麗事を濁流みたいに飲み込む様子が、石井裕也監督の鋭い演出によって表現される。

僕はこのシークエンスで、自分の頭の中に登場人物の思考や人生が流れこんでくるような感覚を覚えた。そこではたと気がついた。僕は原作者・辺見氏や石井監督、そして宮沢らキャスト陣から、重たい何かをそっと、手渡されているのだと。
●「月」からの問いかけに、あなたは何を思うか?
心にやってきたこの“真の希望”は、生半には消えそうにない

本作には非常にさまざまなモチーフが込められている。映画冒頭、洋子は髪の毛を切ってもらっている。髪は人間の不浄のメタファーである。そして洋子と夫・昌平は、職場に向かう道すがら三輪車を見かけ、つらそうに目をそらす。
僕は仕事柄、映画鑑賞中は常にメモを走り書きするが、本作は観ていて手がピタリと止まってしまった。洋子と昌平が刻みつける悲しみや苦しさ、さとくんや陽子(二階堂ふみ)が抱える感情が、僕の心と体へ猛烈に流れ込んできたからだ。

それらの感情の色は、鬱屈としていてとても黒かった。だから僕は、この作品から手渡された“重たい何か”は、最初は「絶望」なのかと思っていた。
しかし、違った。ラストシーン、主人公・洋子が意外とも言えるセリフを放つ。それを真正面から受け止めたとき、僕の心には“真の希望”ともいえる感情がやってきたのだ(少なくとも僕はそのように解釈した)。

ほかの人は僕と同じようには思わないかもしれない。でもそれでいいと僕は思う。この映画のすべてを、僕はまだうまく消化できていないし、消化する必要もないのかもしれない。ただ、映画で示された希望は、絶望よりも速く体中にめぐり、深く、長く残り続けている。
「月」がもたらした感情は一筋縄ではいかないが、人間を前に前に進ませるような感情でもあったように思う。胸の奥で、カタン、カタンと音が鳴っている。あなたも最後まで本作を観届け、感じたことを形にしてみてほしい。