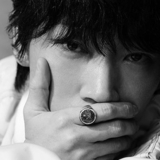月のレビュー・感想・評価
全82件中、1~20件目を表示
さとくんというアンチテーゼを生んだ社会=私たち
相模原障がい者施設殺傷事件をモデルにした作品ということで、正直かなり身構えて鑑賞した。あの出来事をフィクションに取り込むことの是非自体に懐疑的な気持ちを持ってしまったというのが本音だ。
辺見庸の原作は未読だったが、それを読む代わりに「やまゆり園事件」(神奈川新聞取材班・著)というノンフィクションで事件の概要をさらっておいた。原作からは視点人物の変更などかなり構成を変えていると聞いたためでもある。
実際観てみると、本作は事件そのものの実情に肉薄する話ではなかった。植松聖をモデルにしたとされる「さとくん」(植松聖が小学生の頃実際呼ばれていたあだ名と同じ)が何故あのような思想を持つに至ったかという部分は、むしろあえてぼかして描かれているようにさえ見える。
実際、パンフレットにある石井監督のインタビューによると、「生産性のないものを排除する」という思想は今の社会そのものが帯びているものであるため、植松という個人を掘り下げることはしなかったそうだ。
それは結果的に現実の事件に対して謙虚であることにも繋がっているように見えた。完全な創作ならさとくん個人の内面はもっと踏み込みたい部分かもしれないが、そこは「今の社会」の一員である観客自身に自分ごととして考えさせたいというのが本作のスタンスだろう。
ただ一方で、それならさとくんのディテールをあそこまで植松に寄せる必要があったのだろうかという気もした。
キャスティングはさすがに手堅い。個人的には、オダギリジョー演じる昌平が特によかった。自分とは全く共通点がないが彼の悲しみや喜びには感情移入出来た。オダギリジョーは奇矯な役もすれば、市井の人の風情を出すことも出来て、あらためて演技の幅の広い役者だなと思った。
ちょっと驚いたのは、施設の風景の場面で実際の障がい者の方が出演していたということだ。和歌山県有田市の障がい者就労継続支援B型施設「AGALA」の協力で、利用者本人に映画の内容を説明の上出演の意思を確認し、保護者にも了承を得た上で出てもらったという。なお虐待の場面の障がい者は俳優が演じている。
題材が題材だけに監督の覚悟は伝わってきた。だが、いくつか引っ掛かりを感じた部分もある。
ひとつは、障がい者の問題だけでなく、東日本大震災のことや出生前診断のことを絡めていることだ。
言いたいことは何となく分かる。震災においては、綺麗事が真実を覆い隠す一面があったし、出生前診断は、優生思想に繋がりかねない危険をはらんでいるということだろう。それらは、重度障がい者の社会との関係や、さとくんに象徴される命を選別する考え方とたいして違わないのだと。
それでも、ただでさえ繊細さが必要な障がい者を取り巻く問題を語る中で、震災と出生前診断のことにさらっと触れて、障がい者の問題と共通点があるだろうといわれると、私自身はどうしても「同じ俎上に載せていい話なのだろうか」と思ってしまう。
洋子たち夫婦が出生前診断の結果を聞きに行く日を現実に事件が起きた日に重ねているのが分かったシーン(カレンダーに丸印を付ける場面)は、正直そこまでやるのか、と思った。
監督は、自分の子供が産まれた時に感じた「健康な子供じゃなかったらどうしよう」という気持ちを強烈な差別意識だとし、それは自身の狭量さや不寛容さのほかに、社会のせいでそのような気持ちを持つのだと言っている。
出生前診断を受ける人は、内なる差別意識からそのような選択をするのだろうか。選択の理由には、違う意味での切実な事情もあるのではないだろうか。経済的負担、既に障害のある子を持っていたり親自身が疾病などで体力的に障がい児の育児が難しいなど。海外では妊婦の権利として認められ検査に保険が適用される国もあるなど、考え方の分かれる問題だ。これはこれで、本来なら当事者への取材が必要なテーマではないのだろうか。
また、複数の重いテーマを重ねると、重すぎて受け止めきれない人も出てくるだろう(障がい者の物語だけでも正面から描けばそういう人は出るだろうが)。本作を監督の意図通りの重さで受容するには、観る側の心にもある種の余裕が必要だが、観客だってそんな余裕を持って生きている人ばかりではない。
より多くの人たちに受け止めてもらうためには、ただひたすら深刻な描写のみを積み重ねるだけでなく、ある程度の飲み込みやすさも必要な気がする。
もうひとつは、主要キャスト以外の施設の職員2人が、ただの差別意識の強い人間としてしか描かれず、その背景の描写が不十分に見えたことだ。
河村プロデューサーは、事件の背景には社会の構造があると言い、長井プロデューサーも、本作の挑戦を日本社会での生活の根底に流れるシステム自体を問うことだとしている。であれば、あの2人の職員が何故あのような差別的態度を取るに至ったのかという部分こそしっかり描くべきだったのではと思ってしまう。
昌平の職場の先輩の描き方もそうだ。あまりに作為的過ぎる極端なキャラクターで、彼をあのようにした社会の問題より、この先輩個人への嫌悪感が先に立ってしまった。社会の差別意識を、登場人物個人の行動のみで表象することは、見られ方によっては誤解を生むような気がした。
監督は、当時の施設の職員にはできる限りの取材をしたそうだが、かなり「難しかった」ようだ。そのため、ドキュメンタリーという手法では描けないからフィクションで、ということらしい。被害者遺族に取材を試みたかどうかは、私が読んだ範囲のインタビューなどでは言及自体ない。
物語では高畑淳子が遺族の代弁者になっていた。出演時間は短いが、当事者という意味ではさとくんと同じくらい重要な役だ。ただ、本作をもし遺族が観たらどう感じるか、私には全く分からない。
こういう問題を批判されるリスクなしに描くことは途方もなく難しいことだ。作中でさとくんが、洋子がきーちゃんの視点で小説を書いていることについて、利己的な側面があるのではと面罵した。そもそも原作がきーちゃん視点で書かれたものなので観ているこちらもどきっとしたが、監督は自分自身もそういう批判を受け得ることは承知の上ということなのだろう。
私自身は、重度障がい者がどう社会とつながっていくか、という問題については、まず知ることから始めたい、という気持ちになった。気になった点も書いたが監督の意図を感じとった実感もある。
重度障がい者が、施設ではなく、支援を受けつつ地域で暮らすという試みも近年進んでいるという。本作をきっかけに重度障がい者への理解を深める人が増えれば、その試みもいっそう進捗するのではないか。とにかく重い作品だが、そういう希望に繋がることを願う。
みたくない現実から目を背けようとはしない映画
随分、重く苦しい話だが、これは現実にあった事件の話。
私は、この事件をニュースで知ったとき、
「なぜそんな酷いことをするのか」
「虐待や殺してしまうくらいなら、なぜそこで働いているのか」と思った記憶がある。
“障害者の人権・尊厳の保障”
蚊帳の外から言うのは簡単だ。
関わりのないところにいて、現実・実態を知らない私たちに、何が言えるのか。何ができるのか。
映像では伝わらない“ニオイ”が最も現実を突きつける。
まじめで優しく、他者の痛みに敏感だった彼を狂わせたものは、社会の矛盾そのものだった。
さとくんはこう言う。
「でも、ここでは障害者達を物のように扱っています。
鍵をかけて部屋に閉じ込めて、何年も何十年も生きることも死ぬこともできないまま、ただ存在させているだけ。
その現実は見ましたよね?
洋子さん、見て何かしましたか?
自分の都合だけ考えて、何もしなかったんじゃないですか?
ずるいですね、洋子さんは。
ここには誰も来ません。
入所者の家族もほとんど来ません。
神様もここの現実は見ていないでしょうね。
誰にも見られていないから、
みんなめちゃくちゃするんです。
でも、そのおかげで僕は真実に辿り着いたわけです。
やっぱり、あいつら障害者はいらないんだって。
それが、この社会の隠された本音ですよ。
つまりね、この施設は幸か不幸か社会そのものなんですよ。
同じでしょ?障害があるならいないって考えたでしょ?
っていうか中絶しようとしたでしょ?
みんなずるいです。
心のどこかで消えて無くなればいいと思ってるのに、
責任は取りたくないから矢面には立たない。実行しない。
所詮は他人事です。だから僕が代わりにやるんです。」
この言葉を、あなたは完全に否定できるだろうか。
現実を知らない人は無責任で綺麗事ばかり言う
簡単に心ない言葉で「何のために生きてるの?」と問う。
そんな現実に憤りを感じていたさとくんだったが、
鍵をかけて隔離され、糞に塗れた重度の障害者の「臭い」を感じたとき
ようこ達は目を背けて
さとくんはそっと扉を閉じた。
中に入り助けてあげるには、とても勇気のいる状態だった。
彼は、“みんな同じ人間だ”と尊重していた人だった。
「自分とは違う」「関わりたくない」
しかし、あまりにショッキングな光景に
自分の中に社会全体の本音と同じ気持ちがあることに気づいてしまった。
その状況に心が折れてしまったのだろう。
みたくない現実から目を背けようとはしない映画。
ところで、なにかを成すことができなければ
生きてる意味ってないのだろうか?
稀代の殺人鬼だろ?て話
闇堕ち青年のジェノサイド物語とゆう評価もありますが
私は生まれきっての、稀代の殺人鬼物語とゆう見解です。
何故障がい者施設でいじめられながらも、低賃金で働き続けたのか
何故、彼女が聾唖の女性なのか
何故、心無い障がい者は生産性が無いとゆう考えに行き着いたのか
はなから目的は殺人です。
芸術肌の殺人鬼なので
殺しに理由を
殺しとゆう作品に、理由とゆう脚色を付けたいがために立ち回り続けてきたのです。
障がい者とゆう、身体的に自分より弱い立場のものは物理的に健常者より手にかけやすい
いつでも手にかけれる状況で理由を探し続けていました。
聾唖の女性を彼女に選んだのもそういった理由からです。
家でも外でも常に殺せる状況を築き上げていました。
ただ、彼は自分でゆうとおりバカでした。
殺す理由を探しきれずにいた中、元作家とゆう
芸術肌の洋子と巡り合いました。
芸術肌の殺人鬼にとってそれは、殺す理由を探すトリガーとなったのです。
綺麗事で、他人事でものを見るなとゆう描写、表現がたくさんありました。
殺人鬼もそう言っていましたが、彼は自分でゆうとおりバカなので
他人事をなんの権利があってか、自分の事のように生殺与奪の権を握ります。
冨岡義勇がいたならば真っ先に水面切りで真っ二つです。
こいつは稀代の殺人鬼です。
猗窩座でさえ生まれきっての鬼ではありません。
障がい施設当事者です。
十余年になります。である前にいち映画ファンです。まず思ったのは、「詰め込みすぎ」。重い題材が3つ。震災、出産前診断、そして今事件。さらにななめ上いく設定(映像作家の夫と昔名をはせた作家妻、&作家志望の施設職員、ろう者、宗教一家まで)。原作の本がそうなんでしょうが、前知識なしに見始めた時のフィクション感強めのバランスがまず気になった。ラストの「あなたが好きです」これで題材4、家族再生も加わり、焦点がぼやけてる印象。以上がマイナス点かな。
プラス点は犯人が変わりゆく様(多分リアリティがあるんでしょ?)や、彼との交流や妊娠を通して自問自答する主人公、そのロジック、自己矛盾。なにより知的障がい者の実演と厳しい現実、支援困難事例の描写、これは前代未聞で素晴らしいと思った。
以上、総評で星3という印象。バランス的にドキュメンタリー寄りの作品が見たかったが原作を抽出するとこうなったんだろうと推測する。
ちなみにこの事件を通して私が思ったのは、「1、みんな年老いて、生産性が無くなる(ほぼ)。その時植松被告は、自死を選べるのか。私はどうか。2、生産性があること、人、集団を是としているが、それ自体に意味はあるのか?人間社会の存在意義。」等かな。
うーん難しいわ。
仕事探しをしている時に、障がい者施設の仕事に興味を持ったことがある。けど、この映画みて
自分には無理だと思った。
この環境で働いていたら精神もたないし、考え方がおかしくなると思う。
さとくんの言葉、人間の心の底の本心。
みんな本当はそう思っているけど、言わない。
でも、その人の人生を奪っていいとはならない。
ちょっと前に、老人ホームだっけ?実際にあったよね。
さとくんの異変を
ようこさんがなんで気づけたのかわからないけど
みんな「嘘」の世の中で生きているというのは
確かだなーと思った。
この映画は見ている人に何を伝えたいんだろ?
難しいわー🤨
テーマは何?
あの事件を題材にした作品だと思い出したのが半分ぐらい見てからだった。なにせ主人公夫婦の苦悩を中心に描いていると思っちゃっていた。だからなのか何がテーマなのか分からなくなり、思考がとっ散らかってしまった
実際の犯人のその動機に至った経緯って、毎日毎日施設で働いてのとてつもない大変さからくるストレスの連続、と思うのは考えるに容易いと思うのです。障害者施設の闇もあったかもしれないし。それを思想に変換させて作品にした事は、どうなのかな⋯。事件について詳しくないので何とも言えませんが。
事件後と回転寿司屋のラストシーン、寿司の身、告白、ちょっとふざけちゃってるのかもと思いました。
こういうテーマなのに耳の聞こえない人が口を読む事を知らないような表現が2度出てきてビックリした。
犯人の言葉に...
実際にあった障害者大量殺人事件を基にしてるものと推定されます。この映画ハッキリ言って冒頭から重すぎます。ずっしりと重いです。こんな重い展開とテーマで映画というエンタメとして成り立つのかとも思えました。しかしこの映画は社会派映画として見る人の心に訴えかけるものがある。犯人は言います。心がないやつ(意思疎通が出来ない)は人じゃないと。反論する主人公に犯人は問い掛けます。ゴキブリは殺しますよねと。障害者に対して汚いとか臭いとかいなくなればいいのにとか少しでも思った事ありませんかと。その言葉に自分は絶対無いとは言い切れない自分がいたことに恐怖を覚えてしまった。実行することはしないが脳内ではそう望んでる自分がいるのではないかと。実際にああいう施設で働いてるとそういう考えが芽生えても仕方ない部分もあるのかなと。本当に怖い映画です。フィクションだが命の大切さとか簡単に単純に言えない映画でした。
ただただ胸が苦しくなる
実際にあった事件を元にした映画。さとくんが障害者は要らないと思うに至るまでが軽い。師匠のダンナが映画で賞を取るのはいらない。そんな仕事してる場面が一つもないから。結局、こんな酷いニュースがありました。で終わり。障害者の気持ち、親の気持ち、同僚の気持ち、健常者はどう向き合っていくのか、健常者と言われる人はそんなに偉いのか、介護施設職員のメンタルをどう救っていくのか観客に丸投げのまま。
久しぶりに圧倒的された映画でした
宮澤りえさんが主役ですが、宮澤さんが、美人じゃなくて、肌が汚くて、おばちゃん体型で、性的な魅力を感じられなくて、という役を見事に演じられていて、それが本当に良かったです。
素晴らしい役者になりましたね、宮澤りえさん。
磯村勇斗さんも、とても良かった。
話も演技も、久しぶりに圧倒的された映画でした。
それにしても、怖い映画でした。
ホラー的な要素ではなくて。
心が無いのは人間ではないのか…
重く、苦しいテーマ。障がい者、自分だったら幸せなのか、家族であったら恥ずかしくないのか、隠したくないのか、生まれてほしくないのか、居なくなってほしいのか、意思疎通できないのは心がないのか、邪魔だと思わないのか。タブー視される障がい者へのそんな気持ち。それを知らないで言うのは所詮、綺麗事。当然、殺人は論外だが、誰もが思うことがある、人間の闇を描いた映画だった。人間の闇でもあり、それを軌道修正するも、また人間だと思う。
花は花で有るように
アマ2人プラにて視聴
途中きつくなって観るのやめようかと思った
社会的テーマと実在の事件を結びつけたいのはわかるが散らかってて本題軽視 軽視してるのに妙にグロい重い演出ちょいちょい入れてくる。
さとくん(植松)の事件に至った心情が描かれず、聾唖の彼女を労るかっこいい描かれ方してる謎
そして主演の宮沢りえ
一回も笑わなかった 強いて言えば旦那役のオダギリジョーがフランスのなんだかで入賞したことで喜んでた時くらいか
施設で働いていたらそんなに辛いことばかりなんでしょうかね
同僚のイジメ男2人もなんでそんな仕事やってるのか理解不能
嘘がどうとかいうけれど嘘で塗り固めたまさしく切って貼ったような月のような散らかったシーン多い
結局さ、実在の大きい事件を利用としただけなんだよ。視聴側のインパクトのためにね。
出演者が著名で良い俳優陣だからこそ残念
偽善を否定するからこそこれが本物の正義だ、と主張する偽善(ややこしい)
特に後半はスローペース。音と臭いとか必要とか言うシーン入れてくるなら入所者の断末魔の悲鳴声入れるべき。
あかずのとびら開いたら汚物まみれの入所者のマスターベーションしてたとか必要か?別にそんなの見たくないしこれが現実だってえがかれても生理的に無理なだけで現実直視をしてないってことにはならんやろ。ただの面白エピソードだし
落ちが雑にぶつ切り。むしろその事件後の入所者家族や職員のケアまでえがくべきだったのでは
機械に奪われない仕事ランキング上位
「ゴキブリが出たら殺すでしょ?」
劇中、サトくん(磯村勇斗)が重度障害者の事を
ゴキブリに例え、精神的な限界に達した時に
言い放った言葉。
ですが仮にゴキブリだとしても、人間がお金を払い
「このゴキブリは殺してはダメです。」
と言えば、そのゴキブリは殺してはいけません。
そういうシステムです。
"一般的な能力"と言われる物差しが、少し高く感じる現代
受賞歴のある小説家、魅力的な絵が描ける青年、リアルマニア、
コマ撮りアニメを作れるイケメン、等
私より遥かに才能に溢れた人間であっても
職業カーストの下層 と、されてしまう仕事に従事する
人間は少なく無いと思います。
言い方は悪いですが
社会のシステムとして、下層グループ側になってしまった
比較的健康な人間を許容する事の出来る職業、というのは
人間社会である限り必要必至であり、職業需要を生み出して
いかなければいけないのだと
それっぽい事を言う事はできますが
当人的にはそういう事では無いのだと
正論がどうだとか、堪ったものではない のだと思います。
ストレス濃度が高い職業は
ストレスから視野狭窄になりがちで、物事を俯瞰で見る事が
難しくなっていきます。
頭の良し悪しに関係無く、極端な発想に傾倒してしまうのは
仕方がないのだと思います。
月並みな意見にはなりますが、せめて職場の人間関係は良好に、
助け合って生きていきたいです。
職業偏見も、せめて声に出して傷つけ無いで欲しいものですね。
「頭お花畑かよ、ハハハ!」
と一蹴されてしまうのかも。
ですが、この作品に関してのサトくん(磯村勇斗)は周りの人間、
特に先輩方に優しさがあれば何とか防げた事件かもしれない。
この作品において最もドス黒い感情を抱いたのは先輩方です。
もう怒り心頭が止まりません。
それとも職場のストレスであのような性格になってしまった
ということなのでしょうか…
やはりあのキャラクター達にかけてあげられる言葉は無くて…
同じ職業に就いても、後輩の立場故に強く言っても変わらないし
陽子(二階堂ふみ)は本音が強い人間だと理解してあげても酒で
やられるだろうし、サトくんも人間の本質で納得のいく回答を
答えてあげられず、仕事のストレスでどの道ハッパでイカれちまう。
高齢出産は件は夫さんと話して頂くしか無いし、その辺のストレス
で微妙な心理状況だし…
この職場は遅効性の毒かいな
丁寧に詰んだ状況だなこりゃ…
昌平(オダギリジョー)さんのように
ギリギリでも前向きに
それが難しいけど一番大事だと、そういう事でしょうか。
多くの方々が知っている事かもしれませんが
月の裏側は起伏が激しく見た目が悪いそうですね。
扉一つ、丸い窓の後ろには隠したい事柄がある。
そう勝手に捉え
お酒は飲めないから紅茶で気持ちよくなろうと思います。
あとアクション映画みたいなカメラワークになる所も
結構好みで気持ちいいです。
最後に
従事者の方々には頭が下がる想いです。
必死に働く人間と、何かに必死で打ち込んでる人間は
称賛されるべき、なんだと思います。
もっともっと欲しかった
施設の闇の部分が事件のきっかけというか、トリガーというかになるので、その部分を表現しようとしていると思うのですが、闇というか現実の刺激的な部分を表していて、もう少し現実の悪い部分、良い部分織り交ぜて、施設の本質を表現して欲しかったように思います。
それと、さとくんとのやり取りで「認めない」としか反論出来ないのは、辛い経験をしてきた、なおかつ過去に認められたこともある小説家としては物足りないようにも感じました。
制作者側からの意見の押し付けにならないような思いがあるのかもしれないけど、登場人物の一つの意見として、また敢えての製作者側か監督さん自身の意見としてでも、考えを述べて欲しかったとも思います。
正解が何か誰にも判断できないし、繊細な問題で何を言っても反論が出るかもしれないけど、表現者として、そこは意見を発信するべきじゃないのかなと。
最後の昼間の月で発信しているのかとも思えるんだけど、それだと弱いし、遠慮し過ぎにも感じる。
全般的には良さげだけど、もっと踏み込んで欲しいかったなあ。
『選別』すれば必要のないものが必ず生まれる
今のこの社会の尺度で計れば誰もが思うこと。
当事者にならなければ他人は一生悩む事も苦しむ事もないのも事実。
すごく真っ当な事。
でも知ってしまえば⋯⋯何かを変える事が出来るのか。おそらく変わりはせず変えることも出来ないだろう。
さとくんのセリフには耳を塞ぎたくなる理想や現実も多々あった。
モデルとなった事件の被害者の氏名の非公開なども色々な事情などがある事がこの作品の答えの一つと言える。
とても重く辛いテーマに主人公のバックグラウンドを絡めて見えない事や理解しがたい部分を噛み砕いたのがいい。
誰も見たことのない月の裏側を見せてくれた作品。
いつの日かこの作品の答えが、誰もが納得のいく答えが月明かりではなく太陽の下に照らされる社会になればいいと願います。
終わり方が不満
実際の事件を元にされた映画。
犯行の様子は、わりと忠実な感じにしたようですね。
犯行が行われ、ニュースを見てるとこで終わるのはちょっと中途半端か、
その後ももう少し見たかった気がしました。
重いテーマ×重いテーマ
実話を元にした小説の映画化ということですが、胸が苦しくなるほど
重たい作品ですね。障がい者施設ことと夫婦のこと。二つのテーマ(話)が
交差してるって気がして、それが個人的には気に入らなかった。
夫婦のこと、高齢出産やそれに伴うリスク、子を亡くす悲しみ……
それだけでも重たいテーマなのに、施設の問題と絡めるのはどうなんだろうな。
個別に描いて、問題提起してほしいな、と感じました。
なんか、救いがないんですよね、この映画。つらくなるだけ。
なぜさとくん?
森の中に隠されて存在するかのような重度障害者施設。
そこで以前勤務していた元職員が、神の代わりに自分がと話せない意思の疎通ができない入所者を殺害した事件。
元々からあった障害者への差別意識、
自身の彼女とは一線を画し意思の無い者は人でない考え、
大麻等麻薬により精神に異常を来たしていた、
日常の勤務からの凄惨な状況からの不安定な心理状態、
同僚からのイジメ、がひき起こしたのだろうか?
話せない意思を持たない者は人ではないのか⁉️
対比なのか、
同僚洋子は大震災をテーマにした小説で世に出ながら
その後作品が書けなくなっている。
小説が売れないからと障害者施設に勤めに来た。
ここの理由が判然としないが。
夫昌平と二人暮らし、
息子翔一を低酸素脳症で3歳で失ってしまい
夫婦共にその傷あとが癒えていない。
この息子も何も話せなかった。
また洋子は妊娠しているが産むことに躊躇っている。
出産前検査を受けるかどうかも考えている。
堕ろすという出産前の胎児を亡き者にすることも、
殺人と同じことだと、
出産前検査で障害等が見つかったから産まない選択と
何ら変わりはない、と言われていたような。
施設の同僚さとくんは絵が上手くて紙芝居を作り話すが、
臭くて汚いモノをなくそうと言い、
ラストに お爺さんが犬を殺す 設定にしていたが、
🌸花咲か爺さんの話、どうだったかな?
このさとくん、🇯🇵の死刑の際の絶命の様子にも詳しい。
犯人役だなとわかった。
入所者に虐待もしさとくんを虐めて来る同僚なんかは
ある意味チャランポランでコイツらじゃない。
とても自分でこれが正しいと言える言葉が見つからない。
きーくんの母が泣き叫んでいたこともほんとなら
多分亡くなった方にショックを受けてないところも
あるのだろうなあ。
子供さん葬儀後の焼き場のショック‼️
大人子供に関わらず辛い瞬間。
ましてやこの子胃ろうだったとか。楽しみって何だったのか。
嘘だらけの世界の中で、誤った真実に染まる時・・・
実際に起こった犯罪を基に作られた作品、結構見ます。こんな事言うと、危ない人に思われるかもしれないけど、好きなんだからしょうがない。
まぁ、あくまでエンターテイメントとして楽しんでいるんですが、本作品は予想をはるかに超えてました。 何度も見たいって思う作品じゃないけど、面白かった。そして、考えさせられます。ズッシ〜〜ンって感じで、胸が苦しくなって、思いっ切り疲れました。
森の奥にある重度障がい者の施設で働くこととなった元人気作家の堂島洋子(宮沢りえ)。さとくん(磯村勇斗)や陽子(二階堂ふみ)という同僚と出会い、様々な障がいを持つ人達に触れる事で、自分の中の何かが変わっていくのを感じる。
しかし、それに併せ、この重度障がい者施設には、表に出てこない暗部があった・・・
宮沢さんを始めとする豪華で芸達者な役者陣に圧倒されます。
ちょっとしか出てきませんが高畑さんの一言に泣かされました。
【ネタバレ】
とにかく、磯村さんの壊れっぷりが凄まじい。元々、彼が殺人鬼?を演じるって事で、ホラー感覚で見始めたんだけど、とんでもない誤算でした。確かに血塗れにはなりますが、直接的な描写はなかったんじゃないかな。だから尚更、そこに行き着くまでの過程が恐ろしい。
最初から、ちょっと変わった雰囲気を漂わせてはいたんだけど、軟禁されていた障がい者を見た途端、キレちゃった。
話が出来ないという事は、心が無いということで、ヒトとして認められない。ヒトでない者は生きている資格がないから、この世から消してしまおう・・・
この考えに固執されていく。
精神科で治療を受けたみたいだけど、思想が変わることはない。自分は正しいと思い込んでいる。
周りにおかしな人ばかりいると、普通でいる自分を変だと感じてしまうこともあるらしい。
障がい者に対しては、自分も恐怖を感じることがある。身の周りにいるわけではないが、同じ電車に乗る時など近づかないようにしてしまう。やはり、何を考えているのか解らないのは、自分の思いも伝わらないと感じてしまい、何をされるかわからないという偏見を持ってしまう。
だからって、即排除とまではいかないが、違う目で見てしまうという事は否定できない・・・
そんな自分を恥じながらも、どうしようもない虚無感に落ち込んだ一本でした。
覚悟して観ましたが…
題材となった事件はリアルタイムで知っていたし、周りに障害者福祉施設で働く方もいます。
なので、心して鑑賞に臨みました。
とにかく最初の方から
「嘘」だらけの会話が怖くて怖くて。
特に
「あなたには話せるような気がする」
いやいや、それはダメでしょう…とか。
144分の中には、いろんなテーマが提示されていました。
その感想はそれぞれがそれぞれに違うような気がします。
シンプルに私が思ったことは
人間という生き物は決して特別ではないのだな
っていうことでした。
高畑淳子さんが最後、
全てかっさらっていったような気もしました。
タイトルなし(ネタバレ)
UNEXTで鑑賞🎥
すごく胸が痛くなる映画でした。
実話の事件を元にした映画で
だからといって殺していいわけでは
ないけどなあ。
終始暗かったです🥲
全82件中、1~20件目を表示