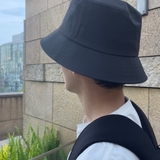月のレビュー・感想・評価
全287件中、141~160件目を表示
人の心とは
実際にあった障害者施設殺傷事件をモチーフにした作品。
カメラワークがちょっと特殊なのと、画面が暗めなので序盤から不気味な雰囲気が満載。
似たようなテーマのロストケアより犯人となる人物を丁寧に描写している。
実際の犯人を忠実に再現したらしく、より生々しく事件を浮かび上がらせている。
事件を起こす直前のさとくんと宮沢りえとの対峙シーンは必見。
さとくんと話しながら自問自答しつつ答えのでない問題に何とか答えようとする。
心がない人は人ではないと言い切るさとくん。
意思疎通ができなければ心がないと言い切れるのか。
精神科の施設に入れられても変わることなく早々に出てきてしまったのは現実の対応力の限界か。
重いテーマだが少しだけ希望のある終わり方だったのが救い。
回転寿司
人間とは?
2016年、やまゆり園における植松聖の為したことをモチーフとして描かれた本作。まだ記憶に新しく、自身がどう感じ何を考えたのか、今どう考えているのか、一定の年齢に達した者ならば皆が思考できるだろう。
今、障害者に関する施策は施設から地域へと題され、施設に収容して日常生活を送ることからの脱却を希求している。そのためにはマンパワーが絶対的に必要なのだが、生産年齢人口の減少が明らかに見込まれるこの国、社会福祉にかけられる予算も脆弱なこの国で可能なのか?という思いは拭えない。脱施設によって、結果家族への負荷が日常になるような。
人間って何ですか?と周囲に問いかけ、あなたは今幸せですか?と障害を有する者たちに問うて回る元施設従業員・さとくん。行動障害を有する者は、関わり方次第でその障害の発現も軽減するが、周囲の者が100%その障害に気を使える者ばかりではない。自身の子どもが突然噛まれたり叩かれたりすることを許容できる親は多くないだろう。それでもなお共生を模索しなければならないのは、理屈としては分かっているが、どこまでできるか?私には自信がない。
どの命も大切だが、時と場合によっては、という思考が私には確実にある。私はそんなに善人ではないのだろう。それでもなお、そこから目を逸らさずに、難しい答えのない問いを死ぬまで考え続けていくこと。その覚悟だけは持っておきたい。安易な答えに飛びついてしまうことなく。
チャレンジングな映画だが、障害者施設殺傷事件そのものの考察からは逃げた脚本の印象
石井裕也 監督による2023年製作(144分/PG12)の日本映画。配給:スターサンズ
劇場公開日:2023年10月13日
相模原障害者施設殺傷事件を題材にした辺見庸の「月」を原作とする映画。「新聞記者」や妖怪の孫」で知られる河村光庸氏(2022年6月心不全で死亡)が企画。
重要だが難しく映画にしにくいテーマに取り組んだ、とてもチャレンジングな映画とは思った。作家役の宮沢りえによる東日本大震災を題材にした小説が綺麗ごとだと二階堂ふみに語らせ、この映画は綺麗な表面的描写にとどまらないぞという石井裕也脚本・監督の意気込みはこちらに伝わってきた。
そして、この原作を映画化するにあたって、石井監督が苦闘した結果が、原作には無い宮沢りえとオダギリジョー夫婦の設定ということらしい。彼ら夫婦の子供は、心臓に障害があり3歳で亡くなってしまった。ずっとベッドで寝たきりで、全く言葉も発することなく亡くなってしまった存在。それは、意思さえ示せない障害者を社会にとって無用なものと決めつけて殺害した優生思想へのアンチテーゼとなっている。息子は懸命に生きようとしていたと訴える、オダギリの言葉は胸に刺さった。
子供の死をずっと引き摺って引き裂かれそうになっていた夫婦が、新たな妊娠を得、障害者出産の恐怖にも打ち勝ち、二人で新たな関係性で生きていこうとする姿は、二人の好演もありかなり感動的ではあった。妻はずっと書けなかった著作を再開し、夫はずっと制作し続けてきたアニメーションで受賞し、創作者としての石井監督自身の拘りの様なものも感じた。
しかし、この夫婦再生の物語と障害者の殺人事件とは基本的には全く別物で、暗いこの事件に真っ正面からたち向かうことからは逃げて、希望のある話題を無理矢理とくっつけた印象を持ってしまった。聖書の「かつてあったことは、これからもあり かつて起こったことは、これからも起こる」(旧約聖書「コヘレトの言葉」)が、宮沢りえの障害者出産への恐怖の増幅、即ち個人的出来事の再現に矮小化されてしまう様なつくりも、とても残念に思えた。
宮沢りえの言葉を発せない障害者との対話、障害者も大切にすべき vs 障害者と関わりたくないのせめぎ合いは、石井監督自身の葛藤の正直な吐露の様に思えた。そして、監督自身が充分に消化しきれていないものをそのまま観客に提示するのは、自分の好みでは無いことを改めて感じさせられた。もう少し、題材と真正面から格闘した末のものが欲しかった。
障害者思いの生真面目な施設職員の青年が、国のためと使命感を持って障害者を次々と殺害する人間に変貌するさまを見事に演じていた磯村優斗の演技は、強く印象に残った。ヤクに手を出していた等、殺人犯の描写も現実には則していた様。ただ、彼の優生思想がどこから来たのかは不明で、モヤモヤ感は残った。綺麗事に嫌悪感を持ち磯村の殺人の立ち会わされる女性職員を、ほぼノーメイクで演じた二階堂ふみにも女優としての心意気の様なものを感じた。それだけに、ラストの回転寿司の皿に乗った3つの寿司でりえ家族の幸せを暗示し、事件の本質的部分との格闘から逃げた様にも見えた石井裕也脚本には、とても残念な思いが残った。
監督石井裕也、原作辺見庸、脚本石井裕也、企画河村光庸、エグゼクティブプロデューサー
河村光庸、製作伊達百合 、竹内力、プロデューサー長井龍 、永井拓郎、アソシエイトプロデューサー堀慎太郎 、行実良、撮影鎌苅洋一、照明長田達也、録音高須賀健吾、美術原田満生、美術プロデューサー堀明元紀、装飾石上淳一、衣装宮本まさ江、ヘアメイク豊川京子、
ヘアメイク(宮沢りえ)千葉友子、特殊メイクスーパーバイザー江川悦子、編集早野亮、
VFXプロデューサー赤羽智史、音響効果柴崎憲治、音楽岩代太郎、特機石塚新、助監督
成瀬朋一、制作担当高明、キャスティング田端利江。
出演
宮沢りえ堂島洋子、磯村勇斗さとくん、長井恵里、大塚ヒロタ、笠原秀幸、板谷由夏、
モロ師岡、鶴見辰吾、原日出子、高畑淳子、二階堂ふみ陽子、オダギリジョー昌平。
見てもらいたい映画の一つ
見終わったあと、ものすごく疲れました。
色んなことを考えながら見たからかもしれません。答えは出ない…出ないと思います。
いろいろな人生で、経験したこともそれぞれ違うし、考え方も違うので。
でも、沢山の人に見てもらいたい映画の一つ。
俳優、製作者、この映画に携わった方達に感謝いたします。
演者の覚悟を感じる
問題提起になる作品だろう
障害者施設を舞台にした作品。おそらくあの事件に少なからず影響を受けているだろう。とても難しいテーマだし,見る人の立場によって色々な意見もあると思う。
私はこの映画で,改めて考えさせられた。
障害のある人との暮らしとは、自分の子供や親がそうだったらどうするか。
磯村の壊れている演技は、恐ろしかった。ああいう人は,きっと普通にいて、でもちょっと付き合ってるだけだとわからないのかもとおもう。
子供を病気で亡くした夫婦が、お互いを労わり合い,それゆえぎこちなく暮らす毎日。小説を書けなくなった妻を尊敬し支える夫。どちらかと言うとチャラい役の似合いそうなオダギリジョーの静かで誠実な演技に引き込まれた。
2人がこれから選択する道はどうなるかわからないけれど、希望を感じさせてくれたことは救いだった。
賛否両論ある作品を遂に観に行けた。
俺個人としては良かったと思う。
殺しの描写も酷いものではなかったし、
俺、自身いつも感じていた感覚だった。
自分は何のために生きているのか?
この世は地獄だ、そんな中でも自分らしく楽しく生きていかなければならない。
社会福祉の資格を取る為の実習で過去に就労支援施設で実習を30日間行った事がある。
その先で支援員の仕事をしたいと考えた事もあった、未だ資格が取れていないので叶っていないけれど…今は介護士として働いている。高齢者の分野でも同じ様な事は多く見てきた、未だに答えは分からない、、でも生きてくれている事で生きようと頑張る支援者の親が居る事もたくさん見てきた。それが自分の立場だったら?といつも考える。
あの事件はあくまでもキッカケにすぎない、、事件自体はとても残念な事ではあるけど社会が隠して行こうとしている事実は受け止めなければならない。
そして何もしないし見ようともしない人達が当たり前に居るのも現実だ。
どちらが健常者で障害者かを常に今の世の中が勝手に決めているだけだと俺はいつもそう思う。
同じ健常者を見ても嫌悪感を感じる存在は山ほどいる世の中で、、自分はどう生きて行こうかと改めて思わせてもらった気がする。
とことん"現実"を突き詰めた作品???
タイトルの末尾に???を付けたのは、さすがに無理があるんじゃ…って思ったからです。
*このような施設を訪問したことは無いので、入居者の方々の表現については触れません。
さすがに施設の場所を山奥すぎませんかマップで調べてみたら普通に県道沿いにありました。マイナスな面を表現したいのはわかりますが、あまりにも露骨過ぎると思いました。
また、主人公の小説家という設定は必要だったのかな?って感じました。確かにその方がキャッチーだし、様々な感情を表現するのが容易になるけど、実際職員さんの中にいらっしゃったのかな?
主人公→理想や非現実(震災の見たくないものを表現しない、亡くなった息子のことばかりなど)、
他の職員→現実(才能がない、読み聞かせは意味が無い、暴力を振るう)
という対比で物語が続く中で、小説家という設定がすごく物語を複雑にしているんじゃないかとずっと考えていました。
とにかく観ることが出来て良かったです。
でももう絶対に観たくないです。
描き方に疑問
元重度最重度知的障がい者施設の職員でしたので、この映画は観ないといけないと思い、観てきました。
まずは、施設の環境の描き方がマイナスの面だけを誇張して描かれていることが、とても残念です。映画のテーマに合わせてプラスの面はあえて捨てたのだとは想像しますが、現実もこうであろうと観た方が誤解されないか、悲しくなります。
パンフレットには、石井監督のインタビューの中に、「この映画で描いた、障害者施設で起こっていることに関しては、全部事実です。障害者施設の中のことに関しては、絶対に嘘はつくまいと思って、事実としてあったことしか描かないと決めていました。」「もちろん、僕が実際に見たのはそういう劣悪な環境の施設ばかりではありませんし、いままで問題があった施設でも、日々改善の努力がなされていることはきちんと協調しておきたいです。」と書かれていました。
監督が言われているように、プラスもマイナスも両面あるんです。それなのに、いろんな施設のマイナスのことだけ集めて、さも津久井やまゆり園の状況のように描くのはひどいです。
私も津久井やまゆり園の現状は、正直分かりません。でも、一度見学した際は、あんなに暗くないし、利用者さんはもっと部屋から出て過ごされていたり、日中活動をされていたりします。笑顔で快適な時間も当然あると思います。スタッフが支援する必要があるので、スタッフ同士であんなにゆっくり話している時間がないと思います。あと、同性介護も徹底されていると思います。施設の場所は自然豊かなところですが、あんな暗い森を超えないといけない場所ではありません。普通に県道沿いです。
一方で、一般的に知的障がい者の施設が、交通の便の悪いところにあり、たくさんの知的障がい者が大規模施設に入所し、地域で暮らすことができず、施設の中で心ない虐待にあってしまうこともまた事実であろうと思います。
なので、この映画が難しいテーマについて問題提起してくれたことについては、敬意を表したいと心から思いますが、あの事件を題材しているのならば、関係者を再度傷つけかねない表現は絶対に避けてほしかったと思うのです。
あとは、この映画を観て、自分自身の内面で起きたことを書かせてもらいます。
以前、施設で働いていた時のことを思い出しました。映画の中で描かれていたように、利用者さんは自傷が止まらなかったり、声を出し続けていたり、私自身が嚙まれたり、排泄物を投げられたりもありました。私の心の中で、怒りや憎しみが湧いたことがあったのも覚えています。自分の中の嫌な面をすごく体験させられました。キャパシティの狭い、優しくない、結局自分が大事で、楽をしたい、ズルい自分を痛感させられました。だから、この映画をみてそんな自分を思い出してきつかったです。それでも、チームで支援を考えて実践する中で、利用者さんの笑顔が増えたり、不快な声が減ったりしていくことも経験しました。心がないと映画の中で言われていましたが、私が出会った方達はみなさん本当に感受性が豊かでとても個性的でした。何年経っても忘れないです。元気に生きていて欲しいです。
自分自身の中に、悪意も好意も両方あり、その自分を見つめ、できることを見極めてやっていくことが大事なのかなと今は納めています。悪意はあってもいいと許すようにしています。いけないのは行為に出てしまうことなのです。
いろんな意味で心が動かされたので、ほとんど書いたことのない映画レビューを書かせてもらいました。
一生整理はつかないだろう
月とは、、
7年前に実際に起きた事件を元に作られた作品だが、フィクションとして成り立っているも
のの、やはり実際に起こった事件とは切りはなせない。
人間は自分以外のものを攻撃する生き物、特に弱者へと向きやすいもの。
障がい者施設での職員と入所者においても悲しいことにその構図が成り立っている。
かつては優生思想が幅を利かせていた時代、それに異議を唱える声はかきけされていた。
今はそうではない、と誰が言えるか、今でもその思想が私たちの心の奥底に潜んでいる、そして何かをきっかけにむくむくとあらわになる。例えば貧困、不幸、思い通りに行かない人生などをきっかけとして。
しかし、自分が嫌なものを排除する資格はない、目を背け見ないようにする、存在を否定する、それできるかもしれない。でもそれは事実ではないし、事実そこに人は存在する。
事実とどう向き合うべきか。
自分がもし障がい者だったら、と考えるのが一番単純で分かりやすいのかもしれない。
自分の身内が、とかでもいい。
月は太陽によって光る。太陽なければ月は暗い物体でしかない。
人もまた月のように 他者との関わりで光り輝く。自ら輝いているように見える人でも同じだ、人を輝かせることができる人こそ幸いなのだろう。
考えさせられるけど答えは出ない
石井裕也監督作品はわりと好きで見ています。たまたま同じ日に『愛にイナズマ』を見てから『月』を見ました。
全く別物のかなり重い作品。
施設の職員として、入所している障害者として、障害者の親として…感じ方は全く違うでしょうし誰が正しいとかもない。施設内での虐待やイジメはあってはならないし、どんな理由があろうと殺人は許されない。
しかしそういう世界に目を向けていなかった自分は何も言えないな。
どなたかのレビューにもあったけど、宮沢りえじゃなかったら見なかったしオダギリジョーがいなかったらもっともっと重い作品になっていたと思う。
闇を照らす 【追記済み11月7日】
フィクションとしても耐え難い描写が並ぶ本作は、モチーフになった事件が永遠に忘れ去られることのないように道を探すため、相当の覚悟で照らす〝月〟になったのだろう。
主人公夫妻の物語に絡めてひとの気持ちのちいさな単位が集まり成り立つ社会の闇の部分をはっきりと突きつけられ、立ち止まらずにいられる人がどのくらいいるのだろうか。
【追記】
哀しみの過去、思うように進まない現在を労わりあうように暮らす夫妻にとって、洋子があの対峙で深く自分に向き合ったことがどう作用したか。
事件に沿わせてひとつの夫妻の人生のシーンを描くことの意義は少なからずその流れを感じとるところにあるようにおもうのだ。
もちろん誰もが同じ境遇や状況ではないが、何かをきっかけに自分の心に向き合うことの大切さがニュースを知ったふたりの行動がそれまでと違うところから見えてくる。
そして、答えをみせずに終わるラストは、それに至る誠実な向き合い方に意味があると言っているような気がしてならない。
照らされるべき闇はまだまだ深く無数だ。
社会の1ピースである私たちのこのあとの人生も続く。
並んでいく時間にいる。
何を捉えてどうすごすか。
強く厳しく問う作品だ。
……………
【洋子と昌平】
冒頭から感じる夫妻は、お互いに相手を思い自分の気持ちは奥へやる。
妻・洋子は、あえて光があたりにくい場所に佇むことで過去をそっと包みこんで何かを守っているかにみえた。
夫・昌平には耐え難いだろうと考え、新たな妊娠を告げることを躊躇するのだが、それは彼女が持つトラウマの深さでもあろう。
はじめて介護の仕事につき疲弊をためながらも家計を支え、昌平に夢を叶えさせたいという気持ちと現実的な生活の切実さ。
後半、彼の作品の入賞を知ったときの体の奥から込み上げてくるようなほっとした泣き笑いに、それまでのすべての感情の解放がある。
ひとり呑み込んできたものの深さが堤防を決壊した川の水のごとく頬の皺を越えて流れ落ちる姿を宮沢さんが鳥肌が立つほどの演技でみせる。
一方、昌平がどこか気楽そうにみえるのは、そうみせているからだ。
洋子に深刻さを見せないようにする彼なりの愛情と優しい人柄なのだと思う。
それでなければ、妻が辛い思いを蒸し返さないように捨てられた三輪車の前で必ず覆い立ち隠す姿はない。
妻に小説を書く意思がでてくると察知し環境を整え協力できるのは、状況をきちんと把握しているからだし、
自分一人でいるときにだけ息子の写真を眺めるのも妻に負担をかけずにいたい妻子への気持ち。
嫌味な職場の先輩にいらついても未来を考えぐっと我慢し、妻をおびやかす危険を感じればすぐに自分が盾になって守る。
そして、妻から妊娠を打ち明けられ歓喜する姿や賞を獲り安堵する様子は、封印されてたきっと本来の姿だ。オダギリジョーがもつ抜群に自然体なのびやかさがやさしく穏やかな愛を伝え涙を誘う。
【洋子の同僚、陽子とさとくん】
施設にはじめて来た洋子を明るく出迎えた人懐っこい陽子。
職場を案内しながら、不安気な洋子に笑顔でここは「誰もが平等」だと言った。しかし陽子もあきらめられない夢を胸に職場の裏腹な現実を黙認し、家庭でも同様に父の裏切りにあきれ、爆発寸前な心理状態で酔えば悪態をつく。
日々、自分がつく嘘や理不尽さでストレスにゆがめられていく眉。
酒を飲み干す様子には、コントロールできない状況の苛立ちや嫌悪が隠せない。
洋子の内心を見透かすような顔つきで自分と似ていると言ったのは牽制なのかもしれない。小説家として名を馳せた洋子に対する嫉妬心や対抗心が、うまく行かない自分の焦りを煽り皮肉めいた発言もしてしまう。
世間から閉ざされたような施設から薄暗い帰路を行く陽子の真っ赤な服の後ろ姿は、夢とは遠い現実にいながら意地を保つための武装にもみえた。
誠実で温厚、真面目に働く印象のさとくんが、事件を起こす危うい思考に囚われていく過程に施設の入所者への対応に疑問を持ちながら、洋子のように相手にされなかったことがある。
あがいても変わらない行き詰まりを味わい続けた正義感は方向を間違えて増大していく。
また、彼の挫折を同僚はそのきっかけと呼んでいたがどうか。責任の所在をきめつけて、我が身を振り返らない周りがつくる危うい構造もまる見えだったように思う。
得意な絵を活かして紙芝居をした時に1番好きなシーンだと言いながら、いらないものがザクザクと出てくる絵を彼はやたらと強調した。
さとくんはきっと感じたかったのだとおもう。
そして彼らにも感じて欲しかったのだ。
自分が置かれ、扱われている状況にもっと疑問を、異議を、と。それぞれに心があることをわかっていたからこそだ。
反して、彼の紙芝居をみている人の反応はまばらでうつろにうつった。
その様子は以前であれば介護士の理解の範疇であるはずが、彼はすでに歪んだ壁をよじ登っている異常な事態だった。そのてっぺんの手前で、期待する手応えを感じられなかったあのとき、ある種の〝不憫さ〟と〝やりきれない切なさ〟が決意になってしまった瞬間だったように思うのだ。
命の尊厳などもはや判断できないほどの悲壮感が彼を満たし切った様子が何を展開していくのか…私は自分の血の気がひいていくのがわかった。
そして、聾唖の彼女を障害はあるが心があると言い、話ができない人には心がないと発言したり、洋子の家で人の死について不気味なくらいたのしそうに興奮気味に話す姿は見逃せない悪い兆候だったのだろう。
………
そんなさとくんの異変に洋子が確信を持ち咎めに行く。
迫真の2人の掛け合いでさとくんは洋子のことも責める。
反論する洋子の相手が洋子自身になり、心のなかとの対峙がものすごい圧を帯びて押してくる。
いつしか、洋子を見据える洋子は、まぎれもなく私の心中を正面から覗き込み問い出した。
とめた呼吸の数が逆流するように押し戻され積み上がる。
私の動揺を捉えてなお、この相手は容赦するつもりがないと肌で感じると、
私の本音がポツリポツリと頭に浮きあがってくる。
目を背けたほうが楽なこと…
たしかにある。
うわずみをさらったように通りすぎようとした…
したかもしれない。
葬り去る社会の一部になってないか…
ないと言いきれない。
ならば
改める覚悟を。
さもなけば、同じような悲劇が起きる。
逃げ道なく考えさせるための投げかけの演出はすごい。
そしてなにより洋子を通じて表した宮沢さんが圧巻だ。
それは、まぎれもなく闇を照らす凛とした月のごとく。
………
夫妻が将来の道を決める回転寿司屋。
洋子の背後に映るニュースをみた
昌平は唖然とする。
私は洋子が気がつく前にまたいつものように立ち塞がるのだろうと思った。
しかし、違った。
躊躇いなく洋子は「できることをしに行かなくちゃ」と駆け出す。
そしてすぐに昌平に思いを告げに引き返した。
〝かつてあったことはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。〟
印象的な旧約聖書の言葉を改めて洋子が不安いっぱいに口にした時点では、彼女が自分につけた足枷が見えた気がしていた。
しかし、それまでとは異なる二人がラストにいたのを見届け、公開日から現在。
洋子を縛っていたあの言葉は、さとくんが起こしてしまった事件に生々しくリンクしていること、月の光に照らされたものが胸を締めつけ立ち止まったままだった私。
ようやく今日、片足が一歩出はじめたかんじだ。
修正済み
【追記】に書き表せていなかった部分を追加しました。
経済合理性の思想に騙されてはいけない
まさか、『愛にイナヅマ』と同じ監督がほぼ同時期?に作った映画だとは⁉️
でも、この監督さん、主演俳優に〝顔〟で演技させるのが好きなのですね。宮沢りえさんが過去の辛い思い出と高齢出産の不安を重ねるあたりはまさに真骨頂。
(障害者に関わる様々な事象やご家族のことを想像すると、俯瞰的に考えることができなくなってしまうので、以下は敢えて当事者の方々とは距離をおいて書いてます。もしかしたら不愉快な思いをされるかもしれませんが、ご容赦ください)
さとくん勇斗さんが、元々持っていた正義感が蝕まれ追い込まれた挙句、狂気に変容する様も見事だし、彼が滔々と語る〝正論〟(ここでは敢えてそう言います)も説得力を持つことになる。
でも、経済合理性を盾に語る人間を誰が批判できるのだろう。
今の世の中は、コスパによる評価が社会の規範になってます。受験競争も社会人になってからの人事評価も目先の結果や成果ばかり追い求めてるから、みんな余裕を無くしてる。勉強が苦手でも気の優しい人間とか、要領は悪いけどなんだか芯は通ってる人間、そういう人は受験や就活という期間限定での競争からは結果的に〝排除〟されていきます。だから、〝大器晩成〟という言葉が死語になりました。
成長には個人差があるのに、それを待てない大人ばかりだから、こどものほうも自分だけがいち早く評価されたくて、人を蹴落とすことばかり覚えてしまう。
受験競争も出世競争も自分が勝ち残るためには、自分が抜きん出る努力をするよりも他人を蹴落とすのが早道。自分のノートを貸して友達が自分よりいい点を取ってしまうなんて事態は全面回避したくなるから、助け合うよりもギスギスしていく。
経済合理性の方が人命より価値があるのだから政府も僕を褒めてくれる、と手紙を書く若者が出現したのは、ある意味で日本政府の国民教育の成果なのですね。さとくんにとっては、それはリアルな現実です。
勲章がもらえるくらいのことをしてるんだぜ、オレ。
宮沢りえさんが、さとくんとのやりとりの中で、自信を失っていくのは、クリエイターである作家ですら、経済合理性の思想に侵され、その論点で発想せざるを得ないから。
人間性の尊重や尊厳、福祉などの制度的な救済。
これらの概念は大人たちに余裕のある成熟した社会ならそれなりに備わっているもので、経済合理性の論点とは別次元のこと。金のことだけ考えたらムダと思えることを社会の枠に収めて運用できるのが成熟した社会。
自分の家族の問題を社会と共有するのが憚られるし、自分の事情に負い目を感じざるを得ないということは、この日本の社会がまだまだ成熟途上(むしろ後退かも?)ということだと思います。
でも、今の政治家は要領よく私利私欲を満たすコスパ脳はあるけれども、余裕を感じさせる成熟した大人とは程遠い人ばかりだし、中年も高齢者も全体的にはどんどん成熟とは反対の方向に時間を重ねている気がします。
小難しいことを長々と書きましたが、簡単に言えば、
フーテンの寅さんのような人が、自分の兄弟であってもにこやかでいられるし、一般社会の人たちもあんな非生産的な人はムダ、とか、あんな人に生活保護費が出るのは怪しからん、などと狭量なことをいうような社会だとすれば、成熟とは程遠い。
そういうことだと私は考えます。
気力体力が充実している時に観ること。
ヒトであることの判断
予想以上に、暗く重い雰囲気の濃厚な作品だった。
投げかけられた問題も難解すぎる。
正解なんて無いだろうけど、だからといって知らんぷりも出来ない、捨置けないタスクを受け取った気分。
心の無いモノは殺して(生命を破壊して)いいのだろうか?……
草刈りを延々としながら滔々と考えてた事があり、雑草を刈りとる事もまた生命を剥奪してる事なら、連続殺人者と似た行為なのか?と考えを巡らせた事もあったのを思い出させられた。
生きる事を許されない存在が有るとしたら、どんな生命体なのか?
生きてるだけで価値が有る、とどこかの政治家が言ってたが、深く掘り下げて考え、その真意を探ると複雑な思いに駆られる。
考えても仕方の無いところにまで展開してしまう……。
誰もが承認欲求のある当事者
序盤で、宮沢りえ氏演じる洋子が障がい者施設に初めて足を踏み入れていく場面の異様な雰囲気には、私自身が初めて訪問教育の臨時講師として重症心身障がい児施設に足を踏み入れたときも同じような雰囲気を感じていて、それはまた、『夜明け前の子どもたち』の序盤にも重なる。本作のパンフレットの評にも、二通諭氏がその作品を比較して取り上げているが、きー氏と誕生日が同じところから共感し、コミュニケーション可能性を感じた様子は、その作品だけでなく、『ジョニーは戦場に行った』『潜水服は蝶の夢をみる』等にも通じるであろうし、発達保障論の肯定的な面を拾い上げるのも重要ではあるけれども、職員の重労働という観点からの退職者の続出という共通な面にも目を向けるべきであろう。『人生、ここにあり!』等のように、当初感じていた異様性が、付き合いを深めるに従って変容していく作品もあるけれども、それらとは最終着地点が違うのだろうとも思った。育てた子どもの疾患のためにわずか3年で命が失われた痛みから立ち直れず、再びの妊娠にも、躊躇し、迷い、分身に言い負かされそうな描写は良かったと思う。虐待から利用者たちを救おうとした行動は、『トガニ』やテレビドラマ『聖者の行進』の支援者たちにも連なるが、そうした努力が途絶してしまうところにも、現実の悲劇の遠因があったのであろう。最後に洋子が「きー」の母のことを思い遣って走り出す姿に、現実の事件後にも、同じような行動をした職員たちの姿が反映されていると思われた。
二階堂ふみ氏演じる陽子は、そうした序盤の異様な雰囲気に連なる異常行動者の一人かと思ったが、健常者の職員であった。しかし、関係を深めてみると、洋子の経歴に賞賛を向けながら、やがては洋子の作品にも、出産への躊躇いにも批判的な意見を述べて追い詰めていく二面性をもった人物として描かれていて、事件の発生に際しては、「さと」の犯行に脅迫と自身の同調によって動かされつつ、利用者の命を奪うことには躊躇いをみせながら立ち会い続けた様子にも、現実の事件後に、同じような行動をした職員たちの姿が反映されていると思われた。
『波紋』でもろう者の恋人のいる青年を演じた磯村勇斗氏が演じる「さと」は、当初は利用者たちに優しい心根をみせ、『花咲か爺さん』の紙芝居を語りきかせていたが、その結末が「汚いもの」と表現していたところが引っかかっていた。それはよくばり爺さんの心だったと思われるのに、その志を喪失したのが残念なところである。先輩職員たちによるいびりによって、理想を失っていく様子は、現実の事件発生の経緯説明とも共通するのであろう。自分との線引きを始めるきっかけとなった重度利用者の姿との遭遇は、漫画『ブラックジャックによろしく(精神科編)』、さらに遡っては有吉佐和子氏作の小説『恍惚の人』での同様の症状の患者を想起したが、その姿に絶望するとは、今日的には学修によって身につけておくべきプロ意識の欠如と指摘されても仕方ないだろうし、2005年2月に石川県内の高齢者グループホームにおいて発生した職員による利用者殺人事件の課題が解消されていないとも思われた。ろう者の恋人との会話にも、手話を使わない部分が目立つように態度が変化していた。洋子と昌平にも同調を求めながら、それぞれの反論を論破した後、政治家に手紙を書いて持論の承認を求め、精神科病院に強制入院させられ、事件直前に退院していた経緯も、現実の事件発生までの経緯と一致していた。"PLAN'75"や『ロストケア』と大きく異なっているのは、特にこの、持論の承認を求めている点であり、あるネット評にも、登場人物それぞれに承認欲求があると指摘されたものがあり、実行犯の本質に最も迫っていることであると言えよう。また、殺される側からの視点で撮影する方法も、観る側を引き込む上で、工夫が凝らされていると思われる。同様に、施設の異様な雰囲気を醸している作品の一つでもある『閉鎖病棟』でも殺人事件が描かれるが、加害者の立場や理由が大きく異なっている。
オダギリジョー氏演じる昌平は、様々な悩みを抱える洋子の夫としては、当初、かなりすれ違っている印象が強く、社会人としても自信なげであったけれども、警備員の仕事をしていて、先輩からの揶揄に反論できるようになって、少しずつ自信を取り戻し、「さと」の言動にも同じように反論していたが、どうも殴り返されたようで、説得には失敗したようであった。終盤で昌平は、ささやかながら先に挙げた承認欲求を満たされた人物として描かれている点でも救いを見出せるとともに、この夫婦は、『福田村事件』における主人公夫婦と同じように、部外者から当事者へと巻き込まれる立場として描かれているとも言えよう。
序盤の場面での異様な雰囲気で連想したまた別の映画作品には、大江健三郎氏原作の『静かな生活』もあったが、改めて観直すと、妹ですら障がい者が社会に迷惑をかけるかもしれないという疑いの目を向けることがあったり、教師への恨みを晴らすために障がいのある家族への支援を装って近づいた男性が、障がい者の無能性をみくびって反撃を受ける様に、障がい者の不思議な能力の一端を描写しているのを改めて見出すことができ、大江氏が障がいのある息子への絶望と意識の転換を見出した経緯を綴った小説『新しい人よ眼ざめよ』にも、改めて光が当てられるべきであろう。
利用者やろう者の恋人役に当事者が抜擢されたのも、評価されるべきであろう。
あなたは無傷で手ぶらで善の側に立とうとするなんてズルいですよ。
重いなあ。問題作だって言ってる人、現実を分かってないって憤る人、そういう人もいるだろうけど、こうして人の嫌がるところに手を突っ込んで問題提起をすることは評価すべきだと思う。少なくとも、知っていながら知らんぷりしているよりも。宮沢りえやオダギリジョーたち役者陣は、おそらく撮り終えた後に疲労困憊だったことだろう。観ているだけのこちらがこれだけ心が重くなったのだから。
検診で子供に障害が見つかった場合、96%の人が中絶を選ぶらしい。洋子(宮沢りえ)も問い詰められる。「同じでしょ?障害があったら中絶しようと思ったでしょ?あなたは無傷で手ぶらで善の側に立とうとするなんてズルいですよ。」見透かされているのだ。いい人であろう、常識人であろう、弱き者の味方であろうと思いながらも、いざ自分が「そちら側」の立場になるかも知れぬと察した時の、人間としての狡さ、小賢しさを。そして、それを素知らぬ顔で違いますよと言い返せぬ正直さを。そうさ自分だって、人には授かった命だからとか何とか体裁のいい言葉で善人振ってしまうんじゃないかと思うもの。心の中では96%の1人でありながら。この映画を観る行為だけで、さもこの問題を知っているかのような似非満足に浸ろうとしていたのだから。洋子の戸惑いは、自分の中にもあるのだ。せめて、そんな自分の中にある「善意のふりした悪意」に自覚していようと思う。
希望と絶望が同時に襲い掛かってきたようなラストは、今の世の中、この問題がまだまだ解決していない、いやむしろ解決のしようのない泥濘なのだと思い知らされたような気分になった。
全287件中、141~160件目を表示