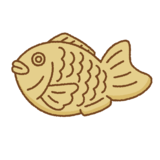イノセンツのレビュー・感想・評価
全52件中、1~20件目を表示
真夏の白夜の童夢。 愛猫家は観ない方が身のためですニャ…。
団地に住む子供たちの秘密の遊びが次第に狂気を帯びてゆく様を描いたスーパーナチュラルホラー。
ノルウェーからの刺客が日本に上陸。北欧の映画には馴染みがなかったのだが、なるほどこれはハリウッドのものとも日本のものとも違う味がする。
夏休みシーズン真っ盛りにも拘らずどこか寒々しい空気が漂っており、白夜の影響で夜でも太陽の光が差し込んでくるという、高温多湿の日本の夏とは全く異なる世界。その幻想的な雰囲気と、疎外された子供たちによる無邪気ながらも残酷な“禁じられた遊び“が一体となり、映画全体の不穏さが1分1秒ごとにどんどん増してゆく。まるで研ぎ澄まされたナイフの刃の様に、白く鋭い切れ味を持った危険な作品である。
さて、監督のエスキル・フォクトは、とある日本の漫画が本作に影響を与えたとインタビューで語っている。その作品とは…そうあの巨匠・大友克洋が生み出した歴史的傑作「童夢」(1980-1981)である。
…いやいやいやいや。これ影響を受けたとかそういう次元じゃないと思うんですけど😅
まぁ確かにお話の筋は全然違うし、最初は「団地」と「超能力を持った子供」くらいしか共通点はないかな、なんて思っていたんだけど、映画が進むにしたがってだんだんと「童夢」濃度は高まってゆく。クライマックスの静かな決闘シーンなんて、はっきり言って丸パクリ。これ大友先生、訴えれば勝てるんじゃ?
イノセントゆえの暴力性という、認めたくはないが確実に我々の周りにも存在している悍ましさを描いていると言う点で、本作はホラーというジャンルの枠を越えた普遍的なメッセージ性を持つ映画になっている。「童夢」では団地で巻き起こる怪奇事件の犯人は頭のボケた老人のチョウさんであり、彼もまた無邪気ゆえの残酷さを読者に見せつけたのだが、やはりその犯人の役割を本物の子供に負わせた本作の方が、より悲しく、救いようのない物語になっている様に思う。
画作りもクールだし、容赦ない恐怖演出と生理的嫌悪感に満ちた残酷表現は観客の目を惹きつける。事程左様に、本作は決して悪い映画ではない。しかし、相手は日本漫画界が誇る大横綱「童夢」である。パクリギリギリのインスパイアによって成り立っている以上、どうしたってこの2作は比較せざるを得ない訳で、そうなるとまぁやはり「童夢」に軍配が上がる。
と言うのも、「童夢」ってなんだかんだで滅茶苦茶エンタメ性が高い漫画で、団地内でのカオスな殺戮シーンなんてもう死ぬほど面白い。そのエンタメ的な面白みを全くコピー出来ていないというのは、やはりいかんと思うのです。どうせパクるなら、サイキッカー同士の死闘から団地の崩壊まで、きっちりと描き切って欲しかった。あのチョウさんを円形の見えないエネルギーによって壁にめり込ませる伝説の「ズン」シーンは映像で見たかったぞ!
「童夢」の圧倒的な画力と構図、ストーリーテリングが三位一体となった非の打ち所のない完成度は、おそらく全漫画史上最高。これに比べれば1億部以上売り上げたあの漫画も、アニメが空前の大ヒットを記録したその漫画も屁の様なもの。まっったくレベルが違う。
世間的には大友といえば「AKIRA」(1982-1990)という事になるのだろうが、本当に凄いのは「童夢」だから!「AKIRA」6巻分の面白みが1巻にギュッと濃縮されている、正に歴史に残るマスターピースである。まだ読んでいない人は今すぐ本屋へGO🏃💨
最後に一点、愛猫家なら間違いなくトラウマになってしまう動物虐待シーンがあるので、そこは覚悟して観る事。私はそのシーンがキツすぎて、マジで観るのを辞めようかと思いました。
映画の中で人間が死んでもなんとも思わないけど、動物が死ぬのは堪らなく辛い…。特に猫とか犬とかそういう愛玩動物を殺すのはダメ、ゼッタイ!!あのシーンを平気で観られる奴は人間じゃねぇ💢
と言う訳で、愛猫家の方は特に、本作ではなく「童夢」を読みましょう。こっちは虐待シーンがないので安心です😊…かわりに人が死にまくるし血もプッシャーって吹き出すけど。
考察必須かもです。
言葉数はそこまで多くない映画なので
しっかり見ながら一人一人の感情を汲み取るような映画でした。
不思議な力を持っている時点から
ストレンジャーシングス的な感じなのかなと思ったのですが、力としては近いものを感じるけどまた違う感じ。
子供がゆえに大人ならダメとわかるその行動をも、とってしまうシーンが多いです。
話し合いで解決がまだできない年齢なのかな。
子どもたちの中にもたくさんの考えがあって
その中での行動があって、小さな子たちの感情を見る映画でした。
最後、窓からたくさんの子どもが下をのぞいていました、あの子たちもまた不思議な力を持った子たちだったんですかね。
これからネタバレ考察見て一致して楽しみたいと思います。
面白いか面白くないかというよりは、ずっと後半戦はハラハラしていました。
ホラーではないけど人間怖い瞬間がちょこちょこあります。
アーシャのお母さんが一番かわいそうです。
娘殺しの母親になってしまって、ただただかわいそう。
童夢という日本の漫画からインスパイアされて作られた作品と、みました。童夢を見ていないのでなんとも言えませんが、とにかくなんだか不思議な感情になる映画でした。
子供の無邪気さは猫をも殺す
暇を持て余した、子供たちの、遊び
遊びですむか!人死んでんねんぞ!
------------------------------------------------
あらすじ
団地に引っ越してきた妹と自閉症の姉
友達ができるか不安だったが男の子の友達ができた
彼は超能力者だった
-----------------------------------------------
いやー面白かったね。
若干終わり方すっきりしないけど
全編じっとりとしたホラー的な雰囲気で、進んでいくから見てて疲れたわ。
力に溺れ、子供特有の万能感と私生活の抑圧された負の感情が溢れ出て、
品性がねじ曲がっている男の子よかったねー。
悪の自覚なき悪役よかったよー。
てか、この作品メインキャストは子供なんですよね。
自閉症の姉、妹、男の子、テレパシー女の子
4人ともすっごいいい演技なんですわ!
子役って何人か出れば違和感を感じる演者が紛れ込むもんですが、
この作品はすごいぜ!4人とも半端ない演者だぜ!
特に自閉症の姉の演技スゲーのよ。憑依系の演者じゃん。
あと男の子の演技、表情ほんといい!
最終的に超能力バトルになるんだがその決着も静かなものよ。
何事もなかったかのように日常は続くんですね。
猫は階段の踊り場から落とされて瀕死状態になるよ
最終的に男の子に首の骨を踏み抜かれてとどめを刺されるよ
男の子の異常性を最初に表す舞台装置として役目を果たしたが
さすがにドン引きである。
エンドロールが上から下へ……
意を決して観たけど、やっぱムナクソ系だった!
エスパー団地(?)っていう設定が面白くて飽きずに観れたけど、
「童夢」が元ネタなのね。
役者の方がみんな上手くて
子供の気持ちや危うさみたいなものがリアルだった。
ラストの個人的解釈
思っていた映画といい意味で予想を裏切られた。淡々とした怖さというか不気味さがあり、 ところどころ不愉快になるシーンがある。
ラストシーンはイーダが力を得た説も個人的にあるかなぁと思って。
足が治ったりギプスが割れるシーンはアナがしてくれたように思えてイーダの力が覚醒したのでは?
ラスト、アナがボードにぐちゃぐちゃに書き殴っていた手を止めたシーンなのですが、イーダはアナの心が読み取れるようになったのではないか?と個人的に解釈したのだがどうだろう。ベンを倒す時、2人で手を繋ぎ力を合わせていたし。カメラのピントがアナに合っていて、奥でそれを見つめているイーダになんとなく違和感を覚えた。無言のままのアナの顔に焦点を当ててるってことは、なにか話してるんじゃないかな?
アナの手が止まったのは、イーダの力を感じ取ったから=絵を描く必要性がなくなった。
それともアナがベンに操られてしまっていた…?
エンドロールが逆さまという情報を読んで、アレエンドロールって普通はどっちだっけ?と感覚がおかしくなってしまった。
これは凄いけど…
猫のシーンは観てるのが辛かった。
あのシーンは本当に観ていられませんでした。
全体的な感想は終始漂う不気味さにどんどん引き込まれました。
そしてちゃんと怖いし、終盤はとても緊張感がありました。
家で1人で映画を観てあんまり声を出すことはないのですが、この映画では怖い所とか痛そうな所で声を出してしまいました。
フィンランドは黒人の人やインド系の人が多いよ
この映画『そんな冗談を言わないの。怖くないから』兎に角、
何を言いたいの?
大友先生をウマシカにするな!!
『沸騰している鍋に触るな!』
超能力って、つまり『ユーリー・ゲラゲラ』なんでしょう。
大友先生の作品の『バビロンの塔の内部』の絵画やアニメの『大砲の街』と比べれば、この映画なにも無い事が分かる。どっかの賞を取ったとか、大友先生の名前を出せば『名作』ってのは短絡的過ぎる。
この映画は殺されてしまったジジ見たいな黒いニャンコ先生の尻尾だよ♥️
子供たち使って、人件費を浮かせて作ったB級ホラーだと思うけどね。どこに賞として評価される部分があるの。百歩譲っても背後が気になる様な薄気味悪さはないし、サイキックスリラーってキャリーとかあったじゃん。使い古されてるよ。
黒いニャンコ先生は尾も白くないでしょ。
黒いニャンコ先生の冥福をお祈りします。
『愛のないAI』に聞いたら、『ヘイト』に繋がるかもしれないって回答だ。
大人が子供をそんなふうに見ているなんて、それこそ薄気味悪い。実存主義は北欧にはないのか?
固唾
ポスターからしてやばかったのだが、序盤から、あ!これ鬱になりそう!ってざわざわした。
大友克洋先生ですか…なんとなく納得。
舞台は団地、引っ越してきた家族。
優しい両親と自閉症の姉アナと妹イーダ。
両親の目はアナに行きがちなのは仕方ないと思うのは大人の目線であって、当のイーダは不満たらたら。
子供だからといってもやり過ぎ感がすごい。
アナを気遣う優しいアイシャ。
彼女は心が読めるだけに、アナの気持ちを代弁しそれを外に発するよう促す。
イーダもきっとアイシャを通してアナにもきちんと目に見える感情がわかり嬉しかったのだろう。
バケーションでほぼ住民のいない大きな団地。
イーダが最初に友達になったのはベンジャミン。
少しのサイキック能力はあったが、イーダやアイシャ、アナと遊んでいるうちに力が暴走し始める。
もともと、母親の愛が薄く冷蔵庫を見る感じとても貧しそう。そりゃすごい力を持ったら闇堕ちしますよ。
悪口言うなっ!て「さん付けろよデコ助野郎!」くらいの勢いでやってきたらすごい力出てたよ!みたいな。これも俺の力なのか〜的に母親を死に至らしめる。なんか童夢もそうなんだけど、鉄雄味を感じたかな〜
心の読めるアイシャはベンの心も分かるが敢えて告げない。彼の闇に気づいていたのだろう。
不穏な音楽、カメラアングル、セリフ説明のあまり無い描写など何をとっても終始固唾を飲む。
子供達の表情もとても良い。
舞台の団地が様々なアングルで撮られていて、その大きな団地に潜む問題を象徴しててとても心に残る。
イーダを守るため、1人外に出るアナ。強く眩しい光が彼女を包む。
対抗して陽に当たり影を強調させるベン。
池を挟んで対峙する2人。握る拳。
すでにバケーションから帰ってきた沢山の住民達の中、静かなバトルが始まる。
共鳴する子供達。
唯一、力を持っていなかったイーダの覚醒。
姉妹の握り合う力でベンは1人きりブランコの上で力尽きる。
全てが終わった後、日常を取り戻す団地の風景。
また磁石ボードでグシャグシャと線を描き始めるアナ。
母に縋り泣きじゃくるイーダ。
最後、アナはガシャっと白紙にする。
それは今まで無意味にやっていたそれではなく、何かの意思を感じられた。
ひょっとしたら、様々な事情を抱えるこの団地で第二、第三のベンが生まれてくるのかもしれない。
ただのサイキックバトルではなく、障害を持つ子供の親、片親、DV、移民、貧富、などの附属物もあり考えさせられる話にはなっていたけど結局、子供達は親に振り回されているだけの話なんだなと…
ネッコは許さない…
子供の好奇心って怖いよね。
子どもらしい感情と思考の変化
そして、手に余る危険な能力…
混ぜるな危険と言うセットが揃い、大体酷い事が起こるのが想像できる。
移住者が沢山いるマンション群に居る子どもたち3人に特殊な能力が発芽し最初は遊び程度に使っていたのが次第に強大な力になっていく様を淡々と見せられる。
BGMはほぼ環境音程度で、音で驚かしてやろうなどとは微塵も考えていない…しかし団地やその周囲の公園と言う日常風景の中、あまりにも異質な力が使われていくのは気味が悪い。
子ども達は皆何かしらの障害を抱えており、自閉症のアンナ、じっとしてられない様子や我慢できない所、残虐性のあるベン、顔に斑点のあるアイシャが力を使える様になる
ろくに会話も出来ない自閉症の姉が両親に構われていること嫉妬して
嫌がらせするイーダとアンナの関係性の変化や発語が可能になったアンナに喜ぶ両親の姿を観ている内は良かったが、猫を惨殺したり、他人を操って人を殺し始めたベンを見ると悲しい気持ちになる
最後の対決シーンは周りは普通に生活している公園で行われ、決着時に子どもだけが彼らの方をチラリと見る。ここでも聞こえてくるのは生活音のみで異色さを際立たせている。
BGMをほとんど付けてない事で実際に在りそうに見えてくるのが面白い
子役の演技が素晴らしい
とにかく、出てくる子供たちの演技がみんな上手すぎて、
その演技力の高さがあるからさらにこの作品の怖さを引き立たせてくれてる気がする。
まだ善悪がしっかりしていない子供たちにあんな力が備わってしまったら、大人が思っている以上に残虐な事が起こるんだろうなと思った。
そしてそれを分かってるのも子供で、でも大人に話しても信じてくれないから自分たちでどうにかしようと考えて、結局、その方法もむごい事をして解決しようとするんだろうなぁ、、(作中の歩道橋から突き落とすアレとか)
最後、戻ってきたベンとアナの一騎打ちはめちゃくちゃカッコよかった…
周りの大人たちは何にも気づかず、楽しく過ごしてて、異変に気付いてるのは子供たちと犬だけ。
注意して辺りを見回したら、この場にいる赤ちゃんみんな泣いてるし、子供たちは同じ方向を向いてるのに、大人は関心がないからなんにも気づかない。笑
家の中にいる子供たちも気付いて、続々とベランダに出てきて様子を見守ってるところとかもなんかカッコよくて、変に騒ぎ立てないところが大人より大人だった。
あの団地なのかあの場所なのか、あそこに住んだら不思議な力を手に入れるのだろうか??
シンプルでセンスのいい映像と不安を掻き立てられる音楽、演技力抜群の子役が揃っている上質な映画でした。
子どもから感じる緊張感が詰まった映画
※動物が酷い目に遭う描写が苦手な方は注意!
猫が登場した時点で嫌な予感がしていましたが、案の定。。。
殺傷事件を起こす人物は、小さい生き物から大きな生き物へ攻撃対象を移していくと聞いたことがあるので、あの流れは必然ではある、と思いましたがやはり辛い…
全体的にセリフや挙動、能力発動中にも派手な描写はなく、静かなトーンで進むところに北欧映画らしさを感じました。
ラストのバトルシーンの決着も、四肢が吹き飛び…のような事はなく、フッと周辺の空気や砂が念力で押され、彼が敗北と共に息絶えた事が分かりました。
(一般的な映画であれば、体が吹き飛んで木に衝突して死亡とか、念力バトルで鼻血が…などの描写にしたくなる気がします)
現実世界でも、倫理を逸脱した行動をとる事がある子どもという存在に緊張感を感じる事が多いのですが、今作は超能力の目覚めというファンタジー要素とその点を絶妙にミックスしていて違和感なく観ることができます。
呆気なく残酷な行動をしてしまう子どもの恐ろしさが映画を通して伝わってきて、最後までヒリヒリした空気感にドキドキしっぱなしでした。
監督は童夢を読んでいるに違いない
子供たちの静かな超能力バトル。
監督は童夢に影響受けていると思う。
もちろん童夢のような派手な展開はないが、団地、子供、超能力、障害者
そしてラストのベランダから覗く子供達など。
大人の知らないところで静かに超能力の戦いが激化していく様子は良かった。
ただ、幼い子に過激な事をさせるのは見ていてちょっと心が痛むかな。
あのような過酷な争いは大人でもなかなか耐えられるものではないからね。
まあ、むしろ子供だからこそ持ち得る残酷さが出来たのかもしれないが。
派手な演出こそないがじわじわとくる恐怖が、平凡な日常に大人が気づかないところで
迫ってくる様子がいい。近くにいる大人は誰も役に立たないという状況はなかなか面白いと思う。
ベンは邪悪だけど、家庭環境をもう少し描いても良かったかもしれない。
ベンが人を傷つけることに躊躇がないのはサイコパスだからなのか環境によるものなのか
わからなかったからね。猫を殺すシーンはサイコパスの象徴なのかとも思ったが、、
前半も面白かったんだけどちょっと静かすぎて退屈かも。
まあ、後半も静かだけどね。
アニメ的なバトルが多い中、静かなバトルでも盛り上がるんだなあと思いました。
良かったと思う。
舞台のノルウェーの団地は結構日本のものと似ていて日本人に総入れ替えしても
普通に気づかないかも。
大人には、秘密。
原題
The Innocents
ノルウェー題名
De uskyldige
感想
大友克洋「童夢」からインスピレーションを得た驚異の映像に、世界が震撼&絶賛
『ミッドサマー」『LAMB/ラム』に続く北欧発のサイキック・スリラー
退屈な夏休み。無垢な子供たちの遊びが、狂気に変わる。
終始不穏な雰囲気が漂いゾッとする作品でした。やっぱり子供って怖いです。
子供たちの静かなる団地サイキックバトルでした。
ベンの純粋な残虐性が恐ろしかったです、猫にトドメを…母親に…。
痛々しい描写ありです。
イーダ、アイシャ、ベンの子役らの自然な感じの演技もよかったです。アナの自閉症の演技は難しかっただろうに…
ラストも静かに終わりましたね。
※衝撃の夏休みが始まる
危険な遊び
イーダ(9歳)
その姉で自閉症のアナ
アラブ系のベンジャミン(ベン)
インド系のアイシャ。
この3人の少女と一人の少年のサイキック・ホラー映画です。
引き込まれました。
不思議で神がかりで邪悪で無垢(?)
でもって、少しはズルい。
でもアナはめっちゃ無敵でかっこよかった!!
自閉症の子どもはある意味で選ばれた子どもかも知れない。
特殊能力を持つ故に、
言葉が話せない、
他者と意思疎通が出来ない、
相手の顔を見ない、
などの代わりに、
聴こえないものを聴き、
見えないものを見、
細密な絵画や、作曲、計算、ジグソーパズルなどが得意、
だったりする。
この北欧ホラーは子どもたち4人がサイキック能力を持ち、
その中の一人が邪悪な心を持っていたことから、
不気味な事件が多発する。
「ミッドサマー」と「LAMB/ラム」の不思議な魅力に取り憑かれた私は、
この映画のまた一味違うサイキック・スリラーにも引き込まれました。
子ども4人が主役。
ノルウェーの低所得者向けの団地に越してきたイーダと姉のアナ。
アナは自閉症で言葉を離さない。
イーダに近づいて来た少年・ベンは見たところアラブ系の顔立ちをしている。
ベンは小石を超能力で移動させたり、大木を真っ二つに折ったりできる。
小石や大木ならまだしも、悪意はエスカレーターして行く。
もう一人の少女・アイシャはインド系の優しい少女。
顔や手ににアトピーなのか白斑がある。
アイラはブランコに揺られていたアナとなぜか意思疎通が出来るようになる。
そしてベンのサイキック能力は人に向かって、
いじめっ子の脚を折ったり、
大人を操っていじめっ子を殺させてしまう。
そして、
遂には自分と敵対して来るアイシャを憎み、
危険を感じたベンは、
アイシャの母親の意思を操ってアイシャを
惨たらしく刺殺させるのだ。
無敵に思えたベンだが、畏れを感じたイーダは
ベンを歩道橋から突き落とす。
それでも平気だったベン。
しかしアイシャを殺されたアナは
最強のサイキッカー。
主導するのはアナ。
水辺に立っと波がさぁーっと押し寄せて来る。
そして砂がサーっと引いてくる。
そしてベンは遂に‼️
この映画が特異なのは、大人が徹底的に無力で蚊帳の外であること。
子どもたちだけの孤独な闘い、
イノセンスとの訣別、
それをメタファーにして描いた成長物語なのだ。
日本の漫画「童夢」by大友克洋の40年前の作品をベースにしている。
北欧と日本・・・遠くとも意外と近いのだと感じた。
そしてこの映画のヒロインは自閉症のアナ!!
アナの超能力はギフト。
アイシャのためにも強く生きてほしい。
タイトルがまさに…
このタイトルから、子供の残酷さを描いたホラーだと思うじゃないですが。それも、間違ってはないけど子供の絶望のようにも思える。主要登場人物のうち2人は、移民ではないかと思えるしシングルマザー家庭に見える。もう一人は自閉症の姉を抱えた家族。大人に頼れない子供達の物語。
なお、サイコスリラーとあるけど、一昔前なら、超能力バトルといっていい内容。
子供達だけの静かな戦い
ほぼ、童夢と言われるけど童夢読んだことないので読んでみたい。
映画としては、すごく良いクオリティだと思う。
面白かったところは、子供達にそれぞれ
ヤングケアラー、親の精神病、ネグレクト、虐待、いじめなどの社会的問題の背景も含めて4人にカルマ値の様なものが設定されているようにみえるところで
自閉症のお姉ちゃんアナが1番白く、次にアナとテレパシーがあるアイシャ、主人公イーダは中立からやや黒寄りベンが1番黒くダークサイドに近いってなっていて。
主人公がカルマ値が悪方向に振っている状態で物語スタートなのが秀逸だなと思った。
子供は無垢な天使ではなく、社会環境や教育、コミュニティによって善悪の判断が成長していく過程と物語が上手く噛み合ってる。
超能力の正体的はなんなのかと考えてみても超常現象とゆうよりは
大人への成長の過程で忘れてしまった子供の感性や想像力による不思議なものってゆう解釈ができるのも好き。
(その辺りはパンフレットの監督インタビューが補助線として読み応えがあった)
主人公のイーダが子供特有の残酷さを持ち合わせていながら、自分で考え、悪と自分の責任を認識し、邪魔だと思っていた姉と手を繋いで戦う一夏の成長物語。この映画の中に大人は出てくるけど子供達に介入せず、ただただ背景として存在するのみで「子供の世界」を馬鹿にすることなく尊厳を持って、クールな目線で捉えてるかっこいい作品だった。
最後の戦いは興奮したし、うんと小さな子供や犬しか気づかない静かな戦いかっこよかった。
悪役として登場するベンは、力が強まることでどんどん暴走し人や動物を傷つけてるが
加害をしたあとに、涙を流したり
本当に孤独を感じている子供でもあって、ただの邪悪な存在として描かないのも、厚みがあって良かった。
子役達は皆んな魅力的だったな。
映画館で鑑賞
子供の実在感
外見は静かに静かに、子供の世界だけで進んでいく話。
クライマックスがまさかの「ただ立ってるだけ」という絵。もちろん遠目にはという話ですが。
「童夢」に似すぎているという話もありますが、純粋であるが故の残酷さが子供達の実在感と共に迫ってきて、見応えのある作品でした。
「超能力」に「科学」を見た
団地(集合マンション)を舞台にした、その辺に普通にいる一般人が繰り広げるサイキックバトル! これはまさに大友克洋の「童夢」を思わせる。「童夢」は漫画世界におけるリアリティを革命的に更新したけど、この映画はさらにそのリアリティを上書きした感じ。現実に超能力が存在したとしたら、どのよう場所でどのような人間にどのような状況で発生するのか、その力がどのようなものなのか、圧倒的なリアリティがある。子役の演技力も驚嘆するしかない。
タイトルの「イノセンツ」というのは、「無邪気」「無垢」「純粋」みたいな意味だろうか? しかしポジティブな意味というよりは、子供が「無知」ゆえに歯止めのかからない残酷さや、他人や動物への想像力の欠如をもつ存在である、非常にあやうい不完全なものでことを示唆しているように思う。
ふつうは子供は無力であるゆえに、その不完全さが大きな問題にならないのだが、それの不完全な存在が大人には見えない(理解の範疇を超えている)強大な力をもってしまったらどうなるのか、と考えざるを得ない。
子供たちの様子や心理は、何か舞台であるノルウェーの社会のゆがみをあらわしているっぽい。同じ集合マンションの中での幸・不幸の差、多様な人種の中での差別(?)、貧富の差みたいなゆがみがあって、最も弱い立場である子供たちがそのゆがみをひきうけている。
ただ、僕はこの映画を観ていて、監督の意図とは全く違うかもしれないのだけど、この子供たちが今の人類を象徴している気がして仕方なかった。
つい数百年ほど前における科学革命で、「科学」という自然に隠されたささやかで神秘的な力を発見し、無邪気に喜ぶ人類。はじめは遊ぶ程度にその力を楽しんでいたが、実験をくり返しながら、この力をもっとうまく使いこなすことに夢中になる。そして、原子爆弾をはじめとする、一歩間違えれば人類を破滅させ、地球環境を一変させることができるくらいな強大な力を手に入れるほどになり、そこではじめてこの力に恐怖を感じるようになった。
人類はこの強大な力をコントロールし、うまく使いこなせていけるだけの、倫理観も、自制心も、智慧も、合理的思考も持ち合わせてはいない、いまだ「幼児」の段階だと思わざるを得ない。
この映画の子供たちが、子供が扱うには危険すぎる強大な超能力をもってしまい、ハラハラどきどきしながら見守る心理は、まさに人類が科学技術をうまく使っていけるか、とハラハラする感じに似ている。
全52件中、1~20件目を表示