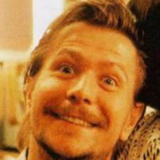違国日記のレビュー・感想・評価
全217件中、21~40件目を表示
このジャンルの作品も好きです。久々のガッキー主演の作品を見ました。...
自己受容ができて初めて他者を本当に受け入れることができる
異文化理解・異文化間コミュニケーションについて話をするときに、外国の人々だけではなく、異世代の人と上手くコミュニケーションができる能力も含まれることに言及されることが少なくない。持っている価値観や知識といった背景的枠組み(スキーマ)が異なる者同士の交流であるからだ。本作も正にそんなことを扱っている作品。
冒頭の事故を除いてさほど大きな事件があるわけではなく、淡々と朝と槙生の二人の、子ども同士の、そして大人同士の日常生活が描かれていく。理解と不理解の揺らぎの中で焦燥感を覚えつつも、自分は自分のままでいいんだという自己受容ができて初めて他者を本当に受け入れることが見えてくる。
心がほわっと暖かくなるような作品。
青春&家族映画
不細工な新垣結衣が楽しめる
けっこう面白い。
言ってみれば不細工な新垣結衣が楽しめる。
最近、韓国ドラマばかり見ていて、女優は美人でキラキラしていて当たり前のような意識があったけど、この新垣結衣は素ではないけど、それを思わせる普通のナリをしている。それがまた魅力的。
相手役の早瀬憩(ドラマ「ブラッシュアップライフ」に出ていたとか)がとても自然で可愛い。犬みたい。
そんな劇的な話ではなく、我々も経験しているような、日常では普通だけど実は重たいものを経験しながら生きている。そんな日常を陳腐な言葉で言うと「みずみずしく」撮っている。
映像は、当たり前の風景だけど、美しく撮られていて心地いい。
編集も監督(瀬田なつき)がやっていてリズムがあるシーンがあったり面白い。
全体的に心地のいい世界が作られていて、もっと見ていたいような気分になる。
「大豆田とわ子~」とか思い出すし、山下敦弘の「リンダ・リンダ・リンダ」とかも思い出す。
韓国映画やドラマもいいけど、こういった日本映画ならではの味わいは捨て難い。
原作途中まで
独特な距離感が生み出す救い
2024 116本目
微妙な共同生活
ストーリーは◎だけど時間が長い!
CSで録画視聴。
新垣結衣は初めて映像で観る。名前は知っているが。
ガッキーこと新垣結衣主演の作品だが、ストーリーが興味深い。もし、こんな事が身近で起こったとなると怖さも感じる。
その中、女子高生朝役の女優は難しいストーリーをよく演じたなと思った。新垣結衣も大人のお姉さんみたいで新鮮だった。
作品はいい作品。ただ、時間がちょっと長い。せめて120分にまとめてほしい。
かけがえのない友達との出会い
うちの娘も高校生の時、部活は軽音部を選びしかもベースだった。初めて楽器屋でベースを買ってあげた事や学祭の時は教室でのミニライブを見たことなどを、今でもよく覚えている。音楽は高校だけで終えたが、その頃の軽音部の友達とは今でもたまに会ってるという。
朝の友達たちとのエピソード(えみりのカミングアウト、森本千世の憤り、三森ちゃんのギターテク等)は映画の中でさりげなく紡がれていたが、充分にいい感じのアクセントになっていた。
きっと、卒業しても大人になっても朝とつるんでいくんだろうなぁ、。と思います。
冒頭、事故で両親を失い茫然自失している朝は、葬儀で親戚たちの心無い言葉が耳をかすめ、たらい(盥)って漢字はどう書くのかと呟く。そこで槙生は「うちにくればいい」「あなたを愛せるかどうかはわからない。でも私は、決してあなたを踏みにじらない」と言う。あとで友人には勢いで言ってしまったと話していたが、後悔など微塵もない。
その後、淡々と流れていく槙生と朝の共同生活と様々なやりとりが、全編にわたり。動いていくがそのすべてが観る人に心地よい風を送ってくれました。
いつまで一緒に暮らしていけるかは分かりませんが、ほぼ親子の親友のような関係で2人はこれから先も生きていくと思います。
ガッキーはいい役者になりました。新人の早瀬憩さんもとってもいいです。
続編があってもいい映画かと思います。期待しています。
槙生の苦悩が心に沁みる
<映画のことば>
「たらいって、どう書くんだっけ。」
「朝、私はあなたの母親が心底、嫌いだった。死んでも、なお憎む気持ちが消えないことにも、うんざりしている。
だから、あなたを愛せるかどうかわからない。
でも私は、決してあなたを踏みにじらない。
もし、帰るところがないなら、うちに来たらいい。
今夜だけじゃなく、明日も、あさっても。
ずっと、うちに帰ってきたらいい。
それから、たらいは、臼に水を入れて、下に皿と書く。
たらい回しは、なしだ。」
「いっしょに、帰りたい。」
実の姉妹でありながら、実里と槙生との仲がしっくりいっていないことの原因は、本作の明確に描くところではなかったかと思いますけれども。
どうやらそれは、家庭を築いて堅実な生活(専業主婦)を選択した姉と、ある意味、自らの才を信じて自らの大道(小説家)を歩もうとする妹との価値観の相違だったようにも思われます。
幼少の頃から病院通いが欠かせす、普通の子供と同じことはできなかったという虚弱な実里にしてみれば、幸いにも壮健な体に恵まれている槙生には、自分の分までより堅実な生活を送ってほしいという思い(あるいは、念慮ともいうべき、凄まじい想い)が槙生に対しては、あったのかも知れませんし、一方の槙生の方でも、我が道を進むことに精一杯で、その姉の真意を慮(おもんぱか)る余裕などは、これっぽっちもなかった―。
槙生がつねづね感じていた反発は、姉の念慮の重さに対してなのかも知れないとも思います。
そして、反対に言えば、通っている同じ血は争えず、妹・槙生としては、姉・実里のそういう価値観自体にではなく、そういう価値観を(遠からぬ関係性のある姉の実里から一方的に)被せられることに、反発していた「だけ」のことなのかも知れません。
上掲の映画のことばは、心底では憎み切れていない実の姉妹関係をはからずも吐露する槙生の言葉として、本作では重要な位置を占めるのではないかと思います。評論子は。
当の本人は「勢いで言ってしまった」とは言うのですけれども。
本作の題名の「違国」…「異なる国」ではなく「違う国」の「違う」は、最初は叔母・槙生と姪・朝との世代の「違い」なのかと考えて鑑賞していましたけれども。
そうではなく(あるいは、それに被せて)姉・実里と妹・槙生との価値観の違い…ということ、あるいは、それらの両方の複合的な意味合いだったのかも知れないとも、思い直しもしました。
いずれにしても、突然に降って湧いた関係ではあったものの、後醍や笠町、えみりや三森、そして実母・京子などを媒介としながら、徐々に徐々に、ゆっくりゆっくり関係性を深めていく槙生と朝との姿が何とも温かく、観終わって、たっぷりの「ほのぼの感」が溢れる一本でもあったと思います。
ただ沈黙するだけだった朝が、槙生の肩に顔を埋めて、両親の死に涙を流すことができるまでになったのも、また軽音楽部では、内心では願っていたボーカルを担うことができたのも、そういう関係性の深まり(と、そのことに伴う心の中のわだかまりからの解放)の結果だったことは、疑う余地もありません。
これも、佳作だったと思います。
評論子は。
(追記)
評論子には、実里と別姓婚の夫との葬儀(精進落とし)の席で、槙生が朝を見ていた時の目付きを、忘れることができそうにありません。
おそらくは、体調が優れないという母・京子に代わって、朝は自分が引き取らなければならないことはアタマでは理解しつつも、実里との確執もあって、感情的には、なかなか素直にはなれないー。
ただただ俯(うつむ)くだけの朝とは対照的に、その燃えるような「内なる葛藤」が、はからずも彼女の目の色に現れていたのではないかとも思います。
(加えて、上掲の映画のことばが直後に出てくるシチュエーションでもありました。)
その点も、観終わって、印象の深かった一本でした。
評論子には。
<映画のことば>
「あたしとお姉ちゃんがダメだったから、あの人の死を悲しむことはできないけど、話を聞くくらいはできるから。その…。」
「自分で手一杯なのに、人の話を聞く余裕なんてないでしょ。」
「よくご存じで。」
「誰が育てたんですか。」
「お母さまです。」
ガッキーさんのファン
夏帆が上手いのは当たり前として
朝ちゃん可愛い
いろんなつながりがあるなと思った
ダメな映画化の典型
マンガのテクスチュアは、線とセリフですよね。線の位置・勢いとセリフの配置とでマンガ独特のロジックを作って、物語を展開させる。だからマンガのセリフをいくら忠実に映像化しても、それだけでは決して「映画」にはならないのです。これは、その当たり前の法則を無視して撮られてしまった作品。とりわけ小説家の女の演技と演出は、説得力を欠いています。
カメラは奮闘していて、新緑の小径をあるく少女二人、湘南の海辺で言葉をかわす作家と少女、空っぽの体育館で秘密を明かす少女…と、映画的な場面は何度も何度も出てきます。そのどれもショット単位ではきちんと秀逸に撮れているのです。しかし、そのたびにそれが「映画」になり損なっている。それは何よりも演出の感覚が通俗的で、編集技術が追いついてないからです。海辺の高台にある実家を作家の女がたずねるところなんて、ほとんどダブルアクションに近い編集エラーがそのまま残ってしまっています。
映画全体を通じてもっとも力強いシーンは、その体育館なんだけど、うーん、どうしてそう何度もカットを割ってしまうのか。秘密を語り出そうとする少女、それを聞き取ろうとする少女、それぞれの顔をもっと黙って凝視していたら、はるかに「映画」になったはず。こうやってちょこまか細かくカットを割って話をドライブしようとするのは、TVドラマ。
要するに映画作品としてはもののみごとに失敗しているのですが、唯一、早瀬憩は恐るべき存在感を残しました。原作のイメージに近いという点でも、口先でひそひそっと発声する今の若い日本人の姿を映画の世界に接続したという点でも、すばらしい成功。この新人だけは、次回作を見てみたい気がします。
住む国は違えど
全217件中、21~40件目を表示