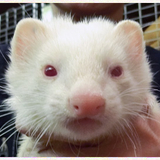哀れなるものたちのレビュー・感想・評価
全672件中、301~320件目を表示
ホラー?コメディー?社会派?
不思議な感覚
内容的には、痛々しいシーンや官能的なシーンなどあり、決して明るい内容でもないし、気持ちの良い物でもない。
だけど役者さんの演技もあり、引き込まれるんですよね。
映像にしろ音楽にしろ、画面がカラーになるところや音が鳴るところなど、映画の魅せ方は良かったですね。
一つ一つのシーンも印象的で、話だけでなく絵や動きでも魅せられました。
先述した通り、ストーリーは全然明るくないんですけど、なんだろう、妙なスッキリ感、満足感があるんですよね。
キャラの成長が明確にわかるのと、悪い(というほど悪キャラじゃないんだけど)キャラも相応の報いをうけるし、最後は落ち着くところに落ち着くのが良かったのかな。
面白かったけど、オススメはしづらいかなw
この世界感は好きだか…。
とりあえず面白かったは面白かったんだが…、私的にこの世界感は好きなので、予告を見た時に難しそうだけど見たいなとの気持ちにさせられたので鑑賞しました。
思った通りに魅せ方❓映し方❓は凄く綺麗だし西洋の雰囲気も出てたし世界に入り込めた。
物語もザックリいったら大人の身体を持って産まれた主役のベラの話しではあるんだけど(本当にザックリだけど(笑))、多少必要ではあったかもしれないが性描写が多いかな…💧思ってたより沢山あった😅、その分の評価を微々たるものだが下げました。
役を演じたエマ・ストーンさんはとても頑張って演じてたんだと思うし良い作品を作りたい気持ちも制作に関わってる所があるなら充分に伝わってきました。
凄く身体張ったと思います👏、作品内容はそれ以外はとても良かったしなんかノミネートされてるのかな❓確かに頷けます👍。
解剖的なグロいのもあってそれは慣れてましたが一応指の隙間から見てた(笑)。
最初はカラーだがすぐにモノクロでしばらく話がすすんでまたカラーになるんだけど、なにも知らないベラが家で過ごしてる間がモノクロで外の世界に出たらカラーになったからベラの世界の見方をそう表現したのかな❓それも美しかったな☺️。
演者さんもベラを作った(❓)人はスパイダーマンの初代ゴブリンだったのやっぱりだし、外の世界に連れ出した人は後で気づいたがアベンジャーズのブルース・バナーの人だったのね、これはわからなかったな〜。
みんな哀れ
耽美系エロに見せかけ、しっかりフェミニズム、ポリコレ
友人に誘われて事前情報ほぼ無しで鑑賞。
20世紀初頭の時代設定のようだがかなり独特な衣装やセットでややファンタジー寄りな感じ。
映画の雰囲気はfemme fatale、マダムエドワルダ、悪徳の栄え、ソドムの市、マルキドサド、澁澤龍彦、ハンスベルメール、球体関節人形などのキーワードを連想させる感じで、そういった類の作品を好んで鑑賞していた学生時代の自分なら神作と思ったのだろうけどなーと、昔を懐かしむ気持ちになりました。
主演のエマストーンの裸体やおしゃれコスチュームを着たビジュアルを記録する為の映画なのかと途中まで思っていましたが、一応主人公ベラの怪奇な出自の真相と、それに決着をつける結末にはなっていたので、話の筋は通っています。
個人的にはベラが人間性を獲得する中で有意義なストーリーやベラの苦悩や葛藤が殆ど描かれなかったので、ほぼ共感できず。
またベラが友好的に接するのは自らを蘇生させた、父親から苛烈な虐待を受けた老外科医と、その助手になり、ベラの婚約者となる知識はあるが少々気弱で小柄な男性、知識階級の老貴婦人とパートナーのイケメン黒人男性、娼館で出会う学のある黒人娼婦などのマイノリティで、
ベラが破滅させるのは強権的な白人男性としっかりフェミニズム、ポリコレ主義が描かれており、最近の洋画はそんなのばっかで正直うんざりしていまいます。
ビジュアルイメージが個人的にどハマりだったので星3.5にしてますが、2時間半もある割に大した感動も無い映画なので、ストーリーだけなら星1です。
美術とか不思議な世界観が好きな人におすすめ
めちゃくちゃなSFなのにきちんと成長を描く
マッドサイエンティスト的な発想でめちゃくちゃな手術をして逆コナンくん的な女性が誕生して、その女性の冒険と成長をきちんと描いているすごい映画。
設定や出来事だけを見たらなかなか倫理的にも心が動揺するような話である一方で、きちんとベラの成長が描かれていてラストのシーンの平穏さになんだか涙が溢れ出た。
自分は駄目でしたネ…。
私の身体は私のもの
亡くなった女性に胎児の脳を移植し、蘇らせるという女性版フランケンシュタインのような設定にまず驚く。幼児の自慰行為から性に目覚め、それから言葉や知識を覚え、社会を知っていくという流れも面白い。
テーマとしては、私の身体は私のもの、硬く言えば「性の自己決定権」ということか。後半になるほどフェミニズム的な色合いが濃くなる。
ただ、作品の構えがあまりに技巧的・人工的なので、感情を揺さぶられるという感じはない。美術・装置は凄い。そして衣装。ビクトリア調のようで現代的な独特さに目を奪われる。
映像としては、モノクロになったり、覗き穴から見るような魚眼レンズになったり、色々工夫しているが、それほど効果的とは思えなかった。
エマ・ストーンは、アンダーヘアまで晒しているが、いやらしい感じはしない。ウィレム・デフォーが最初はマッドサイエンティストと思ったが、切なさも感じさせて好演。ハンナ・シグラが出てきたのには驚いた。
観終わってから、タイトルの哀れなるものたち(原題Poor Things)とは何を指しているか考えている。複数形なので、主人公ベラのことではないのだろうが。
かわいい子には旅をさせよ!
大人の身体に子どもの脳を移植したら
どうなるんだろう?だなんて考えたことなかった。
前述からしてSFっぽいのかなーと思っていたが、
少女の成長に着目した作品。
設定は非日常的だけど、その成長過程はリアルさを感じた。
あらすじ
胎児を身籠ったヴィクトリアは自殺を試みた。
自殺は成功するも天才外科医によって蘇生される。
しかし、それは完全なる蘇生ではなかった。
見た目はヴィクトリア、脳は身籠っていた胎児の脳を移植されたのだ。
ヴィクトリアとして記憶のない女性は“ベラ”という少女として新たな人生を歩み始める。
急速に成長を遂げるベラの様々な体験の話。
かわいい我が子は
ツラい思いをしてほしくないし、
なるべく危険から遠ざけて
安全な場所で暮らしてほしい…!
みたいな気持ち ちょっとわかるかも(!?)
でもそれは子どもの成長には繋がらないし、
様々な経験をしてこそ、自分という“個”が
確立していくと感じた。
善悪も判断できない年齢の子が、
1人or信用できない大人と外の世界を知るのは危険!
信頼できる大人と共に、
様々な経験を経ていくのがいちばん良いんだろうなと思った。
すごいが苦手
ブレードランナー 19世紀
ブレードランナーのレプリカント=レイチェルは精神を安定させるために別人の記憶を移植されていた。この映画のベラは胎児の脳を移植された、言わば記憶の無いレプリカントだ。
なるほど情緒不安定で善悪の区別もできず、マナーやモラルに欠けている。ゆえに成人するまでのモノクロ映像パートは不快なシーンのオンパレードで、これが赤ちゃんや子どもであれば笑って許せるのだけど、成人女性だと眉をひそめてしまう自分自身の感情に驚いてしまう。
しかし心は純粋無垢。それ故に、遊びのつもりでベラを誘惑した弁護士が心底ベラに惚れて自滅していく様は、思わず同情してしまった。弁護士を演じたマーク・ラファロはハルクとは比べ物にならないくらいの芸達者ぶりの演技力。もうハルクは完全に卒業して欲しい。
さらにこれが復讐劇に転じて行く過程は一種のカタルシスさえあるが、オチだけはちょっと不満。
(以下、ネタばれ)
過去の夫に復讐でヤギの脳を移植してしまうが、どうせなら親であるゴッドウィンの脳を移植させて欲しかったな。まあさすがに倫理的にダメかもしれないけど。
油断してました
感想を述べるのがとても困難な映画
ラ・ラ・ランドのエマ・ストーンとプラトゥーンのウィレム・デフォーが共演しており、話題作なので、こっそり朝一番で一人で観てきました。表層的には荒唐無稽で極めてインモラルな映画であり、有名女優の性的描写も観ていて可哀想になりました。一方で映像が幻想的かつ非常にきれいで、ある種寓話的な不思議な風景が続きました。そして観終えたあと、向かいの椅子の背もたれにメガネを強打して、そのままメガネ屋さんに行く羽目になるくらい、頭がクラクラする、強い精神的衝撃を受けた映画でもありました。
シネコンで全国に配給される映画というより、独立系のミニシアターで上映されるようなテイストの映画です。そういう映画が好きか嫌いかでも評価が分かれると思います。とはいえ、観ていて退屈することはなく、観終えたあとは、案外と悪くない気持ちではありましたが。
原題は「POOR THINGS」で、彼女も、彼女に関わった男性も、皆さんPOOR(可哀想な)な人たちであり、さらには主人公の旅の途上で本当にPOOR(貧しい)な人々に遭遇したり、女性も男性もPOOR(可哀想な)な存在なのかしら?とも思える一方、旅はたくさんの経験をさせてくれる、人間を成長させるもので、さらに言えば”生きていることはとてもおもしろいもの”、とも感じさせる映画でした。
ちょっと違いますが、手塚治虫の「ガラスの脳」という古い短編を思い出しました。この漫画に登場する少女も17歳の身体で赤ん坊の脳の状態でしたが、わずかの期間に急速に成長し、再び意識不明になる、とても可哀想な物語でした。それに比べるとエマ・ストーン扮する主人公はハッピーエンドを迎えることができたので、それはそれで良かったのですが、僕の常識やモラルを破壊されそうになったのも確かな、大変な問題作です。
タイトルなし(ネタバレ)
親であれ友達であれだんなであれ恋人であれ
誰かを誘って見に行くような映画じゃないなと思います。
船に乗ってたご婦人とその連れが非常に魅力的でした。
そしてこんなに美しく静かなエンドロールは珍しい…
何かを汲み取ろう、分かろうとすると小難しくなりそうなので途中から放棄しました。
ただただベラとベラに関わる人達が少しでもしあわせになればいいなと思いながら見ていたように思います。
ある意味私もゴッドの視線だったのかな…
ベラの目が印象的
エマ・ストーン演じるベラの目の表情から、ずっと目が離せませんでした。
セットと衣装もとても素晴らしかったです。
ラストはてっきりゴッドが亡くなる前に将軍の身体に脳を移植するのかと思いましたが、そう安易な展開ではありませんでした😅
ベラが婚約者にプロポーズしたシーンが好きです。
原題"Poor Things"とは???
妖怪人間ぽい?と思いきや
全672件中、301~320件目を表示