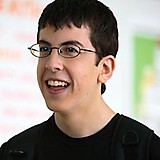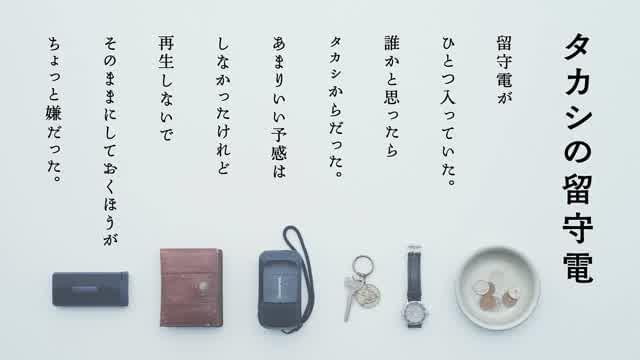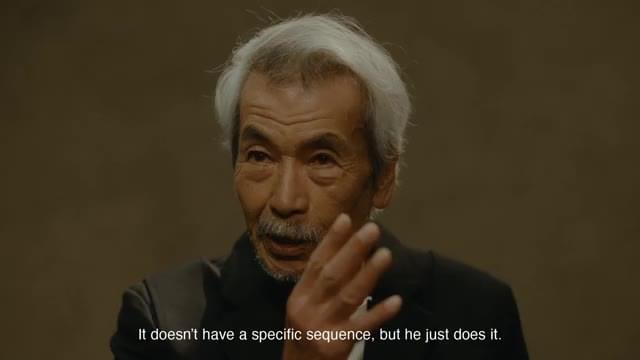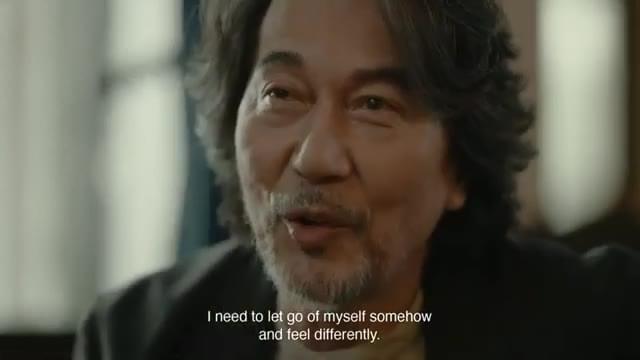PERFECT DAYSのレビュー・感想・評価
全228件中、141~160件目を表示
2度目の鑑賞後の思い・・・あなたの生き方は?と問われれば答えは「No」
先ずは1回目の鑑賞後のレビュー
perfectDaysという映画を私なりに読み取ってみて・・・素直に感動はできなかった。
どうしてフォークナー?どうしてルーリード?どうしてアート作品然としたトイレ?
日常の一瞬に見いだせる美や人生のささやかな喜び、そのメイン素材にこれら小道具がどうにも微妙に作用している気がします。
フォークナー?京都の大学で出来の悪い英文学専攻の学生だった自分にとって、ジョイス、ナボコフ、ピンチョンとならんでunreadable(解読不能)な作家の代表だったフォークナー。「野生の棕櫚」?読みましたよ、もちろん翻訳文庫本で。(原書で読むほど頭も時間もなかったです。あ、ついでに金もね)
そういうことですか。事件らしい事件も起こらない、主人公の淡々とした日常描写が連なるこの映画、実は「野生の棕櫚」で並行して描かれた2つの物語を平山という一人の人物の物語に再構築したものなのか。
モノクロームの映像から伝わってくる不穏な感じはハリーとシャーロットの物語とリンクし、平山の凄惨な過去を想起させる。
そして、現在の平山の淡々とルーティンをこなす日々の描写。それはまさに過去を償う囚人の生活。冒頭のHouse of the Rising Sunは足にball and chainの囚人の歌であり、Lou ReedのPerfect Dayも執拗に過去の行いの清算をリフレインして終わる曲。家出した姪っ子をかくまい数日を共にして、結局母親に引き渡すエピソードは、「野生の棕櫚」のもう一人の主人公である囚人が、洪水から妊婦を助ける物語と重なり・・。テレビもスマホもない部屋は囚人が暮らす監獄の部屋のイメージ。けれど、本と音楽に守られた平山にとって、その部屋は監獄でもあるけれど唯一の安寧を得られる温室でもある。
「野生の棕櫚」の囚人が、一旦得られそうになった自由を捨て、あえて監獄に戻ったように、平山もまた壁のない監獄(温室)での生活をこれからも続けていく。平山がラストシーンで流した涙、それは凄惨な過去を「別の世界」でのことと切り離し、今の新しい世界での生活にようやく平安を見いだせた喜びから流した涙のように見えました。
・・・とまあ、フォークナーの作品やら劇中に平山がかける音楽やら、あれこれ周到に配置された仕掛けをひっくるめて、Perfect Daysという映画を読み解いてみて・・・
でもやっぱり素直に感動はできなかった。
だってね、フォークナーとルーリードで武装した役所広司の「ただものでない感」。人生のささやかな、本当の喜び、豊かさ、美しさ・・・それが、選ばれた特別な人種のものになってしまう感じ。既にピカピカに見えるトイレを更に磨き上げる平山は、引退した美学部教授が骨董の青磁を愛でているようにも見えてしまう。
現代アートのようなトイレ?60年代70年代を想起させる文学作品や音楽を取り上げるなら、まさにその時代全盛を誇った(?)落書きだらけのトイレをなぜ登場させない?人々の欲望や哀しみ、得体のしれない熱情が書きつけられたトイレの落書きがなぜ映し出されない?私の暮らす街には今だそんな落書きだらけの公衆トイレがありますよ、東京にだってまだあるんでしょ?
写真現像屋の親父・・・柴田元幸氏ですよね。東大名誉教授、米文学研究者にしてMason &Dixonなど多くの英米文学作品の翻訳家。ここで彼を写真屋の親父に起用する理由って?
フォークナーのパスティーシュとしてのサイン?
そんなこんなで、皆さんそれなりに感動できる映画にしております、でも隠し味が本当に判る人にはもっと、ね・・・
というのが鼻についてどうしても感動できなかった。何より、歴史のひずみや世の中の矛盾が多くの人々の血を流させている現代の事象を己の「関心領域」の外に置き、監獄=温室に引きこもっている主人公のその閉塞性にどうしてももどかしさを感じてしまった。
社会から孤立したうらぶれた老掃除夫が、トイレの落書きに書きなぐられた様々な言葉に自分の過去を重ねながら、それを消していく行為を通して少しずつ世の中に、未来に向きあう自分を取り戻していく、そんな物語なら感動できたかも、なんて思ってしまう自分はつくづくひねくれ者なのかな・・・
あ、平山さん、あなたにぴったりの曲、I Am A Rock なんてどう?
そして2回目の鑑賞後の今の思い・・・
もし、ヴェンダース監督が、この映画を通して私たちそれぞれに、「で、平山のperfect daysは、あなたの生き方としてあり?」と問うているなら、答えはやっぱりNoです。
「世の中には繋がっているようで繋がっていない、別の世界がある」という平山さんの言葉、それの言い換えに過ぎないのだけどやっぱり私は「世の中は繋がっていないようで繋がっている世界でできている」と、特にニコ、あなたのような若い人に言いたい。「変わらないはずがない」と平山さんが言う「変わる」とは「過去と現在の分断」ではなく「過去と現在、そして未来を繋ぐ」意味にとらえたい。テレビや新聞を通して見る世の中の様々な出来事はどうしても自分の関心領域を侵食し、それ故に心をざわつかせたりオロオロしたり・・・そのくせ、大した行動に出れるわけでもなく(せいぜいやや顔をうつむき加減にしながら、反核や反戦のデモに恐る恐る参加したり、ほんのわずかな小銭を募金箱に入れたり・・・)。選びたい候補者がいないなどと言いながら選挙会場に足を運ぶけど、それは要するに選ぶ明確なビジョンを自分自身が持ち合わせていないことに他ならないわけで・・・
宮沢賢治の「雨ニモマケズ」の中の一節、
ヒドリノトキハナミダヲナガシ
サムサノナツハオロオロアルキ
ミンナニデクノボートヨバレ
ホメラレモセズ
クニモサレズ
だけを実践するような私の日々です・・・やれやれ。
そんな私には、平山さんのような生き方はできない。「今は今、今度は今度」と言い切れず、「今に引きずる過去は、そのまま未来に繋がっていく」し、木漏れ日の美しさは、スナップショットに切り取った一瞬だけでなく、むしろ時の流れの中、光や色の移ろいの中に見出したい。(まあ、さすがに部屋はもう少し整頓したいですけど・・・あ、作りかけのガンプラのパーツどこいった?)
私自身の生き方を見つめ直した上で、あえてこの映画の評価を2度目の鑑賞後は★一つに下げます。
皆さんはどうなのかしら・・・
解釈難しくても楽しい世界
安っぽく役所さんの人生を振り返らないので解釈は色々だと思います。わたしは、エンディングのアップの長回しで、笑っているようにも、泣いているようにも、疲れているようにも、充実しているようにも、明日が楽しみだと言ってるようにも、いかようにも取れる役所さんの顔がすべてのような気がしました。
少なくても平山はこれまでの人生をしっかり咀嚼して、今の今を生きていると思いました。つまりは充実しているということです。キャッチコピーの通りです。憧れます。
映画はとても面白かったです。田舎の映画館にあんなに客がいるとは思いませんでした。どうでもいいことを考えながら観ていたので備忘録としていくつか書いておきます。
同じ場面をセリフ少なくして何度も何度も繰り返す演出、かなり前ですが小林政広監督の「愛の予感」を思い出しました。
あちこちにキャスティングの面白さがありました。日本人監督ならこうはならないかなと。石川さゆりさんは驚きました。川崎ゆり子さん出てたんですね。解説読むまでわかりませんでした。イメージ変わりましたね。
浅草の地下街、桜橋、隅田川など、わたしは18から24まであの辺りに住んでいたので懐かしく、ただ実際の平山の移動にはいくらか無理あるなと思いました。
三浦友和さんでやや無理やりまとめたような気もしましたが「わからないこと、世の中にはまだまだたくさんあるよ。でも終わりだ」にはグッときました。
大都会の片隅、木漏れ日の中で織成すひと時~ 人の出会いと温もりを感じた!
監督:ヴィム・ヴェンダース作品
彼の作品は『パリ、テキサス』『ベルリン・天使の詩』『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』『ミリオンダラー・ホテル』とかで有名なのかな。どの作品も心地よくて一度は目を閉じて寝るかも~www。
今日は「PERFECT DAYS」を観に行ったぞ。
こう言う作風は本当にいつ見ても彼らしいなぁの一言。
主人公 平山、THE TOKYO TOILETの寡黙な清掃作業員:(役:役所広司さん)。
初っ端から都会の公衆トイレ清掃ってヤツをこれでもか~って位見せてくれる。
ちょっとこのシーンは長いかなと思う。人物像を現わすには必要かもだけども。
清掃車内にかかる懐かしの洋楽がメッチャ心地いいなぁ。そう思って聴きいった方も多いだろう。車の停止やドアの開閉で突如寸断されるメロディに、もっと聴きたいなときっと思う事でしょう。
今時見かけないわ~カーステ。音楽アルバムカセット持ってるけどテープ延び延びやで。
絶対SDとかだと思うけどな、やっぱテープのアナログ音質が受けるのかな。
カメラも同じくでデジカメ多い中、銀塩写真て・・・今時現像店が分かんねぇ。
裏ブタ開けてパトロ-ネからのフィルム供給音、懐かしいナ。
音楽も写真もその時代の味ってやつがそこで現わされていると思う。
トイレ清掃中に見かけた3マス並べ?の落書きメモ回し。
相手は?良く見かけるベンチに腰掛けのOLさんなのかな。それとも女子高生?。メモのやり取りが続いていくって事や、カセット音楽を気に入ってくれた彼女や、樹木の根の元で見つけた新しい植物や、遠くで軽く挨拶してくれるお坊さんなど、木漏れ日の中で覗く彼の周囲の人々の心がほんのりと温かい。そう感じます。
叔父さんと慕い突如やってくる家出の姪。念のため妹に連絡して迎えに来させるが、相手は凄い裕福そう。この対比表現が生む見えない境目がこの作品のテーマなのかと感じます。
TT兄弟じゃないけどw(“T”多い)-THE TOKYO TOILET-この清掃作業着は誇れるものではないの?だからこの作品があるんでしょう?そう思うんだな。
誰かが汚れた後を綺麗にする、だから明日が(次が)ある!そう思うんだよネ。
残念な所を一点あげるなら、多分 平山は真面目で独身だけど、居酒屋の女将(役:石川さゆりさん)に好意があった様なんだな。最終的に勘違いだったけども抱きついてた元夫との姿を見て 急にその場から去って、あんなにタバコに酒に急に溺れるかね?あれは有り得んよと思う。
その後 気にして追いかけてきた元夫が まさかの初対面に病名告白。かつ元女房をヨロシクと言うのだ。展開流れが今まで各駅停車でのんびりと旅してた気分だったのに、最後きて急に新幹線に乗って最終目的地に着いた~って感じしたわ。それとラストカットの運転席の場面で真っ直ぐ走っている車なのにハンドルに手を掛けて回しすぎだよと思うw(細かく見ててゴメン)。そこがとっても残念!
「君の名は。」かと思うぐらいとても綺麗な都会の朝焼けシーン。その街中をゆっくりと清掃車がカセット音楽を奏でながら 今日に、明日に ほんのりと温かい心に満たされた彼が走って行く~。
興味ある方は 是非劇場へどうぞ!
成熟かおとぎ話か
『PERFECT DAYS』成熟した社会のおとぎ話でしょうか。ヴィム・ベンダースの一つの提案、年寄りはこの映画を見ると自分の今後はこれでいいやと思うのですが、若い人には物足りないでしょうね。消費は美徳という時代を経験して到達した生活ですから。
高度成長期、バブルそして崩壊
高度成長期、バブル期を通り過ぎて行き着いたところでしょうか。
主人公は、映画では50代の独身のように思われ。
東京の下町の風呂なしアパートに住み。
公園のトイレ清掃で生計を立てている。
これといってお金のかかる趣味があるわけではなく。
室内には、丁寧に育てている観葉植物。
仕事の後は、銭湯でさっぱりして、浅草あたりの安酒屋で一杯。
自宅に戻り、おもに部屋では読書。
まるで、現代の仙人の趣。
年齢からして、日本経済が、イケイケのころも知っているはず。
「24時間戦えますか」なんて時代もありましたね。
自分にとって大切なものとは
そう、この主人公にとっては。
このささやかな生活で、十分幸福なんだと。
人それぞれ器というものがあって。
この主人公は、幸福の器がこの映画の大きさなんだと。
人間ある程度年齢が行けば、ある程度見えててくるのですが。
幸福と感じる器の大きさが、そんなに大きくないほうが、人間をやれるよなと。
この映画を見てるとそう感じさせます。
ヴィム・ヴェンダースの結論でもあるかのようです。
人間一人生きてゆくのには、そんなにお金はかからない。
お金のかけ方にもよりますが。
この主人公のように、幸福感の器はそんなに大きくなく。
そして、お金がなくても創造的に生活できる工夫ができればですが。
ヴィム・ベンダースは、「お金がなくても、幸せになれるよ」と言っているかのようです。
東京の下町とトイレ掃除
ヴィム・ベンダースはこの2つを選択したようです。
東京下町の風景が、なにか刺さるものがあったのでしょうね。
ただ、これはあくまで映画でのお話。
いわゆる、下町幻想でしょうか。
実際には、下町は、首都圏以外から流入した新住民の街。
かつての人情などあるわけもなく。
意外と、殺伐としていて住みにくいところなんですが。
あと公園のトイレ掃除ですよね。
最新のオシャレな公衆トイレしか出てきませんが。
確かに、日本の公衆トイレはかなりキレイになりました。
だけど、この主人公の作業するようなキレイなところばかりでないのが現実。
特に、駅のトイレの掃除などは、かなり心が折れる場面に遭遇するのですが。
このあたりが、現代のおとぎ話でしょうか。
ほぼストレスフリーな生活
主人公のように、収入は少ないが。
人と多く交わることもなく、自分のペースで仕事ができて。
贅沢をしなければ、自らが満足できる生活を送れる。
そんな生き方を提案してるんだろうな。
まあ、それも悪くないけど。
やはり、年寄りになればそうならざる負えないと思うのです。
それでいて、昭和の活気を知っている者にとっては。
あの消費は美徳とまでは言いませんが。
あのエネルギッシュな時代が懐かしいのも事実。
さあ、あなたはどんな人生を送りますか。
すべては、アナタ次第です。
こんどはこんど、いまはいま
太宰治の『人間失格』は「ただ、一さいは過ぎて行きます」という言葉で終わるけれども、その《過ぎていく一切》に光を当て愛おしむこと、その大切さに気づかせてくれるような作品であった。
トイレ清掃の仕事をしている平山氏(演:役所広司)の日常を追った作品、と、言ってしまえばそれだけの映画なのに、エンドロールが流れた後の、感動の深さ。
ドキュメンタリータッチの映像はちょっと是枝裕和監督っぽいかも知れない。作品のテイストは『海街diary』に似ていると思った。だから『海街…』で寝ちゃう人は観ない方がいい(笑)。
観る前は、役所広司主演でちょっと似たようなシチュエーションの作品『すばらしき世界』(2020年)に似た内容かと思っていた。しかしこの『PERFECT…』は想像を超えていた。
平山氏の部屋にはテレビもパソコンもスマホもない。新聞も購読していなさそう。車の中でラジオも聞かない。唯一の情報機器が会社支給らしいガラケー。
音楽はもっぱら古いカセットテープだ。Spotifyなんぞもちろん知らない。写真が趣味だが、持っているのはフィルムカメラだ。彼の身の回りにあるのは皆《失われゆくもの》たちだ。
しかし、そんな彼の暮らしは、何故「美しい」のだろうか。
映画館を出たあと、世界が少し変わって見える。そんな作品に、すごく久しぶりに出会えた。
【蛇足】
①脇役に「タカシ」という名前を安直につけるのはやめてほしい
②平山氏はなぜ寝るときカーテンを閉めないのだろう。
→朝の明るさで目覚めたいから?
③パンフレット売り切れだった、残念!
④カセットテープ巻き戻す場面で笑った。
⑤本を読みながら寝落ちするのは私も。
でもあんなに目覚めはよくない。夜中に一回目が覚めるし。
⑥銭湯の場面。役所広司の身体は年相応に衰えているみたい。
胸まわりの筋肉が落ちていて、意外とみすぼらしい。これも演出か?
⑦あれは研ナオコだったのね!
⑧昼休みとか同じ時間に同じ場所で同じ人に会うのは、あるある。
でも親しくなるわけではない。
⑨幸田文の『木』は持ってたけど数年前にブックオフに売った。
映画の醍醐味…
カンヌ受賞という前評判はあったものの、できる限り心をピュアにして、鑑賞した感想を書き出してみる。
前半は役所広司という「大俳優」が演じているのに、まるでドキュメンタリーを観ているような錯覚を覚えた。
朝目覚め、身支度を整え、小さな器に植えた楓の世話を終えると、車に乗り込み、淡々とトイレ清掃に向き合い、仕事後の銭湯、飲み屋、そして簡素な部屋で眠りにつくまでの読書で一日を終える。
そしてまた新しい朝を迎え…
ただこの繰り返しである日常に、ほんの小さな、些細な出来事が交わることで、人としての尊厳や他者への思い、そして「自分が自分である」という存在を直接的な言葉でなく、スクリーンに投影される主人公の表情や、まるで絵画のような色鮮やかで多彩な景色(風景)から、心が満ち足りるほど感じることができた。
正にこれが映画の醍醐味であり、映画の素晴らしさであることを、改めて思い知ることが出来た作品であった。
この作品のもう一つの見どころは、その映像美であると思う。「綺麗」という言葉では表現できないほどの感動を覚え、それはふと立ち寄った美術館で、立ちすくむくらい見入ってしまう絵画に出会ったようである。
久しぶりに「映画の醍醐味」を感じる作品に出会えたことに感謝。
美しいが、危うい
政治とか経済とか世界情勢とか社会とかと一切隔絶した、一種の晴耕雨読の隠遁生活を描いた作品。
出来事は主人公平山の周りを通り過ぎていく。
平山氏は清掃会社に所属しているので、会社への業務日報なり、定時連絡なり、給与の振り込みなりがあるはずだが、そこも描かれない。
平山氏の実家は裕福な資産家のようだが、資産には興味がないらしく、妹から実家に戻るように提案されても、拒否する。
家族も財産も捨てた、一種の仙人みたいな生活である。
会社員人生とか長いと、煩わしさから解放されたこういう生活に憧れる気持ちがわからないでもない。美しいとも感じる。
でも、交差点で不注意なドライバーが信号無視して突っ込でくるもらい事故だって、現実にはあるわけじゃないか。そう思ってしまう。
小津安二郎を敬愛するのであればカメラはパンを一切しないでほしかったな。
繋がっていなくても、重なり合って生きている
この映画を言葉で表現するのは難しい。表現しきれない何かがある。敢えて言うなら・・・
都会の片隅で生きる一人の善き人の日常を、美しく、純粋に切り取って見せる。ただそれだけなのに、人生とは何か、幸福とは何かについて考えさせられる、ような作品。という感じだろうか。
※キャスティングと音楽の選曲のセンスが凄い!サントラ欲しい。
※年末年始に1回ずつ鑑賞。2024年4月堪らず3回目鑑賞。
■1回目(2023年末)
福山雅治がラジオで「奇跡の映画」と紹介していたのを聞き、年の締めとして映画館へふらっと行って観た。カンヌで役所広司が主演男優賞をとったトイレ清掃員の映画、という事前知識しかない状態での鑑賞。
主人公の平山は、毎日決まった時間に起き、布団を畳み、髭を剃り、歯を磨き、植物に水をやり、空を見上げ、缶コーヒーBOSSを買い、車に乗ってトイレ掃除の仕事に向かう。仕事場では一切の無駄口をたたかず、ムダのない動きでトイレをきれいに磨き上げ、帰宅したら銭湯で一番風呂、浅草地下街で晩酌、読書して床に就く。まるで修行僧のように寡黙にルーティンをこなす日々。
前半は、余計な演出も台詞も音もなく、ゆるい流れで特に大きなイベントも発生しないので、色々と想像を巡らしながら観ることになる(研ナオコにはすぐ気がついたw)。
中盤を過ぎて、「今度は今度、今は今」という言葉を聞いたとき「脚下照顧」という禅語が思い浮かぶ。ああ、やはりこれは、外国人監督が理想の日本人像(令和の東京という俗世に生きる禅僧)を描いた話なのかな・・美しい映像と抜群のセンスの選曲のオシャレなアート映画なのかな・・・と見続けていると・・・
妹と姪との別れのシーンで号泣する平山に壮絶な過去が垣間見え。
ラストシーンで流れる「Feeling Good」に合わせて悲しみ、後悔、喜びといった色々な感情がない交ぜになって泣く役所広司を観て、自分も内側からこみ上げてくるものが・・・
何か凄いものを観た!という感じで呆然としてしばらく動けなかった。
恥ずかしながら、Wim Wenders監督も、「PERFECT DAY」や「Feeling Good」の歌詞もよく知らずに観た1回目。一旦映画館を出た後、戻ってパンフレットを購入。40代中盤まで生きてきて、映画のパンフを購入したのはこれが2作品目。
映画の余韻に浸りながら年を越した。
■2回目(2024年始)
あの場面の台詞の意味は何だったのか?あの映像の意味は?平山の過去に何があった?色々考えながら、これはもう一度観なければ、と年始に再び映画館へ。
1回目は観ているようで観ていなかったこと、気づかなかったことに色々と気づく。
平山は、微笑む。自分を取り巻く人々、街並み、木々に。そして光と影を愛する。トイレの壁に映る木々の影、木漏れ日の下で踊るホームレスを観て幸せそうな笑みを浮かべる。
と思いきや、同僚が突然やめて怒りの感情をむき出しにする。
不意にキスされた後、銭湯でニヤけて湯につかる。
ヤケ酒も飲む。吸えないたばこも吸う。でも、最後は微笑みながら帰宅する。
彼は禅僧なんかじゃない。生身の人間だ。
禅僧のようなルーティン生活をしているのは、つらい過去や孤独に飲み込まれるのを防ぐためではないか?
リズム。一定のリズムを刻み続けるように生きることで今に集中できる(音楽やダンスのように)。そんなことが頭をよぎる。
最後のシーン。「Feeling Good」の歌詞の意味をわかってから観た2度目。役所広司の演技は、顔面だけで平山のこれまでの人生、そして今、これからを表現しているように思えて、泣いてしまった。
■3回目(2024年4月)
3回目の鑑賞で、東京スカイツリーを見上げる構図、複数階層になった首都高を見下ろす構図が何度も出てくることに気づいた。これは平山の視点ではない。Wenders監督の視点だ。監督は、愛する今の東京の街と平山(役所広司)の日常をたった16日という短期間で、瞬間冷凍のように記録し、封印したのだ!この映画は、もう二度と同じように撮れない「奇跡の映画」なのだということを思い知らされた。そして、ラストシーンの朝日の光は、平山のPERFECTな日々がこれからも続くことを示す、人生賛歌の光なのだと私は感じ取った。
■繋がっていなくても、重なり合って生きている
「この世界は、繋がっているように見えて、繋がっていない世界がいくつもある」と言う平山に対して、ニコは「私はどちら側の世界にいるの?(おじさん側の世界って言って欲しい)」と聞く。平山は答えない。
最初、自分(平山)が住む世界は、多くの人が住む世界と違うという意味だと思ったが、回を重ねて観ると、それは多分違うと思った。今、生きている一人一人が、繋がっているように見えて、他人と繋がっていない世界を生きている(みんな孤独)という意味ではないか。でも、影踏みで平山が言った「重なって濃くなる」という言葉から、繋がっていなくても、ときどき重なり合うことで、人と人は関わり合い、生きているんだ、という人生観を平山が持っていると私は思う。
観る人によって、いろんな解釈ができる映画。
そして、孤独を抱えながらも、毎日を新しい気持ちで、生きようと思える映画。
朝、空を見上げるのがしばらく習慣になりそう。
概ね良いかと思いますが…
絶対に日本人ではとれない感覚の映画かと
観る人の年齢や住んでいる環境、東京か田舎か
また人生観で評価は180度変わるかと思います。
わたしは自販機での飲み物を毎日買うシーン。
姪の女性がでてくるシーン、妹さんとの会話シーンは良いですね。
ただ、後半の三浦友和さんがでてる飲み屋から
橋での会話シーンは賛否がわかれるかと思いますね。
あそこから映画がかわりました。
私は、ない方が良かったかとも思いますが
どうでしょう?
ただ、絶対に見たほうがいい映画かと思いますね。
良く言えば静かな映画
特に事件が起きるわけでも、何かが解決するわけでも、だれかが成長するわけでも、伏線が回収されるわけでもない。
厳密にいえば事件が起きたり何かが解決したりだれかが成長しているのかもしれないが、観ている人間の想像力に委ねられる部分が大きい。
ここから何かが始まるのかな? と思わせておいて特に何も始まらなかったり、あとあと関係してくる人間かと思いきやその場限りの人物だったり、ルーティーン動画とか「かもめ食堂」を観たあとのような気分になった。
役所さんの演技をじっくり堪能したい人には良いかもしれない。
個人的な感想では役所さんはスマートでナイスダンディすぎるので、もっと苦み走った芝居のできる醜男で不器用そうな俳優ならもっとハマった気もする。
昭和の雰囲気がする主人公の住居や、淡々と過ぎていくささやかな日常を眺めるのは好きだが、映画館で観るほどではないかなと思ってしまった。
でも自宅のテレビで、大きなイベントのない映画を集中してみるのは難しい気もする。
日常が永遠に続く訳ではない⁈
驚くような事件は何も起こらないのだが、とても心に沁みる作品。やっぱりコロナ禍を経験した後だからこそか? (作品の企画、キッカケは2018年だったようですが…)
役所さんが演じる、淡々とルーチンな日々を送る公衆トイレ清掃員の平山。朝イチの缶コーヒーとカーステのカセットで流すお気に入りの音楽で一日のスイッチを入れ、黙々と清掃作業をこなし、ランチ休憩の境内で木漏れ日を写真に収め、銭湯の一番風呂に感謝し、その後に寄る安居酒屋での一杯に至福の表情を滲ませる。そして、アパートで好きな本を読みながら、せんべい布団で寝落ちする毎日。
そんな日々の中の些細な幸せ。偶然発見したまるバツゲームにちゃめっ気を出し、ホームレスのダンスに感嘆し、木の芽を見つけて大事に持ち帰り慈しむ。
この毎日こそが、パーフェクトデイズだった⁈
ところが、小波のように、同僚の若者が絡んだ小さないざこざがあったり、裕福な実妹の娘が家出して安アパートに訪ねてきたり、休日(休日だけ、腕時計する)のルーチンではあるが平山にはハレの空間の小料理屋の女将と元夫の再会に出くわす、なんて事が起きて…
それらが、平山の日常、そして感情を大きく揺さぶった事を、ラストに役所さんの素晴らしい表情の変化だけで描く。本当に見事なシーンでした。
でも、平山はその後またパーフェクトデイズに帰って行くのでしょう。
女将が常連客のギターに合わせて歌う曲、運転中や休日のアパートでカセットから流れる楽曲がどれも素晴らしかった! あと、浅草やきそば福ちゃん、久々に行きたくなりました!
新年早々に良い作品に出会えて感謝です。
とても味わい深いが、強烈な3D酔いが襲って来た。
iTunesかSpotifyでlou reed の"perfect day"を聴いてみて、好きだったら観ても良いですが、今一つなら観ない方が良いです。
あの曲を映像化したと言っても良い。淡々と始まり抑揚もなく、淡々と終わる。その世界観にしばし意識を浸せるかどうか。
被害者多数の様子でした(笑)。観客のお一人は「役所広司やからもっと面白いと思ったのに」と文句を言ってましたが、役所広司の動の演技を期待してたんでしょう。
敢えて言うと洋楽聴かない人(英語が堪能な人を除く)は楽しめないと思います。歌詞の意味のよく理解できない音楽を楽しめるか、雰囲気を楽しめるかなのかなと。
僕はと言えば楽しめました。この手の山もなければオチも無い映画はそういう楽しみがあるのは分かりますし、功成り名を遂げた巨匠の最新作(最近この手のマスターベーションにうんざりしてるもので…)ですが、映画としてとても丁寧に作られてるのがよく分かる。
個人的にはperfect dayよりもpale blue eyesがグッと来ましたが…。
が、後30分長ければ劇場を出てました。
あの揺らぎを表現した映像は「所謂3D酔い」を引き起こします。半分を過ぎた辺りから気持ち悪くなり出して、前半の単調な展開(後半も大差ないですけど」と相まって一時は限界寸前まで追い込まれました。その意味でも酔いに弱い人は避けた方が良いかなという感想でした。元々の評価は星4ですが、あの拷問のような綺麗な映像で星一つマイナスです(これは僕の完全な体質の話ですけど)。
それと、平山の生活は不可能でしょ…と日本居住者として思いました。あの立地で駐車場代幾らするのよと。実はあの付近の土地は平山の物だったりして…なんて変なことを考えてしまった。ファンタジーなのに、野暮な話ごめんなさい(笑)。
役所広司で成り立っている映画
映画をエンタメとして楽しみたいのであればこの作品はお勧めできない。アートっぽい作品とか好きな人はいいかもね。もう冒頭喋り出すまでが長すぎる。テンポも悪い。
結局なんなのかわからないオチ。そもそもオチもついてない。姪関連のシーンは良かったけど、最後のスナックの元旦那も出す必要あった??どうせだったらもっとあの人の過去とか家族関係をクローズアップして取り扱った方が面白かった。匂わすだけ匂わしといて出さないんかい父親。
役者たちの芝居は流石素晴らしかった。
演出も良かったけど、やはり脚本が私は気に入りませんでした。流石に過大評価かなー
不思議と眠たくならない
ただ淡々と…
平山(役所広司 )のなんの変哲もなく
過ぎ行く1日1日を
見て、感じて、溶け込み同化する感覚
流れる洋楽
mama(石川さゆり )の哀愁漂う歌
ラスト、平山の表情に物語の全てが
込められているようでグッと惹き込まれます。
冒頭2箇所めのトイレがとても印象的
聖地巡礼したくなります🚽🧻
缶コーヒーはBOSS
ネットどころかテレビもラジオも持たず裸電球と電気スタンド、タンスと布団と本とカセットテープ(70〜80年代の主に洋楽)、趣味のモミジの鉢植えくらいしか部屋にないミニマリストな主人公。外の箒の音で目覚め歯磨きと髭剃りをして専用車で仕事に行き林のある神社でコンビニのサンドイッチと牛乳の昼食、仕事が終わったら銭湯と行きつけの居酒屋に行き1日の終わりは読書。休日は濡らしてちぎった新聞紙(新聞を取っているようでもなかったが)を畳に撒いて箒で掃除しコインランドリーと古本屋とフィルムの現像を頼んでお気に入りの小料理屋に行く。我々の多くはこの真反対の生活をしていると思うが日本人は静謐な暮らしを送っているイメージなのかなと思いつつ。
頭の悪い同僚の若者に振り回されて金を貸すハメになったり、長年会っていなかった妹の娘が突然訪ねてきてしばらく同居したり、小料理屋のママが男性(元夫)と抱き合っているのを見てショックを受けたりといったハプニングがあるし、渋谷区内の公衆便所の清掃とは大変な仕事だと思うが、彼の平和な生活は続いていく。
姪とは明るく会話しているものの若者が片思いしている女の子とは殆ど口をきかないくらい無口。娘を引き取りに来た妹は運転手付きの生活をしている金持ちのようだし、彼自身知的なタイプだし、姪がいる時に寝ていた使っていない台所?のダンボールも過去に何かあったのだということを示しているが何かは明かされぬまま。
古いアパートで暮らすトイレ掃除の1人の生活は不幸せか幸せか、人が決めることではない。主人公は幸せそうだが、ラストの泣き笑いは、心のどこかに孤独を感じていたのではないか。
彼の慎ましい生活には、ルーティーンになっている自販機の缶コーヒー、コンビニのサンドイッチといった、別に彼のためにあるわけではないものにもよっている。いくらでも代わりはありそうな平凡なものでも、無くなってしまうと彼の幸せは狂ってくるかもしれないと思うと、こんなつましい生活からビジネス上の理由だけで彼のルーティーンを奪わないで欲しいものだと思った。
色んな役者が出てきたが、古本屋の犬山イヌコが良かったな。
それにしてもどの公衆便所もオシャレ。大昔に『東京トイレガイド』みたいな本がロッキンオンあたりから出版されていたのを思い出した。またクレジットでShibuya city となっており、23区はcity扱いなのだな。
初老の男性の生活を神話的な構造で描く
これはよかった。
初老の男の平凡な日常を神話的な構造で描くというアイデアに驚いた。
内容としては主人公の平山が公共トイレの掃除という仕事に従事する日々を淡々と描く。それだけだと退屈になりそうだが、本作ではジョゼフ・キャンベルの英雄譚のプロットをそのまま使っている。
朝、老婆が竹ぼうきで掃除をする音で平山は目覚める。これは冒険譚において主人公がミッションを命じられる過程にあたる。
身支度をととのえて、車で出発する。
日中はトイレ掃除をする。これがミッションに該当する。
一日働くと、帰宅して、浴場にいき、飲み屋で一杯やって帰る。ここはミッションを達成して報酬を獲得するパートになる。
本を読んで寝る。
寝た後に夢を見る。これはその日の出来事が反映された、あいまいなものが多い。走馬灯のような夢だ。
翌朝、竹ぼうきの音で目覚める。
基本的にはこの生活が繰り返される。
おもしろいのは、平山の動作が細かく描写されるのに、アパートの鍵はかけないところだ。車の鍵などはちゃんとかけるので、意図的に演出しているのだろう。
平山が住んでいるアパートは現実の場所ではなくて、抽象的な母胎に近い場なのではないか。そう考えると、鍵をかける必要はなくなってくる。
平山の動作についてつけくわえると、なにかを見上げるという動作が頻繁に出てくる。これは彼が底にいる人間だから見上げるのだろう。見上げるのはスカイツリーであったり、木であったりする。
本作は植物がよく出てくる。生命の象徴として扱われているだと思う。スカイツリーもその名の通り、ツリーとして扱われているのだろう。特にスカイツリーは世界の中心のような扱いで、平山の生活圏のどこからでも見える。
公共トイレが舞台になるのは、本作がユニクロの取締役が発案した「THE TOKYO TOILET」プロジェクトが発端となってできた映画だからだ。なぜ公共トイレを発案したかというと、トイレは誰もが使う場所であり、多様性にも通じるからだ。
トイレ掃除をしている時の平山は黒子に徹している。利用者が入ってくることもあるが、平山はほとんど存在しないものとして扱われる。多様性を維持するために身をささげる、というのが平山のミッションだともいえる。
そして、トイレ掃除といえば禅的な行為でもあり、彼の質素な生活を印象づける効果もある。
おもしろいのは、平山の生活というか動作のひとつひとつが細かく描写されるのに、彼はトイレにいかないのだ。排泄をしないわけはないので、彼が奉仕をする立場に徹しているという演出意図なのだろう。
本作はポール・オースターの小説「オーギー・レンのクリスマス・ストーリー」すなわち映画「スモーク」で、ハーヴェイ・カイテルが毎朝同じ時間に同じ場所で撮り続けた写真をアルバムにして、「同じ写真に見えるが、一枚一枚全然違うんだ」と語るエピソードを思い出させる。
人生は同じことの繰り返しのように見えるが、実際には日々違うのだ、というのが本作にも共通するメッセージだと思う。
製作費は不明。興行収入は2023年11月29日の段階で2億8千万円。あまり売れているとは言えないが、言うまでもなく批評家受けは良い。なにも考えずに楽しめる娯楽映画もよいが、本作のようなさまざまな解釈が成り立つ作品が作り続けられることを願っている。
何とも切ない映画
主人公の平山だけでなく登場人物全員やるせない気持ちを抱えながら生きている様子が伝わってくるが、あまり多くは語られない。各々それを噛み締めながら生きていて、それこそが人生なのだと痛感させられた。
質素な初老の男の日常映像に惹かれるのは、現代でありながら彼だけ過去に生きているかのような演出だからかも。4:3という珍しいアナログテレビ時代の画面比率、音楽もカセットで聞いているし、昔ながらの銭湯通いは何とも昭和的。
ラストシーン、平山は全然「feeling good」ではないと思う。ただ、そう自分に言い聞かせながら苦痛のなかを生きているだけなのではないだろうか…
一見、毎日穏やかに過ごしていて、そんなパーフェクトデイズな生き方に憧れるなぁ〜っと見せかけて、実は自身の罪を清算する刑務所の規則正しい生活のなか、小さな幸せを見出す囚人の映画のようでもあるなと感じた。
生活と労働、そして音楽は生きる悦び。
「何を幸せと感じるか?それはとても個人的なこと」そうヴェンダース監督、そして平山さんから教えられたような気持ちです。
主人公の平山さんは、親が期待したエリートの道から外れたようだ。道を外れた平山さんは、ひとつひとつ自分の胸に確かめながら、生活と労働を形づくってきた。仕事に欠かせないのは、現場への行き帰り、車の中で好きな音楽を聴くこと。 複雑な組織の人間関係から離れ、ひとり黙々と打ち込める仕事は、平山さんに合っている。汚れたトイレがきれいになれば、達成感もきっとある。嫌なことがあっても、木漏れ陽を見上げれば気持ちが晴れることにも、平山さんは気づいた。
生活の場は下町にある古い風呂なしアパート。家賃、4万ほどだろうか? 夜明けとともに目覚め、身支度し、自販機で飲み物を買って仕事へ出かける。仕事の帰りに銭湯で汗を流し、居酒屋で一杯かたむけながら、お腹を満たす。趣味は、自然に芽吹いた木の苗を持ち帰り、育てること。ぐっときた瞬間の写真を撮り、紙焼きした写真をストックすること。憧れのママがいるスナックでときどきお酒を飲み、ママの歌に触れること。古本屋で買った本を、寝る前に読むこと。
そんな繰り返しの日々を泡立たせるのは、いつも人間。木漏れ陽がそうであるように、毎日も二度とない瞬間の連続。過去を悔いたり、未来を憂うことなく、平山さんは、今ここにある瞬間を味わっている。時には動揺することもあるけれど、いつだって音楽が救ってくれる。
胸に迫るラストシーン。ニーナ・シモンの歌を聴きながら運転する平山さんは、何を見ていただろう? 家族の期待に応えられなかった過去だろうか。蘇った記憶に揺さぶられながらも、心の底から「これでいい」と、平山さんは感じているようだった。
映画館で席に座る前、まわりを見渡したら、初老の方が多かった。わたし自身も、その部類に入る。わたしは主婦で、パートで介護の仕事をしている。このところお金や時間、昔はあった体力さへも減ったと感じる。仕事も生活も「これでいいのか?」と思うことがある。知人の立派な仕事や生活、贅沢な趣味を垣間見ると、落ち込んでしまうこともある。お世辞にも、人間関係の舵取りが上手とは言えない。それなのに、増えすぎたモノや人間関係に、手を焼いている。
けれどこの映画を見て、平山さんに通じる幸せの片鱗が、わたしの暮らしにも散りばめられていることに気づいた。微笑みたくなるような気持ちは感じていたけれど、それが幸せそのものとは認められなかった。
早朝、仕事現場へ自転車で向かい、途中の神社で青空や木々を見上げ、澄んだ水に触れること。高齢の利用者さんと、他愛もないお喋りをしながら笑うこと。若い利用者さんと一緒に童謡を歌う楽しみ。便秘気味の利用者さんが、しっかりウンチしてくれた時の安堵感。
キッチンで音楽を流しながら食器を洗ったり、ベランダの植物を世話すること。洗濯物がパリパリに乾いた時の、お日様の匂い。ごはんや煮物が冬の日差しを浴びて、白い湯気を立ち昇らせている風景。
映画は、平山さんの幸せな日常を映すけれど、平山さん自身は幸せを語らない。人にわかってもらおうとしない。「それでいいの?」と問われても、口ごもるばかり。自分の胸が正直に、それを幸せと感じていればいいのだ。自分なりの労働や生活の幸せの片鱗を、平山さんはこつこつ拾い集めた。そして心から満たされている。
2024年の始まりは、痛ましい災害のニュースに溢れた。沈んだ気持ちの時、この映画に出会い、自然と心が開いた。この映画に対する批判もあるようだ。それもわかる。社会が混乱に陥った時、犠牲を強いられるのは、人々の日常だ。平山さんのささやかな幸せは、いとも簡単にかき消されてしまうだろう。だからこそ、守らなくてはならない。人々の生活に影響を与える立場の人こそ見てほしい。壊さないでほしい。
平山さんという存在が、わたしの心に刻まれたこと。素晴らしい贈り物です。
汚れてないトイレを掃除する世界
個人的には完全に夢物語のような感覚で観ておりました。映画自体は皆様が言う通り、退屈などない映画でした。
汚れてないトイレを高速を使って移動しながら何のトラブルもなく、掃除する仕事。あんなボロアパートながら静寂が保てる環境。ミニマリスト風なのに自転車は2台ある生活。昔の物なのに音が劣化しないテープ。多分老いもこれ以上進行しない腰痛も無い世界。
鑑賞後に、そもそも広告用短編映画だったと言う事を知って納得しました。こういう日々ならパーフェクトで、トイレもキレイに使ってもらえる世界なんですね。これはこれでありなのかもしれないですね。映画ですから!
日々の繰り返しとは何か
平山の1日が始まる、箒をはく音と目覚めのシーンの2回目以降から、日々の繰り返しとは喜びも悲しみも全てそのままに、何事も無かったように引き受けていくことだと感じた。言葉にすると当然のことではある。
その象徴がラストの平山の長いアップの表情だと思う。
あのシーンはこれまでの車内で音楽を聴くのと違い、唯一無二の音楽体験をしたという、この映画のテーマを表現しているが、私には実際の表情というより、象徴的に作られた表現に見えた。踊りと同じような。
人は他人に窺い知れない喜びや悲しみを心に秘めて日々の生活を送っている。
この映画はハリウッドの三幕構成ではなく、独立したエピソードの連作のようになっていて、エピソードごとの感情が、平山の夢のようなモノクロモンタージュや目覚めのシーンで一旦リセットされているように見える。その積み重ねが実際の日々の繰り返しを強く感じさせる。
日々の繰り返しは「儀式」だ。
仕事に向かう、飲み屋に向かう。そのため布団を上げ、身支度する。自販機で飲み物を調達する。
私と世界の意味を形として表している儀式なのだ。
この儀式は生活者として粛々と行われなければならない。
心の込められた儀式を通して私たちは奇跡を見ることができる。もし世界に意味が無いのなら、奇跡も無い。
木漏れ日に決して同じ形の無いことに感動することはないだろう。全ては虚無、偶然の産物だ。
生活の喜びや悲しみも無く、耐えられずに狂って死んでしまうか、あるいは大きな悲しみに遭った時、受け入れられず、立ち直れないだろう。
平山は彼の儀式を通して、奇跡を見ていたのだ。
それが監督の言う、商品ではないプロセス、経験なのかもしれない。
このような面白い映画を身近な浅草でとってもらえたことがとても嬉しい。
トイレ清掃の綺麗な面だけしか描かれていないという指摘があるが、私はそうは思わない。
同僚のセリフや周囲からの扱いの描かれ方だけで充分に思われる。そして、このストーリーをよく企画者が了承したと思う。この映画は偏見や差別も否定していない。
仮にそうした描写が無くても、私たちはトイレ清掃の大変さについて容易に想像がつくのではないか。
そうでなければ、どうして平山の苦しみに感情移入できるのだろう、あるいは彼の修行者のような笑みに感心できるだろう。
彼は言わば出家したシッダールタなのであって、ワーキングプアや独身を肯定するものではない。
コピーのこのように生きれたらという意味はこのように生きれないことを言っている。
ただ、ある一瞬とか、心持ちとしてそうあろうとすることは可能なのではないか。そういう道を示している。
もしこの映画に反物質主義の非現実的な欺瞞とかもやもやを感じるなら、それが私たちが精神と物質のある娑婆世界に生きている証なのだ。
そのような矛盾の中で目に見えない大切なものを求めて生きるのがこの世に生まれた修行なのである。
全228件中、141~160件目を表示