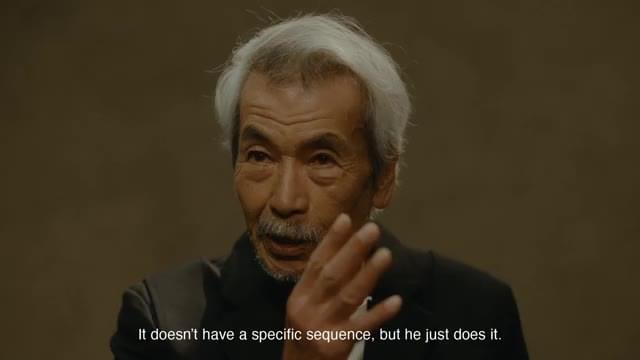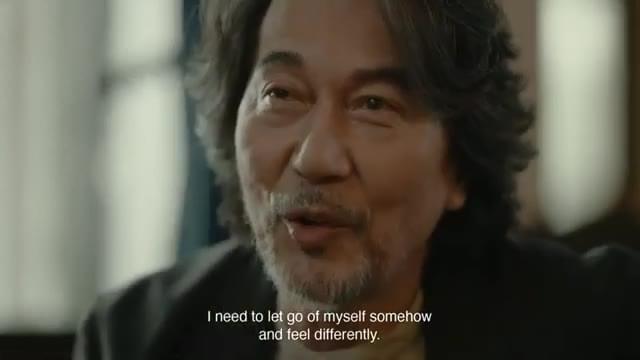PERFECT DAYSのレビュー・感想・評価
全228件中、21~40件目を表示
この映画、そんなに良かったですか?
皆さんのコメントを読んでるとすごいべた褒めなんだけど。
なんか最初から海外での上映を意識してる作品だよなぁ、英語の歌をテープで聞いたり。兄、妹で抱き合ったりする????実際、当方(女性)、兄がいるけど抱き合ったことなんて人生一度もないよ???
てことで、すごい違和感ありあり、って思ってたら監督がヴィム・ヴェンダースって
ドイツ人てことで納得。日本人の監督なら車で聞く曲は日本語の曲だったろうし、兄妹がハグする場面もないよ。
それにしても高倉健さんの「あなたへ」もそうだったけど、寡黙な主人公の映画には必ずおしゃべりで絡んでくるその他の人たちが登場する。基本トイレ掃除は一人でするものだと思うけど。だから仕事仲間と顔見知りになってお互い干渉するような関係まで行くようなことはないと思う。あと、長いこと会ってない親戚のおじさんのところに泊まりに行くような姪とか、ありえない。年頃のお金持ちの女の子よ??家出したからって古いアパート暮らしのおっさんのところに行くことは絶対、ない。しかも公衆トイレの掃除を手伝うとか、絶対ない。
あと、使用した作業着を部屋に干してるの。これもないでしょう、と思った。排泄物は排泄された瞬間から汚物になるので、もし「それ」がついたままの作業着が部屋のなかにあるのは問題。使用した作業着はそのあとすぐ消毒して洗濯しないと、ほかの洗濯物も汚染してしまうので注意が必要なはず。実体験として介護にかかわったものとしてはそういう点も気になってしまう。
ストーリーとして全然あり得ない設定で、日本的な描写、というのか、早朝から掃き清める風景、銭湯、など。当方、東京23区暮らしですが、集合住宅ばかり。
まぁ、そんなこと言っては毎日判で押したような彼の人生が延々と描かれるだけになってしまうから時々人とのふれあいを描くことで変化を持たせる演出になってるわけだけど。
たまたまアマゾンプライムで見たからセリフが全部字幕で出てたので英語の曲の歌詞も字幕に出てて理解できた。で、この曲ってこんな歌詞だったんだ、って発見はうれしかった。当方英語の勉強は多少してきたつもりだったけど曲のヒアリングは全然できてなかったんだ、って改めて思い知った。ほとんどの曲は知ってた曲だったんだけど。これだけは拾い物だった。
「今度は今度、今は今」に込められたヴェンダースのメッセージ
カセットテープが主人公の平山を象徴するものになっている。カセットテープの全盛期は1980年代、バブル景気の頃とぴったり重なる。
また画面が4対3のアナログの画面比率で、カメラが常に平山にフォーカスしているので、何か理由がありそうだ思ってちょっと調べてみた。
そしたら画面比率16対9のハイビジョン試験放送が始まったのが1991年11月で、これはバブル崩壊の時期とほぼ一致する。
これらのことから分かるのは、おそらくバブルの頃に平山の身に何かが起きたということ。
バブル崩壊で多くの人の人生が狂わされたから、平山の人生もそこで大きく変わったんだと思う。
平山がスマホのアプリすら分からないアナログ人間だということは、姪っ子のニコとの会話でも分かる。
(ちなみに平山はガラケーを使っているが通話機能以外使っていない)
つまり、平山の人生はバブル崩壊とともに時が止まっていて、平山はその後30年以上アナログ人間のままで生きてきたってことを画面比率とカセットテープで語ってる。
物語終盤で平山が妹と再会するシーンがある。
運転手付きの高級車から降りてきた妹が、娘のニコがお世話になったお礼に「これ好きだったよね」と言ってオシャレな高級菓子っぽい紙袋を手渡す。
このシーンから分かるのは平山も昔は裕福だったということ。
そしてかつて父親との確執があって、父親がボケてしまった今でも会いに行く気にはならないということ。
つまり父親に対するトラウマが相当深い。
これは勝手な想像になるけど、平山は多分、昔父親が経営する会社で働いていて、バブル崩壊で会社が倒産、その過程で父親と大喧嘩して転職、その後色々あって人間不信になって無口になって、他人と関わらずに済むトイレ清掃の仕事に落ち着いた。
そんな感じじゃないだろうか。
そして妹の方は、自力で事業を起こして今の暮らしを手に入れたか、あるいは裕福な男と結婚して今の暮らしを手に入れたかのどちらかだろう。
では平山はいつからトイレ清掃の仕事を始めたのか?
平山は家出したニコがアパートを訪ねてきた時、最初誰だか思い出せなかった。
「大きくなったなあ」と感慨深げに言っていることから幼い頃のニコしか知らない。
ニコが持ってるカメラも幼い頃平山にプレゼントされた物。
現在のニコが十代後半として、見た目の変化で幼い頃の面影がなくなるほど昔というと、せいぜい9~10歳くらいか。(それよりも幼いと、カメラなんてプレゼントしないと思うし)
だとすると、平山が最後にニコに会ったのは、6~7年くらい前だと推測できる。
つまり平山がトイレ清掃の仕事を始めたのはおそらくその頃から。そして妹がそれを恥じたために妹一家と疎遠になってしまったということだろう。
しかし平山はトイレ清掃の仕事に就いて、慎ましい質素な生活に幸せを見いだせるようになった。
その事は田中泯演じるホームレスの存在で強調されている。
ホームレスは樹木に囲まれた公園ではイキイキとポーズ(光合成のポーズ?)を取っているが、ビルに囲まれた駅前の横断歩道では怯えて戸惑った表情を浮かべていた。
そしてそんなホームレスに対し平山は常に共感の眼差しを注いでいる。ホームレスが楽しそうだと平山も笑い、ホームレスが苦しそうだと平山も目に涙を浮かべる。
つまりホームレスが平山の感情を代弁している。平山は人混みが苦手、というか人間が苦手、そして物言わぬ樹木が好きということだ。
平山の樹木に対する愛情は樹木を育てている部屋の照明でも分かる。朝でも夜でも常に紫色の淡い光が当たっていて、平山が24時間惜しみない愛情を注いで樹木を育てていることが強調されている。
ちなみに物語の中で紫色の光が当たる対象がもう一つだけある。平山が休日だけ通うスナックがあるが、そのスナックのママがカウンター越しに接客していて、平山に近づいた時だけママの顔に紫色の光が当たる。
平山はあまり感情を表に出さないけど、樹木に対するのと同様に、ママに対しても好意を抱いていることが比喩的に表現されている。
平山が仕事についてきたニコと神社で会話するシーンがある。
平山は(格差が広がったことによって)同じ場所に暮らしながら接点のない別々の世界が生まれたことを説明しているが、この映画で描いている問題はそれだけではない。
格差が長引くと身分が固定化しそこから這い上がれなくなる。
平山とニコが自転車で並んで走るシーンでは、ニコが「海へ行こう」と提案したのに対し、平山は「今度」と言ってお茶を濁す。
「今度っていつ?」とニコが尋ねると、平山は「今度は今度、今は今」と笑って答える。
ニコの「海へ行こう」という言葉は現状を変えられるかどうかというメタファー。
ニコには今すぐ何かを始めて何にでも成れる可能性があるが、平山の方は今の年齢(多分60歳前後)で急に生活を変えることもできないし、転職も現実的に難しい。
つまりニコには無限の可能性があるが、平山には何の可能性も残っていない。平山に「今度」はない。だから「いつ?」と聞かれても答えられない。だがニコは「今」すぐにいくらでも新しいことを始められる。
そんな2人の世界がひとつになることはない。自転車で並んで走っていても、二つの線がひとつになることはない。隣どうし並んでいても全く別世界の住人だという残酷な現実がここで描かれている。
だから妹がニコを迎えに来た時、嫌がるニコの味方をせず帰るように促した。
一緒に暮らすのは無理なこと、自分がニコの面倒を見るのは無理なことをよく分かっていたから。
そして妹とニコを乗せた車が去る間際、俯いて涙を流した。家族なのに一緒にいられない現実が悲しくて悔しかったからだろう。
また格差というテーマは他のエピソードでも描かれている。
たとえば平山の下で働くバイトのタカシが「金がなきゃ恋も出来ない」て台詞を何度も繰り返してたけど、そう思いこんでること自体が問題。
「金がないから何もできない」という考え方は「金がないから何もしない」という考え方につながり、タカシが底辺から抜け出す機会を永遠に奪うことになる。
そしてこういう若い世代が増えると、格差は縮まるどころかますます開いていく。
実際タカシには全く労働意欲がなく、平山に金を借りて恋人の店に遊びに行き、最後は突然バイトを辞めてしまう。
恋人のアヤにしてみれば、金を借りてまで店に遊びに来て欲しくはなかったはず。でもタカシにはそれが分からない。
(障害者に偏見なく接する優しさがある一方で、金にばかり固執して他のことに興味がない)
アヤはそんなタカシが悲しくて平山の前で涙を見せたんだと思う。
物語終盤、スナックのママの元夫である友山と平山が影踏みをして遊ぶシーンがあるが、平山と友山、どちらも名前に山の字がつくのは意図的なものだと思う。
友山は末期ガンで顔色は悪いものの身なりはそこそこ良くて、それなりにいい暮らしをしてることが窺える。(少なくとも平山とは対照的)
そんな友山が平山に投げかけた「ふたつの影が重なると濃くなるか」という問い。
平山は「濃くなる。何も変わらないなんてそんな馬鹿なことあるはずがない」とムキになって答える。
格差や職業差別がなくなってふたつの世界がひとつになれば世の中はもっと良くなるはず。
2人の影踏み遊びにはそんなヴィム・ヴェンダースの願いがこめられているように感じた。
この映画って平山自身があまりにも寡黙で自分の過去を何も語らないから、観客が勝手に想像するしかない。
でも役所広司の演技が上手いので平山の感情がつぶさに伝わってくる。
特にラストシーンで役所広司が見せる涙の芝居には深く胸を刺された。長回しの一人芝居で、それまで抑えてた感情が堰を切ったように溢れ出てくる。
バブル後30年以上に渡って続く格差の中で、底辺から抜け出せなくなった男の悲哀が滲み出ていた。
普段は穏やかに暮らしていても、思うようにならなかった人生に何の後悔もないはずがない。
特に仕事に対する差別は平山にとって苦痛だろう。
でもそういう生き方をせざるを得なかった、もしくは他に生き方を選べなかったから、その中でどうにか生きがいを見出し、ささやかな幸せを見つけられた。
平山はそのことに満足し充実した日々を送っている。そういう意味でのパーフェクトデイズ。
(金があれば何でもできるのに。と言ってやる気を失ってるタカシとは対照的)
バブル崩壊後広がった格差、二極化した社会、どんな裕福な人間でも公衆トイレにはお世話になっているのに、清掃員の仕事は蔑んでいる。
迷子の我が子を保護してくれた平山を一瞥するなり、礼も言わずにウェットティッシュで我が子の手を拭いた母親。
兄妹としての愛情を持ちながらもトイレ清掃員というだけで平山を拒絶する妹。
ヴィム・ヴェンダースが日本の社会構造をガチ勉して、社会格差と職業差別をテーマに作った映画。
資本主義の象徴のようなスカイツリーの下で、物言わぬ植物のように無欲で質素な暮らしを続けている平山。その姿は物欲に支配されて人間味を失ってる現代人に対する風刺でもあると思った。
※この映画ってほぼ全編平山の一視点のみで描かれてるけど、一部だけニコの視点で描かれてるシーンがある。
平山の仕事が他人の目にどう映っているのか、ニコの視点を通して客観的に描く必要があったからだと思う。
※※「今度は今度、今は今」のシーン。
一つ前の銭湯のシーンから振り返ると分かりやすい。
まず、平山は妹がニコを迎えに来ることをあらかじめ分かっていた。(銭湯で妹に電話していた)
そして妹がニコを連れて帰ったら、もう当分自分に会わせないようにするだろう事も想像出来た。
だから「今度っていつ?」とニコに聞かれても、いつ行くとは約束できなかった。
また銭湯のシーンで平山とニコは何か食べに行こうと話していた。つまり、自転車に乗っている2人はこれから食事に行くところ。
「今度は今度、今は今」
この台詞の表だけを見るととてもシンプルで、ニコとの休日の締めくくり(食事の時間)を楽しく過ごしたい。先のことはとりあえず置いておいて今を楽しもう。そんな意図だと受け取れる。
しかしこの一連のシーンをメタファーとして考えると上記の感想でも書いた内容になる。
ニコの「海へ行こう」という言葉は現状から抜け出せるかどうかのメタファーであると同時に、ニコが折り合いの悪い母親とではなく、幼い頃から慕っている平山と生きていく選択をしたことを意味するものでもある。
(ニコはこの直前の台詞で「私はおじさんの世界とママの世界どっちの世界にいるの?」と問いを投げかけている。これは裏を返せば自分はどっちの世界で生きていきたいか迷っていると受け取れる)
しかしニコが平山の世界で平山と一緒に生きていく選択をしたところで、経済力のない平山はニコに何も与えてやれない。
それが格差社会の現実であり、平山はそれを身に染みて知っている。
だから「今度っていつ?」という質問に「今度は今度、今は今」とはぐらかす答えを返した。この平山の「今度」は問題を先延ばしにしているだけで、ニコの質問に正面から答えていない。
もっと分かりやすく言うと、裕福な世界の住人であるニコは今すぐ「海」へ行けるが、貧乏な世界の住人である平山は今どころか残りの人生をかけても海へ行けない。
つまり平山には「今」どころか「今度」すらない。それでも「今度」という言葉にすがったのは、自分を慕ってくれてる可愛い姪っ子の前で、自分は「海」へ行けないとは言えなかったから。
だからこの物語でこの「今度」と「今」は決して交わらない物の象徴になっている。
ニコの「今」はあらゆる可能性に満ちているが、平山の「今度」は何のあてもなく頼りないもので、何の可能性も残っていない事を現している。
平山はそれをよく分かった上で「今度は今度、今は今」と言っているが、ニコはまだ何も分かっていないので言葉の表面だけをとらえて「今度は今度、今は今」と無邪気に繰り返している
人生を表情で表現する
主人公の平山は、日常の中にある小さな幸せに気付き、たくさん集めることが出来る、ある意味幸福な人間なのだと思います。
生活に必要なだけの給与で、自分の好きなことを繰り返し行い、余計なしがらみを持たず生きていく人生。
でも自分の周りは確実に変化していることにも気付いている様子。
終盤、新しい一日の始まりを朝日を浴びながら運転している中で見せる表情。
繰り返す毎日の充実感と喜びの中に、不安や後悔が入り交じったような平山の表情は、役所さんにしか出来ない、人生が凝縮されているようで圧巻でした。
タイトルなし(ネタバレ)
平山演じる役所広司さんの寡黙な演技と、同僚である柄本時生さんのチャランポランだけど人たらし系の演技が、思わず微笑んでしまうほど素晴らしい。
平山さんの丁寧な掃除は、心までスッキリする感覚を覚えた。綺麗好きなところと清潔感を大事にしているのかなと言う部分を見て取れた。
寡黙だから車で流れる洋楽と、とてもよく合う。
観客に想像を任せるシーンが2回ほどあったかも。
穏やかな気持ちになれる、リラクゼーション的作品
今日(2025/02/08)から数日間かけて観ました。
無口で影のある男が主体の作品ですが、彼が本作の主人公というべきなのか、少し考えてしまいます。
早朝から出勤。仕事用の車はカセットテープが再生できる旧式。心地よい洋楽が流れるなか現場に到着。
公衆トイレの清掃員という、過酷で孤独な仕事に就いており、仕事終わりに一杯ひっかけて、就寝前に寝室で読書をして眠る。本当に絵に描いたような地味な生活。そんな中起こるわずかな変化やものごとに、自分自身の生活を重ね合わせ、気づくと彼に感情移入して魅入ってしまいました。
『かもめ食堂』、『ツユクサ』、『きのう何食べた?』などのようなゆっくりとした空気の流れが心地よい映画です。
監督が外国人(ヴィム・ヴェンダース)ということもあり、日本人にはない日本ならではの美しさ、おかしな所などを映像やキャストの振る舞いを見られます。
落ち着いた雰囲気の良い映画だと思います。アマプラからどうぞ👋
タイトルなし(ネタバレ)
「PERFECT DAYS」ってどういう意味なのかな、と考えてみた。一日、一日を、精一杯生きるってことかな。同じことの繰り返しに見えるけどいつも何か違う、平凡で大切な毎日を、命を尽くして生きる。
何にも分からないのが良いね。
役所広司はなぜトイレ清掃の仕事をしているのか。父親とどんな確執があったのか。姪っ子はなぜ家出したのか。柄本時生はなぜ突然仕事を辞めたのか。田中泯はなぜホームレスになったのか。飲み屋のママ石川さゆりと、元夫三浦友和はなぜ離婚したのか。皆んなそれぞれのPERFECT DAYSがあるのだ。不器用で、苦くて、それでもいつか必ずお別れする時が訪れる。サヨナラは名残惜しい。
バックで流れる往年の名曲や、古本屋で購入して来る文庫本を丁寧に紐解けば、そこに「なぜ?」に対するヒントが隠されているかもしれません。
映画を見始めてしばらくは、妙な違和感がありました。映像がすごく生々しくて、自分もそこに居るような感覚になるのはどうしてだろう?と。なんか質感が違う。最初は、自分が東京でずっと働いていたからそう思うのかな?と思ったけど、ドキュメンタリー風に撮影したと知って納得しました。使用するカメラが違うんでしょうか?凄く良かったです。匂いや音、風、光、雑踏の生活音も肌で感じられるようでした。
あと、現代的なスカイツリーと、昭和にタイムスリップしたようなレトロな街並みとの対比が面白かったです。ああ東京ってそういう街やんな…一歩路地裏へ入れば混ぜこぜで、そういうとこ大好きだ、、と思いました。無関心なくせにノスタルジックで、切なさが込み上げる不思議な街。
若い時はあまりピンと来ないかもしれません。歳をとってから見ると、きっとグッと来ちゃうと思います。人生は思っているより短い。最後のシーンは本当に言葉になりません。役所広司の素晴らしい演技に涙が止まりません。
何処にでもある哲学
単調な繰り返しの毎日、木の葉、木洩れ日、朝のホウキの音、影など至る所に深い意味と楽しみがある。主人公はどうやら良いところの子で父親に反発してこういう生活をしているらしい。テレビもなく植木と本と写真が楽しみのようだ。東京の公衆便所は様々で面白ろい。多分彼はこの生活に満足し、夢を見ている。日本なのに日本でないような所がある。ハグするところ。日本人はやらない。ハグしたい時があるけれど。でもなんだか見た後に何かが浮かんで残っている。
パーフェクトな日常の中に流れるもの
いまいち評価がわからない作品。東京都心でトイレ清掃員として暮らす60代男性の日常が淡々と映像で映し出される。潔癖で、質素で、単調な日々。それが彼のパーフェクトな毎日なのだ。チャランポランな仕事の同僚に困らされたり、姪っ子が突然やってきたり、行きつけの飲み屋の女将さんの元夫が現れたりと出来事は起きるがドラマは無く、日常に戻っていく。そんな彼の心、感情が揺れたのが妹から入所した父(認知症?)の様子を聞いた時と飲み屋の女将さんの元夫の命が短いという話を聞いた時。淡々と過ごす日常の中でも確実に訪れる老いや死という問題が、時間と共に流れているということを実感させる。
こうした淡々とした映像の中に、その背景にあるであろうドラマを様々に想像し考えを巡らせることが、この作品の面白いところなのかもしれない。
偽善まみれの駄作
過大評価されている作品。東京・渋谷の公衆トイレを清掃する男・平山(役所広司)の静かで淡々とした日常を描いた本作は、観念的で装飾的な「禅」的美学を表面に貼り付けただけの作品に過ぎず、日本の現実を真正面から見据えたものとは到底言えない。むしろ、外国人監督による「エキゾチック・ジャパン」的な視線が強く、実態を無視した日本の理想化されたイメージを押し付ける結果になっている。
まず、本作の最大の問題点は、その退屈さにある。平山の日々は同じ作業の繰り返しであり、映画はそれを執拗に映し出す。公衆トイレを清掃し、同じ道を歩き、コンビニで食事を買い、同じカセットテープを聴き、文庫本を読み就寝する。もちろん、繰り返しの中に微細な変化を見出すことが映画の意図なのかもしれないが、そうした「味わい」は、観客に何ら新たな発見をもたらさない。ただ単に「同じシーンをまた見せられている」という感覚が続き、特に映画後半では、そのマンネリズムが露骨に浮き彫りになる。退屈を美学に昇華できていない点で、これは大きな失敗と言わざるを得ない。
さらに、主人公・平山のキャラクターの掘り下げが極端に浅い点も問題だ。彼の過去には何らかの事情があることが示唆されるが、それは一切語られず、観客は「考察」を強いられる。しかし、その背景が示されないまま、彼の「現在」の姿だけを描いても、観客が感情移入するのは難しい。彼がカセットテープで音楽を聴く、植物を愛でる、モノクロ写真を撮るといった「趣味」の描写が積み重ねられるだけで、彼の内面にはほとんど迫れていない。これでは、ただの「無口で趣のある老人」という記号的なキャラクターになってしまう。
また、日本社会の現実との乖離も目立つ。平山が働く公衆トイレは、あまりにも美しく、実際の清掃員が直面するような過酷な労働環境や社会的な視線は一切描かれない。日本の労働者階級の厳しい現実をすべて覆い隠し、「静謐な生活を送る老人の美しい日常」という虚構を作り上げている。ヴィム・ヴェンダースはこれを「詩的な視点」と言うかもしれないが、それは単なる美化であり、都合のいい省略にすぎない。
加えて、映画の演出はあまりにも説明的で、観客を見下しているようにさえ感じる。例えば、カセットテープから流れる音楽は、「平山の気持ち」を代弁するかのように選曲され、映画のラストでは『House of the Rising Sun』が流れるが、その選択はあまりにもあざとい。観客に「彼の人生に何かあったのだろう」と考えさせようとする意図は見えるが、あまりにも表面的で、映画としての深みを生んでいない。
『PERFECT DAYS』は、映像的な美しさこそあるものの、その美しさは単なる「海外から見た日本の理想像」に過ぎず、映画としての力強さには欠ける。結局のところ、この作品は「静かな映画」という枠に自らを押し込め、退屈さと表層的な美学をもって「芸術性」として売り出しただけの作品なのではないか。
蛇足だが配役も酷い。名だたるバイプレーヤーが数多く出演したが(田中泯、モロ師岡、片桐はいり、あがた森魚、研ナオコetc)顔さえはっきり写さず、「俺ヴィム・ヴェンダース名匠だからね、出してあげるけど端役だよ」笑、みたいな驕りを感じた。
“完璧な日々“と幸せコレクションの1/fゆらぎ
古アパートに住み、毎朝同じ時間に起き、同様の支度を行い、同僚と清掃の仕事をして、銭湯で汗を流し、飲み屋で一杯飲んで、小説の続きを読み、眠くなったら就寝する。ルーティンで埋められた質素な生活、まるでお坊さんみたいと思いました。カセット音楽や文庫本の娯楽はあるし酒も肉も喰う、修行僧でもないお坊さんも今どきこんな感じ、と考えるとトイレ清掃を浄化と考えると公衆便所は檀家、毎日檀家を廻って念仏を唱えて浄化して、眠りにつくと浄土と俗世の間を微睡(まどろ)んでいる、と考えると平山氏の生活はちょっと仏教的で可笑しく見えて来ます。
修行僧の煩悩を排除した質素な生活を最小限とするとそこを何を足していけば自分のとって“完璧な生活“になるのでしょうか。音楽は欲しい今ならスポティファイ、観るなら小説と映画とネットフリックス、ビールと焼き鳥とカレーと寿司とラーメンは食べたい、そして自由なオートバイの旅。逆に足したくないものは理不尽な事を言う雇用主、イヤミを言う課長、騒がしい住処、変な匂いのする街。これくらいがちょうど良いな、と思うと平山氏よりもう少し収入が必要そうです。もっと欲望を剥き出せば海外旅行高級外車都内タワマンザギンでシースーなどなど、挙げればキリがありませんが宝くじでも当たらないと無理無理、結局のところ収入とのバランスで望む望まざるに関わらず取捨選択した結果で生活が築き上られているはず、時にはしんどい生活を送っていることもありますよね。
研究によると刺激が起きる頻度fと刺激の大きさPの関係がP=1/fの反比例、小さな刺激は頻繁に、中くらいの刺激はそこそこに、大きな刺激をたまにという感じでそれぞれ1/fの適切な頻度で起こると快適に感じるそうです(1/fゆらぎ)。例えば音楽とか関連があるようですね。平山氏の場合、綺麗な木漏れ日の写真を撮ったり小さな盆栽を育てているなどなど日々起こる“小さな幸せ“から、トイレで見つけた5目並べで対決したり音楽カセットが結構高値だったり同僚が狙っている女性にキスされたなどなど頻繁には起こらないイレギュラーな幸せ、それら大小合成された幸せの“ゆらぎ“が何でもない生活を充実させているように見えます。とはいえ逆に不快な刺激もある訳で、同僚がいいかげんな奴カセットテープを無くした(盗まれた)同僚にいきなりバックれられて仕事が夜までかかったなどなど本人としては不可抗力のコトもあり、人生は思うようにいかないところもまた刺激的です。
1/fゆらぎを作り出すように大小様々な幸せを程よい頻度で摂取できれば毎日を充実させて行ける、駅前の花屋の花が綺麗だったとか今年の桜の花が綺麗だったとか今日の夕焼けが綺麗だったとか美味しいラーメン屋を見つけたとかボーナスでブランド物を買ったとか最新のオートバイを買ったとか人それぞれ色々な幸せがあると思うのですが、それら大小の幸せを日々発見して自分だけのコレクションにしておくと容易に生活を充実させて行けるんじゃないかと思います。特に「食べること」については幸せの頻度と大きさを自分で御しやすい、と考えると美味しい店は正に“幸せのコレクション“、グルメ番組も流行る訳です。それらに加えて家族の幸せです。昔4人の子供がいる同僚に「子供の数だけ幸せが倍になる」と聴きました。家族もまた大きな幸せのコレクションに出来たなら理想的で最高です。日々折々適宜1/fゆらぎで幸せコレクションを摂取していければ、お金がなくても、やる気が起きなくても、運がついていなくても、何でもない日々を“完璧な日々“に近づけて行けるのかも知れません。
家出した姪が平山氏を頼って尋ねて来て、おそらく独身の平山氏は久しぶりの家族との再会ウキウキしているようで、姪の居心地が悪くならないよう細心の注意を払っているように見えました。滅多に起こらない大きな幸せの到来です。後日高級車レクサスに乗った妹が迎えに来た時の会話からどうやら実家が実業一家のお金持ちで平山氏は上流社会からドロップアウトしたような感じ。と言うことは平山氏はヘブンから堕ちてきた堕天使ルシファーに見えて来て、ベルゼブブ(姪)もヘブンから堕ちてきたんだけどガブリエル(妹)が迎えに来てルシファー(平山)に“大天使ミカエル(父)と仲直りしたら“と助言しているように思えて来ました。あゝこの映画は「カメイド 天使の詩」だったのか!お坊さんの話じゃなかった!
とりあえず幸せコレクションの一つ目は朝起きたら窓を開けて「太陽さーん今日もありがとう!、うわぁー今日もお花が綺麗!、あっ小鳥さーんオハヨウ!」と言うところから始めてみますかね。なんだかハイジとかキャンディで見たようなセリフ、思えば2作品とも“幸せコレクター“のお話でしたか。
胸がギュッとなった作品
「私にとって幸せってなんだろう」って暇になったらすぐ考えてしまうけど、どう頑張ってもいつ考えても世間の尺度で自分の幸せを考えてしまう。それってつまり私も自分がかんじる幸せを他人に当てはめてしまってるってことなんだよな。明日からは小さな幸せを見つけて、それに心躍らせて生きていきたい、そう思える映画でした。あと、ラストのI'm feeling goodの曲が好きすぎてタイミングよすぎて胸がぎゅうううってなった。映画館でまた観たい
Perfect
主人公は多くは語らない
彼の思いやストーリーは、鑑賞者の想像の中
彼は毎日几帳面に生活をし、決して裕福ではない
だが、自分が誰か、どんな習慣をもっているかを知る人が近所にいて、仕事であるトイレ掃除を丁寧に、丹念にやる
趣味のフィルム写真も定期的に現像してはフィルムを買ってその場で詰め次に繋がる
文庫本は読み終えたら古本屋で次の100円の文庫本を買って読み始める
彼の生活と同じく、絶え間ないルーチン
彼が毎晩見る夢は、その日の印象的な出来事がモノクロで流れていく
そして近所のおばあさんのルーチンである竹箒の掃き音で目覚める
影は重なったら濃くなるか?彼の中では濃くなるのだそうだ
その理由は、そうならなければつまらないから
ぐっとくる
数多くのキャラが出ては消えていくが、彼らの人生も深くは描かれない
でも、誰もがいろいろなストーリーを抱えているのだろう
そんな、いろいろな人の人生が主人公の人生に少しずつ重なり、影を濃くして、彼のパーフェクトな日が成り立っているのかもしれない。。。
耳を澄ます
個人的に大好きな「パターソン」にとても雰囲気が似ていた。
平穏で静かな日常を送る平山の視点から見える世界は澄んでいて自然が煌めいている。
平山の毎日を充実させるのは、
・陽の光
・植物
・古本
・ハイボール
・サンドイッチ
・カメラ
・カセットテープ
・缶コーヒー
・人間観察
などなど
平穏な変わらない毎日だからこそ堪能できる。
心の幸せを得るのに、決して贅沢な生活はいらない。
しかし、姪との再会という"イベント"で、平山の表情は一気に明るくなる。平穏な生活で感じる幸せよりも、人との温もりで感じる幸せのほうが遥かに大きいことに気づく。
姪を迎えに来た妹とのやりとりから、人と距離を取るようになった彼の悲しい過去が垣間見えた。
厳格な父のもと育てられ、その期待に応えようと仕事人として忙しなく働いていたのか。。
一族経営の会社で妹とともに父のもと仕事をしていたのか。。
しかし、実利主義で忙しない環境に気を病み、厭世的な生活を送っているのか。。自宅の雑多な荷物の山からそんな背景が想像された。
明らかにはされないが、いろんな想像が頭を巡った。
姉と抱擁を交わした後の涙がとても切なかった。。
本当は大切な人と時間をともにしたいのだろう。でもそれをしたくてもできなかった過去があって、住む世界が違うと信じて、孤独感に蓋をしているのか。。
その後、突然辞めた同僚の尻拭いで朝から晩まで忙しなくトイレ掃除をする場面では、口調は荒くなり、仕事人時代の平山の姿が垣間見えた気がした。
最後の涙はなんだったのか。
美しい朝の景色に感動したのか?世界の美しさに涙が溢れたのか。
日々の幸せを噛み締めると同時に、抑え込んできた孤独感に苛まれ、単調に終わってしまうかもしれない自らの人生に悲しみの涙を流していたのか。
個人的には後者と感じた。
淡々と進み、説明もないのであれこれと想像を膨らますことができてとても良い。
表情だけで機微を表現する役所広司の演技が素晴らしかったです。
リアルじゃないけど、どこかリアルな映画。
観る前に、オチの無い、観てスッキッリするタイプの映画では無いことは感じていたので、がっかりすることも無く、伏線回収を期待すること無く、映像の良さや演技の上手さ、この監督の巧さに集中しながら飽きることなく観れました。面白かった。
前半、平山さんの毎日のルーティンを何度も観せられるんだけど、それがなんでかわからないけど、良くて。
あれ家の鍵閉めないのって、オートロック方式?地味に気になりました。
後半にいくにつれて、、おやっ?っていうシーンがいくつかあって。それが観終わった後に、「あれはなんだったろう……」ってなる。
例えば、姪っ子と自転車に乗ってるけど、2台も自転車あったの?とか、お互いに好意を持ってそうだった飲み屋の女将さんと男が抱き合っているのを目撃した後に平山さんが川でお酒飲んでるところにその男が現れ元夫で余命も短いから会いにきたんだと告げられるとか、、。ちょっとリアルなようで、リアルからズレている。希望的観測をこめた平山さんの妄想??とか思ったり。
本当は妹や姪っ子に会いたいけど会えないのがリアルなのかなと思ったり。
あと、毎晩見ているぼんやりした白黒の夢とか。窓のカーテンを全開で寝ているとろとか。随所随所に、「ただ淡々と毎日を自分なりに楽しんで生きている男」以外の要素が散りばめられていて、何かあって精神的に不安定になったような訳あり過去とか、そんな人生の影を抱えながら生きている様子を勝手に感じさせられる。
あとから考えると、平山さんの表情が全て語っているような気もして。
本当に役所広司さんの演技力が凄くて、本人ですよね、平山さんていますよねって、思うくらい。
観終わった後に、残ったのは、ほんのちょっとだけ恐いというか、狂気じゃないけど、もっとあったかいでもちょっと重い何か。あの日々のルーティンは平山さんの心の平穏を守るためなのかもしれない。
最近はこういう映画より明るくても暗くてもわかりやすい映画をよく観るし、こういう映画は好きじゃない時もあるけれど、この後に残った感じ、なんか分からないけど嫌いじゃないという。
論理的には考察できない感じ。やっぱり監督のヴィム・ヴェンダースさんと俳優さんの上手さが凄いなぁと思う映画でした。
トイレ清掃員の行き方に共感
古びたアパート、でも部屋の中はきれいに整頓された様子から主人公の几帳面さが感じ取れます。公園で見つけた植物を盆栽として育て、毎朝霧吹きで水をやることを怠らない。
朝は食事を取らず、缶コーヒーだけ飲んでトイレ清掃に車で出かける。
車の中では1960年代、70年代の懐メロをカセットテープで聴く。個人的に印象に残ったのは、オーティス・レディングのドックオブベイとアニマルズの朝日のあたる家だった。
昼は公園でサンドイッチを食べ、見上げた樹木の木漏れ日をオリンパスのフィルムカメラで撮る。隣のベンチには同じようにサンドイッチを食べるOL風の女性もいて顔見知りとなるが、特に会話はしない。
夜は地下街の定食屋でお酒と一緒に食べる。アパートにはお風呂がないので銭湯に行く。寝る前には読書する。
休日は自転車に乗って仕事着等をコインランドリーへ洗いに行く。その間、石川さゆり似のママがいるスナックに寄る。古本屋に行って本を買う。店主のおばさんは必ずその本について一言コメントする。カメラ屋にフィルムカメラの写真を受け取りに行き、同時にフィルムを買って帰る。家に帰ってその写真を整理する。気に入らない写真は捨て、気に入ったもののみ残して、アルミケースに入れて押し入れにしまう。押入れにはいくつものアルミケースがきちんと並べられていて、ここでも彼の几帳面さが伺える。
子供を見ると顔が微笑んだり、姪に優しい面がある一方、施設に入居している父親とは何があったかはわからないが、うまくいってないようで、妹が頼んでも会いに行こうとはしない頑固な面もある。
毎日が同じことの繰り返し。でもそのことの尊さを学びました。
現代プロラタの最高傑作
大切なものを見つめなおす機会になる。変わらないなんてバカはことはない。
同じ1日は存在しないし、同じ木漏れ日は2度とない。そんな日常の中にいるからこそ、変わらない静かな日を慈しむことを忘れてはいないか。また、誠実な人間は他者から信頼される。じぶんからもとめることはせず、話しかけることすらなくとも、同僚からも姪からも思い人の前夫からも即座に信頼される。それは誠実に生きてきた人間が獲得する年輪でありオーラである。平山は自分のロールモデルになった。
違和感の正体に気づいた時の気持ち悪さ
アマプラの配信で視聴。
映画公開時からレビューを見たり聞いたりして評判がいいのは知っていました。
ざっと見ての率直な感想はなんとも言えないおじさんのカッコよさ。
毎日同じような生活なのにそれを違った視点や切り方で見せる映像の綺麗さ。
俳優陣の演技の上手さ。そういった感想を抱きました。
最後の平山の涙はどんな涙なのだろうという疑問も残しつつもいい感じに終わったと思っていました。
他人のレビューを読んで平山の涙の訳を考察していました。
と同時に自分の中に一つの違和感が残っている事に気づきました。
それは「実は金持ちの家の出だった事」
これがなんだかもやもやしていました。
レビューを読んでいるとこんな事が書いてありました。
「監督はこんな感じの男がいいよね」と言っていたそうです。
これがどこまで本当でどんな意味なのかは定かではありません。他人のレビューに書いてあっただけですから。
ただ、これを聞いた時に自分の抱いていた違和感の正体に気づいたのです。
話は少し逸れますが、SNSに流れてくる広告で漫画の広告ってやつがあります。
漫画を数ページ読ませてアピールしてくるそんな広告です。
そこで見かけてちょっとエッチな感じにつられ無料分で読んだ漫画がありました。
それはオタクのモテなそうな男が主人公。
しかしそんな男がかわいくてスタイルもよいオタクの女子と知り合い、その日のうちに体の関係をもってしまうのです。
しかし付き合うとかそういう話は無し、オタク話で盛り上がり毎日のように会い体の関係を続けていく、しかし女は男の気分を害するような事は全く言いません。
他の男を匂わせたり、その男に対しての否定を一切しません。
そんな男にとって都合のいい夢のような妄想の話。
この漫画のタイトルが「こういうのがいい」
わかりますか?
作者の理想を漫画にしてるっていう事で、このタイトルってのは作者の言葉だと受け取れるのです。
そう考えた時、この漫画の気持ち悪さに鳥肌が立ちました。
いい体でめんどくさくなくて、共通の趣味で話が盛りる事ができ、自分の事を一切否定しない、そんなセフレがいたらいいなという話を悶々と漫画にしているんです。
作者の現実はわかりませんが、そういう作者像ができてしまったんです。それが気持ち悪い。
話戻ります。
今回のパーフェクトデイズもその漫画と同じなんじゃないか。
そう思った瞬間、違和感や他の事が全てつながったんです。以下羅列します。
・人との会話が苦手、しかし仕事は一生懸命やる。便所掃除にやりがいを感じている。
・自分の中に一本の芯のような、趣味というかライフワークのような、クリエイターのような部分がある。それは人には分かりずらい所まで行ってしまっていて、自分の中の合格が出ないと破り捨ててしまう。しかもそういう創作を何年と続けている。
・自分の趣味嗜好に興味を持ってくれる若い子に突然キスされる。
・家出をした姪は自分を頼ってくる。
自分に興味深々、自分のいった言葉が姪の心に刺さる刺さる。
まだ居たいという姪を無理やり母親に返す。
・実はいい家に生まれているが父親とのいざこざで家を継がずにいる。
父親に言われた「おまえは便所掃除のような底辺の仕事を続けていればよい」と言われたが父親への反抗心もありずっと便所掃除を続けている。(これは僕の妄想)
そんな状況を知っている妹も兄の心配をし続けている。
・好意を持っていた飲み屋の女将の元旦那が「あいつの事は頼みますよ」と言ってくる。
・辛い事はたくさんあるけども楽しい事もある。涙を堪えて踏ん張る男
これらが全て都合よく作られた話と感じてしまい、気持ち悪く感じてしまいました。
実際のおじさんって世間からの扱いはもっとひどいんです。救いようがないんです。
これ間違いない。こんなミラクル何度も起きないって。
そういえばこの映画を良いって言っていた人は40歳くらいから上のおじさんだったなあ。
そういう人間が都合よく気持ちよくなれる映画だったんだよ。
作者の都合のいい妄想を詰め込んでいる。
もっと楽しくて楽な人生があったのに、それを捨ててもそれより大事な何かを取り、それが結局辛い方だったとしても奥歯を噛みしめて、涙を堪えて耐える、そんな男がかっこいいよねって言ってる、自分に酔った人間の映画だと思いました。
かといって物語の創作の芯ってのはそんなものだとも感じます。
こんな恋愛をしてみたい。魔法を使えたらどうするか。とかね。
ただね、都合が良すぎるんですよ。そこが気持ち悪いのです。
しかし、役者の演技、キャストの面白さ。映像の作り方、これらが全て素晴らしく僕の言う気持ち悪さがぼやけているのではないかと感じました。
ヴィム・ベンダース監督の感性が日本の下町にベストマッチ
本作はヴィム・ベンダース監督が日本で撮った作品でかなり話題性があったので劇場でぜひとも観たかったのだが、タイミングが合わず今になってやっと鑑賞。
さすがはヴィム・ベンダース監督、おじさんの撮り方が絶妙だ。本監督作品で個人的に一番好きな「パリ、テキサス」をなんとなく彷彿させる感じがとても良い。
本監督作品らしくお涙頂戴系ではないので特別泣けるというわけではないのだが、主役と妹との遠慮がちな会話シーンなんかはやはりほんのりじーんとくる。
そして終盤の、二枚目ベテラン役者2人の「影踏み遊び」はレジェンドレベルでしょ。
もちろんラストシーンの朝日に照らされた主人公の泣き笑いは胸に深く刻まれる。
何だかんだと最後まで主人公の背景をはっきりとクローズアップしなかったところが、かえってストーリーに奥深さをもたらせたのかも知れない。
それにしても、カセットテープの音は確かに心に残る。
時間と金と思考の無駄使い
カンヌ国際映画祭で〜 との謳い文句と、YouTubeでもアマプラで観れるオススメ映画として大絶賛で紹介している配信者がいたので、騙されたと思って鑑賞。
初老の薄汚いオッサン、汚いアパート、汚い公衆便所の掃除、初老のカラダを晒した銭湯での入浴シーン、1日が終わった後の?オッサンの睡眠中の夢を象徴したかったのかわからんが白黒の意味不明映像(毎晩繰り返す)、ウンザリする仕事終わりからの居酒屋ルーティーン、休日のルーティーン、etcを延々と観せられて、苦痛以外の何物でもなかった。あれだけ高評価なんだから、途中で何かが変わる、そして感動する、そう信じて最後まで観た。
2時間という時間を無駄にした。
そして、不快感と、半ば怒りを覚えた。
だからこそ、こちらにID登録してまでもレビューを書きたくなり、書き残した。
こんな映画、観てはならない!
正直、主人公に近しい世代だからこそ刺さるとまで評させていたので、それも含めて期待して観たのだが、あまりにもおそまつ。そして、罪人でもない限り、こんな主人公みたいなルーティーン生活をしている日本人はいないと思いたい。ある意味終わっている。
希望も何もない。
そういえば伏線と思えるような、トイレ掃除の時に見かける浮浪者や、境内のベンチで毎回会うひとりランチ鬱顔OLとか、マルバツの紙とか、あんなのもなんだったんだ?観客をバカにしているとしか思えない。
とにかく不快極まりない駄作でした。
後から感じたのですが、挿入歌にしても、有名どころのちょい出演にしても、知っている人しかわからないようなモノもあり、これは映画オタクのための映画なんだなぁと思いました。
万人受けする映画ではありません。
〜追記〜
背景の説明が一切ないので、少女が登場したシーンでは想像を膨らませて、主人公の実の娘なのかと思ってずーっと観ていた。実の父を「オジサン」と呼ぶくらい、妻と離婚?してから会っていなかったのが、会いに来たのかと想像を膨らませて観ていたが、トンチンカン。結局、主人公に妻がいたのか、子供がいたのか、そんなのもわからず、少女は後半に主人公の姉?だか妹だかが少女を迎えにくるので、「あー、ホントに姪だったんだ」と、やっと理解する始末。
そして、どなたかのレビューで読んだかもですが、これはいわゆる「水槽の中の金魚」状態です。
居心地の良い小さな水槽の中でほぼ何もしないで寿命をすり減らしていく、この状態に私は不快感を覚えたのかもしれません。
私たちは水槽の中の金魚で満足なはずがないですよね?
少しでも大きな水槽に移ったり、たまには水槽から出たりするそんな楽しみがなくて生きていて、何になるのでしょうか?夢も希望もありません。初老の男にはもうそんなものは無いと言わんばかりのあの不快な水槽生活。これを観せられて、気分がいいわけありませんよ。
自分の人生、こんなんでいいですか?
私は、過去に何があったとしても、こんな収まり方で水槽の中で生き続けたくはありません。
全228件中、21~40件目を表示