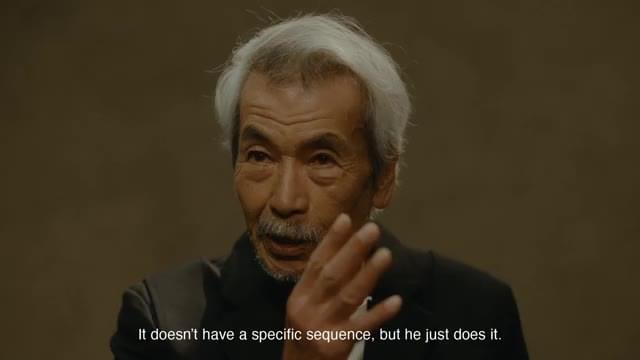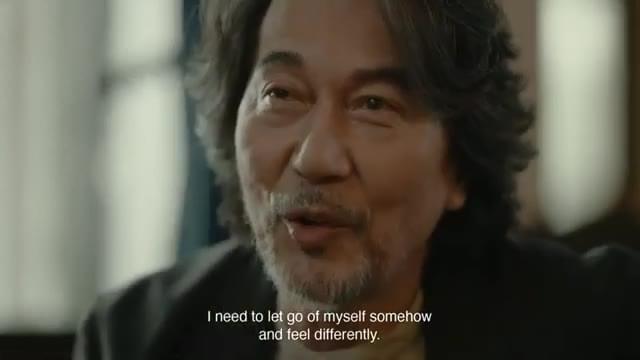「偽善まみれの駄作」PERFECT DAYS るなさんの映画レビュー(感想・評価)
偽善まみれの駄作
過大評価されている作品。東京・渋谷の公衆トイレを清掃する男・平山(役所広司)の静かで淡々とした日常を描いた本作は、観念的で装飾的な「禅」的美学を表面に貼り付けただけの作品に過ぎず、日本の現実を真正面から見据えたものとは到底言えない。むしろ、外国人監督による「エキゾチック・ジャパン」的な視線が強く、実態を無視した日本の理想化されたイメージを押し付ける結果になっている。
まず、本作の最大の問題点は、その退屈さにある。平山の日々は同じ作業の繰り返しであり、映画はそれを執拗に映し出す。公衆トイレを清掃し、同じ道を歩き、コンビニで食事を買い、同じカセットテープを聴き、文庫本を読み就寝する。もちろん、繰り返しの中に微細な変化を見出すことが映画の意図なのかもしれないが、そうした「味わい」は、観客に何ら新たな発見をもたらさない。ただ単に「同じシーンをまた見せられている」という感覚が続き、特に映画後半では、そのマンネリズムが露骨に浮き彫りになる。退屈を美学に昇華できていない点で、これは大きな失敗と言わざるを得ない。
さらに、主人公・平山のキャラクターの掘り下げが極端に浅い点も問題だ。彼の過去には何らかの事情があることが示唆されるが、それは一切語られず、観客は「考察」を強いられる。しかし、その背景が示されないまま、彼の「現在」の姿だけを描いても、観客が感情移入するのは難しい。彼がカセットテープで音楽を聴く、植物を愛でる、モノクロ写真を撮るといった「趣味」の描写が積み重ねられるだけで、彼の内面にはほとんど迫れていない。これでは、ただの「無口で趣のある老人」という記号的なキャラクターになってしまう。
また、日本社会の現実との乖離も目立つ。平山が働く公衆トイレは、あまりにも美しく、実際の清掃員が直面するような過酷な労働環境や社会的な視線は一切描かれない。日本の労働者階級の厳しい現実をすべて覆い隠し、「静謐な生活を送る老人の美しい日常」という虚構を作り上げている。ヴィム・ヴェンダースはこれを「詩的な視点」と言うかもしれないが、それは単なる美化であり、都合のいい省略にすぎない。
加えて、映画の演出はあまりにも説明的で、観客を見下しているようにさえ感じる。例えば、カセットテープから流れる音楽は、「平山の気持ち」を代弁するかのように選曲され、映画のラストでは『House of the Rising Sun』が流れるが、その選択はあまりにもあざとい。観客に「彼の人生に何かあったのだろう」と考えさせようとする意図は見えるが、あまりにも表面的で、映画としての深みを生んでいない。
『PERFECT DAYS』は、映像的な美しさこそあるものの、その美しさは単なる「海外から見た日本の理想像」に過ぎず、映画としての力強さには欠ける。結局のところ、この作品は「静かな映画」という枠に自らを押し込め、退屈さと表層的な美学をもって「芸術性」として売り出しただけの作品なのではないか。
蛇足だが配役も酷い。名だたるバイプレーヤーが数多く出演したが(田中泯、モロ師岡、片桐はいり、あがた森魚、研ナオコetc)顔さえはっきり写さず、「俺ヴィム・ヴェンダース名匠だからね、出してあげるけど端役だよ」笑、みたいな驕りを感じた。