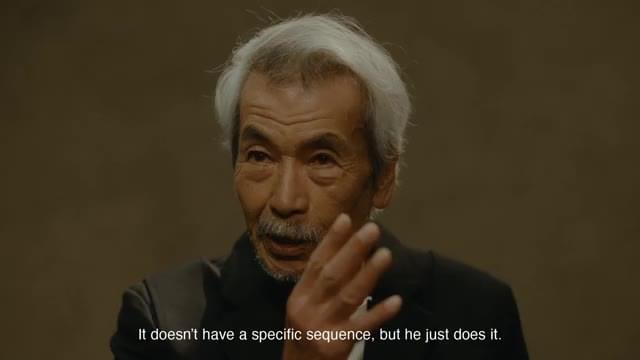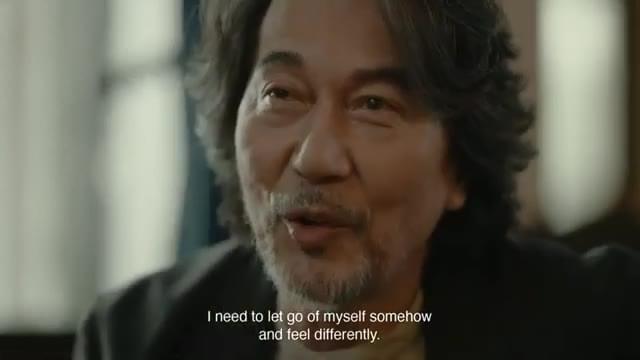「日本人として否定すべき見世物」PERFECT DAYS char1さんの映画レビュー(感想・評価)
日本人として否定すべき見世物
役所広司とヴィムヴェンダースという、映画好きなら誰でも知っているような大御所らの描く「トイレの清掃員」とくれば、それなりに深い洞察や哲学的な意図が含まれているものだろうと期待して行くが、その期待は見事に裏切られた。
ヴェンダースは「日本に理解がある」とされているようだが、残念ながらその洞察力は観光客の域を出ていないと感じた。もう一歩踏み込めば、植民地主義者的な視点にさえ近い。少なくとも、日本人のトイレ清掃員の視点で描かれた映画では決してない。
テンポも良いし、絵も綺麗だし、あまりガチャガチャしてないのでうまい具合に「見れる」が、しかし逆に、それ以上のものはほとんどないに等しい。撮影、サウンド、演技は高い水準にあると思うが、肝心の物語は単調で起伏がなく、面白くない。「自転車泥棒」のように貧困を通して何かを伝えるような社会的意義もない。見世物的なエンタメを提供する以外、無価値な作品だ。
綺麗な包装紙で何重にも包まれているが、一枚ずつ剥がして真意を覗いてみると中々酷い代物だ。
トイレの清掃員が主人公だが、その仕事や生活が好意的に描かれているわけではない。彼の人生には哲学がなく、作中描かれる彼の心理の大部分は「植物や音楽、風呂や酒が好き」という息抜き程度の嗜みと、「後悔の念」だ。そのような主人公の胸中が、物語を経て変わるわけでもない。一体このような人物を撮って公開する意図はなんだろうと考えると、一種の貧困ポルノでしかないと結論をつけざるを得ない。
日本の観光途中で、便器を直接手で洗う清掃員を見て「なんて変わった人生を送っているのだろう」と思った裕福な白人視点でしかないのだ。その見世物的感覚と、渋谷区のトイレ事業に関わる人々がたまたま結びついてできた、ある意味稀有な作品である。
そんな見世物的な感覚は、階級意識に基づいている。田中泯にホームレスを演じさせた事も、貧困を真に理解しようとしないことの表れだろう。みてくれは小綺麗な、ハリボテの貧困だ。
ホームレスで思い出したのが伊丹十三監督の『タンポポ』だが、そこでは監督が自らホームレス役を演じていた。ヴェンダースにもそれくらい気合いを入れて欲しかったが、彼にはそれが出来ないし、やりたくないのだろう。
おそらく監督は本作の主人公よりも、その姉と姪の方に感情移入しているはずだ。「自分がそうなるのは絶対嫌だし考えられない」という姉の意志と、姪の見せる「好奇心」や「物珍しさ」の感情。前者の視点は哀れみと自己責任観・階級差別観であり、後者の方は好意的に捉えられるかもしれないが、実際は共感を欠いた冷徹な見世物的視点である。
「世界が違うのだ」と無口な主人公に作中唯一の長台詞で自ら語らせたのも、「こうはなりたくない」という監督自身の意思表明だろう。「汚れたものには蓋を」の精神。製作者による、階級差別の正当化だ。
映画としてご都合主義的展開も多く、アラが目立つ。素手で菌の沢山ついているところを触っているはずなのに、手を洗うシーンがない。便器を鷲掴みにした手袋のまま、交換手記方式の丸バツゲームの紙を触る。雨の中、合羽を着てるのにフードを被らない。描き方に人間らしさや丁寧さが感じられず、監督はこのような清掃員を「汚れた人間だ」と心の底では思っていることの表れだろう。
序盤、迷子の子どもと手を繋いで、合流した母親が除菌シートで子供の手を拭くシーンがあるが、そりゃ拭いても決して不自然ではない。少なくとも作中一度も手を洗ってないんだから(風呂以外)。主人公は子供の手を拭く母親を見て悲しそうな顔をするが、何かの伏線かと思いきや、それ以降なにもない。ただ嫌な思いをするだけ。なにより、主人公には木を見たら機嫌が治るという、奴隷にうってつけの便利な精神が備わっている。
映画のアラとしての極め付けはおじさん二人で影踏みに興じるシーン。いくら映画でもさすがに無理がある急展開で失笑を禁じ得なかった。
もう一点、気になったのは作中白人が一度も登場しないことだ。ちょい役で黒人女性が一人出てくるが、白人はついぞ一度も出てこない。映画の主要制作スタッフ及びサントラのアーティストの九割が白人なのに、作中、一人も白人が出てこないのは逆に不自然だ。
なぜかと考えると、これは現近代のコロニアリズムに似た形なのだろう。美味しい仕事を独り占めし、自分らの都合にうまく添うように糸を引き、汚れ仕事は下々に任せるといった風だ。斜に見すぎているかもしれないが、決して的外れでもないと思う。
あとは、「オレはこの国の誰も知らないような所を知ってる」という観光客的な心理もあるかもしれない。別の白人が映ると、観光地としての価値が半減するとでも思っているかのような。
物語の起伏がない事はよく指摘されているが、本当にその通りで、例えば、同じく貧困の主人公を題材にした「マッチ売りの少女」で言うなら、少女がただ数日に渡ってマッチを売ったりするだけで終わるような物語で、単に面白くない。
「自転車泥棒」もある意味単調な映画だが、その単調さが貧困のリアルを如実に表していて心に深く刺さるものだった。この映画の単調さは、音楽や風呂など、主人公の現実逃避じみた嗜みで埋められていて中弛みするだけのものだ。
逆に「日本人の映画監督が撮ったドイツ人のトイレ清掃員」という映画は成り立つのか? と考えてみれば、この作品の問題点がわかりやすいと思う。
私は成り立たないと思う。なぜなら、そんな企画を通すようなドイツ人のプロデューサーは多分、存在しないからだ。
清掃員だって、公衆衛生の面において社会になくてはならない重要な仕事だ。当然、全員が後悔の念に塗れながらやっているわけではない。この映画は職業差別的な視点を増強しかねない危うささえある。
私は日本人として、この映画を否定したい。むしろ、日本人であれば否定すべきものだと思う。
この国や文化は見世物ではない。同様に、貧困は見世物ではない。