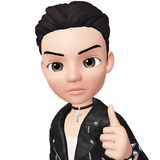関心領域のレビュー・感想・評価
全441件中、41~60件目を表示
最後の音楽……………
こんな怖い音や音楽、聞いたことない
関心領域と言うより無関心領域
でもあんなお庭のあるあんなお家に住みたいな〜
でも隣で繰り広げられてることを考えるととんでも無い
お母さんが翌朝逃げ帰ったのもよく分かる
子供たちもなにか感じているはず
終わりの方に少しだけ差し込まれる
Museum になった現在のアウシュビッツ
記録映画と言ってもいい作品だなぁ
戦争って僕のせいなのか?映画NO1
秀逸なタイトル
無関心である事の恐怖
無関心である事の恐怖を描いた作品
正直内容は説明にある、
収容所と壁一枚を隔てた屋敷で暮らす家族の日常
を描いているだけ
何も起こらない。
ただ日常的に銃声や悲鳴、罵倒する声が聞こえてくる
その事に何も気にせず暮らす人々
その無関心である事の恐怖
慣れる事への恐怖
それを第三者である観客に観せ、
如何にこの状況が異常であるかを知らしめるのが狙い
良作ではあるが他の人のように
何度も観て検証しようとまでは思わない
一度観れば十分かな?
人を選ぶ作品ではある。
この作品は音響がとても重要で、
普通のテレビで鑑賞しても、この作品の真価が分からない
俺は自宅に7.1chドルビーデジタルの音響システムが自宅にあるので
それで映画を観てるので、この恐怖を味わえた
特に導入部とラストの音楽の気味の悪い事!
ここだけでも怖いです!ホラーです(苦笑)
残念な劇場公開
この映画を見終わった後、ドルビーシネマで観たかったなぁと思いが込み上げました。
音と暗闇の表現ではドルビーに勝るものは無しなのですが残念ながら、この映画はドルビーシネマでは公開されませんでした。(配給会社系列の劇場の関係)
クリストファー・ノーランの新作がIMAXで観れないようなものでしょうか。
収容所の隣で住むナチス高官家族の話はBS海外ドキュメンタリーで観ました(かなりの秀作)それでも、この映画では説明不足な箇所が、いくつかありました。
収容所長夫人たちの会話で「カナダでユダヤ人から奪ったドレス」とありましたが、
あれっ,カナダでホロコーストあったかな・・・!?
後でradikoの荻生チキsession特集「ホロコーストはなぜ起きたのか?」で
田野教授によるとカナダとはユダヤ人からの略奪品を集めた倉庫の事を言うそうです。(2001年宇宙の旅じゃないんですからテロップの説明入れてください!)
噂のエンディングは怪奇大作戦第24話「狂気人間(欠番)」のエンディング並みの怖さでした・・・
見せ方はアニエス・ヴァルダの「幸福」と似ていますね。
家族のピクニックで始まり幸せそうな家庭ですが旦那さんには秘密があった・・・
男の身勝手さを客観的に描写して、ある意味怖い映画でした。
関心領域を観たシネコンでは、ほぼ満席でした。エンタメ映画以外での満席は珍しいですね。ある意味、今映画界でノっているA24の戦略にまんまとハマってしまった感がある。
カンヌとアカデミーで箔がつき、洗練されたチラシデザイン、間を持たせた公開までの期間中にメディアで話題にのぼり今現在、行われているウクライナとガザ戦争の影も意識させる作品でもあります。
あの時代、あの場所、【異常】と【正常】の境界線は、どこにあったんだろうか。
-----------------------
異常も、
日々続くと、
正常になる。
-----------------------
映画を見ているとき、
映画「戦場のメリー・クリスマス」のサントラ広告のキャッチコピーを思い出した。
映画に映し出されているのは快適に作り上げられた理想の住居。
そこに住むヘスの幸せな家族。良きパパ、良きママ、良き子供たち。
ただし、暮らしのBGMはアウシュビッツから発せらる音、声、臭い。
非人道的な行為が“そば”にあることは明らかだった。
しかし、ヘスやヘスの家族たちが“それ”を非人道的と考えていたのか、どうか。
彼らだけではない。
当時のドイツ国民もいなくなったユダヤ人の家や部屋に引越し、
そこにあった家具、服、食器などの彼らの財産の一部をタダ同然で手に入れ、
豊かな暮らしを手に入れた。
「音、声、臭い」を直接的に見たり聞かなくても、
ユダヤ人たちに何か良くないことが起こっていることを知ってた。
いや、深く知ろうとはしなかった。考えること、想像することをしなかった。
当時の教会も対戦国である連合国も上層部の人たちは知っていた。
あの映画の奥に潜むさらなる不都合な真実を自分は感じた。
深く知ること、想像することの大切さを思った。
しかし、
あの時代、あの場所、【異常】と【正常】の境界線は、どこにあったんだろうか。
追記>
当時のドイツ国民を単純に機械的に批判するのは簡単なんだけどね。
第一次世界大戦後の賠償金のせいで
彼らを襲ったド貧困(例えば死んだ馬の死肉でさえ奪い合う全国民飢餓的な状況)、
ドイツのプライドと豊かさを取り戻そうというヒトラーの甘い誘惑と、
彼の言った通りに本当に暮らしが豊かになっていった事実など。
ある意味、まやかしだし代償もあったけど、人は豊かさを選ぶ。
あと、映画としてヘス個人とヘス嫁個人の肝がん方にもっと寄ってもよかったような。
虐殺機械
鑑賞者には知識が必要な作品
隣で何が起こってるか知らない。ルドルフ・ヘスは司令官だから当然知っているし、妻も知っているはず。ちょっと怖かったのが、イタズラだとは言え弟を温室に閉じ込めた兄のシーン・・・これは彼らの遺伝子を引き継いでいるということなのか?
現在起こっている戦争。実際にどんな状況なのかもわからないまま、無関心を装っている多くの人たち。ただ、知っているのだけれど、実際に見たわけじゃないから多くを語れないのが本音ではなかろうか。
画面が真っ赤になったまま数秒経つシーンがあったり、突如夢のようにモノクロームになったりする映像の工夫があったり、かなり深く潜在意識に訴えてくるような仕掛があった。あれは何だったんだろう?などと鑑賞後に考えることによって心に残ることになるのだろう。不思議だ。
司令官の実名を使った登場人物だったり、アウシュビッツ収容所の中を一切映し出さずに恐怖を描いたことが凄いこと。我々も同じだ。知っていても知らんぷり。歴史修正主義も登場して情報過多となった世の中において真偽を見極めるのも疲れるものだ。
アメリカ人が描くナチス映画やユダヤ人の大虐殺を取り扱った作品は多くあれど、他の大虐殺については知らんぷりなのでしょう。同じ年に『オッペンハイマー』が賞レースを席巻したことも興味深い。
私達自身の“関心”が問われている
音響が映画の印象を左右する
映画館で観るのは少し怖かったので、配信されるのを待ってU-NEXTで観ました
自宅の音響環境はテレビの音響のみで、仕方ない生活音が入りつつも、結構音量を大きくして観ましたが、
本来感じるべき映画に込められた意図や仕組みは半減していると感じました。銃声もよくわからなかった、、、
不気味さもところどころありましたが、終始気味悪いというわけではありません。
ノイズキャンセリングのイヤフォンやヘッドフォンで観たりしたら、もっと違った印象になったかもしれません。
そもそも自分の理解力が足りないせいもありますが、さらっと観たら何も入ってこない映画にはなる。
映画館で没頭して観る作品だと思います。
言わんとすることは分かる。
壁一枚を隔てた日常と地獄。
かつての非道を描き、現代を生きる我々に問いたいのだろう。
言いたい事はよく分かる。
だが、なんだろうこの胸糞悪さは。
確かに過去の現実としてのナチスの非道はあったし、人類として忘れてはいけないのはよくわかる。
とはいえ、いつまでもナチスナチスうるせーよ!
私はナチス関係者の末裔ではないし、信奉するものでもない。
彼らの行動の結果は悲惨であり糾弾され、人類は2度と行うべきではない所業だ。
そこで、ふと西の方に目を向ける。
今、虐殺はしないまでも民族浄化、民族弾圧が行われている現実があるのでは?
そちらに目を向けず斜に構えて、人類のかつての非道を皮肉るような、そんな姿勢が気に入らない。
躍進し続けるA24スタジオ。
独特の映像美と演出、そして心にざっくりくる作品の数々。
Civil Warまでは良かったが、なんだろう。
ここの作品群に通底する達観したかのような視点での皮肉がだんだん胸糞悪く感じる。
観ればみるほど嫌いになるスタジオだ。
「退屈だ」と感じることが自らの無関心さを突き付ける、なんとも残酷な映画よ
お世辞にも面白いとは言えない映画だが、むしろその「面白くない」「退屈だ」と感じるところにこそ、この映画のスゴさがあるように思う。
というのも、本作には映像の手がかりとなる説明というものが一切なく、カメラもほとんどが固定のロングショットであるため、一定の視点や感情をもって観ることが最初から排除されている。それはおそらく徹底したリアリティーでもって再現したアウシュビッツ横のヘス一家の暮らしを音と映像だけで「観客に体感させる」ことに主眼が置かれているからだろう(実際にいつどのような音がどの音量で聞こえたか、収容所からの音だけで600ページの台本があるらしい)。そら、面白い話になろうはずがない。
が、しかし私たちはホームドラマのように描かれた彼らの恵まれた暮らしの中に、いくつものおぞましい事実を見つける。収容所のユダヤ人から収奪した毛皮を鏡の前で着飾る妻、金歯で遊ぶ子どもたち、そして塀の向こうからは終始、女・子どもの悲鳴や焼却炉の稼働音が聞こえ続ける。「えー、マジか~」「無関心すぎやろ~」と令和に生きる日本人の私は声を上げたくなるが、本当にそうですか?ヘス一家とあなたは何が違うんですか?と、この映画は問うている。
少なくとも本作で描かれる所長のヘスは、仕事熱心で謹厳実直、部下にも慕われ、家庭にあっては子煩悩な良きパパであり、妻とは将来の夢を語り合って結ばれたごく普通の夫婦である(すべて事実らしい)。職業がアウシュビッツの所長であること以外、何らの価値観の相違も見い出せないのだ。産業革命以降の現代社会では職業が人間の唯一の存在形式であり、つまりは巨大な経済的メカニズムの中の歯車としてしか人間が存在しえないことを鑑みれば、自分がもしヘスだったら、ヘス家の住人だったら、違う行動がとれたのか。その答えは、相当に怪しい。
いや、わざわざヘス一家に自分を重ね合わせる必要もないのかもしれない。なぜなら今だって、自分が享受する平和の壁の向こうにはガザやウクライナがあり、もっと言えば7億人もの人間が飢餓線上にあるのだから。そのことを私たちは十分すぎるほど、よく知っている。知っていながら、その事実や悲鳴や誰かの断末魔をヘス一家と同様、都合よくノイズキャンセルしながら生きているのではあるまいか。少なくとも壁の向こうの圧倒的な理不尽により命を落としていく人間から見れば、ヘスも私も大差ない、職務に忠実で無責任な、ただの職業人間に過ぎない。
劇中では、唯一、赤外線カメラで描かれる少女が登場する。これも説明がなく、見るからに怪しく不自然な動きをするので、一瞬、泥棒か何かか?と見まがうが、飢餓で苦しむユダヤ人のために夜間ひそかにリンゴやジャガイモを彼らが見つけやすいように隠している姿らしい。人知れず、リスクを冒しながらも、自らの良心にもとづいて行動する最も人間らしいその少女が、あるいは本来の人間らしさというものが、この社会では赤外線をかざした熱画像でしか見えない(しかも不自然な行為として映る)というのは、なんとも皮肉で、痛烈なメッセージである。
企画・プロットが全ての映画
アマプラで鑑賞。公開当時、映画館で観なかったのには明確な理由がある。それは、話題作として作品の概要を繰り返し聞く内に、すっかり観た気になったから。もっと正確に言えば、「アウシュヴィッツの強制収容所で行われている事を知ってても、その隣で何食わぬ顔で日常生活を行うドイツ人が居た」というコンセプトを知った時点で、本作のメッセージの90%を受け取れた気がしたから。
実際、アマプラで鑑賞しても予想通りだった。本作の正しい見方は、舞台がアウシュヴィッツと知らずに観始めて、「ユダヤ女から宝石を取った」という台詞でもしかしてと思い、中盤でアウシュヴィッツと明言された処で、やはりねと確信するべきなんだと思う。TV等でアウシュヴィッツが舞台と宣伝しまくった時点で、本作を観ても残り10%を確認するぐらいの価値しかないと、本作への「関心」が奪われてしまった。
それでも本作の実験精神は素晴らしい。ただ、説明をナレーションベースにした30分弱のドキュメンタリーでも、同等のメッセージは十分伝わる気もする。
どんな時代と背景があっても、必ず残る良心
世界史に残る大事件
それを題材にした作品
それ故、知識を必要とすると同時に当時の価値観との対比を考慮せざるを得ず、評価そのものは非常に難しい。
ドイツ国民が今でも抱えている集団意識
それは、自分たちの血に流れる「あのこと」への慚愧の念
そしてまたこのような作品によって、「そのこと」を掘り返さえるのだ。
それに加えてこの作品は、単に当時の日常が描かれている点が悩ましい気がする。
さらにそこに足された「象徴」
その意味するのは解らないではないが、現実と非現実的という壁が理解を難しくさせている。
2度差し込まれた暗視スコープ的映像
少女が土手にリンゴを産める行為
少女が舟にリンゴを入れ、スコップ置き場にもリンゴをばらまくシーン
その際少女はケースを拾うが、おそらくその中にあったのが「太陽の光」という代名の歌詞だろう。
これはユダヤ人の希望 届かなくても持つべき希望を象徴している。
当然少女がばらまいたリンゴは希望の象徴で、彼らに届いてほしい願い。
逆に、そんなことは物理的にはできない。
そして、
少女はヘスの家の使用人のマルタ
彼女は危険を冒してまでユダヤ人に一縷の望みを届けている。
そこに差し込まれるのがヘスが娘を寝かしつけるために語るお話。
この対比
タイトルには、生きる上での関心ごとがドイツ人とユダヤ人とでは全く領域が異なることを示しているようだ。
ヘスの妻はそこが楽園だと考える。
夫の転勤でその場所を離れることを断固拒否するほどだ。
息子たちは男だからか、自分たちの住む場所に違和感を持ってはいない。
しかし娘たちは日々不眠症となっているのがわかる。
それは、
ずっと聞こえ続ける銃声と怒号 悲鳴のような声によって影響されているのだろう。
妻へディの母がやってきたがある日突然去っていった。
彼女の置手紙は明らかにされていないが、見た目には楽園に見えても絶え間なく聞こえてくる地獄の叫び声に精神状態がおかしくなると思ったからだろう。
娘へディの関心ごとが裕福な生活であるのと同時に、絶えず聞こえてくる怒号に無関心でいられることが、母にはどうしてもできなかったのだろう。
ヘスは最後に最新式のガス室の構想を思いつく。
深夜 妻へ電話する
階段を下りる時に吐いたのは、彼にも愛する家族がいることで自分たちが何をしているのかを頭の隅で出来ている理解と両親の呵責、または罪悪感の様なものがわずかでもあったからだろう。
それが、
現代 アウシュビッツ強制収容所が資料館となり、そこを掃除する日常の画に切り替わる。
当時誰もが思ってもいなかったことなのだろう。
掃除する彼らに笑顔はない。
ドイツ人全体の贖罪感が漂っている。
たった一人暗い階段を下りていくヘス。
それは紛れもなく地獄へと続いている階段だったのだろう。
独特な澄んだ映像と音響 言葉にならない
第96回アカデミー賞5部門ノミネートで国際長編映画賞・音響賞受賞ということで当初より興味深い作品ではあったが、あまりに重いテーマにて劇場に行く勇気が湧かず結局VODにて鑑賞。
オープニングからかなり独特。いきなり放送事故かと見紛うほど長い真っ暗画面。そして少しずつ音が聞こえてくるのだが、なんだか不安も募る。この時点でざわざわしながらも五感が研ぎ澄まされてきて、鑑賞準備が整ってくるような不思議な感覚。
そして全体を通して独特な澄んだ映像と音響が本作の不穏な空気に拍車をかける。本年度のアカデミー賞音響賞受賞は文句無しという感じ。
とても綺麗なのにとても怖い。とてもピュアなのにとてもダーティー。劇場で観たかったようなVODでうまく緩和できて助かったような。
良い作品だとは思うのだが、いずれにしてもこんな歴史はノーモアだ。言葉にならない。
平和に生きていると
…と言う感じがしました
壁を隔てて地獄と天国のような
天国に住んでいる人たちには
地獄が見えない
隣から銃声の音やわめき声などは
時おりというか毎日聞こえてくるのに
まったく関心を示さない
特に妻のヘスは
夫よりもいまの暮らしが
大切であの家からはどんな事が
あっても離れないだろうなと思った
ほぼこちら側の日常を描いて
あちら側のアウシュビッツ
は銃声の音や人の叫び声
で煙突から白い煙が立ち上がる
以外は収容所中の映像はない
想像するのみ
はたして
その映像を見ている私たちは…
ロシア、ウクライナの戦争にしても
戦争が始まった三年前といまの状況は
戦争が続いているにも関わらず
メディアが取り扱われなくなって
"関心"が薄れてしまう
現状を知らない見ない事もあり
いつしか"対岸の火事"しつつある
関心から抜け落ちていく
全441件中、41~60件目を表示