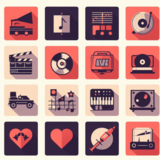関心領域のレビュー・感想・評価
全570件中、41~60件目を表示
一人ひとりが自分の関心領域をどこに持つかが問われている
映画冒頭では真っ暗な中で不調和音が響き、しばらくすると明るい水辺での楽しそうな家族のピクニックの場面に切り替わる。ルドルフ・ヘスとその妻ヘートヴィヒは自然豊かな郊外の一軒家で子どもたちと平和で幸せな生活を営んでいた。どこにでもいそうなドイツ人一家が普通の家庭と何か違うところがあるとすれば、彼らの家の塀を一枚を隔てた所にはアウシュビッツ強制収容所があり、ルドルフがそこの所長だということだけだ。
無知と無関心は異なる。本当に何も知らなければ無知だが、知っているにも関わらず、関心を向けない、或いはあたかも無いかのように振る舞うのは無関心である。ルドルフは職務として隣で何が行われているのか当然知り尽くしている(というより、指示をしている)のだが、ヘートヴィヒや子どもたちは無邪気に隣で何が起きているのか何も知らないかのように振る舞ってはいる。しかし、その言動をよく見ていると確実にわかっていることが理解できる。
人間は見たいものだけを見て、聞きたいことだけを聞いていたいと思うものであり、嫌なことから目を背けている限りは幸せでいられる。しかし、目を背けられた場所には「幸せ」とは対極な状況に置かれた人々がいる。それは第二次大戦の頃だけの話ではなく、いま現在でも全国各地で、そして世界各地で起きていること。
一人ひとりが自分の関心領域をどこに持つかが問われていることを突きつける作品だ。
悪の凡庸性
スティーヴンスピルバーグがこの映画をほめて「特に悪の凡庸性について意識を高める上で多くの良い仕事をしている」と語ったそうです。
スピルバーグが使った「悪の凡庸性」とは哲学者で政治思想家のハンナアーレントが1963年に著した本『エルサレムのアイヒマン:悪の凡庸性についての報告』から引用されています。
本は世界的な知名を得ましたが、とりわけ副題に使われた「悪の凡庸性」がナチスを形容する際の常用フレーズになりました。
このフレーズは裁判におけるアイヒマンの態度に由来しています。
アイヒマンは罪悪感も憎しみも示さず、単に自分は職務を遂行しただけなので責任はない──と主張し、それを押し通しました。
つまり悪の凡庸性とは悪人がもっている無頓着さのことです。
この映画には、ナチスがユダヤ人をコロしたり痛めつけたりしているアウシュビッツのすぐとなりで、優雅なカントリーライフを過ごしているルドルフヘス所長とその妻たちが描かれています。
音や煙や匂いが生活環境へ漂ってはくるものの、かれらは収容所に対して無頓着に生きています。
言ってしまえば縞模様のパジャマの少年(2008)から子供の交流も酷使されるユダヤ人召使いの描写も切り取って優雅なカントリーライフを見せるだけの映画になっています。
悲惨なイメージを一切見せずに牧歌的なカントリーライフときれいな画面構成のみによってナチスの残酷さを浮かび上がらせる──という映画のもくろみは成功していますが、いったんこのレトリックを知ってしまうと、率直に言って、何も起こらない映画ではあります。
しかしレトリックに依存してしまった映画ではなく、じりじりと怖くなってきます。主役は撮影と音響と効果音だと思います。
『この映画は、ライカのレンズを装着したソニー製のヴェニスデジタルカメラで撮影された。グレイザーと撮影監督のŁukasz Żalは、最大10台のカメラを家の中とその周辺に埋め込み、同時に稼働させ続けた。』
『グレイザーとジザルは現代的な外観を目指し、アウシュヴィッツを美化することは望まなかった。その結果、実用的で自然な照明のみが使用された。自然光が得られないポーランド人の少女が登場する夜のシークエンスは、ポーランド軍が提供した赤外線カメラを使って撮影された。』
『グレイザー監督は、収容所内で起きている残虐行為を見せるのではなく、ただ聞かせたかった。そのため音響デザイナーのジョニー・バーンはアウシュヴィッツ関連の出来事、目撃者の証言、収容所の大きな地図などを含む600ページに及ぶ資料を作成し、音の距離や反響を適切に判断できるようにした。彼は撮影が始まる前に、製造機械、火葬場、炉、長靴、当時を正確に再現した銃声、人間の苦痛の音などを含む音響ライブラリを1年かけて構築した。当時アウシュヴィッツに新しく到着した人々の多くがフランス人だったためバーンは2022年にパリで起こった抗議デモや暴動から彼らの声を入手した。』
『イギリスのミュージシャン、ミカ・レヴィは2016年に早くもスコアの制作を開始し、その後グレイザーと編集者のポール・ワッツとともに1年間スタジオで過ごした。「あらゆる可能性を探り尽くした」とレヴィはSight and Soundのインタビューで語っており、チームは音楽が映画にどのように機能するかについてあらゆる可能性を探った。』
(wikipedea、The Zone of Interest (film)より)
印象的だったのは軍用熱カメラをつかったという野外撮影でした。
グレイザー監督は当時じっさいに囚人らに食べ物を届けていたポーランド人少女Aleksandra Bystroń-Kołodziejczyk(1927年7月26日~2016年9月16日)に取材し、アカデミー賞受賞スピーチで映画を彼女に捧げ「生前と同じように映画でも光り輝く少女」と表現したそうです。
16歳のときポーランド国内軍に所属していた彼女は飢えた囚人に果実を届けるため、自転車で収容所に通っていました。囚人らが作業する砂地にリンゴなどを隠し置いていく様子が色のない熱カメラで撮影されていました。それはすごく恐ろしいシーンでした。
嫌悪をあおるためルドルフヘスのかりあげはかなりの剃り上げになっていました。サンドラヒュラーが演じた夫人も、がにまたで大根足でがちがちの結髪で、醜く意地わるい女に描かれていました。
夫人の母親は、隣接する収容所で何が行われているのか察知して、そうそうに立ち去るのですから「悪の凡庸性」は知らなかった、で許容されることではありません。
飢えた囚人のために砂地にりんごをしのばせる少女と、わがままでよく眠るヘス夫人を対比させることで浮かび上がる「悪の凡庸性」とは、すなわち想像力があるかないか、誰かを思いやる気持ちがあるかないか──のことです。映画はそれを言っているのであり、スピルバーグが評価したのもそこでした。
ヘスは昇進しますが階段で嘔吐すると現代へリンクしてアウシュビッツの展示物がうつし出されます。ガス室、トロッコ、かばん、靴、義手義足、囚人服・・・。スタッフが開館前清掃にいそしんでいます。想像力があるかないか──が観衆に向けられてもいる映画だったと思います。
なお邦題はミニマリスト向けのエクステリア情報誌のようだと思いました。
無関心の壁
音楽が歪み感を増幅
なぜ今、
未曾有の表現
本作は、邸宅に据えられた隠しカメラのように家族の暮らしを淡々と映し出す。ドラマやスペクタルの代わりに、問答無用に音と向き合わせ観客の脳みそをフル回転させる。
母性的な老婆が人食い魔女であった〝ヘンゼルとグレーテル〟、リンゴを隠す光の少女、言葉なき詩のピアノの楽譜が、私に「想像せよ!」と訴えかける。
アウシュヴィッツの地獄はどんなに再現しようとしても表象不可能だ。不完全だからこそ、私たちは〝自分で想像すること〟しか、犠牲となった死者に応答する手段はない。それは人間としての倫理的債務だ。私たちに託された債務以外の何ものでもない。想像しない限り過去は繰り返されてしまう。
表象不可能なものに対する、真摯に考え抜かれた未曾有の作品だった。
世の中そのもの
SNSなどで簡単に生々しいニュースを目にする日々では、自分の心を守るために無意識のうちに自分は関心領域を作っていたんだなと思った。
この家族と自分を置き換えすぎて辛くなった。
こんな虐殺の様子をBGMにしながら生活していて、この人達だってきっと極限状態だったとはず、、と思っていたら、子供は問題行動を起こすし、祖母は急にいなくなるし、やっぱり皆ちょっとずつ狂っていくので却って安心した。
映画の中で、寝る前に家中の灯りを几帳面に消していくヘスの姿は、ホロコーストという自分に与えられた仕事を淡々とこなす真面目な人間性をとても表してるなと思った。
怖い!美麗映像と緻密かつ重厚なる音響世界
ベルイマンやポランスキー作品に通じるエレガントなひたひたと内側に水が浸透するような恐ろしさ。
とにかく庭園、建築、衣装、部屋、何から何まで贅沢な一級品。
でもじぶんはあそこには絶対住みたくない!
一晩でも逃げ出したくなります^_^
塀の向こうで何が起きているか知っているのは、
収容所で日がな働くこの一家のあるじと、
われわれ観客だけという!
阿鼻叫喚の声や銃音が、
毎日遠くから聴こえてくる、気味の悪さ。
奥さんは、こんな恵まれた暮らしを手放したくない。
転勤の話が出たら、あなたが単身赴任して!というばかり。
あそこの煙は、銃殺された、おびただしい数の遺体を焼却炉で焼いているからなのだ。
その空気を吸って野菜や木花や人間が生きている日常。
焼却炉を増設するに、設備の冷却や運営をどうするか、淡々と会議がすすめられたり。
見る前から宣伝で、塀の向こうを全く映さないとは聞いていて。
なおさら、その闇が非常に深く感じられましたね。
わかったらおもしろい
アウシュビッツの隣に住む家族の日常を撮った作品。
最初の感想は「題材や視点はいいが変」
どう解釈すればわからないシーンや撮影技法が見られて変だと思った。
ただ、のちに考察を見るとそのシーンの意味や撮影技法が使われた経緯がわかって納得がいった。
作品では終始、一家とアウシュビッツとの繋がりが音で現されていて、すごくリアルで新しい感覚だった。
絵的な話では、シーンのアングルにはもっとこだわってよかったと思った。このテイストだとミッドサマーのような美しくてシュールな絵作りをしてあるかと思ったが、その辺は曖昧というか中途半端だった。
作為的な感じを避けるためにセットのいろんなところにカメラを仕込んでなるべくリアルで客観的な絵作りをしたと解説で見たけど、その他の表現方法に作り込みを感じるので、アングルもしっかり作り込んだ方が作品にまとまりや重みがでる気がした。
普段わたしたちは、身の回りに起きている様々なことに無関心なポーズで生きている。
ニュースなどを見て心を痛めることはあるが、その数時間後には心の底から笑ったりしている。
動物を可愛いと思いながら、食事で出た肉を対して感謝もせずに食べる。
そんな自分がアウシュビッツに関わっていたとしたらどうしただろう。改めて考えるきっかけになった。
隣で何をしているのか
Amazon Prime Videoの配信を視聴。
小説の映画化で、当時を知る者の証言などを参考にしてリアルに再現したとのこと。
今作の登場人物は、家の塀の向こう側で何が起こっているのか ある程度は知っていたとしても、自分たちで築き上げた氣に入った日常が続くなら 一家の主の任務に干渉するメリットは無い。しかし、今の場所を手放すとなると話は違うというわけだ。
何してるのか わかりにくい サーモグラフィのシーンが 意味深であった。
第二次世界大戦が どういうものだったのか、また アウシュビッツ強制収容所で 何が行われていたのか については諸説ある。
数十年前の戦争時代に限らず、現在も 隣や見えないところで 誰が何をしているのか 無関心だったり、関心があっても触れないように していたりする。
時局を見る目が欲しい
NHKの『映像の世紀』でエヴァ・ブラウンが撮ったフィルムの映像を見た。アルプス地方の風光明媚な山荘で過ごすヒットラーと愛人、取り巻きの人たちの贅沢な暮らしぶりが映し出される。また、少し前に『縞模様のパジャマの少年』も見た。本映画とこの2本の共通点はすぐ近くで絶望の中で過ごす人が大勢いる中で、それを見ないようにするか全く関心がないかして過ごす時の権力者たちを描いていること。
『縞模様のパジャマの少年』は主人公に残酷なしっぺ返しが来る衝撃的な結末だが、この映画は淡々と時が流れていく。でも、何不自由なく贅沢な暮らしを満喫しながら、常に聞こえている不自然な音や声の数々が観ているこちら側にじわじわと不快感を感じさせて止まない。説明的な描写がほとんどないということも暖簾に腕押し的なストレスを感じさせて、映画はふっと終わってしまう。
後に残るのは混乱、困惑、不快感、恐怖、そして自らに真実を見極める能力があるだろうかという大いなる疑問。正解は分からない。
この演出からくる雰囲気を味わった事が…
と思ったら『アンダーザスキン』の監督だったのか
BGMは隣のアウシュビッツの焼き場のゴォーと炎が燃え続けている音のみだったり、冒頭から画面真っ暗が数分続いたので音声が出てなかったら、「機械トラブルか?」と思った位焦らされた。
アウシュビッツの隣に住む将校とその家族暮らしを見せつつ、その端々に強制収容所での虐殺方法語らせたりする。
「400から500の“荷”を焼きます」など、あってならない事が平然と話されている。
あの狂った時代を淡々と流していく。
大量虐殺を行っているその隣で送る日常…と自身の子どもに本を読んであげる姿が一致せず、不気味だ。
楽しげな川遊びも、いきなり増水したと思ったら、例の“荷”を
焼いた灰を流しており、子ども達を洗い流した後の浴槽に灰が混じっているのを妻が見て気味悪がっていたりする。
なのに夫が昇格して転属する話がでると、妻は夫に単身赴任を迫る。
阿鼻叫喚の地獄のとなりに住んでいるのに妻はここで子育てすると言う…。
アウシュビッツ女王等と言われていると話す妻がまた気持ち悪い
内側と外側
第二次世界大戦が行われている戦時中の話。
この映画の中では、残酷な虐殺のシーンなどは一切ないのだが音声だけを使ってその物事を恐怖をうまく伝えていた。
人が当たり前のように焼き殺されている中でも普通の暮らしをしている。
その家族は、塀の向こうで行わている行為がどれほどに酷い事というよりも自分たちの生活の方が大事だとそれほどまでに関心を向ける事がない。
自分が感じているものと内側と人から見られている外側も同じようなものかもしれないと感じました。
自分の関心の範囲でしか物事を捉えていないのだが、本質的に最も気にするべきは、外側と内側にある部分。
それは、自分と他人を尊敬しつつもお互いの持ちつ持たれずの関係性の中にあるような事とも言える。
歴史の中でも最もひどい虐殺が行われている中でこれだけ平凡な生活をしている事は、存在していただろう。
実際に今の生きている自分の生活も似たようなものかもれしれない。
世界という広い目線に立ってみれば、自分の問題なんてほんの些細な問題だけど、とても大きな問題のように扱っている。
もっと根本的な解決を見出す事の方が優先されるのに。
歴史の背景にある見えない部分を改めて感じる作品でした。
日常生活に隣接して地獄があることを知りながら観る映像
アウシュヴィッツ収容所に隣接する邸宅での収容所長の中流家族の生活を淡々と描いている。
ホロコーストの場面は一切出てこない。
一家にとっては平和な日常生活が繰り返されるのですが、常に、銃声、悲鳴、得体のしれない音(多分、ガス室を動かしている音とか、焼却炉を動かす音とか、分厚い鉄の扉の鈍い音とか)が、遠く近くから聴こえて来ている。
それでも家族は、全くその音を気にしていない(長女の夢遊病的な行動を除けば)。
例外的に、ドイツから転居してきた妻の母は、中盤に突然、帰国してしまうけれど。
日常生活に隣接して、地獄があることを知りながら観る映像は、恐ろしいと思いました。
時代の空気の再現性が優れている良い映画でした。
副流煙を吸い続けるかのような生活
全く残虐なシーンはない
日常の穏やかな生活の話
ただしそんな生活の中にも闇の部分も描かれている
アウシュビッツ収容所のトップである旦那の女遊び
その妻の使用人への横柄な態度
その子どもの乱暴なメンタル
もしかして収容所から聞こえてくる音や匂い、煙突からの煙などで、人として正しいことが忘れていくのかも
アウシュビッツ収容所の中で起きていることが全く分からない。
ただ、その側に住んでいれば、タバコで言う副流煙のように、その周辺にいることで知らぬ間に蝕まれていくものがあるのかもしれない
最後の音楽……………
戦争って僕のせいなのか?映画NO1
全570件中、41~60件目を表示