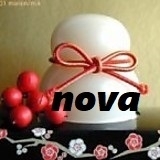関心領域のレビュー・感想・評価
全570件中、521~540件目を表示
前衛的なアウシュビッツもの
「観たことを一生忘れないだろう」
「どんなホラー映画よりも恐ろしい」
って文句が、無機質で不気味な音楽と共に、映画館でガンガン流れてましたが、ハードル上げすぎ(笑)
ホラー映画じゃない(笑)
ほとんど恐くない(笑)
演出も前衛的で、設定も前衛的。
新しい視点、新しい切り口、のアウシュビッツもの。
65~70点ぐらい。
最後は意味深で、考察不可避。
1回観ただけじゃ、なかなか理解できません(笑)
さあ、もう1回観ますか♪
無関心という残酷さ。
実際どうだったのかは別として、無視や見て見ぬふりでもなく、そこには何もない、透明なものだから関心の持ちようもないくらいの無関心さが描かれていた気がする。
作品として表現したいことはわかる気がしたけど、細部のあれこれを理解するには自分にはあまりにもナチスやアウシュヴィッツの知識が無さすぎた気がする。ちょっと知ってる程度だとよくわからないところが多かった気がする。
「冒頭」
かなりの長尺(そう感じただけかも)何も映されない、音だけのシーンから始まる。
あれ?映像だけ映ってないけど??と思うくらい。
音に注目しろよー!って事かなと思うけどなかなか印象的なはじまり方だった。
「なんだか気持ちの悪い映像と音」
どう言う意図かわからなかったけど、なんかドキッ!!とするような音が鳴ったり(気持ちとしてはWindowsのエラー音のような嫌さだったなぁ)
真っ赤に染まる映像や暗視スコープ??みたいな映像か入ったり、ちょいちょい気味の悪い感じの表現が差し込まれていた。
ラストなど含めこのあたりは誰かの解説とかで補完したい!
「無関心な感じのカメラワーク」
本作割と単調だなぁとも思うのには、まぁこれと言ったドラマ性があるわけでもなく、ただただある一家の日常を映すだけで、だからこその関心、無関心が描けているとは思うけど、カメラもどことなく引いた目線で見ているような感じがした。
「エンドロール」
エンドロールで流れる曲がまたなかなかの気味悪さで、こんなのずっと聞かされてたらどうかなりそう…
でもそう感じられたのは本作においてずっと音に注目させられ関心を持たされたからなのかもしれない。
本筋とか言いたいことはわかった気がするんだけど、とにかく色々わかるにはもう少しお勉強が必要だと感じる作品だったなぁという印象。
しっかりとした知識があれば、もっとこの作品の細部や人の怖さを感じられたのかも知れないけど、今の自分には合わない部分が多かった…
環境が人を作る
母親はユダヤ人から奪った毛皮のコートを試着し、ふとポケットに入っていた華やかな色の口紅に気付く
それを何の躊躇もなく手の甲に塗ってみて
気に入ったのか唇につけてみる
満足したのか引き出しに仕舞う
観客は毛皮の持ち主がその華やかな色の口紅をつけて毛皮のコートを着て出かけた思い出を想像し、それを取り上げられたことを想像して嫌な気分になる
母親はそんなことは微塵も想像しないんだろう
自慢の家に美しい花々や野菜やハーブを育てている自慢の庭
壁を隔てて、すぐ隣の地面にたくさんの血が流れ、灰が撒かれているのに
毎日聞こえてくる銃声を太鼓で真似する子供
この地で子育てをしたいという強い言葉に絶句する
無関心ってなんてグロいんだろう
ノー天気な奥さん
第2次世界大戦中、ナチスがポーランドのアウシュビッツ強制収容所を取り囲む40平方キロメートルの地域を「関心領域」と呼び、多くのユダヤ人が殺されたその強制収容所と壁一枚隔てた豪華な邸宅に住むドイツ人の所長とその家族の暮らしを描いた話。
アウシュビッツ強制収容所の中は映さないが、銃声が聞こえたり、不気味な煙が煙突から出ていたりで、殺人が行われていたことは家族も知っていたのかもしれない。
ノー天気な奥さんがちょっとイラッとしたが、当時の特権階級の人を夫に持つと自分がさも偉くなったような錯覚をするものなんだろう。
たぶん、日本が中国や朝鮮でも同様な事をしていたのだろうとは思うが、壁一つ隔てただけの場所に、流石に家族は住まわせてはいないと思い、少し違うのかな、なんて観てた。
邦題が関心領域で、隣に無関心な家族を描いているのが反戦のメッセージなのかも。
難しくて面白くもなく眠くなるが、無関心に対する問題提起作品だと思った。
公開初日、レイトショーにて。 アウシュヴィッツ収容所の隣りで暮らす...
公開初日、レイトショーにて。
アウシュヴィッツ収容所の隣りで暮らす家族の話であることは予告編を観て知っていましたが、
2時間弱、それをどうやって描くのか…?
あまり期待すると、期待したほどでは無かった…と思いがちなので、
とにかくそれだけを期待して観ました。
エンドロールが始まるやいなや席を立つ人、多数…とか、
上映中にあちこちで寝息が聴こえた…とか
そんなレビューもあるなかで、
いやいや、こんなに恐ろしい映画を観たのは初めて。
それも敢えて恐ろしいものを見せずに。
皆、その恐ろしいものが何なのかは
映画やドキュメンタリーで知っている…という前提です。
そしてそれは、
「あるもの」で描かれています。
ネタバレになるので書けませんが、
それによって全て想像できてしまう。
また、
自分の中にも確実に存在する、
見て見ぬふりとか、無関心とか、
考えようとしない…という
悪の恐ろしさも突きつけられる。
今年のアカデミー賞で、
「PERFECT DAYS」とともに
国際長編映画賞にノミネートされていて、
PERFECTDAYSの受賞を願っていましたが、これは負けても仕方が無い…。
ある意味、対極にある作品、と言えます。
「落下の解剖学」で妻役を演じた女優が、今作でもまたまた妻役を。
今作でも主役は彼女かもしれません。
それも、いかにもインテリ風な作家役の前作とは全く違って、
収容所所長の妻になりきっての演技、
女優さんってすごいな、とあらためて思ったのでした。
「愛の反対は無関心」とはまさに正鵠
米アカデミー賞にノミネートされた時から
大注目の作品でした。
よく手入れされた美しい庭を持つドイツ人の邸宅は
アウシュビッツ収容所の隣に位置していた。
時折り、銃声の様な音や悲鳴、怒号が聞こえて来る環境。
それにも増して、一日中、ブオ〜〜と言う様な重低音が
何となく家の中でも聞こえて来ている。
時折、空を覆うアウシュビッツからの煙。
川遊びに興じていてもいつの間にかアウシュビッツから
乳白色の汚泥が流れて来る。
そんな環境で、無垢な子供たちは少しずつ何かが蝕まれて行くのに
この家の女主人は、自分が丹精込めた家や庭から離れるのが嫌で
夫が人事異動でアウシュビッツを離れる話をすると
「あなただけ単身赴任すれば〜〜」などとつれない返事。
なんか現代にも通じるよね〜〜。
隣がアウシュビッツ!全くお構い無し!
そんな事、私の知った事じゃない!
その無関心な状態こそが「関心領域」
重い話と覚悟して観に行ったが
そんなにエゲツナイ描写は無い。
でも、ちょっと想像力を働かせれば〜〜〜
映画館で、逃げられない状況でぜひご覧ください。
で、月に8回ほど映画館で映画を観る
中途半端な映画好きとしては
想像力を総動員して観ると
恐ろしい話だと言うのは良くわかる。
映画の中盤、不機嫌な女主人が召使の女性に八つ当たりする。
例えば時代劇とかで女主人叱られて「今晩は晩飯抜きだよ」
と言われても、命までは取らないのだけど
この「関心領域」の家の中で
よく、その言葉が言えるよね!みたいな〜
この家の隣には何があるのか
確実に解っていて、この女主人はノウノウと暮らしている。
コ〜〜〜〜ワ!!
もちろん、解っていないとは思っていないが
この女主人が解っていても、その頭の中には
「人の命」のことなど、かけらも入っていない事を
改めて突き付けて来る。
翻って現実を生きる私。
この世界の理不尽な出来事を知るたびに
自分の懐と相談しながらのささやかにリンゴを置くしか
手を差し伸べられない小さな自分。
この手の映画は、世界を気にして目を向ける人は
何も言われなくとも観に行くのだろうけど
全く関心の無い人にとってはまさに「無関領域」の外!
「愛の反対は無関心である。」 これは
マザー・テレサの言葉といわれている。
どんなに良くできた映画であろうとも、
全く関心の無い人にいかに届けるのか?
結局その課題が残ってしまうんだよね〜〜
因みに今、ウクライナを攻めるロシア。
パレスチナを殲滅しようとするイスラエル。
チベットを凌辱し、台湾をロックオンする中国。
ロヒンギャを良しとしないミャンマー。
また、国レベルでは無くとも女性や子供が
搾取や暴力に怯えて生きている地域が
今、どれほどあるのだろうか〜〜。
みんな助かって欲しいと祈るだけでも
地球が0.0001ミリでも動くと信じたい。
そこは「幸福」や「夢」を掴むとこかあ?
そういう大前提でのボタンの掛け違いがあるから「幸せの団欒」が「不気味」で仕方がない。そんな中、妻の母は多少「心」があったのかも。
仕事というか工場にでも行くように出かけていく主人公一家の父親。子どもたちも何かを見ないようにしてるとか我慢してるとかじゃない。それが当たり前になってるんだよね。
本当にこれが収容所の隣でなければ、平凡なファミリーの日常なんだけどなあ。
BGMがほとんどないのは映画としての効果はある。それはエンドロールも含めて。
ラストらへんの清掃の場面。あそこだけ現代なんだよね。それも何かのメタファーになってるのかもだけど、考えるのが少し怖い。父親病気なの?でもそれを考察するのが怖い。
強烈なインパクトを与えた問題作という点では★5であるのは間違いない。収容所内をまったく見せないのに気になって仕方がないというのも制作側の手腕だよね。
誰でも言いそうな感想は言いたくないな。多分そんなちゃちなものではないと思うんで
期待度◎鑑賞後の満足度◎ 端的に言うと人間の”生活圏”の話です。
①人は誰しも自分が興味・感心のある事の範囲内で生きている(と考えている)と言える(私的に言うと“安全圏”)。
その圏外の事には基本無関心、興味がない、または他人事。
※なお、日本語では、「興味」と「関心」との違いを下記のように区別しているようです。
(1)「興味」は、おもしろいと感じる気持ちや、知りたいと食指を動かされるような気持ちをいう。
(2)「関心」は、対象に向けて注意を払う心。「興味」が対象のある一点に感情的に向けられることがあるのに対し、「関心」は対象全体に理性的に向けられることが多い。
※英語では、”interest“は、オックスフォードでは、“feeling of wanting to know or learn about something or someone”とあって、やは理性面・地勢面というよりは感情面の話。
無関心」というよりは「無感動」「無神経」「無(感)情」といった方がニュアンスとして近いだろう。
『The zone of internet 』とは元々はドイツ軍がアウシュヴィッツ収容所周辺の事を意図的に指した言葉らしいから、「関心領域」というより「感情(を麻痺させるべき)領域」と言って方が近いのかも(ついでにドイツ語の本来の意味も知りたいところ)。
本作の場合、それがアウシュヴィッツ収容所の隣という極端な例なだけであって、人間とは所詮そんなもの。仕方がない。
だから余計恐ろしい。
②本作の監督が『アンダー・ザ・スキン 種の捕食』と同じ人だと本作を観るちょっと前に知ったばかり。
『アンダー・ザ・スキン 種の補食』、実は密かに好きな映画。今まで観たスカーレット・ヨハンソンが出ている映画の中で一番好きなくらい。
何処か同じ匂いがする(同じ人が撮ったから当たり前だけど)。
③善悪の問題ではないと思う。
勿論、戦争は良いことか悪いことか、正しいか正しくないか、と問われれば良いことではないし正しくもない。でも、戦争はいつまでたっても無くならない。
現在ウクライナやガザ地区で起こっていることも(極端に言えば)元々他人事だったのが、時間が長引くにつれ事態に慣れてきているのが自分でも怖い(勿論心は痛むが、かといって何か出来るわけでもない。募金くらい。)。
ナチスの蛮行は許しがたい。(ついでに言えば、日本軍の蛮行も許しがたいし、ベトナムでのアメリカ軍の蛮行も許しがたい等々)。
アウシュヴィッツ収容所で行われたことは人類の歴史上最悪の悲劇の一つだと思う。
でも、それは“後追い”で知ったから、既に歴史になったからそう思うのである。
この家族を、隣で行われていた恐ろしい事を知りながら無関心でいた或いは何とも思わなかった酷い人達、人非人と非難する、断罪するのは簡単だ。
本当にヒドイ話だったよね、と感想を述べるのも簡単。
でも、もし当事者であればどうだったのか。
夫は少なくとも自分たち(ナチス)がどういう事をしているかは理解していたとは思う。
それが正しいことだと本当に信じていたのか、当時ドイツという国で自分や家族を守って生きていくためにやむを得ずやっていたのかどうかはともかく。
だから突然の吐き気に襲われたのだろう。
あのシーンに突然挿入される現在のアウシュヴィッツ収容所記念館の映像の意味。
妻の方は、敢えて言えば「無関心」というより「無神経」「無情」「無慈悲」と云うべきか。
収容所で捕虜から奪った衣服を平気で使用人に“分けて”上げるし、恐らく匂いや色んな音・肥が聞こえるのに動じている気配もない(母親は居たたまれなくなって家を出てしまうか…かつてユダヤ人家庭で使用人をしていた過去がある)。
アウシュヴィッツから去ることに異常に反発する、というか、あの家は彼女が一から作り上げた彼女の家庭であり王国なのだ。それが全てに優先する。
卑近な例だが現代でも似たような事がないとは言えない。
先に工場があっても後から周りが住宅地になれば、後から来た住民が「臭い」の「音がうるさい」のとクレームする。
自分の家庭の住環境が優先する。
彼女の場合も自分の家・家族の住環境か出、隣がアウシュヴィッツ収容所なのは従。
隣がそうでない方が有り難かっただろうけど、夫が収容所の司令官であれば折り合いをつけるしかないし、何しろ彼女の娘時代からの夢のマイホームで隣は何するものぞ、と自分の家の中を何とか理想通りにデコレートするのに一生懸命だ、
それを笑えるだろうか。
それに本作は彼女をモンスターみたいに描いてはいない。
④現代の殆どの日本人は他人事みたいに思っているけれども(何せ「神道」の国だから“水に流す”のが早いし上手い)、第2次世界大戦中は日本もドイツと同じ枢軸国側で、ユダヤ人殲滅なんて極端なことはしなかったけれども、真珠湾攻撃成功の際には国民挙げて喝采を叫んだろうし(彼方では2,000人死んでます)、本土の捨て石とされた沖縄で4分の1の島民が死んだということ、日本軍が中国や韓国で行ったこと、知らされなかった・無知だったと言えばその通りだが無関心・想像力の欠如とどう隔たりがあるのだろう。
愛の反対
得体の知れない反響と、ほんの些細な家族の営みの描写が怖い。
時間が飛んで「施設」を清掃する人々を追っているところが印象的。
それら管理していく人しかり、この作品しかり、こうして歴史は
継承されていくのでしょうか。
自分にもどこか身につまされるところがあった。
暗澹たる気持ちしか残らない映画
私の住む街に小学校と動物保護センターが隣同士に並んで建っている場所がある。
その、保護センターでは犬や猫など動物の殺処分も行っている。
大多数の子供(隣の学校に通う小学生)はそのことを知らされていないだろうが、授業を受けている時や友達と遊んでいる時に、子供たちのすぐ近くで、動物たちの命が奪われているという事実がある。
もちろん、動物の命と人の命を同列に論じることは正しくないのだろうし、哲学的な小難しい話になってしまうのだが、その子供たちは(子供たちが事実を知れば、ショックを受けることがわかっている大人たちを含めて)『無知のヴェール』に守られてるから、普通の生活をおくれるんだよね。
ただ、これは自分たちの生活圏内で起こっていることでも、日本から遠く離れたウクライナやイスラエルで起こっていることでも同じこと。
人や動物を不幸から救いだすことより、自分たちの平穏な暮らしを優先してしまうのが人間だからね。
自分の私財や命を投げうってでも人や動物を助けようとする人をヒーロー扱いするのはそういうことだよね。
さて、前置きが長くなってしまったが、映画の話。
第二次世界大戦のさなか、ユダヤ人の大量虐殺が行われているドイツの非日常の中の日常を描いた映画。
アウシュビッツでユダヤ人が大勢殺されているのに、その近くで幸せそうに暮らす家族の様子を描いたお話。
第二次世界大戦から約80年。
こうした事実(アウシュビッツなどでのユダヤ人大量虐殺)を文字でしか知らない人も多いだろうから、映像に起こすことは一定の意味はあるんだろうが、目新しさが皆無のため、ある程度の年齢の人たちには、擦られまくった題材を繰り返しているだけにしか思えないかもしれない。
まぁ、ドイツは戦争に負けて、侵攻して来たソビエト軍などに(一般人も含めて)めちゃくちゃにされるからな。
因果応報というか、結果的に『ホロコーストは自分たちとは関係ない』では済まされなかったんだよね。
個人的にはそこまで描いてワンセットではないかと感じた。
普段は優しいお父さんが平然と捕虜移送の話をするシーンやラストの殺されたユダヤ人たちの履いていただろう、大量の靴には多少、ゾッとさせられるところもあったが、ドイツ人たちが殺したとされているユダヤ人の数はあんなものじゃないからね。
ちょっとリアルには感じられなかったな。
映画自体はとても地味で、ハッキリ言って退屈。
まぁ、題材が題材だけに仕方の無いところはあるにしても、映画はエンターテインメントだからね。
観客はお金を支払って楽しむために映画館に行くもの。
観客を楽しませることを放棄して、自分(監督)の撮りたい内容を一方的に押し付けるのは自己満足映画としか言いようがない。
淡々と事実だけを流して、解釈は観客に丸投げってスタイルもどうかと思う。
難しい題材だけに下手に監督の主観を入れれば、確実に否定的な意見が出るだろうからな。そこから逃げた感もある。
観ていてまったく楽しくないし、暗澹たる気持ちを抱えて映画館を出ることになるだけ。
個人的には誰かにおすすめすることは120%有り得ないほど、何がしたいのかわからない映画だった。
映像と音の乖離。表象不可能なものの存在感
2023年。ジョナサン・グレイザー監督。アウシュヴィッツでユダヤ人の集団殺害が本格化すること、収容所所長の家族は壁一つ隔てた地所で優雅に生活していた。収容所からのなんとも不気味な物音が途絶えないなかで、平然と暮らす一家の様子を描く。
子育て、出世、庭園、川遊び。一家の生活はちょっとだけ上流だが標準的な家族生活に過ぎない。妻はイタリア旅行を望み、夫の転勤が決まるとアウシュヴィッツでの暮らしを手放せずに単身赴任を求める。子供たちはほほえましい兄弟げんかをしている。表面的に進行するこうしたごく普通の暮らしの背後に終始、収容所からの音が聞こえているが、つかのまの訪問者である妻の母以外は気に留めている様子はない。それが恐ろしい。音と映像の乖離。アラン・レネとまではいかないが。
犠牲者であるユダヤ人はほぼ画面に登場せず、収容所も遠くから眺められるだけだが、そこにあった「悪」の存在感は半端ない。「表象不可能なもの」の議論を思い出す。描かれないことによる存在感。
サンドラヒュラーと🐕🦺
映像が途切れたようになったり、ずっと焼却炉が稼働してるような音が鳴っていたり とにかく不穏な空気がノンストップ サンドラヒュラー無関心で冷酷な役が板に付いてきてるけど大丈夫でしょうか?胸くそ悪い役どころ見事でした、そしてその洋服はもしや?服ぐらい買えよと思ってしまった
優雅な金髪に長閑な田園風景、すぐ隣では上がる噴煙ととても不気味な風景 しかし誰かの犠牲の上に豪勢な生活が送れる、隣では何が起こっていても無関心というのはもしかしてそこかしこに有る構図なのではと思ったりした
"無関心"という共犯に潜む"凡庸な悪"
自然から始まり、しばらく戦争の影を感じさせない。ドリーショットによる横移動こそあれどカメラ自体は動かない、決してパンしないカメラは、恐ろしいほどに秩序立った"静"の印象を受ける。作中、家の中で同じ画角のショットが度々出てきて、そこで日常が繰り返され、生活風景が繰り広げられていることを際立たせる。メイドたちには「生地1枚ずつ取っていい」と言いながら(そして生地が広げられた机に集うメイドたち)、自分は部屋で高価な服を身にまとい、その様子をあらゆる角度から撮ることで、他に誰もいないことを強調する。
そんなふうに、アウシュヴィッツ強制収容所のすぐ隣で家や庭にも凝りまくって、自分の理想の城(塀で覆われた)を築く奥さん。そんな何気ない生活風景でも、ずっと隣から聞こえる厭な音が、そこでは"人間"らしい生活や振る舞いこそ、何よりも"人間"らしくないということを表していた。ぜひとも耳を澄まして鑑賞してほしい。そうやって数え切れぬほどの人間の命を、何事でもないかのように容易く奪ってきた現実は、本人たちにいつかのしかかるのだろうか…?作品終盤、誰にでもわかるような形で、突然とある手法でそれをハッとさせられる。
あくまでフラットに描かれた"ドラマ性の剥奪"と"凡庸な悪"、"結局他人事"という無関心の壁。ロングショットの多さなど、いかにもヨーロッパ的か。見る前から分かっていたことだけど、やはりキャッチーな内容ではなく、あくまで淡々と進む語り口なので、映画館でウトウトしている人もチラホラといた。そして、『落下の解剖学』に続きこっちでもザンドラ・ヒュラーとは、すげぇ。もはや強烈キャラのイメージになってしまいそうだ。
勝手に関連作品『ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地』『ニュー・オーダー』
ええええー!?
全570件中、521~540件目を表示