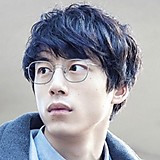関心領域のレビュー・感想・評価
全571件中、21~40件目を表示
権力者が生まれると“思考停止や凡庸さ”の者たちが支配する世に…
アウシュビッツ関連映画は
これまでも随分と鑑賞してきたが、
この作品は少し視点の異なる作品だった。
ある意味、
その“思考停止や凡庸さ”が重大な犯罪を
引き起こしたとするアドルフ・アイヒマンに
関する映画
「スペシャリスト~自覚なき殺戮者~」や
「ハンナ・アーレント」と
根っ子は同じ“無関心”がもたらす悲劇
を描いているのだろう。
そんな“無関心”を象徴するシーンとして、
自宅からチョイ見えする監視塔や
焼却炉の煙突と煙などを背景に描かれる
ルドルフ・ヘス宅での家庭的日常描写は、
制作側の意図が明白な見事な構成に感じた。
但し、この作品で残念だったのが、
せっかくヘス家族の“無関心”日常を
淡々と描くことにより、
それが強制収容所内の地獄絵図を
逆説的に想像させるスゴ技になっていて、
その地獄の匂わしは、収容所からの音声や
使用人と妻の母親の行動の描写で充分な
はずにも関わらず、
私には勇み足的に見える最終盤での
ヘスの精神への寄り添いや
現在のアウシュビッツのシーンで
締めくくってしまった編集だ。
ヘス夫婦の、ある意味トンチンカンな悩み
が、この映画の肝なはずなのに、
多分に、この結果がこれだけの犠牲者が、
と言いたいのだろうが、
最後の最後までヘス家族の
日常生活で終えてもらった方が、
より犯罪への人としての“無関心”さが
浮き出たように感じる。
さて、現在においても、
プーチンロシアを見ても分かるように、
我々が最高指導者に間違った人物を
置いてしまったら、
異議申し立ても不可能な中で
その権力に従属せざるを得ない社会を
生んでしまうとの教訓を得るべきで、
アイヒマンやこの作品でのヘスが
どうのこうの言う以前に、
権力者が生まれると、彼を信望する
“思考停止や凡庸さ”を兼ね備えた者たちに
我々は支配され、
悲惨な社会状況になってしまうことを
肝に銘ずるべきなのだろうと思った。
強制収容所所長の日常
こう聞くとゾッとするかもしれないが。
"彼"とその家族の目線から見ると、実に平和な日常が広がっていた。
ホロコーストを実行していたのは残虐な殺人鬼でもなければ悪魔でもない。
紛れもない人間。
それも我々と何一つ変わりない普通の人間だと言うことが分かる。
逆に言えば誰でも加害者にでも被害者にでもなりうるという事。
そして人々の無関心がそれを助長しうると言う事。
この普遍的事実をセリフや映像ではなく"音"で突きつけてくるアプローチは実に新鮮だった。
これはかつて被害者であったユダヤ人達が、今や虐殺する側になった現代にも非常に重なるものがある。
正直な所、映画としては実に退屈だ。
眠気を誘うシーンばかり。
しかしその"無関心"こそ危険だと言う事に後から振り返り気づくとゾッとするのだ。
決して面白い映画ではない。
でもこういった映画も必要なのだと思う。
無関心でいる人々に関心を持たせる為に。
隣は地獄なのに・・ザ・ギャップ
アウシュビッツの映画なので気が重く観るのを躊躇していた映画。ところが観始めるとホロコーストの惨状は全く描かれず収容所の隣で豊かに暮らす所長一家のホームドラマ風、これは数あるホロコースト映画の中でも異例ですね、恐らく大量のユダヤ人虐殺を行ったアウシュビッツのことは有名なので観客がそれを知っている前提で、真反対の平凡な家庭生活の世界を描くことで別の意味での人間の怖さを表現しようとしたのでしょう。
タイトルの「関心領域」は隣人たちの心理表現かと思ったらナチス親衛隊が強制収容所群一帯を表現するために使った言葉だそう、隣の所長の豪邸は実在したそうだ。
冒頭から3分近いブラックアウト画面や奇妙なモノトーンの夜のシーンなど撮り方も個性的、優劣はともかく、作家性が強すぎて難しい映画でした。
面白くは、ない
今までにないタイプの映画
この映画を事前知識なしで見る人はほとんどいないと思いますが、この映画は説明0の状態で始まり、最後まではっきりとした説明がないまま終わります。
なので本当に事前知識0で見ると面白くないのではないでしょうか?
最低限「アウシュビッツ強制収容所の隣で暮らす一家の日常」という知識は必要です。
通常の映画は目に映るものを楽しむ・耳で聞こえるものを楽しむということが基本ですが、本作では「目に見えない塀の向こうを想像する」「聞こえてくる音声からそれが何の音か想像する」という通常の映画とは全く違う楽しみ方をする映画です。
正直娯楽作品としては楽しみにくい作品ですが、考えさせられる作品としてはめちゃくちゃ素晴らしい映画だと思います。
「関心領域」という邦題も素晴らしいですね。「あなたは塀の向こうに関心がありますか?」という問いかけにも思えます。
無関心であることの恐ろしさを容赦なく暴(あば)き出す
<映画のことば>
「現実を受け入れて、ここを離れよう。」
「嫌よ。あなた一人で行けばいいわ。
あなたは、オラニエンブルクで仕事を。私はここに残って、子供たちを育てる。今までどおりに、アウシュビッツでね。」
「まさか君が来ないなんて。思いもしなかったよ。」
「あれが、私たちの家なのよ。」
世にも恐ろしい虐殺行為が白昼に堂々と行われていたというアウシュビッツというその土地柄…壁一つ隔てた隣では、ユダヤ人に対して歴史に残る大虐殺が行われている、その土地柄で、無邪気にも(?)住まいに固執する、ヘス収容所長の妻・ヘートヴィヒの言動が、評論子にはむしろ不気味にも思われました。
自宅の、ほんの隣では世界史に残るような大量虐殺が行われているというのに…(絶句)。
しかも、ヘス家に集う彼・彼女たちは、ヘス家から塀ひとつを隔てた、すぐ隣では何が…どんなことが行われているかは、知らないわけではなかったようにも見受けられます。
そのことは、家政婦から嫌がらせをされたと思い込んだヘートヴィヒが家政婦(おそらくは送られてきたユダヤ人の中の一人)に向かって「夫に頼んでお前を灰にして、あちこちに撒き散らしてやるから」と悪態をついていたことからも明らかだと、評論子は思います。
無関心でいることの「本当の恐ろしさ」は、ここに極まったとも言うべきでしょう。
本作を観終わって、まず真っ先に評論子の脳裏に浮かんだのは、ドイツの神学者で、反ナチス活動家としても知られたマルティン・ニーメラー(1892-1984)の次の言葉でした。
「ナチスが共産主義者を連れさったとき、私は声をあげなかった。私は共産主義者ではなかったから。/彼らが社会民主主義者を牢獄に入れたとき、私は声をあげなかった。私は社会民主主義者ではなかったから。/彼らが労働組合員らを連れ去ったとき、私は声をあげなかった。私は労働組合員ではなかったから。/彼らが私を連れさったとき、私のために声をあげる者は誰一人残っていなかった。
人は、自らの「関心領域」の外側で行われていることには、まったくを以て無頓着であるという箴言としては、本作の標題は、まさに「そのものズバリ」というべきだとも思います。
そして、そのようなストーリーをドラマ仕立てや劇映画タッチで描くのではなく、ドキュメンタリータッチで、ただ淡々と事態の推移を描いていた点も、構成としては、高く評価できる…否、むしろドキュメンタリータッチで淡々と描かれているからこそ、無関心でいることの本当の恐ろしさが、容赦なく暴き出されていたとも思われます。
本作は、評論子が入っている映画サークルが、毎年選定している年間ベスト作品として、2024年の公開作品として選ばれていた作品になります。
地方都市に住まう評論子にはなかなか鑑賞の機会がありませんでしたが、ようやっと宅配レンタルで観ることができました。
年間ベストに相応しい、重厚な作品で、充分に佳作としての評価に値する一本でもあったとら評論子も思います。
(追記)
先程は「人は、自らの『関心領域』の外側で行われていることには、まったくを以て無頓着である」と書きましたが、これはもちろん、自分の関心領域外で行われていることは知らない(無関心)ということで書いたのですけれども。
しかし、他面では、ヘートヴィヒは「何が行われているか」は知ったうえで、その「知っていること」を意図して関心領域の外へ押し出しているとしたら、それは、まったくの「関心領域」外よりも、数十倍、いや数百倍も空恐ろしいことと思います。
本作のタイトルには、実は、そのダブルミーニング(?)も隠されているのでしょうか。
(追記)
音だけ聞こえてで、映像がないシーンから始まるという本作の構成も、作品の組立てとして、秀逸だったと、評論子は思います。
音がするので、上映が始まっていることはわかるのですが、「絵が出ないということは上映機器(DVDデッキ)の不具合だろうか」と、観ている方を不安にさせる手法は、作品全体に漂う不気味さを、いやが上にも盛り上げる演出として、当たっていたのではないかと、評論子は思います。
(追記)
作中で言及されているヘンゼルとグレーテルの寓話…パン焼き窯でグレーテルを焼こうとした魔女は、ガス室で殺害したユダヤ人の遺体を焼
却炉で焼却したドイツ軍の暗喩だったと、評論子は受け取りました。
(追記)
本作に登場する人々の「関心領域の狭さ」は、取りも直さず彼・彼女らの「心の闇」ともいえると、評論子も思います。
そして、当時のナチスの「エリート意識」「独善さ」「近視眼さ」ということは、別作品『ヒトラーのための虐殺会議』にも描かれていたとおりで、彼らの心にはそういう「闇」が根深く巣くっていたことには疑いがありません。
的確なレビューでそのことを再認識させて下さったレビュアーNOBUさんに感謝するとともに、末筆ですが、ハンドルネームを記してお礼に代えたいと思います。
関心
観逃していた作品、ようやく。
個人的にこの「領域」への関心は高く、堀を隔てたこっちとあっち、180度違っていたことが衝撃だし、怒りも。
よく無関心であんな贅沢な暮らしが出来たな、と腹立たしい。
ヒトラーだけでなく当時のドイツの一般人も同罪な気がしてくる。
という感情を持たせることが本作の狙いだった?
最後に出てくる収容所の記念館?
何万足もの靴、幾つもの鞄が展示されているガラスを黙々と磨くスタッフもまた無関心にも見えてくる。
忘れてはならない、後世に残すべき歴史。
だけど記憶と共に薄れる感情のコントロールは難しいことを痛感する。
人間、自身の利益には目ざといが
アウシュビッツものというよりも、人間の不思議が先立つ。
同じものを見ても抱く感想が異なるように、残虐の極みを躊躇なく合理的に処理し、行われていても理想郷とのたまう。
だから自らの身体の変調の深刻さもスルーなのだろう、たぶん。
けれどこれはアウシュビッツに限らず、世界のどこかの地域と地域としても置き換えられそうだし、実際、無関心と無視、搾取していることも多い。
人は自身の利益には目ざとく関心、執着を持つが、その向こう側にまで想像を巡らせる事は苦手だ。巡らせる事で自分が利益を失うならなおさらあえて目をつむる。だからして、うしろめたさを思い起こさせる1本でもあった。
何となく向こう側がすけているのに、気づいているのに自分可愛さにスルーしてしまう。
昨今のそれが巨悪なのかも。
ネガのような加工がされたシーンが印象的。一番野真実描写なのに非現実的感が脳みそバグらせる。
愛の反対語は無関心です (マザー・テレサ)
隣の家のおじいさんが室内で倒れていて、救急車で運ばれた。去年の夏だ。
40℃の猛暑でも、「電気代はつけっぱなしでも月2000円で済むから大丈夫なんですよ」と、どんなに言ってもエアコンをつけなかった生保受給者だった。
あれほど市役所や包括支援センターに出向いて、あの暮らしぶりと現場のゴミ屋敷の有り様を見に来るようにと訴えたのに。
で、「搬送先ほかは個人情報なのでお教え出来ません」と福祉課で突っぱねられてしまった。そうでしょうね。はい、そうでしょうとも。
隣は何をする人ぞ。
人も職員もこんなにいっぱいいても「関心領域」とはこんなものなのだ。
・・・・・・・・・・・・・
「アウシュヴィッツ絶滅収容所」の塀の隣にはエリート所長の官舎があった事は「縞模様のパジャマの少年」でも描写されていたし、現にその邸宅は今でもそのまま保存されていて見学コースになっているらしい。
5月8日はドイツの無条件降伏の日。
ドイツ・ヴァイツゼッカー大統領の1985年のその日の演説
「荒野の40年」を読み返してみたいと思う。
「過去に目を閉じる者は現在においても目の見えない者になる」
「若い人たちにお願いしたい。他の人びとに対する敵意や憎悪に駆り立てられることのないようにしていただきたい。敵対するのではなく、たがいに手をとり合って生きていくことを学んでほしい。われわれ政治家にもこのことを肝に銘じさせてくれる諸君であってほしい...」と敗戦の記念日に大統領は呼びかけた。
塀を乗り越えようと語りかけたのだ。
・・
そのドイツには「つまづきの石」というプロジェクトがある。
歩道にわざと邪魔な凸凹を付けて、あれは通行人の足を止めさせるわけで。
銘板には
【○年○月○日、ここに住んでいた なにがしは、ドイツ軍に連行され○○収容所で殺された】と刻んであるのだと。
つまづきの石は「バリアフリー化に逆行する」“突起”であるし、「素通りと忘却を阻止する」棘トゲ だ。
目を止めて、その小さな「塀」を乗り越えるために通行人は何かをしなければならない。
よけるか。躓いて転ぶか。立ち止まるか。またぐか。しゃがむか・・
無言だが、忘却を妨げる「つまづきの石」。
ドイツ人にとっての、我が身を貫く痛みのプロジェクトだと思う。
「壁」は、
本人次第なのだ。
広くも狭くも好きに出来る。
高くも低くもあなた次第だ。
目をつぶれば壁は簡単にそこに立つのだ。
・・
「はて?私の『隣人』とは誰のことでしょうか?」
ユダヤ教の指導者が自分を弁護しようとして質問したエピソードは
ルカによる福音書10章25節から37節に。
実話ベースということが1番の恐怖
ねむい!
無関心の罪
愛の反対は無関心とマザーテレサは言った。
アウシュビッツで起きていたことを子供達もなんとなく分かっているが、無関心を貫いている感じが人間の関心とか感じ方って意識しないと通過してしまうんだと感じた。
壁一枚を隔てたアウシュビッツの豪邸に固執する妻に狂気を感じるのか、今も虐殺が行われているガザから離れて暮らしている我々はどうなのか、
それは距離の問題なのか
今のアウシュビッツの清掃をする人々はガザに思いを馳せているのか、
身近に戦争や虐殺がある人のみが関心を持つことなのか、当事者の方が変えられないことがあるのだから外部の人間が関心を持たなければならない
a24は応援しないといけない
新しいかたちの反戦映画
全571件中、21~40件目を表示