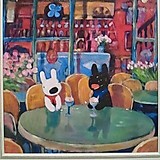君たちはどう生きるかのレビュー・感想・評価
全763件中、21~40件目を表示
タイトルなし(ネタバレ)
壮大な夢をのぞいてるようだった。
所々宮崎駿監督の過去作品を彷彿とされるキャラクターや情景が散りばめられていた。どこか懐かしさもありつつ楽しんで視聴した。なんといってもチャーミングなインコとふわふわなわらわらが可愛い!
父が母の妹と結婚し、既に子供もいる状況って受け入れ難いよなぁ。夏子さんも眞人に寄り添おうとするけれど、他者から見ても疎ましく思われてるよねとおばあちゃん連中に噂されていて。
お父さんもお父さんでいい人なんだけれど、ちょっと嫌な雰囲気が漂っていて。
疎開先では友人関係もうまく行かなくて苦労していた。
ひょんなことから青鷺に誘われて下の世界へ行き、新たな人や生物との出会いを果たす。そこで出会った人たちとたくさんのコミュニケーションを交わし、困難を乗り越えていく。その道程で眞人の心も大きく成長していく。
終盤の夏子さんに初めて母さんと呼び自ら手を差し伸べる強さと下の世界の後継をしないとキッパリ伝える逞しさには感動させられた。
眞人にとってはとても大きな冒険でそこで出会ったみんなとの思い出は少しずつ記憶から消えてしまうんだろうけれど、青鷺と友達になったこと、若かりし実母との出会い、生命の繋がりなど、ずっと胸に刻まれるんだろうなぁ。
やっぱりジブリは素晴らしい。理解が及ばない部分もあるけど、そこはきっと想像の余地を残してくれているのだと思う。何より物語の展開も非常にのびのびと、どうなっちゃうんやこれという感じだったけれど好き放題やってくれていて良かった。物語とはこうでなくでは。
今を生きるに値すると思わせてくれる素晴らしい映画だった。
見えてくる世界 瓦解崩壊
米津玄師さんの地球儀に惚れ込んでいながら、今作は未鑑賞というたいへん失礼な状況!すぐさま地上波で観ました。
実はリアタイで観たんですが、すぐにレビューできなかったのは理由があります。
鑑賞後すぐの感想を書くならば
「?」で完結してしまうからです。
いろいろ考えさせられ…そうになり
うわぁ!と感動し…そうになり、頭の中で蠢くなにかはあるものの、極論言えば「?」に行き着いてしまう感覚に襲われたからです。
数日間様々な方のレビューや、ブログで考察している方、さらには岡田斗司夫さん(禁忌)にも手を出し、
ようやく世界が見えてきました。
宮崎先生本人の物語であること。
異世界での出来事は先生の人生を体現していること。
他諸々めんどうなので書きませんが自分なりの答えは見えてきました。
見えてきましたが、やはり所々の、他の方のレビューに言わせるなら脚本の矛盾点や乱れた筋書きが、ぶつかってくる。
よって、
さいごのインコの城の崩壊のように、
思考が瓦解崩壊したので今レビューしてます。
結局求めてるものがちがったのかも。
幻想的な映像とか、怪我をしたペリカンの描写とか、もうすごいな、としか言えない部分もたしかにあります。
が、異世界に落ちたマヒトに僕が求めていたのはきっとラピュタのような活劇だったのかもしれません。
でも、たぶん、きっと、また大人になってから観ると変わってくるかも。
いっぱい人生経験を積んで、あらゆるモノの表と裏を知ってから観るそのときを、今から楽しみにしておきたいですね!!
なので今の評価は3.5です。次観るときどう感じるか?
次観るときのために、今からどう生きるか?
今作の評価が5になるくらいの人生、どどんと生きていきたいですね。
とにかく美しくて、魅せられます。
公開当時まったく宣伝しないという手法が話題になりましたが、その後の盛り上がり、各賞受賞などさすがは宮崎監督、さすがはジブリと思い気にはなりつつも観てはいませんでした。GW、このタイミングでの地上波放送、日テレさんに感謝です。
個性豊かなばあたち、ワラワラなどかわいいキャラの目白押し、手書きなのに青サギはじめ生き物たちの動きのリアル感、その色彩の鮮やかさなどに圧倒されます。
CG全盛のこの時代だからこそ、この手書きのアニメーションの尊さは、実写で言えばトム・クルーズの体当たり演技にも繋がると言うか、やはり説得力が違います。
もちろんCGも好きなんですがハラハラ感が違うと言うか。。。
久石譲さんの音楽との心地よさも相変わらずで映像との相性バッチリです。
聴き心地の良いあいみょんさんの声ですがちょっとセリフ回しの単調さが気になったのと、2時間超えの作品ながら一気に魅せられたのですが、結局監督が何を描きたかったのか、何か腑に落ちないと言うか、ちょっとモヤっとしました。
とは言え劇場で観た『千と千尋の神隠し』同様、エンドロールに入って主題歌のイントロが静かに流れると何か込み上げてくるものがあり自然と涙が頬を伝ってきました。
「宮崎駿、恐るべし」とあらためて強く感じると同時に、監督から「君たちはどう感じてどう捉えるか」と問われている気さえさせられました。
受取り方は人それぞれ
直後の感想は難しいの一言です。が、実母の妹を継母として受け入れるまでのお話。主人公は自分で現実世界に戻ることを選択。大叔父さんのように理想を追い求め現実から逃避する世界ではなく、悪意ある現実世界で生きていくことを選んだのだ。
鬼才復活 ネタバレあり
訳がわからないとかストーリーが分からないという感想が多く見受けられるがそれだけ日本人の想像力が乏しくなったという事。
昔はゲームにしてもアニメや童話、小説や映画でも訳がわからないところを想像力で楽しんだり補正したり補う空想力で楽しむのが醍醐味だったのに、CGや3D、リアルさばかりを追求されたメディアや駄作に囲まれてわからないものを楽しむ人間の想像力を失ってしまった。
退化した人間、それこそが外の世界へ出て知性を失ってただの鳥に戻ったインコ達のようなもの。
基本線は宮崎駿の人生と子供時代の体験と空想。子供の頃の空想力は感覚で感じた世界をイメージであの映画のようにどんどん広げていく。
大叔父とは高畑勲がモデルであるとご本人が明言しているが、高畑を失った宮崎駿の作品は今作含めあの頃のジブリの名作では無くなっていく。高畑が生きていたら今頃どんな作品作っていたかな?など想像して映画を見たらそのキャラクターが高畑勲だと。
宮崎駿ご本人もきっとそれを感じ考えていたのだと思った。
宮崎駿と久石譲の傑作、風の谷のナウシカですら高畑からすれば30点。
作品を社会的で歴史や現実と整合性を整え哲学的な主題の筋を整えるのが高畑の哲学であり役割だ。
知性を与えられた鳥達はもののけ姫の動物のように知性を持ち大叔父に与えられた仕事を遂行しながら食べさせられていた。
それがスタジオジブリも意味しているのかは分からないがその世界は平和で守られ世界が破綻しない均衡のとれた世界で、戦争からも守られていた。
あえてその世界を壊して飛び出していく主人公。
これは完全に原作ナウシカのナウシカに見えた。
均衡を整えるための墓所の主や文化を守る庭園のヒドラが大叔父、その主が世界を守らせるために選ぶ皇帝がインコの王、ヒドラや博士や喋るシカが鳥達、森の人やユパのかわりにキリコがいる。歪んだ愛情から真の愛に変わる夏子はクシャナとトルメキア王と母、
そして墓所を破壊したナウシカと巨神兵が眞人とヒミ。眞人を守る老婆は大婆やミトたち。
大叔父は宮崎駿にとっても作品の整合性や均衡を守る人であると同時にそれは大人の悪意であると感じていた。本来の駿はミヒャエル・エンデのように想像力全開、子供の空想力全開のわけのわからなさが面白い楽しめる作品をつくりたかった。だから高畑勲を失った事で世間からは駄作といわれたり訳がわからないと言われるようになるが、それこそが自分達の意思で生きれない人間は人間ではないという駿の生き様、哲学の現れ。世界を壊す事になっても与えられた仕事に従事してバランスをとるのではなく自分の意志で冒険をすべきだというメッセージ。
どう生きるか?高畑勲と宮崎駿、少年時代に出来ていた自由な空想、戦争から逃れて描ける冒険の不思議な世界。周りの人達、母親と父親、宮崎少年。
宮崎駿は自分はどう生きたか、行きたいかを改めてこの作品に映したのだと思う。
色々な作品のモチーフや想起させる世界、キャラクターは集大成だったしワラワラはコダマからトトロに変化する過程の中間の存在にも見えた。
宮崎駿の空想力の感覚がナウシカの頃の鬼才、若さに戻ったようにも感じたし久石譲の音楽もやり飽きてつまらなくなった駄作からナウシカやラピュタ、もののけ姫の頃の尖った感覚を取り戻しながら円熟や進化の先にある無駄がなく美しい作品だった。
久石譲にとっても一つの極み、集大成に
なった感覚があると思う。
そして肝心のアオサギは道化師。ナウシカやラピュタやもののけ姫ではクロトワやドーラ一味やジコ坊のようにちょっと悪くて悪意があるけどドジで主人公達を導く道化師のような大人が出てくる。
これが鈴木敏夫なのか誰なのかはわからないけど、悪意のある大人との付き合い方や時に助けになる存在もまた宮崎作品の肝の一つ。
この作品に感じた印象は2人の鬼才復活だった。
鳥嫌いになりますね
子供向けなのだろうが果たして子供たちは何を思うのだろう、恐らく鳥が気味悪く嫌いになってしまうだけの映画ではなかろうか。おじさんが観てもさっぱり分かりませんでした、戦時中と言う設定だから、反戦映画かと思ったがそうでもなく宇宙から来たエイリアンの謎の石が作り出したらしいマルチバースの奇妙な世界で行方不明の継母を探す真人の冒険がダラダラと続きます、2時間越えはちと長すぎます・・。兎に角、作家性が強すぎて、話題作ではありますが今までの名作に比べると独りよがりの難解な冒険ファンタジーでした。
タイトルなし(ネタバレ)
追記
主人公の男の子が自分の頭を石で殴ってけがする場面。
男の子の利発さ図太さ只者でないのが表れてる。
田舎の学校じゃ異物の自分はぼこぼこにやられる。父も見当はずれで真の味方ではない。だから自分に致命傷的傷(痛々しい)を与えて学校に行かされるのを避けたのだ。
いい映画だった。予想以上。思い出のマーニーなどの米林監督、息子吾郎監督の作品や宮崎監督自身の過去作などその他をいろいろ連想した。もちろん欧米の児童小説の世界やアンデルセンや雪の女王なども。
異世界へ飛び込み旅をする。相棒と最良の友達になる。良きアドバイザーと出会う。私は見飽きなかった。
目新しく感じたのが、主人公の男の子がえらく利発な感じだったこと。
もう一つ、主人公の父親が爛れた雰囲気だった。伊藤英明かと思ったがキムタクが声優をしていた。キムタク恐るべし‥‥。魅力的だし、存在感ある。宮崎監督にハマったから、再度、起用されたのだろうか。すごいね、ジャニーズって。
さらに主人公の母がなまなましく美しい。
ディズニーにはないと思う、この映画のような余韻。あらすじに縛られてないからこその良さ。最高級の画力に裏打ちされたイメージがおしげもなく連投される。
ゲド戦記で感じたが、この世を良くしている正義は、地味でかっこわるいぐらい地道な目立たない努力によってささえられている。この映画にもそれを感じた。
宮崎監督自身の人生のストーリーから想起した映画なら、大量のオウム達(大衆のことかと思ったが、他のレビューを読んで思い直した。一緒に仕事している仲間のことだ。)相棒アオサギやキリコやその他は仕事仲間。主人公は監督自身。自分の宿命と向き合いながらコツコツと誠実にアニメを作ってきた、人生をささげてきた。娯楽消費者の考える想像以上、膨大な労力をアニメ制作は必要とする。
感想ですが
ハウルの動く城、千と千尋の神隠しなどを取り込んだそんな感じの映画です。宮崎駿の集大成が詰まった映画なような気がしました。
今まで見てきた崖の上のポニョのような海のシーンや荒地の魔女のような登場人物もののけ姫のような感じの動物の変化
もののけ姫の森の中の生き物に似たような内容よくわからなかったけど声優の声など色んな方がやられていて楽しめた
「母の不在」への直面とその超克。
劇場公開時に観た時には、「さてどんな出来栄えだろうか…」という心持ちで劇場に足を運んだこともあって、十分に本作の素晴らしさを享受しきれなかった感じがした。再鑑賞できないままBlu-ray発売となり、やっとの2度目。作画の素晴らしさ、散りばめられたシンボル的な表現、そして何より宮﨑駿が過去作でも繰り返してきた「母の不在」のモチーフを初めて正面から取り扱ったこと。心を打つ要素は多岐にわたる。
主人公の名前が「眞人(まひと)」というところから既に意味深で、真(まこと)の人であるとはどういうことなのか?という含みが感じられる。戦時中、母の死を契機として自分の周りの世界が受け入れ難いものになっていく。「母の不在」→「世界の拒絶」という構図がまず示される。継母になる人を受け入れられず、転校先の学校からの拒絶と、拒否の意思表示としての自傷を経て、継母が塔の奥へ隠れるところまで至ってから、青サギのいざないによっていよいよ“向こう側”へ踏み込んでいく。塔はその“向こう側”へのポータルになっているのだが、この“向こう側”は完全なる「彼岸」というよりは、「中間」(『チベット死者の書』の言葉を借りれば“バルド”となるか)のように私には感じられ、私たちの合意的現実が生まれる一歩手前の領域という感じだ。青サギ・ペリカン・インコといった鳥たちが多数出てくるのは、鳥は古くから地上界と天上界の橋渡しをするものの象徴なので、まさに中間の存在と言って良い。
ちなみに継母が“向こう側”に隠れたのは、眞人の継母になること(合わせて勝一の後妻になること)を心から受け入れられずに現実世界から退避したということ。ただこの行動が入り口となって、結局はこの母子がきちんと親子になるためのイニシエーションが展開されることになったようにも見えるのがポイントだ。その遥か昔に、大伯父も現実世界から退避して塔の奥に引き籠っているが、「悪意のない純粋な世界を作りたい」というのがその動機であるようだ。ピュアでなどあり得ない現実世界を受け入れられない彼は、クライマックスで眞人に自分の仕事を引き継ぐよう迫る。しかし、眞人は拒否し、現実世界に回帰することを選択する。それは、“向こう側”で様々に経験したことが眞人を変え、受け入れ切れなかった現実世界を受け止める準備が整ったからだと言える。眞人も継母も現実世界に戻り、文字通り「家族」となって終幕を迎える。
以上が、物語全体の流れと大枠の構造であるが、「訳が分からない」という反応がかなりあるようだ。それは、過去の宮﨑駿の作品と比して、親切な説明を排し、ユング心理学で「元型」と呼ばれるような次元でのシンボリックな表現の積み重ねで物語ろうとしているからに他ならない。眠っている時に見た夢の意味が分からなくて悶々としたり、その意味を考えないでいられなかったり…そんな夢見のあとのような気分で、この作品鑑賞後にあれやこれやと反芻して思いを巡らせるのが正しいような気がする。
これは恐らく、大衆向けの娯楽作品を狙ったというより、宮﨑駿個人が自らの内に疼くテーマを掘り下げるために撮った、極めてパーソナルな作品だろうと思われる。こんな作品も大いに歓迎したい。キャリアの終盤にこんな作品を作ったっていいだろう。もう十分過ぎるほどにアニメ製作者として、大衆に貢献してきたのだから。
少々分かりにくいかもしれないが、豊かなイマジネーションの海に揺蕩うことを楽しむことさえできれば、素晴らしい鑑賞体験になるはず。変にジャッジしようとせず、作品世界に浸ってみることをおすすめする。
炎はループし飛びつづける
未来少年コナンに夢中になって以来、なんだかんだずーっと見続けてきた宮崎監督作品。「もののけ」以降は好き嫌い半々位、という程度のオタクですが、宮崎さん高畑さん(大塚康生さんも)の映像群はもうほぼ原風景というか。
開始1分で「あぁ、馴染んだやつを見ている」という沁み入るような感覚をおぼえ、前半のテンポも音も抑えた静かな展開、後半の「ハヤオてんこ盛り」スペクタクルも楽しみました。
面白かったという以上に、自分の内部に何か沸々と湧くものがありました。
鑑賞してから1年以上たち、レビューもいっぱい読んだのですが、特にマヒトの父母と叔母ナツコの関係性について言及してるものに当たらなかったので、今更ですが記しておきたいと思います。あくまで私見です。
亡くなった妻(夫)のきょうだいとの再婚は、現代の感覚からするとトンデモでも昔の日本にはよくあった風習、というのは色んな方が書かれてましたが、あと1つ、「姉妹なら姉のほうが先に結婚しなければならない」という暗黙のルールみたいなものも、昭和には普通にあったんですよね。
ヒサコとナツコ姉妹の場合も、縁談は当然先に長女にきて、しかしマヒトの父に「恋していた」のは妹のナツコのほうだったのでは、と推測しました。
ループする炎の少女であるヒサコは、「マヒトを産む」ために結婚、夫に対してさほど気持ちは無かったんじゃないかなぁ、となんとなく思いました。
清々しい炎のヒミちゃんが作中最も魅力的で、あまりにアッケラカンと晴れ晴れしてて、作中の時制がどうあれ、現世には拘りや未練が全く無さそうなんですよね。
マヒト父、別に悪い奴じゃないけど家父長野郎パパガイバーという感じがあんまり…だったので、少女のヒミちゃんがマヒト父を全く気にかけてない感じがむしろヨカッタ(笑)ですし、「子供に対する母親の愛情に、父親はあんま関係ない」と言い切られたようでもあります。(父と子にはまた全然別の関係性がある)
普段、1番見ないジャンルが「恋愛もの」でラブの機微には疎いほうですが、この映画に限っては、宮崎作品には割と珍しいエロスのある「父と後妻」と、思春期以前の姿で縦横無尽に飛び回る「母」があまりに対照的?で、そんなことを考えてみました。
わかりたいタイプの人には不親切な作品だったかと思いますが、全体通しての隙間やいびつさを私は楽しみました。クライマックスから着地が尻すぼみ気味なのもハヤオ通常運行と思いましたし まだ作りそう、とも。
悪くはないけど
前評判を聞いてたからある程度は覚悟してみたけど、やっぱりこういう現実的なストーリーが無くて、観る人に委ねる系の感じで進んでいくのね。
作品として悪くはないけど、忙しいのに時間をなんとか作って観たい!って感じではなかったかな。
僕たちはどう読み解くか
キービジュアルと公開日の告知以外、予告編なし、ストーリー情報なし、キャスト発表なし、パンフレットの販売すら公開日当日ではなく後日発売という徹底した情報のシャットアウトぶり。
“ジブリ”“宮﨑駿”という一大ブランドだからこそ成せる力技と言えるし、プロデューサーの鈴木敏夫氏のこの強気な姿勢に非常に好感が持てたので、初日の昼IMAX版上映回にて鑑賞。
そんな一切の情報が与えられていない状態で本作を鑑賞する中で、最も理解の手助けとなったのは、監督の前作『風立ちぬ』だった。あちらで二郎とカプローニが会話する場所が、ダンテの「神曲」に代表される、現世とあの世の中間“煉獄”でのシーンであると考察されているが、今作はまさしく、宮﨑駿版「神曲」だったのではないかと思う。
作中でペリカンが語るように、あそこは“地獄”であり、あの世なのだ。
大雑把なあらすじとしては、舞台は第二次大戦中の日本。空襲によって母を喪った主人公の眞人は、父と共に東京を離れ、田舎町で父の再婚相手で亡き母の妹でもある継母と生活する事に。そこで出会った不思議なアオサギによって、眞人は継母を救う為に地獄巡りの旅へと誘われる。
物語のメインとなるのは、この継母を救う為の眞人の地獄巡りと、そこで自分の中の悪意、この世の悪意と向き合い、最後の選択を迫られるというものだが、途中、複数の世界へ通じる無数の扉が登場するシーンがある。
あれは、昨今流行りの多元宇宙論(マルチバース)ではとも思える。我々が空想する“もしもの世界”には、この世ではなくあの世で繋がっているのだと捉えると面白い。
作中、可愛らしい見た目の“わらわら”というキャラクターが登場するが、あの世の住人キリコは、わらわら達が「(これから人間として)生まれるんだよ」と語る。
もしかすると、Aという世界で生まれた人間が死後わらわらとなり、Bという世界で新たに生まれる事もあるかもしれない。輪廻転生は必ずしも同一の世界のみで起こるのではなく、よく都市伝説等で語られる前世の記憶とは、違う世界での前世かもしれないとまで考えを巡らせるのも楽しい。
わらわらが無数に空へと浮かび上がり、生命の二重螺旋構造的な螺旋状で上昇していく様はメタファーとして分かりやすいが、もう一つ、わらわらが白く可愛らしい見た目をしている点は、「生命は生まれた時点では罪も悪意もなき無垢なる存在である」という監督の性善説の肯定とも受け取れる。
また、あの世にて行方不明となった曾祖父が、積み木によって世界のバランスを保つという役割を担っていたが、あの石で出来た積み木は、我々の現実世界の象徴だろう。積み木=罪木なのだ。
実際問題として、この世界には大小様々な悪意が満ち溢れている。世界的に見れば、今も戦争、暴動、略奪があり、日本だけで見ても若年層の自殺率の高さ、SNSでの誹謗中傷、一部権力者や雇用者による人民の搾取と、誰しも1つは心当たりのある悪意があるだろう。眞人の頭部の傷の嘘や、彼を村八分にしようとした学生達だってそうだ。誰しも大なり小なりの悪意を孕んで生きている。
そんな悪意に満ち溢れ、崩壊しかかっている世界を唯一救う術が、穢れなき石だけの積み木で、新たに世界を構築する事だ。
しかし、眞人はそれを拒む。自らも頭部の傷を偽った悪意があり、だからこそ、自分は元居た悪意ある世界へ継母と共に帰っていくと。
物語だからといって、安易に理想郷を組み上げたりはしない監督の意思が、個人的には嬉しい。なぜなら、我々はこの悪意に満ちた世界で、それでも今日を生きなければならないのだから。だからこそ、ここでタイトルの『君たちはどう生きるか』に繋がるのだと思う。
あまりにもシンプルな、しかし決して避けては通れない問題を、監督は引退宣言を撤回してまで、(恐らく最後に)我々に問い掛けてきたのだ。
勿論、アニメーション表現の豊かさは健在だ。冒頭の空襲シーンで、眞人が階段を四つん這いで駆け上がる描写、母の入院する病院まで群衆の中を疾走する描写と、開始早々のジブリ節全開なアニメーション表現に早くも「あぁ、ジブリ作品観てる!」とテンションが上がる。
避難先の屋敷で、父の持ってきた豪華な手土産の入った荷物に群がる、まるでまっくろくろすけを彷彿とさせるような動きの個性的な老女のお手伝いさん達。どこかからタバコを調達して吸う老人お手伝いさんと、宮崎作品で度々目にしてきた老人描写の集大成とも言える演出の数々も光る。
その他、恐らく全て手書きによる人物表現、日本アニメーション技術の最高峰かつ集大成と言わんばかりの表現の数々は枚挙に暇がない。
…とはいえ、では作品としてストーリーが面白いのかと問われると、面白くはない。必要最低限のワードこそ出してはくれるが、それだけでは理解出来ない箇所や、登場人物の心境の変化等に唐突感が否めないシーンも少なくはないし、抽象的だが“行きて帰る”というお得意の王道冒険ストーリーなのに終始ワクワクしなかったのだ。メッセージ性を込みにしても、宮﨑駿監督作ワーストと言ってもいいし、個人的には、前作の『風立ちぬ』で止めておいてほしかったというのが正直な気持ちである。
因みに、チケット販売開始から半日以上経っていたにも関わらず、私が予約した時点では先客はたったの3人、当日も半分にも満たない疎らな客入り。土日の集客率はまだ分からないが、Twitterを見る限りでは、あまりの情報のシャットアウトぶりに、そもそも今日が公開日である事を気付いていない人も散見され、やはり多少の宣伝は必要だったのではと思わなくもない(笑)
とはいえ、事前情報一切なしの状態で映画を観るという貴重な経験を出来た事は良かった。別作品を鑑賞しに行った際の予告やチラシ、SNSでの告知や映画アカウント等、何かしらの情報は仕入れられてしまう現代において、このような経験は最早2度と出来ないのではとすら思うからだ。
何より、恐らくこれが本当に最後の監督作になるであろう宮﨑駿監督、本当にお疲れ様でした!
<鑑賞してほしい作品でした。>
・まず書籍「君たちはどう生きるか」のアニメでないのだと気づきました。原作者が違うので当然のことですけれど、まぎらわしいタイトルの付け方だと思いました。
・本作では、生き方において、自分で考えて行動することの大切さを伝えたかったのかなと思いました。主人公の真人(まひと)が自分で自分を傷つけ、その傷を学校のせいにしたという"うそ"をついたことがありました。けれども、自分をその名にふさわしくない者と恥じ、そのときの弱虫行動をしっかり悔いて生きているというところなどに、感動しました。
・(白い積み木で表現されておりましたが)地球のバランスがくずれ始めており、これから君たち?に世界を支えて一日でも長く安定させていってほしいという思いが表現されていたと感じました。
宮崎駿が伝えたかったこととは
鳥が印象的な不穏なファンタジー。
バサバサ、ドロドロ、ゾワゾワ、グラグラ そんな不穏な擬音語が似合うシーンの連続で不思議な世界に連れていかれる。
不思議なものにフタをしたり、見ていないことにすることの方がきっと簡単なんだな。
子供の頃の不思議な経験を、生まれてくる前の記憶を、忘れる人の方が多いのは事実。そういう記憶が呼び起こされるような、私もこの世界を知っているような気がするのが宮崎作品のうまいところなのかなと思う。
あの世界はけして楽園ではなかった。バランスが違うだけ。
最後に眞人は先祖に託されようとした役割を継がず、現実へと戻った。
自らの悪なるものを忘れないと誓って。
宮崎が伝えたかったことってなんだろう。
押し付けられた、おかしな一部の世界のしきたりに囚われないで、現実を生きよということか。
捨てるのも致し方ないが、そこでもがいた経験が人を強くし、磨くということか。
財産が奪われていくことへの警鐘?また、それにこだわりすぎるなという警告?
いずれにせよ、こうして世界は、生命は続いてゆくのかと果てしない世に思いを馳せた。
宮崎がこれまでのキャリアで得、その素晴らしさゆえにどんどん膨れ上がってしまった、とてつもなく巨大な重荷。どんな思いでバランスをとろうと努力していて、持て余していて、辛くなっているのかが表現されているようにも見えた。
眞人の選んだラストが宮崎の望むことでもないような気はする。
最近、個人的によく目にする出会うものがあって、それがパラレルワールドだったり輪廻天昇だったりする。
後はそのアカシックレコードだったり、過去未来のその時間の概念を覆すみたいなそーゆー全く新しい一言的な
この作品も、その世界観が後、現実とあの頭の中って言う形で表現されてて、つながりを感じる部分が多々あった。
観る人によって変わるストーリー
ずっと気になっていた今作をやっと観ました。
初見での感想としては、まずまずと言ったところ。
はじまりから途中の方まで「ずっと何を観ているんだろう…?」という疑問でしかなく、
どこが伏線で、あとになにを回収してくれるのか、
ラストを予想しながら観ていました。
そんな中で、原作がありながらもこのストーリーを映画化するにあたり、どこから絵コンテを描き、どのように構成してゆくか、
その制作過程に興味が湧いた。
まひとが塔の世界に入ってから、あんなに生意気だったアオサギがまひとを慕っていたことにも何か意味が隠されている気がしたり。。
誰かがレビューで、これは宮崎駿監督が築き上げたジブリという世界についての物語ではないか?と書いていたのを見た。
レビューではこう。
大叔父様が宮崎駿監督で、まひとが宮崎吾朗監督、
インコのキングはジブリを軽視し否す者を模したのではないか?
大叔父様が月日をかけて作り上げた世界、積み上げた積み木を、
インコのキングは俺にも簡単にできると素早く組み立てたがすぐに崩れ、それを認めまいと全て壊した。
それこそがジブリを軽視し、壊そうとする者たちを表現しているのでは?……と。
なるほど…と納得したと共に、
そう思えば今作の中にちらほらと、これまでのジブリ作品に登場したキャラクターに似たキャラクターや演出が散りばめられていたなあと思い返した。
例えばまひとがアオサギに連れられ母に似たものと対面するシーンで、母はスライムのように溶けた。それはまるで「ハウルの動く城」のハウルが溶けた時のようだったし、
白いたくさんのワラワラは「風の谷のナウシカ」、
まひとが庭で見つけた血だらけのペリカンは「千と千尋の神隠し」のハク、
これまでどこかで見覚えのあるキャラクターや演出が確かにあった。
(白いたくさんのワラワラが宙に螺旋状に浮かび上がるシーンに関しては、ディズニー作品の「ソウルフルワールド」みたいだなと正直思ったけれど…)
真相こそわからないが、あれはどういうこと?と振り返り考察することはどこか人生と似ているような。
一度では理解しきれない難しい物語。として好きな人は大好きな作品だろうなあと思った。
ただ、これをお金を払って映画館で観ていたら…と思うと、勿体無いな。というのが本音。
面白く無い
単純に面白く無い。意味不明。
そりゃあ、考察したら色々と深い意味は有るんだろうけど、考察したいと思えるほどに興味が出ない。一度見て、意味不明だからもういいやと言う感じ。
父親の再婚相手が、母親の妹(主人公の血筋から言えば叔母)でそちらの実家がある地方へ疎開。まぁ、昔は配偶者が死んだ場合、その兄妹と再婚って言うのは良く有った話。
が、主人公は叔母をあまり良くは思ってない。が、異世界?に入り込んでしまい、終盤はいきなり叔母を「お母さん」呼び。そんな風に変わる場面無かったんだが。
相変わらず声優を使わず。豪華と言えば豪華だけど、下手な人は本当に下手。
希望の物語だった。号泣した。
以前見た時のレビューを書いておきたいと思って備忘録。
前情報で難解だという意見も多い作品だったが、見てみたらもうドバドバに泣いてしまった。
たしかにものすごく哲学的で、ストーリーとしてはおもしろい!と一言でくくれるようなものではなかったため、宮崎駿以外がこのような作品を作ったとして、世間でここまで評価されるかどうかはわからない。
ただ私はものすごく感動した。
「滅びゆくこの世界で、愛する君と同じ速度で共に歩むことすらできないが、それでも僕は前を向いて生きる」という希望の物語をみたんだ…と思ってむせび泣いた。素晴らしいものを見た。
大叔父さんから積み木を託される終盤のシーンに、この映画のテーマというか伝えたかったところを感じて涙してしまった。
もし自分だったら、こんな作品を世に残すことができたのなら、もう死んでもいいと思えてしまうのではないかとさえ思った。
あと映画全体の世界観が好き過ぎた。
画面をずっと見れる。
ムチムチの魚を捌くシーンはかなり興奮した。
理解できない人を容赦なく斬り捨てていく迷作
前提としてあくまでも私自身ジブリのファンであり、批判したり攻撃したい気は一切ない。ただ他のレビューでも私と同じく様々な疑問を持った方がいらっしゃたため、これから視聴するか検討している方々に対し私なりの意見を述べたいと思った。普段映画を見ないため、他の方に比べれば知識不足であることは自明である。そして一部ネタバレを含むため、注意していただきたい。このことに留意してレビューを読んでいただけたら幸いである。
宮崎駿監督の映画ということで見に行った。流石ジブリと言わんばかりにアニメーションはやはり素晴らしく作画もよかった。音響も良かった。しかし同時に内容面においてかなり違和感を覚えた。
まず人物構成である。主人公の義理の母の描写は正直いらないのではないかと思った。彼女がいる事で物語に感情移入しにくかったと共に一種の困惑を感じた。ずっと心に異物混入している感覚を覚えた。ジブリらしくない設定で完全な迷走だと私は考える。彼女の存在は別に居なくてもよかったし、なにより主人公が土壇場で彼女に対しての評価を掌返しする感覚は私にはとても理解し難かった。あの展開は流石に論理の飛躍が過ぎる。
また、全体的に布石が多すぎて散漫な印象を受けた。これらの要素が分かりやすく劇中で回収される訳ではないので見れば見るほど理解できず、歯痒さを感じる。
確かに概要を見ると今作は宮崎駿にとっての実験的試みであると記載されている。所謂アニメーションというカテゴリではないのだろう。芸術作品に近い位置付けなのだろうか、ある程度その手の知識の蓄積がある人を前提に作成したと感じる。(ちなみに筆者は世界史選択のため文化史などは学習済み)
ここからは意見の分かれる部分だと思うので、一意見として読んでいただきたいが、難解とは決して美徳ではない。万人にわかる必要はないが、背景知識を持っていない人を置き去りにして分かる人にだけ相手をするというある意味無責任な作品の作り方には些か疑問である。そして今回その感覚を宮崎駿の作品に感じたことは非常に残念である。正直鑑賞した後の後味の悪さは今までに経験したことないものだった。もう一度書いておくがこのレビューは決してジブリや宮崎駿に対する批判ではない。あくまでも一般人の率直な意見として参考にして頂ければ幸いである。
スルメ映画
観た直後はよくわからんってなった。
ジブリはもっとファンタジー色強めの方が好きだし。
凡人には理解できないけど、アカデミー賞を受賞したからみんな便乗して称賛してるんだなと。
こんなもん星2じゃ。
で、レビューするのにいろいろ思い返したり調べたりしてたんだけど、気付いたら星の数が増えてた。
実は天空の城ラピュタだったり、もののけ姫だったり、ハウルの動く城だったり、思い出のマーニーだったり、これまでのジブリ作品を観たことがある人ならニヤッとさせられるシーンがあちこちに散りばめられてる。
たくさんの人がいろいろと考察してて、調べれば調べるほどどんどん面白くなってくる。
ポスター1枚だけで、一切のプロモーションなしに映画を公開するとい試みもかっこいい。
あと、音楽がやばい。
地球儀を映画館で聴いた時も鳥肌だったけど、改めて聴くとじんわりと心に溶けていくような感じ。
どうやったらあんな曲が作れるんだろう。
不思議。
おそらく万人にはウケないし、誰かにお勧めしにくい映画ではあると思う。
でも、何故か惹きつけられる魅力がある。
そんな映画だった。
宮崎駿監督、よく頑張りましたね。
あなたは素敵です。
太平洋戦争中の財閥のお坊っちゃん
公開から半年以上経って、アカデミー賞国際長編アニメ賞受賞後のシネコン再上映のラストギリギリの月曜日にはじめて鑑賞しました。
貸切でした。
リアルなホームシアターでした。
アカデミー賞受賞は功労賞的な受賞だと薄々感じておりました。
焼夷弾降り注ぐ空襲で入院中の母親を失くした少年が父親とまるで古河庭園のような西洋建築の豪邸の母親の実家に疎開してくる。鷺沼駅につくとそこには母親の実妹夏子がいて、お腹には父親の子供がすでにいることを峰不二子並の超美人の本人から手をお腹に導かれて、告られる。
ガーン!
親父やるじゃねぇか。
手回しがよすぎやしないか。
夕方帰って来た父親と夏子さんは熱い抱擁に接吻。のぞき見ていたのを見つからないように自分の部屋に戻るシーンは少年の罪悪感と羞恥心を描く。塞ぎ込むのも無理はない。古い母屋には7人のお手伝いのお婆さん。まるで白雪姫と7人の小人。父親は広大な敷地に工場を建てて、戦闘機の部品を作って軍に収めているようだ。戦況の悪化を知っていて、さらに需給が見込めるとあからさまに喜んでいる。三菱?岩崎家か?その庭園には大きなアオサギがいて、喋りかけてくる。くちばしの中に酒飲みオヤジの真っ赤なデカ鼻から繋がったいやらしい歯肉に白い頑丈そうな歯がみえる。三木のり平が頭に浮かぶ。アオサギは大人になったもうひとりの眞人の意識だったのか。
正直に言いますと、見終わって、なんだかよくわからないストーリーで、支離滅裂とさえ思ってしまいました。
オープニングの設定からは母親を失くしたばかりで、その傷も癒えないうちにおばさんを新しい母親として受け入れなければならず、疎開先の学校でも周りと反りがあわないから、いぢめられて、1日で不登校。おまけに自分の側頭部を石で傷つけて結構な流血。自作自演の登校拒否の偽装工作。アオサギは何者か?下の世界ではペリカンがいっぱいいるイギリスの海岸みたいな風景、オバQやゴマちゃんみたいな白い生き物。杉山とく子みたいなお手伝いのおばちゃんがキリコっていう男勝りの女船乗りに大変身。ヒミっていう火をあやつり、ペリカンを追っ払うのが夏子おばさんの姉たから、死んだ母親だよなぁ。夏子おばさんより小柄でかわいい系だった。さらにインコの軍隊を率いる帝国の王様が大叔父。
そんなにしてまで新しいお母さんの夏子を探して連れて帰らなきゃいけないのか? 実の母親に会いたくて仕方ないはずなのに? どっちなのよって思ってしまいました。
母親が成長した眞人に宛てた一冊の本の内容も知らないし、わからないので·····
トトロ、魔女の宅急便は何回も観ていますし、好きなんだけど。だんだん難解になりますなぁ。
これは宮崎駿監督の幼少期の実話に基づく自伝的ファンタジーなんでしょうね。
父親のほうはあまり好きじゃなくて、母親の家系のほうが誇らしかったんでしょう。
おそらく自分を偽って生きることや自戒が綯い交ぜになって、辛かったんでしょうね。
財閥のお坊ちゃんのはなしだから、カンケーないっていえば、カンケーないし、まぁいいか。
全763件中、21~40件目を表示