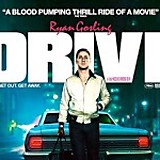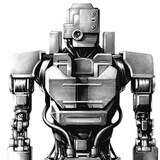君たちはどう生きるかのレビュー・感想・評価
全2100件中、1081~1100件目を表示
「自分を写す鏡」であり「風の時代」を象徴する作品 ~じっくり考察あり~
2回見ました。
●●「本作は自分を写す鏡」
岡田斗司夫さん曰く
「本作品は自分を写す鏡」
であり、自分もしっくりくる作品評です。
「内容が難しい」と感じるとしたら、普段から物事を難しく考える癖が付いている。
「内容が分かった」と感じるとしたら、普段から物事をシンプルにとらえている。
「つまらない」と感じるとしたら、「こういう展開、物語だったら面白さを感じる」という枠組みを無意識のうちに、自分の中に設定しており、それに合致しなかったから。
「面白い」と感じるとしたら、様々な事柄に対して、自ら面白さを見出してしまうから。
また
「この作品はエンタメではなくアート」
とも述べておられました。
ですので、エンタメを求めて映画を見た人からすると、物足りなさを感じ「駄作」という評価になるのかもしれません。
一方、先入観なく映画をありのまま見て感じ取ろうとする人は、十人十色のものを感じたうえで「これはこれで面白い」という評価になるのかなと思います。
その意味で、万人受けする映画ではないという評価も妥当かもしれません。
●●作品から受け取ったメッセージ
・現実を受け入れる
・運命を受け入れる
・自分の意識をありのまま反映したものが世界の姿
・自分の意識・内面ときちんと向き合う
・誰もが自分の中に、悪意、闇を抱えており、それを認めて受け入れる
・世界を良いものにするか悪いものにするかは自分次第
・人間には自由意思があるので自由に決めていい
・さあ、君たちはどう生きる?
●●感想
面白かったですし、考察自体も楽しいです。
「風の時代」を象徴するスピリチュアルな作品だと感じました。
●●シーンごとの考察1
○火事で母が亡くなる夢から目が覚めて、ベッドで涙する眞人
○亡き母からの贈り物「君たちはどう生きるか」を読んで涙する眞人
→亡き母を忘れられず、継母・夏子を受け入れられなかったが、小説を読むことで、実母からのメッセージを受け取り、夏子を母として受け入れようと心境が変化。
→だからこそ、行方不明になった夏子を探しに行き、必死に連れ戻そうとした。
○人間を食べようとするペリカン
(眞人は青鷺の羽根を持っていたから無事だった)
○わらわらを食べるペリカン
○目の前で力尽きようとするペリカンが語る下の世界の状況
→下の世界は、食べ物を得るにも事欠くありさま
→どこまで飛んでも、同じ地点に戻ってしまう無限ループな世界
→ペリカンは飛行能力すら失われつつあり、種の衰退、忍び寄る滅びさえ予感させるような絶望的状況
○殺生を許されていないため、漁ができず、キリコが捕った巨大魚のおすそ分けを待つ半透明人間たち
○狭い石造りの巣に、押し込められるように暮らす多数のインコたち
○インコ大王のお付きインコ「(果物がなる木々を見て)ここは楽園か~?(涙)」
→支配する側の大叔父だけが、天国のような生活をしており、支配される?側の大多数の生き物は、いつも苦しい生活をしている。
○宇宙から飛来した隕石
→宇宙には高度に発達した文明、高次の存在(宇宙人)がいることのメタファー
○「石」との契約
→新たな世界を創造できるようになる。
○「石」
・宇宙からやって来た
・意識を持つ
・世界を新たに創造する力を持つ
・契約を交わした人間に対し「世界創造の石」を与え、その人間はこれを使うことで、新たな世界を創造できるようになる
・その石は、最初は、善悪、陰陽などの色に染まっていない(性質や属性が何もない)
・石には意思が宿る
・創造主の意識・意思が、そのまっさらな「世界創造の石」に、ありのままインプットされ、その石はそれをそのまま世界の姿としてアウトプット…世界を物理的に形作る
○大叔父
・「石」と契約を交わした下の世界の創造主
・争いも愚かさもない、みんな豊かで幸せに生きる世界を作りたかった
・ところが、大叔父が住む領域だけは楽園になったが、ペリカンやインコなど他の生き物が住む領域は、とても生きづらい地獄のような世界になってしまった
・というのも、創造主たる大叔父の意識の中に悪意が含まれており、それがそのまま下の世界にも反映されたから
・それが地獄と言われる下の世界の姿だった
→だから、どれだけ楽園を作りたいと願い苦心しても、それが叶うことはなかった。自分の悪意も一緒に世界の形になってしまうので。
→大叔父自身も、自分の内面にある何かしらの悪意が原因で、地獄のような世界になってしまっていることを自覚しながらも、その悪意がなんであるか掴みきれておらず、これ以上どうにも改善できないことに、もどかしさのようなものを感じている
→スピリチュアルで言えば、「『統合』の必要性は理解しながらも、自分の中に潜んでいる統合すべきネガティブな感情・波動をとらえることができていない」状態
(※悪や闇は排除すべきものではなく、誰しも自分の内にそれがあり、自分の中の闇と光を「統合」することで、抑圧的で不安や苦しみに満ちた現実から、自由で喜びや豊かさに満ちた現実になっていく)
○眞人「この積み木は、悪意に満ちた「石」でできている。木じゃない。」
大叔父「その通り。それを分かる君にこそ、後を継いでもらいたい。」
○生き物(人間)を殺すための刃物を研磨機(石)で研ぐインコ
○研磨機の土台は木製
→石にはそれを利用する者の意思が宿る。つまり、石を使う者に悪意があれば、そこに悪意が宿るということのメタファー
→木は植物であり精霊が宿るので、利用する者の意思が宿ることはない、ということのメタファー(木の精霊は描かれていない)
→大叔父は、自分の血を引き、かつ、若いのでまだ悪意を抱いていないであろう眞人に、創造主の地位を継いでもらい、地獄のようなこの世界を楽園のような世界にして欲しかった。
→スピリチュアルで言えば、大叔父は、自分自身の「統合」をあきらめて、まだ意識が分離していない(=統合されている)であろう眞人に、下の世界を託そうとした
○大叔父が暮らす楽園ではばたく小さなインコを見て「ご先祖様~」とつぶやくお付きインコ
→大叔父が小さなインコをどこかの時代から連れてきて、喋るインコへと進化させた
→大叔父の人間不信ここに極まれり
○眞人「この傷は自分の悪意のしるしです。」
と自身で付けた頭の傷を大叔父に示し、やんわりと後継ぎをお断り。
→眞人は、自分にも悪意があることを公言できるくらいに、自分自身でそれを認め受け入れることができた
→スピリチュアルでいうネガティブ、闇を「統合」した瞬間
→また、血縁、家柄などに束縛されない自由意思の発露
■■大叔父の悪意とは?
○「愚かな鳥よ」と青鷺に言い放った心
→他の存在を蔑み、差別し、自分のほうが優位な存在であるとみなすその心
→軽蔑や優越感は、「相手は間違っていて劣った存在だが、それと比べて、自分は正しく優れている」という自己肯定感を歪んだ形で感じたいという心理の表れ
→「どうせ自分なんて…」という劣等感や無価値観、自己否定や自分を卑下する心理の裏返しでもある
→差別は、「自分は清いが、相手は汚れている」という一方的な決め付けであり、嫌なもの不快なものは排除したいという穢れ意識の表れ
→親族以外の人間を招き入れないのも穢れ意識の表れ
→「鳥は下等」とみなすその意識が、「世界創造の石」に宿り、鳥たち他の生き物が生活していくには大変な環境、地獄のような世界として姿を現すことになった。
→創造主たる大叔父は、地獄になっている原因がそこにあることに気付いていない。自分の内にある何らかの悪意に原因があるということまでは認識しているのだが…。
○元の世界から突然行方不明になった心の内
→人間同士の争い、愚かさ、醜さを目にした際に自分が感じる苦しみから逃れたいがために、現実から目を背け、他人を寄せ付けず、自分だけの世界に閉じこもった
→大叔父が感じていた苦しみとは、ケガや飢えや病気などの身体的なものではなく、自分の心の中の動きであり、そこから目を背けるということは、自分自身と向き合っていないということ
→すなわち、自分の中の悪意と向き合えていないということ
●●青鷺(あおさぎ)
眞人のもう一人の自分、または
眞人の意識・魂の一部
→多分見る人によって、どうにでも解釈できる存在です。
→終盤、インコもペリカンもインコ大王も、鳥たちはみな眞人が元々いた世界に来て、鳥の姿になった(戻った?)のに、ふと気づくと、青鷺の姿だけ消えていた。
①ジブリ関係者の擬鳥人化
②別の時代から来た青い鷺
③眞人のご先祖様
④眞人の守護霊
⑤眞人のそのときどきの意識・心を投影した存在
⑥眞人の分身・魂の一部
⑦大叔父の分身
⑧ヒミの分身
⑨天使、天狗のような高次元の存在
⑩宇宙人
⑪宇宙から飛来した隕石の意識のかけら
⑫「世界創造の石」そのもの
⑬集合的無意識・超意識・宇宙意識
⑭その他
どれが近いと思いますか?
自分は⑤⑥がしっくりくる感じですかねー。
そのときそのときの眞人の意識を投影して振る舞う存在かなと。
お話が進んでくると、的確なアドバイスをするなど、スピリチュアルで言う守護霊やハイヤーセルフのような振る舞いもするようになります。
○青鷺「助けて眞人。お母さんが助けを求めてる。」
→眞人が無意識のうちに「お母さんに会いたい」という実母に抱いていた未練・願望が、青鷺を介して、そういうセリフとなって現れた。
○「本当は、夏子なんていなくなればいいと思ってるだろ?」
→「君たちはどう生きるか」を読んで涙し、夏子を母として受け入れると決めた眞人に、その覚悟を問うてきた
○「お前の心臓を食らってやる」
→眞人が青鷺に敵対意識を、なんならコロしてやろうという意思を持っていたので、その意識をそのまま鏡のように、青鷺が示す敵対姿勢として写し出した
○「隠れろ」
→だんだんと青鷺を信頼するようになっていったので、彼もそれに呼応して、的確な助言をするように
○「じゃあな友達」
→「青鷺も友達だ」と偽りのない心を叫んだので、その友好意識がそのまま投影され、爽やかグッバイに
●●シーンごとの考察2
○悪意が反映された下の世界の崩壊
→現実世界においても、闇側が作った様々な支配体制・ピラミッド構造がこれから崩壊していくことのメタファー
○下の世界にいた人間は、みな元の時代に戻る
→それぞれの自由意思で、それぞれ歩む道を決める。
○ヒミ「あたし、火、平気だよ。それに、あなたを生むなんて素敵じゃない。」と元の時代に戻ることを決め、眞人もそれを尊重する。
→自由意思の尊重
→火事で亡くなる世界線のまま?
→それとも、火耐性がついたから大丈夫?
→あるいは、火を自由に扱えたのは、下の世界のときだけで、元の時代に戻って火に触れたら、普通にやけどする?
○下の世界で生きること自体に苦労していたインコとペリカンも、眞人と同じ世界に来る(戻る?)ことで、みな自由に伸び伸びと羽ばたいていった。インコ大王も来た。
→これから眞人も自由に生きていく明るい未来を暗示
○「みんな友達だ!!!」
→人間とも、鳥とも、青鷺とも、みんなと仲良く生きていくという決意表明
→「愚かな鳥よ」と他の存在を蔑み、その意識が原因で、地獄のような世界を創造してしまった大叔父との対比
→でも、大叔父も最後の最後で「眞人、行け。元の世界へ戻れー」と眞人の意思を尊重して、その背中を押してくれたんですよね。
→自分が作った世界が崩壊を迎え、命も尽きてしまうかもしれない瞬間だったのに、子孫の幸せを心の底から願ってくれた。
そんな大叔父も含め
「きっと、この眞人なら、みんなと協力して、みんな豊かで幸せに暮らせる世界を作る…!」
そんな期待を胸に抱かずにはいられない。
そして、物語はエンディングを迎える…
…君たちは、君たち自身の世界に戻って来たよ・・
さあ、君たちはどう生きる?
若者達よ しなやかに生きてゆけ
序盤のシーンが胸に迫る。
過去作品のワンシーンを思い起こさせてくれる映像にワクワクした。
スタジオジブリならではの温かみのある躍動感溢れた映像を、劇場で堪能出来た事に感謝。
やや難解な印象の作品でしたが、退出時に未だ幼いお子さん達の姿も見かけました。ジブリ作品故、かも知れませんね。
映画館での鑑賞
ダメだ。
全く刺さりませんでした。
元々ジブリ作品は自ら進んで観たことがなく、今まで付き合いでいくつか嫌々観たくらいです。
しかし今回は宣伝ナシだったので、まんまとその策略にハマり初めて自らジブリ作品を観ようと思い観に行きました。
やっぱりダメだ。この独特の世界観。あの7人のお婆ちゃんキャラが出てきた時点で、一気に萎えた。こういうジブリ特有の雰囲気、かつ過去に見たことあるようなキャラ出すのやめてくれ。何かが違うんじゃないかと少しでも期待した私がバカだった。その後もジブリジブリしたキャラが色々出現。
話も何がなんだか。最終的に何を伝えたいのかもよくわからず。観終わった後には「クソつまらなかった」しか出てこなかった。やっぱり私にはジブリは合わない。
2度目で素直に入ってきた
「Day Dayの情報だけ」
ART作品として観たくなる
2回目鑑賞
青鷺は宮崎駿監督の姿 もしくは人間の本質
(かっこいい時もずるい時もある)
大叔父は宮崎駿監督のメッセージ
(この世に生まれた作品への愛)
に観えました。
一度きりの人生、やりたい事をやれるのは幸せなことで
とても羨ましいです。
成功した人とは比べられないですが、私は私で、
残りの人生、どう生きるか、とあらためて考えてます。
きっと、ちゃんと自分で考えてからの行動、その時の選択肢もどれも正解なんだから。
君たちはどう生きるか 監督から私達へのメッセージ
プロモーションがないので当初は公開されることも知らず。SNSで観た人の感想で、公開を知った。
おしなべて、解釈が分かれる映画だという。
キービジュアルだけで、絵に似つかわしくないタイトル(キャッチコピー)
どんな映画か、さっぱり分からず、
監督のエゴだけの作品でしかないなら、観たくないなと迷った。
⚠️以下は、読まずに映画を観てほしい⚠️
難解だと事前の口コミで聞いてもいたが、
非常に宮崎駿らしい映画だった。
どこかおどろおどろしいファンタジー、彼の映画は子供に向けた作品でありながら、原始的な闇があり、子供をすくませる。
現にこれまでの作品でも、子供が怖いと泣き出し映画館を出ていく姿を何度も観た。
今作で難解なのはその世界観で、世界のルールを飲み込みさえすれば、物語を楽しむことができる。
屋敷に落ちてきた力ある石。
その力を得て、大叔父は世界を創り上げた。後継者を求めて、子孫を呼び寄せる。
その世界は意図してか、無意識なのか宮崎駿のこれまでの作品風景がそこここにパッチワークのように散りばめられ、既視感を覚えた人も少なくないはずだ。
老いてなお、彼の中にはこれほど豊かなイマジネーションがあることに、改めて驚く。
そして大叔父と主人公は邂逅する。
世界はバランスの悪い積み木を重ねるように、保つことが困難で、
1日1日を迎えることが、どれほど難解かを語る。
主人公に、おまえが世界をつくるんだと諭し、平和で穏やかな未来を作ることを願う。
これこそが、宮崎駿が私達に伝えたいこと。
「君たちはどう生きるか」
政府により国民は搾取され、貧困に追い込まれ、
自ら戦争へと突き進む今の日本をみて、どれほど歯痒いだろうかと思う。
私達の明日は、私達自身がつかみとれ、きっとこのメッセージを届けたくて、この映画を作ったんだろうと、心打たれた。
ただ、物語の起承転結としては弱く、映画そのものの魅力はやや欠けたのは残念。
それでも、観て良かった。
観るべき映画だった。
子供たちには難しいかもしれないが、私は観てほしい。
圧倒されました。
何時も以上の宮さん世界を堪能出来る作品
内容は、監督・原作・脚本を宮崎駿が仕切る。『君たちはどう生きるか』を本人の人生観と解釈でまとめ上げたファンタジーパラレル宮崎駿作品。印象的な台詞は、アオサギの『あばよっトモダチ!』です。友達の少なさと友達と呼ばれる存在の大切さを人生において素直に受け止める事の出来る今の状態を表しているようで印象的でした。印象的なシチュエーションでは、様々な年齢と立場で描かれるイマジナリー自分が混在する構成が面白かった。映画で語る言葉とは自分が一番聴きたい思いたい言葉なのかもしれません。その様な意味で、自ずからの全裸姿を嬉しくも怖く感じました。印象的なシーンでは、生と死・自由と束縛・罪と罰などのメタファーが多用されていた事が印象的でした。色とりどりなインコ🦜や白くふわふわ丸い奴や様々な時代や地方の船の列など、葛藤がカタルシスを昇華させていく様に感じ。しかし、倒れる塔の一斉に飛び立つインコ達には、一抹の寂しさも感じられる作品でした。死して屍拾うもの無しって割り切りもある様で混在している気持ちの表れが映像表現として素晴らしいと感じました。しかしっ!ジブリファンならずとも、夢のまた夢のお話は少し分かりづらく山が単調で睡魔が訪れる事もありました。数々の宮崎駿作品さながらまだ表層しか味わっておらず、この後発売されるパンフレットが楽しみで、何倍も深い所まで楽しめる事に期待してます。これからも手は動かさずとも少しでも面白い作品を作られる事を期待してます。そして、アニメーターという呪いを楽しめる一人のファンとして期待してます。
話しはシンプル
アニメが苦手で、ジブリ作品を1本も見た事がありません。
しかし、予告なし、賛否両論分かれる、説教じみたタイトル、に惹かれて観に行きました。
内容は複雑な場面転換のように見えて、そこはアニメの世界、自由な発想であり得ない異次元を行ったり来たりしますが、芯となるストーリーはシンプルだと感じました。
教えとか教訓とかそんな大仰なことではなく、シンプルに胸に刺ささりました。
親が子を思う気持ち、人を大切に思う気持ちと、最後はホンワカした気持ちになりました。
ジブリを1本も観た事がない、が自慢だったのですが、唯一観てしまいました(笑)
これから他の作品を観ることはないですが、これは良かったと宣伝します。
宮﨑駿の内なる世界
わかるかわからないかで言えばわからない。
観終わってからじっくり考えて、大叔父は宮﨑駿自身のことで内なる世界をギリギリ保ちながら眞人のような後継者が現れるのを待っているんだろうか、とか、あの塔の中は誰もが皆、生と死の間の存在なんだろうか、とかぼんやり考えてみたけど正解はわからない。
もしかしたら宮﨑駿自身も明確に私達に伝えたいことが定まってる訳ではなく、今の自分自身の中にあるものをありったけ出しただけなのかもしれない。まさに宮﨑駿の頭の中の世界。
咀嚼しきれてないからもう1回観ておこうかな。
言われてるとおりこれまでのジブリ作品のオマージュがあちこちにあってそれがわかるとちょっと楽しい。主役の眞人も今までのジブリ男子の色んな要素を持ってるし、今までの
ジブリ男子らしくない要素ももっている。(将来絶対イイ男になる!)
ネタバレではないと思うけど一応ネタバレ設定にしておこう。
ジブリ史上
宮崎駿は全体を監督してない 別の人が作ってる
ジブリ最高の名作
日本人の日常生活から物語ははじまり、やがてファンタジーの世界へ、そして現実の世界に戻る。主人公が抱えたトラウマや苛立ち、葛藤がファンタジーの世界での登場人物との関わりやぶつかりを経て解消され昇華される。人生や世の中の問題…生と死、老い、友情、恋愛、成長、退行、愚かさ、勇気、挑戦、弱さ、天地創造とは、性的マイノリティー、人間性、権力欲、優しさ、強さ、絆などの数々が盛り込まれ、その答えを言葉ではなく、映像で示している。なので、その人の感性により、感じ取れる人、何も感じない人に分かれるし、感じ取れる人でもその分量は異なってくる。そして、宮崎駿が伝えたい「君たちはどう生きるか」を映画を通して映像で伝えているメッセージは、自分で考えること、前を向いて生きること、正直であること、人と本音でぶつかりあうことにより物事の進展がある、自分の短所を認めることが自分を成長させる、人の死の悲しみを感じることは悪いことではないがそれに囚われすぎずに眼の前に居る人間(登場人物の夏子、おばあさんたち、アオサギ…)も見ること、大事な人が亡くなって悲しい気持ちは大事だが、今眼の前にいる人間に心を開いていくことにより、いまを生きることが出来る、亡くなった人のことも忘れる必要はない、時間は一方向に向かって進んでいるばかりではなく、現在から過去へと進んだり、ある点からある点へと飛び越えたりするものであるので、時間軸に囚われずに「今」に存在すること…などを感じ取ったが他にもまだまだ気がつかないメッセージが作品の中に込められていると思う。そして、「君たちはどう生きるか」には、学校に通うべき年齢の主人公にとっての学校生活がほとんど出てこない。学校生活を送らずとも成長は出来る、だから学校生活にこだわる必要はない、老人や大人からも生きることについて学んだり、安心を与えられたりすることがある、という現代の不登校の子供たちへのメッセージも込められていると思った。
宮崎駿監督は天才であると確信させられる映画である。
ディズニーとの縁が深い宮崎駿監督ならではだが、お屋敷の使用人の老女たちは、白雪姫の七人の小人のように主人公たちを助け、主人公の母親のヒミは白雪姫と似ている髪型、服装をしているなど、ディズニーとのつながりが深い宮崎駿監督ならではのディズニーへの恩返しのような一面も感じられた。
宣伝無しはイイ宣伝になった
今回は賛否あると話題になってるから確かめに観に行った。
描写の表現は相変わらずといった感じで、そこはさすがと思った。
「よくわからない」「理解できない」という声もあるが、漫画、アニメ、小説とはそういうもんです。
手塚治虫先生からの遺言、「漫画はどんどん嘘を描きなさい」。
漫画はそもそも実写映画ではないので、独り言も頻繁に言うし、突然変身したり、普通なら死んでるような事が起こっても生きている。
特に宮崎作品はそうだ。
この作品を観てると大友克洋先生の『アキラ』を思い出したのは私だけ?
もう何でもありって作品です。
なので別にそれに意味を求めてもいない。
ただ、笑えるわけでもなく、泣けるわけでもなく、感動もしなかったのが本音です。
嘘つかずに感想を述べると、そんな感じです。
監督本人がその場に居たら、社交辞令で「感動しました」って言うかもしれませんが。
人が一所懸命作った作品に点数つけるのはおこがましいけど、決して悪い作品とは思いませんが、私の個人的評価ですので悪しからず。
大衆向けアニメ映画ではありません
自分自身はほとんどジブリ作品を見たことがなく
かなり昔に「もののけ姫」「千と千尋の神隠し」を観たくらい
最近は「アーヤと魔女」を観たが
ジブリを観ない一般人とあまり変わらないと思います。
ストーリーはわかりにくい
全体としては、戦争中に母親を亡くした主人公が
新しい母親をうまく家族として受け入れられず
異世界の冒険を通じて
家族を受け入れていく感じだが
全体的にわかりにくいように思う
異世界の冒険は
後付けで説明をされているように感じて
設定が唐突にでてくるイメージが強かった
キャラクターは全体的によかったと思うが
前情報がまったくないので、アオサギがおじさんみたいになった姿は
ちょっとびっくりした。
異世界での大叔父などは宮崎駿監督自身のメタファーかと思ったりしたので
この作品はメタファーが多くあるのかなとは思ったが
ジブリ作品をあまり知らないのでそこらへんはわからない。
大叔父の跡継ぎを
自分で自分を傷つけたことを理由に拒絶する
ラストでインコ大王が激怒して
世界を構築しているとされる積み木をメチャクチャにして、
世界が崩壊してしまい
そこから、主人公は脱出するという感じだった
個人的に作画はメチャクチャよかった
しかし、ストーリーは大衆向けではないので広告を一切なしなのは、そういうところが理由かなと思った
往年のジブリファンだと違う感想なのかな?
小さい子供が見るには
魚っぽい生き物を包丁で解体するところや
石で主人公が自分を傷つけるところなど
子供が見るにはキツイ部分がそこそこあったりするので
子供向けとも思えない
原作本とされる「君たちはどう生きるか」という本は
劇中で読むシーンがあるくらいで内容は関係ない
宮崎駿だから許される映画
黒澤明の「夢」
夏目漱石の「夢十夜」
村上春樹の「海辺のカフカ」
この映画を見ながら、上記の作品のことを考えていました。
事前情報無しっていうのもなんとなくわかります。
これ、どうやってプロモーションするのが正解なんでしょうか?
母を失った少年が異世界に迷い込んで…
豪華声優キャストでお送りする…
「君たちはどう生きるか」、宮崎駿による脳内解釈…
どれも引きが弱そうです。
となるとやはり事前情報無しっていうプロモーションが正解なんでしょうか…。
映画の内容にしてもプロモーションにしても、宮崎駿だから許される感じです。
私個人としてはとても面白かった(興味深かった)です。
今までの培(ツチカ)って来た業績が無いと,語る事が赦(ユル)されない重たいタイトル…。
巧(ウマ)い具合に解り易く伝えられる言葉が今一見当たらない⁈という処…。
こんなタイトル自体は、そんじゃ其所(ソコ)らの人には恐れ多くてそうは簡単に言ってはいけない!&世の中?若(モ)しくは世間様に認められている程の何と云(イ)えば当て嵌まるのかは定かでは無いが、例えば『称号』?(私が勝手に宮崎駿の地位を表現する為に作ったモノの事)を与えられた人にしか付けられないと思わせたタイトルだと私は思う。ソレが赦(ユル)される“宮崎駿”が語る作品に面白味を感じ取れた事は強く言いたい感じ。
やたらと眼にした“意味分からん⁈"風な言葉を頻繁に見た様な気がした…&何処かの誰かのレビューを参考にさせて貰った中で、あまり良く知らん所でも有るが,息子<宮崎吾郎>への世代交代と言えば確かに話は全ては話が丸く収まる気がしたのも確かで有り…。
映画作品のシナリオの中で(アニメーションは特に)意味を問い正したら,面白いものも詰まらんモノに換えてしまう様な気がしてしまうんだが如何(イカガ)なもので有ろうか?
私自身の独断の意見なのだが(そりゃそうだ!こうやって語る事自体が,語る事で飯を食っている様な所謂(イワユル)プロの評論家な訳でも無い事を踏まえた上で悪しからず…)、別に只単に独りの映画好きが身の程知らず?で勝手に語ってるだけで有り。
声優陣は<顔を揃える訳も無い,有り得ん錚々(ソウソウ)たるメンバー>の中のストーリーの中の設定で、話題になる箇所も一杯有って全てを取り上げていたら私は特にだが,寝てる暇?は無くなってしまう処なので、あの積み木を世の中に喩(タト)えたシナリオは素晴らしいモノだと思えた処…。
で、何
70年前に書かれた、数年前にはマンガ版も出版された青少年向けの小説“きみたちはどう生きるか”が原作、、、ではないようです。モチーフにはなっていますが。
少年がファンタジー世界に迷い込んで大冒険。青鷺が頭の部分をはずすと中年太りのおっさんに変化、謎の船乗り女性、炎を操る少女、インコの王国や国王、ファンタジー世界のバランスを調節する大叔父さん、これらは何かの比喩なのか。タイトルのきみたちはどう生きるかは誰に何を問いかけているのか?最後にファンタジー世界が崩壊して現実世界戻ってメデタシメデタシ?
結局どう理解すればいいのか分からないし、これを受け手側が自由に解釈しろというのも無責任な気がします。色々な人が色々解説していますので参考にしてもいいと思いますが、個人的にはこのようなご自由に解釈してください、あるいは言わなくても過去の映画とか見れば分かるだろ的な映画は嫌いです。
客の入りはいいから、そのうちテレビ放送するでしょう。そこで見れば十分かと思います。個人的には駄作と判定。時間の無駄、、、までとは言いませんが。
全2100件中、1081~1100件目を表示