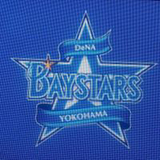君たちはどう生きるかのレビュー・感想・評価
全2097件中、321~340件目を表示
2023 120本目(劇場10作目)
この作品もだいぶ前に
もののけ姫が自分の最高傑作なので
近年の宮崎作品はちょっとって感じでした。
この作品は、おしいかな
ファンタジーなんだけど理解不能な所もあり
何より子供達が楽しめるかな
宮崎さん次回作は、もののけ、ナウシカ、ラピュタの感じでお願いします!
劇場でぜひ観よう
何となく観ることに二の足を踏んでいたが、冒険活劇感満載で、単純に面白かった。
これは、宮﨑駿監督の集大成!その要素を惜しげもなくふんだんに盛り込んでいる。
(若手のつくり手が観たらどのように感じるのだろうか)
オープニングの、美しくもやや不安を感じる作画で、もう引き込まれた。
練り込まれたストーリー、躍動するキャラクター、観ていて気持ちよかった。
エンドクレジットも素敵。
80歳を過ぎてもこんな発想できるものかと感服。
色んな愛が描かれているようにも感じた。
いまリアルに映画館でこの作品を観ることができることを思うと感慨深い。
海外向けの予告をみたが、国内向けには予告もつくらなかったのか。
きちんと回収されている、タイトルの「君たちはどう生きるか」を推してプロモーションをおこなったらどうだったのだろう。
多くの方に観ていただきたい。
(10.29.一部修正・追記)
不条理なこの世界でどう生きるか
メッセージを極限まで抑えたポスターと、公開前の無きに等しい広告宣伝。宮崎監督のファン層は余計に興奮を掻き立てられただろうが、そのほかの多くの映画好きは冷静だった。そして公開後のロングランと、賛否両論乱れ飛ぶレビュー、宮崎監督の制作の真意を図ろうとする批評の数々。
本作の評価が大きくわかれる要因のひとつが、メッセージの不明瞭さかもしれない。誰がみても明快なストーリーとは言えない、複数の論点が重層的に入れ込まれている。一回観ただけでは、あのシーンはどういう意味が込められているのか、わからないものもあるし、複数回観てもわからないものもある。宮崎監督に尋ねても明快な答えが得られないものもあるかもしれない。映画も、小説も、音楽も、制作者が世に出した時点から作品自体がひとり歩きしていく。本作も公開後、宮崎駿監督の手を離れて観客の手に委ねられたと捉えれば、どう読み取るかは観客の自由。解釈に正解も誤りもない。
本作の大きなテーマのひとつが、「異界とのつながり」だ。
眞人は側頭部に自ら大きな傷を負うことで、異界への扉が開かれる。
異界の媒介者である、青サギもキリコにも傷がある。先に異界に迷い込んだ、夏子も心と体に傷を負っているよう。傷によって誘われるものとは、たんなる幻覚世界か、それともマルチバースの世界か。
異界の創造主である大叔父は、不条理にまみれた「この世」に嫌気をさし、予定調和の世界を創ろうとしている。しかし、そこはすべての生き物にとっての楽園ではなく、老ペリカンの嘆きのように、閉ざされた環境で他者のいのちの犠牲のもとに成立しており、その犠牲の社会構造は「この世」と何ら変わらない。
異界に理想郷を作ろうとした大叔父。現実世界の理不尽さに嫌悪感を感じつつも、「上の世界」に「母親」の夏子と父のもとに戻り、不条理な現世で生きていくことを決めた眞人。
石などの非・人間の存在も魅力的な役割を担っている。
眞人を「下の世界」に導くのは、傷をつけた大きな石だし、石の塔の主である大叔父が「下の世界」を創ってきた源は穢されていない石だ。夏子は石で覆われた産屋のなかの石でできたベットに横たわっている。夏子を救わんとする眞人とヒミの侵入に、石は負の応答をする。そして「上の世界」に戻った眞人が「下の世界」を覚えていられる訳は、ポケットに入っていた、穢されていない石の存在である。
石や、鳥たち(童話で擬人化されやすい哺乳類たちではない)、そして火などの非・人間が行為主体としていききと描かれている。人間が自然を支配する構造ができあがってくる近代以降、不可視化されてきた非・人間の存在を蘇生させるところは宮崎監督の真骨頂といえる。
製作委員会方式によらず、宮崎監督が本当に作りたいものを、作りたい人だけで作った貴重な作品。
宮崎アニメの集大成!
ようやく、終映近いかもと重い腰をあげて観ました。
「ハウルの動く城」後半で、完全に置いてきぼりに遭って以来、新作ジブリ作品から遠ざかっていましたが、久々に映画館で鑑賞しました。
古今東西のファンタジー小説、冒険物語のごった煮感はあります。
場面がどんどん切り替わり、ラストどうなるんだろう?と、眞人と様々な世界を冒険するのは、楽しかったです。
こういうお話は、ラスト、元の世界に戻るお約束なので、安心して観れます。
宮崎さん世代にとって、戦争の傷跡って大きい。
それをまざまざと感じました。
昭和生まれの私は、親や祖父母、親族から間接的にそれを感じ取った世代です。
世界が再び、戦争のフェーズに入ろうとしている今、私には何ができるのか、考えていきます。
エンドロールの米津玄師さんの「地球儀」は、心に沁みました。
泣きました…。
単体で聴くより、ずっとよい、主題歌ってすごいです。
そして、豪華な声優陣に驚き。
帰宅後、ホームページで誰がどの役か確認しました(^-^;
今まで500本以上の映画を観てきましたが、「風の谷のナウシカ」は私の不動の1位です。
コロナ禍で、映画館で鑑賞できたことは、僥倖でした(6回観ました!)。
ナウシカに出会わせてくれた宮崎監督には、ホントに心から感謝しています。
ありがとうございました。
またもや宿題をくださった
ジブリの集大成かと思いました。
見ているとアレやコレがでてきます。
私はこの映画、好きです。
(過去に意味の分からないままのジブリ作品は正直ありますがこの作品は好きかな)
主人公的な人とそうでない人との区別で美醜のかきわけ方。ビジュアルはなんとも分かりやすい。
まず湯婆婆みたいなひとたちがいっぱいいるー!と思いゾッとしたけど、守ってくれているお婆ちゃんたち。実はとても感謝すべきだしよく見るととても愛らしかったかな。
お砂糖が高級な時代。
学校に寄付したという当時の300円は今だといくらに相当するのだろう?
DATSUNで転校生の眞人は登校するが…。ヤダ、あんな父親…
だけど眞人は親に対して敬語で接し、とても良い子。
(自ら)怪我をしたときは涙が出た……。
出血シーンは基本苦手だが、此の宮崎駿作品は何故か目を逸らすことなく観れました。
なつこさん、なつこおかあさん……と最後は呼び方変わりましたね。
異空間への入口…
地獄?天国??
Disney映画で『パイレーツ・オブ・カリビアン』の一部を彷彿とさせるシーンもあったように思います。
積み木を地球上の平和(?)に例えて当て嵌めている…
いろんな鳥たちのお出まし…。
コウノトリかと思いきやペリカンは生まれてくる前のわらわらを食べてしまう……でもそれが仕事だという。
鳥目、、最後は鳥頭で浅はか… あーあ。。
興奮した鳥頭…、周りは止められそうに見えてもソコは誰も止められない(止めない、その隙もない?)もんなんですね。
意外と現実にあるこの世界もそんなもんなんでしょうか。一部の人達のエゴで他のみんなが巻き込まれている。。
エンドロールはシンプル。
ジブリのこだわりのブルーの色で米津さんの優しい歌声「地球儀」がしみます。
このブルーの色は古くから出ているサントラCD
(たしか、徳間からのジャケ、歌詞カード?がトトロイラストの…)もそうだと思いました。
ブルーにもイロイロな表現があるようで、物凄く拘り、ありますよね。
独り言です。
どう生きれば良いんですかね…
やっぱり映画館で観たほうがいいよなと思い、滑り込みで鑑賞
小さめのスクリーンだったのが逆に良かった
大伯父さんは宮崎駿監督ってことでいいのかな
眞人も宮崎駿監督っぽいけど…
塔はスタジオジブリ=積み木、石は創造主?
ワラワラは人間って言ってたけど、きっと宮崎駿のアイディアで、ペリカンは内部の人かな…?
インコも内部の人かなー日テレっぽい
アオサギは鈴木敏夫プロデューサー…かも
ネタバレがほとんど耳に入ってこなかったけど、ネタバレしようがないからだったんだろうな
眞人が自分でつけた頭の傷、自分で悪意と言っていたけど本当に悪意なのかな
悪意だとしたら、それは眞人だけの悪意なのか
そうさせた何かは悪意ではないのか
自分はこんな感じで生きるけど、君たちはどう生きんの?
って言われましても…どう生きれば…(呆然)となった
どうすればいいんですかねえ…
レンタルで
美術館なら星5 エンターテイメントなら星1
小さい子供さんは まず楽しめません
解説、伏線回収がほぼ無いから
映像見てるダケでは正直訳がわからん この1言です
評価が割れるのも
よーーーくわかります
しかし映像の緻密さや
音域の広さは とんでもねぇなぁと最初から痛感させられましたね
流石はジブリアニメ
さっくり言うなら
塔は多様な時間軸、世界線に出入り出来る中立の世界
↑も自分の解釈にしかすぎず
しっかりした解説、説明は一切ない
エヴァかっての
しかしながら
自分の世界を自分で作り上げる事は
生きてる人間全てに当てはまる事であり
だれもそれから逃げられない自分にはどうしようもない状況であれ
自分の選択肢で 世界は動く、変わる
そういった意味合いで
君たちはどう生きるか かなぁ???
老兵は死なず、ただ消えゆくのみ?
幼少の頃より宮崎駿監督の作品は見続けています。久石譲氏の音楽の素晴らしさと相まって、美しく描かれた風情の中で生き生きと動き回るキャクラクターたちは、宮崎駿監督が作品に吹き込む生命の素晴らしさをまざまざと見せつけてきました。
見るものを魅了する珠玉の作品の数々は、監督が同時代の天才であることを象徴していたようでした。
そう、その時代では。
今はどうでしょうか?監督の他にも様々なアニメや監督が生まれています。
その中で生み出された本作は、まるで宮崎駿監督が若い世代の監督に刺激を受け、自分の描きたかった作品をひたすらにまとめ上げたのではないのか?そう思えました。
もしも監督がまだ若く、才能のみならず勢いも持ち合わせていたのなら、ともすれば散文的な作品に陥ち入りかねない数々を、一つの作品としてまとめ上げる強大な説得力を、その作品に吹き込むことができていたのではないでしょうか。
しかし、もはやその力は失われたのでしょうか、本作はただひたすら監督の描きたかった場面と場面をつなぎ合わせただけの、ツギハギだらけの作品に仕上がったように思えます。
作中に主人公の叔父が、主人公に跡を継いでくれないかと問いかけるシーンがあります。多くの方がこれは象徴的なシーンだと捉えるでしょう。当方もそうです。しかし、既に、ともすれば監督を超える才能を持つ新進気鋭の作家が出てきている中で、自分の跡を継いで欲しいというその台詞は、ある意味高慢とも感じました。
しかし思い返してみれば、そのセリフは同時に、宮崎駿という作家は、まだ死んでいないにだ、と捉えることができました。この作品は遺作などではなく、若い才能に嫉妬した監督が、自分ならこのシーンはこう表現するんだ、こうできるんだ、そう高らかに宣言している、そういった意地とも見れると感じました。
老兵は死なず、ただ消えゆくのみとなるのか、または再び作品を作ろうとするのか。これが本作の楽しみ方でした。
ジブリの集大成。映画館で見られて良かった。
映画館で見ながら、宮崎駿監督の作品は今回で最後なんだなぁ…と、うるっときた。
想像と違って今までのジブリが全て詰め込まれていたと思う。タイトルだけ見たら、戦時中を生き抜く青年や、あの本のアニメ化だと先入観を持っていた人も多かったはず。
ストーリーは、日本がまだ平和ではなかった時代、「苦しい現実」から始まる。今の日本だったら、何かしら夢を抱きはじめる年頃の青年。戦争で母を失い、道を歩いていても軍人を称え、父は自己中心的、新しい母は実母に似ていても心を開けない。学校では暴行被害。自傷。感情を押し殺す毎日。いつまでも未来が見えなくて心が死にそうな青年は、半人間の青サギに心の闇を見透かされ、まとわりつく青サギを消そうとすることで、とうとう大叔父が創り上げた「下の世界」に連れて行かれてしまうところから、宮崎監督の世界が繰り広げられていく。
真人は一冊の本と出会っていた。夢なのか現実なのか自分の体がどこにあるのか。彷徨う中で、生と死の残酷な世の中を見せる大叔父の精神世界に飲み込まれそうになったが、キリコやヒミ、夏子の世界とも交わり、生きてほしい、自分も生きたいと思えるようになっていく。徐々に真人は自分の力で自らの精神世界を築き上げていき、この世における自分の存在、自分の役割を理解することができるようになっていった。そして、大人になって現実に戻り、本は母からだったと気づく。
目まぐるしい場面展開や抽象的な会話が、いかにも夢を見ているような幻想的な世界を表していて簡単に理解することは難しいが、宮崎監督としては、見てくれた方々に、自分の隠れたメッセージをどう理解してくれたか、受け止めてくれたかをむしろ知りたいはずだと思う。
世界観
「宮崎駿監督」「スタジオジブリ」ときて、期待しない人はいないと思う。
しかし、伝えたい事がよくわからず、キャラにも思い入れ出来ず、なんて感想したらいいのかわからない。
物語に引き込まれる事なく終わってしまった。
題名は主人公が手にした本の題名だという事を後から知って、そこは理解できた。(タイトルと内容が結びつかないなと思っていたので。)
でも、よくわからないキャラがたくさん出てきて、少し気持ち悪いキャラも居て、鳥は悪者?と思ったり、なんだか色々ホラーなシーンにみえてしまった。
子供も大人も楽しめる、もっと夢のある作品を期待していただけに少し残念。
ただ、ジブリ作品を観てきた人なら、これはあのキャラ?これはあのシーンに似てる!?って言う世界観を感じる楽しみはあります。
タイトルと中身のギャップ
いや、最高でした。これまでのジブリ映画で一番好きかもと思った。トト...
いや、最高でした。これまでのジブリ映画で一番好きかもと思った。トトロ、ラピュタ、魔女、、とジブリ映画と共に育った世代ですが、2023年にもなって、こんなどえらい新作を観られるなんて思ってなかった。のっけから動きの全部がすごかった。随所随所に、天才の反射神経を感じる瞬間、動き、エピソードが散りばめられてて、この映画のどこにどこまで宮崎さんが関わっているのかなんて知らないけど、すごすぎた。天才たちがいる、、と思った。興奮しっぱなしで二時間半がたった。階段をのぼる、という動きひとつとっても、その人の気持ちが伝わってくる。わざわざアニメーション映画で作る意味ってこういうことだよなあ、、セリフより、画面の動き全部で、今どういう状況でどういう気持ちなのか、この先どういう展開の予感なのかが全部伝わってきてすごかった。ファンタジー世界をアニメーション映画で見せてもらえる醍醐味がすごかった。次から次に別の扉が開きまくって、今何してる途中だっけ!?っていうのは常にあって、でもこれこれこれだよっていう気持ち。まみれてこんがらかって気づいたら別のドアから戻っている感じ、、骨格は古き良きいくつもの物語たちを踏襲しつつ、具体的な細部や動きがサイケでハートフルでとにかく本当に最高でした。映画館でまだ見たい!
駿の集大成
映画館にて鑑賞
最近のジブリ映画には期待してなかったので見にいくつもりはなかったが、あまりに話題になっていたので気になって鑑賞した。
今作は今までのジブリと違い、全編にわたり暗い雰囲気に包まれている。
ジブリでは明るい世界観が多いし、暗い世界でも懸命に生きようとする主人公が多い。
冒頭の空襲の火災のシーンはアニメでしか表現できないリアルさがあり素晴らしかった。
また新居へ引っ越した後の不安感などもおどろおどろしい雰囲気で表現できていて良かった。
また出会ってすぐに母親になる、弟を妊娠してる宣言をし、お腹を触らせる夏子さんは気味悪い。
母親になることを認めれない気持ちが自傷行為へとつながる。
ただ青サギとのやり取りから物語が進行していく
初めて青サギがしゃべるシーンは衝撃だがマヒトは全く驚いてない事に違和感を感じる。
夢の中の話という設定なのか?
建物の中に導かれるまでは非常に良かった。
ただその後地下に行ってからは本当に悪夢を見てるようなイメージだ
とりあえず全てが荒唐無稽で意味がわからない。
またコダマを連想させるワラワラやナウシカみたいな森、ラピュタ、カリオストロを連想させるオウムの帝国、城
オウムに支配されてる世界
なんでオウム?
ある意味で今までの集大成のような映画となっている
また出てくる大叔父さんが宮崎駿のモデルなのだろう
マヒトも駿だが、吾郎や米林の役割も有るのだろうか?
世界を維持していた13個の積み木は今まで作った13本の作品を意識しているのだろう
その世界の運営(ジブリの運営)を譲ろうとするが断られてしまう、大王(鈴木p)がその様を見て怒り出す。そしてその世界は滅びていく。
これはジブリの世界を暗に表しているのではないだろうか。
そして現実に帰ってきて母親とも仲直りし大円団となるがストーリーの展開的にはおもしろくない
2度3度見に行こうとは全く思わない
宮崎駿作品は絵に関しては素晴らしいが
肝心のストーリーが訳わからなくて何を言いたいのかわからない事が多い
特にハウルすぎてから
イラストレーターとしては素晴らしいが
誰か舵取り役の人が必要だろう
それがプロデューサーや監督だ思うが
ジブリはアニメ界に大きな功績を果たしたが、今や知名度だけでもう崩壊するだけの帝国となっているだろう。
今後日テレと手を組むことでどう変わるのか気になるところである
映像はこれぞといった感じ
これぞ宮崎駿監督という映像の連続なのだが。
内容はタイトル通りなんだけど、別世界への扉を「アリスと不思議の国」のごとく描く。またその世界が多重構造で独創的な構成のため、馴染むまでの過程が上映時間に見合ってない様に感じた。
映像のみでも楽しめる作品にはなってるんだけど、別世界の構図や鳥(青鷺やペリカン、インコ)を使うことへのこだわりといった点などをいつもなら力技で押し切るんだけど、今回はその押し切る力が弱く感じた。
全2097件中、321~340件目を表示