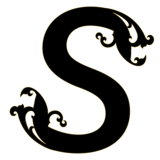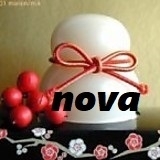ウーマン・トーキング 私たちの選択のレビュー・感想・評価
全105件中、61~80件目を表示
考えさせられる作品
実際に起きたレイプ事件を題材にした作品だが、色々考えさせられた。エンタメ作品として鑑賞せず社会問題の一部として鑑賞した方がいい作品。
女性たちが集まり自分たちの将来について話し合う。赦すか、残って闘うか、村から去るか。赦すとどうなるか、残って闘うとどうなるか、村から去るとどうなるか。議論のシーンを見ると哲学的な要素も含むなと痛感した。女性たちの議論を書記を担当した男性のオーガストが何かを感じ、女性たちを励まし、ケアをする。オーガストの役割も作品のポイントだろう。色々考えさせられた作品。今年公開したSHESAIDを観たときと同じ感覚だった。未鑑賞の方はエンタメ感覚は捨てた方がいいと思います。
途中退席
今日こそ、神の御業の日。この日を楽しみ喜びましょう。
タイトルなし
多数決取るところがクライマックス
予告で見て小洒落ていると思ったのですが、識字率が低い故なんですね
そして米の西部劇ぐらいの時代?ではなく2010年ボリビア(ウユニ湖がある、南十字星が見える羨ましい) 女性は学校にも通えず家畜みたいな扱い まだまだそのような地が有るのだと知る 闘うを選んでドンパチ大暴れ、自由を掴み取るみたいな話だと勝手に想像していたので肩透かし しかし雰囲気、演技はとても良かった 昨今強い女性の映画がメインなので新鮮といえば新鮮 誰をも傷付けず去ることだって出来るのだ 何だかトムホの出演してたカオスウォーキングを今度は女性側から描いてみましたみたいな感じでした
男性として、社会というシステムの中で、無自覚に利益を得る側にいる
2010 年、自給自足で生活するキリスト教一派の村で起きた連続レイプ事件。これまで女性たちはそれを「悪魔の仕業」「作り話」である、と男性たちによって否定されていたが、ある日それが実際に犯罪だったことが明らかになる。タイムリミットは男性たちが街へと出かけている2日間。緊迫感のなか、尊厳を奪われた彼女たちは自らの未来を懸けた話し合いを行う―(公式サイトより)。
正直に告白すると、序盤は「どうしてこんなに作品が入ってこないのだろう...?もしかしてつまらない映画なのか...?」と感じていた。前評判通りではない作品はままある。個人の好みも、観ているシチュエーションも影響するだろう。
豊かな田園風景と鳥のさえずりに囲まれた女性たちの熱い議論をぼんやりと眺めていた時、「そういったように女性を扱う社会に生まれた男性もまた被害者と言えるのでは?」的なセリフが出た刹那、鈍い痛みを覚えた。
もしかしたら、わたし自身が男性として、社会というシステムの中で、無自覚に利益を得る側にいて、どの登場人物にも感情移入できないから、作品が理解できないのではなかろうかという、どことなく恥に近いような感覚に襲われた。
そのシーンを境に、わたし自身がなり得ない性を持つ彼女たちの話し合いの場面が正視しづらくなった。彼女たちをここまで追い込んだのは、男性という「性」そのものではなく、男性の持つ「無自覚」である。
不遇な環境のせいで識字を持たない彼女たちが、恐怖や葛藤、母性、信仰について、時に理路整然と、時に感情的に吐露しぶつけ合う中で、単にどちらかの選択肢を選ぶのではない結論に至る様は、まさに「止揚」と呼ぶべき気高さがあった。
村を追放されたオーガストが大学へ進み、知識を得て(時々、理不尽に罵倒されながらも)中立な書記という役割として戻ってくる設定に、この映画で描かれた問題の解決が見え隠れする。知ることを増やすことこそが未来。
女たちにも権利はある
珍しくレビューをチラッと見ていて2010年の設定というのは認識していたが、やはり1900年代ぐらいとしか思えないような未発展な村での話。
村の女たちは牛の鎮静剤で気を失ってる間に乱暴され、それを悪魔の仕業とし欺瞞行為を繰り返す村の男たち。レイプ魔の仕業ということならある話かもしれないが、これが村の男たちだということ。女たちを守るべきであるはずの村の男たちだということ。そしてその村の男たちによって、家族までもが傷つけられていたとは、そんな事あるのだろうか。驚愕でしかない。イカれている。
そんな村の男たちに虐げられ傷つけられ、学べるのは男の子供たちだけ。女たちや女の子供たちはは読み書きすら許されず、厚い信仰により赦すという教えが選択肢にある。女たちは、男たちの暴力に抗えない運命を辿るだけだったのだ。
架空の村とは言え、実際に2005年から2009年にあった事件が元となっている話とは驚愕し、なんともやるせない。ほんの10数年前に起きていたという現実には信じ難く心が痛い。
男たちが村を出て戻ってくるまでの2日間で、女たちは男たちを赦すのか、戦うのか、村を出るのか決断を迫られる。この話し合いが女たちにとって初めての命を懸けた選択になるのだ。今まで男たちに意見した事などなく、それでも悪魔の仕業が男たちの所業と分かった以上、自分を、自分の子供
たちを、家族を守るためにどうするべきか。
どう決断したらいいのかあぐね果てるが、最終的にとった手段は女たちにとって未来が開けたに違いないと思いたい。
他のレビューにもあったけれど、2010年の国勢調査で車が回って来たのも違和感を感じるぐらいの村の未発展ぶりだった。そして突然のDaydream Believer。よりその違和感を掻き立てた。
あの国勢調査員 ブラッド・ピットだよね???違う う???
星3.5か4.0しかないから3.5だけど、3.8ぐらいかな。
23-078
評価高すぎて微妙
結局男は、女が怖いのだろうな~~
男たちが揃って出かけてしまった小さな村で
これまで男たちが女性達にやってきた事に対して
残された女性たちがこの後、
どう生きてゆくのかを、女性達で選挙をするも
同数で決着がつかない。
そこでそれぞれの意見を代表する女性たちが
数人で議論をして決めることになり
薄暗い納屋の中で白熱する議論の様子を
丁寧に描いてゆく。
一見時代劇に見える様な昔の装束の女優達。
それがまさか21世紀の話とは!!
薄暗い納屋のシーンの合間に、
女性たちが守ろうとする子供達の遊ぶ姿や、
一人村に残っている男性、
農夫から教師になり、女性たちに同情的な
こころ優しいオーガストと、
レイプ被害によって妊娠中のオーナの
細やかな心の交流シーンなど
納屋の外のシーンが印象的に描かれていて
この女性や子供達に幸あれ!と
心の底から願わずにいられないです。
で、月に8回ほど映画館で映画を観る
中途半端な映画好きとしては
米アカデミー賞の脚色賞受賞作なので
ざっくりした内容は知っていたのですが
予告編の画面から、西部開拓時代の話だと
勝手に思い込んでいたのでちゃんと観て、
その内容に改めて驚愕しました!
もとになった事件そのものがまずショッキング!
21世紀にまだ女性たちに読み書きすら教えないなんて
その女性蔑視はどこの宗教も一緒じゃん!!
宗教とはやはり、危ういシステムなのだな~~
と同時に、宗教の教義と言う名を借りて
女性たちの権利を奪うってことは
結局男は、女が怖いのだろうな~~
女性たちは自分自身の怒りを超えて
子供たちを守るためにある決断をします。
たまたま、旧統一教会問題で
宗教二世の問題がクローズアップされましたが
この映画の中の女性たちは目が曇っていなかった。
女の子達には誰にも蹂躙されずに生きてゆく権利があるはず。
それは親であっても奪えない権利であり
また、男の子達も「加害者にしない教育の仕方」があるはず。
女性たちの議論はそこまで愛に満ちて進んでゆきます。
映画が終わってエンドロール時
音楽の後に自然音が続く。
鳥のさえずりから始まり~~
最後までしっかり聴いて下さい。
人の顔と名前と所属と主張がスッと入ってこない
最初に「寓話」であることを明示して欲しかった
敬虔なキリスト教徒の話なのに、冒頭の投票で、いきなり「赦す」という選択肢が除外されたことに違和感を感じる。
しかも、復讐や殺人につながりかねない「戦う」という選択肢の得票数が、「出て行く」と同数であるということにも驚く。
よほど腹の虫が治まらないのか、それとも自尊心が強いからなのかと思っていたら、中盤で2010年の話だと分かり、こんな閉鎖的な社会にもようやく女性解放の波が押し寄せたのかと、少し納得した。
ただし、いくらアーミッシュのような宗教的なコミュニティだとしても、司法や行政の手は届くだろうし、タリバンでもあるまいし、女性に教育の機会を与えないのは度が過ぎるだろうという疑問が残る。
南十字星が出てきて、初めて舞台がアメリカではないことが分かるのだが、それだったら、これが(解説にあるように)現代のボリビアでの事件を下敷きにした「寓話」であるということを、最初に明示してもらいたかった。
そうすれば、次々に湧き上がってくる違和感や疑問に気を取られることなく、女性たちの白熱した討論にもっと入り込むことができたのではないかと思えるのである。
知識や教養はないものの、知性や理性に裏打ちされた彼女たちの主張には、直接心に響いてくるような重みを感じることができる。
恐怖や憎しみの対象である加害者の男たちが、はっきりと画面に映し出されないため、観客が、討論の行方を、冷静かつ客観的に見守ることができるようにもなっている。
すでに結論は出ているのだが、全員がそれに納得できている訳ではない。
そんな中、彼女たちが、宗教的な「善」の価値観や「子供たちのため」という信念に基づいて、誰もが同意できる解釈を導き出す過程は見応えがあった。
「善なることリスト」を作ろうかな。
未来を見据えた物語だった。
まず、テンポ感が素晴らしく良い。
本題に時間をかけるために、
説明を簡潔に時間をかけず、
しかし分かりやすく見せることに成功している。
さらに、話が進むにつれて見えてくる
人物それぞれのバックグラウンド。
ある人が何故そんな態度をとってしまうのか、
どうしてその台詞を聞いて笑って、
どうしてその台詞を言うときに涙がこぼれてしまうのか。
綿密に作られたその造形に圧倒された。
唯一登場した成人男性の作り込みも良かったし、
キャスティングも最高だった…。
フランシス・マクドーマンドの役柄が若干気にはなったのだが、
おそらく彼女は顔の傷を悪く言われてきたのだろう。
あの村の男たちなら、やりかねない。
だから、外に孫たちを出すのも躊躇った。
自分と同じ目に合わないように。
そう受け取った。
全編を通して思い返したことがある。
全く別の時代、別の国、別の人々。
それでも想ったのは、今まで見てきた周囲の女性たちだし、
自分の女性性のことだった。
色んな苦悩を抱えていたあの女性たちは、この映画を観て
どう思うだろう。
ラスト、本当に素晴らしいものを観せてくれて
ありがとうという気持ちになった。
女性と子供だけで村を出ていく、ああいうのを
映像にして視覚的に観せてくれるだなんて。
これは夢や幻想じゃないんだな、と思った。
信じうる何かがそこにあった。
未来への可能性を信じたくなった。
Sleepy Jean
コレが2010年とは…
怯えずに話ができる場に混ぜてもらえたような気持ち
これから自分達はどうするかを二日間で決める為の、会議でありながら全く「会議」的でない空間と時間に居合わせた。柄は異なっても同じような服で化粧なし、マウントも媚びも根回しもなく議事進行役も居ない。紛糾しても落ちつかせてくれたり謝ったり謝ってくれる。オーナ(ルーニー・マーラ)の存在がみんなの間に信頼を作り出していて、怯えずに一緒に考えて対話する空気がゆっくりと醸成されていった。笑いもあるし母、娘、孫、姪がいる中で一人一人が言葉を述べる。議事録作成は大学出の男性、女性達から唯一信頼されている男性のオーガスト(ベン・ウィショー)。書かれた議事録は自分達のためでなく他者に自分達の思考と決断の経緯を読んでもらうため。
みな、知性と理性と冷静を持ち合わせている。それは何に依るのだろう?信仰心だろうか?彼女たちの決断と行動は自分の子ども達を守るためであり、考える権利を保持するためだ。出て行った先のいつかどこかで、信仰とは、神とは何なのか考えることになると思う。宗教も権力構造から自由ではない。
素晴らしい女優たちとベン・ウィショーのいる納屋、井戸端、屋根の上。立体的な空間の中、干し草の匂いや手触りを感じながらみんなが緊張なく穏やかに話している。ヴァンゼー会議とは真逆で裏返し。それにこの映画には音楽がある。ジョーカー、TAR、そして本作と続くヒドゥル・グナドッティル。
最後のシーンは「屋根の上のヴァイオリン弾き」のようだったが、この映画では話し合いの上で合意のもと自らの意思で立ち去る。強制退去でも逃亡でもない。ただ立ち去る。どこへ?はどうでもよく、地図を手にとにかく離れる、去る、新しい世界へ。
グレタ(最年長の一人)の台詞。示唆があってキュートで空気を和ませる笑いがあって好き💕
1)馬二頭を操って馬車移動するとき溝があってはまりやすい道を行く時は下でなくて遠くを見るといいのよ。
2)この入れ歯大き過ぎる、と外す。
3)「私もうすぐ死ぬ・・・」あ、メガネが曇っていただけ!
モンキーズ…
全105件中、61~80件目を表示