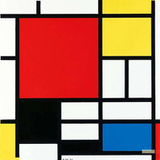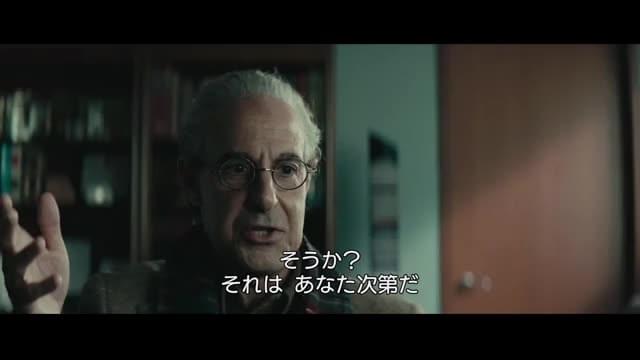ワース 命の値段のレビュー・感想・評価
全93件中、21~40件目を表示
タイトルなし(ネタバレ)
志が高く挑んだ仕事なのに、遺族に嫌われまくって、嫌われても構わないと、それでも挑み続けてるのは素晴らしい事なのだが、それ自惚れず、やり方を変更するのは凄かった。
金持ち?の万年筆を分解してサインを拒むシーンと、
どう補償額が変わったのかが分からなかった。
最後、浮気されてた奥さんが、「相手のことを殺してやりたい」と言いながらも、その子供たちに補償金が降りるよう書類を渡したのは痺れた。
いかに敬意を示せるか、いかに寄り添えるか。
アメリカは弁護士がアンビュランスチェイサーと揶揄されるほどの訴訟大国。マクドナルドのコーヒーでやけどしたとして数億円の賠償金を勝ち取った事案や喫煙者によるタバコ会社への法外な賠償金が認められた事案等々。その賠償額の6割を弁護士が成功報酬として手にするもんだから、こういった企業への訴訟は後を絶たない。
9・11テロの被害者遺族から航空会社に訴訟を起こされると国の経済は大打撃を被るとして、補償金事業が立ち上げられる。これは航空会社を守るための訴訟封じの策でもあり、劇中の「汚れ仕事」という言葉が示すように被害者遺族への人道的支援を第一の目的としたものかは疑問がある。
ただ、国の経済的ダメージを避けつつ、被害者遺族への早急な支援を幅広く行えるということでは評価に値するものなのだろう。訴訟費用を工面できない貧困家庭や、長期間の訴訟による精神的負担などを考慮すると。
かつて民事賠償請求訴訟を多く手掛けてきた弁護士のケンは国を揺るがすテロを目の当たりにして、愛国心から難しい特別代理人の仕事を引き受ける。彼は彼なりの使命感から被害者遺族を救いたかった。
しかし、彼の補償金の算出方法が被害者遺族たちを傷つける。あくまでも民事訴訟においては損害賠償額は逸失利益をもとに算出されるので当然収入の違いで受け取れる賠償額には差が出てきてしまう。それを根拠にした計算方法を聞いて説明会は人々のやじで騒然となる。
学生相手の講義では得意げに命の値段を算出していたケン、しかし今回はそうはいかなかった。人々の悲しみ、犠牲となった家族への思いはけして計算では算出できないものなのだから。
何とか公正な数式で算出した補償額で人々を納得させようと苦戦するケン、しかし申請期限が近づくなか一向に基金への申請数は伸びない。
ケンは見誤っていた。被害者遺族が不満なのは金額に差がつけられてるからだろうと。だが、彼らはけして金額を多くもらいたいのではなかった。国民の一人として自分の家族の命に差をつけられるのが我慢ならなかったのだ。アメリカ国民として証券マンもウエイトレスも犠牲となったのは同じ尊い命なのだから。ケンは数字にこだわるあまりそんな個々の人たちの思いを理解し寄り添う姿勢を示せていなかった。
偶然にも面談することで深く関わることになる消防士の妻との交流や反対派リーダーのウルフとの対話の中で彼は自分の過ちに気づいてゆく。
計算式にこだわるのではなく、自分に与えられた裁量をもって人々の個別の意見を聞き柔軟な方法で補償額を算出する。個々の人々の境遇や思いに寄り添う姿勢こそが大切だと気付いたのだった。固定された計算式に人を当てはめるのではなく、人に当てはめて計算することを。
それに気づいたケンは被害者遺族の話に耳を傾け誠実に対応してゆく。政府の計算マシーンだった彼は個々の遺族たちの事情をくみ取っていった。
そうした彼の態度が、人々を納得させた。人々は国が我々個々人を見てくれてるのだと、敬意を表してくれたのだと。お金の額ではなく、国が遺族に寄り添ってくれたと判断したからこそ人々は基金に参加する。次々と申請は舞い込み補償事業を定めた法案は無事施行されることとなる。そしてその後申請期限以降の延長も認められ様々な不備も改善されてより広くの被害者遺族の救済につなげられることとなった。
始まりは訴訟封じのお国ファーストであった事業が当事者たちの努力により被害者遺族ファーストへと変わっていったのだった。
本作ではケンのパートナーであるカミールやスタッフたちが被害者遺族と面談を続けるうちに精神的に追い詰められてゆくさまが丁寧に描かれていた。実際、それぞれの被害者遺族の話はドキュメンタリータッチで真に迫っており、とても聞いててつらくなる話ばかりだった。恐らく話自体は被害者遺族から聞いた本当の話なのだろう。本作自体が被害者遺族に寄り添った作品としてよくできていたと思う。
また、冒頭で書いたような多額な賠償金目当ての訴訟が乱発されるアメリカ社会への批判を込めた作品とも思えた。
これだけ多くの被害者遺族に寄り添い、困難な事業を成功させたケンやカミールをはじめとするスタッフたちには敬意を表したい。
ケンは政府の予算マシーンから、遺族の悲しみに寄り添う人に変わった。
2001年の世界同時多発事故のワールドトレードセンターへの
航空機の突入。
それはビルに勤めていた人、出入りしていた人そして救助に当たった
消防士や警官など。
その他ペンタゴンへ突っ込んだ航空機の死者など、
7000人の賠償・・・と言う前代未聞の大プロジェクト。
【9・11補償基金プロジェクト】を丹念に記録した
ドラマ仕立ての映画です。
プロジェクトがスタートしたのは事故から僅か3日目のことでした。
政府から指名されたのは《政府の予算マシーン》を自認する
弁護士ケネス・ファインバーグ(マイケル・キートン)。
私の第一印象も《予算カッター》みたいな人・・・そう思いました。
事実ケン(ケネスの愛称)も事務的に事を進めて、早く遺族に賠償金を
渡す事で頭が一杯だったのですが、1人の遺族と話し合い彼の提言を
真摯に受け止めたことから、まったく違うアプローチに変わるのです。
遺族たちは哀しみを誰かに語り、苦しみを訴えたかったのです。
その事にケンは気づいたのです。
そのアドバイスをくれた人はチャールズ・ウルフさん。
妻のキャサリンがいつもより30分早く出勤したばかりに
事故に遭ったのです。
悔やんでも悔やみきれないのはチャールズさんも同じ。
その事をきっかけにファインバーグさんは、一人ひとりの遺族と面談。
延べ900回に及んだ面会。
ファインバーグさんの姿勢は遺族に寄り添ったものに変わったのです。
映画では賠償請求の最終締め切り日の2003年12月24日にあわせて、
あと何年何ヶ月と何日。
申し込み人数は15%。
あと何ヶ月と何日。
申込者はまだたった30%・・・などと、カウントダウンしていきます。
本当に事務担当の職員一人一人が真面目。
チャールズさんの会合を聴きに行きスパイと間違えられる程でした。
一番大きな決断。
それは年収による賠償金とは別に、遺族への精神的な苦しみに対する
補償金額を、予定していた5万ドルから10万ドルに倍増したのです。
より人間らしい誠意ある補償金事業でした。
(賠償金の平均額は一人2億4000万円ほどでした)
映画の中で印象的な二つのエピソード。
同性婚を夢見るカップルの1人が亡くなりました。
彼らの住むバージニア州は同性婚を認めていないのです。
ファインバーグさんは州議会に掛け合い同性婚を認める法律に変えるまで
尽力するのですが、死んだ彼の両親が頑なにパートナーを認めない。
そんな例もありました。
もう一つの例は、消防士の妻で8歳6歳4歳の男の子の母親カレン。
実は夫のニックにはもう一つの家庭があり、
幼い子供が2人残されたのです。
最後の最後まで賠償金を要らないと拒むカレン。
「相手の女が死ねばいい・・そう思っていた。子供の名前は?」
「ジェナとベル」女の子は3歳と1歳だった。
「念願の娘ね」
ニックは娘を欲しがっていたそうです。
亡くなった7000人の一人一人にドラマがあるのです。
ラストでケンの誠意は97%の被害者に伝わり事業は成功するのです。
ケンを演じたマイケル・キートン。
いつものようにカッと目を見開いてオーラを発することもなく、
地味で外連味のない弁護士ケンが悩みつつ一歩一歩地道に努力する姿を
表現して素晴らしかったです。
ケンに成り切っていました。
この映画の姿勢を誰よりも知り演じていました。
人の命
大惨事で人命が失われた時、国や会社が遺族にできることとは‥‥?
初め国の方針通り、計算方式で一人一人の給料にあった補償金を出すつもりだったケン•ファインバーグ弁護士。
最初から皆平等、一律という意見もある中。
同性愛カップル、消防士の兄と弟、を始め様々な被害者から実態を聞き到底ファインバーグ弁護士の計算方式では解決しきれないと痛感するスタッフたち。
また反対に役員待遇の人へ上限引き上げを持ちかけるリー。
補償基金分配プロジェクトである故、湯水の如く出すこともできない。
また図らずも、同性愛カップル、州によって認められない、ややこしいアメリカ🇺🇸、また亡くなった人の両親から認めない、と言われるもう片方の人。
消防士の亡くなった弟の方、あろうことか、
別家族の存在がわかり、弁護士は隠そうとするが。弟の妻は夫に亡くなられ、裏切られダブルショック。夫の兄は知っていて庇う。だけど、この奥さん偉い❗️夫の子供だからと言い聞かせたんだろな。
被害者支援のチャールズと何度か話し合い被害者の気持ちを聞く中で、ファインバーグ弁護士は自分の間違いに気づく。
一人一人と話し、それぞれの事情を聞き考える中で、必ずしも一律に計算などできるものではない、と。
このただただ被害者並びに遺族の為、そして国の為にと無報酬で考え奔走するファインバーグ弁護士の変容を見ることはできる。
しかし、最初の計算方式を取り入れているわけで、どのように人々に分配したのかは描かれていない。
ただ7000人という人数を見れば、ファインバーグ弁護士相当優秀であり大変な苦悩を乗り越え偉業を成し遂げられた功労者と言えるだろう。
『沈まぬ太陽』(特にTV版)でも、被害者遺族への賠償金申請について何年も担当者が足を運び対応する苦労が描かれていた。本作の同性愛カップルの事例のように夫を亡くした妻の為である筈が、夫の両親が口を挟んで来てややこしくなって妻が精神的に追い込まれる様子も描かれている。
また.現在の日本では遺族が被害者が亡くなった際の真実を知ろうと裁判を起こそうとすれば被害者の生涯賃金を算出していく内容でしかできないらしい。聴覚障害を持つ10歳の女の子だったが、親としては障害有りで減額される事に再度ショックを受けてお金欲しさでなく一人の人間として見て欲しいと願っても誤解されかねない現状に愕然とする様子がニュースで映し出されていた。
そして3.11の大川小学校裁判に於いても、県•教育委員会•学校と闘って補償金を勝ち得たが、親にとっては、子供が帰って来てさえくれればいいのである。
2024/8/6たまたま鑑賞。
遺族の話で、夫を亡くした方、夫はエレベーターが満員だとわかると自身は諦めて他の人に譲り次を待つ、と言った。次は来たのか、妻に電話してユーモアも言うが、呼吸できなくなった、と電話を切る。
二度と電話もかかって来ないし、‥。
なぜこんな人の良い方が犠牲になるのか⁉️
犠牲になった乗務員の姉、体調の悪い同僚とフライトを代わってのこと、と。親切にした方がなぜ⁉️と
また改めて思ってしまった。
解なし問題との向き合い方
9・11同時多発テロの事件性は広く知られているが,その後,遺族に対してどのような対応がとられたのかはあまり知られていない。実際は補償基金を設立し,遺族に対して保証金が支払われたということである。だが,原理的に一人一人の「命」に値段をつけることはできない。便宜的に生涯賃金を概算することはできるが,人間の尊厳をそこへ繰り込むことは困難だからだ。ケネス・ファインバーグ(マイケル・キートン)はその「唯一解のない問い」に取り組んだ実在の弁護士である。補償を計算式で合理的に処理していこうとするファインバーグはヒューマニズム観点から批判を受け,遺族の声に耳を傾け,双方は少しずつ歩み寄っていく。ファインバーグは「大切なのは公平さでなく前へ進むことだ」とし,遺族にプログラムへの参加を求める。白と黒,0と100で物事をすべて割り切っていくことはできない。しかし,さまざまな境遇の遺族と対話し,かけがえのない背景を知っていくなかでファインバーグは自らの合理性を手放していく。「死」を数字でなく,個別的なものであるととらえること。ファインバーグがそのことに気づくことで,遺族のプログラム参加率は90パーセントを超えた。真実はここになかったかもしれないが,本作がテーマにしているのは「命に値段をつけられるか?」という深遠な問いであり,この物語それ自体がひとつの解を提示していることに価値がある。さまざまなファクターが絡み合った複雑な問題にベストな解答はない。そこには無数のベターがあるだけだ。そしてそれらはいずれも最後に「人間」という壁にぶちあたる。「人間」は数学的解法が通用しないひとつの「問い」である。それを理解したファインバーグはこの後もいくつかの災害補償プログラムに関わっている。
成長、変化に老若なし
弁護士の成長物語
学び考えるきっかけになる
復興の背景には倫理的に非常に難しい問題があることを学べました。
驚くべきは、この過酷な仕事を無償で引き受けた弁護士がいて、これを成し遂げたことです。
アメリカ同時多発テロの被害者遺族を救済するために立ち上げられた補償基金プログラム。
プロジェクトの特別管理人ケン・ファインバーグは、補償金額の算定式を決定し、被害者遺族の80%の賛同を得るために奔走します。
宣伝文から想像していたのは、人の命を値段をつける算定式の決定プロセスでしたが、それは冒頭であっさり片づけられます。
本作の大部分は、算定式は変更できないけれど、どうにかしてこの条件を被害者遺族に受け入れてもらうために奔走する内容です。
最終的には80%を超える申請を得るに至りますが、主人公が特別管理人として補償基金プログラム制度にどの程度影響を及ぼせたのかよくわからないままなので、大きなカタルシスは感じられませんでした。
ケネス・ファインバーグ氏のインタビュー記事を読んでみると、映画に盛り込むべき大事なエピソードが他にもあったのではと感じられます。
エンターテイメントとして人にお勧めするのは悩ましいところですが、個人的にはとても勉強になる作品でした。
鑑賞後にいくつか関連記事を読んでいると、東日本大震災や阪神・淡路大震災に照らした議論や分析がなされていることもわかります。
いまだ最適な答えがない難題に向き合っている法律家の方々には尊敬の念を覚えます。
「耳を傾けること」の大切さが痛いほど伝わってくる一作
テロの犠牲となった様々な背景を持った人々の補償額、つまり「命の値段」をどう付けるのか、という答えを出すことが非常に困難な問題をテーマに据えた本作、あまりにも大きな問いだったためか、誰もが納得できる結末となっているかどうかは評価が分かれるところではあります。
しかし本作が提示するものとは、明確なゴールや答えではなく、やるせない思いを抱えた人々の言葉の声を聴くことの重要性です。作中でテロの遺族が語る言葉は、たとえ作品用にある程度編集または改変した部分があるだろうとは言え、非常に重みを持って伝わってきます。マイケル・キートン演じるファインバーグ弁護士が、最初は職業意識から業務を引き受けたというちょっと突き放した姿勢から、徐々に遺族の心情に寄り添っていこうとする過程は、大きな山場を設けなくとも十分説得力があり、ここはキートンの演技力が際立っていました。映像も柔らかく全体を包むような静かなトーンで統一されており、キートンの内面の静かな変化と同期しています。
分かりやすい感動を求めてしまうとちょっと微妙な気持ちで鑑賞を終えることになるかもしれませんが、同時多発テロという巨大な悲劇と凶行のこれまでなかなか知られてこなかった側面を知りたい、という人にとっては特に意味のある作品であると言えるでしょう。テロの映像そのものは非常に限定的かつ抑制的にしか使われていないので、そうした直接的な描写が苦手な人も動揺することはなさそうです(もっとも、その分遺族の証言の辛さ、重さはとても大きなものとなっていますが)。
どんなに忙しくても精神的に追い込まれていても、家族や親族とのイベントを欠かさないキートンの良い人ぶりもまた、本作の感銘ポイント!
思い悩みます
命の価値は同じだが、社会的価値は年収ベース。
9/11の7000人の死者に値段をつける汚れ役を無償で買ってでた弁護士の実話。
観ながら人の命の価値やら、裏表やらを考えさせられる映画ですわ。
目標人数になかなか達なかったのは、ざっくり年収ベースの方程式の初期設定額が低すぎたって事だと思う。
あと被害者と言うか遺族がお金では埋められない悲しみなんじゃ!って気持ちと、、まあくれるなら貰っとこ、、と言う気持ちの折り合いを付ける時間が必要だった事なんだろうと思う。
まあ、決め手は一人ひとりに寄り添う信頼関係構築って事なんだな。時間も手間もかかるし、欲望や嘘や知りたくもないダークサイド噴き出して来て大変だけど。
一番凄いと思ったのはエンドロール直前のその後の彼の働きっぷりだった。いくつもの見直しと、再受け付。
そしていくつもの難しい事件を引き受けている。
無償で頑張った元はとれてる。
難しいね。
マイケル・キートン良いね。
初めからすごい悪い人でもなく突然とてもいい人になった訳でも無く。
真面目に働いてる人がごく普通に認められたくて、でも色々制限がある中で最善を尽くそうとした結果。という感じ。
事件のことはみなが知ってるけどその後も人生は続く。いや、続かなかった人の家族の人生、と言うべきか。
お金なんていらないし、人の人生に値段をつけてそれが人の善し悪しなの?価値なの?ってなると本当に難しい。
だって確かに小さい頃から努力して勉強して例えば医者になった、大企業に勤めた。って人とそれなりに楽して、適当に好きなように生きた人。値段をつけるなら、差が出てしまうよね。
でもだからと言ってその人の価値がそれで決まるか。と言われとら違うんだよなぁ。
お金、というわかりやすい価値で人の価値は決まらない。
でも他人からお前はいくらの価値だよ。なんて言われたら………
なににせよ、テロでなくても毎日事故、殺人等々で被害者家族は発生している。
そんなことが起こらない世の中には絶対にならない。
でもいかに少なくしていくことは出来ると思うんだけど………。世の中悪い方にしか進んでない気がするなぁ。
色んな人に見て欲しい。
スゴく泣かせにかかってる訳でも無く、考えさせられますね。
chatGPTには回答できない、、、
chatGPTには回答できない、、、
いや、
GPTだからこそできる、
GPTにしか、
回答できないのかもしれない。
国の論理よりも、
国民の感情が大事。
と、
国の政策の、
本音と建前を逆転させた、
人間の心に向き合う社会への、
歴史的転換点の記録、
その価値→worth。
を
マイケル・キートンと、
周囲のキャストが、
少ないセリフ、
細かな視線、巧みな表情で、
事実を積み上げていく。
worth 価値、数字で表せる価値のようなもの。
劇中のセリフにもあった、
dignity 尊厳。
生涯賃金は数式で計算可能、
だが、
尊厳は数値化できるのか?
本作のメインプロットを主人公のdignityへの気づきと、
捉えると作品のスケールが矮小化されてしまう。
本作は米国社会のあらゆる状況下の国民のdignityに対する具体的な施作、政策の進化、
がメインプロットと捉えると、
本作で、問われている意味を理解しやすいのかもしれない。
【ワース 尊厳の価値】
AIはすでにdignityを理解している。
シン・シンギュラリティは、
尊厳を具体的実践的活動に落とし込むAI、
と、
尊厳を無視して利益を優先するhuman、
との臨界点なのかもしれない。
そう解釈すると、
米国はすでにシンギュラリティは克服可能かどうかは置いておいて、国として具体的政策の試行錯誤の第一歩は始めてる証拠の作品と解釈できる。
【蛇足】
そうすると、
人工知能と人間の、
明らかな能力の差を、
話題にするよりも、
人としての価値基準について話題にする方がいい。
具体的施作の足枷になってる物、事、人、
とは。
つい先日、日本では、
尊厳には価値がない(と捉えられてもしかたない)判断が出た、しかも裁判所の判断。
憲法よりも数式だそうだ。
chatGPTなら一発回答だろう。
ヒトの能力を数値化するという事は、
一定の事実を根拠に、
フィクションを書き連ねて、
積み上げて、
わかったような答えを出すという事。
数字なんて概念、
人は存在する。
適当に答えられるよ、
なあGPT!
不条理な出来事の納め方
命の「価値」とは?
911で亡くなった方々の補償を担う(国の)特別管理人になる弁護士とそのチームの物語。
とても重いテーマをかかげ人の命の価値をどう弾き出すのか?その金額で納得を得られるのか?
その中で彼が選択する道(基準と倫理観)の先に何があるのだろうか。そして何を守れるのだろうか。
それぞれが抱くまた抱えるものを通し、その「価値」を考えさせられ、彼の決断に心が揺さぶられた。
全93件中、21~40件目を表示