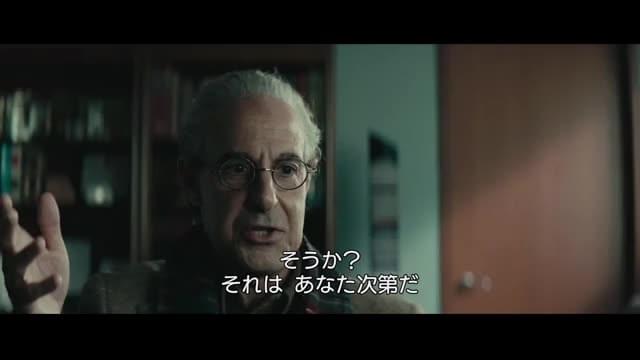ワース 命の値段のレビュー・感想・評価
全92件中、1~20件目を表示
命は金に変えられない、というけれど
人の命はお金には代えられないと誰もが思う。しかし、それを生業にする人がいる。それも酷い意味ではなく、遺族を救うために。911で犠牲になった人々の遺族に補償金を分配する仕事に就いた弁護士が直面する苦難。政府には集団訴訟を防ぐという目的がある、遺族側には大切な家族の命を金でランク付けしてほしくないという思いがある。遺族が本当に求めるものは何か、エリート弁護士が直面する心のひだを丹念に描いた作品だ。
この映画を観て、『「生きる」大川小学校 津波裁判を闘った人たち』を思い出した。津波で子どもたちを失った遺族は真相究明を何より求めていたが、学校側は自らの過失から逃げるばかりで真相を隠そうとする。最終手段で訴訟に踏み切った遺族たちには子供の命を金に変えるのかと心無い声を浴びせる者もいたという。遺族が求める者は金ではなく、尊厳と真相。どうすればその2つを遺族に届けることができるのか、終わりのない問いを、それでも諦めずに当事者たちは続けているのだと思い知らされた。
マイケル・キートンだからこそ体現しえた難しい立場と、その変わりゆく姿に胸打たれる
重く切実なテーマを突きつけてくる良作だ。これは米同時多発テロの発生からそれほど年月が経ってない頃の実話。まだ傷が癒えず気持ちの整理のつかない中で基金説明会に足を運んだ人々の、犠牲者の値段や計算式を突きつけられた胸中はいかに複雑で痛ましいものだったことだろうか。すべての人々を納得させる方法がない中、マイケル・キートン演じる主人公は責任者役として無償で身を捧げる。これは彼にとって疑いようのない正義であり社会的使命だったはずだが、彼の官僚主義的なやり方は思わぬ猛反感を浴びることに。少しバランスを欠くと無神経で気に触る人間に映りかねない役柄を、キートンが実直に演じ、彼の難しい立場と大きな心境の変化を、観客と等身大の目線で分かち合う。彼と理性的に対峙するスタンリー・テュッチの存在感も素晴らしい。人々の悲しみや痛みに寄り添う”あるべき姿勢”は何かを的確に点描していくサラ・コランジェロ監督の筆致が光る。
悪賢い起業家、誠実な弁護士。両極端を演じ切るマイケル・キートンの円熟
「ファウンダー ハンバーガー帝国のヒミツ」(2017)でマイケル・キートンが演じたレイ・クロックは、今あるバーガー店のコンセプトを生み出したマクドナルド兄弟と共同で創業しながら、結果的に兄弟を会社から追い出して莫大な利益を手にする狡猾で憎たらしいビジネスマン。一方「ワース 命の値段」での役は、9.11テロ被害者遺族の補償基金プログラムで個々の補償金額を算定する難しい役目をプロボノで引き受け、さまざまな事情を抱えた遺族らに向き合う誠実で忍耐強い弁護士。両極端なキャラクターなのにどちらも説得力十分で、キートンの演技の幅広さを改めて思い知らされる。
よく知られるようにアメリカは訴訟大国で、法廷物の映画や法律事務所を舞台にしたドラマの人気が根強いお国柄もあるのだが、本作の場合、法律家(+国)と遺族たちが対立から、困難な交渉を経て……という大方の予想通りに話が進むので、盛り上がりに若干欠ける面はあるかもしれない。とはいえ、被害者と遺族の事情に合わせて補償額を算定した実話、つまり命の値段を決める過程をドラマタイズして商業映画にするなんていかにもアメリカらしいし、社会派のスタンスとヒューマンな要素のバランスも悪くない。日本だとこの手の題材はまず映画にならないだろうなとは思う。
対話が果たす正義
飛行機は突っ込まなかったとか
事前に知っていた人がいたとか
ビル関係者は、保険をかけていたとか
崩壊の原因は、巧みに仕掛けられた爆弾だったとか
実は米国という国家が、この事件に関わっていたとか
犯人とされる人々の技能では、操縦できるわけがないとか
陰謀論か、事実かの検証は結局、闇の中になるんだろうけど
本当にこれを計画した人がいたとしたら、人間の心を持ってはいない
いや、最早、人間ではないな
DS達が、金儲けのために簡単に戦争を起こし、ほくそ笑んでいる現代では
他人のために心労を尽くす人々の存在を知るだけでも、希望を見いだせる
事実を元に、これだけ多くの被害者の生の証言を、
全世界に知らしめたこの作品の意義は、到底計り知れないと思う
リアルな映像や叫び声等ではなく
淡々と当事者の言葉で、悲惨さを訴えていくこの構成は、共感できるし見事だ
じわじわと胸に迫り来るどうしようもない怒りにも似た感情が
この映画を、この事件を風化させない原動力になる
たとえ、裁判にしたくなかったから起ち上げた基金だったとしても、
5560人に70億ドル(148億円)も支払う米国って凄いと思う
どこかの国では、地震の復興資金も当事者に届かず、その地域はほったらかしにされ
枠の被害者にも、アレが原因だったとは、ほとんど認定しないのとは
まさに、雲泥の差だ
プログラムに参加しなかったのが、わずか94人
勿論、金額的にも内容的にも不満を持ってる人が多いのは分かるけれど
この基金が、2003年に終了するも 2011年 2019年に
再開され、延長されたというのは驚きだ
ケン・ファインバーグが主役なのはわかるし、マイケルは適役だったのだけれど
チャールズ・ウルフこそ、ヒーローでもある
2人の絶妙な関係と、大人の対応が、この基金の成功へと導き、多くの人が救われた
心残りは、対象者として認められなかったゲイの存在だ
でも、久々に、いい映画を見た気がする
派手さはないけど
人の命に値付けする仕事
9.11同時多発テロ事件の被害者への補償基金プログラムの管理人に指名された弁護士の物語。
補償金算定のプロである彼は、遺族の境遇に胸を痛めながらも、補償基金プログラムが設立された趣旨に則り、管理人としての使命を果たすべくプロ意識を発揮して効率的にプログラムを構築します。
つまり、冒頭で明かされる舞台裏の通り補償基金プログラムとは、あまりに多い対象者に対して最小の補償金で済ませるために設立された、という目的に従って。
亡くなった時の年齢、年収、扶養家族の人数。
これらの要素から数式で導き出される「合理的」な金額。
WTCに入居していた金融機関に勤めるエリート達。
救助のさなかに命を落とした警察官と消防士。
清掃、デリバリーなどに従事していた低所得の移民たち…
彼らの命の値段はそれぞれに異なると。
人の命の値段は同じではないことに遺族たちは深く傷つき、プログラムに反発します。
亡くした人に言いたかったこと、言えなかったことへの後悔。
プログラムの期限である2年あまりの日々の中で否応なく明かされる故人の秘密。
故人と遺族たちの人となりを深く知るにつれて、弁護士は人間の命を数式で金銭価値に換算すること疑問を抱き、ついにある決断をします。
そしてスピード感溢れるクライマックスヘ。
どうすればよかったか!?
最近話題になった映画のタイトルのごとく、何が最善だっのかという思いは繰り返し、誰の胸にも去来するのではないでしょうか。
だからこそ、我々は常にその時々で最善だと思う選択をし続けることが大切だということを改めて考えさせられた映画でした。
驕りと改心
アメリカ同時多発テロ事件。死傷された方々の補償を任された弁護士の苦悩と再生を描く物語。
実話を基にした作品のようですね。何気なく鑑賞を始めましたが、とても良い作品だったと思います。
映画は、主人公ケン・ファインバーグ再生の物語。
理論家で数字に強く、その強みを屈指して弁護士の頂点に上り詰めた主人公。ただ、成功の過程で、大切な人間性、感受性が失われて行きます。
そんな彼が、7000人もの悲嘆にくれる遺族の感情を理解出来ずに怒らせ、立ち往生します。
補償チームのメンバー、遺族の人々とのかかわり、それによる主人公の心境の変化がとても丁寧に描かれていて心に迫ります。
マイケル・キートンやスタンリー・トゥッチ等、役者陣の演技も素晴らしく、隙がない作品でした。
私的評価は4.5。
最高点を付けるには少し地味過ぎるように思われ、少しだけ評点を落としました。
可哀想可哀想言うだけの先が観たかったのに
命の値段をつけなければならなくなった主人公が、命に多寡はあるのか?と苦悩する物語だとばかり思っていた。
実際、その要素が全くなかったわけではないし、思い込んでいた自分に非があるので、違ったことによるマイナスは加味しないようにしたつもりだ。
それでも低評価になってしまったのには理由がある。
この作品が、どんな物語だったかというと、過剰なほどに被害者可哀想でしょ、遺族可哀想でしょ、そしてアメリカ可哀想でしょ、するだけのものだった。
確かに亡くなった方は悲劇である。そんなこと言われなくても分かる。そういった要素があることも構わない。しかし過剰だ。
はっきり言ってそれしかなかったともいえる。
被害者や遺族が酷い目にあったことを見るドキュメンタリーが見たいのではない。そんなものが見たいなら最初からそれを観る。
言い換えるならば、「作られた」映画が観たいのである。もう分かりきっている被害者可哀想以上の何かを、創作でもいいので望んでいるのだ。
例えば、「ものすごくうるさくて、ありえないほど近い」のように、被害者可哀想、遺族可哀想からもう一歩進んだ部分が欲しかった。
テーマがテーマなだけに内容が悪かったとは言いにくいし、実際悪くもないと言えるが、映画としては全く面白くなかった。
唯一面白かったと言える部分は、経済の安定のために補償金を出すってところくらいだろう。そんなこと考えたこともなかったので、最初から善意などない訴訟大国の恐ろしさを見た気がした。
人を導くのは理動ではなく感動!試される起業家精神!
公平さとはなんなのか?を考えさせられる作品でした。
主人公のケン・ファインバーグは単なる弁護士ではなく起業家のような挑戦者として、
混沌とした状況の中で命の価値を金銭で評価するという難題に立ち向かいます。
困難に直面した時、起業家がどのように問題を解決し、人々を救うのか、その姿がリアルに描かれています。
起業家としての視点で見ると、彼の役割はリスク管理や利益追求だけでなく、社会的責任を果たすことが求められます。彼の決断は被害者遺族の人生を大きく左右するため、その重みがひしひしと伝わってきました。
葛藤とともに、弁護士事務所のチームと共にこの巨大なプロジェクトに取り組んでいるため、個人の判断が周りにも大きく影響していました。
ケンのチームがどのようにして信頼関係を築き、共に困難を乗り越えていくのか、そのプロセスは起業家精神の本質を描いていて、私自身の活動にとっても身になるものでした!
合理的な人には新たな価値観を知るものとして、特におすすめですが、
すべての起業家やビジネスパーソンにとって、リーダーシップと社会貢献の真の意味を再認識させてくれる作品ですので、ぜひ一度、ご覧になってみてください。
あなたは橋じゃない
ケン・ファインバーグ。ユダヤ人弁護士。9.11の補償で、人に値段をつける「汚れ仕事」をかって出る特別管理人。
この補償基金プログラムの反対派の先鋒チャールズ・ウルフ。
相反する二人の掛け合いが本作の見どころ。マイケル・キートンとスタンリー・トゥッチ。彼らの激論に補償対象者約7,000人の命運が掛かっている。
被害者の哀しみの有り様も様々だ。命に対する考え方もそれぞれ違う。政府の関係者たちも好き勝手なことをまくしたてる。
この板挟みはきついぞ。そんじゃそこらのクレーム処理とは訳が違う。
「あなたは橋じゃない」
ウルフはファインバーグは言う。
いい格好して、単なる懸け橋になろうという魂胆はあさはかなのかもしれない。
落としどころが極めて難しい。
が、本作は、落としどころを学ぶには、最強のバイブルだと思った。
テロで亡くなった人の生命に値段をつける。 一定の計算式に基づいて金...
実話物で学ぶ
国家側を主人公とした映画
難しい話でも感動
2001年9月11日の同時多発テロで、アメリカ政府は被害者救済のために基金を設立。遺族と交渉するために、ケン・ファインバーグが率いるの弁護士団が引き受ける。独自の計算式で保証金の分配をしようとし、基金への申請者80%以上を目指すが。
テロ発生直前から描かれていて、みるみる広がる緊迫感に悲しくなります。ファインバーグはおごりもあったかも知りませんが、「汚れ役」を無償で引き受けたことに驚きました。困難かつ多くの補償を扱ってきたという自負で引き受け、事務的に処理しようとするファインバーグだったが、想像以上の難題に直面。面倒な存在だったウルフが誠実で重要な役割となり、ファインバーグは被害者に寄り添う姿勢に変化させます。お金の難しい話ですが、感動しました。遺族の電話が、弁護士の「訴えろ」という売りこみで鳴りっぱなし、というのはひどい話です。具体的にどう配分したのかは触れられていなかったのが、ものたりない。
被害者の心の傷の深さ
<映画のことば>
すべての被害者と遺族とが損害賠償を求めれば、会社は潰れ(アメリカ経済は破綻に瀕す)る。そうなれば、テロリストに屈したのと同じ。流通も出張の便も停滞、経済全体が機能しなくなる。まさに国家の危機です。
航空機を乗っ取ってワールドトレードセンタービルに突っ込ませるという不法行為をしたのはアルカイダな訳ですから、最終的には、その賠償責任はアルカイダに持っていく以外にない訳ですけれども。
どっこい、個々の乗客は航空会社との契約(航空機による旅客運送契約)に基づいて飛行機に乗ってる訳ですから、最終的に航空会社がアルカイダに求償するかどうかは別として、求められれば、直接に航空会社は乗客に対して債務不履行責任(乗客を安全に目的地まで空輸する義務の違反)を負わなければならない立場。
そして、乗客以外の被害者に対しては、自社の航空機による死傷事故として、直接の不法行為責任。
好き好んで外国のテロ集団を相手に賠償請求するという人は、数としてそう多くはないでしょうから…。
結局のところ、9.11の被害者は、まず航空会社から賠償を受けることを考えるのが穏当なところ。
確かに集団訴訟を起こされたりしたら、その対応だけで、とんでもない費用(弁護士代などの訴訟費用と、訴訟の処理に関わる職員の人件費)というお話になることででしょう。
(よほど極限的な事例ででもなければ、訴訟を見越して費用を予算し、必要な人員をあらかじめ雇用しているケースなどない。)
航空会社が破綻してしまい、飛行機が飛ばなくなると、ビジネスはたちまち行き詰まり、経済そのものがストップしてしまうかも知れません。
何せ、国土の広いアメリカは、海外はおろか、国内の移動も航空機頼みというお国柄。
それに、そんな大規模な事件が係属することになる裁判所の方だって、人員的にも予算的にも、そんなキャパシティは見込んでいない―。
おそらくはパンクしてしまって、他の訴訟事件も処理できない事態に陥ってしまい、司法機能も麻痺してしまうことでしょう。
そこで、政府が(おそらくは航空各社の拠出も得て)基金を作って被害者に賠償金を払うという便法を採ることで、被害者の要求が航空会社に対する訴訟に移行することを防いで事態を鎮静化する(悪い言葉で言えば、被害者にお金を握らせて、そのまま厄介な問題にフタをしてしまう)ー。
ファインバーグ弁護士が特別管理人とやらに就任した、この補償基金の目的は、ざっくりと言ってしまえば、そういうこと。
覚悟の上で、敢えてその「汚れ仕事」を引き受けたファインバーグ弁護士には、社会的意義のある仕事に従事するという男気もあったのかも知れませんけれども。
しかし、それまで弁護士として「負け」を知らなかった彼には、この困難な仕事も、自分なら片づけられるという自負もあったのだろうと思います。評論子は。
つまり、客観的な計算式こそが、被害者の納得を引き出す切り札だと(負け方を知らないという)彼はは考え、そこに勝機を見いだして、この仕事を引き受けたことも、疑いがないと思います。
「調停のプロ」として、多くの事件を解決してきた自負が、彼にそう考えさせたのでしょう。
そのことは「いつも通りの仕事をすれば、きっと大勢の人を救える」と論じた、事務所のスタッフを前にした彼の演説からも窺われます。
(このプロポノ・パブリコを成功させれば、彼の「敏腕弁護士」としての評価は確実なものとなり、弁護士業務の上でもそのメリットは計り知れないという胸算用もあったことでしょう。本作には描かれてはいませんでしたけれども。)
補償金には政府の公金も含まれる以上、飽くまでも客観的な基準(計算式)が必要とするファインバーグ弁護士の主張と、補償に当たっては飽くまでも個々の被害者・遺族の実相を見るべきだとするチャーリーの主張を軸に、事態(本作のストーリー)は展開するのですけれども。
しかし、被害者は、ファインバーグ弁護士が想定していたよりも、被害者・遺族の心の傷は、ずっとずっと、もっとずっと遥かに深かったーそれが、彼の一番の誤算だったのだと評論子は思います。
これだけ桁違いの被害を受けていれば、単なる交通事故や医療過誤などの賠償事案とは、被害者・遺族の心情は、比べ物にならないほど複雑だったと。
そのことに思いが至ると、なお、9.11の被害者・遺族の心の傷の深さを思わずにはいられません。評論子は。
「いろいろな人が電話をかけてきて言う。あなた方は補償金を受けろ、弁護士たちは訴えろと。でも、誰も、ご主人のご遺体が見つかりましたという電話はくれない。もう、電話はいらない。」というカレンの台詞が、耳に残って離れません。
彼・彼女らの心の傷の深さを静かに静かに、しかし鮮明に浮き彫りにする一本として、佳作であったと思います。
(追記)
まず、カミールという得難い優秀な助手を得ることができ、次いで、実は「敵側」であるはずの被害者・遺族の側からもチャーリーという協力者(理解者?援助者?)を得ことができた。
ファインバーグ弁護士が大役を果たすことができた理由も、人を得たことが大きかったのだろうと思います。評論子は。
そして、カレンは、妻としての自分のプライドは脇に置いてまで、亡き夫の隠し子の今後を心配し、ファインバーグ弁護士に彼・彼女らにも補償金が渡るように手配を頼む―。
やっぱり、この世は、人と人と、そして人との関係で出来上がっているのだということを、改めて実感した一本でもありました。評論子には。
(追々記)
今の法律では、損害賠償はお金ですることになっているので(金銭賠償の原則)、例えば死亡交通事故の被害者や遺族に対する損害賠償も、慰謝料や逸失利益(生きて働いていたなら得られたであろう収入から、想定される生活費の額と中間利息=都度に入るはずだったお金がいっぺんにもらえるメリットを評価したもの=を差し引いたもの)が、お金で支払われることにはなるのですけれども。
この金額が、しばしば「命の値段」として、いわば独り歩きをしがちなことには、なんともやりきれない思いがします。評論子は。
「金銭賠償が原則だ」というのは、たいていの場合、原状回復ができないから(死んだ人を生き返らせて遺族の下に帰らせてあげることは、加害者=生身の人間には不可能)。
それで、次善の策として、いろいろなことに遣えるお金というモノ=金銭で賠償しようというだけの話な訳ですから。
要するに、「お金を払うことなら、加害者にもできる(はず)」というだけの話。
決して、それが「命の値段」を指し示したりするものではないのですけれども。
賠償額は飽くまでも賠償額なのであり、それ以上でもそれ以下でもなく、いわんや「命の値段」などではあり得ない―。
そんな単純な賠償額を「命の値段」という風潮は、何とか改まらないかと思うのも、評論子だけではないと思います。
会話ができる大人とできない大人
映画「ファウンダー」でマイケル・キートンが好きになったので、ほぼジャケットがファウンダーな本作も鑑賞してみたくなりました。
遺族救済を目的とした補償基金プログラムは、テロの被害者の人生に値段をつけることで残された者に対する救済としている。その「値段のつけ方」は、金持ちも貧乏人も平等で一律に払われるべきだ…とすれば、金持ちに合わせることになり莫大なお金が動くことになる。それを避けるために“プログラム”と称して被害者が生きていたらと仮定した先の人生に値段をつけてその額を支払い救済する。
計算式を前面に押し出し淡々と説明し遺族に理解を求めようとする主人公ケン、自身も妻を亡くし遺族に寄り添いコミュニティを構築し、補償基金プログラムに意見をするチャールズ。
印象的だったのは、最初の補償基金プログラムの説明会の後、ケンとチャールズのやりとりで「私はこれからあなたを叩く」と宣言するところ。それに対しケンは「…そう。残念だ」と言う。
日本なら「これからあなたを叩く」の返しは、「え?」になって、陰気な感じになりそうです。意見を主張し合うことを前提としている、意見を交わすことが当たり前にある。相手が自分と違うことも当然であると常に思っているからこそ「そう、残念だ」と返せる。こういう平然とした会話が日本に足りない。
会話ができる大人は、主張を聞く。ケンとチャールズは、互いの主張を聞き入れたからこそ、良い方向へ導けたのだと気がする。訴訟になれば時間もお金もかかる、裁判中はずっと悲しい出来事を思い出さなければいけない。早期解決を求めることは、生きてる者を次に進めることにもなる。国側と国民側の代表で話し合い出た折衷案に納得した人らが95%いた。
話し合い・主張を聞き合うことの大切さがこの映画にはあるかなと思います。
タイトルなし(ネタバレ)
志が高く挑んだ仕事なのに、遺族に嫌われまくって、嫌われても構わないと、それでも挑み続けてるのは素晴らしい事なのだが、それ自惚れず、やり方を変更するのは凄かった。
金持ち?の万年筆を分解してサインを拒むシーンと、
どう補償額が変わったのかが分からなかった。
最後、浮気されてた奥さんが、「相手のことを殺してやりたい」と言いながらも、その子供たちに補償金が降りるよう書類を渡したのは痺れた。
全92件中、1~20件目を表示