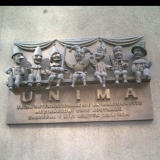きみの色のレビュー・感想・評価
全259件中、181~200件目を表示
若者のキラキラした青春を描くことに定評がある山田
山田は今回も、高校生くらいのヤングの日常生活に散りばめられたきらめく一瞬を丁寧に、鮮やかに描いてくれましたね😀45分くらいで「やめてくれぇ...もうキラキラはたくさんだぁ...やめ...」ってなるくらいキラキラした青春映画でした
主人公はけいおんの唯ちゃんをもっとフワフワにした妖精みたいな子で、主人公たちに対して否定的な人も、意地悪や醒めたことをいう同級生もいないので、現実的な舞台設定の割には物語的にちょっとリアリティーないというかぬるくて「それでいいの?」となる部分もありましたが、そういう世間との軋轢を表現したい作品でもないと思うのでまぁいいのかな
個人的には、なんとなく見終わったあとの感じがバグダッドカフェ見た後の様な後味でした
おばあちゃんのヴィヴィアンっぽいジャケットとかキャラが立ってて良かったです🤗
きみの色、わたしの色、山田尚子の色
『リズと青い鳥』以来5年ぶりとなる山田尚子監督の長編アニメ映画。
オリジナルとなる新作で描くのは、『リズと青い鳥』や出世作で代表作である『けいおん!』同様、監督の得意とする“青春×音楽”。バンドを組んだ女子二人と男子一人。
思春期を描かせたら右に出る者が居ない繊細な心理描写と現アニメ界随一の映像センス。8年前の重たい題材の『聲の形』も大ヒット。川村元気がプロデュースで山田作品に初参加し、細田守や新海誠に続けるか…?
今年のアニメ映画の中でも注目と期待の一本だが、賛否両論。
“賛”は期待通りの山田作品の声だが、“否”は作風や内容などを指摘する声多々。
しかし、これが山田作品ではなかろうか。
昨今のアニメーションはどうしても、個性が立ったキャラ、メリハリのある展開、劇的な感動などが求められる。作る側もそれを意識し、見る側もそれを期待。人気や大ヒットに繋がる。
『けいおん!』などで“日常系アニメ”が人気を博したのは一昔前。アニメーションで“日常”を描くのはなかなかに難しい。
山田監督はそれを描き続けている。何気ない日常の一コマやナチュラルな姿。『けいおん!』は元より、『たまこまーけっと』はその極み。ずっとこのスタイル。重たい題材を扱った『聲の形』が稀だっただけ。
内容については一理ある部分も。トツ子は何故人の感情が“色”で見えるのか。きみが中退し、祖母と暮らす理由。母親からの跡継ぎに悩むルイ。これらの背景が今一つ描き込み不足。
説明過多な描写は端から描くつもりは無かったのかもしれない。あくまで、3人の青春が織り成すハーモニー。
そうなってくると、内容や作風云々より、感性の好み。これが自分に合うか、否か。
“人の感情が色で見える”というトツ子の設定も独特の感性。『聲の形』でも人の顔に✕印が見えるのと同様に、“青春”という視点を具現化。思春期の複雑な年頃に見たくないもの、その時しか見えないもの。その視点が秀逸。
好みの問題は仕方ない。しかし個人的には、期待通りの山田ワールド。
繊細で自然でありつつ、ふわっと温もり豊か。とにかく終始、心地よかった。あまりに心地よくて、このまま眠りに就きたいと感じたほど。
3人が組んだバンド“しろねこ堂”による劇中オリジナル曲。
きみのしっとり系やミスチルが手掛けた本作の主題歌もいいが、トツ子のユニークな“♪︎水金地火木土天アーメン”。『けいおん!』の“放課後ティータイム”や“ふわふわ時間(タイム)”と通じる青春の可愛らしさ。
トツ子は唯やたまこタイプのおっとりマイペース。
きみは澪タイプのクール美少女。高石あかりが歌声も披露。『ベイビーわるきゅーれ』で気になってから、売れっ子ぶりが嬉しい。
ルイの繊細さと優しさ。テルミンを使うのも目新しい。
3人の友情とも淡い恋とも言える関係。その距離感も絶妙。
“シスター・ガッキー”が昔やっていたというロックなバンド“ゴッド・オールマイティー”が気になるぅ~。さわちゃん先生みたいな…?
3人各々が抱える悩みや感受性。
ネガティブな事ばかりじゃない。
美しさ、明るさ、楽しさ。
それらを全て込めて歌う。今この青春の時を。
別れ。旅立ち。「頑張れー!」のエールも立派な歌だ。出会った喜びと幸せ。
『けいおん!』『たまこまーけっと』の可愛らしさ。
『聲の形』の複雑さ。
『リズと青い鳥』の繊細さ。
本作もまた“らしさ”たっぷり。
これが山田尚子の“色”だ。
何もかもが悪い意味で『甘い』駄作
まず前提として自分はリズと青い鳥の大ファンです。何回も見てその繊細な感情描写と、甘えのない客観的かつ愛に満ちたふたりへの目線に感服しました。
聲の形も、展開が強引なところはあったがそこそこおもろかったです。
だけど、今回の映画。
なんですか、これ?
ただただ思いつきと作者の都合で流れていく強引な展開、その割にドラマの軸もなく散漫で、山田尚子さんの好きをぼんやり並べただけの価値のないもの。
キャラクターの葛藤も浅く、その解決もやりたい演出のオマケで「なんとなく形だけ整えた」ようなもの。
なんか名作作った監督さんって、自分に甘くなって視野が狭くなって、こういう作品に逃げ込みがちですよね。
押井守がパト2、攻殻機動隊以降、パッとしない思い込みの垂れ流し的作品を続けてたことにも近いです。
原作キャラをお借りして、足りない部分を埋めてもらって、良い距離感で作品作ってた一番評価されてた時期を忘れないで生涯謙虚に創作してもらいたいものです。
後、作品内での「音楽」の置き方が本当に雑で、響け!ユーフォニウムというあれだけ真剣に音と向かい合った作品からなんも学んでないんかなと。
練習もろくにせず、才能裏付けもなく(色がどうこうといった曖昧なものはありましたが)、思いつきでパッとやったものが、何故か大評価されて客は踊りだす…みたいな作者の内面願望ご都合世界。
そもそも見せ場のライブシーンに関してもたいしたドラマがなく、とりあえず置いただけの家庭の事情が「なんとなく」解決するだけで感動のかけらもない。
雰囲気だけで良いという一部のファンだけ見て、これで良いんだと突っ走ることがないように、謙虚に初心に帰ってほしいと山田尚子監督には心から思います。
大好きだった作家が、これから一生自己愛垂れ流していくだけの作家に変貌することほど悲しいことはないので。
でもまぁそういうの心地良いんでしょうね。
そういう「気持ちよく作ってるな」というのだけは悪い意味で伝わってた映画でした。
まぁとりあえずご都合なキャラの発作で話を展開させる開き直り、演出家のエゴだけは最低限なくして欲しいものです。
ぽい、がツマラン。平家物語は快作だったが。
ガッキー
危なっかしい
殆ど初心者の3人でバンドを組んで、人前で披露するなんて何だかとても危なっかしい感じがしましたが、それなりにまとまってたし、みんなも乗ってくれて良かったですね。何となく色んなものから逃げていた3人が前を向いて行くキッカケになって良かったです。
淡い青春の1頁 。
トツ子、きみ、ルイがとつじょバンドを組むことになり友情を育んでいく。
トツ子の ”バンドやろーぜ” 発言が唐突過ぎて、言った本人すら、アワワヽ(;´Д`)ノ、私はいったい何てことを口走ってしまったんだ状態でうろたえてしまっている。
カトリック系の高校に通い毎日祈りを捧げる敬けんなクリスチャンだから、神の啓示、天啓が閃いたに違いない(^^)。 「汝ら3人、バンドを組むべし」
トツ子をしろねこ堂に導いた白ネコさんも神の御使いで、3人の出会いも神の御業であり奇跡の出逢いである。ウンウン(^^)。
ただしルイ君は”作永きみ”をナンパした感がチョッピリある。行きつけの古書店でキレイな同世代女子がギター弾いているとなれば、そりゃあ同世代男子が気にするのは当然である。
やっぱしルイ君、チョッピリではなく、ガッツリ ナンパである。
3人にはそれぞれ抱えた悩みも有るのだが、それを深く詳細に描いてドラマにして行くわけではない。回りから見れば別にドラマチックでもセンセーショナルでもない普通の日常かもしれない。
だけど3人にしてみてば新しい出会いとバンド活動はかなり刺激的であり、個々に抱える事情も当人たちにとっては重いものである。そして映画ではそれに伴う喜びや悲しみの感情が、表情、しぐさ、色、音楽で細やかに表現されていく。
印象に残った所など
・トツ子が学校を辞めたきみを探す。だけどトツ子は、きみの色を見つけられない。トツ子の回りは白く色褪せてしまう。
別れや何かを失ったことで心にポッカリ穴が空き、空虚感から世界が色褪せて見えるのは、これまた皆さまご存知のとおり。
・トツ子ときみが懲罰のゴミ拾いをする。これ高校時代のの思い出としていつか懐かしく思い出されるやつかもしれないと思った。
・シスター日吉子がトツ子にロック系のバンドGod almightyをやってたことを消し去りたいと言うと、トツ子はお気に入りの祈りの中の一節 「変えられないものは受け入れるウンヌン」を伝える。
「おお、シスターも若い頃はブブイブイ言わせてたんだな。けどシスターにとって消し去りたい黒歴史なのかな? 」 などとも思った。
・島を去り東京へ向かうルイ君。ルイ君の乗る船に気づいたきみは埠頭を走る走る。埠頭を走るきみにルイ君も気付く。僕はこの船から見た埠頭とそこをダッシュするきみの遠景が1番好きな場面だ。トツ子も後から走る走る。
埠頭の端まで来た2人は船に向かって大声で叫ぶ。この時のきみの叫び声がスゴくて、声優さん声つぶれちゃわない?大丈夫?などと余計な心配をする。
・観賞後、ポスターのタイトルを見て 作永きみの ”きみ” と”君” のダブルミーニングであることに気付く。
気付くの遅えよオレ、何でフライヤーや 映画.com の解説読んだときに気付かんかなあ。せめて鑑賞中には気付けよと思った次第である。ずっと ”君” だと思ってた。
世界がきれいに見える、素敵な時間を映画館で。
ルックバックを観にいくたびに目にしていた本作の予告編。
感じる映画だと期待して鑑賞し、素敵な時間をすごせた。
トツ子がみる色とりどりの世界に序盤から心を奪われる。
長崎が舞台ということで、土地ならではの花やきれいな海はもちろん、人々まで色がついて見える、こんな世界があったらな、と思う。
キリスト教の学校や教会の神聖さ、静けさも、鑑賞者の背筋が伸び、作品に集中できる環境にさせてもらった。
キャラクターも優しくも繊細なタッチで表情を見ているだけで楽しい。万人に媚びず、アニメアニメしてない作風に好感が持てる。
声優は「色」という観点では、声に色がつきすぎていない俳優陣がとても良かった。たぶん有名俳優が声をあてると、それだけでイメージが引っ張られてしまっただろう。
そして、この作品のもう一つの中心である、音楽。
「音が色に見える」という言葉の通り、キャッチーで、楽しくて、鳥肌がたってしまった。
きれいで美しい世界観の中でロックとポップな楽曲のギャップが良い刺激になっている。
物語に大きな展開はなく拍子抜けする人もいるかもしれないが、あくまで「色」を際立たせるための土台のようなもの。
ストーリーの浮き沈みで観客の気持ちが動いては雑音が混ざってしまうので、ちょうどよかった。
色で、光で、音で、そして表情で楽しむ、素敵な作品だった。
水金地火木土天アーメン〜
ほっこり
変えられぬものを受け入れる冷静さ
ストーリーが弱く監督の趣味全開の作品?
設定は長崎のミッション系の学校で雰囲気はありますが、ストーリーが貧弱です。
人間関係の描写も「色が好き」だからということで済まされいる印象を受け、自分自身を登場人物に投影したりすることは困難です。
また、「花」「鳥」「動物」「食べ物」のカットがたくさん出てきますが、ぶつ切れでストーリーの腰を折っています。
エンディングのMr.Childrenの歌が浮いているような印象を受けました。聲の形の際のthe whoのMy generationの方がまだ違和感なく聴けました。
昔のジブリは鈴木敏夫氏が上手く大衆化したと聞いています。山田尚子監督の才能は素晴らしいと思うので上手く周りのスタッフが大衆作品に落とし込んで欲しいと思いました。
すごく優しい気持ちになれる
「けいおん!」からのコンビ、山田尚子監督と吉田玲子脚本作品なので公開を楽しみにしていました。
人に色を感じる女の子トツ子が綺麗な色を持っていることで惹かれたきみちゃんとひょんなことでバンドを組むことになったルイ君の3人の青春物語。
物語全編、悪い人が出てこないからスリルやサスペンスとは縁遠く、観る人を選ぶかもだけど、自分としては優しい雰囲気は良いなぁと思うし、観終わった後もふわりとした気持ちになりました。(特に学校の先生であるシスター日吉子の心配りはジーンとするものがあった)
京アニ時代の作品「リズと青い鳥」に通じる、いやそれ以上のゆっくりとした流れで、最後の方はきみちゃんがルイ君に恋している感じが出てるんだけど、それがほんのりと感じるところで抑えていることがすごく好ましかった。
クライマックスのバンドの演奏も素人っぽさが出ており、(楽器もキーボード2人とギターとテルミン??)今のブームであるバンドアニメとは一線を画す物語と感じました。
教会と市内電車で九州出身ならすぐに舞台は長崎市内だと思いましたが、エンドロールで上五島ってあったから、えつ!ルイ君は上五島に住んでるの?長崎市内と上五島ってそんなにすぐに行けるの?って疑問はありますが、その辺はアニメの御愛嬌ってとこですかね。
謎、ふんわり不思議系、意味不明
水面のきらめきを見ているような感覚と近いのかも。
賞を取るのも納得 絶妙なバランス感に拍手
話題に上がり始めてから情報をなるべく耳に入れずに鑑賞。
先入観は少な目での感想。
3人だけじゃない 先生や親も含めてそれぞれが良い距離感だった
出会いの場所となったしろねこ堂もワクワクさせるけどファンタジー過ぎずステキだった。
もっと色をゴリゴリに押してくるかと思ってたけどそうじゃなかった
色についての能力が一つの色になっているっていう感覚は見事だったし
音楽で個性を出し、それぞれの色が混ざる、包み込む表現は美しかった
ステキなセンスの世界観。世界に受ける世界観だと思った。
不思議さと現実の交差するアニメの世界でテルミンをぶち込んできてカセットに録音
表現は語彙力無くて申し訳ないけど正直しびれました。
見てるだけ、聴いてるだけで鳥肌が立つことが多く、さすがの展開と音楽。
海外の人だったら終わったらスタンディングオベーションだなーと
自分も拍手をおくりたいと思いながらエンドロール後も席で少し余韻に浸っていました。
先生も見事だったなー。ガッキーぽい役だなーと思ってたら
そのままガッキーだったのはちょっとうれしかった。
映画館で観るべき作品。
がっかりしました。
半年前から楽しみにしていた本作品。
端的にいうと全く面白くありませんでした。ここまでお金を払って後悔したのは、過去を振り返っても覚えがありません。
主人公日暮トツ子は人を色で識別する女の子なのですが、まず第一にこの設定がいまいち活きていない気がします。
様々な葛藤や悩みを前にしてそれを色で表現するのかと思いきや、特段何か起こることはなく淡々と物語が進んでいき観ているこちら側は見事な肩透かしを喰らうことになります。ちなみにこの現象は他のキャラクター、ひいては作品全体で行われます。
それでも時には各場面で色が交わり、そこから発展するようなこともあるのですが、私的には誰かとの対話や他の人物が感情を波立たせた瞬間には「こういう色になるんだ」といった内面での発露を視覚的にわかりやすく表現して、もっと色を全面に押し出した内容にすれば良かったと思います。
他二人のバンドメンバーについても色々ありますが、特に作永きみの退学に関しては疑問が浮かぶばかりです。高校生という親の庇護下にありながら(彼女の場合は祖母)独断で学校を辞めるという決断をする、というのは百歩譲ってのみこみましょう。ですが、厳格かつ格式高そうなミッションスクールで、親元に何一つ連絡がいかないというのは如何なものでしょうか? その上辞めた理由がしょぼすぎます。いくらなんでも見切り発車すぎて、若さ故の過ちという一線を超えた向こう側に彼女は立っています。つまり意味がわからないのです。
そしてバンドメンバー唯一の男の子影平ルイに関しても、とってつけたような悩みでそこには物語としての面白みが感じません。
というか演奏シーンの最後の曲、シスター日吉子と主人公の友達以外は初見だった? にも関わらずなぜあんな仲良く踊ってるんです? 腕を組んで楽しそうに踊っていたシスター達も少し前まで、一ヶ月の反省文と奉仕活動させてましたよね?
最後の最後に安っぽいミュージカルを見せられて、これで溜飲が下がると思っていたら大間違いですよ。いつだって、観客は置いてけぼりになってました。
しまいには演奏後にバレエを踊って、不意に「色がわかった」なんて言われてもこちら側は「?」で一杯です。
公開二日目、シアターには三百席も用意されています。
ですが、七人しかいませんでした。選りすぐりの精鋭達です。
その精鋭達が明かりがついた直後、余韻に浸ることもなく皆同じようにして俯き、背中を丸めながら一直線に同じ方向に向かって歩き出しました。
帰りのエレベーターに精鋭の内、私含め三人が同乗していましたが、その内の一人が携帯を見ながらため息を吐いていたのは忘れられません。
それがこの作品の完成度を物語る何よりの証左だと思います。
彩りあふれる音楽活劇青春アニメ
青春群像劇の(数回の鑑賞後に評価アップ)
プロットのような、基本形をなぞったような作品。
しかし見所や面白さがない訳ではないので、鑑賞に耐えうるに充分だと思う。
まずトツ子ちゃんがとても可愛いこと。
容姿ではなく性格や行動がとても可愛らしい。
彼女は人が発する色が見え、たまに変な子扱いされるらしい。
キミちゃんは優等生である重圧に耐えられず学校を辞めた女の子。
聖歌隊のエースであり育てのお婆様も学校の卒業生であることから、もしかすると彼女は将来的にシスターになることを期待されていたのかも。それが自分のしたいことなのかを悩んでの退学だったのでしょうか。
ルイ君は音楽がやりたいが、離島の医師をする母の跡継ぎになる為に期待を受けている。
そんな3人がひょんな事からバンドを組み交流が始まります。アオハル、青春です。
2時間弱に収める為に掘り下げが無いのが残念だが最後のライブシーンはとでも良かった。
キミちゃんのお婆様とルイ君のお母さんがとても美人で素敵だ。
人の期待に応える為に自分を律するのは辛いが、期待を裏切るのはもっと辛い。
その辺りはトツ子ちゃんが帰省先から帰る時に両親からいっぱいのお土産を持たされてるシーンや、キミちゃんのお婆様がパート先で修学旅行のしおりを持つ女子校生達を見掛けるとこで観て取れる。
私も早くに親元を離れたのでトツ子ちゃんのお見送りシーンは結構くるものがありました。
ライトに創られた作品ですから気分の落ちてる時に観ると良い作品ですね。
とにかく絵が優しく綺麗です。
最後にルイ君が離島から大学へ行く為に旅立ちますが、この3人の話はまだ続くのかもしれません。
エンドロール後3人が動画におさまるシーンの後、end、finでも 終 でも無く "see you " とありましたので続編があるのかもね。
期待してます、トツ子ちゃんにまた会いたいですね。
追記
数回見直して印象が変わりました。
何度も観ることで彼らに感情移入してしまいます。
最後のライブの後のトツ子のバレーダンスシーンに魅了されます。何度観ても飽きませんし、ずっと観ていたい。
もっと評価されていい作品です。
見事な傑作
全259件中、181~200件目を表示