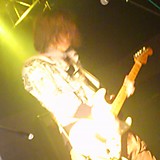きみの色のレビュー・感想・評価
全260件中、1~20件目を表示
悩みを共有しながら築かれる絆
山田尚子の作品はゆるい雰囲気が特徴で、本作でも彼女の独自性が表れていました。
京アニ出身ということで、『けいおん』のバンド演奏や『リズと青い鳥』の心理描写など、過去作の要素がたくさん盛り込まれていました。近年の大ヒット作にありがちなリアルな背景と激しい動きとは異なるテイストになっており、絵本のような温かいタッチに癒されました。そのため、「こういうのが観たかった!」と思えるぐらい新鮮な気持ちになれました(勿論、大ヒット作ならではの面白さもありますが)。
メインの登場人物も魅力的でした。トツ子は相手の色が見える不思議ちゃんで、きみはクールで友達思い、ルイは2人を支える存在みたいで素敵でした。それぞれが悩みを共有しつつ、バンド練習を通して築かれる絆が素晴らしかったです。たとえ変えられない現実に直面しても、それを受け入れて3人が成長していく姿に感動しました。
池袋のIMAXで観ましたが、大画面を活かした派手な作品とは違った良さがありました。柔らかくて引き込まれるような色彩や、全身に響くギターと電子ビートの臨場感が凄かったです。特に最後のライブシーンは、学園祭に参加したような迫力がありました。「水金地火木土天アーメン」も、独特な歌詞とメロディが癖になるぐらい印象的でした。
全体的に平和で、不思議な感覚を味わうことがでした。ゆるい雰囲気が好きな人にはおすすめです。
さて、トツ子さんは何色だったのか。
とても淡いタッチのアニメーション。ストーリーにロジックを感じないシーンの連なりは、それぞれ柔らかく楽しく美しく描かれていた。気が付くとスノードームの中に居たという演出が素晴らしかった。
登場人物にまったく嫌味を感じない。清廉なシスターの先生は、信仰の視点から理解が深く優しかった。お洒落なおばあさんはしっかりと厳しく優しそう。主人公、トツ子さんもそのお母さんも、微笑ましくなるプニプニとした安心感。その優しさに甘えたくなりそうになる。退学してしまったキミさんも、医師の家系のルイ君も、そんなトツ子さんに頼ることも大きいだろう。
演奏する姿も良いですね。初心者なのか一本指で叩くキーボード。ルイ君のテルミンは、あんなに滑らかな手つきを再現して貰っているのに、トツ子は2枚絵のパタパタアニメーションってw そこ、笑うところですか?
見せ場のライブ、三曲三様でまったく違う音色で鮮烈。キミさんのまっすぐな歌声がとても美しい。今時、ビブラートはかけないんですね。昔からビブラートの歌声に憧れたものだったけど。昔話と言えば、先生、まるで「けいおん」の「さわちゃん先生」じゃないですかw リフとか言い出したから、セリフより前にピンときた。当時の面影は見せなかったけど、チラリと軽やかに舞う姿が美しい。他にも、暗がりで舞い踊る観客の姿も面白い。
舞うと言えば、花壇の中を華麗に舞うトツ子さん。自分が何色なのかを掴んだのか。この踊るシーンも説明がなく、解釈が難しい。「色を掴んだ」イコール「将来の進路決定」の暗示かな。「色が見える」という不思議な才能。それ自体も何かの暗示か、単なる能力者か。そういえば、「音」も「音色」と、「色」と表現するんですね。
全体通して、友情の楽しさ、面白さ、清い尊さが描かれた映画だったのかと思う。友達と一緒に遊んでご飯を食べて、悩みを相談したり秘密を共有して隠し事をしたり。そんな友情を描いた青春群像というべきでしょうか。
最後のスタッフロール、尻尾の先まで面白かった。映画館で観る人、灯りが点くまで席を立たない方が良いかも。
(追記)
勢いで書いたレビューから少し考え足したことがあったので追記。
先生がまるで「けいおん」の「さわちゃん先生」みたいだと書いたけど、その先生の過去を書いたお陰で、おばあさんに打ち明けるキミさんや、母親と将来を話すルイ君、それぞれの親御さんにも過去があり、その「共感」から産まれる優しさを感じられる気がする。どんな話になったのか画かれてはいないけど、トツ子さんのエピソードでは具体的な会話シーンがあり、つまりは、他の子達もそんな感じなのだろうと類推できていた気がする。
登場人物の三者三様、それぞれ悩みを抱え、それを打ち明け、語り合うことで乗り越えていく。ライブの歌が三曲三様だったのもそのためか。レビュー文頭でロジックを感じないと書いたけど、自分の感じた映画のロジックはこんな感じです。懐かしさを感じさせる映画の舞台、親や教師の目を盗んで友達同士でする隠し事、それぞれに悩みを抱えながら、社会に向かって卒業していく。共感、ノスタルジー、そこからくる優しい映画であったのだなと考える次第です。
映画のスタッフロールでも、曲作りはパソコンでシーケンスソフト使っておきながら、カセットテープで生録とかw テープの懐かしさの共感ってこともあるけど、あの音色の感触もテープならではだったのかな。CD屋とか行くと、テープ版とか結構売られてますよね。
「衝突」ではなく「理解」で描く、暖かな青春物語。
◯作品全体
この作品には青春の苦悩にありがちな「衝突」の可能性がいたるところにある。男女関係、家族との不調和、学校のルール、そして「色が見える」という人とは違う特性。誰かと衝突し、傷つき、大人になる…こうした描写によって物語に起伏を作る。そういう作品になる要素にあふれている。
しかし山田監督がそうしなかったのは、相手を理解することの暖かさにスポットを当てたかったからじゃないか、と感じた。
トツ子ときみの関係性が象徴的だ。トツ子は退学したきみに対して、退学した理由を聞こうとしたりしない。一緒に時間を過ごす中で、ポロッとこぼれ落ちるようにきみは退学した理由を語りだすが、そこには衝突では描けない、理解の暖かさがあった。
ルイが島を出て遠くの大学へ通う、と伝えるシーンもそうだ。ともすればバンド作品特有の解散問題に発展する流れだが、トツ子ときみはそれを暖かく受け入れる。トツ子ときみは自身の嘘で誰かに迷惑をかけながらも、自分のやりたいことを成している。だから、衝突をしなくても理解できる。それぞれが自分自身にとってとても大事な問題を抱えているから、それを誰かに伝える難しさも知っている。それでも、離れ離れになるのは寂しい…その別れは普遍的かもしれないけれど、登場人物の心を繊細に描いているからこそ、「青春のほろ苦さ」が燦々と輝いていた。
そして誰かに気持ちを伝えることが苦しさだけではないことを、本作では音楽で表現していた。気持ちを表現することがどれだけ人を惹きつけ、心を踊らせてくれるのかは学園祭のシーンのとおりだ。
その後の中庭で踊るトツ子は、気持ちを表現できた喜びに溢れていた。トツ子のバレエは上手ではないけれど、見ているこちらまで溢れ出てくる達成感のような感情が印象的だった。
必要なのは衝突による物語の起伏ではなく、それぞれがそれぞれを理解して包み込む、暖かさ。先生や家族、クラスメイトたちも含め、その暖かな人の気持ちの描写が徹底されていて、とても優しい気持ちにさせてくれる映画だった。
◯カメラワークとか
・山田監督がよく使う、人物を画面端に寄せて空白を作る画面。今作は今まで以上に「感情の隙間」を感じさせる画面になってた。自分の中でもはっきりとしていない、相手に伝えるのも難しい感情、みたいな。きみが退学したあとの教会のシーンとかで使われていた。
・きみの造形は山田監督のこだわりを感じるなあ。クールな外見からフード付きのダボダボパーカー着てるのとか(『けいおん』の秋山澪っぽい)、パーカーで髪の毛が膨らんでる後ろ姿とか、髪の毛を耳にかける仕草とか(『リズと青い鳥』の鎧塚みぞれっぽい)、自分の気持ちを話すときに爪を見る芝居とか。
・瞳のアップショットの演出がやっぱり好きだなあ。本作だと本屋できみを見つけたトツ子のシーンとかで使われてたけど、その目線の先にあるトツ子だけの特別な光景っていうのを、その目線の先を見せずに表現するっていう。山田監督のが一番濃度濃い気がする。
・島を出ていくルイを追う、堤防できみが走るカット。引きのカメラで横位置、手ブレのドラマティックさがとても良い。山田監督作品だと『けいおん』1話とか『劇場版けいおん』、『たまこラブストーリー』、『聲の形』、『モダンラブ・東京』とかいろんなところで使ってる演出だけど、心の機微を感じる山田監督作品での「走る」はすごく大きなアクションとして映えるなぁと感じる。
◯その他
・ルイのデザインとか芝居作画はちょっとかわいくなり過ぎちゃってる。「ゆるふわ男子」をちょっと通り越してしまってるような…。
・きみ役・髙石あかりの声がすごく良かった。『べいびーわるきゅーれ』でも思ったけど、声の芝居がすごく自然。
・宗教上の理由で山田監督作品に点数は付けられません。
音の良い映画
山田尚子監督は、このところ張り詰めた緊張感の作品が続いていたのだが、久しぶりに軽やかな作風に戻ってきた。この軽やかさは『けいおん!』や『たまこ』シリーズの頃を思い出させるのだけど、退行では決してなく、進化した上でのあえての軽やかさといった感じだ。音楽を題材にしていることも含めて、懐かしさもあり、同時にサイエンスSARUに拠点を移して獲得した新しさもさらに突き詰めている。
色々な魅力がある作品なのだけど、ここでは音楽を含めた音について書いてみたい。山田監督の映像の心地よさというのは、音のセンスにもある気がしている。音楽に対してこだわりが強い人というのは、多分ファンにとっての共通認識だけれど、本作ではその意識が特に高い。色々な楽器が出てくるのも色々な音色をスクリーンで聴かせたいという現れだろうと思う。アニメは映像について語られることが多いのだが、映画の構成要素は映像と音である。山田監督はアニメ作家の中で、かなり音にもこだわりがあるタイプ。自然音もSEこすごい心地よい作品なので、これを味わうために、是非劇場で見てほしい作品だ。
ことばに頼らない丹念で繊細な語り口
主人公トツ子のナレーションで始まるが、見終わってみると、秘めていた心情を打ち明けるような説明くさいセリフはない。主人公たちの過去も匂わせるだけで具体的な説明はなく、心のうちはほぼちょっとした身体の動きやさりげない間で表現されていて、これが最初に観る山田尚子作品なわけではまったくないが、なんと繊細な語り口だろうとしみじみ思う。終盤になっての恋愛っぽい要素(恋愛だと断言はしない)も、序盤の本屋のシーンからいかにきみちゃんがルイくんのことが気になっているかを丹念に積み上げていて、言葉は少なくとも非常に親切な作りでもあると思う。しかしそれにしてもミス◯ルについては、作品世界に寄せようとしているだけに余計にノイズに感じてしまい、しかも最後にお口直しみたいにポストクレジットがあるのだから、ミス◯ルだって立つ瀬がないでしょ!と思ってしまった次第です。監督らがいくつかのインタビュー記事で主題歌について語ってはいたが、やっぱりあの3人の物語の後に、誰かが書いた歌詞はいらなかったのではという意見です。
音と色、そして青春の息遣いが柔らかく沁み渡っていく
主人公トツ子は何かにつまずいたり、壁に直面している女の子というわけではない。むしろ普通の子と同じ。でもだからこそ、この歳ならではの漠然とした感情を抱え、ふんわりとした穏やかさを持ちつつ、彼女は今日も教会堂で人知れず祈りを捧げる。人の色が見えるというトツ子。彼女がずっと友達になりたかった、綺麗な色を持つ同級生。さらにもう一人を交えて、突如組むことになった3人バンド。話はとんとん拍子で進んでいくが、淡いタッチで感情を柔らかく湛えるアニメーションや牛尾憲輔による虹色の音楽も相まって、彼らの友情の日々は澄み切ったハーモニーを奏でゆく。巨大なことを成し遂げるわけでも、大きな発見があるわけでもないし、よくある仲違いから和解へと至る物語というわけでもない。でもどうしてこんなに深遠に触れるのか。個々の音が重なり合う瞬間、無性に心が震えるのは何故なのか。鑑賞後も一筋の色がずっと胸中を照らし続ける作品である。
思いのほか良すぎた…
ゆるーくほんわかはじまった
聖書の1節がじんわりとしみる
なんて 油断していたら
なんかめちゃめちゃ涙が出ちゃって
ライブシーンが3曲もあるのに飽きなくって
エンドロール(クレジット)も余韻に浸りながらみた
字幕モードだからか ミスチルの歌詞も読めて
さらに余韻
おまけのラストシーンにほっこり
キラキラと尊い
彼女の目にはどんな色が見えていたのかな
予備知識がなかったので
髙石あかりちゃんに
新垣結衣ちゃんに
戸田恵子さん
物語の余韻に 驚きも加わってしまいました
ほかの誰かにもおすすめしたくなる作品
拍手
水金地火木土天アーメン」のアレンジが始まるところからのドライブ感
きみって名前だったのね
いろいろひどい
まず声優。
「アニメは声優を起用しろ!」とそこまで強く思っていないが、本作に関しては間違いなく声優を起用すべきだった。
主人公も演技が下手で、感情移入する余裕を与えてくれなかった。
また、いまいち何を目指している作品なのかわからないストーリー。
各登場人物が抱えている思春期特有の悩みを乗り越えていく感じなのだろうが、悩みも共感できる感じではなく、「がんばれ!」と応援したくなるものでもない。
なにより「この子たちがバンドをやる必要性」が全く見えてこない。
なぜバンドなのか。他の表現方法でも良かったのではないか。
「バンドを選んだ」ということに説得力を持たせるストーリーでもなく、終始フワフワしていた印象。
せめて後半のライブシーンで熱いパンクロックみたいな曲調なら青春感を醸し出し、「なんやかんやいい感じの青春アニメ」になれたのかもしれないが、小室サウンドを無理矢理ギターロックに掛け合わせたような、なんとも乗りにくく、熱さもないものだった。
とても残念。
仕草で伝えるアニメーション
予告編で判断してはいけない、と映画好きであるならば何度も胸に刻んだはずでしたが、なんとしても劇場で観ておきたいはずの映画でした。
ノットフォーミーな映画、なはずもなく、その動き、目線、音の出方、(ボーン・スリッピー!ブルーマンデー!)、を愛せる私たちにはたまらない2時間の映画でした。
カットが変わるタイミングはまさにここだというタイミングで、もうこれは私の映画でした、というしかなかったです。
何ものでもない、何も得意でもない私たちを祝福したい、その想いをアニメーションの動きと色彩で表現したい、それをたくさん受け止めました。
サイエンスSARUでは夜明け告げるルーのうたでも音楽を作成していますが、それに感じた小っ恥ずかしさはまるで感じず、音楽に救われた経験をおもだしました。
素晴らしかったです
あったかソーメン
カトリック系(かな?ちょっとその辺は疎くてわかりませんが…)の学校を舞台に最初は淡々と過ぎていきますが、途中から急展開で進んでいきます。
教会が舞台となっているため、少し暗い感じも赦しや教えとして進んでいくので、楽しく最期まで暗い気持ちにならずに観られます。
学校に通う女の子と学校を辞めてしまった女の子、その子が働いている本屋で出会う男の子と3人でバンドを組み、それぞれの秘密や後悔や不安等を音楽を通して受け入れていく様が描かれています。
途中で恋なんじゃないか?みたいなニュアンスがありながらも最期まで敢えて触れなかったのは良かったと思います。
匂わせるだけ匂わせて最後観た人がどう感じるかは自由というやり方は割と好きな見せ方です。
星3にはギリギリ届かないぐらいにしたかったのですが、0.5刻みなので2.5とさせて頂きました。
追伸、ミスチルが歌ってることに驚きましたが、作中の水金地火木の方が惹かれました
ニーバーの祈り
きっと誰もが色を纏っている。
高校生のトツ子は、人が「色」で見えるというある種の特殊能力を持っている。同じ学校に通っていた美しい色を放つ少女きみに憧れを抱いているが、ある日突然きみが学校を退学したことを知る。どうしてもきみに会いたいトツ子は本屋でバイトしている噂を元に彼女を探し始めて…ってあたりが序盤のあらすじ。
全体的に優しいトーンで優しい色で語り口までぜんぶ優しい。トツ子は誰にでも穏やかできみちゃんもルイくんも落ち着いた印象。でもバンドを組んで結束感が高まると徐々にテンションも上がっていくのがよかった。
3人が秘密の共有も何だか絆を深くさせたような…きみちゃんは学校を勝手にやめたことを祖母に言えないでいて、ルイくんは医者を継ぐことを願っている母に音楽が好きなことが言えない。トツ子は一見何もなさそうに思えるんだけど、子供の頃に通っていたバレエ教室でジゼルが踊りきれずにやめてしまった事が心の傷になっているように思えた。あんなにバレエが好きだったのに。もしかしたらトツ子が自分の色だけ見えなかったのは、自己肯定感の低さからかもしれない。
結局、きみちゃんとルイくんはちゃんと秘密を明らかにして家族をライブに見てほしいと言う。ライブシーンがとても良くて、最終的には観客も踊り出すぐらいに盛り上がる。いつも味方になってくれたシスター日吉子がいちばん嬉しそうにも思えた。
トツ子が幼少期に踊りきれなかったジゼルを校庭で踊るシーンがとても好き。太陽にかざした手が鮮やかな赤色に見えて、トツ子の心がやっと解き放たれたように感じた。
ラストのきみちゃんの『がんばれー』って叫ぶ大きな声にちょっと泣いた。
『きみの色』ってタイトルはきみちゃんのことを指しているのかと思ってたけど、観客に向けた言葉なのかもしれないね。誰もが自分の色を持っていて、それが少しでも鮮やかに人生を彩れるように日々を大事に生きていきたいと思えるようなお話だった。
無色透明にはなりたくない
少し天然が入っていて、人が色で見える女の子、不満は多いけど優しい女の子、医者を継がなければというプレッシャーに耐える男の子、三人の高校三年生の成長物語。
いろんなトラブルが起きるけど、親を含めた周りの大人たちが、ちょっとだけ手を貸して見守る。
あたたかい絵柄とキャラのちょっとした弾けっぷりが微笑ましい。
淡い色と緩やかに流れる時間🩵
高校生の女の子二人と男の子一人ときたら、当然好いた好かれたが幅を利かせて入ってくるかとおもいきや、最後まで淡い色と緩やかに流れる時間で押し切った、そんなんできるんだ。ともかく全体的雰囲気が何か心に刺さりました^_^
長崎とか、また或いは広島とかそんな海に近い街にある女子のミッションスクールで話が始まる。学校がある街の描写も緩やかな雰囲気でとても良い。
話はと言うとそれなりの秘密とそれなりの共有とそれなりの達成感を得ておしまい、という感じ。これは何かを成し遂げたり何かの未来を期待したり何かの憤りや喜びを期待するタイプの映画ではなく、一緒にその世界を"体験"する感じの映画に思えた。そういう意味では体験型アトラクションや、ロールプレイングゲームというかそんな感じです。
この映画の良いところだか、もしかしたら情報に溢れ溺れそうになってる2020年代だからこそ、モノやメディアといった点では、まだまだ何にも無い昭和の感覚を残し、ゆっくりした時間の流れと言うか、小さな出来事の積み重ねを求めている人に刺さるのかなと。自分も含めて。
追伸
エンディング曲はいらんかったか…。
水金地火木・土天アーメン~♪
トツ子、きみ、ルイの3人がバンドを組む、聖バレンタインデイに学校で演奏会、拍手喝さい。トツ子は人物の印象が色になって見える少女なのでタイトルに色がついているのだろうが「きみ」は君ではなく、仲間の「きみ」のことでしょう、綺麗な青色にみえるそうです。冒頭、トツ子が語る色の説明、
「生物が色を認識する感覚は進化の結果として獲得したらしい」
「光を受けた物体がその光の色を吸収、反射して瞳の網膜を通じて脳に色を届ける」
「色と言うのは光の波のようなもので、赤いリンゴ、緑色の葉っぱ、青い魚、長さの違う光の波で色んな形になる」
と、すごい学術的説明、子供たちには難しいかもしれないが、トツ子の「感じる色」という詩的表現の前置きとして伝えておきたかったのでしょう、製作陣は生真面目ですね。
確かにファンタジックなアニメなので色も綺麗ですが、正確には色でなく音色の豊かな青春ミュージカル寄りでしょう。テルミンなんて世界最古の電子楽器、青年ルイが演奏なんて奇抜な脚色でした。
水金地火木土天アーメン
バンドにはドラマーがいて、ベーシストがいる。という従来のロックの常識的な感覚は今やもう化石のようなものなのか。偶然と必然が入り混じったシチュエーションからバンドを始めようといった展開は好きだけど、もう誰々の楽器が何々でと考える必要もない時代なんでしょうね。時代はDTMからスタートで、ベースもドラムも要らない。これもYOASOBI効果かもしれません。
きみのギターはビートルズで有名になったリッケンバッカー。ルイが使っていたDAWソフトは多分CUBASE。さすがにテルミンのメーカーはわからん!それにしてもゴミ置き場にヤマハのDX7?が置いてあったのは凄い。オレでも持って帰るわ!
やっぱルイ君は医者を目指してるだけあって頭がよさそう。テルミンなんて高校生は使わんぞってか、知ってる人はどれだけいるのやら。ネットで調べてみると、使用楽器を色々乗せてあるサイトも見つけた。ギターアンプやエフェクター、シールドまで。そういや、きみのシールドの巻き方がリアルだったなぁ・・・そしてメトロノームの代わりに「ニュートンのゆりかご」も。
『けいおん』もそうだったけど、ゆるい感覚でバンドを始めるのが現代的。まぁDTMがあれば楽器弾けなくても音楽理論知らなくても作曲できますからね。何をやりたいのかわからない、何かを変えたいって人には向いている作品だったかと思います。「色」に関してはそれほどストーリーに絡んでこなかったのが残念なところ・・・
全260件中、1~20件目を表示