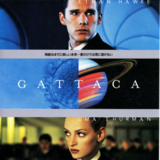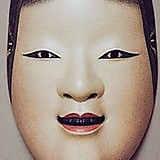怪物のレビュー・感想・評価
全1019件中、901~920件目を表示
切ない。ホンマに切ない。たまらなく切ない。
コリャ是枝を巨匠再認定するしかないかと。前作も是枝らしさ全開でしたが、今回は技巧的な脚本も素晴らしくて脱帽です。
ラストの解釈ですよ。コレがまた。
普通に捉えれば、大人2人が捜索に入った時間・天候と、子供達が脱出した時間・天候が折り合わないが故、子供達は天に召されたものと見るのが合理性あり。
でですよ。
以前、似たようなラストの映画があってですね。イランの巨匠アミール・ナデリ監督の「山(モンテ)」です。監督の舞台挨拶付き上映を見る機会があり上映後に直接質問したんです。
「極貧で身なりも貧しかった一家が、ラストシーンで綺麗な姿になるのは一家が亡くなった事を示唆しているのですか?」
答えは「あれはワタシからのギフトです。亡くなってはいない。表現としての加飾に過ぎません。」
横転した列車の窓から降りた2人の前に広がる青空は2人の出発を祝う、是枝監督からの贈り物。と言う解釈をしても良いのかと。
いずれにしても是枝監督自身は語りそうにありませんけど。
映画は3部、と言うか三面構成。Phase1は母親主観。Phase2は教師主観。Phase3が湊主観。この三面目の依里くんが可愛すぎます。切な過ぎます。もう、何から何まであざといくらいに可愛い。もうね。メチャクチャ切なくなりますもん。
君たちは化け物なんかじゃない。怪物でもない。自分自身に誇りを持って。好きな人を好きになって良いから。
は、「彼女が好きなものは」の主題でもありました。同じですね、コレも。
良かった。
とっても。
かいぶつだーれだ?
映画館の特報で観た時から気になってた作品。特報の最後に「かいぶつだーれだ?」と一文字ずつ出てゾワッとした。きっとホラーやサスペンスみたいな怖い作品だろう。
でも、実際本編を鑑賞した時に騙されたとの感覚に陥った。何故本編と違う印象を持たせるのかと!
作品を鑑賞していくなかで、「誰が本当の怪物なのか?」、「怪物はいるのか?」等、自分の視えている虚実入り混じった主観により、考えが二転三転する。それぞれの立場でそれぞれの主観や考え方に共感できるところがあるからかもしれない。
でも、それは当事者達は当事者の虚実入り混じった視点のみしか持っていないため、良かれと思ったふとした相手への気遣いさえも、受け取る側には気遣いにならないということにも気付かされた。
また中盤に、扉があって前に進めない線路のシーンがあったが、単純に線路を人生の線路・レール等のことを言ってるのかと思ったが、内容からレールに沿ってないと思う人もいるこの子どもたちを表現するのに違和感があった。
しかし、ラストに子どもたち二人が楽しそうに走って行く中で、中盤にはあった扉がなくなっており、その先にも進めるようになっているシーンで映画は終わる。
僕は、大人たちのレールに従わないと「怪物」のままである子どもたちが、親のために自分の「将来」の扉を閉じていたものが、二人が亡くなったことで、怪物から開放され、子どもたちが望む将来へと繋がる線路へ進めるようになったのではないかと感じた。
とても考えさせられる映画だった。
ところで、感想を書いているのはあくまで僕の感想であり、共感してくれた方には感謝しますが、それを無条件に受け入れることは、作品の内容に沿うのでしょうか?作中の大人たちと同じかもしれません。
レビューの冒頭で書いた映画の特報の件は僕の先入観でこんな映画だろうと思ってたのは、視えていない部分が多くあり、一部分を視ただけで、主観によりわかった気になっていただけかもしれないと考えされられて、なんて素晴らしい特報だったのだろうと考えを改めホラーよりもサスペンスよりも怖い作品となった。
「かいぶつだーれだ?」
多様と多角の尊重
わりと全員怪物です
タイトルの怪物とは、その人物にとって得体の知れない恐怖の対象のことであると感じました。
母親→学校という組織
先生→嘘をつく生徒
子供→自分自身
先生が追い詰められていく流れに必然性があったのかはちょっと疑問だし、作文のメッセージに気付いただけで全て理解して嵐の早朝に謝りに行くのはもはや狂人ですが笑、3パートに分かれる視点別の構成は全体的に悪くなかったと思います。
ただ、子供が自分の内面に苦悩する描写に、ここ最近の性的マイノリティを扱う表現をちょいちょい差し込んできたのはやや強引な印象がありました。。
それでも説明っぽい台詞は少なかったのでまだ良かったです。
彼らが旅立ったラストシーンには、閉鎖された世界から解き放たれたカタルシスと美しさがありました。
そのまんまヤン。是枝監督にしては失敗だと思った。何を言いたいのか❓
当然だが、ネタバレはヤバいので書かないが
悪い奴は すぐわかる
イヤイヤ 乗り込んで、正当性をまくし立てて、顔を近づけて、鼻に触る【以下全文、私の独断と偏見の個人的な意見です。
客観的ではない 個人的な感想にすぎません 全文 良い⭕️⭕️好作品と思われる方もたくさんおられるかと感じました】
以下 全文個人的感想です。
乗り込む様
何様❗️警察呼んだ方が良い
さすがに謝罪やマスコミレベルになると それが事実と異なるならば
名誉毀損じゃないの・・・と言う描写【この作品自体は濃厚な立派な作品です。素晴らしい
ただ 昔のケーキ🍰の生クリームと同じで、昭和のケーキ🍰
観る人の意識、経験則により、評価は割れる と思いました】
【描写について 詰め寄る描写が↓☟ 明らかに ☟↓ 的に 思いました、先生【永山瑛太さん演ずる】
次の行の如しですよ 保利先生🧑🏫
名誉毀損は立派な刑法犯
なんだよコレ
1時間30分の内容をクドクドと2時間以上は勘弁してほしい。
それと 子供の場面が 事前予想どおり、長すぎる
二人の少年の相関性はわかったが、もう少しコンパクトにできるだろう。
是枝監督の是枝ファンで 8割の大入
だが脚本は任せない方が良かったと思う
あと、プロデューサーが 自分の学校の宣伝入れてていやらしいことこの上ない。
いやらしい、いやらしい
どうでもいいが有料パンフに学科まで入れんなよ まさに お子ちゃま
いくら是枝さんが有能でも、プロデュースする人、脚本家は選んだ方が良いと思った。
それと 豚の脳🐖🧠なんて 全然馴染めない 適当違和感ワード
それ言うなら 猿の脳 か サメの🦈脳🧠【🌳さんすまぬ】
やっぱり LiLiCo は結構 不偏不党 王様のブランチ 10年ぶりにみたが
LiLiCoさんの 歯切れの悪さが よくわかった。
是枝監督はコレまでも日本映画への貢献度高いから普通の星⭐️⭐️⭐️🤩。
有能な脚本家 素晴らしい有能なプロデュースかもしれないが私には響かなかった。
私にとっては ドット疲れる作品でした。
桐島部活やめるってよ 的。
怪物だーれだ
『誰でも手に入れられるものを"幸せ"と言う』
多分、表題に今作の全てを込めている台詞を、田中裕子が呟くこと、これで今作のテーマを一点集中突破した出来映えだと最大限に感心させられた この台詞は絶対的に皮肉であり、人はそれぞれの幸せを本来持ち得るモノという多様性を得なければ未来は訪れないという、まぁ、保守派の人達にしてみれば、温ま湯だと揶揄されるプロットだろうと容易に想像出来る、"万引き家族"と同様、ネット上で物議を醸し出すストーリーである 確信犯的に作っている制作陣の好戦的な姿勢に好き嫌いがハッキリと分れる提言に、その意志を認めざるを得ないのは、もしかしたら左右両方に巡り巡って好かれるのかもしれないと、穿った観方さえしてしまうチャレンジングさである 絶対日和らない、という凄みに、餌巻きされた否定派達は心底小躍りしただろうと予想する
只、自分が感じたことは別に上記の事に集約されることではないと感じる 他の考察サイトでも述べられていて心底合点がいったのだが、カンヌが称賛したクィア賞の本質ではなく、今作は、成長期に於ける有り余った性欲が、色々なところに発露してしまうという現象に集約される物語なのだと腑に落ちた あの子役2人が未来にどうなるのかなんてものはストーリーに提示されていないどころか、もしかしたらラストシーンはイマジネーションパートかも知れないのだ そんなあやふやなシークエンスの中で、性への目覚めの真相等、当人ですら分らないし、歳を取って振り返っても"トチ狂った"のか"方向性を決定づけた"のか、それは振り子のようなタイミングだけなのだと断じる
本当に、狭いところを付きながらも普遍性を語る制作陣及び役者陣、頭が下がるほかない内容であった
追記
所謂、『感動ポルノ』問題という事案がある 今作も又批判の中の一議題として囂しい
視点を切り分けた構成である今作は、本当の子供達の姿を周りの大人は気付いていない、しかし、先生のみが鏡文字で気付いたのではと思われる節を匂わせる いや、匂わせなので、本当の正体は分っていないかもだし、父親のおかしな言動や、他のクラスメートの嘘や不穏な喧嘩や雰囲気等々、自分では手に負えない問題の数々が実はあのクラスには積み重なっていたのだろうと・・・ もしあれが現実に日本のどこかの学級で起っていたとして上手く捌ける教師や教育委員会がいるのだろうか? なので、二人に何らかしらの関係性を見出した先生のキャラ設定の微妙さを考え出した制作陣に尊敬する
人間は善悪の二元論ではない そしてもしかしたら発達障害的な行動をしている人だって、もしかしたら真実を掴んでいるのかもしれない
話は横道に逸れてしまったが、今作ラストの『銀河鉄道の夜』的ファンタジーに、結局不幸にさせて感動させる落とし処だろうと邪推する観客もいると思う 『マイノリティは不幸になる』という結論で、可哀想という感情を観客に植え付ける それは正に高みの見物(シス&ヘテロ)として、そういう星の下に生まれた人達が運命として消えてしまうことに哀しさを安易に得たいと願うこと しかしそれは今作に於いて些か考察が足りない
理由は横道に逸れた先生のキャラがそれをブレイクスルーしていることが明らかだから
願わくば親が気付いて理解して揚げて欲しい しかし両人の親ともシングルという協調作業が困難な家庭環境(両親がいたってダメな場合が多々)に於いてその願望を押しつけるのは残念ながら解決不可能である
そう、今作はキチンと、だれが怪物なのかを暗喩として示しているばかりでなく、そのどうしようもない岩盤を開けるのは、もしかして思いも依らぬ変人かもしれないという、これもファンタジーかも知れないが、その可能性をフィクションとしてではあるが提示した物語ではないかと考える
本来ならば、第3の壁を破り、観客に問い掛ける演出だって乱暴だが在っても不思議じゃない 曰わく「あんた達、感動していないで、二人の子供がこんな悩んでいるのに胡座かいて当事者意識なんて持っていないんじゃないか? あんた達の事なかれ主義がこうして不幸を再生産しているんだぞ!」って、校長先生辺りが、あの死んだ目で問い掛けてくれたら、もしかしてパルム・ドール?・・・・な訳ないかw
あまりに美しすぎる
「担任の先生からいじめを受けてるかもしれない」
この事件を、母、担任の先生、本人
3つの目線で構成される今作。
予告の時から「1番の怪物は誰なのか」を探す作品なんだと思ってた。
実際、本編中も、母と担任のパートでは、
誰が怪物なのか探しながら見ていた。
「うわー、担任が良くないよこれ」
「いやいや周りの児童も…」
「えー?もしかしてお母さんもなかなか?」
みたいな。
でも本人目線になってから、全く違う作品に変貌した。
本人たちは今回の事件の犯人探しだとか、謝罪だとか、そんなこととは全く違うところで、
とんでもなく大きな問題を抱えていて、
それを自力で解決するにはあまりにも子供だった。
思春期にもまだ満たない子供の
心の葛藤とか、揺れ動く様とか、
そういった部分がすごく美しく残酷に描かれていて
めちゃくちゃに!!!!!好き!!!!!!
すごい!!!!!!好き!!!!!!!
怪物とは
かいぶつ、だーれだ。
結局誰なんだろう。
モンスターペアレントの母親 か
まるで聞き耳を持たない教師 か
孫の死を利用するような校長 か
性の問題を病気扱いする父親 か
様々な視点で「怪物」が描かれる。
母親にとって先生らは怪物に見えただろうし、
先生らにとってはえげつないモンスターペアレントは怪物にしか見えないだろうし。
「男が男を好きなのは気持ち悪い」
「男が女と仲良くするのは気持ち悪い」
これは小学生だったらシンプルな理由で当たり前。
お母さんに愛されてる麦野くん
お父さんに虐待されてる星川くん
星川くんはめちゃめちゃ強い子で
麦野くんは周りに流されてる
「男が男を好きなのは気持ち悪い」
ふと思い出して怖くなる。小学生だったらそらそう。
最初は、「男らしく」髪をきるまでする湊。
でも、あんな憎らしい笑 校長がファインプレー。
そして、自分を認める麦野くん。
お父さんのようにはなれないし、
お母さんが言ってたような普通にはなれない。
それを踏まえた上で認めた麦野くんは強い。
最後のシーン。いつの間にか風も、雨も止んで。
まるで生まれ変わったように、晴れている。
いつも閉まってる柵もなく、線路の上を心が晴れたように走り出していく。
これには色々な解釈があると思うけど、やっぱりあえて明言しないとこがもう分かってはりますわ。
対比があったり、色んなテーマが混在してるなかでこんなにも見やすく、こんなスッキリしてるのは名作としか言えなくないか。
映画でければできないこと、今多くの人に見てもらう意味がある!
羅生門スタイルと言うなかれ
もう一つの“誰も知らない”
カンヌで二冠。またしても是枝裕和がカンヌを賑わす。
役者たちから名演技を引き出し、文句の付けようがない名演出は、自身の新たな代表作誕生に相応しい。
しかし今回は、坂元裕二による脚本も大きい。是枝が自身で脚本を手掛けなかったのはデビュー作の『幻の光』以来。
脚本の本質をしっかり読み解いたのも、それほどこの脚本に魅了されたという事でもあろう。
確かにこの脚本の見事さには唸らされる。伏線や意味深な描写をちりばめ、回収や繋ぎ方、展開に引き込まれる。脚本賞も納得。
坂元裕二は多くの人気TVドラマを手掛け、『花束みたいな恋をした』を大ヒットに導き、本作で栄誉に輝き、今後TVドラマのみならず映画界でも重宝されるだろう。
兼ねてからリスペクトし合い、コラボを望んでいたという二人。そこに奏でられる故・坂本龍一。
全ての才が素晴らしい形で結集し、世界に放たれた。
これはもう“奇跡”や“偶然”ではない。“運命”で“必然”だったのだ。
話はある一つの“事件”を、3つの異なる視点から語られていく。
所謂“羅生門スタイル”。映画の常套手法だが、どうしてこうも見る側は“矛盾”に引き込まれるのか。
勿論それも、脚本の巧みさあってこそ。
シングルマザーの早織。夫を亡くし、一人息子の湊にたっぷりの愛情を注ぎ、大事に育てている。
最近、湊の様子がおかしい。靴を片方無くし、汚れた服。突然自分で髪を切り、怪我も…。奇行も目立つ。
問いただし、何があったかやっと聞き出すと、学校で担任教師から体罰や酷い言葉を掛けられたという。
お前の脳ミソは豚の脳ミソ。
早織は学校に抗議。が…
何の感情も無く、機械的な口調の、“形”だけの謝罪ではない謝罪。
心ここに非ずの校長。マニュアル通りただ頭を下げるだけの教頭ら。担任の保利に至っては、事の重大さや自分が何をしたかすらも分かってない。
何なの、この学校、教師たち!?
保利の母子家庭を貶す余計な一言やさらに息子さんがいじめをしているとまで言い出し、火に油を注ぐ。
一瞬息子を疑うが、被害を受けたという生徒(依里)に会い、事実無根の確信を得る。
事件はニュースにもなり、保利は休職。
これで一応一件落着と思ったある日、嵐の夜、湊が突然姿を消す…。
傍目には、息子を守るシングルマザーの戦い。
早織から見れば、学校や教師たちが“怪物”。
一人息子を大事に思う早織の言動は誰もが共感する所だが…、うっすら過剰やウザさも感じる。
つまりは“モンスターペアレント”。学校から見れば、早織が“怪物”。
“怪物”とは誰か、何か…?
各々の視点によって、“怪物”は全く異なる。
担任の保利の視点。
ここでの保利は、早織の視点とは全く違う人物像。
早織の視点では大人/社会人として全くの無責任(もっと砕けて言うと、ムカつく!)に見えるが、保利自身の視点では、至って普通の人物。と言うより、真面目で生徒思いのいい先生。
誰がどう見るか、見えるかによって人の印象は変わってくる。
恋人との関係も良好で、生徒からも好かれ、まだ日は浅いが教職にやりがいを見出だしていた。
そんな時クラスで起きた生徒同士のいざこざ。
間違いのない対応をしたつもりが、それが問題視され…。
体罰があった。たまたま肘が生徒の鼻にぶつかっただけ。
先生が怖い。事の収束に奔走しただけ。
体罰教師のレッテル。マスコミにも嗅ぎ付けられ、恋人とも関係が…。
挙げ句の果てに学校から、責任と罪を一人擦り付けられる。
精神的に追い詰められていく…。
保利から見た“怪物”とは…?
自分を見放したら学校。同僚たち。
それは早織も同じかもしれないが、早織視点の場合は非を認めず憤り募るのに対し、保利視点での学校は闇深い不条理な場。
似てるようで、意味合いも微妙に異なる。
また、嘘を付いた生徒たちも“怪物”。
ある時、そんな“怪物”の秘密を知る。
それを見逃し、気付かなかった自分も、愚かな“怪物”…。
“羅生門スタイル”の醍醐味は、最後に伏線が回収され、それらが繋がり、全てが明かされていくカタルシス。
本作のキーキャラは、二人の子供。
湊と依里。
二人だけの秘密と真実。彼らから見た“怪物”とは…?
学校でいじめに遭う依里。
そんな依里を気掛かりに思いつつも、助けてあげられない湊。自分へ苛立ちを感じる。
ひょんな事から密かに親交を持つ二人。
依里が見つけた森の奥に廃棄された電車。“秘密基地”は、二人だけの“世界”。
二人共、何かを抱えている。
母子家庭の湊。父親は事故死したが、その時父は…。
父子家庭の依里。父からは“病気”とされ、DVも…。
“病気”とは、普通の男の子とは違うから。
“豚の脳ミソ”も依里が父親に言われた言葉。
二人を取り巻く…いや、圧する大人たち、社会。
二人から見れば、その全てが“怪物”なのだ。
その“怪物”に、僕たちはどうすればいいのか…?
生まれ変わりや品質改良。ありのままではいられないのか…?
カンヌで受賞した“クィア・パルム賞”。LGBTなどを扱った作品へ贈られる。
そこから分かる通り、二人の関係は友情を超えた同性愛を匂わす。
いやはっきりと、想い合っている。
親、学校、周囲、社会…それらから見れば、変わった僕たちが“怪物”。
でも一体、どちらが“怪物”なのだろう…?
ピュアな秘密を抱える子供たちか…?
保身を固持しようとする彼ら以外の全てか…?
見た人それぞれに訴える。受け止め方がある。見方がある。
だから単純に答えは出せない。
実は今も、果たしてこうでいいのか、もっと違う視点ではないのか?…などと自問自答しながらレビューを書いている。
まだ受け止め切れない自分がいる。
作品が訴え、問い掛けるものや、まだ残された謎。湊の父親の死の疑惑、校長の孫の死の噂、ビル防火の犯人…。
また見返しても、暫く経っても、それはずっと続く事だろう。
私の心に残る作品であり続けるだろう。
書いていたら今すぐにでも見返したいくらいだ。
名演出、名脚本。心に染み入る遺曲。
安藤サクラの名演。
永山瑛太の完璧な演じ分け。
田中裕子の存在感。
高畑充希、中村獅童、東京03角田らも魅せる名アンサンブル。
中でも二人の子役、黒川想矢と柊木陽太。
実力派や名優たちを食ってしまうほど、圧巻。
是枝監督は普段は子役にはナチュラルな演技を要求するが、本作ではディスカッションし、作り上げていったという。
それほどこだわり抜いたほど、作品の要なのだ。
重厚なドラマで、サスペンスフルな雰囲気も。
あの楽器の音色も印象的。まるで、怪物の言葉に出来ない鳴き声のよう。
終始、重く、暗く…。
が、ラストシーンだけ光輝く。
嵐が過ぎ去り、美しい陽光の中、二人が駆け出した先には…?
このラストシーン、ひょっとしたら…? の意味合いもある。
でも私は敢えて、希望ある終わり方と捉えたい。
二人だけが知っている。
これももう一つの、“誰も知らない”。
怪物はだ〜れだ⁉️
予告編でながれるこの言葉が、この映画のキーになる。
母親、教師、子供のそれぞれの視点から、起こった出来事について語られる。このストーリーが見事に、3人のそれぞれの立場と行動を正当化するのだ。この情報からはこうなるよねというふうに、納得してしまう。特に最初の母親には思わず感情移入してしまった。
ところが教師の視点なると全然ちがうものが見えてくる。これはすごい。展開が読めなくなる。
そして最後に子供の視点。2人の予想外の秘密があきらかになり、物語はクライマックスとなる。
答えはもちろんない。
でも、怪物はそれぞれが自分の立場で作り出す幻想なのではないかと思えた。怪物なんているのだろうか、それぞれが自分の視点で作り出しているのではないかと思えてしまう。この映画で唯一、真の怪物なのは、いじめられている少年の父親だけだった。
もう少し早く教師が真実に気がついたら展開は変わったのだろうか。子供達の無邪気な笑顔と内に秘めた心の叫びに思わず涙してしまう。
キーとなる母親の安藤サクラ、教師の瑛太、校長の田中裕子、そして2人の子役の演技は素晴らしかった。
序盤面白かったですが、期待値ほどではない空気が劇場に漂う。。。
金曜レイトショー『怪物』
野球中止で急遽鑑賞〜レイトショー料金の値上に涙。。。
何年先までスケジュール埋まってるのか!?毎年公開される是枝作品
監督の名前だけで期待値上がり、毎年恒例のカンヌでは脚本賞受賞
キャスト的には、俳優陣も誰か受賞しそうな前兆あったので意外な感じがしての鑑賞
序盤、先日まで放送されてたドラマ『ブラッシュアップライフ』かよ!?って感じのシーンも笑えた^^;
異常な教師vsモンスターペアレント的な母親が繰り広げる展開
瑛太vs安藤さくらvs田中裕子は、母親目線→教師目線と目線がかわり見応えありましたが・・・
子供達の真実って描写から不穏な雰囲気に。。。。
子供達のLGBTの第一段階を遠回しに見せられてのあのラスト
どう解釈するのかは鑑賞者によって違うでしょね。
私的には期待値下回り・・・
配信で良かったかなって感じで、エンドロール始まると席立つ人多く釣られて席立ちました^^;
*坂本龍一さんのご冥福をお祈り致します*
まんまと罠に引っかかる
怪物は一体誰なのか・・・次々と現れる怪物候補。
真の怪物は?ああ、この少年っぽいな・・・などと推理したら最後、突きつけられるのは
「はい、あなたも同罪でーす」
という罠。
ラスト。
先入観、偏見、常識、自意識・・・あらゆる概念から抜け出して純化し、歓喜する2つの魂。
「はい、正解はこれでーす」
私が間違っていました。悔い改めます。
という映画でした。
話に引き込まれました
全1019件中、901~920件目を表示