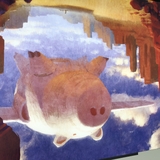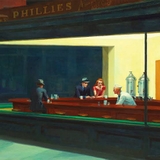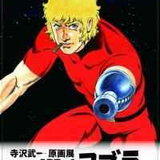怪物のレビュー・感想・評価
全1019件中、861~880件目を表示
心に嵐が吹き荒れる
嵐の日に嵐の映画を見た。
理解出来ない人間の恐ろしさに心がゾワゾワしっぱなし。
噂と憶測が混ざり合い、湿度を帯びた重い空気が身体中にまとわりついて息がしづらい感覚に。…観客も嵐に巻き込まれていきます。
行動の裏には理由がある。嘘の裏には守りたい何かがある。
それぞれの立場から描かれる真実。点と点が繋がる奇跡に心が震えました。
田中裕子さんのセリフが深く胸に残ります。
今じゃないいつか。ここじゃないどこかへ。早まらないで。
嵐の後の澄んだ空気が、真新しく生まれ変わった世界を見せてくれるはず。
聴きたくなった曲:キリンジ『台風一過』
観たくなった映画:黒澤明『羅生門』
近藤龍人さんの真正面から役者を見据える長回しが大好きなのですが、斜めからのアップにも同じ興奮を感じました。
「私はこのシーンの為にこの映画を観たのだな。」と思えます。
瑛太さんの笑顔もすごい。
ラストの見解…
二人は亡くなってると思います。母親と保利先生が電車に着いたのは夜、ラストシーンで二人が電車から脱出したのは夜明けです。夜明けまで電車にいたなら先に発見されているはずです。あとは「生まれ変わるなら…」という発言が繰り返されていることから、嫌な想いをしない世界で生まれ変わったのかなと。
全体の感想としては総じて良かったのですが、母親目線で見たときの校長と保利先生のキャラクターが、保利先生編以降とあまりに別人で、構成づくりのためにちょっと都合良すぎかなとは思いました。保利先生の本来の性格からは、母親編で見せたような振る舞いはしないと思います。それも含めて物事の一側面だけをみると誤解しかねない、という教訓だとは思うのですが。
【是枝裕和監督】彼の常套手段に騙されてはいけない!?
是枝裕和監督✕脚本・坂元裕二✕音楽・坂本龍一=ドリームチームで描く、映画『怪物』を鑑賞しました。
坂元裕二氏の三部構成からなる脚本は秀逸でした。
第一章・麦野早織(安藤サクラ)の視点。
第二章・保利道敏(永山瑛太)の視点。
第三章・湊(黒川想矢・子役)の視点。
ひとつの出来事を、それぞれ角度を変えて描く、テクニカルな構成に見応えがありました。
ですが、第三章だけ、やや平板で間延びした感じで残念でした。
(ここからは、あくまでも個人的な意見です。)
子役二人の演技と脚本には目を見張るものがありますが、大したストーリーでもないのに、わざとわかりにくくして焦点をぼやかしながら、丸投げのクライマックスヘと導く…是枝裕和監督の常套手段は、やはり監督のよほどのファン以外に受け入れられないような気がします。
私的には、本作品もオススメできる最低ラインかなと思います。
怪物は自分の中にもあると知ること。
子供の純粋さと大人の一方的な思い込みが生んだのが「怪物」なのか…
自分の中にも怪物(思い込み)はいると知っている事が大事かもしれない。
みんな幸せになりたいだけなのに。
問題なく日常を過ごしていければいいだけなのに。理想の自分にはなれないジレンマ。問題を解決しようとすればするほど深みにはまってしまう状態。わかります。
学校は子供にとって戦場で、やらなければやられる思惑の混沌。男だから強くあれと言われる日常。母親には心配をかけたくない子供。でも大人の事情を実は知ってる子供。
隠れて本当の自分を2人で育むだけが自分達の心の安全地帯で、せつない。
どうかラストの場面はその時代を乗り越えた2人の姿でありますように。
つらさを癒やす・・・
色々な視点
怪物は私たち大人なのかな。
2人の少年が、ある嵐の日の朝、姿を消す。彼らの身に何が起きたのか。子供の親、担任教師、そして子供自身の三者三様の視点から描かれていきます。そして、それぞれの真実が明らかになり、「怪物」の真相に辿り着くっていうスートーリーです。
最初の1.2部の保護者や教師の映像からはなにが真実でなにが嘘なのか、ミステリー形式でゾワゾワします。モンスターペアレンツ、イジメや体罰、学校の事なかれ主義、高齢者の運転問題など巧みに是枝監督が得意とする社会問題を内包させながら、物語は進みます。子供自身の視点から描かれる最後の3部でさらにLGBTQ問題が加わり、3つが重なり合いながら、真実は明らかになります。
わたし大人は自分の視点でしかものをみることができないという大人達の哀しみを1.2部では描き、それを子供が健気に受け取め、苦しみ、最後は解放?されていく。1番最後はファンタジー(死の暗喩)を感じました。
校長先生役の田中裕子が楽器を2人で演奏しながら、湊に語った言葉がこの映画が言いたかったメッセージとわたしは受けとりました。
タイトルなし
役者陣素晴らしい
怪物街diary‼️❓
久しぶりに時間を忘れて観て、深く考えさせる、凄い作品でした。
いろいろ詰め込み過ぎて、分裂気味な展開でしたが強く引き込まれて。
いろんな怪物が出てきますが、極め付けは父親役の中村獅なんたらです、実生活でもこんなんなのでしょうか、子供を豚の脳扱いにして暴力も酷い。
それに校長、教頭などの陰湿な体質、孫を轢き殺しても平気なはずだよ。
シングルマザーが被害妄想気味なのはステレオタイプですが。
良いところでは少年二人の交友関係、監督は子供の演出が最高です。
根拠のない噂話が真面目な人を追い込んでいく、これが本物の怪物かもしれませんね。
それと、壮絶ないじめをする子供、家族に辛く当たる親、保身が全ての校長教頭、それらも怪物。
高畑充希もきれいでした。
映画代が値上げしましたが五倍くらい価値のある映画🎞🎟🎬🎦是非。
ださいニット
2回観た
主観と客観
見終わったあとはなんだかなと思った
瑛太や校長設定は映画の都合で一貫性がなく感じだし、子供達の友情或いはそれ以上の関係に瑛太だけ犠牲になってしまっただけのように思えた
ただ一晩経って改めて考えるとあの映画の登場人物はみんな一生懸命に生きてることに気づいた
主観的に悪いことをしているとわかっているけどそうせざるを得ない
それが客観的には怪物にうつる
獅童はオールドスタイルで子供に手をあげているような父親に映ったが本当にそうだったのだろうかと考えなおす
子供の体のあざも教室で喧嘩した時についたかもしれないし、いじめられた時についたかもしれない
獅童がただの暴力的な親父だったらあんなに中性的な服を買ってあげるだろうか
父子家庭の設定がきいていると感じた
星3くらいかなと思ったけど5に
怪物は
サイコサスペンスの傑作と思う
「怪物」の基本情報が他者からの伝聞に限られ、そしてシーンの切り取りかたや演出が実に巧妙で、鑑賞者の頭の中でそれぞれ個人的に「最も怖い怪物」を想起させるという手法が実に効果的でした。
私は最初に出現した分かり易い「怪物」が、ノッシノッシと学校という密閉型の世界で治外法権的に暴れ回る単純な話、立ち向かう科学特捜隊の肝っ玉母さん(笑)の奮闘ぶりくらいで終始すんのかな・・・と前半の盛り上がりを見て期待してたんですけど、そんなに単純なもんでもなく、実に複雑怪奇な拡がりを見せます。
被害者が多数現れ、状況はなんとなく把握しつつ、怪物の正体も二転三転し見えない怪物の恐怖が積み重なる展開です。いや、サスペンスとして、怪獣ものの新作として(笑)、本当に素晴らしい。
また、まあイジメ問題なんかを正しく扱っている点で言うまでもないですが、「子供の善性の否定」なんかをきっちり差し込んでるあたりはむしろ、人としての個性を認めている印象で大変興味深いです。
洋画では社会派作品でもありがちですが子供=純粋無垢、等しく天使、うそなんてつきません!・・・とかいうディ◯ニー的馬鹿な幻想がないだけ説得力があります。
誰しも理不尽に怪物の被害者となり得る、また怪物とみなされ集中砲火を受ける可能性がある、実際怪物にさえなる・・・ということを痛感させられる作品です。しかもところどころ実に耽美的でもあり、たぶん傑作の部類だと思います。
ぜひご鑑賞を!
小学5年生という絶妙の設定
物事は人によって見え方感じ方が異なってくる。だから同じ出来事について視点を変えることで真相を描いていく物語の手法が成り立つ。本作では安藤サクラ演じる母親の視点、永山瑛太演じる先生の視点、そして子どもたちの視点を順番に見せることで真相を描く。
怪物だーれだ?のフレーズが予告編で頻繁に使われていたから、ちょっとしたミステリーかと思わせておいて(ミステリー的な部分もあるが)、実は2人の少年の関係を描いた物語だった。予告編以上の情報を入れていなかったから少し驚いた。
やはり坂元裕二の脚本はすごい。あの出来事は実はこんなことだったんですってさり気なく見せる伏線回収。周りに理解されないままあの2人の少年が、関係性を深めていく展開がどうしようもなく切ない。もっとどうにかならなかったの?という思いと、何かを切り開くにはまだ幼いよなという思いが入り交じる。そして愛と友情が曖昧に混じり合った関係性。そういう意味で2人が小学5年生というのが絶妙の設定だった。あれが中学生になるともっと性的な匂いが強くなって別のテイストになっていたに違いない。
最後の2人の笑顔と咆哮のシーンが、問題は何も解決していないのに幸福感にあふれていて、切なくて美しかった。ラストシーンの別の解釈を聞いてなるほどと思ったが、明確な決定打はない。あくまで観ている側に委ねられた終わり方だ。本来あまり好きな手法ではないが、あの美しさにこのラストはこれでいいと納得してしまった。安藤サクラや永山瑛太、田中裕子たちの演技もよかったが、2人の少年の演技が特に素晴らしい。あの子たちのこれからを期待したい。
是枝裕和監督作品で一番好きだったのが「海街diary」だったが、本作はそれを更新することになった。どうやら個人的には誰かが作った話を監督した是枝作品の方が好きみたいだ。
素晴らしき美少年BL映画
鑑賞後の感想はレビュータイトルそのままです。
力のある作品なので飽きずに観ることが出来、
美少年2人のロマンスにときめき、最後は思わず涙してしまいました。
ただ劇中3部構成の
①比較的普通のお母さんが子どもの怪我や奇行を不安に思い、不信感しか持たない担任や、まともに対応してくれない学校への不満が募っていくサスペンスパート
②平凡な新任男性教師が反論の余地もないまま実態のない暴力教師に仕立て上げられ社会的に抹殺される転落劇パート
上記2部がラストのBLパートに果たして必要だったのかと思うと疑問。
特に②の教師パートは映画全体の中ではかなり薄っぺらい印象。①パートの母親や受け持っている学級の生徒とのシーンもあまりなく、1人の子どもの嘘で暴力教師に仕立て上げられていく過程に説得力が無い印象を受けました。
このパートやるなら同性愛傾向のある自分の息子を豚の脳を持っていると虐待する父親の心情を見たかったと思う。
また①パートの安藤さくらさんの演技が凄かっただけに、それがラストにあまりつながっていない印象を受けたのも残念。
タイトルの怪物については鑑賞者それぞれで考えてね、と言う終わり方です。
個人的には名監督が撮った美少年BLに感化されて、危ない性癖をもつ怪物にならないようにしなければ!と思いました笑笑
怪物に託されたタイトルの真意とは
全1019件中、861~880件目を表示