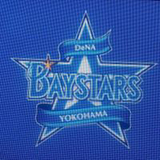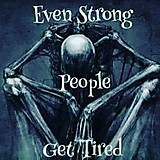怪物のレビュー・感想・評価
全1009件中、581~600件目を表示
ホモセクシュアリティな感情と人間の幸せとは
この作品は、安藤さくらが単純に教師の子供への暴力(本当は暴力ではない)を、勇気凛々と解決していくストーリーと最初は思っていましたが、途中からその想像は見事に打ち砕かれました。結論を言ってしまえば、本当の主人公である2人の少年のホモセクシュアリティな感情が、嘘を誘発し、引き起こした人間模様だと私には思えました。いじめ問題をさまざまな視点から見ると、真実は全く違うのです。その不思議なストーリー展開は、脚本家の面目躍如なのでしょうか。物語が進行していくに従って、真実が全て明らかになっていくところは、まるで鮮やかな謎解きのようです。時間軸は何度も引き戻されて、これでもかこれでもかと真実を明らかにして行きます。つまり安藤さくらの正義も、永山瑛太の正義も、全て意味を持たなくなるほど昇華していくのです。怪物というテーマについても、出演者たち全てが怪物に見えましたが、最終的には怪物でもなんでもないのです。ただ、全員が縁起の法則によって絡み合い、感情をぶつけ合い、時には憎み合ったり、罵り合ったりしていますが、結局全ての事象はなんの意味もなく、ただ、それを見る人が、幸福だの不幸だのと判断しているに過ぎないということを、この作品では教えてくれている気がしました。ラストの、少年たちが走り回る姿は、青春の喜び、至高の喜びに満ちていましたが、これはどんな人の人生も、完璧なのだと示唆してくれているように思えました。
追記 田中裕子のセリフ。「誰もが手に入れられるものが本当の幸せ」。含蓄のある言葉です。
後半が残念
怪物はいなかった
是枝作品だから結局そうなるんだろうなと思ったけど。瑛太目線の中盤まではすごく面白かった。後半はダレてきて、なんとか小さい方の子役の演技力でもった感じ。
中村獅童がいい味だしてたからもっと掘り下げて欲しかったなー。こどもを虐待する理由が(自分は学歴もありエリートだったのに妻に逃げられ酒におぼれ、頼みの子供が同性愛者なのが許せないから?)もう少しほしかった。
個人的に、是枝作品の一番の怪物は「誰も知らない」のYOUだと思う。
追記
見終わったあとはこんな終わりか。という感じだったが、あとからチクチクと色々なシーンを思い出す。一度見なのに内容を鮮明に思い出せる作品になった。
特別な映画ファンや是枝監督ファンではないのですが、面白かったです!...
人物の描かれ方、投げかけ方が素晴らしかった
自分は、子供がいて働く母だから、シングルではないけど初めのパートには割とすっと入っていけた。分かりやすかった。そりゃそうだろう、すごく辛いだろうと思った。それがダメなことではない。最後の子供達と緑の多い秘密基地のパート、子供は無垢なもの、子供だからなにをしてもいいとはいかない。どのパートにも良さと行きすぎてる面がある。途中から、不気味に響く音の正体がわかった時に、何だかそんなこともあるよなって思った。私の心の中でもトロンボーンやホルンが鳴り響くこともある。
音楽と、脚本は素晴らしかった。喋りすぎない脚本。坂元裕二さんは軽妙な会話のやり取りが魅力だと思っていたけど、特に子役の少ないセリフの中に複雑な思いを込めていて、対して大人たちのセリフは軽く、感情的だった。田中裕子のセリフはすごく深かった。一人一人の人物の描き方、投げかけ方良かったです。
誇張はあるがリアル
怪物だーれだ?
登場してくる人たち、それぞれに思いや正義があって、怪物な芽も持っている。
本人の知りうる限りでは、普通なことも違うところからみたら、筋違いでしかないことも。
そんなあり得る日常を演じている俳優陣が素敵。
音楽やごく自然な風景もいい。
それぞれの人物のスクリーンには出てこなかった裏設定を考えると、怪物になってしまう原因もあると思ったり。
いろいろな視点で思ってみるという、鑑賞後の楽しみをいただきました。
三幕目でミステリー構造から脱却し、物語性を消失させる子供たち
ゲイであると自認しながら、それをどうにか隠して生きてきた自分としてはいくらカンヌ主要賞である脚本賞とクィア・パルムを満場一致で受賞した映画とはいえ、少し見るのが不安なところもあったのですが、間違いなく大傑作であると同時に、よくぞここまで繊細で誠実に攻めた内容を日本で作り上げ、放映まで持ってこれたなととてもびっくりしています。
ある海外批評誌の記者がカンヌ映画祭で本作を鑑賞した時、「羅生門(藪の中)の構造を使うと一般の映画好きは無意識にミステリーだとカテゴライズするが、この映画は『他者の痛みの共有』のためにこの構造を転用していて、奇しくもそのジャンル的な構造を批評的に打ち壊すことに成功している」と大絶賛していて、その批評が頭の片隅に残りながら先日映画を見たのですが、見ている間はそういった「批評する自分」を置き去りにするほどの映画としての強さにとにかく圧倒されました。視聴後もしばし呆然としていたのですが、すぐに決定稿のシナリオとパンフレットを購入し、その内容を確認した後、監督、脚本、音楽、撮影にこれほどの才能が集まるとこういった映画が日本でも放映されるんだなとなぜか少し泣けてしまいました。
TAR、アフターサンと最近の映画は自分の好みに合うことも多かったのですが、この「怪物」はそれらを超えて自分にとって間違いなく大切な作品になりました。
ガチガチの構造に準拠した合理的なミステリーを見せてほしい人と構造ごといらない昔ながらのシネフィルの2パターンの人が日本人の観客には多いとよく映画監督や映画批評家で言っている人が多いのですが、パンフで脚本家も言っていた「最後、三幕目で物語性(構造)を無くす」という発想がこの映画のテーマそのものとリンクしてることに気がついて鳥肌がたち、これの凄さに気がついて脚本賞を受賞させたカンヌの審査員である監督や各国の映画祭のプロデューサーたちの確かな目と、なぜカンヌがこれほどまで世界で評価されている映画祭なのかを改めて実感しました。
スコセッシやアフターサンの監督が言っていたように「構造的に準拠した合理性からの脱却」は今活躍してる監督全員が抱える裏テーマであり、そういう部分こそ、「最大公約数なデータ集積では書けない人間の『ゆらぎ』」という形で評価される評も海外の批評誌でよく見かけるようになりましたが、そういった視点をさらに包括させるような素晴らしい映画だと感じました。
だって人間だからね
観終えた後でもモヤッとした霧が晴れなかったのはヨリ君の父である中村獅童、ホリ先が自宅に行った際「あんた大学は?」と尋ね、自らを「前はXX不動産(?)だった」と語るプライド臭プンプンの男が自らの子供を「バケモノ」だと言い、妻は何処へ?そして玄関のチャイムはガムテで塞がれ、最後にはヨリ君はバスタブの中痣だらけでグッタリ、御本人は暴風雨の中路上で酒を煽る。うーん、子供のどこにバケモノを感じ、なぜ虐待に至ったのだろう?ここの描写はもう少し丁寧にしてほしかったな。
まあ、それはさておき作品全体を通じ「人間ってそうだよなぁ」と思わせる象徴は高畑充希さんの有り様だったと思います。優しい言葉をかけているようで実は不干渉、自分に嫌なことが及んできそうになれば逃げるに限る。
誰もがそうですが、心無い言葉や根拠のない憶測を口にしたとき、大概は「いやいやいや、そんなことありえないでしょ」と返すのだろうが、例えば「ホリ先は火事の時ガールズバーにいた」・「実は孫をひいたのは校長」・「ホリ先が階段から突き落とした」・「お前女みたいだな」なんてことがどこかのタイミングで多数の意見になった途端、それに異を唱えるのではなく黙り込む、黙示の承認をしてしまうのが人間だからね。
そう思ったら、今作のようなお話は未来永劫我が国では起こり得るのだろうなと、ちょっと虚しさが拭えなくなるものを観させてもらった気がします。
さて、ラストシーンですが、校長とラッパを吹きあったミナト君が「自分はありのまま、嘘はつかない」と踏ん切りをつけヨリ君の家へ行き、二人の秘密基地で一夜を過ごした翌朝「ガコッ」と開けたドアから駆け出す、ああ、子供二人には明るい光が差し込むのか、そこだけでも救いがあった。なんてスクリーンを見つめながら思ったのですが、帰りの道すがら、どうにも台風一過の風景にしては風景が泥だらけじゃなくお花畑感満載だったので、これは別の世界に行ってしまったのかもしれないなと考えを改めたのですが、それよりも前の中村獅童の路上飲んだくれシーンとヨリ君のバスタブグッタリシーンもあったから、まだまだ別の展開もあったのだろうか、受け取り方はそれぞれにお任せします、7日もしれませんね。
ワタシ的には「どうすればよかったのだろう」と考えるのではなく「日本人の性で、発想の大転換がない限りこの手の出来事はなくせない」だろうと無力さを感じる作品でした。
緊張感と、もやもや感
一言で言って「すっきりしない、難しい映画」でした。
そこが主眼というか狙いなのかもしれません。
最後まで「どうなるのかよくわからない」緊張感で見せてくれて、面白さもあるにはあるのですが、圧倒的な引き込まれ感まではありませんでした。
自分なりの勝手な解釈ですが、タイトルにある『怪物』とは、単語そのものから一番に連想する恐ろしいイメージではなく、登場人物に(つまり人間誰しもに)内在する「怪しい物(あるいは不確かな物)」という意味で、映画にはその点での主題が貫かれ、タイトルにも持ってきたのではないか…と感じました。
登場人物はそれぞれに「自分の身にふりかかる何かを避けたり逃げたりする」時に、嘘をついたり暴れたり走って逃げたり、罪をなすりつけたりします。
普段の生活では出す必要のないそんな「怪物的な内面」が出た時、登場人物各人の関係性において実際に対峙する相手が「怪物」になる、という場面も多く登場します。
主役の2人の少年にとっての怪物は何だったのか。父や母、学校なのでしょうか。そこは曖昧にしたまま、2人はおそらく「あちらの世界(この世ではない)」で幸せそうにしている場面で終わります。
でも、最後にそうならなければいけない必然性に説得力が欠ける気がしました。
いかに上っ面しか見てないかを思い知らされます。
レビューが難しい為、前知識を全く入れたくない方はスルー願います。
夫が亡くなり、女手ひとつで育ててきた大切な息子。
その息子の水筒から泥が出てくる。靴が片方無くなっている。ケガをして帰ってくる・・・。
平穏な日常のシーンが、いや〜な空気に変わってくる。
いじめがテーマかぁと思っていた矢先、ビル火災のシーンがスイッチとなり、登場人物のターンが変わる。
そして、同じ出来事が別視点で描かれていきます。
すると、今まで信じてきた認知がひっくり返る。
共通に起こっている出来事が、見方によってここまで変わってしまうものなのか。
真実を捉えることの難しさを感じさせられる作品でしたね。
それにしても、視点が変わることでの伏線回収が非常に面白く、そしてその反面恐ろしさを感じました。
理解できているつもりが、実は上っ面しか見えない事が現実にはいくらでもあるわけで・・・
怪物だーれだ?
って、各登場人物のパート毎にコロコロ見方を変えちゃってる自分自身こそが怪物なんじゃないかと思っちゃいますね😅
もしかしたら、あの後更に別の視点で見せられてたら、あの子達の印象だって更に変わる可能性だってあるわけで・・・
なんかすごい作品でした✨
ちなみに、ロケ地が地元なんですけど、いつこんなに撮影してたんだろうと思うくらい、想像以上に馴染みの場所が舞台となっておりビックリでした!
聖地巡礼しまくれちゃいますね😁
現代社会の歪みの集結
来年還暦の自分が過ごして来た時には無かった、現代社会の矛盾や善悪の全てを一気に描いた様な作品、疲れたしそして観終わった後まで考えさされる秀逸な作品でした。
怪物だーれだ
親の視点、先生の視点、子どもの視点。
視点が変わる度に登場人物が違う人間に見えてきて感情がぐちゃぐちゃになる。
音楽も必要最小限で、ストーリーをダイレクトに突き付けてくるような重さを感じる。
ラストシーンは人それぞれの捉え方があるだろうけど、「え、終わり?」とも思ってしまったw
果たして怪物は一体誰なのか。
あなたが思う怪物は、もしかしたら…
結局怪物はいなかったということ?
色んな人や物事が怪物のように見えるけど
視点を変えて見ると怪物なんていませんでしたってことなのかな?
みなとくんがほり先生にやられた、先生に言われたと嘘をついた理由や
みなとくんが猫で遊んでた→そんなこと言ってませんという女子生徒の発言など
結局最後までよく分からず終わった部分がいくつかあった。
説明不足なのか、伏線を回収し忘れたのか、物語を怪しく進めるために無理に入れた展開なのか、それともただ私の理解不足か何か見落としてしまったのか、、
そして、みんなの勘違いが重なっていたことは分かったけど
何も解決していないし、当人たちの誤解も解けていないし、ほり先生が社会的に死んだし、これで完結しちゃっていいの?と思った。
でもだんだん裏側が明かされて繋がっていくような展開の映画が好きなので、初見では見ていて面白かったです。
もう一度見たいとは思わないな。
誰もが「怪物」を飼っている
みんなホントに高評価なわけ?
怪物、いえいえ、ふつうの人間のおなはしだよ
脚本は同じ時間軸を視点を変えてトレースするように構成されており、前半と中間が謎掛け、後半がその答え合わせのようになっていて、上手い展開だなとは思いました。
ですが、台詞回しに不自然さを感じます、特に前半と中間はミスリードしてやろう、してやろうとするような違和感が残りました。
「私が喋っているのは人間?」
「あれは化物ですよ」
なんなんですか、あの台詞回し、個人的にはいただけませんな〜ぁ
予告編からして、もうすでにミスリードしてやろう感を醸し出しているのも気に入らない
後半は一転、少年二人が主人公でテイストがまるで違って、BLになりそうでどきどきしましたが(笑)違う意味で、ほほうって感じで楽しめました。
結局、怪物なんてどこにもいないじゃない、わざわざ怪物探しなんかさせようとする意図も観終えてしまえば個人的にはしらけてしまった。
少年二人のお話に、安藤サクラも永山瑛太も中村獅童も怪物と言うよりむしろピエロに見えました。
唯一、人間然として、人間臭い、田中裕子さんは良かったです。
怪物なんていない、人間の話です。
是枝裕和だから⭐をつけたり私はしませんので悪しからず、この映画の⭐は皆さん、是枝裕和に忖度し過ぎだと思います。
全1009件中、581~600件目を表示