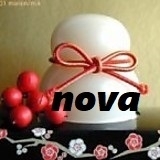怪物のレビュー・感想・評価
全1009件中、521~540件目を表示
自分の中に潜んでいる怪物性に気付かされました…
公開前から何かと話題になっていた本作ですが、内容については全くの予備知識無しで観ることが出来ました。
色んな視点から語られる真実。
それぞれの立場にたてば全てが真実。
その中で、勝手に犯人を決めつけている自分…。
あぁ…怖っ!
ラストシーンですが、三途の川を越えて、二人はようやく望み通りの新しい人生へと歩み出す…と希望に満ちた解釈をしたのですが、どうでしょうか?…っちゅーても死んでるんですが(笑)
あの火事は対岸の火事ではなかった
湊かなえさんの「告白」を思い出しました。物語は全く違いますが、親、先生、生徒の視点によって見方がガラリと変わって反転する立場に、足場が崩れるような不安定な気持ち悪さを感じた。本当の事実は誰だったのかといえば、この物語でいえは主人公たる二人の少年になると思う。怪物って誰だろう?じゃなくて、そもそも怪物を探している側が「怪物」じゃないと何故言い切れるのだろうか?冒頭の火事は、対岸の火事ではなかったということ。
また、校長先生の言った「幸せとは~」に悲しさがあるけれど、ほんの少しのあたたかい視線も感じるのは、私のただの願望だろうか。最後の二人の少年の姿も同じく、そうであって欲しいと願わずにはいられない。
これもまたきっと、独りよがりなんだと思う。
それぞれの・・・
タイトルなし(ネタバレ)
長野県諏訪湖にほど近い小学校。
クリーニング店で働くシングルマザーの麦野早織(安藤サクラ)は、ある日、5年生のひとり息子・湊(黒川想矢)がいじめに遭っているのではないかとの疑念を抱く。
幾日か経た後、その疑念は確信にかわり、いじめの主体は教師にあるように思えた早織は、学校へクレームを入れに訪れた。
そこでは、担任教師の保利(永山瑛太)のみならず、校長先生(田中裕子)も死んだような眼をして、頭を下げるだけだった・・・
そして、、担任の保利からはなぜこのような事態になったのかはまるで理解ができないままで、保利の眼では湊を虐待したことなど一度もなかったとしか思えなかった・・・
といったところからはじまる物語で、母親・早織と担任教師・保利からみた事態の顛末はまるで異なっている・・・というのが映画の導入部。
いや、導入部と書いたけれど、ここまでで1時間以上経過している。
それぞれの視点からの事態は、様相が異なっており、いわゆる黒澤明監督『羅生門』的でもある。
で、大人ふたりの視点からの物語のあとに少年の視点の物語がつづられるわけで、早織の息子・湊と彼の友人・依里(柊木陽太)の物語が本編のメイン。
ここで映画かれる物語は、かつてならば「奇妙な」と形容される類の友情譚なのだけれど、現代の価値観からいえばそれほど奇妙でもない。
依里は、ある種のギフテッドのような才能があるのだけれど、周囲との同調性はなく、なかんずく中性的な魅力にあふれている。
(ギフテッド的才能なのはわかりづらく、観ている間はある種の発達障害にも感じられました)
さて、そんな依里だから周囲の男子生徒(男子だけなのは、よく見るとわかる)からは疎外されて、いじめの対象になっているのだが、本人は唯々諾々、馬耳東風、そんな馬鹿なことには当事者でありながら我関せず。
そんな依里に好意を抱いていく湊の物語として、一本の独立した映画でもよかったのではないかしらん、と思った次第。
思春期前夜の少年の恋愛とも友情ともつかない物語を、映画は、『銀河鉄道の夜』『スタンド・バイ・ミー』のモチーフも用いて描いていきます。
坂本龍一の音楽と相まって、切ない感じが醸し出されてきます。
さらに、依里少年の無邪気さが、意図的な邪気はないのだけど、すべてが善意ではないという感じで、妙に大人以上に大人びていて不気味なところも魅力なのだが・・・
で、個人的に評価が悩ましいと感じたのは、前半の大人ふたりの視点をわざわざ切り出してみせる必要があったのかどうか、というところ。
たしかに、ものごとは一面的でなく、みた人によってそれぞれの受け捉え方はかわり、真実とは遠ざかっているのかもしれませんが、後半の少年たちの物語と比べると、なんだか図式的になっているような感じがしないでもない。
また、後半の少年たちの物語に、校長先生の視点がはいっているもの、観ている方を混乱させます。
(組織のなかで、虚(嘘)をとおして、自分を守ろうとする身という共通点はあるものの。また、校長先生と少年ふたりが同じコインの表裏というにしては、なにかコンテキスト的には弱い感じもするわけで。)
ということで、ラストシーンも含めて傑出したシーンもあるのだけれど、どこか「ヌエ的な映画」という感じを拭い去ることができず、もろ手を挙げて評価するところまではいかなかったです。
なお、ヌエというのは「猿の顔、狸の胴体、虎の手足、尾は蛇」という日本の昔の架空の動物ですが、ま、その実、レッサーパンダだよね、という動物学者もいるようです。
ははは、レッサーパンダ。
湊くんと依里くんのようでかわいいね。
怪物は内に潜む
人は「自分の見たいモノしか見ない」現代的なテーマ
お話そのものは多くのメディアで紹介されているので
多くは触れませんが、色んな方の考察で語られているように
所謂「羅生門形式」
同じ一つの事実でも、それを見る者によって
全く違う印象になってしまう。
と言う作りの映画。
カンヌ映画祭でクィア・パルム賞を受賞したので
LGBTQに興味が有る無しで偏った味方をされなければ良いのですが〜
LGBTQの話はもちろん重要な要素ではあるけど
そこがメインではなくて、
この投稿のタイトルの様に
「人は自分の見たいモノしか見ない」
現在のネット社会の大きな問題であると同時に
人間の普遍的な部分なのでしょうね。
ネットの無かった時代にも
「人の口に戸は立てられない」とか
「人の噂も75日」とか言われるように
中途半端な情報と思い込みっていうのは
時に人の人生を狂わせることもある。
そう言う諸々の人間の愚かさこそが
「怪物」
なのかな〜〜と思ったりしました。
で、月に8回ほど映画館で映画を観る
中途半端な映画好きとしては
考察のしがいのある映画でしたね。
ストレートではなく意味深な場面の多い映画であり
正直、そこはミスリードでしょ!と
突っ込みたくなる(苦笑)場面もあるのですが、
そこも含めてなかなかに楽しめました。
一回の鑑賞では消化しきれない映画なので
時間が合えばもう一度観たいです。
昨年の流行語だったか?
「〇〇らしいよ〜 知らんけど〜〜」
って言うのあったのですが
私、これ、全然笑えない!!
「知らんのなら言うな!!」ってなってしまう。
人間の間違った思い込みと
情報の垂れ流しの罪深さよね〜〜。
兎に角見応えがあります。
映画館で全集中でご覧下さい!!
想像で
補う「余白」が、たくさんある作品。
映像がヒントで、多くは語られず、
ピアノの音色に翻弄され、導かれ、癒される。
出来事の「結果」から
(良くないことばかり)考えてしまって
心拍数が上がる。
でもそれは「大人側」の
短絡的で断片的なもの。
「子ども達」は、大人に「気をつかい」、
嘘をつく。
事実を隠し、
自分を、大切なものを守ろうとするのは
大人も子どもも同じで、、
そうすると、
したたかで、嘘つきで
裏表のある人達ばかりが
生き残ってしまう、、
あの子は、家業を手伝うよい子、?
「優しさ」を見逃さず、守るには、、?
正直で、噓が下手な、不器用な人達を、、
「ナマケモノ」の特性を身に付けて
大人になったのが、保利先生なのでは、?
、罵倒に鈍感過ぎる、
「耐える」ことに慣れ過ぎてる?
彼は何故、キャリー、?
時々映る、川と湖、、?
「ポニョ」「スタンドバイミー」
「リバーズ・エッジ」も見え隠れ
「みんな、病んでる
必死で生きてる」
人も物事も、
多面的で複雑なことを
心して、
大人のフィルターが濁りがち
なことを、認めて、、
子ども達の「逞しさ」を信じたい、と思った。
誰もが手にするもの 誰かが手にするもの
ヒトは誰もが安心して暮らせる世界を目指した結果、誰もが生きづらい世界になりました。何故かな?。大人が生きづらい世界にいる子供たちには、どんな現実と未来が用意されたかな?。
こういう映画が創られたこと、こういう映画が評価されることに、戸惑いを禁じ得ません。つまり、誰もが手に入れるものより、誰かが手に入れるものに、ヒトは共感することになります。校長先生の謂うところの、どうでもいいものに、ヒトは惹かれるわけです。きっと私もね。そんな私が手に入れたものは、かなり怪しい物みたい。
何とかしようとする大人達が造る、何ともならない世界。無邪気に他者を破壊する、壊れた子供。そのまま大人になった、壊れた大人に気を遣いながら、壊れないようにもがく子供。その狭間で何とか足掻く親。皆様は、誰に共感できます?。
時系列の組み方が絶妙ですね。まず御見物に、?を想起させて、シャッフルした時間で御見物に、!を届ける。やはり脚本の勝利でしょう。「パルプ フィクション」を彷彿とさせます。ただ私としては、こと無かれ世界のラスボスとして、怪物級のオーラを放つ田中裕子に、何か賞あげたいなー。
私、是枝氏の映画を総て観たわけではないですが、ちょっと変わったかな?。これまで、どん詰まりの先にある、光のようなものを描く映画が多かった気がしますが、本作は、さらにその先まで突き抜けちゃった感が…。
未来を生きる子供たちに、私達は何を遺すの?。
皆様の歩む先に、出発の音が、聞こえますように…。
人間の数だけ怪物がいる
主に、湊の母、担任教師、湊と星川くんの3部展開。
3人の視点に加えて、校長、学校の先生達、同じクラスの小学生達、ママ友達の[閉鎖感・退屈・嫉妬・弱さ]による少しずつ複雑に積み重なったすれ違いや嘘が、各々にとっての怪物になる、そんな話。
湊の母は決して過保護ではなく、夫が事故死したので夫の分も頑張ろうとして息子のことを第一に考えるあまり、本当のことを湊の口から聞き出す方法が性急でストレートすぎて湊に嘘をつかせてしまったのかな…。
もともと不器用なタイプなのかもしれない、夫が不倫旅行で事故死しちゃうくらいだから、不倫も気づかなかったのかも。
担任教師も、真面目な人だけど湊や生徒の嘘でメディアに叩かれ辞職に追い込まれてしまう。
薄情女にプロポーズしちゃうあたりも、人の心を読み切れない若造を表現したのだろうか。いい人なんだけどね。
「真実は誰かの口から語られたこと」という幻想をそのまま信用している大人達。それを利用する子供達。
『事実は一つ』だけど『真実は人の数ほどある』というのに。
絶対性別感、先生は潔癖でないといけない神話、親からのクレームは全て受け入れる、波風立たせない風潮、を逆手に取り、閉鎖的な町で退屈を持て余したママ達や教諭達は事実無根な噂話で担当教師を追い込む。
クラス内のいじめも同じ。湊の隣の席の女の子も、湊のことが好きなのに自分を見てくれない嫉妬心から星川くんがいじめられているのを見てみないふりどころか焚きつける。
小学生のうまく言語化できない憤りによる嘘や行動は自分の人生を振り返ると思い当たる節がありすぎる。
決して悪気があるわけじゃないところもせつない。
校長も目も心も死んでたけど、ラストで本当は真っ当な先生だったことがわかる。
きっと、今まで同じようなことが起こるたびに先生や生徒を守ろうとしたけど、うまくいかなくて疲弊し心を殺さないと続けられなかったんだろうな。
星川くんと湊が秘密基地の中で怪物当てクイズやってる時、湊のお題のナマケモノの特技を「攻撃されてもフワフワして心を殺してやり過ごす」的な説明したら、「わたしは星川依里ですか」って返したところ泣けた。ああ、ちゃんと見てくれてる人がいる、って嬉しかっただろうな。
フィクションの映画なのに、作品中に流れるテレビ番組にLGBTQ表現で出演したのは「ぺえ」。
全体的にすごくリアルな演出してる上、架空のテレビ番組に本当の情報を入れてくるあたりギミックが凝りすぎててうへぇ〜!ってなった。
監督に是枝さん、脚本に坂元さん、音楽に坂本龍一、企画に川村元気、って最強の布陣だな。
ほんとにどうでもいい話だけど、「ある男」でも安藤サクラは旦那2人に先立たれ、今回も先立たれて、しかも子供ももしかしたら先立たれ、万引き家族では誰も家族じゃないし、薄幸感がたまらんんん。
作品を鑑賞している観客の認識をジェットコースターのように揺さぶる構...
ミステリー版すれ違いコントな感じ
誰が怪物だったのか。
皆さんのレビューで分かりやすい解説がいくつか載っていたので、私はこの作品の題名について考えたことを述べたいと思う。
羅生門スタイルで進んでいく物語だが、はじめの母親視点では、教師側が怪物に見えた。
そして、後半教師側の視点となると、母親側、もしくは子供が怪物かもしれないと視える。
結局のところ母親も子供も担任も怪物ではないと分かったのだが、では誰が怪物だったのか。
それはこの映画を視ている我々こそなんじゃないだろうか。
演出一つで対象を怪物だと思い込む…
少なくとも私はその怪物のひとりになってしまった。
今後のものの見方について一面だけみて結論づけるのは怖いと感じた。
誰が怪物なのか?凄い映画です。92点
怪物はあなたの隣にもいる
ヒリヒリして
是枝監督の映画は初めて見ましたが、映像の美しさやカットの妙がとても素敵でそりゃ評価の高い監督なんだなと納得。
映画論は分からないので、ただ自分の感想ですが、シングルマザーにいじめに虐待に教育現場問題、モンスターペアレント、LGBTと詰め込みまくって(それなのにまとまっているのはすごいことなんだと思いますが)、ちょっと疲れてしまいました。
飴のシーンと消しゴム拾うところが違和感。なぜ先生を貶めたのかも考察が浅いのかよく分かりませんでした。そしてこれから小学生になっていく子どもを持つ親としては、そんな嘘つかれたら分からないよと怖くなってしまいました。
湿度を感じる映画
個人的に印象に残る映画って、
湿度を感じる映画だなぁと思います。
全然違いますが、パラサイトを見た時も同じようなじめっとした空気を終始感じました。笑
人の怒り、焦り、後悔、憎しみ…様々な感情が、
役者さんたちの芝居、そして映像を通して湿度を持ってとてもリアルに伝わってきました。
特に保利先生の視点からのシーンでは、
追い詰められる保利先生の焦りや怒りが、流れ落ちる不快な汗を通してとても伝わりました。
人間の想像力には悲しいかな限界があって、
この映画は3人の視点から描かれているけれど、それでも全部を描き切れることは到底ない。
"答えはないからこそ面白い"というありきたりな結末ではなく、観終わった後に
"人間ってなんなんだろう"
"私たちの見えてるものって主観でしかないんだな"と、
ちょっとじとっとした、なんとなく不快な後味が残りました…。
でも、いい映画です。
全1009件中、521~540件目を表示