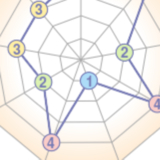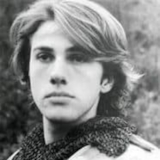ゴジラ-1.0のレビュー・感想・評価
全2054件中、701~720件目を表示
VFXがすごい
正直ゴジラシリーズは自分の好みではないのでこの作品を見るつもりはなかったのですが、予告編では銀座を暴れまわるゴジラにちょっと興味が湧いたのと日米双方の評価が上々とのことなのでこの機会に見ることにしました。
今回の主役は神木隆之介。彼はちょっとナヨっとした線が細そうなイメージがあるのですが、今回は元特攻隊員という役。
VFXで描かれた戦後直後の街並みの様子は驚くほど本当に良くできている、ゴジラが街中を暴れまわる様子は確かに凄かった。
ただ、元特攻隊員なのに今回もまた生きて帰ってきちゃったし、なんとなく物語的にはすっきりしないかな。ビジュアルとストーリーがちょっとアンバランスなところが気になりました。
ゴジラ━1.0満足
誰でも楽しめるゴジラ映画!かも
ゴジラ-1.0・・ ではなく、戦後間もない日本の成長(プラス)への側面こそ強く感じた
そして、僕が今まで観たゴジラ映画(邦画・洋画)の中で、抜群に素晴らしい映画だった
いや、僕の好きないくつかのゴジラ映画には、また違う素晴らしさがあるが、今回のゴジラ映画は総合的にずば抜けた素晴らしさがあった
戦後間もない日本が舞台ということで、設定の無理やり感が目立つかと思いきや、あの当時が背景だからこそみせられる素晴らしい脚本と演出に脱帽
冒頭の展開が、伏線として本編に最初から最後までガッツリと効いていたのも演出の妙であろう
今までのゴジラ映画でありそうでなかった、普通一般の映画と同等に感じる人間ドラマと関係性の面白さがしっかりありつつ、だけれどもテンポよく激しいアクションシーン、ゴジラの魅せ場などがうまく融合していた
人間ドラマがしっかりしているから、主人公を筆頭に主要キャストに大いに感情移入してしまう・・ そしてそこに【大災害ゴジラ】の圧倒的な存在感!! その融合が素晴らしい!!
今回のゴジラは、今まで以上に【災害の象徴】と【核兵器の象徴】としての印象が強く、特に近年、もしくは未来に起こるとされている大災害を観るかの如くであった
プロトンビームが凄まじい!!
ちなみに、朝ドラ【らんまん】にハマっていた人は、さらに上乗せして大いに楽しめること間違いなし!
ゴジラ映画、怪獣映画は苦手だという人にも大いにお勧めできる映画です!!(^^)
#ゴジラ #山崎貴
音楽の力は偉大✨
アキコちゃんかわいかったねぇ☺️
西武ゆうえんちでらんまんをくらえ!
みたいな映画でした
殺意つよめのゴジラに
らんまんを口に詰め込まれました
胸の大きめのゴジラ
足大きくて泳ぎ上手そう
登場人物全員、演技力が♾️カンストみたいなひとたちばかりでした。怒涛の演技力を浴びました。安藤サクラさんの怒鳴り声なんて空気が凍る。博士のメガネがずっと傾いてた気がする。あの髪型どうなってるの。らんまんふたりは流石の演技力。モブの人たちもいちいち良い存在感で良い演技をされていた
アキコちゃんかわいかったねぇ☺️
楽しめました!
2回目はIMAXで見ました。海外評価が高く、もう一度見直して見ました。1回目で気づかなかった仕掛けも見つける事ができました。
ゴジラの登場シーンは少なからず多からずで、怖さと興奮です。登場人物の精一杯な演技は好感持てます。皆頑張っていた。
音楽も最高で、あの定番メロディが流れてくると思わずポロッとします。
色んなレトロなオートバイや飛行機、軍艦など何気なく見ていましたが、全部こだわりがあったとはコメントなどを見て知りました。その上で見ると更に楽しめました。
YouTubeのコメントもゴジラに関して沢山あり、日々更新されていてそれも楽しめました。
冒頭に書きましたが、海外での評価は高く(とても嬉しい)自分も同じ評価です。映画なので、素直に楽しみたいですね。
生きろ!...嫁と二人して号泣しました
最近、邦画も洋画も期待外ればかり。ゴジラも平成シリーズ?を数本観た程度でとてもよく眠れた記憶があります(笑)
熱烈に推して来る怪獣マニアの友人の瞳の輝きに負けて(笑)さして興味のない嫁を連れて、これも友人推薦のIMAXレーザーで観賞して来ました。
これはね...怪獣映画ではありません。
全ての登場人物に感情移入してしまいます。クライマックスでは頑張れ!!と泣きながら心の中で叫んでいました。野田さんの『生きるための戦いです...』橘さんの敷島君への『生きろ!』沁みましたね~。
米国での高評価もうなづけます。ちっちゃな事には突っ込みません(笑)
それにしても伊福部氏のゴジラのテーマ?ってこんな凄い音楽だったのね♪︎
東京タワーくらいかと思ったらエベレストだった
評判がいいのは聞いていたので期待はしてたが、ホントにはるか上をきた神のなかの神作品(東京タワーくらいだと思ったらエベレストくらい)だった。
映像から神。すさまじい迫力と臨場感。とく戦闘機のシーンはまるで西武園ゆうえんちのゴジラザライドに乗っているかのような迫力。街と人を蹂躙していくシーンは恐怖も絶望も、ゴジラのカッコよさも全部詰まってる。熱線のシーンの必殺技感(ガチかっこいい)。ハリウッドにもひけをとらないと思う。
音楽もシーンの魅力を百倍に増幅してくる。
シンゴジラのときは音が無駄にデカすぎて軽く音酔いしてしまったのだが、本作ではそんなことはなく、シーンにベストマッチしていて、迫力をさらにプラスしていた。
ストーリーもよかった。ゴジラ映画は人間ドラマはもうどうでもいいと思っているのだが、今作は人間ドラマがいい。ベタと言えばベタだし、ご都合と言われたらまあ分からなくはないし、あーこうなるよねと予測はできたが、それでも、上手くまとまってるし、めちゃくちゃ感情移入できた。ゴジラ映画の人間ドラマとして完璧だった。ないないづくしのなかで戦争を生き残った人たちが団結して、なんとかしてゴジラに立ち向かうという展開もいい。後半は激アツ展開の連続でもうワクワクしっぱなし。ゴジラ撃破のためのあのアイデアもすごい(よく思い付いたな)。
キャラもよかった。とくに佐々木蔵之介のキャラは結構気に入った。キャラが生き生きしていて、それぞれに魅せ場もあって、キャラを上手く生かしきれている。
この映画はこれまで見た映画のなかでも最高の作品のひとつだし、ゴジラ作品のなかでも最高クラス。今年最高クラスの映画で間違いない。
ゴジラの皮をかぶった人間ドラマ
ゴジラや特撮ファンではないので特に観る予定はなかったのですが、全米でもヒットしていると聞き、興味を引かれて観に行きました。だって、第2次世界大戦後の日本を舞台にしたゴジラ映画で、字幕で観ることに慣れていないアメリカの観客を満足させることができるなんて余程のことですもの。
感動した!泣いた!という声もゴジラのコアなファンの過剰な反応じゃないかなぁって。
でも、舐めていました、すみません。ゴジラ・マイナスワンは怪獣映画の皮をかぶっただけの、ちゃんとした人間ドラマでした。戦争の虚しさ、もたらされるトラウマ、苦難の中の助け合いと復興、ささやかな平穏の幸せ、そして突然襲い掛かる災害とそれに懸命に抗う人々、生きたいという願いと許し。根底にある物悲しさ。日本人にはめちゃくちゃ刺さる人間ドラマが展開されます。
ゴジラ映画という割にはゴジラがほとんど出てこないことに驚きましたが、それが気にならないほど人間ドラマに引き込まれました。ちょっとだけ現実に引き戻されたのは、人間ドラマの長さにふと気が付いたとき、「え、こんなに人間ドラマ部分長くてもアメリカ人ちゃんと観てくれてるの?!」っていう驚きを覚えたからでしたw(あちらの映画見てると観客が怪獣映画目当てで映画館に足を運んだなら、ドカン、バキッ、ガシャーンとアクション・びっくり要素満載じゃないとアメリカ人は満足できないんじゃって考えてしまってw 偏見でしたね)
なによりも、神木君、こんなにいい役者さんに育っていたんですね。前から好きでしたけど、少年のイメージが強かったのに、この映画の中では「青年」そして成熟した「父親」へと顔を変えていきます。「やれやれ泣かしにくるかな」と普段であればやや白け気味になってしまうようなシーンでも、神木君の演技に一瞬でぐいっと引き込まれ、気が付いたら涙が流れていました。ゴジラという非現実的で理不尽かつ巨大な脅威に対する「恐ろしい」という感情を本物にしたのは神木君や他の役者さんたちの演技力に他なりません。
確かにハリウッドの映画に比べたら「あ、ここ予算足りなかったか」と思うような箇所は所々にはありました。でも、VFXの進歩によってもはや昔ほどの差はなくなったように思います(監督がVFXまで担当しているとかびっくりですよw)。なにより、ポリコレや人種問題を抱えているために無理矢理な設定や同じようなコンテンツしか焼き直せない昨今のハリウッドに比べて、日本のエンタメはまだまだカオスなまでに自由です。
アニメにしろ、特撮にしろ、日本が独自の進化を遂げてきたエンタメのジャンルを皮切りに、日本のエンタメ業界はまだまだ世界へと躍進していくことができる。ゴジラ・マイナスワンは、そんな可能性と希望に溢れた作品だと思います。
[個人ノート:クレジットにSQUARE ENIXが出てたのにはびっくりw ゲームもCGがすごいものね~]
ゴジラだけ凄かった
ゴジラ周りの映像だけ凄かったです。
戦艦や戦闘機の映像も凄く良かったです。
ただ人間ドラマの部分が??という場面が多かったです。
とくにクライマックスのあたりです。
ゴジラ討伐作戦のための準備の進行と同時に、敷島は隠れて戦闘機に爆弾を積んでゴジラに特攻することを計画します。
敷島が仲間を死なせてしまった罪悪感や妻をゴジラに殺された恨みからゴジラを倒して死にたいと思ってる という展開は分かるのですが、作戦が成功するか失敗するか分からない段階で特攻ありきで動く意味が分かりませんでした。
わが子のアキコを隣人に託していることからも特攻して死ぬことは彼の中で確定しているのでしょうが、そう考える伏線のようなものもなかったので見ながらこの展開の理由を考えいました分かりませんでした。
ラストでは敷島は死ぬことを止めて生き残り、妻の典子が実は生きていたというハッピーエンドで終わります。
しかし、この一連の流れは映画を見ている立場からすると、敷島は妻は実は生きているのに思い込みで特攻を計画して、下手すると無駄死にだったけど結果的に生き残ったから良かったね
という物凄く間抜けな話になるのではと感想を持ちました。
ほかにもこのように細かい気になった個所があるのですが、おそらく監督や制作陣は「こういう風にするとみてる人は感動するハズ」という展開を思い付いてそこから逆算でストーリーを考えているのだと思います。
例えばラスト付近でゴジラ討伐作戦が失敗しそうになったときにたくさんのひとが船で助けに来るという展開があります。
これは「敵に負けそうになったときに味方が助けに来るって熱い展開だよね」という展開あ
りきで作られたのでしょう。
しかしなぜ彼らがそう行動したのか?と描写がまったくないために説得力がなく感情を動かされません。
また、作品の舞台を終戦直後の日本にした理由も監督が昔「always 三丁目の夕日」という時代設定の近い作品を成功させた経験を生かしたいという理由のためだけに採用されたのだと思います。
そのためセットや小物に至るまで非常にレベルの高い背景美術を実現していますが、なぜ終戦直後でなくてはならなかったのか?という理由が作品からすっぽり抜けているように感じられました。
ゴジラが出てくるシーンの楽しさと人間ドラマパートのつまらなさの落差をトータルで評価すると低いものになってしまいました。
待ってましたぁー♪
人は逃げる時に何処へ向かうのか。
ゴジラ-1は当初北米で1週間のみの限定公開の筈が、好評だったため期限が延長された。
海外の批評もすこぶる良く、英語圏でのSNSの評判も良い。
僕はこの監督と相性が悪く、毎回強制的に泣かせようとする圧力が苦手でしんどかった。
結果今回もしんどかった。
所々にある脚本のアラと役者に対する演出の低さ、フレームの構成による画面の美しさを殆ど感じることがなく、ただただ製作陣が好きなシーンを撮って繋げているだけ、そうとしか思えなかった。
冒頭の特攻できなかった兵の生き方がこの映画の主軸なのだが、そこはまあ良いとして、集団が逃げる時に同じ方向に逃げる非効率なことをするだろうか。
対照的なのがスピルバーグの宇宙戦争。
人々は直進しつつも脇の建物に逃げる。
多分これが普通の逃げ方だと思う。
四散しない人々の動きのせいで、かえって不自然なシーンに思える。
日本の戦艦(駆逐艦?)が途中合流して砲撃するシーンは良いが、甲板で傍観するだけの水兵のお陰で、軍人の存在を感じない。沈没するギリギリまで主砲を撃ち続けた砲兵を映すだけでももっとドラマになった筈。
後半の先頭で駆けつけた小型船団もあの短時間で曳航出来るのも違和感を感じる。その間ゴジラは待っててくれたのか。
演出面で言えば、最後の震電の突撃の無音状態。
その無音のまま突撃させればいいのに絶望感だけ演出しているので感動が弱い。あの無音状態はもっと続けば良かったと思う。
欲を言えば、海面の向こう側の太陽を影にして震電が飛び込んでくれば絵も美しかった筈。
僕には所々アラが目につき、イマイチ感情が乗らずそのまま終わる映画だった。
シンゴジラの様な理屈っぽい要素は少なく、監督のここで泣けと言う圧力に耐えながら、何故上陸したのか謎のゴジラを見守るだけの映画。
うーん、僕が求めていたのとは違う気がする。
やっぱり面白くない
世間的(主に海外?)で大好評だったので、基本「映画館」なんて行かないのに行ってきました。
感想としてはタイトル通り。
ダメな部分や面白くないと思った部分は時系列順(よく覚えてないから大体)で書き殴ります。
・臨時着陸場が超狭い感じが出すぎていて、自主映画のよう
・演技がクサイ(数十年も邦画に対して思う事)
・とってつけたように出てくる子連れ女性
・長年一緒に4畳半のようなレベルで生活しながらも他人
↑だから感情移入し辛い
・いちいちこれみよがしに出してくる子供シーン(血縁無し
↑上に同じ。子供出しとけば感動するだろノリが酷い
・学者の初登場シーンの職と後半の立場のギャップ
・主人公jが乗るオンボロ船相手にやたらとおっそいゴジラ
・上記のあと、他の軍艦等には素早い動き(笑
・ゴジラがドムみたい下半身。顔が田舎の土建屋。
・ゴジラの行動原理、仕草、ノロマ具合
・リアリティのない逃げ惑う民間人
・ご都合主義ここに極まれりなヒロイン電車シーン
・なぜか主人公だけが残るゴジラの攻撃
・最悪なシーン「電報」
・さらに最悪なのが起爆スイッチ説明のあとのシーン
(↑馬鹿でもわかるレベルでしらける。その前のチラ見でさえ萎えるほど過剰演技なのに、視聴者馬鹿にしすぎ)
・蚊みたいな戦闘機を必死に追いかけるゴジラ
・陸上でも届かないのにも関わらず海まで追いかける(笑
・すっとろい船相手に、速く動けるゴジラが戦闘機に気を取られてるテイからの、巻きつける作戦成功シーン(動けよ・・
・案の定、特攻アリきのストーリーでフィニッシュ
・見事に最悪シーンの回収で無事帰還
・挙句の果てに最悪シーン「電報」ここに絡んできてハッピーエンド(ワロタ
いやもう、ほんとなんていうか、クッソおもしろくないです。
個人的にどうやら邦画が嫌いらしくて、あのくっさい劇画風というか宝塚のような、過剰な演技とセリフが無理。
大作としてはあり。
皆様の熱いレビューに、またしても動かされた
ホントに最近、観たい❗️と思う作品が無くて足が遠のいてました。
それでも、劇場に行けるタイミングがあり、そこから何観ようか、3択でした。
「N」か「T」か「G」か
やはり決め手は、こちらでのレビューでした。
いやー、皆さん熱いなー😳
思い入れゼロの自分が観に行っても良いもんだろうか❓
と半ば躊躇いつつ、いざゴジラへ。
思い入れゼロ、とは言いましたが、
「シン・ゴジラ」はとても楽しんだ人です。
観る前は、アレを超えるゴジラは無いだろう、山﨑貴だし、なんて思ってました。
戦時中の話になってるのも、「永遠のゼロ」「アルキメデスの大戦」とかで味を占めたのか、と意地悪い解釈。
だがしかし、ゴジラの存在感たるや、圧巻‼️
VFXてここまでキテルんかー‼️スゲー‼️😱
ゴジラの出立も去る事ながら、
プロットも悪くなかった。
多少目を瞑ったのはあるが😅
大戦が終わり、生きている人たちには、大戦で死んでいった同胞への後めたさは、戦地に行った行かないを問わず誰にでもあり、特攻から逃げた敷島浩一は人一倍ソレを感じていたであろう。更に典子の件もあり、浩一のゴジラ殲滅への執念はかなりエクストリームである。
こういった流れは良い。
対ゴジラへのスムーズな流れ。
何故か途中醒める。
神木くんは、そのエクストリームな浩一をもっとエクストリームにやって欲しかった。寝床で「私はホントに生きているのか❓」と錯乱してる時、もっと嗚咽や慟哭が欲しい。杉咲花を見習って下さい。
蔵之介はキャラとしては良いが、セリフがくどい。
美波ちゃんは、今一番娘にしたいNo. 1であるので特に問題無い🤣
が、電車のシーン、すごい耐えたねー。
最近やった「M・Iデッドレコニング」観てから撮ったのかなー🤣
そして、ポツンと橋爪功🤣
吉岡秀隆が意外と良かった。まあいつもあんな役ばかりだが、「この国は命を粗末にし過ぎてきました」あのシーン、セリフは刺さった。
優香のダンナも、途中足引き摺るのやめたけど好漢でした👍
こうして、ゴジラに対峙した人々の話をしっかり描いて、そのモチベーションもしっかり見せて、お涙頂戴シーンも作って、割とちゃんとした映画だなーと感心しました。
思えば「シン・ゴジラ」は、対ゴジラよりも、その出演者たちの群像劇が多すぎて、ゴジラ作品というより、一時期の三谷幸喜作品の様な感じすら出てましたね。役者が豪華なだけ、みたいな。アレはアレで良かったですよ勿論。
石原さとみの「ガッヅゥィーラ」以外は🤣
という訳で、シンゴジとは別物の、新しいスタンダードか出来たのかな。続編ありそうだし。首の痣説明してくれよ。
またしても皆様のレビューで良い作品に巡り会えました‼️
ありがとうございました🙇🏻♂️
身近に怖い
こんなに恐いゴジラをみたのは初めてだ。
私的な好き嫌いでもの申すのなら、圧倒的にシンゴジラのほうが話は好みだが、それは全体を俯瞰して対処すべきゴジラという存在に、国全体の問題に立ち向かう国家公務員が、民間の協力を得ながら役目を全うし、リスクを背負ながら決断を迅速に下した政治家の姿に魅力を感じたからだ。
一方、本作のゴジラは怪獣としての獣の恐さが圧巻だった。最初の登場シーンから恐い。だからあのゴジラに立ち向かった勇気は、戦争を知らない世代の私には計ることができないのではないかと思った。
兄を特攻で亡くした亡き父と一緒に見て、そして語りたい作品は、初代とこのゴジラ。
全2054件中、701~720件目を表示