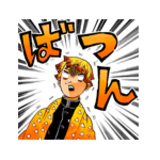ティルのレビュー・感想・評価
全80件中、21~40件目を表示
1955年
沁みる、見てよかった、かな。
見るかかなり迷う。
ネタバレ以外のレビューを見ると、見てよかったとの感想もちらほらと。冬休みに子供がスキ―教室に行ってる間に旦那と鑑賞、見てよかったかな。
映画の概要どおりの内容です。
カメラ好きな撮り方です、景色もキレイ。
古き良きアメリカ。
子供の表情、うちの子供に似ているな~と旦那と意見が一致。
子供はかわいい。
南と北でこんなに違ったんだな~と、初めて知った。
南北戦争なんて興味なかったけど、南と北でこんなに違ったんだな~とか、南北戦争の結果次第ではアメリカも分裂していた可能性もあったのだな~とか、逆の結果で統一されていたら奴隷解放されず今もだった可能性もあったんだな~とか、いろいろ思う。
リンカーンはスゴイね。
あと、カルピス劇場のトムソーヤの冒険を見ていたときの違和感、あれが分かった。お手伝いさんや畑作業の人がみな黒人なんだよ。なんでだろう?って子供心に思ってた。
あそこミシシッピ州だったよね?、ミシシッピ川の近く?。
ラスカルや赤毛のアンにハイジはDVD買ったのだけど、トムソーヤだけは違和感あって好きになれなかった(人種差別を感じさせる作品だったからなんだな)。
真面目な旦那が見終わった後になんども横で言う。
同じ人間なのになんであんなひどいことができるのだろうかと。
返事をすこし考える。
わたし、昆虫キライなんですよ、大がつくほど、同じ生き物なのに許せないんです。
とくに見た目がアウトでカマキリ、バッタ、こおろぎ(ゴキ)など。
蝶やてんとう虫やトンボなどの見た目が可愛い昆虫は触れるし全く平気。
アリさんも平気だな。
ちなみに旦那はゴキも平気な人でね、手でつかめる。
子供もバッタとか平気だな、カマキリは嫌いみたいだけど。
それで。
カマキリやバッタやコオロギと室内で出くわすと、私はもう尋常ではいられない。
殺虫剤をやたらかけたり、
手元に殺虫剤がないときは食器洗剤大量にかけたりしました。虫さんごめんなさい。
もう息絶えてるにとにかく襲ってきそうで恐怖が勝るため、これでもかというほど殺虫剤や食器洗剤をかけまくる。
何もない時は掃除機で吸い取ったり。
それをしているときに逃げられたら部屋にいるのも怖いから目を離せないし、でもそのままでもいられないから目で存在を確認しながら掃除機に手を伸ばして吸い取ります。
今は一人暮らしじゃないし、虫がでるような部屋じゃないから問題ないですが、虫がでる部屋で暮らしていたときはそんなかんじでした。
上記がわたしの旦那への回答です。
「わたしにとってのカマキリやバッタだったのではないかと思う」と返事をしました。
当然のこと旦那は理解できず、何言ってんだ?みたいな顔されました。
「相手に対してひどいことができるということは、自分より低く見ているからで、同じ人間とは認識していないと思う」ということを再度伝えました。
旦那、無言。
人種差別って、人種差別にすら本当はなっていないのではないかなと思う。
たぶん人種って思われていない、だからできちゃうんですよ、たぶん。
少し前に観光先に行くため直行バスに乗りました。
すごく混んでいて座れなかったのですが何故か一か所だけ席が空いていました。
空いていた理由は二人掛けの席に黒人の男性が座っていたからです。
そこまで拒否らなくてもって、なんかガックリしました。
うちの子供、英会話ならっているせいか、外人誰でもOKなんですよ。
喜んで座っていました。
うちの子が座ったら、私に隣に座るかと聞かれたので大丈夫と答えました。
子供に何か話かけてくれとしつこく言われて仕方なく...。
アメリカから来たと言われたので、
アメリカのどこかと聞いたら、なんと!ニューヨークでした、すごい!と子供と盛り上がる。
ニューヨーク行ったことありますか?と日本語で聞かれて、そこからは日本語での会話になりました。ディズニーランドがフロリダにあるとか。
目がとてもキレイな人でした。
バス降りたあとで、子供と話したことは。
世界の中心の町、ニューヨークに住めるということは、彼は教授か社長などのスゴイ人物かもしれない、ニューヨークは家賃が高いから仕事がしっかりしていないと住めない。
人を肩書や見た目で判断すると逆にだまされることもあるんだよ。
どんな場所でも、悪いひとはいるし、良い人もいる。
付き合っていくうちに少しずつ分かっていくことなんだよ、とかね。
今でも、黒人の妊婦さんは産院でスタッフから差別を感じたことがある人が多いそうです。
白人と黒人とでスタッフの対応が違うらしいです。
若い頃に同僚と見た、天使にラブソングをの人がお婆さん役でした。
見た目変わっていたので分からなかった。
ウーピー・ゴールドバーグは、忘れられる前に自分たちが語り継ぐ必要があると、どこかのインタビューで答えていました。
この映画は概要どおりに進むし内容が暗いため集客が見込めないとの意見が多かったそうですが、ウーピー・ゴールドバーグが自分も出るし見てもらえるからとのことで、作成されたそうです。
今もガザとイスラエル、ウクライナとロシアとか、色々あるけど。
現地に行って何かをすることはできないけれど。
目を逸らさないで、遠くからでも声を上げ続けることも大事なことなんじゃないかな、とか改めて思いました。
母親の愛情が映画全体に感じるやさしい映画でもあります。
知らないことは意外と多い
黒人差別の埋もれていた史実のひとつ
1 白人に殺された黒人少年の事件を巡り、差別と闘った母親の記録
2 ティルは、殺された少年の苗字。1955年夏、軍職員で経済力のある母親とシカゴで暮らす少年は、親類のいるミシシッピ州に遊びに行き、白人女性に口笛を吹いた。あってはならないことで、少年は親類の家から白人に拉致され惨殺された。母親は・・・。
3 この映画のリンチ事件が起きた時代では、①人種分離を内容とする州法は合法とされ、ミシシッピ州でも公共施設や私人において制度的な差別が行われていたこと、②黒人の地位の向上を目的とする団体「NAACP」が地道に活動しており、事件後母親を支援したこと、③公民権運動の大衆的な広がりは1955年12月のアラバマ州でのバスボイコット運動を端緒とされており、この事件はその前夜に起きたこと、④政府機関では、トルーマン大統領は軍での人種差別の禁止と軍職員の白人以外の採用を認めており、母親は陸軍職員であった。
4 映画は、史実に基づき、母親を中心に描かれているが、人物造形が良い。夫が戦死し戦後の混乱期を経て白人並みの暮らしをしている。苦労があった反面彼女の支えとなったのは息子の存在であろう。2人の絆が強いことで子を失った深い悲しみが伝わってきた。そして彼女の精神的な強さはここから発揮される。遺体を引き取り、葬儀であるがままの姿や死臭をさらけ出し、新聞に取り上げてもらう。裁判にもかかわる。他方、目の前でティルを拉致された親類が母親と対面したときに見せた表情に、後悔とともに手出ししたくても皆殺しになってしまう恐怖心が見えて底の深さを感じた。
5 映画の最後に、2022年にティルの名を冠した反リンチ法が制定されたことが紹介された。この法律により、人種差別によるリンチはヘイトクライムの一つとしてようやく処罰の対象となった。実に事件から67年後であった。この映画によって埋もれていた黒人差別の史実の一つを知ることができた。
二度殺されることのつらさ
公民権法の前のアメリカの黒人差別のひどさは少し知っているから、この話のなんとなくの流れは想像がつく。事実を元にしている話だし。映画としての盛り上がりみたいなものもあまりない。でも、それでいい。それくらいに衝撃的な事件だった。
とにかく彼が殺されたきっかけがひどい。口笛を吹いただけだから。しかもその日に連れ去られたのかと思っていたが、数日たってからだった。侮辱されたと感じたとしてもそこまで怒りが持続するか?しかも惨殺する?あの執念がすごい。当時のアメリカ南部の怖さを感じた。
遺体が見つかった後にティル親子が受ける仕打ちも相当ひどい。息子は二度殺されたと呟く母親が印象的だ。判決を聞かずにその土地を離れようとする態度も。たしかにあんなの裁判とは呼べない。陪審員が入ってきた時の絶望感はなかなかのものだった。昔の陪審員の構成なんてあんなものだとはいえやはり恣意的なものとしか思えない。
最後のメイミーのスピーチがまたいい。強烈な弾圧や酷い暴力は、強固な闘士を生み出すということだ。また、最後のテロップは、この事件が本当の意味で終わっていないことを意識させるものだった。とても重く受け止めたい。
Till a day win true equality
公民権運動を大きく前進させたエメット・ティル事件の映画化。
ウーピー·ゴールドバーグとヘイリー·ベネットが出てるので観なきゃと思いながらも年を越してしまいました。上映館が非常に少ない。久しぶりに車を出して遠くのシアターに観に行きました。
観てよかったです。
いや、観なきゃいけない映画です。
ウーピーゴールドバーグもヘイリーベネットもすごく太っていました。
ヘイリー·ベネット、第二子妊娠中に撮影?と思いましたよ。
法廷で大嘘こいてイヤな女でした。
旦那だけが話を耳に挟んでやったのかと思ったからです。
1955年を昔と思えない歳なので、ほんとうに驚きました。
映画化に68年かかるなんて。
BLMが起こってからやっとです。
あの指輪がなかったら、完全に身元不明のドザエモンでした。
こういうことは氷山の一角だったことに驚きました。
おばさん夫婦の住むミシシッピー州(南部)にシカゴ(北部)から夏休みにおばあちゃんの助言で行ったボボ君。
店番のお姉さんに女優さんみたいだねって言って、瓶に入ったチューインガムを自分で取り出したときはこちらもヒヤヒヤしました。コラコラ、手づかみはだめでしょう。お姉さんに取ってもらいなさい! でもその後お姉さんの手に触れたりしないようにしないといけないよ。ウィル·スミスが主演男優賞取って、ビンタ事件で一悶着あったテニスの姉妹作品でも父親が子供の時のエピソードでちょっとそんな話がありましたから。
グリーンブックでの差別描写なんかうんと生温いと思ってしまった。
黒人の子供相手の駄菓子屋なのにねぇ。
1955年に戦争未亡人となった母親は空軍で働くただひとりの黒人女性だったということなので、聡明な人だったんでしょうね。旦那さんは朝鮮戦争で亡くなったんでしょうかね。
黒人の労働力で潤った南部が黒人差別が長く残り、南北戦争で南部と戦った北部ではテレビ、ステレオ、冷蔵庫がある暮らしが出来ていた。アメリカってわからない国ですね。たぶん、南北戦争は黒人奴隷制とは本質的に異なるメンツによる戦争だったんでしょうね。
2022年のエメット・ティル·リンチ法制定。リンチはだめに決まってるのにねぇ。驚いて呆れました。
エメット・ティル反リンチ法が成立したのは事件の67年後というのに驚き
この映画で取り扱われている事件が起きたのは1955年。実話です。
事件を映画的な見せ方をしているとは思うものの、
事件の悲惨さは十二分に伝わってきましたし、
当時のミシシッピ州における人種差別の酷さも、まざまざと見せつけられました。
子を亡くした母である、本作の主人公を演じたダニエル・デッドワイラーの
熱演には胸が熱くなりましたし、その後の活動にも不屈の精神を感じ胸を打たれました。
それにしても、この事件が起きてから反リンチ法が成立するまでに67年を要していることが
人種差別問題の根深さを感じますし、
ここ数年で「多様性」が映画でもよく扱われるようになりましたが、
そうそう簡単に解決する問題ではないなと率直に思いました。
なぜ、解決しないのか、、、は、昨年公開の邦画『月』が核心をついていると思います。
人間の本音と建前の自問自答を迫られる作品ですが、
人間の先入観(育った環境や教育も大いに関係していると思います)は、
そう簡単に払拭されるものではないと、あらためて気づかされ、考えさせられました。
本作もそこに思い至った次第です。
「ティル」は殺された子どもの名前では
なく、殺された子とその母親の二人のファミリーネーム(名字)だった。映画を見る前はてっきり、殺された子どもの名前とばっかり思っていたが、見終えてみると母親のティルのこと(「も」)なのかな、と。
昨年見た「ソフト/クワイエット」や「キリング・オブ・ケネス・チェンバレン」に連なる、心がえぐられるような映画だった。ただ、2作に比べて、画面が明るく音楽が陽気なのが救いになった。
翌日、命をかけて証言してくれる黒人の大叔父を恫喝する母親と、その母親に育てられた(素直なよい子ではあったが)あまちゃんの息子は、好きになれなかった。
とはいえ、証言に立って、息子の生まれた頃の話をするシーンには胸がつまった。また「誰かに起きたことは私に起きたこと」(正確ではない)という台詞は、心に刻んでおきたい。
反リンチ法が成立したのが2022年だったという事実にアメリカでの人種差別の根深さを感じた。
大坂なおみさんが全米オープンの7枚のマスクの後、私の知らない名前の書かれたマスクを着けている写真を見たことがあったが「Emmett Till」と書かれていたことに初めて気がついた。
胸が張り裂ける思い
最初から最後まで胸が痛かった
悲劇になるのが分かっていたので、戦争未亡人のメイミーが息子を愛して慈しんでいる描写が続く冒頭からずっと胸が痛かった。息子を惨殺されてからはさらに、その心中が直球で伝わってきて、彼女と一緒に心で慟哭していました。
シカゴでは、デパートでメイミーに失礼な口を聞いた白人の店員に「白人にもそういうの?」と反論できるくらいなのに、南部のミシシッピでは、14歳の子供が店員の女性に「女優さんみたい」と言ってふざけて口笛を吹いただけで惨殺されてしまうような社会。
メイミーは、アメリカ空軍で唯一の黒人女性職員、きちんとした教育を受けた、優秀な人なのだろう。理性的、論理的で思慮深く、だからこそ、息子の死を嘆き悲しむだけでなく犯人たちに報いを受けさせるべく行動ができたし、さらにはアメリカ国家に対して、黒人全体の利益のために戦っていくことができたんだと思う。
北部には、このような黒人女性もいるような状況で、想像を絶する地域格差だ。
裁判が始終胸糞悪い。事件が起きたところを管轄する司法のもとで行われるので裁判官も陪審員も白人(男性)だけで、最初から不平等で理不尽なできレース。メイミーが、「私のボーイは二度殺された」という言葉が刺さる。
エンドロールで示された、発端となったキャロラインは何の罪にも問われず、惨殺の実行犯の夫ともう一人も、エメットを殺害したことを白状しながらも大金を手にしてゆうゆうと人生を送ったとか、後日談ももやもやする。
社会を変えるのは時間がかかる。
過程で犠牲を出し、その屍を乗り越えていくようなものだったりする。
メイミーの戦いはすぐには結果が出なかったが、社会を動かす大きな力になったことは間違いないので、若干の救いにはなった。それを示唆するように、裁判を諦めてミシシッピを出ていくメイミーたちに、街の黒人たちがそれぞれに敬意を表するところは胸熱だった。
主演のダニエル・デッドワイラーが圧巻の演技。
重い内容でしたが、それとは別に50年代のファッションが素敵。
ワンピースやスーツ、それに合わせたアクセサリー、手袋、など、コーディネートも素敵でした。
心に刻みます
この時代の黒人差別をテーマにした映画は、幾度となく観ていて、いつも胸を押し潰されそうになる。
世の中酷いのは黒人差別だけではないが、あってはいけないことが、普通に行われていて何とも心が痛い。
人を人と思わない残酷な仕打ち。
なぜ。なんで。どうして。
でも観なくては。
その時代を生きていない私は、その酷さを知らない私は、様々な映画で心に刻む。
ここで語るのも恐ろしい事件だった。
純粋で明るく、まだあどけない一人息子を、白人からの迫害から守りたくて、あれだけ心配して、そしてくれぐれも注意を払うよう言って聞かせ、それでようやく州外の親戚宅へ送り出した母親。
あんなにも心配になるほど危険な状況とはあんまりではないだろうか。
でもそうだ。何も悪くないのに黒人が差別によって虐げられていた時代。確かにそういう時代はあったのだから。
その心配はまさかの展開へと的中してしまう。母親のメイミーがどんなに辛く、悲しかっただろう。
ティルは純粋に白人の女性を綺麗だと思い、それを口にしただけだった。そしてその思いを口笛で表現しただけだった。
でもそれが、その時代白人にとってはそんなにも許されない行為だったのか?そんなことで銃を持ち出すとはどんな脳をしてるのだろう?子供のした事なのにに黒人だと言うだけで許せず、大人が、そして悲しいことに白人に支配されているとは言え、ティルと同じ黒人までもが加担し、子供をリンチする。死に至るほどに。
肌の色は違えど 同じ人間なのに。
何故そんなことができるのか。
なぜ。なんで。どうして。
酷すぎた。
事件のリンチについては、痛々しい描写はなかったものの、事件の残酷さは十分に伝わって来た。
リンチで殺したうえに、川に捨てるとは。
どうしてそれが、しっかりと罪に問われないのだろう。
そして、当の口笛を吹かれて怒り、銃を持ち出した女性は、裁判では嘘ばかりの証言。馬鹿馬鹿しかったが、そんな事がまかり通ってしまうのだ。裁判すら黒人差別で行なわれるのだから。
だけれども、メイミーは勇敢だった。愛するの息子がされた所業を、変わり果てた姿を世に知らしめることで、確実に理不尽な黒人差別と戦う大きな第1歩を勝ち取ったと言える。
未(イマダ)だに(日本人?)私は白人と黒人の差別は浅はかだった…。
もしかしたら今更の事なのかもしれない…。
実は凄〜く&滅茶苦茶深刻な問題なのに、
日本人と言うか,私自身が未(イマダ)だに黒人と白人の差別問題の重大さを全く理解していない事に気付かされた。
この作品の事件は非常に有名な話のようで、改めて調べ直し,私自身の無知さを思い知らされた。
1955年アフリカ系アメリカ人の少年は親類を訪(タズ)ねた時に,夫と営んでいた食料品店の女性に口笛を吹いた事で、白人女性といちゃついてたと(勝手に真実とは裏腹に)され,その女性の夫と腹違いの兄の2人で暴行の上で殺害された。
その母親は、息子の酷(ヒド)い仕打ちを世間に棺(ヒツギ)の中で顔が見える状態で公表し,人種差別による“リンチ”された事を訴(ウッタ)えた真実の話で熱くなっちゃった!
映画が良い!とかでは無いと思う。
そう云(イ)う黒人と白人の差別に寄る現実問題を,ちゃんと理解しとかんといかん!なんて事を訴えた作品に思えた。
本来,(私は知らな過ぎた)この事は知ってて常識の範囲という事になるんだろうかなぁ〜?!
フラストレーションがたまりっぱなし
終わっていない合衆国の南北問題は、終わらない。
心配性な母親メイミー・ティルの迫真の演技と、
陽気で無邪気な14歳の息子エメットの相関が問題点の落差を予感させながらこの事件の問題の深さを浮き出させている。
つまり南北戦争は、
1861年4月12日から1865年4月9日にかけて、
北部のアメリカ合衆国と合衆国から分離した南部のアメリカ連合国の間で行われた内戦であり、
奴隷制存続を主張するミシシッピ州やフロリダ州など南部11州が合衆国を脱退してアメリカ連合国を結成し、
合衆国にとどまったその他の北部23州との間で戦争となった。
そして「エメット・ティル反リンチ法」と名付けられた事件の結末は、
2022年、
バイデン米大統領は3月29日、人種差別によるリンチを連邦法で憎悪犯罪と定める法案に署名し、成立させた。
被害者の死亡や重傷に至る憎悪犯罪をリンチ罪で起訴することが可能になった。
バイデン氏は「人種的憎悪は過去の問題ではない。現在も続いている」と強調した。
それはそうだ、
合衆国が加担しているウクライナ戦争もイスラエル問題も同じ病巣なのだから。
(^◇^)
ティル
1950年代アメリカで、
アフリカ系アメリカ人による公民権運動を大きく前進させるきっかけとなった
実在の事件「エメット・ティル殺害事件」を劇映画化。
1955年、イリノイ州シカゴ。
夫を戦争で亡くしたメイミー・ティルは、
空軍で唯一の黒人女性職員として働きながら、
14歳の息子エメットと平穏に暮らしていた。
ある日、エメットは初めて生まれ故郷を離れ、
ミシシッピ州マネーの親戚宅を訪れる。
しかし彼は飲食雑貨店で白人女性キャロリンに向けて口笛を吹いたことで白人の怒りを買い、
8月28日、白人集団に拉致されて凄惨なリンチの末に殺されてしまう。
息子の変わり果てた姿と対面したメイミーは、この陰惨な事件を世間に知らしめるべく、
ある大胆な行動を起こす。
「ザ・ハーダー・ゼイ・フォール 報復の荒野」のダニエル・デッドワイラーが主人公メイミーを熱演し、
ゴッサム・インディペンデント映画賞など数々の女優賞を受賞。
名優ウーピー・ゴールドバーグが共演し、製作にも名を連ねる。
( ◠‿◠ )
差別はなくならないからこそ声をあげ続けるべき
黒人差別の告発映画、飽きもせずと言うと極めて詭弁ですが、定期的に差別の実態を暴く作品が商業映画ベースに乗る意味を考えたい。要は差別は現時点においても一向に無くならない、だからこそ訴え続ける必要がある。本作で描かれる事件によってなんと69年も経ってエメット・ティル・リンチ法がやっと成立したことを契機に制作されたのでしょう。当然にシリアスな感動作に納まり、興行的にも批評的にも成功作が多い。だから制作されるわけではないけれど、例えば本作制作のウーピー・ゴールドバーグは過去にも類似作品を提供し続けている。まるで使命であるかのように取り組む姿勢には頭が下がるのみ。
本作は1955年の時点での悲劇を描くが、大きなポイントは同じUSでも北部シカゴと南部ミシシッピーにおける黒人差別の実態の違いにあると言う事。本作の主役であるメイミーはシカゴに住み、キチンとした教育を受け、立派な家を持ち、白人と同等の仕事を持っている知識人である。彼女の14歳の息子を社会勉強とばかりミシシッピーに住む兄弟にしばし預ける事が発端。ここシカゴではデパートで差別的慇懃な対応をされても、それをはね付ける発言が通る環境がある。一方のミシシッピーでは、女性店主をハリウッド女優のようとお世辞を言いちょいと口笛吹いた、ただそれだけでその場で殺される現実だと言う事。
案の定の悲劇に、裁判を中心に描かれるのが南部のどうしようもない差別の実態。ニガーと呼び、白人を侮辱することは死刑も同罪、コットンフィールドの様相は奴隷時代とほとんど変わりない。この悲劇を全米に広める事しかメイミーには手段がなく、その過程が本作の要となる。それにしても裁判での茶番と言うより悪意が公然と行われていたことは驚くべきこと。被害者とされる女性主人に至っては、誰も目撃者がいない事に目を付け、多分弁護士と相談しての、嘘八百証言を裁判所の聖書の前で展開する醜悪。陪審員は全員白人の中年で男ばかり、全く正義なんぞ欠片も存在しない。
女性だと言うシノニエ・ブコウスキー監督はごくオーソドックスに役者の演技に寄り添って描くものの、平板なのは否めず、メイミーの怒りをもっと激しく表現してもよかったのではないか。主人公メイミー役のダニエル・デッドワイラーは、終始威厳を身にまとい怒りを内包し、身なりに気を遣う大人として演じ、圧巻の演技を見せつける。本作最大のヒール役の女主人、何処かで見覚えありますねえ、と思ったら「シラノ」や「ビルベリー・エレジー」そして「スワロー」「ガールズ・オン・ザ・トレイン」での気怠い雰囲気を纏った美人さんヘイリー・ベネットではないですか。
秀逸なのはミシシッピーでの埋葬を拒否、シカゴへ帰還した変わり果てた我が子の姿を安置所で対面するシーン。真横からのショットで、間にちょうど敷居があり惨い体を見えない工夫と見せかけて、ゆっくりと足から上半身の残酷な姿を映し、最後は葬儀の場での遺体の公開シーンで初めて膨れ上がった顔面をスクリーン叩き付ける演出。この醜悪を晒す事こそが本作の目的と言っても過言ではない。
以降の事はラストにテロップにて示されるが、本当に最近になってやっとリンチ法が成立した事実には驚きしかない。差別は虐めと同じで、強者もしくは多数派が、弱者もしくは少数派に対して行う対立軸。この仮想敵を作らないと動けないのが人間の弱さ。米国だけが酷いのではなく、この日本においても差別論者は数多蔓延ってますよね。
【"僕は綺麗な白人女性に口笛を吹いただけなのに。”1955年の夏、アメリカ南部の黒人蔑視の風潮を理解していないシカゴから来た少年の身に起きた事。少年の母の毅然とした態度・行動が沁みる作品。】
■エメットは1955年の夏休みに、ミシシッピ州の叔父の家を一人訪ねる。彼は初めての南部の生活を楽しんでいたが、当時のアメリカ南部で黒人が白人に対してしてはいけない事を何気なくしてしまう。
◆感想
・序盤はエメットが少しお調子者だが、そんな彼を愛する母メイミー(ダニエル・デッドワイラー)の姿が描かれるが、その後の展開がフライヤーなどに記載されているので、憂鬱な気分で鑑賞する。
・エメットがミシシッピ州の叔父夫婦の家に行き、小作人である彼らと共に綿花を収獲するシーンも、エメットが南部の人種差別の事をキチンと理解していない事が伺える。
■エメットは叔父の子供達と、ブライアント食料品店に行き、中を興味深げに見まわしながらレジに立っていたブライアント・キャロライン(ヘイリー・ベネット:素敵な女優さんなのに、役に恵まれないなあ。)の顔を見て、”映画女優さんみたいですね。”と言い自分の財布に入っている白人女優の写真を見せる。
そして、店を去る時にエメットはキャロラインの顔を見て”口笛”を吹いてしまうのである。
ー 当時のアメリカ南部では白人にとって黒人から口笛を吹かれるというのは侮蔑されたと捉えられてしまう行為なのである。
(現代でも、口笛は揶揄の表現と捉えられる事がある。)ー
慌てて逃げる叔父の子供達。何が起こったのか分からないエメットの困惑の表情。
そして、翌晩にキャロラインの夫ブライアントと仲間のマイラムが叔父の家に銃を持って押し入り、エメットを連れ去ってしまうのである。
・行方不明になったエメットの身を案じるメイミー。だが、そこにエメットの訃報が入り彼女は失神する。
■だが、そこからメイミーの息子及び全ての黒人たちの尊厳を取り戻す行動が始まるのである。彼女はNAACP(全米有色人種地位向上協議会)の支援の中、ミシシッピ州に乗り込み変わり果てたエメットの遺骸と対面し、足の先から膝と指でなぞって行き、最後は銃弾を撃ち込まれた頭部にキスをするのである。
更に、メイミーはエメットをミシシッピ州で埋葬する事を拒否し、シカゴに運ばせ正装させて、”敢えて”息子の顔が見えるように棺桶の顔の部分の蓋を開け、弔問者に見せるのである。
ー 物凄い胆力であるし、勇気のいる行動である。今作では、母親の強さをダニエル・デッドワイラーが、見事に演じていると思う。ー
・ミシシッピ州で行われた、”限りなく白い裁判”で、キャロラインが行った嘘の証言を聞いている途中でメイミーは憤然として席を立つ。
そして、大勢の黒人たちの前で言い放った彼女の言葉は、値千金である。
何故ならそれが、公民権運動を推し進めるきっかけになったからである。
<エンドロールでテロップで流れた事実には、猛烈に腹が立つ。ナント数年後にブライアントと仲間のマイラムが雑誌のインタビューに応じ、エメット殺害を認めインタビューの報酬として多額の謝礼を貰い、生涯安穏と暮らしたと流れるテロップである。1955年当時のアメリカの司法制度は、メイミーが言う通り、人種差別に寛容だった瑕疵ある制度であることが良く分かる。
だが、僅かなる救いは、皮肉じみたトーンでテロップで流れる2022年に「エメット・ティル反リンチ法」が成立したことであろうか。事件から60年以上も後に・・。>
全80件中、21~40件目を表示