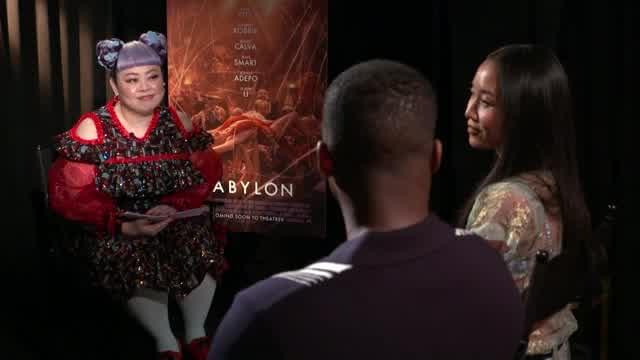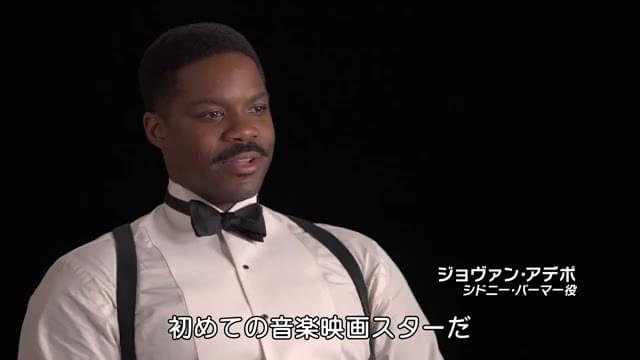「やがて歴史の一部へ」バビロン 因果さんの映画レビュー(感想・評価)
やがて歴史の一部へ
冒頭、丘の上の屋敷で夜な夜な開かれる泥酔とエログロナンセンスの狂宴。「ガルボも来るらしい」の一言で全てが不問になる特権的空間。それは1920年代映画産業のひたすら夢と欲望に満ちた未来への展望を端的に示している。
メキシコ系移民のマニーとホワイト・プアのネリーは共にその宴のパワフルなアトモスフィアに魅せられ、『ラ・ラ・ランド』ばりの運命論的予定調和で映画界に巻き込まれてゆく。サイレント映画界きっての売れっ子作家であるジャックのもとで敏腕プロデューサーとしての仕事ぶりを発揮するマニーと、代役で参加した作品でセックス・シンボルとしての才能を惜しげもなく開花させてゆくネリーの姿が小気味のいいモンタージュで重ねられていくシークエンスには、彼らの全能感が、ひいては20年代映画産業の全能感が滲み出ている。
ただ、それが蜃気楼に過ぎないことを我々は既に知っている。トーキー、恐慌、ヘイズコード、20年代の栄華はそう長くは続かない。あらかじめ衰退の宿命を背負った物語の上で、彼らがいかにして生きていく、あるいは死んでいくのか。そこが本作の眼目だ。
サイレント映画の巨匠・ジャックは1927年公開の『ジャズ・シンガー』が切り開いたトーキーという新潮流の前に挫折を味わう。落ち目の彼に対する評論家のエレノアの言葉は救済であり同時に死刑の宣告でもある。「時代はやがて終わる、あなたは忘れられてゆく、でも100年後にあなたのフィルムを誰かが映写機にかけたなら、あなたはいつでも甦ることができる」。その通りだ。今や倉庫からフィルムを引っ張り出してくる必要すらない。アプリを開き、再生ボタンを押すだけで亡霊たちは鮮やかに踊り出す。
ただ、ジャックはそれに耐えられなかった。彼は通りがかりのホテルマンに100ドルを渡し「これからは君の時代だ」と嘯き、それから自室で命を絶った。
ネリーもまた30年代の腐臭に耐えることができない。サイレントからトーキーへの過渡期においては、作中に示される通り、録音機材に合わせて演者が事細かに動きを合わせる必要がある。豪放磊落でアドリブ主義的なネリーがトーキーに挑むというのはトラを犬小屋で飼うような錯誤に近い。ワンカット撮り終わるだけで大歓声が上がるような現場にやがてプロデューサーは辟易し、彼女は映画スタジオから緩やかに放逐されていく。
一方プロデューサーとして順調に成り上がりつつあったマニーは、彼女をトレンディな(つまり30年代的な)映画女優に生まれ変わらせるべく、彼女を映画人たちの集うパーティーに招待する。冒頭の混沌としたパーティーとは打って変わってスノッブで衒学的な緊張感が漂う会場にネリーはどうにか馴染もうとするが、当然ながら上手くいかない。パーティーの参加者たちがハロルド・ロイドの話題に興じているのは言うまでもなくネリーへの遠回しな嘲笑だ。ロイドはサイレントからトーキーへの転換に失敗した代表的俳優である。結局彼女は我慢し切れず半狂乱で会場をメチャクチャに荒らし、罵詈雑言と吐瀉物を吐きつけ立ち去っていく。
いよいよ女優生命を絶たれたネリーはドラッグとギャンブルに溺れていく。マニーはそんな彼女を最後まで見捨てられず、メキシコへの逃避行を打診する。しかしアメリカン・ニューシネマの純粋な若者たちが「自由」の理想郷としてメキシコを目指しながらもその途中で破滅的な死を迎えたように、純粋なネリーもまたメキシコには決して辿り着けない。彼女は車を降り、闇の中へと静かに消えていく。そして数年後、ハリウッド全体がカトリック由来の禁欲主義的な自主規制要綱(=ヘイズ・コード)に包まれていく中、新聞の三面記事に彼女の死が報じられる。
マニーはジャックやネリーと異なり、サイレントからトーキーへの過渡期を乗り切ってプロデューサーとしての存在感を強めていく。かつて丘の上の屋敷での狂宴の向こう側に夢見た、カオティックでパッショネイトな映画世界はもはやそこにはなかったが、彼はそのことから巧みに目を背けながら淡々と仕事をこなす。しかし彼の20年代への憧憬はネリーへの不変の恋慕として尾を引き続ける。結局彼はネリーがギャンブルでこさえた借金を肩代わりし、ギャングの追走を逃れるべくネリーにメキシコ亡命を打診する。こうして「時代遅れの映画人」の馬脚を現してしまったマニーは、ギャングに「L.Aから出て行け!」と銃を突きつけられ、ジャックやネリー同様にハリウッドを去る。かくして20年代の耀いは完全に消滅する。
数十年後、妻と娘を連れたマニーがハリウッドを訪れる。昔ここで働いていたんだ、とマニーは感慨深く呟くが、娘は「飽きちゃった」と興味さえ示さない。トーキーが飽きられる時代、モノクロが飽きられる時代を経て、映画は遂に「映画それ自体が飽きられる時代」に差しかかりつつある。時は1952年。ジョセフ・マッカーシーが先導し、エリア・カザンがその片棒を担いだ「赤狩り」によってハリウッド自体が疲弊していたこともあり、アメリカ人の週末の娯楽は既に映画からテレビへと少しずつ移行しつつあった。
マニーは失意に暮れながら近所の映画館に入る。そこで彼はハッと目を瞠る。上映作品はジーン・ケリーとスタンリー・ドーネンの『雨に唄えば』。本作が優れたミュージカル映画である一方で優れた「ハリウッド内幕モノ」でもあることは周知の事実だ。そこではマニーやネリーやジャックたちが人生を投じた青春時代が、すなわちサイレントからトーキーへの過渡期のハリウッドの光景が映し出されていた。途絶したかに思えた20年代の耀いは、今まさに鮮やかなテクニカラーに彩られ現前していた。ただし、否定的な意味合いで。カメラは愛憎入り混じった様子でポロポロと涙を流すマニーを離れ、観客の一人一人を、ほどなく全体を俯瞰で映し出す。客席はほとんど埋まっている。
やがてマニーの自省的独白とともに、無数の映画史の断片が矢継ぎ早に明滅する。リュミエール兄弟『ラ・シオタ駅への列車の到着』、ジョルジュ・メリエス『月世界旅行』、カール・テオドア・ドライヤー『裁かるゝジャンヌ』、ルイス・ブニュエル『アンダルシアの犬』、ウィリアム・ワイラー『ベン・ハー』、スタンリー・キューブリック『2001年宇宙の旅』、スティーブン・リズバーガー『トロン』、ジェームズ・キャメロン『ターミネーター2』『アバター』…。映画史の100年が怒涛のモンタージュとなって画面に押し寄せる。
それはジュゼッペ・トルナトーレ『ニュー・シネマ・パラダイス』の再奏と呼ぶにはあまりにも性急で病的だ。そして最後にマニーが言う。「いつまでも長く続くものの一部になりたい」。
この一連のシークエンスには、単なる映画讃美的な射程をゆうに超越したアンビバレンスがある。マニーたちの終ぞ実らなかった夢が遥か未来の映画にくっきりと彫琢されているということ、すなわち「映画史」なるものの強靭な歴史性。一方でたかだか数分のモンタージュによってその全史を語り尽くせてしまうというフラジャイリティー。100年という長さ、あるいは短さ。目の前の映像が自分の人生と繋がっているという興奮。自分が今そこにいないという落胆。映画は夢だ、いや幻想だ。許せない、ありがとう、殺してやる、愛してる。
しかしその愛憎の果てに、我々はやはりこの赤いシートに戻ってきてしまう。呆けた顔で銀幕を見上げてしまう。ウディ・アレン『カイロの紫のバラ』で凄絶に映画から裏切りを受けてもなお懲りずに映画館へやってくるシシリアのように。たぶん、映画にはある種の魔性があるのだと思う。それが何なのかはわからないし、わかるのならもう映画を観る必要はない。
総括すれば、本作は「それでも俺は映画が好きなんだ」というディミアン・チャゼルの捻転した愛情を、コメディとシリアス、過去と現在、愛と憎悪を往還しながら複層的、立体的に浮かび上がらせた歴史映画あるいは内幕モノあるいはメロドラマあるいは映画の映画だ。
『バビロン』というタイトルには、チャゼルの20年代ハリウッドへのノスタルジックな憧憬が滲み出ている。しかし遠い未来、監督も演者も観客も土の下で眠る頃、この作品もまた新たなバビロンとして同様の視線を注がれることになるに違いない。D・W・グリフィスやセシル・B・デミルと同じようにディミアン・チャゼルが名画座にかかる日がきっとやってくる。
いつまでも長く続くものの一部になるのだ。