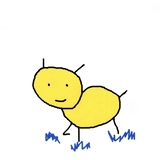TAR ターのレビュー・感想・評価
全259件中、121~140件目を表示
これは傑作だった、そして好きだった、
「幅を広げる哲学」
権力の魔性
週刊文春の映画欄で辛口評者5人中4人が5つ星を付けていたので、気になって観に行ったが、まさかここまで難解な映画だとは思わなかった。ネットのネタバレサイトなどを読み込みようやく理解ができるようになるまで多くの時間を要した。なにしろ不親切な映画なのである。送り付けられてきた本の表紙をターはなぜ破いて捨ててしまったか、ターは足を踏み外して転んだだけで顔にあんな大ケガをするのか、ラストシーンの観客はなぜみんなコスプレをしていたのか、なんの説明もない。また、自殺したクリスタという物語のキーとなる人物はどこに出演していたのか、わからない。観賞後は疑問点ばかりだったが、それを1つ1つ解釈できてくると、実に多層的で奥深い映画ということがわかり、もう一度観てみたいという気持ちになった。
ターはクラシック界では数少ない女性指揮者であり、レズビアンを公表していてパートナーとともに養子縁組の子供を育てている。いわばマイノリティの側に位置している人間であるが、ベルリンフィルの首席指揮者という世界的な権威としてマジョリティの側で権力を行使する立場になっている。結局、マイノリティだろうと、権力の側に立ってしまえば権力に支配されるということがわかる。権力者というのは自分では高尚で倫理的な振る舞いができている人格者だと思い込んでいるが、罪に意識がなく相手を傷つけていることがある。権力の存在に気付かないのは権力者本人なのだ。
こういう権力者の横暴の物語を観ると、同じエンタメの世界で同じ同性愛者ということもあって、日本のジャニーズ事務所性加害問題が想起せずにはいられない。権力の絶頂期にはなにをやっても許されてしまっても、満つれば欠けるのが世の習いであるならば、必ずどこかで(死後であっても)しっぺ返しをくらい、人々に与えた不利益の重い代償を払わなければいけない。しかし、一度でも成功を収めた者は転んでもただでは起きず、後で再生してくることがあるのも世の習いである。
どう観たら良かったのだろう?
完全に観かたを間違えました。
予告編を未見のまま、ポスターに書いてある「狂気」というワードを見て観賞したのですが、言うほど「狂気」さを感じられなくて面白くなかったです。
オーケストラ界の優秀な女性指揮者の転落を描いた話で、最初は「オーケストラの指揮者」はどういう存在か、どのように考えながら指揮を取るか等が興味深いし、その説明を講演会という形で説明していく自然さが良かったと思います。
演じたケイト・ブランシェットも素晴らしかったです。ほぼ一人劇場で長回しで演技していきながらも自然に表現されてました。特に終盤の場面は圧巻です!
ただ、前述した通り「狂気」さを求め過ぎたためかその要素をあまり感じられずに淡々と物語が進んでいくにつれて、次第に退屈に感じていきました。
あと考察が必要な場面も多いですが、いかんせん退屈に感じたためにそこまで引き込まれませんでした。
心が震えた
創作活動の苦しみと哀しみ
指揮者というのは音楽の感動を身振り手振りで大げさに表現するだけの人達で、別に指揮者がいなくとも演奏は成り立つのではないか・・・・等の不埒な誤解を中学生のころは思っていましたが、後で大きな誤りであることがわかり、深く頭を垂れた記憶があります。
自分の持つ音のイメージとの小さな違いを見過ごさず、それを自分のイメージに近づけるために取るコミュニケーション手段は、デジタルでシュミレーションされた合成音などではなく、指揮者の口から発せられる音のイメージを表す形容詞と発声の緩急、そして全身の動き。作曲者のイメージから惹起された指揮者のイメージ。そしてそれがが楽団員のイメージと一致した瞬間に、一つの音が創造され、それが全体の大河となって響きだす。その創作の過程はまさに神がかり的で、その神がかり的な創作の瞬間を、同時に神がかり的なケイトブランシェットが演じきっていて、鳥肌が立ちました。
妥協は許されない世界。でも、それ故にその人格には不可避的に、不要なものは切って棄てる、暴君的な攻撃性を帯びることとなります。そしてその攻撃性はやがて、自分の生きる支えとなっているものとの矛盾を抱えるようになり、そしてそれが・・・・という物語。その矛盾が彼女の人格を徐々にむしばんでゆく光景は、一部タスコフスキーやヒッチコックの作品を連想させる演出で息をのみました。
カラヤンにインスパイヤされた脚本のようですが、カラヤンにはこの映画のような結末はなかったようなので、創作でしょう。でもプライベートジェットを利用するところとか愛車(多分ポルシェ)を乗り回すところなど共通点は多いようで、創作活動のもつ一種破壊的な側面の真実と哀しみがよく抽出されているように思いました。
マーラー、エルガーなどの作品の練習風景、バッハを題材とした講義風景は圧巻で、音も素晴らしく、その音楽と物語が渾然一体となって、身体の芯を射貫かれたような印象で、いくつかのシーンでは涙が出てきました。クラシック音楽好きでなくとも楽しめると思いますが、クラシック音楽好きは多分外せない作品と思いました。そしてできることなら是非劇場で。
頂点って、恐ろしい。
ヒリヒリした焦燥感
ケイト・ブランシェットすごい
最初のインタビューシーンからして、長回しと思うが、よくこんなに台本記憶して切れよく語れるなと驚く。魅力的な主人公。途中から怒涛の展開、最後びっくりの終わり方。割と長時間だったと思うがあっという間に終わった。
張りつめた糸
いやぁ~、見応えあったなぁ。ひじょうに完成度の高い作品だと思いました。
内容的に言って、あまり好きなタイプの映画ではないけれど、これは秀作です。文句をつけようにも、そういうところがほとんど見あたらない。
極限まで引っ張られた、硬く冷たい糸。その、いまにも切れそうな透明の糸をたどって我々鑑賞者は物語の中を進んでいく。
その糸は、細かく震え、ときに大きく、激しく振動し、狂気の音色を奏でる(大むかしに観た、『ほんとうのジャクリーヌ・デュ・プレ』を想起しました)。
凝ったシナリオ、端正な映像、練りに練られたカメラワーク。そして美しく迫力に満ちた音楽……。
ケイト・ブランシェットの演技については、まさに「圧巻」の一言。
「鑑賞する」というよりは、「体験する」と言ったほうがいいような、濃密な2時間半でした。
今もマーラーの5番の冒頭が頭の中で繰りかえし鳴っています。
追記
僕はクラシック音楽もいちおう聴くけれど、「『リディア・ター』という指揮者は記憶にないなぁ。コロナ禍の説明があるから、つい最近まで生きていた人なのかなぁ」、なんて思っていたら、架空の人物だったんですね。まんまとやられました。
知らぬ間に毒が体を廻っている映画
2回観て分かったこと、分からなかったこと
今年の米国アカデミー賞で、作品賞ほか6部門でノミネートされた「TAR/ター」が、満を持して日本公開されましたので観に行って来ました。アカデミー賞では、本命「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」が作品賞や監督賞、主演女優賞などを獲得する結果となり、対抗馬と目された本作は無冠に終わってしまいました。しかし現実社会の諸問題とクラシック音楽業界の諸問題を見事に融合させた本作の出来栄えは、エブエブに負けず劣らず驚嘆すべき仕上がりとなっていました。
ただ、巷間言われているように、実に分かりにくい作品であることもまた事実。普通なら1回観て分からなければそれでお仕舞いなのですが、見落としたことがあるんじゃないか、見落とした部分に実は面白さが埋まっているのではないのかと思い、1週間置いて2回目の鑑賞をしてきた上での感想を述べたいと思います。
まず本作の「分かりにくさ」というのは、第一にジャンルが特定できないということが原因なのではないかと思います。公式パンフレットによれば、「サイコスリラー」とされていますが、この範疇だけに収まる作品では勿論ありません。それではどういう作品なのかと言えば、キャンセル・カルチャーやジェンダー論を扱った点では社会派ドラマであり、映像や音声の不気味さに注目すればホラー映画とも言えるし、権力を握った人物の横暴やそれに振り回される組織を描いた点を観れば政治ドラマでもあり、さらにはクラシック楽団の内輪話を克明に取材している点を観ればお仕事系ドラマであり、またこれが個人的には一番しっくり来るのですが、映画というツールを利用した芸術論でもあるとも言えるのではないかと思えました。こうした多様な要素を含んだ作品であるため、観る者によってはどこに注目していいのか分からず、結果的に理解不能、詰まらない作品だと思ったとしても不思議ではないと感じたところです。
また、英語が分かる人ならまだいいのかも知れませんが、基本的に字幕を追う当方のような観客にとっては、セリフを読むのに忙しくて、肝心の映像が頭に入って来ず、結果良く分からないというドツボに嵌るケースもあるんじゃないかと思えました。現に私も最初に観た時は、字幕を読むのに必死で、かつクラシック用語や作曲家、演奏家の名前がちょくちょく出てくることで、都度都度消化しきれない部分がありました。
何やらネガティブな要素を並べてしまいましたが、1回目の鑑賞後に各種解説を読んだり観たりした結果、前述の通り見落とした部分が多々あるのではないかと思うに至り、それを確かめるために2回目を観に行った次第です。その結果、各種解説の力を借りたことも手伝って、新しい気付きが結構あって、評価は一変しました。
というのも、1回目の時は、主役を演じたケイト・ブランシェットの熱演には大いに拍手を送りたいと思ったものの、彼女が演じたリディア・ターの傍若無人で自己中心的な振る舞いには正直不快感しかなく、全く感情移入できませんでした。ところが周辺知識を得て、さらにはストーリーも一通り頭に入った上で観ると、最終的にリディア・ターが実に魅力的な人物に観えて来るのだから面白いものです。
何故そうした変化が起こったのか?例えば劇中、ジュリアード音楽院での講義のシーンで、父権主義的で20人の子供がいたバッハを全否定する学生とディベートするリディア・ターは、「バッハに20人の子供がいたことと、彼の作品の芸術性に何の関係があるのか?」と言って大作曲家としてのバッハの作品と才能を称えます。この学生とのやり取りがスマートフォンで撮影され、後々リディアが窮地に追い込まれる原因となる訳ですが、芸術家の個人的な所業と作品の芸術性を紐付けていいのかというのは、実に興味深いテーマでした。勿論このやり取りを以ってリディアが良い人であるなどと言うつもりはありませんが、自身の芸術家としての自負をバッハに重ねる自信と、それを裏付ける実績には、一聴に値する論だと言わねばならないでしょう。
昨今過去の言動が掘り起こされてバッシングされるアーティストがいて、一時的に彼らの作品がメディアから忌避されるということがあります。これが「キャンセル・カルチャー」という奴ですが、バッハの個人的な生き方が断罪され、それによって彼の作品群が否定されるなら、現代音楽の根底が崩れる可能性すらある一大事となります。でも現代的なジェンダー論とか人権感覚を以ってバッハを断罪することが優先されるなら、それもまたあり得るということになる訳で、事は非常に複雑と言えるのではないかと思います。
折しも歌舞伎の市川猿之助さんが、週刊誌でゲイであることや、後輩やスタッフに対してセクハラやパワハラを行っていたことが暴露され、ご本人が自殺未遂を図り、ご両親が(恐らくは)自殺されるという事件が起きました。ゲイであることや、後輩やスタッフにセクハラ、パワハラしているというのは、まさにリディア・ターそのものな訳ですが、仮にこの自殺事件が起きなかったとして、明治座での公演はどうなったのか、来月公開される映画「緊急取調室」はどうなるのかなど、リディアの提示する芸術論は、まさに今現在起きている現実の問題であるというところが凄いところでした。
また、スリラー、ホラー的な部分に着目すると、リディアを追い詰めていく首謀者が誰であるかが、最後まで明かされずに映画は終わります。この辺りのモヤモヤ感が、評価を下げる一因にもなり得るようにも思えましたが、鑑賞後に観客に推理する自由を与えてくれたと思えば、逆にありがたいことだとも思えます(ちょっと強引だけど)。また、みんながスマートフォンを持っている現在、リディアほどの有名人ではなくとも、誰しもがネットに動画を晒されるリスクを持っているので、その辺りの怖さを改めて気付かせてくれる作品でもありました。
以上、2回観た感想を長々と書きました。2回観てすら、最後にリディアが舞台上で起こした暴力事件の経緯が理解できないのですが、それは3回目に観る時の課題としたいと思います(3回目がいつかは分からないけど)。いずれにしても、最初に書いたように一つのジャンルに絞れるような作品ではないため、感想も十人十色だと思います。私としては、特に芸術論の部分に興味が行ったのと、あとは何と言ってもケイト・ブランシェットの熱演に脱帽させられました。
そんな訳で、評価は文句なしの★5とします。
もっとクレイジーな
前後半で
ひとり芝居で充分だった。
音の演出が素晴らしい
自分はクラシック音楽に明るくないというのもあるが、指揮者というともっぱら男性というイメージを持っていた。しかし、本作で描かれているように、数は少ないながら女性の指揮者もいるということである。古い伝統と格式が重んじられる世界なので指揮者=男性というイメージを抱きがちだが、確かに今の時代であれば、彼女のような天才的な女性の指揮者が登場しても不思議ではない。
リディア・ターは女性で初めてベルリンフィルの首席指揮者になった才女である。このキャラクターには、男尊女卑的な組織に対するアンチテーゼが込められているように思った。
序盤の公開対談や音大における講義のシーンからも、そのことは伺える。彼女はレズビアンのリベラリストである。そんな彼女がクラシック音楽の世界でトップの座に就いたというのは、強い女性像を象徴しているとも言える。
ただ、こうしたジェンダー論は、物語が進行するにつれて、それほど重要な要素ではなかったということが分かってくる。
結局、この映画は栄光からの転落を描く、よくあるドラマだったのである。
トップに輝いた者が背負う宿命と言えばいいだろうか。嫉妬や恨み、陰謀によって徐々に精神的に追い詰められ惨めに落ちぶれていくという破滅のドラマで、映画の冒頭で期待していたものとは異なる方向へドラマが展開されていったことにやや肩透かしを食らってしまった。主人公を女性にするのであれば、もう少し違ったアプローチの仕方があったのではないだろうか。
もちろん、女性にしたことによって、本作は一つの特色を出すことには成功していると思う。これが男性だったら、更に俗っぽいドラマになっていただろう。そういう意味ではケイト・ブランシェットをキャスティングした意義は大いにあるように思う。しかし、ジェンダー論はこの場合はノイズになるだけで、かえってドラマの芯をぼかしてしまっているような気がした。
そのケイト・ブランシェットの熱演は見事である。彼女を含めた周囲のキャストも全て魅力的で、とりわけ後半から登場するチェロ奏者オルガは一際印象に残った。演じたソフィー・カウアーは本職がチェリストで今回が映画初出演というのを後で知って驚いた。若さと才能に溢れた奔放なキャラクターは短い出番ながら強烈なインパクトを残す。
製作、監督、脚本を務めたトッド・フィールドも円熟味を帯びた演出を披露している。すべてを容易に”ひけらかさない”語り口が緊迫感を上手く醸造し、上映時間2時間半強を間延びすることなく見せ切ったあたりは見事である。寡作ながら改めて氏の演出力の高さが再確認できた。
音の演出も色々と工夫が凝らされていて面白かった。チャイムが鳴る音やメトロノーム、冷蔵庫のコンプレッサー、ドアをノックする音がリディアの不安定な精神状態を上手く表現していた。実際に鳴っているのか?それとも幻聴なのか?彼女の中で判然としないあたりがサイコスリラーのように楽しめた。
怖いと言えば、リディアの強迫観念が生み出した悪夢シーンも不条理ホラーさながらの怖さで、画面に異様な雰囲気を創り出していた。
尚、音の演出で重要だと思ったのはチャイムの音である。リディアは部屋の中でその音を度々耳にするが、どこから鳴っているのか分からずそのままにしてしまう。実はその音はチャイムの音ではなく、隣人が発する救命コールだった。映画を観た人なら分かると思うが、彼女がその音を気にかけていたなら、隣人は”ああいう事態”にはならなかったかもしれない。
このエピソードから分かる通り、彼女は基本的に他者の意見、声には耳を貸さないタイプの人間なのである。この情にほだされない非情さゆえに、彼女は現在の栄光を手に出来たのかもしれない。しかし、同時にそのせいで彼女は恨みや嫉妬を買い自身の立場を危うくしてしまった。このチャイムの音のエピソードは、そんなリディアの人間性を見事に表しているように思う。
全259件中、121~140件目を表示