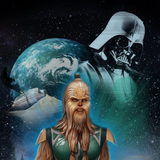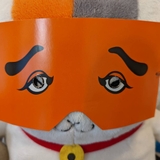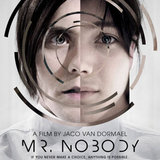ザ・メニューのレビュー・感想・評価
全312件中、121~140件目を表示
帰りに買って食べた
最後まで!!!!!!!!
もっと死をテーマにした理由は欲しかったな
タイトルなし(ネタバレ)
現代のグルメな人達と個性的な発想のレストランを皮肉ったブラックユーモア映画。
客は味もろくにわからない奴がやれ芸術的だのやれ値段だのやれ詳しい解説だのとまさに現代のSNS時代の悪いところを誇張しており、
一方でレストランは客には伝わらないようなセンスと演出で客の1番の欲求である食欲は二の次となっているような状況。
いい皮肉っぷりで好き。
まさに驚愕のフルコース・サスペンス!!
アニヤ見たさに鑑賞。
彼女にはこういう映画がよく似合う。
世界一予約が取れない孤島の高級レストラン。
崇拝される伝説のカリスマシェフ。
参加した客たちの胸糞悪さも相まって料理は美味しそうに見えず。
食のためには金に糸目をつけない自称食通民への皮肉たっぷりの映画。
アニヤが頬張るチーズバーガーとフライドポテトがめっちゃ美味しそうだ!!
日本でいうとおにぎりと漬物かな?
食べる物には健康上気にかけてるけれど、贅沢なグルメ派が苦手なのである意味小気味よかったかも。。。
怖い怖い。
何事もほどほどに。
レビューを見ないで観たほうが良い
究極且つ至高のフルコース、その名は"復讐"... 料理に人生を捧げた人々が仇敵達を"料理"する断罪スリラーコメディー映画
今や引く手あまたでいろんな映画でお見掛けする若手人気女優アニャ・テイラー=ジョイや英国重鎮男優のレイフ・ファインズら豪華キャストが一堂に介した料理を題材とするハリウッド大作。
その味わいは意外にもジャンクフード的というか、気取った上流階級の人たちが彼らにコケにされた人々に不気味な逆襲をされるいわば『世にも奇妙な物語』ないし『ブラック・ミラー』の如きシニカルな見せ場と解り易い教訓に満ちており、登場する癖のあるキャラクターたちが七転八倒する様に驚き楽しむ、万人向けの小気味良いブラックコメディ―に仕上がっています。
何も見目麗しいカッコいい姿を見るだけがキャスト目当てということではなし、主要キャストの中にお好きな方がいればそれぞれがドイヒーな目に遭って四苦八苦する姿を是非とも劇場でご照覧あれ、ということで。
死ぬほど素敵な夜へようこそ
有名シェフのディナーに招待された癖のある客たち。それぞれが個性的に食事をすすめるなか、段々と狂気的なメニューが提供されていく。
繊細な料理を提供するような高級店の客層は様々。味もわからず女性相手のステータスに利用したり、虚栄心を満たす、箔をつける、知識の発散など、一度の食事に千ドル以上払えるような“庶民”ではない者たちが今回は招待される。
コース料理が進むにつれてその内容に文句をつけたりするものの、最終的には料理だと言われれば自身が焼かれることさえ受け入れてしまう。
サスペンスとは謳っているが、メッセージを踏まえるとブラックコメディが近いように感じる。
値段によってよく分からないままに料理の価値を決めることへの皮肉。
結局チーズバーガーが1番美味いよね。
これはゾクゾクした
「ブニュエル」 meets 「エル・ブリ」! これぞ、バーガーとポテトでもむさぼりながら観る映画(笑)。
なんかサスペンスのふりしてるけど、明らかに笑かしにかかってるよね。
こういうときのレイフ・ファインズって、マジ楽しそうで最高。
アメリカで、この手のモンティ・パイソンとかジャン・ピエール・ジュネみたいなテイストのハイセンス・お馬鹿映画が作られるのって、意外と珍しいような。
孤島に集められた12人。
予約のとれない超高級フレンチに招待されたディナー客だ。
そこに一人だけ混じる「招かれざる客」。
まあ誰でも考えることだろうから、別に書いてもいいと思うけど、
冒頭はまごうことなき『そして誰もいなくなった』のパロディでスタートする。
で、どこまでパロってるかは、最後まで観てのお楽しみというわけ。
映画としては、いろいろ真面目に考えだすと理不尽きわまりない内容だが、
●物語の先を読ませない。
●話はひたすらエスカレートする。
この二点だけは徹底して押さえて作られているので、正直観ていて不満はいっさい感じなかった。
映画が終わる頃、右手に置いてあるお茶がぜんぜん減っていないことに気づく。
惹き込まれていた証拠、時間を忘れて没入していた証拠だ。
ジャンルとしては、いちおう「グルメ映画」の系統に属する。
ただ、まっとうな晩餐会映画の極北に名作『バベットの晩餐会』があるとするならば(祇園会館で『八月の鯨』と併映。懐かしい!)、よりミステリー寄りという意味では『シェフ殿、ご用心』や『ディナーラッシュ』に近いし、より頭がおかしいという意味では平山夢明の『DINER』(映画もあるはず)やマルコ・フェレーリの怪作『最後の晩餐』に近いといえるのかもしれない。
何より、(本人たちの望むような)ディナーに「なかなかありつけない」という意味では、ルイス・ブニュエルの『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』を、同じくディナーから「帰りたくても帰れない」という意味では、同じ監督の『皆殺しの天使』を、強く意識した映画であることは間違いない(実際、本作は『皆殺しの天使』から扉の意匠を借りている)。
そもそも、やっていることの一連の不条理性や、ブルジョワジー批判の風刺劇というコンセプト自体、まんまブニュエルなわけだし。ああ、それと今気づいたけど、自慰行為を観ていてほしいとか、親子のふりしてやってほしいとか頼む変態性欲のオヤジってのも、思い切りブニュエルの『昼顔』へのオマージュだよね……。
でも、今まで観たグルメ映画のなかで、何に一番似ているかというと、この映画は『エル・ブリの秘密 世界一予約のとれないレストラン』に、とても似ている。
てか、料理をひとめ見りゃわかるけど、これ、まんま『エル・ブリ(エル・ブジ)』ですから。
入江に面する立地も。超予約困難店という設定も。
要するに、これって『エル・ブリ』にたかっていたブルジョワジーの食通(フーディ)と、伝説のシェフ、フェラン・アドリアみたいになりたい自意識過剰のコンセプト系創作フレンチのシェフどもを、徹底的に小馬鹿にして、愚弄して、貶めるために作られた、じつに志の低い映画なんだよね(笑)。
『エル・ブリ』は、約50席しかないシートに世界中から年間200万件もの予約希望が殺到し、「世界一予約が取れないレストラン」と呼ばれていた、スペインに実在した伝説のレストランである。
「実在した」というのは、2011年に閉店したからで、それでもフェラン・アドリアの遺伝子は、そこで学んだ多数の弟子たち(常時60人以上のシェフが働いていた)によって、全世界に広まっている。
映画に出てくる「人工イクラ(アルギン酸カプセル)」などを用いた「分子ガストロノミー」は、まさに『エル・ブリ』の代名詞といっていい手法だ。和の素材(本作だと梅干し)の利用も、『エル・ブリ』の十八番だった。厨房見学がコース料理の一部を成していたという『エル・ブリ』の特色も、映画ではそのまま援用されている。
製作陣がどれくらい『エル・ブリ』を元ネタにしているかというと、観たらだれでも「似ている」ことはわかるのに、その名が「パンフに一カ所しか出てこないこと」にも表れている。
パクリ方がヒドすぎて、もはや、おいそれと名前を出せないくらいなのだ。
『ザ・メニュー』では、『エル・ブリ』のような、コンセプト重視のフレンチを志向するシェフ(およびその弟子たち)と、それを称揚してやまない特権階級のフーディ(食通)が、まとめて徹底的に小馬鹿にされている。
そのやり口は、高尚なブルジョワジー批判というよりは、ある意味子供がやるような品性下劣な貶めようであり、「こんな連中ムカつくからみんなまとめて●●ばいいのに」を地で行く、「貧乏人のやっかみ」を全力で充足させる、じつに底意地の悪いものだ。
みんな観ていて不思議に思うだろう。
この映画で、なぜ客たちは連帯して戦わないのか。
それは、彼らが「ブルジョワジー」だからだ。
『皆殺しの天使』と一緒で、彼らはそもそも先験的に「ここから出られない」存在なのだ。
あるいは、見習いシェフたちが、なんでスローヴェクに唯々諾々と従っているのか、不思議に思う観客もいるだろう。
それは、本作がバカな小金持ちをぶった切る返す刀で、料理業界のオーナーシェフと見習いたちの示す異様な「カルト性」(=「グル」と「信者」の関係性)をもぶった切ることを、「そもそもの目的」とした映画だからだ。
要するに、客側も料理人側も、「なんでこんなことになってるのか観客には皆目理解できない」イロジカルさにこそ、作り手の本当の意図がこめられているということだ。
こんな悪意に満ちた映画を撮りながら、「レストラン業界を槍玉に挙げるのは実は綱渡りの連続で、本当に慎重に物事を進めていきました。料理に携わる人々への敬意と、芸術性に対するリスペクトは忘れないように心がけたのです」とか、しゃあしゃあとインタビューで答えている監督のマーク・マイロッドは、まあまあ筋金入りのろくでなしだと思う(誉め言葉)。
実際に彼は、サンフランシスコの3つ星レストランの有名シェフ、ドミニク・クレンに料理監修を依頼することで、ある意味での「正統性」と「リスペクト」を本当に実現しているわけだが、逆に言えば、ドミニク・クレンにここまで協力させておいてこの映画の内容ってのは、マジで性格が悪いと僕は思う。
この監督さん、テレビ畑の人らしいけど、これまで撮ってたのが『ゲーム・オブ・スローンズ』と『メディア王~華麗なる一族』らしい。
つまり彼は、テレビでも徹底してブルジョワジー批判を主題にしながら、それを「真剣に描き出す」ことで題材に対するリスペクトも忘れないという芸風で、延々と風刺劇を作ってきた監督なのだ。やはり筋金入りである。
出演陣は総じて、素晴らしかった。
『ムカデ人間』のハイター博士のように、頭のおかしな理屈を並べながら、熱く料理を語りつづけるスローヴィク役のレイフ・ファインズは、まさにあて書きのようなはまり役。
対するヒロイン、アニャ・テイラー=ジョイ(『クイーンズ・ギャンビッド』の人)は、生身の人間なのに、キャメロンの『アバター』みたいに見える超個性的な美貌が、インパクト&説得力十分だ。
あと、東洋系の得体の知れない給仕長エルサを演じるホン・チャウが、凄い存在感を発揮していた(今日び、ハリウッド映画でステロタイプの「ミステリアス・チャイニーズ」が出てくるのはむしろ珍しいから、ちょっとドキドキした)。
で、観終わって、思った。
これは、むしろ場末の映画館で、バーガーとポテトでもがつがつ喰いながら観てるような貧乏なアメリカ人こそが、いちばん溜飲を下げながら楽しめる映画なんだな、と。
終演23時半。
僕は残念なことに食べながらの鑑賞はしなかったので、
かわりに映画館を出たその脚で、歌舞伎町のど真ん中にある「ショーグンバーガー」へと向かったのだった……。
まあ、2500円もする和牛100%の食べログ百名店にわざわざ選んで行ってる時点で、むしろスローヴェクからすれば僕も「あちら側の人間」に入っちゃうんだろうけど(笑)。
身につまされる、、
ニューヨークから車で1時間程行った所に、
その周辺一帯が敷地で、
向かう途中からレストラン体験になるという店があると聞いた記憶を思い出しました。
そこがモデル?
私も美味しい物を食べる為、世界あちこちに出掛けていますが、確かにああいったレストランに皮肉満載なのは、一理あるかも、、
そこに行く事だけがステイタスで、お皿の内容覚えてない人居るかもなあ。
逆に気持ち悪い程、レストランに傾倒してオタクな人。
私はどっちでもないけど、パンの無いパン皿の風刺はね、確かに。
SAWの様にそこに囚われる理由が明確では無く、
何処にでも居そうなお金持ち達が犠牲になるのが、
途中迄のお皿は、いかにも有りそうな料理で
劇場型のレストランや分子ガストロノミーの店を思い出して、
なんかイロイロ突きつけれた気もしました。
アーニャのとても個性的な美型はとても素敵
PIGも合わせて観て欲しい
全312件中、121~140件目を表示