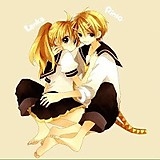CLOSE クロースのレビュー・感想・評価
全141件中、1~20件目を表示
誰にでもある意図的に友達を避けた少年の日々が甦る
ルーカス・ドン監督が前作『Girl ガール』に続いて放った作品は、やはり他者との違いに悩み、苦しむ少年たちの葛藤を描いているが、本作の方がより幅広い共感を得るかも知れない。なぜなら、子供の頃、大好きな友達がいたとする。でも、その友達との関係を周囲から奇異な目で見られ、それが嫌で関係を絶ってしまった、なんて経験は誰にでもあるはずだから。
主人公のレオはいつも一緒にいる、暮らしていると言ってもいい親友のレミとの関係を、クラスの女子から『カップルなの?』と聞かれたことが妙に恥ずかしくて、レミとの距離を置き始める。仲間外れになることを恐れて、新しい友達と仲良くし、それまでやってなかったアイスホッケーにもトライしてみる。そして、いつものようにレミの家に泊まっても、同じマットレスで寝ることがなくなった。何となく、あくまで何となくやったことが、果たして、どんな悲劇を引き起こすのか!?
子供だからとは言えない、残酷な仕打ちがもたらす予期せぬ出来事の顛末を描く映画は、やがて、少年らしい結末をレオに与える。その清々しさは半端ないのだが、注目すべきは子供たちを見守る大人たちの眼差しだ。生きていくこの世界には色々が出来事があって、色々な人々が重なり合って成り立っている。そこもまた、本作の視野の広さを象徴している。
末長く愛され、観る者の心を揺さぶり続けるであろう一作
少年たちの純真な思いに深く寄り添った傑作だ。舞台はベルギー郊外の自然に包まれた地域。いつも何の躊躇いもなく仲睦まじく戯れる13歳のレオとレミだったが、ある日、その様子をクラスメイトから揶揄されたことでレオの感情には戸惑いが生まれ、つい何となくレミを遠ざけてしまい・・・。ここからの展開に関してはできれば情報を入れずに臨んでほしいところ。何が起こるかは明かさないが、これはある意味、少年が自分の中の本心と切実に向き合おうとする物語であり、その心情を思うといまだに涙がこみ上げてくるほどだ。ドラマを彩る青々とした木々が胸に滲み入るように美しく、農園で収穫される花々の色味は、時として残酷に思えるほど鮮烈。その狭間を駆け抜けていく少年たちの表情と躍動が素晴らしく、脇で支える大人たちの演技にも心酔させられる。このルーカス・ドン監督による長編2作目は、今後、末長く愛され、観る者の心を揺さぶり続けるであろう。
叙情的な美しい映像で子供の純粋さと残酷さを描く心に響く作品
久々に心を打たれるような思いで映画を見ました。とてもよかったです。見終わった後しばらく深く物思いにふけりたくなります。誰もが持っている純粋さと残酷さが子供の頃はオブラートに包まれず出てしまいます。この少年2人は特別に強くつながっていたので反動が大きく出てしまいました。2人は2人で一つとも言えるくらい存在を互いに依存していました。1人にとっては自分自身が半分欠けてしまったような喪失感を抱いたに違いありません。そしてことが起きます。ことが起きてからすぐには心に馴染みませんが徐々に1人がいなくなったことがレオの心に沁みてきて喪失感と罪意識が増していきます。果たしてレオはどうなるのか、このあたりから頼むから希望を持たせてほしいと願いながらハラハラして見ていましたがレミの母親が最後にレオを抱きしめることでレオもレミの母親も私も救ってくれました。セリフも多くはなくそれぞれの心象風景を役者の演技と叙情的な美しい映像で表現していきます。最後はとても心地の良い余韻に包まれました。ガス・ヴァン・サントの映画にも似た子供の純粋さと親心にちゃんと向き合った誰かに勧めたい作品でした。
青春の1ページでは到底済まされないほどに重い
ジャケットの雰囲気からはちょっとした流行り系かとあまり食指が動かなかったが、第95回アカデミー賞国際長編映画賞ノミネート作品ということで鑑賞。
観てみると意外にもというべきか、思春期直前の少年の友情がテーマともいえるストーリー。掘り下げればもっと秘めた想いもきっとあるのだとも思うが、男性であれば誰もが一度は感じたことがある苦いような酸っぱいような想いが、きれいな映像と音楽に乗って深いところで絡みあう。そしてまさかの悲劇と深い苦悩。当然そこには切ない青春の1ページでは到底済まされないほどの重さと影がある。
本作はテーマも独特だが、映像もかなり独特。手振れ!? 画素が粗い!? それでいてとてつもなくクリアな映像がストーリーをさらに深いところまで導く。この撮り方が取り返しのつかない悲しみを深めるのか和らげるのか判別がつかないが、いずれにしても心の奥底まで染み入ってくる。
ストーリー良し映像良しでとても完成度の高い作品だとは思うのだが、このある意味でタブーともいえるリアルさの渦には、個人的にはお腹いっぱいになってしまい消化しきれなかったのが正直なところかな。
クロースフレンド 仲良し 親友
美少年の親友ふたりを主人公にしてこのテーマは切なすぎた。
死 という最終手段をもって 残された少年の葛藤と切なさを繊細に描く
言葉がみつからないな..
ラスト
振り向いた少年は そこに何を見たんだろう 見つけたんだろう 見つけるんだろう
再生が描かれない悲劇映画
いじめですらない
行けばいい、慣れた家でしょ
序盤は綺麗な風景に似つかわしい仲良しコンビの所作に、目を細める思いで眺めてられた。
学校に通いだしてから、表現し難い緊張感に少し息苦しさを覚え、中盤以降は更に上まるヒリつく空気感と喪失感で、情緒乱されるかんかく……。
誰にでも有る事だと思うし、誰を責めるべきでもない、どうしようもないやるせなさがズシリとのしかかる…。
しばらく引きずりそうな寂寥感をうえつけられた。
嫌な作品ではない、かといって面白い作品でもない、良作ではある。
なんて切ない・・・
これ、観てる辛かった。
いつも一緒に居る仲の良い男の子二人が、
ある日、学校で「付き合ってるの?」と、からかわれる。
その日を境に二人の間がギクシャクし始める
俺にもこういう経験あるのです
いつも二人で行動してた友人がいて、
正にこうやってからかわれて、ぎくしゃくしてしまった
映画ではこの結果、とても辛い事が起こってしまうのだが
その後の演出がとても上手い!
何気ない日常が淡々と続いていくんだけど、
時折見せる悲しみにくれる姿の痛々しいこと!
最後まで自責の念に苦しんでるまま終わってしまう残酷さ!
あるシーンがある映画のラスト・シーンに酷似していた
その映画とは是枝裕和監督作品「怪物」
絶対に是枝裕和はこの映画を観て、あのシーンを撮ったと思う!
自然の良さ
特別なセットや人物はいない。
みんなどこにでも居るようなキャラクター、関係性。
説明的なセリフも一切なく、会話のテンポも役者に任せてる感じがして良い。言葉はいらないというかのようにレオ役の表情をフル活用してる。涙の流し方が上手すぎました、、。
人間関係がテーマだと思うが、自然を含ませた映像、これが何よりもいい。
花の中を駆けるシーン。花の美しさは色褪せない。
レオが竹林の中で手にした棒。バットとか攻撃性の高いものでないのは彼に敵意がないからであろう。
行く宛てのない感情が表出した結果を表すのに相応しいと思った。
このか細い体に背負わせるにはあまりにも重過ぎる
映画としてはとても良かった。
会話の中の感情の流れをゆっくり丁寧に見せてくれて、
感情移入出来るように作られていたと思うのだけど、
その分レオの背負ったものが重過ぎてとてもしんどい
映画だった。
もちろん自分にこんな経験はないのだけど、
一番大切なものが分かってるはずなのに、
上手く立ち回れず、一つの言葉で傷つき過敏に反応し
友だちを遠ざけてしまう事なんか誰にでもある事だと
思う。
そして、その友情を誰かで埋めようとするけど
全然埋める事が出来ず大切さに気付くことなんてよくある
話で、だけどレオは気付いた時には独りぼっち。
何をしても、忘れようとガムシャラに動いても
もう後戻りは出来ないこの切なさが
最後まで続き、映画が終わってもラストのレオの顔を
思い出し生きてる限りこれを背負っていくのかと思うと
辛くて仕方なかった。
ただ映画自体は辛くて暗く描くのではなくて、
優しい色彩とどこか温かくレオを見守るような
目線で描かれており美しい映画だなと思いました。
これぞ映画の妙
あいまいなものを抱える勇気
心の棘
幼馴染のレオとレミは家族ぐるみの付き合いで、まるで兄弟のように仲が良く何をするのもいつも一緒だった。二人にとってそれは当たり前のことの様に思われた。中学に入学した二人のそんな姿を見た同級生からカップルなのかと聞かれ、からかわれるまでは。
この年頃の子供は何かと繊細で、また人生経験も浅いことから周囲の目がやたらと気になる。自分が女の子みたいだとからかわれたレオ、たわいもない子供の意地悪でもそれを深刻に受け止めてしまう。
そのせいでレミと距離を置くようになり、他の同級生たちとつるむようになったレオの変化についていけずさみしさを募らせるレミ。いつも二人一緒が当たり前だった、それなのにレオは自分を置いて行った。ショックを抑えきれないレミはレオと激しい喧嘩をしてしまう。
それからしばらくして遠足の日にレミの姿はなかった。何かせわしなく連絡を取り合う教師たちの姿を見て不安を募らせるレオ。学校には保護者達が迎えに来ているという。レオの不安は現実のものとなった。
それは誰のせいでもない不幸な出来事だった。でもレオはその事実をなかなか受け入れられない。どんなにホッケーの練習に没頭しようとも心から離れない。それはまるで心に刺さった棘のようにレオの心に居座り続け彼に痛みを与えた。
練習中に腕を骨折して治療を受けるレオは思わず泣き出してしまう。父は骨折したんだから痛くて当然だと慰める。でも痛いのは腕じゃない、心が痛いんだ。
レオは生涯この罪悪感を背負って生きていくのだろう。たとえレミの母親が許してくれても、けして誰のせいでもない不幸な出来事だったと言われても彼は自分を許せないだろう。
心に刺さった棘が年月を経て風化し、尖った先端が丸みを帯びてきて痛みが和らいでいってもそれは彼の心に居座り続け、何かのきっかけで不意に思い出される。そして棘はやがては粉々の塵となり彼の記憶の中に散らばり小さく見えなくなってもかすかな記憶として居続けるだろう、幼き頃の親友への思いとして。
未熟さゆえに何気ない言動で相手を傷つけてしまった、誰もが有するであろうそんな幼き頃の苦い記憶を思い出させてくれるノスタルジックな作品。少年期の繊細な心の揺れ動きを見事に描いた。
「コット 始まりの夏」に引き続きこちらも演技経験の少ない新人俳優による素晴らしい作品だった。光の演出も素晴らしく、花畑を疾走する二人の少年の姿が美しかった。本作も劇場鑑賞を逃したことが悔やまれた。
負の感情が連鎖しない
13歳のレオとレミは大親友で、しょっちゅうレオはレミの家に
泊まりにいくほど、家族ぐるみでの仲の良さなのだが、
この二人の仲の良さを学校でからかわれて、
レオがいじめ的な扱いを受けるようになり、
レオは自身を守るために、レミにそっけない態度をとるようになる・・。
レオとレミに「二人はつきあっているの?」と問う早熟の女子や、
いかにも子どもっぽくからかう男子がリアルで、
そこから脱却するために、
レオが行動を変えていくという心理は誰もが理解できるはず。
(こういうことが大人社会でも起きていないかハッとさせられた)
中盤、レオには耐え難いショックな出来事が起きるが、
それでも淡々と日常を過ごしていく姿はどこか痛々しくもあり、
やはり時折見せる後悔の念と、そこに背中を押されたラスト近くの
シーンは猛烈に感動できる。
そして劇場内はすすり泣きの大合唱となった。
特に本作における大人の子どもへの包容力は目を見張るものがあり、
負の感情の連鎖にならないところが本当に素晴らしいと思った。
舞台となっているベルギーの花畑が素晴らしく美しく、
また、映画における画質/画面の色味も素晴らしい。
第75回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で見事グランプリを
受賞した本作。
確かな傑作であることは間違いない。
全141件中、1~20件目を表示