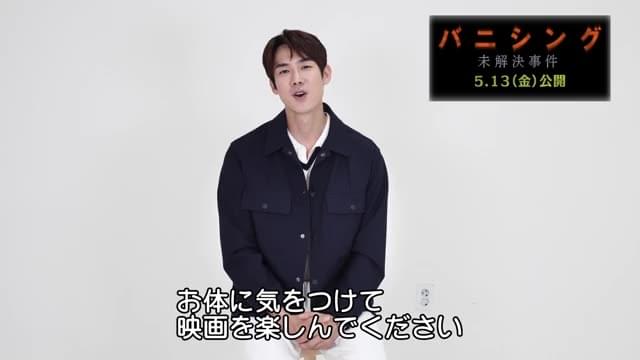「臓器売買の闇ビジネスを題材に、英中仏韓のフィルターを通して完成した社会派サスペンス」バニシング 未解決事件 高森 郁哉さんの映画レビュー(感想・評価)
臓器売買の闇ビジネスを題材に、英中仏韓のフィルターを通して完成した社会派サスペンス
映画の成立過程がかなりのレアケースで面白い。原作小説は、スコットランド出身の作家ピーター・メイによる“チャイナ・スリラーズ”シリーズの第3作「The Killing Room」(2001年)。同シリーズは北京の刑事と米国人女性の法医学者が協力して難事件を解決するというもので、作者は毎年のように中国に取材旅行をして警察や社会の状況を小説に活かしたという。原作が執筆、発表された頃は、中国が「一人っ子政策」を推進していた時期でもあり、二人目の子を妊娠した女性が堕胎せざるを得ない状況がストーリーに反映されたようだ。
「The Killing Room」の映画化は、フランスと韓国の共同製作、フランス人監督の体制で進められることになった。脚色の段階で、原作通り中国を舞台にするのは検閲の問題もあり断念して韓国の首都ソウルに置き換え、主人公もソウルの刑事ジノ(ユ・ヨンソク)とフランス人の法医学者アリス(オルガ・キュリレンコ)に変更された。ジノとアリスが出会ってからいい雰囲気になるまでが早すぎるように感じたが、シリーズ第3作である原作(2人は1作目から関係を築いている)の影響と考えれば納得がいく。
臓器や胎盤を摘出する対象として、中国から出稼ぎに来ている若い女性ばかりが狙われるというプロットも、原作の名残だろう。ただ、正規の国際的な臓器移植ネットワークのシステムをハッキングしたり、出稼ぎの中国人女性を家政婦として派遣する業者がいたりと、相当大がかりな闇組織が動いていそうな割には、実際に稼働しているメンバーが5人ぐらいしか登場しないなど、予算不足の印象も受ける。
とはいえ、細かい点を気にしなければ、興味深い題材を描く社会派サスペンスとしてそれなりに楽しめるだろう。