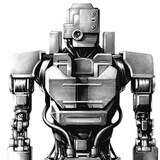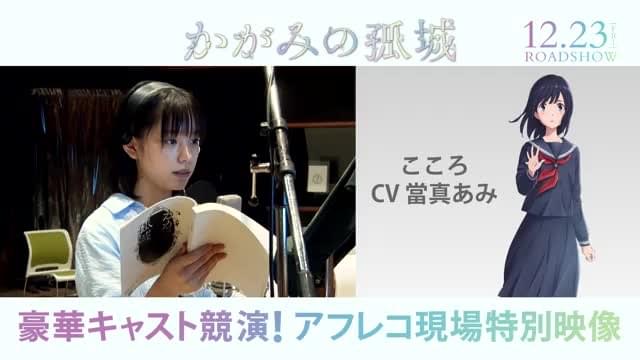かがみの孤城のレビュー・感想・評価
全454件中、301~320件目を表示
最後に全員の姿を見たかったけどムリか
パラレルワールドではなく、時代が
ずれているのと、
オオカミ様が姉ちゃんは予測出来たけど、
キタジマ先生があの人は分からなかった。
初めてもう一度観たいと感じた映画
あけましておめでとうございます。
他作品のレビューはかなり辛口ですが、この映画だけは忖度や依怙贔屓なく素晴らしい作品です。
主人公のこころが真田という陰湿な女子のいじめを苦に不登校になってしまい家族にも理解されず苦しんでいるのが前半です。
ある日こころが不思議な鏡に引き込まれ、同じ中学生7人に出会い登場人物たちがお互いにそれぞれ良い方向に変わっていくのが見ていてとても楽しい。
一人ひとりのキャラクターもとても見ていて、好きになれます。
終盤でファンタジー要素もありますが見ていて苦にならないちょうど良い加減になってますし明かされなかった登場人物たちの抱えている苦しみもわかってきます。
私自身も学生時代や社会人生活で何度も人間関係の壁にぶち当たりましたがその経験があるからこそ、観ていて共感や理解ができる作品であるとも感じれます。
もう一度見たい
イジメがリアルっぽい
原作小説は未読です
本作は7人の子どもたちが
城に集められて、願いを叶えるために鍵を探すことを
オオカミ様から告げられる
7人集められるが基本的に
こころ、アキ、リオンが3人が中心となるように感じる
他の4人もそれぞれエピソードがあるのかもしれないが
ラストで少し明かされる感じで終わる
こころに対するイジメ描写はかなりリアルな感じがし
キツイものがあり
アキが襲われる部分もかなりキツイものがあるので
観るときにそこらへんは注意したほうがいいかもしれない
家に大人数で押しかけるのは現実にあったらヤバいな
願いを叶えるために鍵を探すのは
序盤はあまり進展がなく
共同生活的なものが中心をしている感じになる
そこから、こころがどのように学校に行けなくなったとか
ほかの子どもたちもいっていないということが明かされる
ラストで集められた子どもたちは
それぞれ違う年代から集められたと明かされる
アキは未来には喜多嶋先生になると明かされる
後半になるとイジメの首謀者だった女子が
まったくでなくなり、イジメが結局どうなったのかわからないが
「イジメっ子と和解をする」ということがない部分がリアルなのかもしれない
ラストの展開が伏線を回収するというのはよかったが
ちょっと駆け足っぽいと思った
こころが友達の家に行って、絵画を見て
鍵のありかがわかるというところは
ちょっと説明が省略してる感じがあったな
17時をすぎるとオオカミに食べられるというのは
最初に説明をされていたが
オオカミというのはどういうものなのかわからない中で
そのシーンが出てきたからあっさりしていたなとは思った
不登校の理由とか、学校の先生がイジメ問題にうまく対応できなかったりするところとかは
リアルだなとは思った
最後にこころとリオンが会うシーンで
イジメっ子が男子をこころにけしかける可能性を思い出さないかと思ったが
孤城で成長したので大丈夫だと解釈をした
鑑賞動機:劇場予告3割、辻村深月原作3割、評判2割、ついで2割
原作未読。どうしても観たいわけではなかったけど、観てもいいかなくらいの軽い気持ちで観た。…! 2022最後の劇場鑑賞で当たり引いた! やったよ、姉ちゃん!
事前知識は劇場予告程度だったのがよかった。これは完全にやられた。一旦VARによる審議が行われたが、この特殊状況下であり理由もありセーフの判断。そして全貌が明らかになってみると、思った以上に複雑な構造をしていて、かつ、そうであることが、「わかってくれる人がいる」ということに繋がり、物語の核心と密接に関連していて、そこにまた心動かされた。あ、ネタバレしてる? ポチッと。
隣を歩いてくれる人がきっといるというメッセージは、毎日を闘っている人たちへの力強いエールであり、未来を照らす希望の灯でもあり、繋がっていくタスキになって次の誰かが一歩踏み出すための力になる。
『ハケンアニメ!』と同じく、内容に興収が見合ってない、全くもってけしからん状況下にある映画である。きちんとした仕事はきちんと評価されるべきである。
ところでそのメタセリフ、松竹さん的にはオッケーなんすか?
原作ありものの、正しい映画化の典型例
珍しく原作既読。
なので文庫でも八百ページ近い長編を
二時間の尺に納めるには、
相応の整理が必要だろうとの気がかり。
とは言え、物語を構成する三つの大きな謎(伏線ではない)、
孤城に集められた七人に纏わる謎
鍵の在りかに纏わる謎
「オオカミさま」に纏わる謎
に関わる部分は省略が効かず、
ではそれ以外をどう工夫するかが見もの。
もっとも原作を閲読中には、
物語の主線となる一番目の謎の見当は
上巻の中ほど前に判ってしまい(「喜多嶋先生」についても)、
既に読んでいる人間にそのことを話したら
「つまんね~やつだなぁ~(「チコちゃん」風)。
もっと物語の世界観に没入できんのかい!」となじられた経験。
おっと、閑話休題。
ため、最初の謎については、巧い処理ができるのでは、とも
思っていたら案の定。
文書を読んで頭の中で想像するのと、
視覚情報として直接入って来るのでは雲泥の差。
ヒントの見せ方も巧みで、遥かに真相に辿り着き易くなっている。
二番目の謎についても同様。
読者であれば作者がぶら下げた「レッドヘリング」にがぶりと齧り付き、
それを離せず最後まで懊悩するも、
絵面で見せられればやはり理解は進もうというもの。
三番目の謎については、手掛かりの出し方が上手い。
他の人の背景は最後の最後まで殆ど語られないにもかかわらず、
肝心のエピソードについては詳細に触れられ、
全体的に、鑑賞者層を想定した、相当に丁寧な造り。
映画化にあたりばさっと省略されていたのは、
主人公のそれを除いて、個々人の背景。
それでも、最後のシークエンスで急いた様に提示し、
それなりの理解をさせてしまうのは、作り手の手練も間違いないが
原作の緻密な構想が奏功したとも言えるだろう。
先に挙げた諸点は当然のこととして、
それ以外の面に於いても、映像の力を再認識。
とりわけ、七人が孤城を去る場面は、
本を読んだ時には取り立てての感慨を持たなかったのに、
本編では思わず熱い想いが込み上げて来る。
多くの鑑賞者が、同じ感情を持ったのではないだろうか。
監督の『原恵一』は
〔嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲(2001年)〕や
〔嵐を呼ぶ アッパレ!戦国大合戦(2002年)〕の評価が高いけれど、
個人的には『森絵都』の原作を映画化した〔カラフル(2010年)〕の方がツボ。
奇しくもこちらも原作既読。
案内人が存在し、
且つ「再生」の物語りとの共通点があるのは不思議。
原作未読ですが面白かったです
見る前は謎解きやSFチックなゲームをするのかと思っていたのですが違いました。
真面目な内容で集められた子供達が鏡の中での交流を通して悩みを解決する過程がよく描かれていたと思います。
同時期に上映されているアニメ映画のすずめの戸締まりと比較するとあちらはエンタメに寄っていてあまり真面目に考えずに楽しむ、こちらは現代の子供の悩みについて考えさせられる映画でした。
話の構成もよく出来ていてどんでん返しが多くありました。比較的分かりやすいので賛否はあると思いますがこうなんじゃないか?と展開を予想しながら見るのも面白いと思います。
悪い所をあげるとするとまずは特典内容ですね。見る前からここで星半分マイナスです。3種類ランダムというのはどうなんでしょうか。私は一回しか見ませんが別の時期に3つとか選べるようにしないと特典が欲しくて複数回見る人が可哀想です。
予算が有名アニメ映画と比べると少ないのかチープに見えてしまう部分もありましたが仕方ないと思います。あんまり面白くなかったのですずめの戸締まりにつぎ込む予算を少し回して欲しい。
あとはこんなことに気づかないのか?という内容にツッコミを入れたくなる所もあったのでツッコミどころが許せない人にはおすすめ出来ません。
純粋に人を想う貴重な作品
近年のオシャレでキラキラ作画を魅せるアニメとは違う。本当に観る人の人生のために作られている映画作品。
ファンタジーミステリーを通して、今の生きづらさの先には、数々の可能性があるのだと人を励ます作品。既存の学校に居場所を無くした中学生が主人公ですが、登場人物も多いですし、とりまく大人模様もあり、大人でも自分ごととして力をもらえる。
原監督が職業監督に徹したとコメントしているように、原作の辻村さんの「あの時の10代の私に届けたい物語」を2時間で伝えることに徹したのだと思った。
かつての自分にかけてやりたい言葉、それはそれだけで同じような誰かを救う可能性がある強いメッセージだと思います。
謎解きも分かりやすいかもしれないし、オシャレな表現はない。かなり地味な前半がゆっくり進む。
でもだからこそ、2時間でこころちゃんの心の機微が明確に立ち上がっている。
そしてラストで彼女は一気に突き進む、その爽快感がすごいです。
真面目な話です
急にリオンくんの家族にフォーカスするのがうーーん
ひとことReview!
イジメなどで生きるのが辛くなった子供達への応援歌か。悩みは一人で抱えるのではなく、他人に打ち明けて、共に悩み、打開していく。それが大事だと言う事を教えてくれる。
SFやファンタジーの諸要素を見事に融合させつつ、紛れもなく優れたジュブナイル作品として完成した一作
2018年の本屋大賞を受賞した辻村深月の原作を、未読のまま鑑賞した観客による感想です。
原作未読の上、ほとんど予告すら見ていなかったので、どんな物語なのか全く未知だったのですが、それがむしろ奏功して、上映中は登場人物達の目線で、この物語に様々に張り巡らされた謎を体感することができました。
上映が始まった直後は、確かに美しくて味のある映像だけど、表情や動きが乏しくて、何だか地味な作品…、と感じていました。しかし程なくして、彼らの境遇が徐々に明らかになってくると、この静かな描写も物語の一部なのだということが理解できました。
鏡を通じて別の世界の城に入り込むという設定や中学生の彼らの言動や悩み、そしてやがて明らかになる孤城の世界の謎など、作中には様々な要素が張り巡らされています。実際のところそれら一つひとつは既存の小説や映画で見たことがあるようなものが多く、真新しさを感じる場面はそれほど多くありませんでした。何なら、本作と同時期に公開している大ヒットアニメ映画と被る要素も。しかし本作は、そのような、既におなじみとなった(場合によっては陳腐と思えるような)要素を巧みに組み合わせて、見事な世界観を構築した上に、物語としても比類のないものに高めているところが素晴らしいです。優れた原作があるとはいえ、原監督はアニメの超絶技巧だけでなく、物語の作り手としても一級の作家であることを証明しました。
なお、本作が好きな方には、映画ではなくゲームなんだけど、「題名にとある数字の入った、本作とほぼ同じ年代の少年少女達が主人公の作品」を是非おすすめしたいところです(本作の内容にかかわるため、あえて題名は伏せるけど)。
キャラデに騙された(>。<)。
主人公が幼く見えたから観るのを悩んでいたのだが、観に行って正解でした(>。<)。ファンタジー観過ぎて、途中で展開や人間関係読めちゃったけど、それでも面白かったし・・・泣けるねえ(ToT)。
こういうキャラデだと、大人にはハードル高いから、そこで損してるかも(´ω`)。ただし、予告編にこの主人公の声を多用したのは正解。大人・・・特に年寄り(私)には、この島本須美タイプの清楚な声に弱いのだ(^m^ )。で・・・
めっちゃ個人的な意見なのですが
この主人公演じてる声優さんで
いつか・・・ぜひ・・・
『ナウシカ』の続編
作ってほしいな(*゚∀゚*)。こういう声質・・・イメージピッタリだと思うけどなあ(o゚∀゚o)。まだちと下手くそだけど、この子の今後に期待する(^O^)。
てか、もっと公開時期ズラせば良かったのに・・・と思ってしまう( ̄▽ ̄;)。『すずめの戸締まり』『スラムダンク』『アバター2』『Dr.コトー』などと同時期(ノД`)。なんなら『ワンピース』にも、話題はほぼ持って行かれてる(>。<)。それでもそこそこな興行収入上げてるから、良かったのかな?。
これは辻村深月がスゴイとしか
題材はありふれてるの。
原作がポプラ社から出てるし、少年少女向きの話だと思うのね。
ふつうに描かれたら、かつての少年少女は物語に入り込めない。でも、きちんと、引きずり込んでくれる手腕の高さ。
みんなが現実世界で会えないのはなんでなのか、どういう関係性なのかは、そんなに複雑な設定じゃないんだけど、明らかになるところの面白さはあって、ラストで現実世界での関連を描いて納得させる。
手練の技だね。すごいよ辻村深月。声優も豪華で良かったよ。
うーん
間違いなく良作
原作未履修で行きましたが全く問題ありませんでした。
まずとにかくわかりやすいです。
少し複雑なストーリーですが、伏線から結末までめちゃくちゃ分かりやすく仕上げられてます。
小さい子供から大人まで楽しめる難易度です。
本格的な隠し要素、ミステリ等を扱う作品を普段から観ている人にとってはわかり易すぎる、もどかしいと感じるかもしれませんが、扱ってるテーマを考えると全ての年齢かつライトな層まで皆が楽しめるこれで大正解だと思います。
観る人の気持ちに寄り添った素敵な作品です。
ストーリー
びっくりするくらい良いです。
そりゃ本屋大賞取るわって感じ。
今作いじめを扱う描写があるのですが、教師やいじめっ子の解像度の高さといったら、ちょっと辛くなるくらいです。(トラウマになるレベルではありません、安心してください。)
だからこそお子さんが居る方はぜひ一緒に見に行って欲しいです。
今後何かあった時、思い出すような作品になると思います。
全454件中、301~320件目を表示