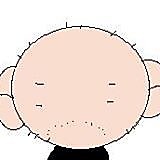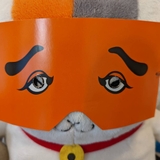プレデター ザ・プレイのレビュー・感想・評価
全77件中、41~60件目を表示
特典映像のコマンチ語吹替版で鑑賞するのがベスト。旧作へのリスペクトに溢れた画期的なフォーマットのプリクェル
1987年公開のシリーズ第1作『プレデター』から35年後に舞台を18世紀まで巻き戻すという大胆な発想のプリクェル。コマンチ族の武器は手斧や弓矢というプリミティブなものなので、プレデターとどんな戦いを見せるのかに注目していましたが物語はそんな単純なものではなくアメリカ開拓史にも踏み込んだかなり泥臭いウェスタン。『カウボーイ&エイリアン』にもちょっと似た感触がありますが、こちらはコマンチ族の物語なのでプレデター以外にも敵はいて凄惨な殺し合いがこれでもかと繰り広げられます。
他のシリーズ作を一つも見ていなくても全然楽しめる作りにはなっていますが、要所要所にシリーズに対する目配せが散りばめられているのが楽しいです。名セリフも絶妙なタイミングで再現されているのでシリーズファンも大満足。アンバー・ミッドサンダーの迫真の演技がとにかく素晴らしく、治癒師としての知識も駆使して愛犬サリイとともに未知の敵と闘うヒロイン、ナルのカッと見開いた瞳は1作目の主人公ダッチ少佐と同等の勇猛さに満ちていました。
本来ならばスクリーンで観るべき作品ですが、本作Disney+での配信オンリーなのは残念。オリジナルは英語版ですが特典映像としてコマンチ語吹替版があるのでそちらで観るとより臨場感が感じられます。ただし、そちらには英語字幕しか付かないので多言語の字幕に慣れていない人にはちょっとハードルが高いかも知れません。
しかし残念なのは邦題。原題が“Prey”という“Predator”と全く逆の単語であることに意味があるのに台無しになっています。
まさかのラビットハンターVSプレデター
原題は『インディアンVSプレデター』B級映画
って感じの内容です。
とにかく酷い。
理由①主人公シリーズ中最弱
兄がインディアン狩人(部族長)である妹が主人公。
狩人に憧れるが鹿も狩れない、中ボスには手も足も出ない。やっと狩れたのはウサギだけ。
そんな描写が冒頭から30〜40分続きます。
時代背景的にもありえない(女性狩人が)。
理由②プレデターもシリーズ中最弱?
好敵手を求める戦士。のはずですが、
シリーズ中最もテクノロジーが追いついていない時代の連中に
これまでと変わらぬ超ハイテク装備で圧倒します。
裸一貫で戦う事なく終わります。
理由③得体が知れてしまっているが故のマンネリ?
シリーズ通してプレデターの圧倒的な強さからホラー映画のような恐怖心も煽られる映画でしたが、迫り来る恐怖心への煽りがむちゃくちゃ弱い。
理由④死亡フラグ通りに進行
相手がプレデター故仕方ないのですが、
「あ、多分こいつ死ぬな。」を超える人間がいません。
兄なんて特に。出て来た瞬間からフラグ立ちまくってます。
総じて
最弱VS最弱
プレデター2を見た時、
ハリガンに渡った銃の持ち主に
相当な期待と壮絶な戦いを思い描いたと思いますが
イメージしていた人物とは程遠い結果でした。
やっぱり大きなスクリーンで。
高評価にだまされた。
好き嫌いは分かれそうだけど
ディズニープラスで視聴。
最強の“狩猟民族”プレデターvs地球人の闘いを描くシリーズ第5弾にして、他作品の前日譚となる作品。
狩猟民族のネイティブアメリカンとプレデターの取り合わせは、これまでありそうでなかった組み合わせで新鮮だった。
主人公の女性ナルは戦士を目指すが、しかし他の戦士(男)には差別されていて――という内容に、「また、ポリコレかよ」とうんざりする人もいるかもだけど、他の男戦士より力が劣る分を観察と頭脳と知識で最強生物のプレデターに対抗するという内容は、シリーズ本来のコンセプトにも沿っていると思ったし、個人的には楽しく観られた。
むしろ、300年も前のネイティブアメリカンの世界観なのに、あまりにも現代の価値観過ぎる(男たちがナルに対して甘すぎる)印象だったかな。
まぁ、その辺をリアルに描きすぎると観客が引いちゃうからってのも分かるけど。
プレデターのデザインもネイティブアメリカンに寄せている感じがカッコよかったし、1時間40分という長さも程よく、気楽に観られるのもいい。
あと、ワンコが可愛かった。
セリフの言語の選び方が意外と深い話
まずは総合評価として★3.5を与えたい。
その理由として、「映像美」「美術のこだわり」「CG(視覚効果)」の3点を挙げる。
より具体的には、ロケーション、ヘアメイク、衣装、大道具・小道具(セット)、そしてカメラによる撮影が良かった。
舞台として1700年代初頭のアメリカの未開拓領域、主人公としてネイティブ・アメリカン(コマンチ族)を選び、素朴で野性味のあるサバイバルを演出した。
美術へのこだわりにより、被写体にごまかしがなく、観賞に耐えうる映像作りを成し遂げた。
アメリカ建国(1776年)以前の入植時代を背景として、スペイン人が登場したのもよい。
さらにクマとの戦闘シーンもある本作は、『レヴェナント:蘇りし者』(2015,アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ監督)を想起させる。
アカデミー賞3部門を獲得したこの名作と比較してしまうと、ところどころ拙速さが気になるものの、100分という短尺のなかで素朴さ、自然との交わり、野生味(そして若干のゴア表現)を終始一貫して描くことができているのではないだろうか。
「拙速」な部分をより丁寧に描き、部分的に肉付けを行えば、素晴らしい作品に仕上がるのではないだろうか。
音楽に関しては凡庸で、むしろデジタルに、電子音楽を使用するなどの挑戦を行ってもいい。
またプレデターの目的も謎で、「闘争」(抗争)の匂いを嗅ぎつけて現れるというシリーズの約束から外れる。
その点を補完するように今作では「食物連鎖の頂点争い」が描かれる。
タイトルにある「プレイ」とは、"prey"のことで、猛禽類、あるいは猛禽類の獲物を意味するが、要は「狩るものが狩られる側に立つこと」を意味する。
コマンチ族は狩る側でもあり、強力な野生動物に狩られることもある側でもある。
そこにスペイン人入植者たちが登場し、頂点捕食者の座を獲得するかと思いきや、プレデター、そして主人公によって壊滅させられる。(このようにプレデターは「敵」ではあるが「悪」ではなく、シリーズを通じてしばしば悪役を消してくれるヒーローでもある。これが誇り高い戦闘部族に対するリスペクトである)
主人公たちは動物を狩る人間であるが、スペイン人の登場により狩られる側になる。しかしそのスペイン人もプレデターと主人公によって倒され、主人公とプレデターとの頂上決戦となる。
このような、狩るものが狩られる側に転ずるという闘争の全体が"prey"という単語に集約されている。
作中しばしば、この食物連鎖を象徴するシーンが、野生動物を通じて描かれる。
ところで前述の「拙速」さとは、例えば巨大なクマとの遭遇が、安易に戦闘に発展してしまうところ、などだ。野生動物は、生き物を見ればなんでも襲い、殺してしまうような生き物だろうか。
本作では「食物連鎖」(あるいは頂点捕食者)を描く都合上、生き物同士が遭遇すると常に「上下関係」(優劣、大小関係)を決定しようとしてしまう。
実際の自然界において、生き物同士の遭遇は必ずしも殺し合いには発展しないだろう。空腹であるとか、育児中であるとかの理由で動物が凶暴になることは知られているが、常にそうだというわけではない。
『ジュラシック・ワールド』(2015)や『ジュラシック・ワールド/炎の王国』(2018) が、第1作『ジュラシック・パーク』(1993)に比べて圧倒的に劣る理由は、人間の敵という側面だけを持つ恐竜を登場させてしまい、「畏怖」の対象(尊敬と恐怖両方の対象)である恐竜の姿を損なわせてしまった点にある。第1作における恐竜は、恐怖の対象でもあり、動物に対する愛情の対象でもあった。
これと同じことが本作においても言える。動物は、ただただ凶暴な側面だけがピックアップされている。
こう言った点をクリアすること、つまり安易な戦闘に発展させないことや、野生動物たちの持つ様々な表情を満遍なく描きつつも主人公との生存競争に発展する様を丁寧に描写することによって、本作は真に「自然に溶け込んだ」作品になれると言えるのではないだろうか。
・・・・・
主人公をコマンチとして描くにあたり、スペイン人の登場、その下劣さ、彼らの全滅は、おそらく白人によるネイティブ・アメリカン迫害の歴史を省みての白人なりの「へり下り」であり、この映画もまたポリコレの側面を持つ。
主人公は女性であり、性別役割分業に抗う姿が描かれる。
個人的な疑問であるが、わざわざ性別役割分業だとか、男性を「女性に対して決めつけを行う悪者」として描かずに、単に活躍する女性像を描くことはできないのだろうか。
ハリウッドにはすでに『エイリアン』(1979)だとか『ターミネーター2』(1991)のように、男性との比較・差異の描写を介することなく、純粋に活躍(アクション)する女性像を描いた事例が存在する。
『プレデター』シリーズにおいても、『エイリアンVSプレデター』(2004)は、女性主人公がプレデターと協力して活躍する作品であった。
(エイリアンは男性器のメタファーであり、宇宙船という閉鎖空間は膣を象徴する存在で、さらにはエイリアンによる"妊娠"を描いた作品であるという視点もあるが)『エイリアン』シリーズに対して、「主人公を男性にしろ」と文句をつける人は存在しないし、主人公が活躍さえしていれば、それが男性だろうと女性だろうと観客はあまり気にしないものである。(というのが個人的な意見だが、どうだろうか)
・・・・・
さて、「映像美」「美術」「視覚効果」において優れる本作であるが、前述の通りところどころ拙速である。
「映像」「美術」「視覚効果」における丁寧さが、末端まで及ばなかったのではないだろうか。
脚本、編集、アクションなどにおいては不足が見られる。(Disney+作品に対してそこまで指摘してはいけないだろうか...)
食傷気味な『プレデター』(ついでに言えば『エイリアン』)シリーズであるが、素朴な舞台設定により原点回帰がもたらされたのではないだろうか。
肉付けによって膨らませれば「化ける」可能性もあるので、この路線で進んで欲しい。
ちなみに以前『エイリアンVSプレデター』の小説版(竹書房)を読んだことがあるが、そこでは現代よりも前、プレデターが何度も地球を訪れ人間と接触する様子が描かれていた。
・・・・・
本作でスペイン人が登場する理由は、主人公たちコマンチ族が住んでいたのがアメリカ南西部だからだ。
18世紀初頭、アメリカ南西部を統治していたのはスペイン人である。メキシコがスペイン語圏であるのもその名残だ。
重要なのは白人が登場することだ。白人が登場してネイティブアメリカンを侵略した歴史を描ければよい。
コマンチ族がアメリカ南西部に住んでいたことや、18世紀初頭の統治者がスペイン人であったことを知らない視聴者も多い。そのため実際の遭遇確率はスペイン人が高かったとしても、白人に英語を話させるという選択肢もある。
だが本作では、より正確な史実に基づき、スペイン語を話すことにしたようである。
それならば主人公達も正確な歴史考証に基づき、全編を通じてコマンチの言語を話せばよいのではないか?という指摘も考えられる。
『アポカリプト』(2006年, メル・ギブソン監督)という映画では、マヤ人を描く物語で、実際に全編をマヤ語で撮影してしまった(!)
本作、主人公はコマンチの言語も英語も両方話すが、英語をどこかで習得したのか、それとも(映画によくあるように)「本当はコマンチ語を話しているがセリフが英語なだけ」なのかは不明である。
スペイン人の通訳と主人公が会話するさいの会話は英語で行われるが、2人が話しているのが「本当に英語」なのか、それともコマンチの言語なのかが不明だ。
スペイン人がどこかでコマンチ語を習得したのも謎だから、英語を覚えているほうが自然だが、ヨーロッパ人と接触していない(であろう)主人公がどこかで英語を習得しているのも不思議だ。
だが劇中で、西洋人とはどこかで交流する必要がある。
というのも主人公がスペイン人から銃の使用法を学ぶシーンがあるし、『プレデター2』のラストシーンで登場した銃を西洋人から受けとらせたいからだ。(これが本作の製作者の狙いだ)
単に銃を盗むような展開でもいい。そうなれば言語を介在する必要がないからだ。しかしそうするとなぜ銃だけ盗むのか?という疑問が生じる。他の色々な物に混ざって銃も盗んだことにしてもいいが、銃をよりピックアップするため、やはり本来の目的通り武器として、主人公に使用させたい。
だが考証に正確でいようとすると、当時の銃の使い方は複雑であるため、主人公に銃の使い方を学ばせる必要がある。するとどうしても言語による会話が必要となる。
そのような思考過程を経た結果、「英語のセリフだが、本当はコマンチ語を話しているのだろう」という観客の認識につけ込み、スペイン人通訳との会話を英語で行わせることを思いついたのだろう。
絶妙なやり方であり、映画でよくあることを逆手に取ったやり方だが、上記のように「いま2人が話している英語は、本当に英語なのか?それともコマンチ語なのか?」という疑問を抱くまでは有効である。
リアリズムと演劇性がうまく融合した形だ。(この点は芸術の域だと思う)
・・・
つまり、「『プレデター2』に登場した銃が本作で主人公の手に渡る」というラストへ向かうため、逆算的に「銃をスペイン人から受け取ること」「銃を使用してプレデターに抗戦すること」「銃の使用法を覚えるために言語が必要であること」「主人公はコマンチ語しか話せないがスペイン人(通訳)は英語も話せること」から「主人公はコマンチ語と英語のセリフを織り交ぜて会話する」という解決策に至ったのだろう。
序盤から、ラストに向けての伏線が張られていたことになる。
観客は主人公が英語を話しても、「映画によくあるように、英語を話しているけど本当はコマンチ語なんだろう」と解釈してくれる。
主人公のセリフは全て英語にせずコマンチ語を織り交ぜたのはスパイス的演出であり、多少の考証的配慮でもある。(また、英語で会話するほうが主人公が観客の支持を得られやすいという利点もある)
スペイン人がスペイン語を話すという点に関しては英語以外の言語を話させることで異文化との接触をアピールした結果として考証的正確性に従うことになったが、主人公が英語を主軸としてコマンチ語を織り交ぜるという言う点では作品の見やすさと演出を重視したようである。(やはり話す言語が分からないというのは異文化との接触をアピールしやすい。つまりアメリカ人がスペイン語をわからないということである)
製作国がアメリカではかった場合、あるいは映画の舞台がアメリカでなかった場合、また違ったやり方になったのではないだろうか?
「プレデター ザ・プレイ」プレデタークラスタでは無いので、今作が原...
特に「プレデター」ファンではなくコマンチ族の女の子がヒロインという設定にひかれて観たが、それなりには楽しませてもらった。
①コロナに感染し自宅監禁で配信しか観れず、最初に選んだのがこれ。その前に『LOVE DEATH + ROBOTS』というNETFLIXのTVシリーズを観たけど。各エピソードの出来はまちまちだったが、最後の「彼女の声(LIBARO)」が一番良かった。②というのは置いといて、プレデターというキャラには全く興味がなく今回相手がコマンチ族で女の子ということオンリーでチョイス。1作目(しか観てないけど)は、“「ある集団がある場所で正体不明の敵に襲われて、その敵の正体を暴いていくという謎解きとその敵を何とか倒すというカタルシスを味わわせる映画」が数限りなくある中で、その敵が周期的に地球に狩りにくる透明になれる不細工な異星人であった”、と目先を変えたところに面白さはあったが所詮一回きりのアイデアだと思っていた。③先ず狩る方が透明になる、って狡いと思いません?普通は狩られる方が何とか助かる為に透明になるというか背景に隠れるものなのに(自然界では大体そう)。食物にするとか自分の生存に関わる為の狩りなら透明になるのも百歩譲って仕方ないとしても、単に狩るために透明になってコッソリ獲物に近づくなんてセコいわ。しかも透明になるのもそうだけど他にも色んな武器装備をして技術的に劣る者(人間)を狩るのも姑息だし。しかも、そういう奴らを誇り高い戦士みたいに扱うのは矛盾していません?キツネ狩り(馬に乗り銃や弓を持った人間が無防備なウサギを狩る)の逆発想で、狩られる方を人間にして、その恐怖とサバイバルのスリル、返り討ちにするというカタルシスを味わわせるという主旨は分かるし、1作目はその面白さを巧く伝えていたが、同じ設定を続けるのならば余程サプライジングなアイデアかプロットにしないと。④そこで今回は誇り高き狩人(という設定の)異星人と、自分の土地を知りつくしている誇り高きコマンチ族の戦士(である女の子)とが知勇を尽くして戦う筋書きだと期待したが、南米のジャングルが北米の森(+平原)に、狩られる方が現代の兵士から300年前のネィティヴ・アメリカンと新大陸の侵略者である白人に変わっただけで、結局同じことの繰り返し。異星間移動出来て300年後の地球でも未だ作れない武器装備が出来るくらいなら、この惑星の住人の戦力(と自分たちの戦力との違い)が分かっているだろうに、それでも狩ろうとするのは殆ど苛めかサドかと思ってしまう。まあ、この時代(18世紀初頭)から間もなく白人がコマンチ族をはじめネィティヴ・アメリカンに行う仕打ちに比べたら未だかわいい方だけど。⑤最後はコマンチ族の少女が勝つに決まっているから、さて、どんな風に倒すのだろう(途中彼女が底無し沼にはまるシーンで「ここ使うんだろうなぁ」とは予想出来た)というのが楽しみである訳だがよくわからないうちに終わってしまった(年取って私の目が着いていけなかったからかもしれないけど)。ともかく、狩る方の驕りが足を掬ったか、最後に勝つのは武器や装備ではなく何れだけ知恵が回るのか、ということなのだろうけど、勇敢な戦士同士が死力を尽くして闘い劣性の筈の方が最後に何とか勝ち抜いたというカタルシスがなく肩透かし。⑥しかし、透明になったり重装備しないと狩れないということは、プレデターって丸裸にすると実は弱っちいのかと疑念を抱くね。⑦まあ、女の子の健気な大活躍と最後まで飽きさせなかったのでそこそこの点にしましたが、また観たいとは思わないね。
女ではなく戦士として認められたいがゆえに挑む"試練の狩り"... 絶対的な力を持つ捕食者に知略で立ち向かうケレン味溢れるバトルアクションが炸裂!!
これまでの『プレデター』シリーズはその時点での現代かもしくは未来が舞台でしたが、本作は18世紀初頭の狩猟部族とプレデターとの闘いがテーマ。
男は狩りで食料を捕り、女は衣・住を担う男尊女卑のコマンチ族のコミュニティーの中で誰よりも自尊心の強い少女が周囲に認められようと女だてらに"試練の狩り"に挑み、正体不明の怪物に仲間を蹂躙される極限状況の中でそのサバイバル能力を開花させていくアクションスリラー。
序盤、自らを戦士として認めてもらうためのライオンをターゲットとした"試練の狩り"に赴きますが、女だからと軽んじられつつも、優秀な戦士である兄のタアベの推挙、そして既に認められている薬学と獣の行動学の知識を活用してその機会を得るところがコマンチ族内での自己プロデュースの描写としてなかなか上手いところです。
で、本来の獲物が"何者か"に先んじて殺害されたことで一行が異変に気付くわけですが、普段から"戦闘"を常としている狩猟民族ゆえにステルス迷彩や重火器といった明らかなオーバーテクノロジーを持つ"敵"を認識しての臨戦態勢を執るその姿は他作品でのプレデターに接敵する現代人よりも明らかにスムーズであり、現実の戦闘が"武装の進化=戦闘力の向上"という単純な比例構造ではないことを言外に語っている演出が圧巻です。
ともあれ、やはり基本的なスペックに歴然たる差が有るがゆえに一人また一人とコマンチ族の戦士たちなのですが、ただ為す術無くやられるだけでなく味方の敗北から戦術を見出していく姿はまさに戦闘民族であり、それは主人公も例外ではなく、仲間の死に戦慄しながらも一方では極めて冷静にプレデターの弱視による視認範囲やサーモグラフでのサーチによる死角、レーザーアローのマスクとの連動法則を看破していきます。
最終的に次回作や一作目への繋がりのような引きらしい引きは無しで・・・・・・まぁ、それはそれで潔くて良かったように思います。もしかするとその後、狩られたプレデターの復讐にその仲間が大挙して現れたのかもしれませんが。
あらためて振り返ってみるとそこまで過去作へのオマージュだったり系譜だったりを感じないというか、それもそのはずで当初から極力プレデターシリーズの一篇としてのプロモーションをしていなかったということで、あくまで一作品としての存立と面白さを追求した仕上がりになっています。
そのため、過去のプレデターシリーズ一切未見の方も楽しめるはずで、時系列的にも一番過去ですし、サバイバルアクションが好きな人には持って来いな作品だと思います。
こまけぇこたぁいいんだよ!!←細かくない件
なんでこんなクソ寒い、闘争も少ない土地にプレデターが来るのか?
プレデターに真に認められるべき戦士は兄貴じゃね?タイマンで互角に渡り合ってたやん
あとプレデターの最期バカすぎるだろ、前もマスクが手元にないのに勝手に作動して兄貴に当たらない矢打ちまくってたのにラストでも同じポカやって自殺とかコントかよ
無誘導なら真っ直ぐ飛ぶだけなんだろうけど誘導状態か無誘導状態か確認してから打てよ
妹が使ってた体温を下げる秘薬、プレデターの目眩しになる温度が何度か知らんが低体温症になるしそもそもあんな俊敏に動けなくなるわ。設定バカすぎ。あと1715のマスケット銃、妹なんであれだけ持って帰ったの?他にも戦利品はあったのにプレデターの首とマスケット銃だけ、プレデター2と矛盾しない?
ラスト酋長の兄貴が死んだ情報は村に入ってなくて妹もまだまだ兄の死を語ってないのになんでいきなり酋長就任した?プレデターがライオンより強いとか誰も知らんだろ、なんか変な生首持って来ただけやん。エンドロールでプレデターが大挙して襲って来るトコで終わったけどプレデターそんな事しないから。遺体の回収と妹へのプレゼントならまだ分かるけど明らかに艦隊で来たやん。
コレ主題は妹は「知恵が高く狩りの知識もあるけど大物を獲った事は1度もない、女は獲物を獲れないと舐められてるから見返したい」「初の大物はなんとプレデター」ま、時代が作った映画なんだろうけどこの高得点はないわ、プレデター1を100としたら30くらいの映画
大自然のなかでの闘いに緊張
物語の舞台は、300年前のアメリカ。初めて地球を訪れたプレデターと、インディアン部族との戦いが描かれます。
アーノルド・シュワルツェネッガー主演の第1作目に近い緊張感が全体的に漂っていて、すごくすごく良かったです。なにが緊張感を生み出していたのか思い返してみますと…。徐々に忍び寄ってくるプレデターの姿や、大自然でのインディアンたちの暮らしぶりなどが、とても丹念に作られていたことなのかなと。
リアルな描写なのかはわかりませんが、インディアンたちの知恵、感覚の鋭さ、生き方など、時間を割いて丁寧に描いている。これらも大きな見どころです。私は早々にバトルがはじまると思っていたので、上記の丁寧さはすごく魅力的に映りました。
バトルについては動きが現代っぽいようにも感じましたが、かっこよくて好みでした。主人公もめっちゃ格闘しててすげぇです。あと、野生のクマが恐ろしい。暴力そのもの。プレデターなみの恐怖を抱きました。
動物といえば、主人公のパートナーのイヌがとっても賢くて頼りになり、可愛らしい。殺伐とした雰囲気のなかで、良いアクセントになっていました。ほかにも様々な野生動物たちが登場しますが、きちんと意味がありました。そういう細かなつくりこみも良いですね。
過去作のオマージュがいくつか見られてグッときました。それが効果的に使われていて、知っている人なら「おおっ!これは!」と思うはず。過去作につながりがあるみたいですよ。
原点回帰にやっと成功!
プレデターはこれくらいシンプルなのが良い!笑
もともと深い意味はない生き物なんだから、エイリアンみたいに宗教的なテーマに行かず、人数も増やさず、体が急にデカくもならず、単純に何かヤバい生き物としてガチンコバトル映画として作り上げたのが素晴らしい。
"インディアンVSプレデターVS西部開拓中の白人"というプロットは完全にマニア向けB級映画です。
しかし、「レヴェナント:蘇りし者」を彷彿とさせるアメリカの自然を背景にしたバトル(熊ファイトもあります!笑)は美しく、ビッグスクリーン映え間違いなしなのだが、配信オンリーなのが残念。
"マッドマックス 怒りのデス・ロード"に着想を得たという本作。新デザインのプレデターもカッコ良い。
今年の中でも好きな一本になった。
原点回帰な起源のお話はシンプルで面白い
自宅レイトショーDisney+『プレデター:ザ・プレイ』
プレデターといえばシュワちゃん1987バージョンが一番面白かったんですが・・・
この新作は、近未来ではなく300年前って設定
狩猟しながら生活する民族の少女が、ハンターとして成長しながらプレデターと対峙するストーリー
近代武器を使わず技を磨いて頭を使って挑む姿が、新鮮です。
シリーズ好きならテンポもいいし99分とシンプルに楽しめると思いますよ。
最初期作観ていると面白さが1.5倍増しになります!
ストーリーで40分まで大きく進まない
初見だとイライラすると思う
でも大きく進まない部分がこまやかな伏線になっていますので気にかけてください
後半に前半のシーンが生かされています
後・まったく観ていない方は
最初期作観てください
この作品の良さが1.5倍良くなります
『プレデター』から装飾品を取っ払ったら神作が出来た
この作品 なんか展開全然ないやん、とか序盤がチンチラし過ぎとかいう意見がチラホラあるみたいやけど、それは違う(かなと思った)
『プレデター』という素材から無駄を省いた、というより必要最低限なものを映像化したという印象
プレデターの文明を写すわけでもなく(AVP2)、人間との共闘を描くわけでもなく(AVP)、そしてプレデター2みたいなプレデターのキャラクター性(子供は殺さないとか)を前面に押し出すと言う訳でもない
ただ"なんか宇宙から来たプレデターって名前の宇宙生物が無慈悲に襲ってくるってだけ"
それが凄くいい! まさに"原点回帰""シンプル・イズ・ベスト"というのがめっちゃしっくり来る
台詞もいくつか有名なものをそのまま使ったりしていて、観ている時めっちゃ胸が熱くなったw
そして映画としての展開というか話の進め方も良かったと思う
題名の『PREY』(獲物)
自然界で主人公側も普段から狩りをしてる、要はプレデターと同じことしてるってこと
狩りをしに来たプレデターも相手がその気になれば獲物になる、人間もプレデターも狩る側であり獲物でもある、っていう視点がかなり面白いと思った(それは劇中の台詞でも表現されてた)
PREYはホントにしっくり来る題名だと思う
Prey(獲物)の対義語はPredator(捕食者)
今作はプレデターが(前から突っ込まれてたけど)狩りをするヤツ(=Hunter)じゃなくて、本来の意味の捕食者としての立場感が強く感じたかな
※やってることは狩りだけど、獲物視点の作品だからそう見えるって方が正しいかも?
とにかく満足な作品でした!
劇場で観たかったな…
全77件中、41~60件目を表示