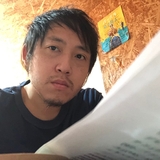コーダ あいのうたのレビュー・感想・評価
全732件中、701~720件目を表示
予備知識なく、ふらりと
4点以上ついてるって、あまりないので、ふらりと観に行ったら、とてもステキな映画でした。
エミリア・ジョーンズ、大好きになってしまいましたね。
ルビーとマイルズの丸太超えのキスシーンは微笑ましいし、
V先生もいい人過ぎるし、オーディションの結果辺りからラストまでは、涙でいっぱいでした。
歌の途中で、無音になり、周りの人の様子で、娘の才能
気づいたお父さんが良かった!
問題提起型と見るか原作ありと見るか…。
今年18本目(合計291本目/今月18本目)。
多くの方が書かれている通り、フランス映画を参考にして作られたという事情があるため、それが下敷きで、ある程度オリジナル設定があるというところはありますが「下敷き」がある以上、元ネタは大きく超えていないというところです。
もっとも元ネタ映画も見ていませんが…(元ネタ映画を見たことは前提な作りになっていない)。
このような「コーダ」(デフファミリーで、聴者の存在)をどうとらえるかは、現在ではいわゆるヤングケアラーの問題として今も議論されているところです。当然それは法律等は違ってもどの国でも同じでしょう。
ただ、そこに関する論点はあまりなく(一応はあるが、表立っては登場しない)、「コーダ」の方(女性の主人公)の歌の部分に大半寄せているので、問題提起型ととらえると、そこの部分が不足しているかな…という点は避けられないと思います。
かつ、この映画は実話ベースではないとはいえ、現在の日本(2021~2022)ではよく知られているヤングケアラーをどう考えるか、という点に気が付く方はかなり多いので、そこをどう取るか…(まったく無視するか、個人で考えるか…)という論点になりそうな気がします。
ひるがえって日本の事情を見ると、日本では「このような」家族も、基本的には民法の範囲でまずは考慮されます。しかし民法の親族編を見ると、特に「親→子」という概念で書かれていることに気が付きます(親族総則)。つまり、「子は親の指定する住居に住まなければならない」や、(今は改正が議論されていますが、俗にいう)「懲戒権」は定められているものの、「親→子」に対する条文ばかりであり、逆に「子は親を大切にしなければならない」などは一切存在せず、せいぜい親族相続の総則として「直系内では互いに扶養しましょう」という程度の、もはや理念条文というようにしか取れないものしかなかったりします。
すると、親がどうであれ(この映画のケースであれ、知的(精神)障害であれ)、子がどのような人生を選択するかは子の自由であり、どのような職業を選択するかも自由な話です(憲法22)。ここで、子が特定の職業についたときに、育てた親側が経済的に行き詰ったとき、日本でいえば生活保護法等が存在しますが…、それを頼ったときに、行政が子に対して「お互いに助け合わなきゃいけないんだから、大学(職業)をやめろとか、職業はこれにしろとか介入し始める」のが無理なのは、どう考えても明らかです。
一方でそればかりを主張すると親側は誰が面倒を見るのかという問題は残り続けるので、最悪、行政が合理的に判断して生活保護を受給させることしかできず、そうするとこの映画でいう「ヤングケアラーの子の将来の選択権」という、この映画で述べたかったであろう点がほぼほぼ存在せず(もちろん、日米で法律の差はあるとしても、根幹となる法律自体は多少の条文の差はあるとしても存在すると考えるのが妥当)、どのように解するのか…というのがかなり微妙です。
このような点まで考慮して下記のように採点しています。
---------------------------------------
(減点0.2) この映画はアメリカ映画です。したがって手話もアメリカ手話(ASL)基準ですが、日本手話(中間手話/JSL)とはまったく違います。しかし俗にいう「バリアフリー上映」ではありません。一方でアメリカ手話をテーマにした「サウンド・オブ・メタル」がそうだった(ちゃんと字幕がついていた)のも事実です。
であるなら、趣旨内容的に「バリアフリー上映にすることが常識的に見て望まれるし、かつ、そうあるべき」映画でそうでないのは、結局「誰に見てほしいのか」が怪しく、趣旨として「(全員が)デフファミリーの家族」か「コーダの子がいるデフファミリー」の家庭「も」当然に想定していると解するのが妥当ですが、この映画は「無聾」以上にバリアフリーではないので(アメリカ手話は日本手話(中間手話)と互換性がないため)、趣旨が理解しがたいという点はあろうかと思います。
(減点0.1) この映画はPG12 の扱いです。これは多少なりとも性表現が出るからであり実際の表現こそ最小限(それでもPG12)なものの、「字幕でうまくかわしている」パターンです。
しかし、この「字幕のかわし方」が比ゆ的にすぎるため、言葉(日本語)の習得に苦労する当事者には「やや」きついのではないか…と思える点もなきにしもあらずというところです(今のろう教育と30~40年くらい前のそれは、まったく教え方が異なる)。
※ このことは「(ろう教育における)9歳の壁」という論点があり、「比ゆ的な表現が多く登場する小学3年くらいの国語から、一気に理解できなくなる」ということは広く言われていることで、今現在(2021~2022)はかなり克服されているとされますが、既卒の方には十分な教育が提供されなかった過去もあるのであり(事実、2000年ころまでは「高等部まで出ても、国語だけ極端に成績が悪い」ということはよく言われていた)、「当事者の方」が行かれても、理解の差はかなりわかれるのではないか…と思います。
※ 日本では、日本国憲法で「義務教育を受けさせる義務」(「受ける義務」ではないので注意)が定められていた一方で、1979年(昭和54年)までは「義務教育免除・猶予」という名の「教育拒否」が公然と行われていた(この年に旧養護学校(現:特殊支援学校)ができた)こともあり、その関係から、50歳くらいの方以上と、制度が充実した20~30代で、ある程度国語力に差があると言われます。
※ このことは、今でも「大検」(高認)とは別に「中学校卒業程度認定試験」(中認)という試験が存在することと大きくかかわってきます。この「中学校卒業程度認定試験」は正式名称が「就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験」なのです。
日本ではこのような事情があり、実際に「当事者の方」が行かれることも想定できる(ただし、バリアフリー上映ではない)のに、字幕が極端に比ゆ的表現になっており(←PG12なので)、それもそれで「巻き込んで「当然想定すべき視聴者が」理解不能になるのはやめてね」ということであって、そこはどうなのか…というところです。
---------------------------------------
特報‼️❓日本でのリメイクは、ヒロインは高畑充希、彼氏は北村匠海‼️❓
また新しい世界を知ることができた
歌が最高!!!
物語の前半は、正直普通だった。セックスとケンカ、聴覚障がい者の説明等、、、。
後半からは、良かったかな。まぁなんと言っても主人公
歌が上手い。心に響く!あと性格。良すぎ。
家族愛を感じて終わりには感動もするけれど、耳が聞こえない以上に親が酷い。思春期・反抗期の親としてはないと思う。それに、いい娘に甘えすぎている。家庭状況や金銭的にしょうがないところもあるけれど、それでも可哀想。最後のお父さんや兄貴には良かったが、ちょいみんな自己中心すぎる気がする。
ただただ主人公が、可愛くて・いい子で終わり方が良かったので良かった、、、本当に、、、
飛び込みのシーンとかは、個人的にかなり好きです。
優しい気持ちになるなー。
かなり物足りない。
素敵なお話
フランス版のエールも好きでした。
あちらは牧場(だったはず?)こちらは漁師。
コンサートシーン親目線のシーンが流れるのだが無音が続く。
あー応援したくても応援できないよね、分からないもの。
でも、周りの人を見て喜ぶ姿泣ける。
自分の好きのものを親にわかって貰えないのも、子供の好きな物を理解できないのもつらいね。
だけどそれは耳の聞こえない聞こえるだけの話ではないね。色んなことで言えることだし。
他人を理解するってのは難しいけど、それでも色々飲み込んで一緒に時には別々に生きていくんだよねぇ。人間は。と思いました。
【”人はお互いに誰かを必要とし、助け合っている。けれど、自らの夢を諦めてはいけない。”稀有な歌の才能を持つ若き女性が悩みながらも、家族の愛に包まれて、夢に向かって生きる姿が琴線に響く作品。】
ー ルビー(エミリア・ジョーンズ:スタア誕生である・・。)は、”CODA:耳の不自由な親を持つ子供”として、漁業を営む、聾唖の父、兄、そして母の手話通訳者として、家族を助けて来た。
けれど、ルビーも、明るくて、少し性生活に奔放な両親や、正義感の強い兄に深い愛情を持ち、彼らの愛に包まれて育って来た。ー
◆感想
・序盤はコメディ要素を絡めながら、ルビー一家がお互いに助け合いながら、漁業を営む姿が描かれる。
- ルビーも午前3時起きで、父、兄と一緒に漁に出るシーン。ルビーが網を上げながら歌うシーンは彼女には、歌の天賦の才がある事を、観る側に伝えている。
そして、皆、楽しそうだ・・。漁協には、鱈を高く買って貰えないこと以外は・・。ー
・ルビーの父が”インキンタムシ”になって、当然お母さん(マーリー・マトリン:聾唖のオスカー受賞者ですね。)も・・。
- この後にも、多数出てくるのであるが、かなりお下品な言葉でも、手話があるんだなあ、ビックリ。そして、その風景が可笑しくて・・。仲の良い家族とは、当たり前だが、良いモノであるなあ。ー
・ルビー一家は、漁協に頼らず、漁業を行うことを決意。今まで以上に増す、ルビーの必要性。
だが、ルビーは未だ17歳。憧れの男子マイルズが合唱クラブに入ったのを見て、自分も同じクラブへ・・。
- クラブの顧問のV先生は、少し変わり者だが、指導者としては優秀で、ルビーの歌の才能を見抜く。ここら辺の遣り取りも面白い。腹式呼吸の発声法など。
そして、V先生は、マイルズも目指すバークレー音楽大学進学を勧めるのだが・・。
この辺りから、ルビーの悩みが描かれる。夢である歌の道を進むのか、家族のために漁業を手伝うのか・・。
一方、マイルズとの仲も急接近。二人で、ルビーの秘密の池の崖から飛び込むシーン。
好きだなあ、この展開・・。-
・ルビーの家を訪れたマイルズが、聞いたもの。
それは、ルビーの両親が”合体”する際に発する大きな声であった・・。
そして、テレカクシで、ルビーの父がマイルズに手話で”兵士は帽子を被れ!”と伝えるシーン。
- クスクス笑いながら鑑賞。
アンナ手話ってあるのかな、と思って資料を見たら、”ALS”と言う手話だそうである。
しかも、世界には200もの手話が有るという・・。
(そういえば、「ドライブ・マイ・カー」でも、韓国手話があったなあ・・。)
マイルズがルビーに言った言葉が素敵で、
”仲が良い両親は、羨ましいよ。俺の両親なんか・・。”
マイルズ、良い奴である。ー
■今作の白眉のシーン幾つか。(個人的感想です。)
・ルビーが所属する合唱クラブの発表会に、両親と兄が行くシーン。最初は、”今日の夕飯はなーに?””スパゲッティよ”などと、手話で会話する両親。
だが、ルビーとマイルズのデュエットになった途端に、無音になるシーン。
ルビーの両親が、周りをキョロキョロ見ると、ハンカチで涙を拭く女性や、感激の表情を浮かべる人々。
- 映画構成として、実に上手い。聾唖の人の感覚が一瞬分かった気がする。
そして、ルビーの父が
”自分の娘の歌声は、人々にこんなに感動を与えるのだ!”と悟るシーンでもある。
そして、家に帰った際に、父がルビーに”俺に歌ってくれ”と頼み、二人でトラックの荷台に腰掛け、父は歌うルビーの首筋をそっと両手で触る。
きっと、父には、娘の心の響きが伝わって来たのであろう。-
・両親と兄(いつも、三人は一緒である。)は、娘にバークレー音楽大学を受験させるために、オンボロトラックを走らせ、会場に・・。
普段着で、劇場に立つルビー。絶妙のタイミングでV先生が登場。伴奏を買って出る。
ルビーは、ジョニ・ミッチェルの「青春の光と影」を歌い出すが、緊張の為か精彩がない。
V先生は、咄嗟にピアノをワザとミスする。(やはり、良い先生だ。)
ルビーが審査員の上を見ると、2Fには、両親と兄の姿が・・。
- このシーンは、青春の惑いと、両親への愛を歌ったジョニ・ミッチェルの「青春の光と影」の歌詞の内容が、ルビー自身の境遇とシンクロしており、更にルビーを演じたエミリア・ジョーンズの張りのある伸びやかな歌声と相まっていて・・。琴線に響いてしまったよ・・。ー
<今作は、音楽映画としても、若者の成長物語としても、家族愛を描いた映画としても、恋愛を描いた映画としても、一級品だと思った作品である。
マイルズの結果は残念だったが、”必ず次年度はバークレー音楽大学に合格して、ルビーを男として、堂々と迎えに行けよ!”と思った作品でもある。>
家族愛
主人公の家族は、主人公以外の3人は聾唖者であり、生活する上で大変なことも多くあるが、愛情に満ち溢れている。その点でこの家族は幸福と言える。健常者であって名声と富を得たとしても、愛のない人生は虚しいものだから。
ヤングケアラーである主人公も大変だったろうが、彼女の兄もまた大変だったと思う。でもこの兄の妹に対する愛情も尊い。
学校のコンサートで全く歌が聞こえないのを苦痛に感じてたであろう両親が、大学の試験会場では手話を交えての娘の歌に感動している姿に涙が出た。
見終わったあと、心が洗われたような気持ちにさせてくれる映画だった。
ラスト泣けます
美しい歌声と物語に何度も涙が頬をつたう
歌うことが生きがいのルビー、合唱部の先生に才能を認められ音大受験に挑むも、家族の中で唯一健聴者として家族を助けているルビーは進学を諦めこれまで通り家族を支えるか、自分の夢を追うのかで選択を迫られる。
どのようにしてその思いが届くのだろうか。。。
【文句なしの脚本と楽曲と歌】
脚本がずば抜けて素晴らしい。
ルビーを優しく見守り背中を押すキャラの濃いメキシコ出身のV先生の存在も素晴らしかった!
美しく伸びやかな歌声が心を大きく揺さぶる。
学校でのコンサート、ルビーと父の夜空の下でのシーン、ラストのオーディションシーンは圧巻です。何度涙を拭ったことか、、、。
一見、暗い作品と思いきや、時にコミカルに、ロマンスもあって、笑って泣ける最高にハッピーな作品です。今年入って一番のオススメ作品かと。
コーダとは、耳の聞こえない親を持つ子どもを意味する。そして本作は音楽記号の“コーダ”とも掛けている。
ちなみに、普段パンフレットを買わない私が今作では買いました。楽譜に見立てたパンフレット(見た目もソナチネやソナタの楽譜の表紙に似てる)もとっても素敵!じっくり読み込んで、また追記するかもです!
漁師なのにはワケがある
『エール!』は大好きな映画なので、アメリカでリメイクすると、いったいどんな違いが出るのか?とても楽しみでした。
やっぱり圧巻のラストシーンには号泣!!
まず一番気になっていた下ネタ問題(←そこ?)
てっきりアメリカ版は別のアプローチでくるかと思ってましたが、ガッツリ入れてきた〜〜!
むしろ増量ww
父親の手話のディテールが細かくて、パントマイムを見ているかのように、言葉でなくてもしっかり伝わる下ネタ。すごい(^^;)
PG12です。
生きていくうえで下の問題は避けては通れません。(エロに限らず)
病院のシーンでは、社会と家族との仲介者であるということが、どういったことなのかが具体的にわかって、ハッとさせられます。
そして、主人公のリアクションの違いから、それぞれの映画の違いも見えてきます。
『エール!』のポーラちゃんは一生懸命に通訳していたけど
『コーダ』のルビーちゃんは、口にするのを少しためらっている。
邦題のダブルミーニングからしても
◾️『エール!』yell応援の掛け声 フランス語のaileは翼
⇒ 家族からの巣立ちがテーマ。社会と家族の仲介者であることが家族の中の居場所だった少女が、自分の翼に気づいて親の理解を超えた世界へ羽ばたいていく物語
◾️『コーダ』音楽用語coda 両親が聾唖者の子供(Children of Deaf Adults)
⇒ ヤングケアラー問題がテーマ。もちろん巣立ちの物語ですが、それに至るまでの葛藤には聾唖者の家族が抱える問題とCODAにかかる負荷が描かれている。
しかしアメリカ映画ってすごいですね。
多くの人にわかりやすく伝わるように組み立てられている。
家族を愛するがゆえの葛藤が生まれる状況を作るのがホントに上手い!
だから家族のなりわいを漁師にしたのか!!
海の上には他の船もいるし、魚は新鮮なうちに売らなければいけない。
健常者のコミュニティと関わらざるを得ない状況下では、仲介者の存在は必須。
すぐに通訳が手配出来ない(費用もかかる)自分が居なくなると家族が困る。
より依存性の強いヤングケアラー問題が浮き彫りになってきます。
ちなみに『エール!』は酪農家。マーケットでチーズを売ったり、自分達のペースで生活している。確かに仲介者としての負荷はあるものの、社会問題としてまでは描かれていないように感じました。
それはフランスのお国柄もあるのかも?
聾唖者を無理に健常者のコミュニティに入れることなく、健常者の物差しで見ない。耳が聞こえないのも個性と言い切れる。イジメのようなシーンが無いのもそのせい?
主人公の交友関係で言うと
『エール!』のポーラの親友マチルドの、ちょっと変なキャラクターが好きだったので、『コーダ』では出番が少なくて残念でした。
恋愛エピソードは多めでしたね。恋愛を通して人として成長していく過程も良かった。
合唱部の仲間たちは皆んな個性的なキャラがたってて、練習シーンも楽しかった♪
『エール!』に負けず劣らず音楽の先生がクセ者なところも良かったし、練習方法もユニーク。
歌う時の気持ちを語るシーンには感動しました。
よくもこれだけ盛りだくさんの内容をスッキリと纏められたもんだ。
やっぱりアメリカ映画って抑えるポイントがキチッとしていてすごい。
そして、『エール!』と『コーダ』の両方に言えることは
間違いなく歌の持つ力と映画の持つ力を堪能できる作品だということです。
オリジナル版を意識しつつ独自の設定を散りばめることで繊細な人物描写を実現した!!
フランス映画『エール!』のアメリカリメイク作品。
大まかなプロットや演出などは、似た部分も多く、セリフに関してもそのまま使用しているものも多い。
恋愛要素が追加されていたり、楽曲はアメリカで親しまれている曲に変更されていたり、細かい設定などが変更されている。
細かい部分でいえば、例えばオリジナル版では農場という設定だったが、今作では漁師という設定に変更されているし、音楽教師の個性が強調されていて、既婚者になっている。弟ではなく兄がいる設定など、随所にオリジナル設定が散りばめられている。
実際に聴覚障害のある俳優をキャスティングしていった結果として、オリジナル版と似た俳優になっているのは奇跡といえるだろう。
設定を漁師にしたことで、健聴者が船に同乗しないといけない状況をより具体的に作り、家族が依存しているという環境を強調しているのと同時に、ルビーも家族を手伝うことで、ひとりだけ健聴者であることへの疎外感を埋めていることも描いていて、互いに依存し合う関係性が強固なものとなっている様子が、オリジナル版よりも凄く感じられた。
自分の歌声に対して、可能性を見出していくことが、結果的に家族と孤立してしまうことになる。
理想と現実の絶妙な距離感、一番歌声を聴いてほしい家族に聴いてもらうことのもどかしさの中で、どう歌を伝えるのか、そしてそれが家族にどう伝わるかの描き方は、オリジナル版に沿っていながらも、ストーリーを通して今作独自に繊細に描いてきた結果的要素が加わり、見事なまでの完成形となった。
ルビー役のエミリア・ジョーンズの歌唱力も大きな役割を果たしていて、ちゃんと才能があると感じさせる説得力には感心するのみだ。
泣かされました
惹き込まれる歌唱力✨
前向きになる作品
試写会で観ました。
CODA(コーダ)とは
Children of Deaf Adults の頭文字で
「耳の聞こえない親のもとで育った
耳の聞こえる子ども」のこと。
両親と兄が耳が聴こえなくて
主人公の妹だけが健聴者
という家族の話。
必然的に手話通訳者となっている主人公。
つねに家族から頼られて生きてきた。
でも、
家族のためだけに生きるのが
彼女の人生ではない。
彼女が自分の夢に向かって動き出した時、
彼女ナシで生きていくことを
余儀なくされる家族。
しかも、彼女の夢は「歌」
彼女の声が聴こえない家族は困惑します。
家族のためには
夢を諦めた方がいいのではないか?
思い悩みます。
最終的には
爽やかな前向きな結末が待っています。
ぜひ観てほしい。オススメです。
全732件中、701~720件目を表示