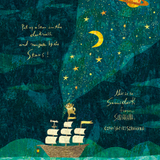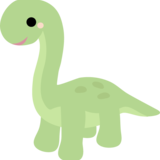コーダ あいのうたのレビュー・感想・評価
全732件中、41~60件目を表示
「Both Sides Now」は最高の映画主題歌
2022年3月31日(木)
満を持してアカデミー賞作品賞他3部門受賞の「Coda あいのうた」を観る。
アカデミー賞受賞式の前に観ようと思っていたのだが、見損なっていた。
待った甲斐あってTOHOシネマズ新宿は本日のみ番組編成上かスクリーン9(キャパ499)での上映。音の良い劇場で観られて良かった。
先週、約20年振りに会った映画の友人と「Both Sides Now」は最高の映画主題歌だが、主題歌に使われた映画「青春の光と影」が最低だったと言う話をして意気投合したばかりだった。それが最高の映画でクライマックスに主人公が熱唱する歌で帰って来た。私の中の最高の映画主題歌「Both Sides Now」がやっと最高の映画主題歌として歌われたのだ。こりゃ泣けるわ。この映画が作品賞で良かった。
クワイヤを指導するV先生が良い。歌う時の気持ちを言葉で表現出来ない彼女に手話で表現させる。彼女が最初に皆の前で歌えなかったのを歌わせたのと同様に、出せなかった物を出させる彼の存在が大きい。
そして音大入試の時のピアノ伴奏でのV先生のナイスアシスト。(!) 緊張で歌い出せない彼女に前奏をわざとミスる。そして、やり直し。彼女は家族の前で手話付きで見事に歌い上げる。
また、秋のコンサートの無音の描写。映画の無音のシーンが、これ程雄弁だった事もあるまい。(後日、リメイク元のフランス映画「エール」をCSで観たが、無音のシーンの演出は同じだったので、そのままの手法を使ったという事か)
当然、リメイク元の「エール」で歌われるのは「Both Sides Now」ではない。
私にとって彼女が歌う唄が「Both Sides Now」だった事が、この映画が私にとって特別な物になった。
父親の借金や漁業組合の事等、課題を如何に解決するかが描かれていない部分もあるが、全編を通じて1度しか発せられない父親の言葉「GO!」で許す。
家族愛にあふれる感動作
もう何度見たかも忘れるくらい繰り返し視聴している一本。
タイトルの「CODA」というのはChildren of Deaf Adultsの略で、親がろう者で子供が健聴者の場合の子を差す。
「コーダの子」は幼いころから親の通訳として連れ添う事が多く、それ故に時に重要な責任を負う事もあるため、心的ストレスが問題視されることもある。
その責任感から一般的な親子よりも結びつきが強く、なによりも家族を優先する自己犠牲の傾向が強いとされる。
この映画の素晴らしいところはやはり「ろう」の俳優さんを使っているところだ。
両親と兄役を本当のろう者を使う事でよりリアルな演技となり、作品の世界観に引き込まれる。
また、従来の障碍者を描いた作品というのは彼らを「社会的弱者」として扱うことが多いが、この作品は(娘のおかげとはいえ)健常者と同等の生活をしており、自立した人間として描かれていることに好感が持てる。
主人公ルビー・ロッシ役のエミリア・ジョーンズさんもまた多感な高校生を好演。
9か月の間手話とボイストレーニングを行ったとの事だが、手話の上手さもさることながら彼女の美声には思わずうっとりしてしまう。
どんなに良い作品でも、キャラクターに魅力が無いとつまらなく感じてしまうものだが、その点では非常に成功している。
内容もまた素晴らしく、「コーダの子」が抱える問題を積極的に描き、家族への愛と自分の夢との葛藤する様が見ている側の心をも揺さぶるのだ。
この作品はリメイクではあるが、非常に優れた名作であると評価したい。
音のある世界と無い世界をつなぐもの
映画を観るときは、できるだけ原作や事前情報を頭に入れずに観るようにしている(この情報洪水社会では意図せず情報がインプットされてしまうことも多いのだが・・・)。
しかし、このように身体に障害がある人々が登場する作品だと、事前情報を入れていなくても、「健常者としての自分」をどうしても意識してしまう。従って、映画を正当に評価できるかどうかというとそれは疑わしい。
もし、ルビーの家族が健常者だったら、この作品はここまでの支持を勝ち得ただろうか?サンダンス映画祭で見いだされ、オスカーを獲得しただろうか?恐らくそうはなっていないだろう。ありふれた家族愛と成功を描いたストーリーだ。
しかし、だからといって、この作品が過大に評価されているとは思わない。
主人公ルビーは、この一家にとって音のある世界と無い世界を繋ぐ役目を果たしている。家族もそれを頼りに生活している。しかし、彼女は家族が最も理解しがたいであろう「音楽」の世界へ進もうとする。これを宗教や価値観の違いを乗り越えて互いを理解をする、応援する物語だと読み替えるとどうなるか?とても困難な話のように思う。
それを乗り越えたられたのは、家族の愛の力だ、と言ってしまえばそうかもしれないが、そんな単純なものではないと思いたい。家族も、ルビーのことを理解しようという意思を持ち、行動しなければ、わかり合えることはなかったはずだ。
ルビーのステージでの歌唱シーンは、この作品の表現手法の素晴らしさを堪能できる。
高校生の娘の晴れ舞台。その澄んだ歌声が一転、無音のトーキー映画の世界になる。我々は父や母と同じ世界に、束の間、入り込む。周囲の人々の反応を確かめる父母。音がなくとも、娘の声が人々を感動させる本物だと知る。そして、彼女の本心を理解する。
バークリーの入学試験。手話を交えて歌う娘。音は聴こえなくても、その声は家族に届く。
父は、娘に言う。俺におまえの歌を聴かせてくれ。もっと大きな声で歌ってくれ。
そして、首を、頬をさわりながらその歌声を手触りで、感じ取る。
娘の歌を聴きたい。この身体で感じたい。その強い意思が伝わってきた。
父親を演じたトロイ・コッツァーの演技は、際立っていた。
愛があればわかり合えるなんて、そんな簡単なもんじゃない。理解しようという意思と心がなければ。
この家族を繋いだもの。それは、ルビーの歌。そして、互いを理解し、支えよう、応援しようという家族の前向きな意思の力だったように思う。
「青春の光と影」いい曲ですね。
家族愛を描いた傑作
今から十数年前、とあるきっかけで両親は聾者だが本人は聴者である人の講演を聞く機会があった。彼曰く、いわゆるCODA(Children of Deaf Adultsの略、本人は聴者であるが、両親は聾者であることの略称)は、生まれた時から、両親と外部の人とを繋ぐ「翻訳者」としての立場を担うことが運命づけられているとのことだった。
まさにこの映画のルビーそのものである。
この映画を見て、児童虐待だとか、支配的な両親であるといった意見も見受けられるが、CODAの実態をよく理解していないと思う。
聾者の両親にとって、CODAは外界と自分たちを繋ぐ唯一の存在、自分の半身のような存在なのである。
そこには、一般的な親子関係では想像のつかないような強い関係性が存在している。
しかし、この映画はその強い関係性を超えてまで主人公が夢を追うのと同時に家族をものすごく大切に思っていること、つまり家族愛が大きなテーマとなっている映画だと思っている。
そのような常識では考えられないくらいの強烈な、宿命づけられた関係性を断ち切ってまで自分の人生を生きていこうとするルビーの姿に心が打たれる映画なのである。
よく話題になる、コンサート中の無音の演出だが、私からすればこれは表面的な演出・テクニックにすぎないと思っている。
この映画は、難聴者の疎外感をテーマにしているわけではなく、ルビーとその家族たちの絆を描いているのだ。
絶賛すべきは、ジョニ・ミッチェルを歌うオーディションのシーンと、何といってもラストの家を出ていくシーンであろう。
一度家族に別れを言うのものの、いざ車を動かすと耐えがたい寂しさが込み上げてくる。
そこで、「ちょっと待って」と車を止めて、家族と抱擁を交わしに行く。
残された家族からすれば、ルビーがいなくなることは自分たちの半身を失うのと同じようなものだ。
しかし、彼らは「行ってこい」とルビーの背中を優しく押す。ルビーを愛しているからこそ彼女を送り出し、別々の生き方を選んだのである。
お互い、自分の半身である、かけがえのない存在との別れなのだ。
このシーンがこの映画のすべてであると感じた。
ルビーと家族が本当に大切に思い合っていることがすごく伝わる名シーンだと思う。
映画のパッケージにも使われている「本当に愛している」のサインを送るルビーの姿から、家族愛と青春、夢や希望を一度に感じられる、稀に見る傑作であると感じた。
いい話のようでいて、浅い
主人公が可愛くて随所で綺麗な歌声も聞けるのでそれなりに雰囲気は良い。
でもよく考えるまでもなく腑に落ちないところがたくさんあった。
何であの程度の努力で名門音大に受かるんだよ?
KPOPアイドルはもっと歌ガチってるって。
家業と音楽の板挟みという苦難を結局どう乗り越えたの?
そこがちゃんと描写されてないから「元からちょっと歌が上手かったから運良く受かっただけ」にしか見えないんだよ。
本番オーディションなのに何で家族が入ってきたからって手話混じりで歌うんだよ?もっと発声に集中しろよ?人生がかかってるんだぞ?
何で部外者が入ってきたのに試験続行するんだよ?
歌い直しとかルール的にOKなの?
結局最後通訳はどうやって用意したんだよ?
何かよくわかんないけど恋も進学も家業もうまくいきました、では当然感動出来るはずもなく。
進研ゼミの漫画じゃないんだからさ。
大切なものをすべて押さえている、素晴らしい映画
ええ、当方それなりにヒネクレた人生を送ってきたものでね。
「家族みんなが耳が聴こえなくて、1人だけ耳が聴こえる健気なティーンのガールが、歌の才能を見出され…」
的なプロットを聞かされると、
「出ましたね…これは。大丈夫なんですか?貴重な休日の2時間を使ってお涙頂戴ですか?だいいちそんなCHARAみたいな邦題よくつけまし(略)」となってしまうクチなのです。
なのですが、いやぁやられました。
序盤からルビー一家の漁業の描写がもう豊かだし、みんな目がいいですね。社会はクソだし、辛いことばっかりだけど、陽気に楽しく生きていく。その傍に音楽と、そしてユーモアがある。ゴスペル、ブルースに始まり、映画で音楽を取り扱う時はこういう「寄り添い感」が大切。
家族それぞれがそこそこくたびれてるんだけど、生きしぶとくて、嫌なことにも負けなくて、汚い言葉も平気で言うし、あとパパママの性欲がメチャメチャ強い笑 こういうのも大切。そして、毒親といえば毒親なんですけど、ギリギリで見てて不愉快なラインに落ちてない。そのバランス!重いテーマを扱っていますがこの映画はエンターテイメント。それもとっても大切。
個人的に、見てる最中にプロット感を想起させない描写の映画が好きで。ああ、こういう事を描こうとしてるんだろうな、と思いながら見るよりも、その時々で起こる事象が魅力的で、何これクスクス、ってなってる間に、気がつくとストーリーが動いてる映画の方が好み。その意味でこの映画は素晴らしい映画でした。みんなチャーミングですよね。
耳が聞こえない家族と、歌に魅了された娘。構造的に、娘の夢に家族は寄り添ってあげられない。この根本的な断絶とそしてそこを微かに埋める「身体的アプローチとしての音楽」。パパ曰く、ケツが揺れるラップは最高だ!耳が聞こえなくても、振動という形で感じられる「音楽」がある。あ、なるほどそう言うのは分かるんだねパパ。…このシーンが大きく終盤まで響く伏線になってきます。これも本当に美しかった。耳の聞こえないパパは、ルビーの歌を、首筋を触って声帯が震えるのを感じることでしか理解できない。そういうシーンも、変なタメなくスッと目の前に提示されて、まぁ泣きました笑。発表会でいきなり音がなくなるのも、ベタだけどズルイですよね。
結局のところこういう映画こそ、「キャラクター」というか、登場人物の「実在感」のようなものが本当に大切なんだなと思いました。目の前の生活に翻弄されてルビーのやりたいことを押し潰しちゃいそうなパパママ。でも本当はそんなこと望んじゃいない。普段の行動からそれがしっかり見える。ルビーに悪態をつきながら、家族に潰されるなと思いの丈をぶちまけるアニキもホントに最高。この世に悪い人なんかいない。
あとV先生もステキ。いかにもなヒネクレと熱さ。クセ強な音楽教師。こまごまとした描写がこれも大事な例ですよね。終始クスクスっとしてる間にいつの間にか涙が出ているというか。それとマイルズ君がめっちゃ怖がってたくせにルビーを止めてひと足先に崖から飛び降りちゃうのとかキュン過ぎでしょう。こういう小さな「Yes!」の積み重ねがモノづくりにはホント大切ですよね。
という事で終始感情揺さぶりポイント満載の素晴らしい映画でした。美しいものを見た気持ちになれたので5点です!最高!
※話ずれますけど個人的にCLASHが大好きなので中盤のI fought the lawも良かったです。もう全部よかった。
良作だがアカデミー賞受賞は正直疑問、肝心の「歌」に爆発力が無い
フランス版「エール」のリメイク、トロイコッツァーはじめ俳優陣の演技、脚色は素晴らしい。
あらすじは特に書かないがこの作品のキモはなんと言っても主演エミリア・ジョーンズの歌唱力。耳の聴こえない家族の中、唯一聴こえる彼女の才能である“歌”で奇跡を起こすという話しは、まさに「スター誕生」のサクセスストーリーなのだが、肝心の「歌」に爆発力が無い、勿論下手な訳では無いし充分上手いのだが、「アリースター誕生」のレディーガガに及ばないのは仕方ないとしても、AGT(アメリカズ・ゴット・タレント)・BGTに出てくる素人の方がはるかに鳥肌立つほどの爆発的歌唱力を披露している。
歌のもつ力がどれほどのものなのかを表現してこその本作。コーラス部の合唱シーンもドラマ「グリー」の方が良いのでは無いかと思う。
映画作品なので、奇跡的サクセスストーリーを期待していると肩透かしかもしれない。
この年のアカデミー賞最多ノミネートは『パワー・オブ・ザ・ドッグ』(Netflix作品)(その他「ドライブマイカー」もノミネート)
アカデミー賞作品賞の投票は、アカデミー会員の全員に権利があり、10本のノミネート作品からランクづけして投票するのだが、1位が一番少ない作品が却下され、それを1位にした人は2位が1位になるという繰り上げ方式で、結果的に最後に過半数をとった作品が受賞となる。つまり極端に賛否が分かれる作品は残りづらく「誰もが素直に感動できる」作品ということで、予想外の受賞となったとも言えるのかもしれない。
タイトルなし(ネタバレ)
前半ほんとにルビーが気の毒で辛かった。
特に合唱部に入ったって言ったときに「反抗期なの?」ってひどすぎる。
でも兄のセリフや行動を見てるとちょっと印象が変わってきて、ルビーが家族を守らなきゃいけないって思ってやってることが逆に自立を妨げてるんだよね。
「家族の犠牲になるな」って言葉にはそういう意味も込められてるんだと思う。
音大に推薦されるほどの歌唱力ではなかったけどピュアな歌声は素敵だったし、音が消えて聾者視点になる演出も切なくて良かった。
本当の愛とは
不器用でもいい。間違ってもいい。そこに本当の愛さえあればきっといい家族になれるんだろう。ルビーのお兄さんは、一貫してルビーの自由な未来を願っている。自立するために仲間と飲み会に行って関係性をつくろうと頑張ったり、1人で業者と取引しようとしたり、ときにはルビーに頼る家族にも反発する。兄としてずっと妹の未来を願っている。ろう者であっても、支えられるばかりになりたくない。頼れる兄貴でいたいから。お母さんは、典型的な子離れできていない母親だった。親にとって子どもはずっと子どもだというけど、こういう親多いんじゃないかな。ろう者と聴者の隔たりをいちばん感じているのもお母さんだ。それはきっと自分の親と自分がうまくいっていなかったから。ルビーは「ダメな母親なのは、耳のせいじゃない」と冗談まじりに言う。それはきっと本音だろう。耳が聞こえるかと心が通じ合えるかは別問題だ。それはこの映画が教えてくれる。人間は自分にコンプレックスがあるとき、つい不都合をそのせいにしてしまいがちだ。でもそのせいじゃないことは多くある。例えば容姿に自信がない人は、人間関係や恋愛がうまくいかないとき要旨をその原因と思い込んでしまうが、実は内面の問題だったりする。障がいだって同じだ。人間にとって障がいの有無などほんの一部分に過ぎない。けどそんな母親も、不器用ながらルビーを愛している。お金がない中でも娘のために赤いドレスを買ってあげたり。不器用でもストレートな愛情はきっと届く。お父さんは、誰よりもルビーの可能性を信じている。理解したいと心から願っている。コンクールで、ルビーの表情、観客の様子を見渡し、ルビーがどれだけ音楽を好きか、才能があるかを理解しようとしている。音がない世界で、ルビーの歌を感じたいときっと誰より願ってる。不器用で綺麗な形の家族ではないかもしれないけど、疑いようのない愛情がそこにはある。それはきっといちばん大事。V先生も愛情を持っている。ルビーの才能を信じ続け、最後まで諦めず細い道を作っていてくれた。家族のことも、他の人から馬鹿にされていることも関係なく、1人の生徒としてときには厳しく正面からぶつかってくれる。この映画のキャストは実際にろう者が演じている。みんな素晴らしい演技だ。お父さん役のトロイ・コッツァーは助演男優賞を獲得した。悲劇の対象として、守られるべき存在として障がい者を描くわけでなく、自立した魅力的な人物として描いているところもいい。この映画はアカデミー作品賞をとった。このような素晴らしい映画が最高の評価を受けて本当によかった。
素敵なオリジナルあっての素敵なリメーク
第94回のアカデミー賞で作品賞・助演男優賞・脚色賞、ノミネートされた部門すべてを制覇、まずは拍手を贈りたい。2015年のフランス映画『エール!』の英語版リメークである。前年のサンダンス映画祭でのグランプリがあったとはいえ、アメリカ国内での公開はAppleTV+での配信のみ。この年アカデミー賞大本命『パワー・オブ・ザ・ドッグ』とともに、配信作の主要部門でのノミネートは今や当たり前の時代になったが、今回配信作初の作品賞受賞はアカデミー賞の歴史に残る快挙といっていいだろう。
オリジナルではパリ郊外の酪農家一家だった設定が、今作では漁港の町に暮らす漁師の家族の物語に変わった。四人の家族のうち3人が耳が聞こえない。ただ一人健常者の娘が家族の耳になっている。一家の誰もがそれを当たり前のこととして受け止め、障がいのあることが嘘みたいに明るく真っすぐに生きている。その娘が都会の大学への進学を前にして、家を離れることが一家の問題として大きくのしかかってくる。前作から本作へと受け継がれる基本的な設定だ。だがここで重要なのは、家族の成り立ちが変わったことで、一家から娘がいなくなることによる家業への影響の度合いがより深刻になった点だと思う。酪農家なら気楽で漁師なら深刻だなどというつもりは全くない。どちらの家族にとっても大きな決断を迫られる問題なのだ。あっけらかんとしてどこまでも明るかった前作に比べ、今作ではどこか深刻な気配が漂うのは、この家業の設定の改変によるところが大きいからなのだと思う。
前作では姉と弟だった兄弟の設定が今作では兄と妹に変わったことでのめぼしい効果は今作の美点になった。進学をあきらめかけた妹に「家族の犠牲になるな」と手話で激励する兄。自分の障がいが妹の人生までをも変えてしまうことへの怒りや悲しみ、妹を思う兄の心根が胸を打つ。前作にはなかった今作の素晴らしいシーンの一つだ。
一度はあきらめた進学のためのオーディションの朝、誰より早く一番に起きて娘を揺り起こしオーディションを受けろと衝き動かす父。車に乗って一家総出で会場に向かう家族。「出て行く私を許して。逃げるんじゃない、旅経つんだから」と手話を交えて歌う娘。聞こえないその歌に精一杯のエールを送る父母と兄。映画終盤の流れはきっちり前作を踏襲してやはり胸を打つ。オリジナルへのリスペクトである。
もし前作を見ていない人がいたら、DVDでも配信でもいいから是非見てほしい。アカデミー賞で作品賞を獲得した映画にはこんな素敵なオリジナルがあったこと。本作の制作に関わった人たちが、どうしてこれをリメークしたかったのかが必ずわかると思うからだ
単なる苦境を克服して誕生する歌手のサクセスストーリーではない
🔳押し付けないハンデある人たちの心情
聴覚障害というハンデを持ちながら強く生きる家族に対し世間は必ずしも優しくない。それでも明るく、時には社会の不条理にそれぞれの形で立ち向かう家族の姿が自然と見ている人の心を引き込んでいく。
🔳第一クライマックスの静寂がどんなメッセージをも超越
衝撃的な表現力だった。どんな観客も主人公の美しい歌声を聴きたくなるだろう。ましてやその歌声それが家族なら。そんな家族の気持ちを表現するための表現は主人公の最高の歌を期待していたものに実に容赦無い。ここで見るものの誰もが主人公に家族側が背負ってきたハンデの凄まじさを知ることになる。単に歌手のサクセスストーリーを描きたかったのではないという監督の信念を感じさせられた。
🔳トレードオフされているヤングケアラー問題
聴覚障害の家族の元に生まれた主人公はヤングケアラーにあてはまる。この主人公は自分の歌に希望を見出すことが出来た。現実にはそうした境遇にない人が少なくないであろう。声もあげられず、与えられた境遇に甘んじながら生きている子供たちがいることに思いを馳せるとこの作品を手放しで賞賛しづらいものがある。
🔳聴覚障害者にとって手話の歌とは
さらに聴覚障害がある人に手話で歌を共有する価値を過大に評価していないだろうか。音の振動のリズムと手話が調和して伝わる感覚やその他にも視覚で音楽を表現する試みはあるだろう。それで聴覚障害者も一緒に感動を共有しているかどうかは聴覚保持者は確信を持てないはずだ。それでもそうした試みの価値は評価されて良いが、真に感動を共有できる手段を追求しないと単なる思い込みで終わってしまう。
手話は、世界に溢れる言語のひとつ
手話は、世界に溢れる言語のひとつ。
優しくて美しい、
コミュニケーションのひとつなのだと気づくはず。
素晴らしかった。
ただ、素晴らしかった。
後半ずっと泣いてました。
「コーダ」とは、
「Children of Deaf Adults」の略で
耳が聴こえない親を持つ聴こえる子どものことを言うそう。
両親と兄、家族の中で1人だけ耳が聞こえる歌が好きな女の子。
これは、彼女の困難と葛藤、そして生き様を通して描かれる、家族の愛と成長の物語。
ろう者視点とコーダ視点、健聴者視点それぞれの世界がリアルに描かれていて、『マイノリティとどう向き合うべきか』を突きつけられる。
セリフの一つ一つ、手話の一つ一つが突き刺さった。
歌が好き。
なぜわかってくれようとしないのか。
逃げたい。苦しい。理解したい。助けたい。
愛してる。
それぞれが、それぞれの環境や境遇の中で自分の人生を生きている。
それを知り、考えること。
大切だと思わせてくれる素敵な作品でした。
是非とも映画館で
それぞれの"音"を楽しんでほしい。
☆☆☆☆ 配給会社、タイトル狙いすぎ(u_u) まあ、それは置いと...
☆☆☆☆
配給会社、タイトル狙いすぎ(u_u)
まあ、それは置いといて…
とても良かったなあ〜(´ω`)
ここまでウェルメイドに徹して作られていると、好感が持てる。
但し、少しばかり毒っ気のある作品が好みな人にはオススメしませんが、、、
実は鑑賞後直ぐにネット繋がりの映画仲間に「超オススメ!」と伝えたところ。
「リメイクですよね!」との返事。
「?」あらら本当だ!ここ数年は、鑑賞前には予告編以上の情報を観ずに鑑賞する事が多いので。
(原作本がある日本映画はまた別として)
この作品がフランス映画『エール』のリメイクだった事を知らずに鑑賞していた。
慌てて、当時の自分のレビューを見ると…
あらららら、、、日付と劇場名だけ💧
確かに鑑賞中には既視感強めに感じていたのは事実。でも直ぐに『エール』の事を思い出せなかったのだから、それ程には自分には刺さらなかったのだろう(。-_-。)
前半からかなりの下ネタを繰り出しては観客を笑わせて行く。
でもその下ネタが、決して観ている観客に眉をひそめさせる下ネタではなく。寧ろ微笑ましい下ネタなので、観客側に嫌な思いを抱かせない。
真面目な場面が続いた後には、そんなクスクスとさせてくれる場面がある為に、どんどんと引き込まれて行った。
とかく聾唖者を扱うだけに、深刻な内容になりやすいところでの笑いの場面でもあり。私の様な健常者でも、聾唖者の人の気持ちに寄り添えているのでは?との思いにさせて貰える。
(但し、その思いが果たして聾唖者の方達から観て、どの様に映ったのか?は完全には分からない。当たり前の事なのだけれども…)
と、ここまで書いたところでやっと元ネタでもある『エール』のストーリー展開を思い出して来た。
ほぼ元ネタ通りのストーリー展開だったのではないだろうか。(ちょっと記憶が怪しいですけど)
おそらくは、最後のオーディション場面で涙腺崩壊する人が多いのではないでしょうか?
実際問題、私もこの場面で遂に涙腺崩壊を起こしたのです。
でも、そこに至る前の場面にこそ私の心に刺さった場面がありました。
それこそが、ルビーの歌声を(心で)初めて〝 聴いて 〟周りの人達の喜びの表情から感じた《家族》の想いでした。
特別に凄い演出であったり、映像に凝っていたりするわけではないのですが。的確に観ている観客の心の隙間に入り込んで来る爽やかな風の匂いを感じたのでした。
あの黒澤明が生前に言った言葉をちょっとだけ思い出した。
「作品にはそれを作った人の性格がでるんだよ!」
(正確ではないけれど、それに近い意味で)
この作品を監督したのは女性で、まだ作品数はこれで2本目らしいですね。
その演出であり作風から、心優しい人なのでは?との思いをさせてくれて、早くも次回作品が楽しみになっています。
ところで、多分元ネタの『エール!』には無かったと思えるのが、若い2人が池の上にある大きな岩から飛び込む場面。
スティーブ・テシックの自伝的脚本でピーター・イェーツが監督した青春映画の傑作『ヤング・ゼネレーション』
アメリカ映画界では名作との認識が浸透しているだけに。岩や崖から池や湖に飛び込む映画が有ると『ヤング・ゼネレーション』?と、ついつい思ってしまう。80年代映画大好きおっさんであります(^^;;
「◯◯になるな!」
兄貴かっこいいぞ!
2022年 1月21日 TOHOシネマズ日比谷/スクリーン9
ここで見る星は海で眺める星ほどキラめいてないな
前半 笑える 、後半 泣ける
全732件中、41~60件目を表示