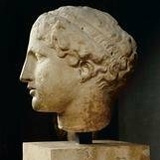コーダ あいのうたのレビュー・感想・評価
全733件中、221~240件目を表示
コーダの意味を知る
長い事生きてるのに 知りませんでした。
日本でそういう言い方するようになったのは近年なのでしょうか?
と思って調べたら
1980年代にアメリカで生まれた言葉である。1994年、D-PRO主催 THE DEAF DAY'94でのレスリー・グリア氏(米国/ろう者)の講演にて、日本で初めて『CODA』という名称と概要が紹介された。その後、成人したコーダが初めて集まり「J-CODA(ジェイコーダ、Japan Children of Deaf Adults)」が結成された。以降、一時期活動に間が空いたものの2000年頃に活動を再開。2015年に組織化して会員登録を開始した。
だそうで、なるほど。
という出だしが 無粋なくらい良い映画である事は間違いなくて
エールっていうフランス映画見た時の
あのあまりの荒削りっぷりにびっくりして
アメリカ映画にリメイクは そりゃあアリだろうと思ったが
その通りに 素晴らしくリメイクされていた。
牛を飼うチーズ農家が 漁業へと変換され
それに伴う事故が 彼女を家族に縛り付ける理由となり
弟は兄になり
彼女に家を出ろという。
あとフランス映画の方では かなりとっ散らかった印象のお父さんの選挙もなかった。
歌のうまさも極め付けで
オーディションでプロダクションというのではなく
大学に というのも 真っ当に見えた。
と つらつらと 違いを並べてしまったけれど
そういう事でなく とても良い作品となっていた。
コーダ(聞こえない親をもつ聞こえる子供のこと)
思ったより下ネタ過激でびっくり
お母さんと娘のシーンで大号泣
小学生の時にお母さん亡くしてるからああいう関係憧れる。いいなぁ。
お兄ちゃんも優しすぎて泣いた。
映画館であの静寂シーン体験したかった。
家族3人は実際にも耳が聞こえないらしい。だからあれほどリアルな演技ができるのか。耳が聞こえる有名俳優が演じるよりもこっちの方が大正解。
愛が包む名作。
Amazonプライム 吹替版にて視聴
フランス映画「エール!」を米リメイクした作品。
障碍者を題材にしたフランス版のリメイクと言うと「最強の二人」を思い浮かべてしまうが、
こちらは舞台設定をよりドラマチックに修正したようだ。
「エール!」については未視聴なので、対比については割愛。
聾者の家族の中、通訳のように生きる主人公のルビー。
しかし、召使のような訳ではなく、家族の愛の中で身を寄せ合って暮らしている。
彼女は歌が好きだが、家族の理解は得られない。そんな中、音楽の先生に才能を見出され……
と言った内容の本作。
本作のテーマは「理解と共感におけるハンディキャップの壁」と「家族の中の犠牲を是とするか」の2点だと感じた。
話者とのコミュニケーションの難しさ。これは聾を扱う上では必須だ。近年の映画では「聲の形」が一番適格に描いていたと思う(ヒロインの非現実性以外)
そこに主人公の音楽的才能を理解する事の難しさも加わってくる。
なるほど、これは共感出来ないことを共感させられる。とても苦しい演出だ。
しかし本作は、むしろそこから先を越えた、家族として娘の夢を後押しする事を描いている。
愛が全てを包むような読後感を与えてくれる。それが素晴らしい。
この物語の性質上、主人公の才能を説得力のある描写で表す必要があるのだが、
ルビーことエミリア・ジョーンスの歌が上手すぎて納得させられる。
特にラストの歌唱シーンは最高だ。
あそこまでの歌唱シーンは近年類を見ないくらいの心の揺さぶり方だ。
例えるなら「バーレスク」のテス(シェール)の歌唱シーン「You Haven't Seen the Last of Me」クラスの出来だった。
劇場で観たかったような。一人で静かに観たいような。
そんな宝箱のような作品だったと思う。
大切な出会い…
聴覚障害者の両親、兄の通訳をし、高校卒業後には経済的理由から家業である漁師になろうとしていたルビー。しかし、音楽教師に出会うことによって、才能を見出され、歌うことの楽しさ、友達との交流など、人間的に成長していく。家族も彼女の歌は聞こえないが、周囲の人の反応を見て、娘の才能、やりたいことに気付き、音楽大学への進学への夢を後押しする。聴覚障害というハンデを描くが、良い意味でも悪い意味でも、彼ら家族を聖人君子のようには描かいておらず、ユーモアを交えており、見ているこちらを元気付けてくれるような作品だった。彼女も素晴らしいが先生や家族も素晴らしかった。
後味のいい映画
無欲の潔さ
きょうび、ネットに帰属するわたしたちがいちばん腐心していること──といえば、自然さである。
ほんとは、ぜんぶ作為でやっている。
たとえば美容系インフルエンサーが一日をつづった動画は、寝室にカメラをセットして、いかにも起きました体で起きる。そこから一度もカメラ目線することなく、普段やっていないような朝食をつくりメイク・身支度をして仕事へでかける。帰宅した体でマンションの扉が開き、普段やってないような夜食をつくり、バスタイムからお肌のお手入れなどを見せて就寝する。・・・。
平素を装っているが、まちがいなく総てテイクを見て、なんなら何度か撮り直している。
自然にやっていないのに自然なように見せるのが、配信者の前提にある。だからこそ天然をもっている人がウケる。たとえホントの天然でなくても、天然が自然にみえる人がウケる。
論争の際、汲々と反駁したときなどに「おや必死だね」といなされることがある。必死はよく使われる嘲弄の表現であり、必死さは見えてしまうと見苦しいクールorスマートの反義語である。ところがYoutube、Tiktok、SNS、ブログetc、それらのオーナーで、PVや再生をかせごうと必死でない人間など一人も存在しない。
たんなる偶然やふとしたはずみでネットに動画や文をあげることはない。すでに成功した者からじぶんのような無名の者に至るまで、誰もが作為と承認欲をもって投稿するわけである。
だからこそ、どうしても欲しいのが、それをなんの気もなしにやっているのだという自然さである。「おれはなにも期待してはいないよ」というナチュラルor無欲な空気感である。
映画も登場人物の生活環境を自然に見せたい。
コーダは漁師一家の底引き網漁からはじまる。
父と兄とルビー(エミリア・ジョーンズ)が網にかかった魚を選別している。かれらの様子も船もロケーションもそれを日常としている気配=自然さが際立っていた。
率直なところ、リメイクのコーダが海外で絶賛されているのを知ったとき、権利を買い取ったとはいえ、元映画(La Famille Bélier、2014)よりも大きな栄誉に浴しているのが、なんとなく不可解だった。日本には二番煎じという言葉がある。
おそらくコーダはリメイクを二番煎じととらえられないよう、徹底的に、環境や人物のつくり込みをしたはずだった。自然さに腐心したはずだった。その意気込みが冒頭から伝わってきたわけである。
ルビーはちいさな体躯にぶかぶかのマリンフォードをはき、それがルーチンのように高らかに歌っていた。そのはじまりで、彼女が歌がうまいことや生活環境、塵塚の鶴orとびが鷹を生む──物語の概観を察知することができた。自然さに説得力があった。
また、母ジャッキーを演じた聴覚障害者のマーリー・マトリンはシアン・ヘダー監督のオファーにたいして、相手役となる夫をじっさいのろう役者から選ばなければ出演しないと突っぱねたそうだ。
その要求が飲まれTroy Kotsurがえらばれ(男性の)ろう者として初めてオスカーを獲った。
つくり込まれた自然さとほんとのろう者をつかったリアリティ。──外堀から再構築している気配がリメイクの枠を超え、海外での絶賛は頷けるものだった。
映画の核心は歌の才能に自覚のないルビーの自然さだと思う。
前述したとおり、自然さの対義語は作為である。もしルビーが歌がうまいことを自覚し、自己顕示欲をむきだしにしてしまえば、映画の魅力は半減どころか、失われてしまったに違いない。
思春期にある自信のない少女、漁師や荒波の似合わない少女、家族4人中ただひとりの健常者、その境遇がコーダを青天井にドラマチックにしている。琴線をくすぐられた。
漁師の娘事情を描きながら、しっかりコメディもしつつ、弱者(=家族の障がいや家計の苦しさ)をひけらかすことなく、きれいなシンデレラ曲線が描かれる。──もっとも観衆寄りの映画祭サンダンスでの観客賞は当然だろう。
逆境を跳ね返すうつくしい多幸感の映画。
ルビーの夢に寄り添った濃密な2時間だった。
(なお、マイルズくん目当てに合唱部入るときガーティが、
If you start, you know, beatboxing or doing that cup clapping thing, we’re done, yeah?(ボイパとかCupsとかはじめたら絶交だかんね)と釘差したところ、ツボりました。)
余談になるが、かえりみて、成功する人とは、その能力に無自覚なものではなかろうか。
バズりのような得体の知れない名利のために、わたしたちはネット上へ文や動画をあげることがある。
その単なる作為を、野心とか野望のようなものだと勘違いしているふしがある。
しかし夢を追っている人は、作為的ではない。
コーダがかぎりなくさわやかに見えるのは、承認欲まみれの現代人から見てルビーの自然さがうらやましいから──なのかもしれない。なんてね。
自分を愛して信じて生きる
明日も笑顔で生きていこうと思える作品。
聴覚障害をもっているがユーモアのある両親。
周りからバカにされようと、家族が楽しければそれでいいといった仲の良さが伝わってくる。
障害を持っていても明るいところは見習おうと思う。
でも、やっぱり声も歌も聞きたいんだよね。それが、娘だとよっぽど。そんな、少し弱い部分も見せてくれる。
この映画を見て、今までに無いほど綺麗でサラサラな涙が流れた気がする。
真にあいのうた。
昨年度のアカデミー作品賞に輝いた作品。
何故劇場で観に行かなかったのか、、、非常に後悔。
CODAとはChild of Deaf Adultsの略称で、聾者の親に育てられた子供の略。
主人公の少女は家族の中で唯一耳が聞こえるために、いつも通訳をしなくてはいけない。
音楽の道に進みたい気持ちはあるのだが、そもそも家族は音楽そのものを理解できない。
こうした逆境を用意するというのは話作りの基本なのだが、ここまで設定が生きた作品はなかなかない。
非常に演出や役者の演技が素晴らしく、ラストシーンはえも言われぬ感動がこれでもかと押し寄せてくる。
どれだけ嫌いになっても憎もうとも、家族は結局愛を伝えたくなる存在。
このことを如実に体験させてくれる素晴らしい映画。
個人的な満足度は34000円ほど。
旅立ちのとき
「コーダ(coda)」とは聴こえない親を持つ、聴こえる子供をさす言葉だと言う。
ルビーはまさしく「コーダ」である。
だから日常生活の多くを耳の聴こえない両親・兄の通訳者として、
お金のこと、役所のこと、医院の付き添いと、17歳のルビーには荷の重い
過酷な日々。
オマケに早朝から漁の手伝いまで・・・。
この映画は2022年のアカデミー賞作品賞を受賞した映画で、
父親役のトロイ・コッツアーは助演男優賞を受賞した。
トロイ・コッツアーは自身も聾唖の俳優です。
彼無くしてこの映画の成功無し・・・そう思うほど、強烈な印象を
残しました。
本当に今時珍しいほどアクが強く個性的!
一番に胸を打たれたのは、
合唱の発表会でルビーが歌うので聴きに行きます。
合唱が終わりマイルズとのデュエットの途中で、
映画が突然、無音になります。
聾唖の両親には、こんな風に「無音のステージ」なのですね!
まわりが喝采をしてはじめて、娘の歌が素晴らしいことを知るのです。
「聴こえない」ことの切なさを、私も追体験しました。
映画は合唱指導のヴェルナルド先生の強烈に個性も有り、
音楽に溢れた楽しい映画です。
音楽シーン。
オーディションの「青春の光と影」
随分の古い曲をルビーは歌います。
カーペンターズの好きな私はとても懐かしく嬉しかったです。
2番からは会場の両親たちに手話を付けて歌うルビー。
グッと込み上げるシーンでした。
人生のステージに代打の必要な時は必ず来ます。
代打がレギュラーを取って変わることも普通に有りますね。
ルビーが音楽の勉強にボストンへ旅立つことになり・・・
住み慣れた我が家を離れて行きます。
(SEXが大好きなお父さんとお母さん)
その元気があればまだまだ頑張れます。
湿っぽくならずに前向きな素敵な映画でした。
チョッと期待値上げすぎたかな^^;
自宅レイトショーAmazonプライムビデオ『コーダ あいのうた』
話題作ながらコロナ期間でのタイミング悪く劇場鑑賞出来なかった作品
アカデミー賞で、作品・助演男優・脚色賞受賞
耳の聞こえない両親に育てられた娘の家族・仕事・スクールライフの日常を描いた作品
家族の中で、1人だけ健常者の娘の葛藤の描写は絶妙で・・・
ろう者俳優初のオスカー受賞のお父さん役の俳優さんの演技もリアルを超えたリアル
日常描写も生々しく、周囲との壁を感じながらも明るく生きれる理由は”家族愛”
主人公のルビーの歌の才能を見出す先生との関係は、セッションを彷彿とさせるも・・・・
音楽シーンも凄いんだと思ってたので、チョッと期待値下回った感じ^^;;;
ラストの合唱会場でのシーンも家族には娘の声は聞こえないだけに、そういう演出だったんでしょうね。
その部分含めて、配信でも十分伝わってくる良作でした。
確かに畜産より漁業
所々に納得できるところはあった。
家族の職業が変わった事や。
初潮が両親に話になってたり。
村長選が漁業組合になってたり。
ただ、若干エールの最後の歌の方が感動したかと。
説得力があった。
それでもいい
耳が聞こえない家族の中で1人だけ耳が聞こえる女の子がいる家族があった。
その子には、耳が聞こえない家族の為に自分を犠牲にして働く事があったりしていた。
そんな事を兄は、あまりよく思っていなかった。
年頃の女の子ならではの悩みがある中で自分の家族の苦しみを背負って頑張ろうとする少女の姿描かれていた。
耳が聞こえないとハンデは、健常者で到底分かり得ない事かもしれない。
自分が聞こえているから何となく相手に合わせてしまうかもしれない。
それでも自分は、相手の深い所まで近づく事が出来たら嬉しいなと思う。
現実は、なかなか難しいかもしれない。
でも、少しでも相手のことをを思うだけでも違ってくるのかなと感じました。
歌が胸打つ
耳が聴こえない家族の中でただ1人聴くことの出来るルビー。通訳として家族と他の人を繋ぐ役割を小さい頃から自然とやってきた。音楽に出会い、家族が共有出来ないものを目指す。ルビーの発表会を見に行ったあと、歌を手で感じようとする父とのやり取りで号泣した。
手話付きで歌うところも号泣。
どんな家族でも、かけがえのないものにはかわりない。
正直、🎦エールの後に見るのはつらかった・・
リメイクと言う事を考えたら本当はもう少し星を減らした評価となるのが実感。本作品の方を評価する声が高い中、個人的にはかなり首をかしげながら見ていた。特に性文化の描き方がいくらアメリカの片田舎とは言え、あれはない。案の定早々に切り上げた感が強く、あれだったら描かない方がいい。他にもっとルビーの思春期を表現できる方法があったのではないかと思う。脚本でエリック・ラルディゴがそのまま入っているので避けようがなかったのであろう・・・。スランス文化とアメリカ文化が妙な混合を起こし何とも居心地わる感が漂った。選曲にもその辺のちぐはぐ感が付いて回る。本作品はその選曲がかなり偏っている。と言うより選曲センスが決定的に合わない。それが致命的でこの作品を正当に評価できなくなっている。特に最後のシーンはその選曲と言い、謳い上げの描写と言い、圧倒的に🎦エールの方がしっくりくる。まさに感動のエールに身を任せられるのである。本作品には残念ながら・・・共鳴は無かった。
全733件中、221~240件目を表示