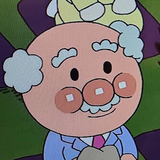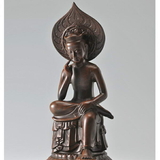ラーゲリより愛を込めてのレビュー・感想・評価
全431件中、401~420件目を表示
後世に伝えるべき愛の実話
歴史の教科書で習ったはずのシベリア抑留をなぜ私は全く記憶してなかったのだろう。データで教えられても実感が湧かなかったからすぐ忘れてしまったかもしれません。
しかし今回この映画で自分と近い年齢の俳優達が極限まで追い込んで、人間模様を中心に描いてくれたので、自分に置き換えて色々考える事が出来たし、ひとたび戦争が起こればこれだけの非人道的で理不尽な事が起こるんだと強く感じ恐怖さえ覚えました。
山本幡男さんを完全無欠のヒーローでは無く、弱さや絶望を抱く姿を描く事で、我々と同じ人間が愛や希望 絆によって強くなれる事を教えて貰った気がします。
後半は原作のタイトルになっている遺書が中心になるのですが、これが実話で有る事に涙が溢れました。
主要キャストの皆さんの演技が素晴らしいのは勿論、捕虜として画面の端に映っている方お一人お一人の演技が素晴らしく、それがこの映画の厚みを出している気がしました。
主題歌Soranjiもこの映画を若い人に観てもらう大きなキッカケになるでしょうし、素直に良い楽曲で最後に救われた気持ちになれました。
戦争体験者が少なくなった今、この奇跡の実話を映画で広く若い人に伝える事は素晴らしいと思います。
この冬泣ける映画
公開のタイミングが悪すぎる
実話が伝える愛の物語
生きる希望
泣きすぎて泣きすぎて。感動しました。
死ぬ覚悟より生きる覚悟を
忘れてはいけない、伝えていかなければならない大切なことを、若い人に人気のあるキャストで映画化することはとても評価したい。ありがたいことである。
最初の夫婦、親子が引き離されるシーン。あの状況で夫を置き去りにしないでしょ。掴みからひっかかったので、ずっと批判的に観てしまった。残念。
多分、脚本が悪いんでしょう。時々演出もよくないんでしょう。
松坂桃李の回想みたいになってるナレーションがあまり生きてこない。
シベリア抑留の希望のなさ、寒さ、飢えがあまり伝わってこない。
獣でなく人間だって訴えるシーンがあったけど、獣扱いされてるシーンが少なくて、なんなら水浴びしたり野球したりしてるシーンの方が長かった。
着ているものがすべて洗い立てみたいにきれいだし、顔も汚れていない。髭は伸びてるけど。
ノートや鉛筆も新品みたい。
南極物語か、犬で泣かさないで。
登場人物が泣きすぎ
いつまでもダラダラ終わらない。映画じゃなくテレビドラマを見ているみたい。最後に伝えたいことがあったんでしょうが、映画はエンドマークでパッと終わって欲しい。
テレビで見た抑留体験者の実録・ドキュメンタリーの方がずっと胸にくるものがあった。
期待が大きかっただけに残念。
劇場から出て来た女性の方たちはみんな目を真っ赤にしてました。
タイトルは「ラーゲリから来た遺書」のままの方がよかったと思う。
間違いなく涙腺崩壊です
二宮くんには泣かされる
人間の醜さを深く掘り下げてこそ、その美しさが際立ったのではないだろうか?
確かに泣ける。
だが、それは、遺書を暗記することによって日本に持ち帰った4人の男たちの熱い思いに胸を打たれたからであって、主人公の生き様に感動したからではない。
主人公が、そこまで仲間から慕われたのは、過酷な状況下でも人間性を失わず、周りの人々に希望を与え続けたからだろう。
とは言うものの、主人公は、上官やロシア兵にあからさまに反抗するだけの無鉄砲な人物にしか見えず、その心の美しさのようなものを実感することはできない。
また、抑留者たちが希望を見い出すシーンとして印象的なのは、皆で野球をするところと、日本との手紙のやり取りが許されるところだが、主人公は、野球をするきっかけは作ったものの、結局、いつものように独房送りにされただけに過ぎない。
皆が、ハンガーストライキをしたり、遺書を暗記したりしてまで主人公を慕う理由が、今一つ腑に落ちないのである。
収容所の過酷さも、劣悪な環境下での重労働ばかりが強調されているが、本当に恐ろしいのは、同じ日本人でありながら、軍隊の階級を笠に着て威張り散らす上官たちや、共産主義教育の名の下に同胞を吊し上げる転向者たちなのではないだろうか?
当たり障りのない娯楽作を目指したためか、そこのところはさらりと触れられているだけだが、人間の持つそうした暗くて重たい側面をしっかりと描いてこそ、主人公の高潔な人間性や希望を失わない精神性が、より明確になったのではないだろうか?
「戦争の酷さ」を描く以上、人間の本性が剥き出しなる戦争の実態を、避けて通ることはできないのではないかと思うのである。
人に勧めたい映画
ただ、生きるだけじゃダメなんだ。
展開が読めてしまうノンフィクション映画の難しさ
見応えあり
全431件中、401~420件目を表示