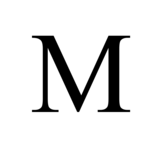ラーゲリより愛を込めてのレビュー・感想・評価
全551件中、221~240件目を表示
構成良し俳優さん良し
お客さんの反応が良かったので観てきました。
まず、ストーリーの構成がうまいなと思いました。予想しやすい展開だけど、それをも気にしない迫真の演技及び伏線の出しかた、回収の仕方。良かったです。最後の遺書のシーンでは、遺書を受け継いだ4人が家に来ますが、4通あった手紙の担当の仕方が良かったです。奥さんを失った相沢さん(桐谷健太)が担当したのは奥さん宛の遺書。お母さんを失った松田さん(松坂桃李)が担当したのはお母さん宛の遺書。主人公(二宮和也)を父のように慕っていた新ちゃん(中島健人)が担当したのは子供たち宛の遺書。そして、上司である原さん(安田顕)が担当したのは冒頭の書き出し部分。これは、遺書を書かせることを決めた原さんだからだと思いました。それぞれ4人の状況に合わせたことで、より深い遺書になりました。とても良かったです。
見たかった映画なので、満足しました。
私たちのお父さん世代は大概、第二次世界大戦に行っています。私の父は衛生兵らしく戦争のことは一言も話しません。義父は暁部隊で全滅した部隊ですが、物資輸送班で崖に落ちて命拾いしたそうです。義父の話では気が狂った兵士は穴に埋められたと話してました。ラーゲリーで亡くなった人を葬るシーンでこうだったと思いました。本当にあった話で山本さんの勇気ある行動は皆と仲間のの絆を深めて最後は涙が止まりませんでした。百歳で亡くなった歌人の母が貸してくれた、シベリア抑留の方の歌集を見せてもらったら、悲惨な毎日を歌にして凄さを感じました。二宮君はじめ、役者の皆さんの演技も素晴らしかった。辺見じゅんさん原作で、車の無い私は1時間に1本のバスに乗ってやっと見ることが出来ました。駅前の映画館は何とか行けますが見たい映画は少ないです。
「希望」を持って生き続ける。
生きろ!それでも生きろ!山本!
2022 No.1涙活映画認定📽
2022年最もあたしの涙腺にインパクトを与えた映画📽予告の段階からこれは泣くやつだよね?ってのはわかっていたけど、泣かせるポイントが正に予想の斜め上を行ってた。「あ〜そっちか〜」的な。
大概、原作のある作品ってタイトル変えると失敗するパターンが多い気がするんだけど、コレに関しては映画版のタイトルを変更してくれたことに完全に感謝の念しかない。原作そのままだったらネタバレもいいとこwww
戦争って多かれ少なかれ人の精神を壊すものなんだろうけど、そんな中でも理性ある人間らしさを忘れない山本さんの人としての魅力と、理不尽な捕虜生活の中で本能的な人間らしさ剝き出しになっている周りの人達の対比が見事でした。
ラスト20分は涙腺崩壊ゾーン。覚悟して観るように。
反動の日本兵は、シベリアの土となれ
不戦の誓い、新たに
太平洋戦争の敗戦を契機として、旧日本軍は解体され、新たな戦後の体制が築かれた。戦力の不保持を明記した日本国憲法もその一つである。憲法9条があっても敵国からの攻撃は防げないという主張もあるようだが、国家権力が自ら戦争を他国にふっかけることを制限する必要性はある。これこそ、先の大戦からの教訓である。防衛力強化を進める動きもあるようだが、専守防衛の原則に照らし、判断してもらいたい。
上記のごとく、講釈を垂れてみたが、今作では、旧ソ連のシベリアに抑留された旧日本軍兵士の過酷な生活が描かれた。加えて、兵士という職業の過酷さを思い知らされた。兵士が敵国民を殺す場面があったが、殺される方はもちろん、殺す方(兵士)もまた堪え難い精神的な苦痛を強いられることがよくわかった。戦争があらゆる人間を狂わせてしまうということについて、現代の権力者は自覚的であってほしい。また、前線に立つのは若者である。権力者は戦争が若者を捨て駒のごとく酷使する行いであるということにも思いを致してほしい。
むごたらしい戦争は決して起こしてはならない。人間の幸福追求を制限するからだ。一度始めた戦争は、なかなかやめることができない。戦争が終わっても理不尽な状況に置かれた兵士が多数存在していたことが十分それを主張する根拠となりうる。凡人が戦争の最中に希望を感じることは難しく、絶望を味わうことの方がずっと多いはずだ。
しかし、主人公・山本は、シベリアに抑留されてもなお、自ら希望を捨てることなく、また、日本に残した家族らの幸福を願い続けた。なかなか真似できるものではない。彼が希望を持ち続けたからこそ、救われた人々もいる。山本の周囲で共に暮らす兵士たちにも注目しながら鑑賞してほしい。
学校の先生お勧め映画
今もすぐそこで行われてる事
人を思いやる気持ちは人を支えて人を変える
戦争とは人間を捨てること
ならず者国家がウクライナに攻めてからもうすぐ1年が経とうとしている今、日本も台湾有事などが取り上げられるようになった今こそ、見るべき映画です。
いつ隣国から自衛隊基地を潰しに来るかわからないからのもありますが、1人の日本人として知っておく事実もたくさんありました。
この映画で私自身が受け取ったメッセージとしては
①戦争とは人間を捨てること
ニュースだけを見ていると、領土の奪い合いにしか見えない戦争だが、そこに関わっている一人一人は「人間」であることを忘れてはいけない。誰かの子どもであり、親であり、家族がいること。先人たちの「戦争は絶対に起こしてはいけない」という思いは人が死ぬことの残酷さだけではなく、人が「人間」らしさを捨てなければいけない苛虐的な残忍さこそが戦争をしてはいけない本当の意味ではないのか、考えさせられました。
②言葉とは思いを伝えるためにある
この作品とみるとなぜ言葉が存在するのか分かるような気がする。もちろんコミュニケーションだと謳う人も多い。それでも人に思いを伝えること、生きていた証を残すことも言葉の役割ではないか実感する。生きるとはどういうことなのかそれぞれ映画を見て考えて欲しい。
③「当たり前」は当たり前ではない
私たちは毎日「家」という帰る場所があり、美味しいご飯、兵器が飛び交うことのない綺麗な空があるのは本当に幸せなことなんだと再確認できた。いつ「日常」が壊れるか分からない。だからこそ周りの人たち、家族、そして環境に感謝しようと思える素晴らしい作品だった。人間生きているだけで偉いという言葉はわりかし間違ってはいないと思う。生きているだけで家族に安堵を与えることは常に誰かのために生きているに等しいのはないか。だからこそ1人1人の命の尊さを忘れてはいけない。
クリスマスイブの報道特集にウクライナの子どもたちがサンタさんにお願いするドキュメンタリーがあったが、日本の子どもたちのようにゲームや本ではなく、「世界平和」と書いている子どもがほとんどでした。戦争という人間の汚い部分を純粋な時期に見てはいけないはずなのに苦しんでいる子どもがたくさんいました。日本もいつ戦争に巻き込まれるか分かりません。だからこそ多くの人たちに見て欲しい、そんな作品でした。
どこにぶつけたら
事実に遥かに届かぬ凡作
映画鑑賞後に原作を読んで、評価が変わりました。
最初星1個だったけど。
山本幡男という人の存在、その人格と精神と行動の一端を、この映画を見たことで知ることができるということが何より重要かもと思ったからです。
実際、あの手紙の場面、演じている俳優の皆さんは真剣そのものだったし、当然作り手も、それを少しでも良い形で届けようと全力を傾けていたはず。
そして、それには確かに胸を打たれたので。
それは手紙の文章そのものの力だって最初のレビューには書いて、それはそうかもしれないけど、この映画のその場面を見て感じるものがあったからこそ、原作を手に取ったわけなので。
以下がそのレビューで、まあめちゃくちゃけなしてて、確かに今でもそんなにいい映画とは思えないんだけど、、山本幡男という人をここまでメジャーな作品にして世に出してくれた作り手の人たちを、尊敬を持って讃えざるを得ないと、原作を読み終えた今は感じています。
しかしそれにしても、アムール句会の話は、ちゃんと入れて欲しかったなあ!!
+++++
現代の普通のドラマを撮ることを生業にした人が、シベリア抑留の収容所についていろいろ調べた上で、極めて表面的に再現し、物語は想像力で補って、形にしたという感じ。
しかしその想像力が、全く足りてないという印象で・・・。
作り手の教養が、主人公であるその人に遠く及ばないのだと思う。
たがらそもそもこのスタッフで、ちゃんとリアリティのある映画にするのは無理だっだんだろう。
実物を引用していると思われる手紙の文章だけが、突出して素晴らしくて、その場面だけ突然に胸に迫ってくる。
その場面というか、文章が、かな。
それ以外はなんというか、、下手な学生劇団の芝居を見てる気がした。
思いつきで作ったような薄っぺらい場面で満たされたシナリオと、全くリアルさを感じない、安っぽくて軽いセリフを並べた脚本。
こんなので感動しちゃうってのは、ちょっとどうなんだろう?
客席でもところどころですすり泣きが聞こえて、マジかよ!って思った。
あまり映画見てない人たちなのかな。
もっとちゃんとした映画見た方がいいんじゃないだろうか。
まあ感動するのは勝手だけど。
なんかこの題材が、こんな映画にしかならないのが残念だ。
二宮和也や北川景子は魅力ある演者だと思うし、その他のちょい役の脇役にも何人か素晴らしい人がいて、、しかしこの映画は彼らのしっかりした存在感に見合う作品では全くなかったと思う。
低評価民の言いたいことも分かるが…
確かに収容所のセットは納得いく物ではないかもしれないし、水浴びを許可された時に魚を獲る中島健人の裸体はパン1枚で生きてる人間には程遠くて、そこら辺のリアリティは詰めきれてないかもしれん。
だけれども、それを大いに覆せる「内容」が確かにあった。
低評価民は、ほぼ皆セットの事ばかりを気にしているが、俺個人としてはそんなことどうでも良くなるくらい内容良くて泣いたよ。
俺ここ5年くらい創作物で泣いてないのに…やられたわ…
こんなに映画で泣いたのは初めてです
こんなに映画で泣いたの初めてでした。
本当に苦しくて悲しくてでも希望を信じて、家族に会いたくて頑張る山本さんや周りの仲間たち。本当に感動でしかないです。
山本さんがいたから周りの仲間たちの考えも沢山変わっていったんだと思います。
松田さんが山本さんを大きな病院で見てもらいたいのでストライキするというシーンみんなが団結していて山本さんへの愛を感じましたし、感動できました。
終盤の山本さんがガンとわかった時から涙が止まらなかったです。がんを打ち明けるシーンで相澤さんは初めは怖いし嫌な人だと思っていたけど、本当は優しい人だったのかなとも思えるシーンでした。あの時のセリフが頭から離れません。
家族に会えずに死ぬ事がどれだけ辛いか、想像しただけで胸が痛くなり号泣しました。
終盤の山本さんの死を知ったモジミさんが号泣するシーンが1番泣けました。
奥智哉くん目当てで見に行きましたが、本当に見てよかったし、みんなに見てほしいと思える映画でした。
2回見ました本当に2回目だと視点が変わってきたり、最初の山本さんと家族が別れて『またすぐ会える』と言ったのが、ああこれが最後だったんだなと思うと悲しかったです。
また、セリフの意味を考えたりして勉強になったし、1番最後の山本さんが『家族みんなでこうして集まれる日』と言っていたシーンあたりで今ある生活の幸せを知りました。
あまり良いレビューをしていない人もいますが、私はとっっても良かったと思います!純粋に感動できました。チープだったとかキャストミスとか言ってる人もいますが私は全然気になりませんでした、、、まあ気になる人もいるのかもしれませんが。文句を言ってる人達はかなり厳しい人達なんですね、別に演技は下手では無いし良かったと思います、、、というか二宮和也さんは本当に演技が上手くてハズレがないなと思いましたし、北川景子さん、桐谷健太さん、松坂桃李さん、安田顕さん、中島健人さんの演技が本当に良かったです、映画に入り込めました。
素敵な作品をありがとうございます!人生で1番見てよかった映画だと私は感じました。
そして主題歌のsoranjiにも泣きました泣
毎日聴いてます、、、歌詞を聞くと映画を思い出して泣きそうになります。
タイトルなし(ネタバレ)
太平洋戦争の最末期、ソ連は日ソ中立条約を一方的に破棄し、満州に攻め込んできた。
終結後、現地にいた日本軍人たちは、シベリアの強制収容所において強制労働をさせられることになった。
ロシア文学を専攻し、ロシア語が堪能な山本幡男一等兵(二宮和也)もその一人であった。
戦争終結後、捕虜を抑留することは国際法違反のなか、山本らはわずかな食糧を頼りに、極寒での強制労働を強いられていたが、そんな日々にあっても山本は希望を捨てなかった・・・
といった物語。
シベリア抑留についての映画はかなり珍しく、わたしの記憶の中でも観た覚えがありません。
なので、若い人の多くはそのような事実をあまり知らないかもしれません。
映画は、強制労働の中での日々を丹念に描き、日本人捕虜たちの間に残る旧軍時代の階級制問題なども丹念に描いていきます。
国内で撮ったであろうけれど、雪中の映像も多く、過酷な撮影だったかもしれません。
山本以外にも魅力的な人物は登場します。
自分を卑怯者といって憚らない松田(松坂桃李)―彼が狂言回し的役割を担っています。
軍人気質が抜けない相沢(桐谷健太)。
軍人ではなく一介の漁師の倅でありながら漁中に拿捕されスパイ容疑を掛けられて抑留されている青年・青年(中島健人)。
元慶応野球部の4番、山本の先輩であり、山本をロシア文学の道へ誘った原(安田顕)。
それぞれに印象深いエピソードが描かれます。
そしてクライマックスは、故郷日本への帰還となるわけですが、山本は重篤な病に斃れてしまいます。
この展開がこの映画の良いところで、タイトルにあるとおり、山本はひと足早く先に日本に帰郷した家族へ向けて「愛」を残します。
斃れた山本の言葉を帰還した4人が家族に伝える・・・
派手な戦闘シーンはほとんどない映画ですが、普遍的で普通の美しい心・思いを儚くしてしまう、それが戦争だと改めて感じました。
<追記>
戦死した戦友の声を届ける映画には、今井正監督、渥美清主演『あゝ声なき友』があります。
未見なので、観てみたいですね。
昭和47年公開作品なので、まだまだ生々しい戦争の傷跡が記憶にも、実際の風景にも残っていたものと思われます。
全551件中、221~240件目を表示