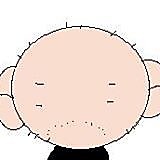土を喰らう十二ヵ月のレビュー・感想・評価
全125件中、1~20件目を表示
オーガニック幻想論
ハッキリとは覚えていないが、この作品の予告編が松竹系の劇場で流れ始めたのはコロナが始まる前後辺りだったと思う。途中で撮影が止まったりしていたのかも知れないが、公開まで随分かかったという印象が強い。
13年ほど前に妻を亡くした作家のツトムは信州の山里の村に住み、畑の野菜や山で採れた山菜などを自らの手で調理して食べ、その様子をエッセイとしてまとめている。時折り訪れる、娘ほどの歳の編集者のマチコとは恋人の関係で、作った料理を一緒に食べることがツトムにとって至福の時間になっている……。
原案は水上勉の随筆。年始から年末までの一年間を歳時記に沿ってすべて手作りの旬の料理を食べていく生活は、半世紀くらい前までは日本のあちこちで普通に見られた姿であろう。祖母が梅干しを干したり、祖父が白菜を何樽もつけたりしている姿は、子ども時代の自分にとっては当たり前の光景だった。
巷ではヴィーガンが大流行りで、スローライフに憧れ、自給自足の生活を夢見る人は決して少なくはないと思う。実際、劇中に登場する(土井善晴の手による)素朴な料理はどれも美味しそう。
で、お前はそんな生活を送りたいか?と問われたら、休暇で気分転換に1日か2日するのはいいけれど、年間を通して毎日は絶対に嫌。なんだかんだで利便性を享受したいというのが、意識低い系の個人としての本音。
実際、ウチの人間には優しいがソトの人間には冷たいムラ社会からどんどん逃げ出していったのが、この半世紀だろう。幻想論・理想論ではなく、いったいどれだけの人がそんなところに戻りたいのだろうか?でも、ムラ社会のメンタリティは、現代社会の中に、いまだに色濃く染み付いているんだけどね……。
年の離れた恋人
あの沢田研二が山暮らしの親父役を演じるとは!
沢田研二は、二枚目の歌手のイメージしかなかったので、白髪で腹が出た姿が意外だった。しかし、料理は手慣れたもので、日頃から料理していることが伺い知れる。
冒頭、軽快なジャズの音楽で始まる。東京から来る編集者かつ恋人・真知子の訪れは、このジャズのように心躍るものだったに違いない。真知子が里芋や筍など、旬な野菜を頬張っている様は、本当においしそうで、よだれが出そうになる。
映画の中で出てくる料理は、どれも素材を活かしてシンプル。白ごはんと沢庵と味噌汁の朝ごはん、焼いた山菜に味噌をつけて食べる、これだけで充分なんだよな、と思う。都会に住んでいると食べ物が溢れていて、食材のありがたみを忘れしまっている。
信州の山奥で、四季折々の野菜を山で獲ったり、畑で育てたり…自然と共に生きる生活に憧れるものの、雪で閉ざされた冬はとても厳しくて、私にはできそうにない。だけど、このような穏やかな生活をしてみたいなぁ、と心から思う。
あるがままの死
どうりで編集者役の松たか子が「ツトムさん、ツトムさん」と作家役の沢田研二をなれなれしく呼ぶと思ったら、この映画ベストセラー作家水上勉の『土を喰らう日々』が原作だったのである。同作家原作、川島雄三監督の怪作『雁の寺』を以前拝見した時に、水上が幼き頃口減らしのため寺の小僧に出されトラウマをかかえさせられた事実を知っていた私。本作は、水上がその寺を13才で脱走するまでに、厳しい和尚さんから学んだ四季折々の精進料理をもてなす様子が、ツトムんの死生観とともに語られる禅問答なのである。
水上は軽井沢で原作小説を認めたというが、心筋梗塞を患い移住した長野の小村が映画の舞台となっている。奥さんを亡くして13年、未だに自宅に遺骨を置いているツトムさんには、マチコさん(松たか子)という担当編集者兼恋人がいる。蕨に筍、紫蘇と梅干し、ほんれん草や大根、なすにキュウリ。自宅の畑や近くの森林から収穫した食材を、沢田研二に吹き替えなしで調理させているらしい。その料理監修は土井善晴が担当している。
中江裕司監督が土井に監修をお願いしにいった時「どの程度本気なんですか?」と逆に突っ込まれ、なかなか監修を引き受けてもらえなかったのだとか。どうせだったら、半分タレントのような仕事をしている土井をカメオ出演させるぐらいの“遊び”があってもよかったと思うのだが、とってもマジな土井先生「料理は器が命」とばかりに入れ物にも相当こだわったそうなのだ。そのせいかツトムさんの作る素朴な素人精進料理と豪華な器の組み合わせが、かなりアンバランスに見えてしまうである。
肝心の沢田研二の料理の腕前は、シロさんには遠く及ばず、見た目にも普段やってない観丸だしだった。が、食い専門のマチコを演じた松たか子はあえてその料理の腕前を封印したそうなのである。まあ実際作家先生の腕前も、ちょい役で登場している檀ふみのお父さんに比べれば月とすっぽん、沢田研二と大差はなかったのかもしれない。時折小説に書かれているであろう文言を、沢田自らが読み上げる禅問答が、むしろこの映画の白眉といえるだろう。
「あるがままの死がわからぬゆえ、一度死んでみることにした」それは恋人マチコさんとの別離によるボッチ生活であり、一人で生まれ一人で死ぬ人間本来の姿にたち戻る、ということだったのではないだろうか。「身体を動かせば腹が減り、腹が減れば飯が美味しい」こんな単純な生活習慣が、今の日本人からすっかり失われてしまっている現状をご覧になったら水上勉はどう思ったことだろう。完全自給自足とはいわないまでも、せめて外食やコンビニ弁当は週半分にして、残り半分自炊で旬の“土”を味わいたいものである。
お料理映画なので
やはりお料理そのものが美味しそうに見えないといけないです。
囲炉裏を囲んで漬け物つまみつつ日本酒をいただくシーンは、自分もしたいと思いました。
主人公の生活を丁寧に描いていてよいのですが、若い恋人がいる設定がいまいちピンとこなかった。
一緒に見た人は松たか子のことを「亡くなった奥さんの連れ子??」と思っていたようです。
当初の予定通り、志村けんさんが主演ならしっくりきていたのかもしれません。
素朴で素敵な暮らしです
私は施設で働いているのだが、ほぼ寝たきりの老女がいる。壁には若かりし頃のジュリーの写真が貼ってある。
老女のケアをする時はジュリーの話を振る。映画好きの私「いま彼の映画やってるんですよ」老女「見てきて」
…老女の楽しみの為に、まぁ私も興味はあったから早速映画館へ。
こんな生活力のある男性素敵じゃないですか!土間・囲炉裏の設えられた古民家で彼女を手作りの料理でもてなす。滋養たっぷり!&酒。私にはインスタレーションアートです。どんな旅館より最高ー。
ジュリーのどアップ数秒間は凄みがあった。これを見て何を思えば良いのだろう…と思いながらも目をそらさず。壁の写真と違いすぎる。…成長したのだなぁ!
後日、映画を大絶賛して老女に伝えた。ジュリーがとっても素敵だとも。彼女の目はキラキラ輝き、私は映画を見て良かったなぁ、とホッとしたのだ。
筍と木の芽
老人版「リトル・フォレスト」
レンタルビデオで視聴。
沢田研二演じる老作家ツトムのある1年を、食を通して描くというコンセプトは、老人版「リトル・フォレスト」という感じ。もしくはリトル~の方が原作となる水上勉の料理エッセイに影響を受けている可能性もあるけど。
ここ何年かの流行として、洋の東西を問わず老いや死について描く「老人エンターテイメント」的作品が増えている印象だけど、本作もその系譜にあって、前半では食=生をメインに描き、中盤のツトムが心筋梗塞で倒れてからは老い=死が物語を侵食し、そしてラストは再び食=生で〆るという構成になっていて、これは若い人にはピンとこないだろうと。
逆に人生を重ねた中高年には、土井善晴が手掛けた劇中の素朴な料理やツトムの生活も含め、メッチャ刺さるんじゃないかな。里山で採れた山菜の味同様、年を重ねないと理解できない世界もあって、本作はそれを描いているのだと思う。
ただ、劇中で描かれるツトムと編集者で恋人の真知子との関係や距離感が、島耕作的なというかお爺ちゃんの妄想っぽくて、いくら沢田研二とはいえやや気持ち悪さを感じた。
沢田研二の演技に脱帽
ついに200作目。CSで視聴した。
水上勉の原作を映画化したものだが、食への
思いが伝わった。
沢田研二の演技に脱帽。ここまで上手いとは驚いた。
ただ、ストーリーは以外と平凡。
食とは何か考えてみたくなる作品。
「太陽を盗んだ男」から「土を喰らう男」へ‼️
持ってる価値観で感想が変わりそうだが…
タイトル、あらすじから察すれば、噛み合わない観客が観に来る要素少ない。
観ている観客もそれなりに満足そうに帰っていく。「良かったなぁ…」と家族、友人と言い合いながら退場していく。こういう作品を私はよい作品としている。
映画を不特定多数と集まって観るとこう言う要素が加味されて新鮮だったり共感出来たりする。
勿論、前の席のヤツが…とか周りかうるさかった…食べ物が、香水が臭かった…ネタバレし始めた…等色々あるかもしれないが、それもこの間の作品を観に行った記憶として、映画体験として残っていく思い出だと思う。
さて作品についてだが、極めて簡素で地味な雰囲気が全編に渡って続く。
庭の畑や近隣でとれる産物で日々を暮らしている様子が伝わってくる。
山菜に根菜、ぬか漬け、梅干しとか派手さはないが食べたくなる。
器用な物書きジュリーとその彼女松たか子のヘンテコな関係がどうなるのか?とヒヤヒヤしているとやはり…。
人間独りが良いとか言い出したら、最後はだいたい想像つくもんだな。
死んでみると寝ている姿を見ると“人間人生1/3は寝てるから1/3死んでるようなもんだろ?”とは思う。
しかしながら、このおじさんの真似をするのは大変だから、明日からの食事だけちょっと変えたい気分になった。
影響受けやすい自分に笑う。
四季に食べれるものを作って、取って、食べる。素朴な料理だけど、どれ...
生きることと食べることと、そして輪廻
<映画のことば>
人間は不思議な動物で、匂いや味覚で、とんてもない暦の引出しが開く。
口に入れるものが土から出た以上、心深く、暦を経て土地の絆が味覚に絡みついている。
いうまでもなく、人間の体は口から入ったものから出来上がっている訳ですし(ごく一部の栄養素を除いて、人間が自分の体内で生成することはできないらしい)。
そして、本作からは、その人間が口に入れる素材の多くが土から生まれること、そして土から生まれた素材の「素朴さ」「自然さ」を大切にすることの「本物の豊かさ」をたっぷりと教えてもらうことができたように思います。
亜熱帯から温帯、そして亜寒帯と、幅広い気候帯にに属する日本は、春夏秋冬の季節の移り変と、わりがハッキリとしていて、その季節ごと季節ごとの食材の豊かさにも、心を奪われます。
改めて「生きることは食べること」なのであり、「食べることは生きること」なのだという思いをいっそう強く感じました。
本作を観て。評論子は。
同じく料理を素材とする作品として、他作『大統領の料理人』を同時期に観たのは、ほんのたまたまなのですけれども。
同作にたくさん登場する美味しそうな料理とはまた違った「素朴さの豊かさ」みたいなことを味わうことができたことは、幸いだったと思います。映画ファンとしての評論子としては。
「100年フード」を始めとして、食文化の振興に旗を振っている文化庁が配給会社とタイアップしたということで、公共施設等に大々的にボスターが張り出されたりした作品なので、「どんなものだろう」と食指が動いて鑑賞してみることにした一本でした。
文化庁の能書き(ウェブサイト)では、「今回のタイアップを通じて、我が国の豊かな食文化への理解と関心が深まり、四季の食文化を体験するために各地域へ足を運ぶ機会が増えるなど、食文化がより身近なものとなることを期待しています。」とされていたものです。
まずまずの佳作であったと思います。評論子は。
(追記)
邦題は「土」にかかわる事柄で、文字どおり土から産み出される食材の話なのですけれども。
しかし、本作でもツトムが急病で生死の境をさまよいましたが、その土から産み出される食べ物を食べる人間も、行く行くは土に還っていく存在です。
その輪廻を本作から感じ取ったレビュアー諸氏も少なくなかったようですが、評論子も、まったく同じ感慨です。
<映画のことば>
生活することは体を使うことで、体を使えば腹も減る。腹が減れば、メシもうまい!
空腹が何よりの調味料であることは、時代の古今、洋の東西を問わないのだろうと思いました。
全125件中、1~20件目を表示