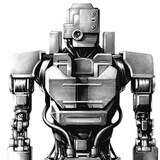アリスとテレスのまぼろし工場のレビュー・感想・評価
全89件中、61~80件目を表示
アリスもテレスも出てこない懐かしきセカイ系
CITY HUNTERを観賞後に暇だったので観賞。
なので一切の前知識を入れずに観た。
人ではなく街全体が転移、現実で言う神隠しにあったという物語。
物語が進むにつれ、思春期の少年たちの恋模様や謎の少女の登場
それは彼らの住む街に起きた出来事が明らかになっていく。
見ていて正に感じたのはノスタルジック感である。
エヴァ、ラーゼフォン、最終兵器彼女、イリヤなどなど
学生時代に大流行したセカイ系に触れていた世代としてはその独特な雰囲気に面白さというよりも懐かしさを感じた。
自分たちの世界よりも少女の未来のために動くその様は正に青春セカイ系である。
ただ、食料とかどーしてんだろ?
というどうでもいい事が頭を過り
キャラクターの動きや演出にある生々しいエロティックな雰囲気が気になった。
正直、今観賞した直後なのだが
「面白かった〜」
というよりも
「懐かしかったな…」
の感情が勝っている。
1週間後にどうなっているかが、私にとって真の感想を言える時なのかもしれない。
この映画は生煮えで食べられない
映画にとって長いこと・多いことは損なことがよくわかる映画。上映時間を今の2/3にしたらもっと見られるものになる。
長所:
・「佐上」。ゆでガエル状況で権力を握ったのは、普段さえないASDのゲイだった。
・90年代の田舎の雰囲気をよく再現している。肝試し時の私服、ゲームセンター入口のテーブル周りは必見
短所:
・編集。場面ごとにいらないカットが多すぎて間延びしている。特に終盤のカーチェイスは、尺が長いわりにプロットへはほとんど影響がなく、時間が経つにつれて緊張感がなくなっていくだけ。観客の知っている情報を何度も出さなくてよい。
・多すぎるキャラクター。主人公の男友人カルテット(この時点で多い。トリオで十分)、それに同じ数の女同級生、多数の製鉄所関係者に家族周りに周囲の民間人と、2時間恋愛映画でこの人数をさばききるのは至難の業。結局、終盤になると突拍子もなく怪物に食われて人数が減っていく。本当はサメ映画だったのか?
・主人公の魅力のなさ。今時ちょっと口調が荒いだけのナードじゃ、なぜヒロインたちからモテているのかよくわからない。少なくとももっとイケメンにできなかったのか。にしても、顔について褒めている場面はなかった。
総評:
実在しない1クールアニメをそのまま繋げた劇場版という風情。1900-2000円/人の価値はない。
ひっくり返ず!
異世界からの脱出劇であり、異世界の人々の生活劇であり、恋愛劇であり、
そんなをまぜこぜにした作品。
色んな映画作品で、主人公が異世界からの脱出とか、別に、主人公以外の脱出、それだけの話しのものは多くあるけど、
この作品の様に脱出しない、いわばそこに残った住民を焦点にして話しが進むストーリーは珍しい。又、その世界が………の想像から作り出した世界。目先を変えれば悲しい想像世界での物語。
……これだけ盛った設定のストーリーと脚本を作った人、映画にするのに大分苦労したと思う。(舞台が単に鉄鋼所のある町ではなくアニメで鉄鋼所自体をメインにしたのも斬新だった。又、色んな理由つけての異世界?ではなくスムーズに設定している。)
面白かったです。
……ただ、最後の…と父母の再開のシーンを
出していないのは何か理由があったのですか?なにかの狙いですか?
出していれば大分感動的に締めくくれたとおもいますが。
幻の世界と少し先の未来。
幻の町と実在する街の話。
製鉄所のある街見伏、ある日の夜、爆発事故が…その製鉄所の爆発事故から別の世界へ行(逝)ってしまった正宗と町の住人達のストーリー。
いつも親しくしてもらってるレビュアーさんのアドバイスと、他のレビュアーさんのレビュータイトルを見てこの作品はちゃんと観ないと分かりにくい作品なんだなと思い、ガッツリ目を見開いて鑑賞(笑)
ここから書く感想は自分なりの解釈、自分の勝手な解釈で泣けた…
製鉄所の爆発事故で製鉄所周辺?町全体が壊滅。爆発事故に気づき窓を開けた正宗…その後に別の世界(亡くなってしまった世界)に…
学校で嫌いとは裏腹、佐上睦美に製鉄所へ連れてかれる…
その製鉄所で狼少女五美と正宗を会わせる。睦美は既にその狼少女五美を自分の娘と気づいてるし、ひび割れた隙間の世界から旦那の姿は確認して分かっているから正宗を会わせた…
少し未来、祭りのある日の夜、存在してた五美は両親の言う事を聴かず何らかのきっかけで存在しない町、見伏へ…
ストーリーが進みにつれ壊滅した町、見伏のカラクリに気づき正宗、睦美と仲間達は存在しない町から存在する街へ送り帰そうと…。
こんな感じで解釈してしまったけど正解は分からない…分からないけど勝手な解釈で何か泣けた。
頭で思ってる事が上手く書けない。
ちょっと理解しにくい感じの作品だけど雰囲気は良かった。
追記
下書き保存出来る様にして…
一発目に書いたレビューもっと細かくかいたんだけど消えちゃった…なのでザックリな感じに。(妥協)
ちょっと引く
岡田磨里さんの映画は前作も素晴らしかったので今回も楽しみにしていた。中学生の繊細な心模様を丁寧に描いていて、いいなと思っていたら、途中でドン引きな事実が明らかになる。
イツミが登場して、知的障害児かと思ったら、ネグレクトされて知能の発達が遅れている子だった。しかもヒロインのムツミがネグレクトしているのが原因で残酷すぎる。相当な長い年月のネグレクトだ。その間ちょっとも心を通わせようとしていない。かわいそうだ。しかし、ムツミも中学生で役割を押し付けられたヤングケアラーだ。彼女の責任じゃないけど、彼女が暗いのは、それは心を病むだろうと納得する。イツミとムツミに対して厳しすぎる。ムツミの父親は頭がおかしいのでどうしようもないけど、主人公の父親やおじさんは近くで知っていたのに放置している。ダメだ。ふざけないで欲しい。
工場の爆発で、現実世界と切り離された幻の世界に生きているとのことだけど、今一つピンと来ない。なんだよ狼って、なんでそんなのが存在して機能しているのか、腑に落ちない。独自ルールが過ぎている。
日産PAOのマニュアル車、かっこいい。時代が90年代なのは、現実世界とのギャップから逆算して設定したのかな。
よかった
•最初訳が分からなくて少し退屈だったけど一気に面白くなった!
•最後展開読めたけど泣けてきた!最後の言い合いは予想できなかったけど
•何でもできると思って生きていきたい!
エッグ・コーヒー
ミルクセーキみたいなもんかと思ったら、ベトナムコーヒーのコンデンスミルクに卵黄を入れて攪拌したものを上に乗せるという飲み物らしい コーヒーに直接生卵をぶち込むイメージを始めに想像していたので、何にせよ"ネーミング"って大事だなと思った次第
さて、本作題名だが、アリスやテレスなんて名前の対象物や者は出てこない これが、上段のエッグコーヒーの件と関連付けた 題名だけみて映画の内容を想像するなということ 勿論、アリストテレスというギリシャ哲学者の格言が台詞であるが、自分はその方面が全く無見識なので、その影響も感想に取り入れられない あくまでストーリーと作画の感想のみである
プロットとしては時間固定(1日が繰り返されるが季節や身体の成長・変化は進まない)中での閉塞感をベースにした青春ストーリーといったところだろう 『あの花』からの一連の私小説的作劇の監督なのだからその辺りは又新たなアイデアを織込んだ構成になっている
但し、物語展開が困難を極める流れになっているのが腑に落ちないのである 多分、この順序は、テレビアニメで10話程分ならば順当な進め方であろう それを映画で、しかも実世界と勘違いさせる構成にしたのかが、中々のクセモノである チャレンジングなことは大いに評価したいのだが、観客への信頼感が過度なのではと疑ってしまうのだ 登場人物の秘密位のレベルならば引っ張っても世界観は揺るがないが、そもそもの設定自体が後ろに押してしまうと、物語に感情移入する時間を削がれるのではと思うのだが・・・ そして後回しになった分、監督御得意のクライマックスの高揚感も、上手に演出できていないのかなと感じてしまうのである
オオカミ少女、失神ごっこ、高いところの飛び降り、等々伏線の回収とクライマックスの混ぜ込みは、かなりの理解力速度を要求されてしまう
核心的ではなく、メタファー的な湾曲表現で語られるが、父親と娘の恋愛要素、それに伴う母親の嫉妬 又は狭い世界での恋慕とかのやや倫理観を揺さぶるストーリーは、監督独自の谷崎史観に基づいた設定でそれ自体は面白い挑戦的内容であるので、そこは応援したいし共感を大いに持つ 特に、キスシーンの歯がぶつかる音はアニメではなかなか描かれない希有なシーンであろう
監督が試してみたいという強い意志を伝える作劇として、大いに称賛したいのだが、今回は自分の読解力の無さ故、申し訳ない批評になってしまった事を恥じる
全編からにおい立つ猛烈な「岡田麿里」臭。出来不出来を超越した「個性」にただひれ伏す。
青くさい。
生理くさい。
露悪的で、挑発的。
とにかく「岡田麿里」の臭気が凄い。
むんむんに漂っている。
アニメーションという、特異なメディアにおいて、
絵コンテもひかず、一枚の絵も描かず、
ただ脚本しか書いていない監督の体臭が、
ここまで濃密に作品全体を汚染しているってのは、
やはりただごとではない。
ふつうじゃない。
絵は描けなくても、
絵コンテは人任せでも、
ここまで「作りたい作品が作れる」。
ここまで極私的で、独善的で、セルフメイドな代物を、
何百人ものスタッフをこき使って、人に絵を描かせて、ちゃんと形にできる。
僕は、岡田麿里って人は、本当に恐ろしいクリエイターだと思う。
― ― ― ―
彼女が『さよならの朝に約束の花をかざろう』を発表したときは、心底驚いた。
僕の知る限り、アニメ業界で「脚本」から「監督」に成り上がったのは、この人が初めてだったからだ。
たいていの監督は、作画マンか制作進行から演出を経て出世する。大地丙太郎のように撮影あがりの人もいるが、彼も結局は制作進行と演出を経験している。マッチ棒人間でもいいから、絵コンテを描く。ここがこなせない監督というのは、通例いないのではないか。
ところが、岡田麿里は、脚本からマジで監督に上り詰めた。
それは、逆に言えば、本当に凄いことなのだと思う。
一流の演出家と作画マンが「それでもこの人のホンで、この人の指導のもとでアニメを作りたい」と一堂に集ってくれたということなのだから。
スタジオやプロデューサーが、たとえ絵コンテなんか切れなくても、この人ならアニメ監督が出来ると太鼓判を押したということなのだから。
要するに、岡田麿里は、圧倒的な「書く」才能で、「描く」業界を調伏してみせたのだ。
そして、ふたたび彼女は監督として降臨した。
2作目が許されたということは、間違いなく、皆が彼女を監督として認めたということだ。
僕は、そんな岡田麿里を無条件に尊敬する。
― ― ― ―
岡田麿里には、クセがある。
濃密で、濃厚な。
それは、「青春」を描くときに、とくにあらわになる。
生臭さと、女臭さと、精液臭さ。
誰かに傷つけられる痛みと、
誰かを傷つけることを厭わないエゴと。
そのやりくちは半ば露悪的で、若干痛々しい。
でも、脚本家自身の空回りや、あてつけがましさや、うざい自意識過剰ぶりもひっくるめて、やがては圧倒的な「個性」のなかに、視聴者を巻き込んでゆく。
最初は半笑いで岡田麿里の奇行とやりすぎをドン引きしながら観ていても、そのうち観客の多くは作品世界に引き込まれ、羞恥を覚えながらも固唾をのんで見守るようになる。
本作でいえば、やはり五実(「ゴミ」とも読めるのはなんとも)に顔を舐められるシーンと、睦実(六つの罪なんだね)との終盤の濃密なキスシーン。
あの、「キャ―――」ってなる、粘っこさとエロっぽさと、にちゃっとした感じが、まさに岡田麿里なんだよなあ。
個人的には、すばらしいと思う。
アニメって実は、そこはホントに重要なんだよね。
最初に初代プリキュアの変身シーンを見たときの「とんでもないものを見させられたような羞恥心」や、最初に『ラブライブ!』の欲情しきった牝アへ顔ライブを見たときの「ヤバすぎて体中がぞわぞわするような犯罪臭」が、そのうち一般化して、大衆化して、巨額の収入を生み出す一大キャラクター産業へと成長する原動力になっていったわけだから。
アニメには、こっぱずかしくなるような「ふりきれた描写」が必要不可欠なのだ。
だから、僕個人としては蕁麻疹が出そうなくらいに気持ち悪いけど、『あの花』のラストは多分あれでいいのだと思うし、僕個人は正視できなくて耳をふさぎたかったとしても、『ここさけ』のミュージカルシーンだって、多分あれでいいのだと思う。人をドン引きさせるくらいの恥ずかしい青春を描かせて、岡田麿里の右に出る者はいない。
(僕の感性で受容可能な範疇に収まる作品でいうと、岡田麿里脚本の最高傑作は、何と言っても『true tears』にとどめを刺すと思っている。)
― ― ― ―
というわけで、僕は「臭い」青春ものの書き手としての岡田麿里には、許せる部分も許せない部分もひっくるめて、全幅の信頼を置いている。
一方で、正直なことを言うと、ファンタジー的な世界観の語り口には、けっこうひっかかることが多い。
『凪のあすから』なんかも、海と行き来する設定自体が、僕にとってはあり得なさ過ぎて、個人的にまるではまれなかった。『あの花』にも根本的な幽霊の条件設定に大きな矛盾と欠陥があると思うし、しかもその設定を説得力をもって呈示する能力に、この人は欠けているのではないかと思っている。
今回でも、街で起きている現象がなんなのかを、必ずしも明示しないままで進んでいくために、予備知識無しで観始めると、結構とまどう部分が大きい。
時間が止まっているってのも、はっきり明かされるのはだいぶ後だし。
とにかく登場人物の言動に、得心のいかないところがあまりに多すぎる。
で、観ているうちに世界観の「真相」が徐々に明らかになってくるわけだが、それで違和感が解消されるかというと、居心地の悪い感じはおさまらないどころか、増幅されていく一方なのだ。
いろいろ考えていて、ふと思いつくことがある。
これは『さよ朝』でも全く同じことを感じたのだけれど、
岡田麿里という人はどうやら、「いつまでも変わらないこと」「齢をとらないこと」を、「マイナスの要素」として最初からとらえているらしいのだ。
え、そうなの?
永遠の生って、ふつうに人間が求める至高の目標なんじゃないのか?
いつまでも老人、いつまでも妊婦ってのは確かに可哀想だと思うけど、いつまでも若者って、これだけ特権性の強い「勝ち組」が他に存在するんだろうか?
美少女のままで、何人もの愛する人と出逢って、看取って、また出逢ってを繰り返すのが「苦痛だ」って感覚、それ一般的なのか?
少なくとも、僕なら何の問題もなく、大万歳で受け入れられそうなんだけど。
いや、「前提として永遠の生って最高、永遠の若さって最高」ってところからスタートして、「それを後からひっくり返す」のなら、十分に理解できるのだ。
「最初はみんな喜んだ。でも何年も繰り返すうちに、閉塞感と無力感におそわれるようになった。そのうち、相手を傷つける遊び、身体に痛みを覚えるような遊びばかりをやるようになった。そうでもしないと生きている実感が得られないからだ」
こういうロジックなら、よくわかる。すっとはいってくる。
いわゆる『人魚の森』みたいな、八百比丘尼の悲劇ですよね。
しかし、岡田麿里は、最初から「若さを繰り返す」ことを、「時の牢獄」だと感じていること、「重荷」「苦痛」「不幸」「罰」「呪い」だと捉えていることをまるで隠そうとしない。
おそらく、彼女自身の青春が、浮かばれなかったから。
彼女本人が、引きこもりで、しんどくて、抑うつ的な十代だったから。
でもなあ。やっぱり、その感性はかなり変わってるんじゃないのかな。
少なくとも、僕はかなりひねくれていると思う。
いくらどう考えても、外から観て『さよ朝』のマキアはたいして可哀想じゃないし、
外から観て本作の中学生たちもたいして可哀想じゃない。
僕に言わせれば、見伏町はいろいろ問題を抱えてはいても、本質的な部分では「ユートピア」だとしか言いようがないからだ。
とはいえ、街の「他の住人」が、「現状を維持すること」を唯々諾々と受け入れて、毎日同じ生活をガチで繰り返しているらしいことも、逆の意味であまりに噓臭すぎて信じがたいし、作り手にとって都合がよすぎるように思う。
ふつうに、出られない、閉じ込められている、時すら止まっている、という絶対的に閉塞的な状況に陥ったら、もっと大衆はパニックになるはずだし、早い時期からセクトに分かれて路線闘争なんかが勃発していておかしくないはずだ。
しかも、街でいちばん頭がおかしいと見ただけで分かるような人間に、文句もいわずに付き従うなんてことが起きるとは、僕にはとても思えない。
街の法則にもよくわからない部分が多い。
なんで、告白して傷ついた園部ちゃんはひび割れてオオカミに食われて、
さんざん傷つけあったりいちゃいちゃしたりしてる主人公二人は平気なのか。
誰がオオカミに食われて、誰が食われないかのルールが最後までよくわからない。
(園部、仙波と単に苛められる系、根暗系から先に消えるだけなのかもしれないが)
目の前で告白したデブが消滅する衝撃のトラウマに襲われたばかりの同級生たちが、原さんの告白で、またも野次馬的にはやし立てているのは正気の沙汰なのか。
という感じで、今回もファンタジーという意味では、いろいろ気になるところは多かったかも。
― ― ― ―
パンフの岡田麿里のインタビューを読んでいて、
「狼少年のように嘘つきな女の子と、狼に育てられたような野性的な女の子、二人の異なる狼少女のお話を書こうと思ったのが出発点です」
といっていて、そこは「なるほど!」と思った。
その趣向自体は面白いんだけど、岡田麿里ってマジで容赦ないなあと思うのは、ヒロインの睦実をちっともまともな女としては描いていないところで、そこは、みんな忘れてはいけないし、騙されてはいけないと思う。
睦実は、なんだかんだ言い訳はつけているものの、4年だか5年だかの長きにわたって、五実を実質ネグレクトしてきた「ガチでろくでもない女」なのだ。
1週間や2週間の話ではない。何年ものあいだ、言葉も教えず、閉じ込めたまま、臭い状態で、おまるで小便をさせながら、オオカミ少女として放置してきたのだ。わざと。しかも、五実が別のマルチバースの自分が産んだ「娘」であることを知りながらのこの所業である。
その後、娘である五実は自然な形で正宗に初恋に似た感情を抱くわけだが、現世の睦実はそんな娘に敵愾心を燃やし、お前は彼氏である正宗を奪おうとするライバルだと明快に宣言する。まさに「最初に出逢う異性をめぐって、同性の親との葛藤が生じる」というエレクトラ・コンプレックスのケーススタディである。
いや、女とはもともとみんなそういう生き物で、誰しもが「内なる妻と母の闘争」を抱えていて、だから母娘とはこうやって張り合い、愛し合いあがらも憎しみ合うものなのだ、と岡田麿里は問うているのかもしれない。
で、この「毒親」睦実はどうなるかというと、何年も五実を苦しめていた罰でも受けるのかと思いきや、あにはからんや、無事、異世界から来た五実を「改めて元の世界に産み落とす」ことに成功したうえで、自分は永遠に続くかもしれない正宗との恋愛の勝者として、閉ざされた見伏町の正宗の胸へと帰っていくのだ。
これが、「ハッピーエンド」として描かれているらしいところに、岡田麿里という人の真の恐ろしさが見て取れる。
そう、この作品は突き詰めていうと、「ろくでもない睦実」に対して、正宗には「好きだ」と言わせ、仲間たちには「戻ってこい」と言わせ、実際に彼女にとって思い通りの結末を与えてやることで、彼女を全面的に「救済」するのが真の目的の物語なのだ。
そして、岡田麿里には、それを大半の観客に「なんかよかった! ハッピーエンドで!」と力業で思わせてしまう「物語る力」がある。
僕も、これだけ五実にひどいことをしていたはずの睦実のことを、最後のほうは超応援してたし、超可愛いと思ったし、超幸せになってほしいと素直に思った(笑)。
いろいろとひっかかるところや、なんだかひどいと思うところや、これでいいのかと思うところも多々あるんだけど、結局、最後は「良い映画を観た」って気分で劇場を後にしたわけだから、今回も岡田麿里との勝負は、完敗といったところか。
うーん、やはり、凄い監督さんである。
最後に。声優陣はマジ完璧。
とくに上田麗奈と久野美咲は無双状態。
やっぱり、こういうのはガチの声優さんにやってもらうに限るなあ。
あと、「スイートペイン」は超笑いました。
こういうのは、ほんと岡田さん上手いね。
あの花を思い出して泣きました
あの花もそうでしたが、どっちの選択をしても誰かが傷つくと分かっていながらも、進まなければいけない。
そして死んだ世界でも絵を描き続けていたら、絵が上手くなっていた
という、今生きていることと、無駄な事はないということに
当たり前のことに気付かされます。
良作だと思うが人を選ぶアニメ映画
工場の事故により
時間が止まった世界で
いつか戻れるように変化をしないように生活しているという
舞台は昭和の日本だと思うが
世界観は独特である。
その変化をしない世界で政宗は睦実につれられて
まともにしゃべることができない少女の五実の世話をまかせられる。
そして、同級生が狼みたいな煙につつまれて消えてしまったことで
この世界の秘密を知ろうする。
この世界は現実と切り離された世界で
いつか消えてなくなってしまうという。
五実は現実世界の人間で
現実の政宗と睦実の子供らしい。
この世界では変化をしようとすると消えてしまうらしいが
カップルになった同級生たちは消えなかったので
なんとなく世界に失望したら、消えてしまうのかなと思った。
政宗たちは五実を現実に戻そうとするが
そのなかでは子供たちだけではなく
大人たちも世界を維持するために五実を現実にもどすのも阻止しようとしたり、
逆に自分の力で世界を維持する大人がでたりするところはなんとなくリアルだなと思った。
子どもが自動車を運転できるのは
変化を嫌う世界なのに大人の都合が優先されるのかな?
政宗の父親と叔父は
似ていて最初、同一人物かと思った。
良作だが、世界観や
恋愛、失恋をテーマにしている感じで人を選ぶ作品だろう。
本編を見てもタイトルの「アリスとテレス」のことはよくわからなかった。
哲学に詳しい人ならわかるのかな?
【”空と心のひび割れ。”時が止まった異世界での少年少女の複雑な恋物語を、アリストテレスの哲学的な概念の一つである”エネルゲイア”をベースに、二人が未来を目指す姿を描いた作品。】
■製鉄所の爆発が引き金になり、時間が奇妙な形で止まり異世界となった見布町が舞台。
空は宝石の欠片の如くひび割れ、その向こうには現実世界があるという設定が斬新である。
・エネルゲイア:アリストテレス哲学の概念の一つ。現実態とも訳される。
◆感想
・鑑賞後にドッと疲れた作品である。
異様な世界観と、物語構成や人物造形にやや瑕疵があるため脳内フル回転で補完して観たせいであろう。
序でに言うと、劇中で述べられた”エネルゲイア”を思い出すのに苦労したせいもある。
・正宗は同級生の睦実が好きなのだが、睦実はツレナイ。
だが、二人は一度だけ雪が積もる中、抱き合い接吻をする。
そして、正宗の事が好きな女の子はその姿を見て、心にひび割れが出来、空のひび割れの中から現れる、狼のような白い煙に巻かれて消える。
ー 彼女が、現実世界に戻ったのか、良く分からない・・。-
・そして、正宗が睦実に連れられていった製鉄所内に居た野生の少女イツミ。
ー 現実世界では、正宗と睦実は夫婦であり、イツミは二人の子でありながら異世界に来てしまった事が途中から分かるのである。-
<岡田監督による不可思議な世界観と設定は斬新で、その中での正宗と睦実の恋する衝動により、我が子イツミを現実世界に戻そうとする姿などは面白かった。
だが、物語に一部瑕疵があったり、人物の描き方もやや粗い部分があり(特に睦実かなあ。)、ヒジョーに疲れた作品。
面白かったけどね。>
恋する 衝動が、世界を 壊す
原作・脚本・監督: 岡田麿里
副監督: 平松禎史
美術監督: 東地和生
キャラデザ: 石井百合子
音楽: 横山克
〔敬称略m(_ _)m〕
加えて、中島みゆきさんが書き下ろした主題歌、MAPPA初のオリジナル劇場アニメーション作品とくれば、期待しない方が無理。
公開をずっと!ずっと!待ちわびておりました!
初日8時半から鑑賞!
岡田麿里監督の作家性が爆発している作品でした!!!٩( ᐛ )و
役者の演技も素晴らしかったですし、繊細で力強くて、幻想的で細部にまでこだわりを感じた映像!
もしかすると作品を食ってしまうかも?の、みゆきさん起用の主題歌も見事に後押し!最高でした!!
監督自らお話しされていますが、田舎の閉鎖的な場所で、母子家庭で育った事。お母様との不仲。
思春期に不登校、引きこもりを経験。
そんな時期の自らの置かれた環境や葛藤などを全てをぶつけた、その過去を昇華させた作品なんじゃないかと思いました。
印象的な名シーンや名セリフが多く、全ての想いを語り尽くせません。
⚪︎冒頭のドアップ!
フクロウ時計の目玉が左右に動き「時を刻んでいる」意味深なシーン。
⚪︎正宗が教室を移動する時に屋上にいる睦実の姿「影」を見上げるシーンがたまらない。
⚪︎好きな気持ちを見せ物にされたと泣いた園部。自身無さげな感じとは裏腹に、心の中のドロドロとした感情。
⚪︎フライヤーの表紙にもなっている、五実が手のひらをかざし、あちらの世界の陽の光を感じるシーン。手のひらが光に透けてとても美しい。
⚪︎バス停での原と安見の会話。
「スイートペイン」私もこんな会話していましたよ(^。^)
特別なんかじゃなく、どこにでもいる普通の女の子達だったよね。
⚪︎正宗のグループの中でも地味目な仙波が、この世界だからこそ持てたという将来の夢。変化を望みそして。。
⚪︎アニメ史上最高のシーンになり得るだろう。正宗と睦実のキスシーン!!
閉鎖された街、永遠の冬に閉じ込められた人々。
⚪︎匂い。。
臭くないでしょ。まぼろしだから。
⚪︎痛み。。
失神ゲーム。高所からの飛び降り遊び。
⚪︎睦実が上履きを盗む。。
攻撃。精神的な苦痛(暴力)
⚪︎スカートをまくって見せる。。
情動。からかい。
閉鎖された街では匂いもないし寒さも感じない。
生きている実感を求めて、痛み・暴力・性的な衝動に興味が向かうというのは、見ていて不快にもなるし、危険な事だが、、私にはまともな感情に見えた。
生々しい性の描き方、鬱屈した感情、不安、孤立、好き、嫌い。。
加えて主人公達の置かれた特殊な環境。
思春期の複雑な思いが交差した
「衝動」の凄まじさを感じた。
それは世界をも壊す衝動だった。
キーとなる「五実」という隔離されて言葉も話せない狼のような少女。
何も知らない無邪気さ、素直さ。
そして正宗に対する初めての恋。
五実の心の変化が均等を揺るがすきっかけとなっていく。
女が好きだけど、好きな女がいるわけじゃない
でも。。嫌いな女ならいる。
菊入正宗 は、佐上睦実 が 嫌 い
2人と関わる事で、正宗の心にも又、変化が起き、考えるようになっていく。
恐れず突き進む姿に力強い意志を感じた。
又、睦実と五実の「女同士」としての描かれ方には「マリーらしさ」全開のいやらしさも滲み出ており、そこまで言うかのあのセリフも、やはり名セリフだった。
列車の上で本音をぶつけ合い、五実の将来を考える愛情を見せてくれた睦実に泣かされました。
SFとしての描写が甘いとか、永遠にある物質、ラストの描かれ方への好みなど、いつもならケチをつける部分もありましたが、とことん感情に沿っていて、そこがブレなかったからこそ力強い作品になり、感動したのだと思います。
思春期の頃の心の中にあった、あの得体の知れない衝動や葛藤、情動を見事に表現してくれた秀作です!!
最後におじいちゃん。ボケてるのか?思うてごめん。グッジョブ!
生き方は選べる
ジュブナイルSF映画、工場の事故をきっかけに停滞した世界に生きる
住人達の中の少年少女の物語
この手のものに珍しい所としては全て現実に戻るのが正しいとは限らない所ですかね
神様がくれた世界だしそりゃそうかもしれませんね。
未来の世界には生きられないけど死んだ訳ではない現実でもそうかもしれませんが
結局色んなものを受け入れて生きていくしかないのが人間なんでしょうかね。
映画としては面白いとは思いましたが、コンポデッキや何度も出てきた昔流行った
フクロウ時計、ブルマの体操着、長いスカート、年代的には70~80年代ですかね
頑張ってやり過ぎてて今とは色々感覚が違うので伝わらない部分もある気がしますね?
監督の前作のさよ朝と関連ありそうな部分は永遠とそうじゃない存在との対比でしょうか
本人の中の題材なんでしょうかね?次回作が気になりますね
変わらない世界
閉じ込められた世界、だけでなく、時が変わらない世界という残酷さやもどかしさ、鬱々とした思いが渦巻いていたなぁと思います。
いつまでも大人になれない主人公、もだけど、いつまでも妊婦のままの女性、の方が気持ちを保てない気がします。
その世界を保とうとする人と変わりたいと願う人、ここは絶対に相容れないですよね。
なんか、そこら辺のもやもやが、「いたい」の気持ちから変わっていくとこが…なんだかなぁと思う反面、「すき」になると変わってしまうよなぁっと納得してしまうとこもあり、見終わっても、ズーンとしています。
政宗家族の物語!
製鉄所の爆発から時が止まった町…。
現在の時代から一人の少女が…五実!正体は…政宗の?
製鉄所からでる神機狼?謎だらけのストーリーさすが岡田監督の脚本…無茶苦茶面白かったし作画が神ってました。
MAPPA…伊達じゃない…脱帽です!
中島みゆきの主題歌もすごくあってました。
(^^)感じとるしかないだろう
いろんな見方ができるのでしょうね。ぱっと見パラレルワールド的で量子の世界の話か?と思いましたが、単純に考えて子供を授かり産まれるまでのストーリーなんじゃないのか?と思いました。恋の衝動 リビドー、トンネルは産道、あたらしい世界の誕生、、、。子供が可愛いと思う反面旦那は取られないというライバル心。かわりにあたらしい世界と可能性の約束。うまく言えないが命の誕生、あたらしい世界の誕生の話なんだろうと勝手に解釈しましたがね、、、、。
「カワイイ女の子」を描きたかった製作者
ただそれだけだと思う
でもジョブナイルってそういうことだっけ?
失敗を恐れて動けなかったり、動いてもみても失敗ばかりだったり
だけど、動いたら希望もあるってことだろって劇中でも引用してることなのに、何も物語では語ってない
世界に拒絶されて消された人たちが哀れすぎる
ラストで取ってつけたような「この映画は〇〇がテーマでした!!」みたいなのがあったけど、どうなのそれ?
そのテーマなら、消されたあの人はどうなったのでしょうか?
考えれば考えるほど、憤りが溢れてきます。
脚本を読んだプロデューサーはこれでGOサイン出したのよね?
哲学的なのに等身大ファンタジーという怪作
まず言いたいのは「凄い映画」だということ。それも、今まであまり感じたことのないタイプの「凄さ」だった。
●「母と娘の情念」から「生きるとは」へ
この作品を見て感じたのは、今までずっと私の頭に引っ掛かっていた「変化」「成長」「家族とは」「愛情ってなに」などの「キーワード」が、「生きることは」に向けて「きれいに線で結ばれた」という気がする、ということだ。それは、この作品が持つ「哲学的」な面のおかげだろう。現にタイトルが哲学者だし、哲学用語も出てくる。例えば「哲学奥義エネルゲイアー」。
でも、キーワード達を結んだのは「哲学的な抽象的なもの」ではない。それは「母と娘の情念」というありふれたものだ。そういう「ありふれたもの」を武器に、色々なものの奥に潜む本質に切り込む。そんな「無茶なこと」ができたのは、ファンタジーの設定の巧みさのお陰だろう。
●ファンタジー設定の巧みさ
「生きることを奪われた人たちの思い」が作り出した「変化を止めた並行世界」。そこに迷い込んだ少女は、少女のままの母親に出会い、同じ男性を好きになり、母に敗れる。その「痛み」は「人が宿命的に求めるもの」で、現実でも幻想のなかでも変わらない「生きるとは何か?に迫るもの」だった。荒っぽく要約するなら、そういうお話だと思う。
ポイントは、変化を止められた世界にいることで、「痛みがもつ深い意味」が浮き彫りになる設定になっていること。私たちは痛みや変化なしに生きられない。もし時間を止めたとしても、人が生きている限り、正宗のように絵が上達するのだ。そう素直に感じられる。
そこから成長についても考えさせられる。人は「成長するために変化する」と思いがちだ。でも本当は順番が逆だ。人には「変化という宿命」があるから「成長も」する(成長以外の変化もする)。もちろん成長は素晴らしい。でも成長のために変化すると捉えるのは「倒錯」なのだ。そういう「キーワードの並ぶ順番」に気づかせられるファンタジー設定となっている。
●私の中で繋がったキーワード
私の中で「線で繋がった」と感じたものを言葉にするとこうなる。
「情念(嫉妬、愛情、恋愛)」の中心には「痛み」がある。
その「痛み」は「変化を生み出す心の構造」と分かちがたく繋がっている。
その心の構造が「ある方向性」で作用した結果を私たちは「成長」と呼ぶ。
でも、この作品についてもう少し考えると、もっといろいろなことが見えてくる予感がする。特に、繋がっている気がするけどまだよくわからないのは「鎮魂」だ。
●まだ繋がらないキーワード「鎮魂」
大災害によって生きることを奪われた多くの人々の思いが作り出す幻影。この設定は、どうしても3.11の東日本大震災を思い出す。そしてあの時突然生きることを奪われた人たちの幻影は、まだ生き続けているのではないか。私たちの記憶の中に残っている限り、その幻影は消えて無くならないのではないか。そういうことを考えてしまう。
その幻影はあの日のあの時刻のまま凍り付いてしまっているかのように感じられる。でも本当は、その人々は記憶の中で息づいている限り、変化が起きている。それは科学的には「記憶の劣化」と言われる。でも本当は「息づいている限り変化を止めない人間の本性」に根差したものなのかもしれない。そういう変化そのものに「鎮魂」というものの本質があるのかもしれない。
●鎮魂から「生きるとは」へ
人は失った人の記憶が薄れていくことを悲しむ。でもその「記憶の薄れ」を「幻想の中の人の目線」で語りなおすなら「変化を求めて前に進むことを選び、幻想の範囲を抜け出した」と言えるのかもしれない。そしてそれを「残された人目線」に戻すなら「幻想の中の人を閉じ込めることをやめ、彼らの意志に任せて、解放する」ということだ。それは「鎮魂」の本質に近いのかもしれない。そしてそのことはきっと「私たちが生きること」と線で繋がっているはずだ。
硬派でありながらも比較的わかりやすい物語でした。
長いです。
☆初め予告を見た時、嫌な予感がしました。そばかすの姫やバブルのように作画や設定に全振りして、視聴者置いてけぼりになりそうだって思ったからです。
実際は、世界観の直接的な説明や小難しいナレーションはなく、主人公周りの会話や絵だけで"あ、そういう状況なんだ"と察しやすいストーリーでした。
描写はところどころ艶っぽく子供(14歳)なのになんでこんなにエロく表現する必要があるんだ??って少し奇妙な感じでした。途中でわかりますが、精神はある程度、成長してきているようなので、その表れかなって思います。
お腹の中の赤ちゃんが成長しなかったり、姿が子供のまま運転免許証がに認められたりと身体の成長だけが止まっている状態ですですね。
なによりもキスシーンが生々しいというか、場所も状況も影響もなにもかも気にしないキスだったのがすごく印象に残ってます。
そんで主題歌が秀逸です。
流行っているアーティストを起用する方がキャッチーだし、目と耳を引くと思っていたのですが、中島みゆきさんの"心音"を聴いた瞬間、まるで何事も無かった一瞬の出来事のような、絵本を中の物語を体験ような感覚になりました。
ただ、いくつか気になるところはありました。
・睦美の父をあんな性格にする必要性
・心の変化がダメということに気付いたきっかけ
・最後に鉄工場で神隠しがあったとタクシー運転手が言っていますが、成長の止まったあの世界で消された人(心が変化した人)は現実世界でも消えるの?って疑問が残りました。
いつみちゃんが現実世界から幻想世界に来てしまったことが神隠しならすぐに納得出来たんですが…
また、"車の運転=大人"を一つの要素として示唆していると感じました。
運転免許証って取得したとき少し大人になったきがしませんでした??
大人から逃げる時は走り(子供)で、徒党を組んでなにかする時は車(大人)って思いました。
余談
アニメ会社の名前だけで宣伝効果のある時代になったんだなーって驚きました。スタジオジブリはまだしも"MAPPA制作"で宣伝できるのすごいと思いました。進撃の巨人やチェンソーマンでの実績だったり、アニメに対する風潮が変わったのが大きいですね!!
全89件中、61~80件目を表示