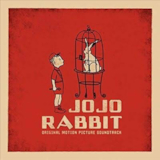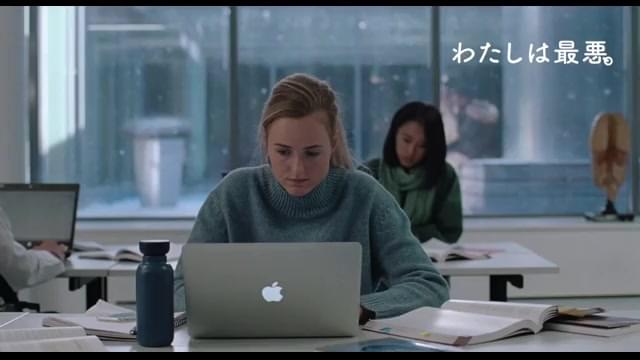わたしは最悪。のレビュー・感想・評価
全139件中、121~139件目を表示
鑑賞動機:ポスターと邦題のギャップ3割、トリアーだと?3割、脚本賞候補4割。
人生における大きな選択は先が見えず、不安になるという点で主人公に共...
男子ってそう思ってんだ〜
確かに「最悪」かもしれない…。
この映画は“共感”ではなく、“共感できない”を求めているということになるだろう。
自由はいいと思うが、かなりまわりを振り回して生きていると言える。
先日公開された「パリ23区」を思い出したが、この手の映画は表面的ものを描くしか方法がないので、最後は結論なく、なんとなく終わるしかないだろう。
合作の中にフランスが入っているので、フランス映画の匂いも漂う。
北欧の〇〇など、日本ではいい意味で使われている場合もあるが、映画を見る限り、価値観は混沌としている。
映画とは“共感”や“感動”を得るものだと思っていたが、もうすでに、そういうものではなくなっているらしい。
暗い映画館の中で、傍観者になるのは、寂しいことだと思う。
それは誰の身にも往々にして起こり有り得ること
成績優秀だから医学部を目指すとは
日本でも良く聞くハナシ。
そこには「医は仁術」との視点は欠けている様にも思われるが
本作の主人公『ユリヤ(レナーテ・レインスヴェ)』も
それを地で行くような進路選択。
程なく、適性について疑問を抱き、次は心理学、
更には写真と次々と目標が変わって行く。
その過程で、付き合う男性もとっかえひっかえとなるのだが、
はてこれは、一種の自分探しの挫折の繰り返しと捉えれば良いのか。
ストリー上は三人目の相手となるのか、
一回り以上年上のコミック作家『アクセル』との日々は
最初は穏やかなものだった。
しかし自身の家族との相克、彼の家族との葛藤、更には
子を産み母となる可能性が見えてくると
彼女はまた、同じことを繰り返す。
忍び込んだパーティの会場で会った『アイヴィン』は
カフェの店員だが若く、魅力に溢れている。
共にパートナーのある身。
浮気未満の一夜限りの関係のつもりでいたのに、
惹かれ合う二人は、ひょんなことから再会し
焼け木杭には火が付ついてしまう。
しかし、彼とも、何かコトが起これば、
立ち向かうよりも回避を選ぶのでは、と
鑑賞者の側が感じ始めた矢先、
突然の知らせが舞い込む。
そうした『ユリヤ』の生き方は、傍から見ていると
釈然としないものに思えてしまう。
とは言え、難題に対して
常に正面から立ち向かうことを選択する人間は
世の中にどれほど居るのだろうか。
それは男性でも女性でも同様で、
ここではややカリカチュアライズされてはいるものの、
万人に共通の弱さと捉える。
それらを全て吞み込んで、
「自分はこれで良いのだ」と自己肯定できることが
窮屈に生きないための一つの方便にも思える。
勿論、自身を甘やかし過ぎれば、
違う意味で駄目人間になってしまうだろうが。
人夫々に幸せのカタチがあり、他人にはとやかく言う権利は無いものの、
事有る毎に一方的に突然の別れを告げられる方は
堪ったものではないけれど。
現代映画の最前線なのかもしれない
たぶんタイトルはちょっとニュアンスが違うのでは、と思う。悪いことがあって舌打ちするようなのでなくて、たぶん自虐的にいう私は最悪の女、なんですね。違うか。
予告編みてイメージしてたのとは違いはしたけど、とにかく繊細でリアルでファンタジックで、女性監督のオリジナルシナリオなのかと思うのと男性なのですね。たまげた。日本の男性監督にはこれは撮れまい。というほどに細やかな瞬間を狙った映画で何が近いかというと「リコリスピザ」とか「カモンカモン」かもしれない。ひと昔前の映画が描き出してない映画としてのドラマ。映画でないと描けない時間のドラマ。
12章に分かれて…と説明が入るとおり、モノローグと私小説的要素のエッセンスで主人公の「今」までが描かれ、人間関係における「今」がはじまって別の人が現れて「今」が更新されてゆく。男にも女にも等しく「過去」が出来て「今」が更新され、去ってゆく人の今と遭遇する。やはり最後はじわっとくる。「横道世之介」が好きなのはこういうことなのかもしれない、と思ったりした。
ひとつ、こんな同時代的に「1秒先の彼女」と同じようなファンタスティックなシーンに出くわすというのは、これも時代なのか。雰囲気はまったく違うけど。そして、あちらの台湾の街角とこちらのオスローもとても魅力的だった。
そもそも「時間」をテーマにした映画で時間を止める、というのを具体的にやるっていうのも手が混んでますな。
主演の女優さんが、私の好みのタイプだったので観てみた。
簡単にこの映画の内容をいうと、自分探しをしている若い女性の話である。あと2週間もすれば、私は67歳になる。孫も3人いる。もう、とうに自分探し(正確には諦めた)は終わっているが、迷うことは今でもある。
60歳で鬱病を発病し、再発と寛解を繰り返している。最近の診断では気分循環障害(軽い躁うつ病)と言われた。だから、人生を迷っている主人公に共感できる。
映画の作り方が、私の好みではなかった。故に作品に集中できなかった。中盤辺りから、映画らしい幻想(イリュージョン)が入って集中できた。私の好きな作曲家モーリス・ラベルの「ラ・メール・ロア」が流れて嬉しくなった。映画の中で使われたのを始めて聴いた。
人生に迷っている若い人に勧めたい映画である。聞き慣れない言語で話している。ノルウェー語だった。
女性の吐いたタバコの煙を男性が吸い込む場面があります。そのエロいこと。これだけで官能を刺激させ、現実の性行為よりもエロティックです。
谷崎潤一郎や川端康成或いは三島由紀夫が喜ぶ姿が目に浮かびます。
私の人生なのに傍観者で、脇役しか演じられない。
共感はできないが彼女なりに成長しているのだろう
学業成績抜群なのだが違う道に進むほど可能性の幅を狭めているように思えてならない。
それは父親の言い訳癖によるものか母親の何でも容認する姿勢によるものなのか読み取れなかったけれど、とにかく残念だ。
恋愛も残念だが、別れを告げられた男性からすればポカ~ンとなるだろうな、なのにあいしてしまっている男どもが可哀想すぎた。
作品を通じて学んだことは、切羽詰まったって直ぐに逃げを打たず一旦頑張ってみよう、かな。
ノルウェーの美しい街並みは印象に残りました。
気が付いたら彼女の幸せを願っていました
男性諸氏‼️
たまには頭をフル回転して、女性がキャリアを積むことや身体的生理的な違いやそのことからくる不安などを自分のこととして想像してみよう❗️
何を偉そうに!
そんなこと、これまでだって考えてきたさ、という方ももう一度ゼロベースから想像力を働かせてみてください。なんだか今までは、理解したつもりになっていた、或いは、理解した振りをしていただけだっだかも⁈
なにせ、ユリヤの語りかける力が凄い。
言葉だけでなく、視線、息遣いなどすべての表情が男性側がいい加減にやり過ごすことを許してくれません。理屈抜きで迫ってきます。圧倒されます。
劇中、自然体で話せる、という会話がありましたが、この映画は見るこちらもいつの間にか映画の世界に巻き込まれています。
〝テーマ〟として捉えるのではなく、劇中の登場人物のひとりとして向き合わされます。
正解のない答えを一緒に考えさせられます。
最後まで正解らしきものなんて出せやしないけれど、彼女が幸せになることを心から願っているうちにエンドロールも終わる。
そんなちょっと不思議な映画。
主人公の成長が感じられない
人は何歳になっても成長するものだが、主人公の成長が描かれない、あるいは感じられないため、感情移入もできないし、共感もできない。
面白かったのは、パーティーで出逢った2人が、お互いに「浮気ではない」ギリギリの線を攻めながら濃密な関係になっていくシーンと、2人以外の時間が丸1日静止するシーン、そしてドラッグてラリるシーンぐらいで、それを除けば、退屈でつまらない話がダラダラと続くだけだった。
結局、主人公は、結婚することも、子供を持つこともあきらめ、仕事に邁進するということなのだろうか?そうだとしたら、いかにも現代的な選択ではあるのだろうが、あまりにも寂しいし、物語として薄っぺらいと感じてしまうのである。
問題山積みの世界で生きる私たち
女性の権利/地位向上、環境破壊、少子化 --- 今日の世界を取り巻くあらゆる状況に言及しながら、そんな時代を生きる女性のリアルを12章に章立てながら赤裸々に綴る。もう30歳だけど何もうまくいかず、だらだらと日々をやり過ごすよう。そうした日常から救い出してくれるようなトキメキや刺激/情熱を追い求めて胸焦がしても、結局また人生の二択で間違えちゃう遠慮の無さとすぐに移る興味。共感する人はとことん共感できそうな内容で、どうしたって走っても抜け出せないで引き戻される現実。
世界は今日も終わりに向かっているけど、自分のことで手一杯なときもある。そんなこと分かってるけど、どうしようもないから、最低最悪な自分。自己評価も落ちちゃうけど今日もなんとかやってます。自らの手で逃したものに思いを馳せながらも生きていくロマコメと言うべきかドラメディと言うべきか、『フランシス・ハ』なんかも思い出した人生のポートレート!"普通"の幸せって難しい…。
大人の男性への憧れか、女性蔑視コミック「ボブキャット」の作家とはじめはくっ付く。からの、見れば見るほどアダム・ドライバー似のアイヴァン。ズルズルと男性関係を続けては、自分から別れを告げる。人として合うか合わないか、見た目じゃなくて中身や波長なんて言うは易しだけど、実際行き詰まったときの決断でそこまで先を見越して選ぶのは難しいから経験値。けどきっとまた同じ過ちをしてしまうのだろう。"君はいい母親になる"...? --- 最後の哀しみというより束の間の安堵の表情にも見える顔が印象に残った。
『パリ13区』にあった直視するのも痛々しい赤裸々も厭わない奔放さとそれに伴う重い代償をまとめて引き受ける優しさが印象的などこまでも美しいドラマ
原題はノルウェー語で“Verdens Verste Menneske“、直訳するとWorld’s Worst Personなのでこの邦題になったのは解りますが、映画にはそんな人間は一人も出てこないので主演のレナーテ・レインスベのインタビューを参照したところ、このフレーズはノルウェーにおける慣用句で自分が誰かを傷つけたり、または自分がやったことに満足出来なかった時に自虐的に吐き捨てる言葉だとのこと。頭を抱えながら「あーやっちゃった」と自戒することだと捉えると、直感で行動し出会った人に影響を受けてまたあさっての方向に弾けていく主人公ユリヤが延々と繰り返す身も蓋もない試行錯誤と重なります。この辺りの赤裸々な会話や奇行の数々やユリヤの家系やサーミ人の話などといったスパイシーなウィットがぎっしり詰まっているので、観ているこちらは苦笑させられたり顔が引きつったり大忙し。そんなユリヤはどこまでもチャーミングですが、彼女の周りにいる人達も個性的。悪い意味で印象的なのはユリヤの父ハラルド。面倒臭いことを避けるために言い訳をこれでもかと重ねて逃げる卑屈な感じがめちゃくちゃリアルでした。
世界はなぜかユリヤを中心に回り続けるので、ユリヤがスイッチ一つでオスロの街を静止させて軌道修正することも許します。アニメ版の『時をかける少女』や台湾のファンタジーコメディ『1秒先の彼女』にもあった表現ですがそれをファンタジーではないドラマの中にさりげなく挿入したところに、誰しも自分の意志で好きなタイミングで人生をやり直していいんだという優しい抱擁を感じました。しかしその代償は思いもよらぬ形で返ってくるというしっぺ返しもあるので、爽やかだけどずっしり重いドラマになっています。
過激な描写も厭わない奔放な演出は『パリ13区』とよく似ていますが、R18+だった『パリ〜』に対して本作はR15+。恣意的にも程があるレイティングは全くもって理解不能ですが、クリストファー・クロスの『風立ちぬ』やアート・ガーファンクルの『春の予感』(ちなみにボサノヴァの名曲『三月の水』のカバーですが、三月がブラジルの秋に当たることは無視されています)といった70’sポップスからのサントラチョイスが個人的にツボでした。
全139件中、121~139件目を表示