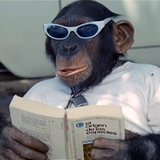コンパートメント No.6のレビュー・感想・評価
全92件中、21~40件目を表示
恋愛手前のむず痒くて楽しい時間
旅行中に出会った第一印象が最悪のガサツな男と、目的地までのゆったりとした時間で恋愛の手前の距離感で寄り添う話。
話が進むにつれてくっつくのか〜?!という微妙な関係をむず痒く思ってしまう。だがそれが楽しくてにやにやする。曖昧な関係や相手への愛情が確立されるまでのモラトリアムにもどかしく思う、以外と純愛系のラブロマンス。
フィンランドやロシアといった場所の映画特有の何が起こるわけでもなく、くすんだ映像が続くけど暗くなくて暖かい、という雰囲気がかなり好み。もう一回くらい見たいな。
電車旅がしたくなった
予告編を見て気になっていた映画を見てまいりました。
予告での主人公2人の表情がなんとなく気になっていた
女性の嫌そうな顔と、男性の悪そうな無邪気な顔。
それと流れていた音楽が良い。
主人公の二人の事はもちろん知らず、制作国はロシアとヨーロッパの合作だったらしい。
これは見に行くしかないと思い、初日に見に行った。
見ての感想は、主人公の男はめっちゃいい奴だった。
女性はおばちゃんかと思ったら女学生だった。
描かれていた時代も今ではなく、ハンディカムとウォークマンを使っていた時代(1990~2000年代?)。
映画の中の音楽も良かったし、めっちゃ異国感を感じた。
良い雰囲気の映画でした。
最初の印象が最悪な男女が最後は結びつくという話に『バルカン超特急』を思い出した
私が学生の時に大好きだった映画『めぐり逢えたら』の中で出てきた映画だ。
かなり古い映画(ヒッチコック)なので見た事はないが、出会いが最悪な男女が最後に結ばれるというストーリーというと『バルカン超特急』を思い出してしまう。
それと、私の過去の列車移動での出来事を思い出した。
15年以上前に、八戸から札幌へ電車で移動する事があった。(当時の私は仙台市に住んでいた)
八戸で仕事があり、次の日なぜか札幌の北海道支店で会議があって、三沢空港から千歳に飛ぶかと思ったらよい時間がなく電車を選択したのだ。
当時は新幹線が通ってないので特急。(確かスーパー白鳥、北斗)
青森駅の付く直前で斜め前の座席に財布があるのに気付いた。
さっきまでサラリーマンのオッサンが乗っていた。
少し離れた席の高校生らしき3人組がいて、チラチラ座席を見ている。
すると車掌が歩いてきたので呼び止め財布がある旨を伝えた。
車掌と二人で中を見てみると10万くらいは現金が入っていたと思う。
学生たちに財布を取られる事もなく、良い事をしたという思いで少し心地よい気分になっていた。
その後も電車に乗り続け青函トンネルを抜け、五稜郭駅で少しの停車時間があった。
当時の私は喫煙者だったので、すかさず降りた駅の喫煙所に向かった。
すると私と同じような喫煙者達が数名同じようにタバコを吸いに来ていた。
何とはなしに、喫煙者には車内で吸えない時間が長いのは辛いですねーという話になり少しの雑談が始まった。
聞くと行先はみんな札幌、若い男性は札幌在住。おばちゃんは青森の人だった。
五稜郭駅前には何かあるのかを聞くと何もないとの事。
2~3本吸って座席に戻った。
見知らぬ人との会話が楽しかった。
ノートPCを出して車内で仕事をしようと思ったが、電車が妙に揺れる。
後で調べたところ、この辺の電車はディーゼル車(パンタグラフは無い)なので揺れるらしい。。
酔ってしまうので仕事は止めた。
その後にトイレに行くと五稜郭駅で一緒にタバコを吸った若者と会った。
彼の会社は出張時に指定席には乗れないので自由席に乗っているとの事で(指定席料金が自腹になる)、私が指定席だと知るとやたら羨ましがられた。
話はだいぶそれたが、電車旅がしたくなった。
なかなか昔の思い出話のような出来事が起こる事はないだろう。。
仕事でならいろいろと電車には乗った事はあるが、プライベートでの電車の思い出はほとんど無い。
そんな事を考えさせる映画だった。
最近見る映画は邦画が多かったので、良い洋画が見れて満足。
世界最北の温み
1990年代。フィンランドからモスクワの大学に留学しているラウラ。交際しているイリーナと、ムルマンスクの岩面彫刻を見に行く予定だったが、イリーナが行けずにラウラは一人寝台列車に。しかしリョーハというロシアの青年と、6号客室で相部屋に。粗野な彼にうんざりするも、客室の変更はできなかった。
うわっ、こんな奴と何日も一緒なんて。男の自分でもやだな、まして女だったら。とみんな思いますが、粗野だけど少年のようなリョーハに、だんだん親しみを覚えるのが良いです。さらに面倒見がとてもいいときています。ラウラは、いかにもフィンランドのじぇごくさい(田舎くさい)顔つきでも、徐々にかわいく見えてきます。見かけで人を判断してはいけないな。
ムルマンスクの駅は、世界最北だそうです。
ウクライナ侵攻前の作品。再びこんな作品がつくられるのを願います。
まさかの
どんでん返し
むか〜し、むかしに乗った寝台列車が記憶の彼方から蘇ってきた
あの頃は貧乏だったのに幸せだったなぁ……
ロシアにもあの日本の寝台列車に似た列車があると知り親しみを感じた
ただ、酔っぱらいのリョーハが絡むあたりまでは、チョイスを間違えたと思ってたが、映画が進むに連れ、じわりじわりと曇りだった空が晴れてくるのを感じた
ラストシーン
「ハイスタ・ヴィットゥ」が、実は愛してるではなく(くたばれ)だと知った時の、なんとも爽やかな微笑みが主人公のラウラの笑顔よりも早く自分の中で生まれていた
ロシア人って可愛い!!
プラットフォームで雪と戯れてすねる?彼もキュンです
ソックリの似顔絵をもらった時の心情が青い目を通して表れたシーンもキュンです
ラウラのために夢を叶えようと奔走する姿もキュンです
ムルマンスクに向かう車の後部座席でお互いが寄り添って寝てるシーンもキュンです
最果ての地で猛吹雪の中、大人の男女が子供のように遊ぶシーンもキュンです
見ず知らずのラウラ達にお酒をくれたロシア人は、日本の田舎にいる親切な村人達とオーバーラップしてGood
メディア等によって作られ刷り込まれたイメージとはかけ離れたロシア人がそこにいた
きっとウクライナ侵攻でロシアだけが悪者にされているのも刷り込みなのだろう
エンドロールが流れ始めた時には、日本晴れならぬロシア晴れ?のスッキリした雲一つない青空が心に広がっていた
人生における出会いの「妙」が、自分の中で暖かく熟成していくのを感じた
後で、カンヌ国際映画祭でグランプリを取ったと知って、ビックリ&納得
そして監督のこの映画に込めた想いを知れば知るほど、感慨深くなっていく
あぁ、いい映画に出合えてよかった
これも「妙」
旅は道連れ世は情け
ヘイ。ヘイヘイ。
Haista vittu ハイスタ・ヴィットゥ!
=いつも むっつり顔だ
=すぐシワだらけになるぞ
=ありがとう余計なお世話よ
旅は道連れ世は情けだ。
僕も旅先で、思いもかけずに出会った人たちのことを思い出す。
汽車で、飛行機で、そして時には船で。たまたま言葉を交わしたあの人の事や、この人の事・・
珠玉の出会いがそこにあり、一生忘れられないあの人たちの言葉が、旅の最大の土産になる。
映画は、フィンランドからの留学生ラウラが、モスクワからの夜行列車の乗客となり、辺鄙な町、最北の地ムルマンスクまで「岩絵」=ペトログリフを見にいく話だ。
旅の恥は掻き捨てとか、
袖振り合うも多生の縁とか、
人生を旅に喩えることわざはたくさんある。
鉱山で働くロシア人リョーハ。
ぶきっちょで純朴で優しいのだ。
見ているこちらを度々クスクス笑わせてくれる彼。
やっとこさ打ち解けたと思った矢先、コンパートメントの6号室が、せっかくの二人状態から(お邪魔虫の登場で) 三人になってしまったあのシチュエーションの、あの可笑しみと言ったらない。
同郷同士の「フィンランド語」と「英語」で仲良く話し始めるラウラとギター弾きのお邪魔虫野郎。これは辛いものなのだ。リョーハは英語はおろか、字を書くことさえこんなに苦手だから。
僕は太平洋航路で、僕を挟んだ両隣の席の男性二人に、僕の頭上を越えてのこのお喋りをやられてしまって、もう居たたまれずに とうとう席を移動した事があったし、
ヨーロッパの夜行列車では、往路は「それ」で往生したので、帰り便は話しかけられないようにshutoutオーラを出していた。
何時間も向かい合わせで、あるいは一晩かけて、小さな車内で、笑ったり感心したり、相手の生活や自分の故郷のエピソードを喋り続けるなんて
このリスニング持続の緊張と、英会話の気詰まり感ったらひとたまりもない。
それがコンパートメントなのだ。
そもそも かつての「馬車」の構造が列車の客室の造作にそのままひきづがれている、― それが「旅ガチャ」のコンパートメントなのだ。
うざい酔っぱらいの男リョーハと、構って欲しくないラウラ。可笑しくて可哀想で、共感しきりだ。
しかし、そんな僕にも「コンパートメントで良かった」と思えた旅があった ―
学生寮時代、真夜中に散歩に出て、何だかもう限界を感じて、世界の果まで逃げたくなって、下駄履きのままで、ふと乗ってしまった長崎までのブルートレイン。
こんなにも寂しい人や傷だらけのお客を一室に乗せて、二等寝台は西国までひた走るものだ。
長崎まで逃げる人あり、逃げてきたその長崎に辛酸の過去をおして戻る人あり。
みかんを食べながらみんなで励まし合った。
手を振って別れた。
・ ・
夜汽車は旅情だ。
いつの間にか停まっている駅で、ふと目が覚めて寝台から身を乗りだし、カーテンを少し開けて外を見てみる。
鉄軌は静まり、青白い蛍光灯のホームが見える。
何処を走ってきたのか、何処に停まっているのか。わからないけれど「人はみんな孤独だ」と、旅の途中、無人駅は教えてくれるだろう。
孤独を確かめるために、そして物思いにふけるために、人は夜汽車に乗るのかもしれない。
モスクワで聞いた本の言葉。
マリリン・モンローの言葉。
おばあさんの言葉。
ラウラに必要だった言葉が、彼女の乗り換え駅ごとの“時刻表"になる。
そして、この旅の物語の“羅針盤"になっている。
その後二人はどうなったかって?
それは観てのお楽しみ。
一昔前のラブ・ストーリーが、まるで凍土の中から現れたような、胸が痛くなる恋物語だった。
鉄道映画の逸品。
切なく優しい旅映画。人々の表情を楽しむ。
旅に出たくなりました
狭いコンパートメント
初対面で2人きり
横柄で粗暴なふるまい
揃ってしまったアンラッキー
それはひくなぁ…
目的地に辿り着くまで我慢しなきゃいけないなんて
楽しみにしていた旅の始まりに
大はずれくじをひいたどんより感も当然だ
ただでさえ、恋人のドタキャンからの続き
萎える、萎える
さあどうなる
そんな旅の始まりにふさわしい極寒の地が車窓に映る。
仄暗い景色の厳しい冷たさは
長く住むほどに人の辛抱強さを養うのだろうか。
駅に居た数人の年配者の防寒具に北風が刺し
見え隠れする横顔の線が何かを物語る。
そんなところも
昔住んだところの空気感にそっくりで
カチカチ凍るまつ毛の変な重さと
感覚がなくなる手足の先の他人ぽさを
今この時のように蘇らせながら
私は小窓を一緒に覗く。
朴訥で無愛想な車掌には
我が国の接客とちがうそれが
悪気ないそこでのスタンダードだったりすること。
求めすぎるとかすり傷などいくらでもつくこと。
慣れてくればそれもありかもで
なぜなら
それはその人の全てじゃないこともわかるから。
むしろ今、要らないやりすぎにでくわすときの
不自然さがちらつきもした。
それもその人の全てじゃないんだけれど。
食卓を花で飾ることを大切にするすてきな文化
耐熱ガラスに透ける茶葉の安らぎ
カーテン生地にとりこまれていくタバコの煙
人柄がみえる親切さの加減
水まわりの事情の不確かさと同じくらいに起きる絵に描いたような裏切り
そんなときにこそだから静かに伝わるやさしさなど。
最初からどう転がるかわからない不安や疑惑で
ずっと落ちつかず
いや大丈夫かな?とほっとしたりの繰り返しを
彼女目線で味わう。
やがて、だんだんと変わる印象と
お互いに行き来しだした
信頼や友情やほのかな想いも。
鋭い上目づかいに隠れていた
彼の不器用な人懐っこさややさしさ
少年のような純朴さをみつけながら
解されていく彼女の細やかな目の演技が逸品だ。
そしてふたりだけにわかるメッセージ。
変わっていく心の在り方からじんわりとした温かさが
伝わってくる心地よさに浸ったあとは
目的までの過程にも味わいがつまるそんな1人旅が
できた彼女の経験をうらやましくも思う。
何気なく観たが
感じることで変わり得る人生に似ていた
小さなコンパートメント。
なんてさりげなく心をゆする作品なんだ。
最悪だと思っていた相手が天使だった
可笑しくて可愛くて、シンと胸に沁みる
不凍港ムルマンスクは露軍最重要軍事拠点
フィンランド人監督ユホ・クオスマネンのインタビュー記事を読むと、本作は単純なレイルロード・ラブコメではなさそうなのである。おそらく、ロシアがウクライナに侵攻し、対露感情が一気に悪化する以前のフィンランドを寓話的に描いた作品なのだろう。第二次大戦時はナチスドイツに味方したフィンランドにとってロシアは因縁の相手国。「また奴らが攻めてくる」そんなフィンランドが過去の歴史において背負うことになったトラウマが、ここもと国内で勢いを増してきたことに対し、監督クオスマネンは大変な危惧を抱いているという。
ムルマンスク行きの列車に乗ったフィンランドからの留学生ラウラは、そこでロシア人肉体労働者リョーハと同室に。恋人のイリーナが2人で行くはずだった旅行をキャンセルしてしまったのだ。無礼千万なリョーハの振る舞が嫌で嫌でたまらなかったラウラだが、ふとしたきっかけでリョーハの優しさに触れ次第に考えを改めていくラウラだった.....「人間同士の触れ合いは、いつも部分的にすぎない」このマリリン・モンローの言葉は、イリーナとの肉体関係の暗喩とも、リョーハ=ロシアとラウラ=フィンランドの関係を暗示しているともいえなくない。
狭いコンパートメントを仕切るミニテーブルは、ロシアとフィンランドが過去何度も一戦を交えてきた国境のメタファーなのだろうか。知らない間にロシア人家族が客室に居座っているとラウラの機嫌が悪くなり、手癖の悪いフィンランド人ギタリストをラウラが客室に連れてくるとリョーハがへそを曲げてふて寝をする。2人の目的地が“ムルマンスク”という点がまた意味深なのである。えっ?ペトログリフを見たかっただけじゃないの?北部地方唯一の不凍港であるムルマンスクは、かつてはソ連軍とフィンランド軍の激戦地でもあり、現在はロシア軍の最重要軍事拠点でもあるのだ。かつて大韓航空機が撃墜された場所もここムルマンスクの地なのである。
イリーナが旅行をキャンセル、ホテルの従業員やタクシードライバーが案内を拒んだ真の理由は、軍事秘密漏洩を防ぐための当局の指示だったと思われる。ムルマンスクで起きた政治家暗殺事件などもリョーハが読み上げる新聞記事として、監督クオスマネンは映画に反映させたらしいのである。古代人が海岸の岩肌に描いたとされるペトログリフを見たがっている理由を聞かれたラウラがこう答えるのである。「過去を知れば現在を理解できるから」と。つまり、ソ連(ロシア)とフィンランドの過去の経緯を知らないと、本作に隠された政治意図も、フィンランドがNATOに加盟したがった理由も理解できませんよ、と言っているのだ。
しかし監督はこうも考えるのである。国籍やジェンダー、職業、体型?など社会的背景の全てが正反対のリョーハとラウラがまるで兄妹のようにお互いを思いやったように、敵対しているロシア人とフィンランド人であってもお互いを理解し合えるのではないか、と。「人はみんな孤独さ」とか「全てが遠く感じるわ」とか人は諦め顔で嘆くけれど、いつしかラウラの中で“ハイスタ・ヴィットゥ(くたばれ)”という言葉の意味が“I love you”に変容したように、両国関係が将来的に改善することを祈りながら。
ラストシーンの笑顔が良かった 70点
基準点 20点満点
1.派手な絵だったか? 18点
(俳優の顔、絵)
2.ドラマ性はあるか?12点
(主人公の成長、過去、悲しみなど)
3.アトラクションの連続だったか?6点
(見ててドキドキしたか?)
4.芸術性はあったか?14点
(ドラマとは違う)
5.その他 20点
(期待度は?)
寝台列車での話なので絵はずっと地味ですが、主人公と男性が絵を観に行くシーンはとても寒そうでガチでその現場に行っているので顔が真っ赤になっていて、俳優は体張るなぁと思った。
ドラマ性はあります。最初の冒頭で彼女と主人公は一緒に旅行するつもりが彼女が仕事の都合で行けず、そこから物語が進む。もう少し主人公の生い立ち、男性のあの態度、いろいろ深く知りたいなぁと思った。
場面はやっと後半になり列車から街中、絵を見に行くシーンになりますがずっとあの雰囲気。いやあれがまたいいのか。ドラマと違うのはちゃんとその場で行って撮影していること。これは1番デカい。編集やCGでもやれるがやはり現場に行くことがより面白い映画になるかもしれない。
期待は予想通り。ヒューマンドラマでした。この年代の背景を知ればより映画が楽しめると思う。1990年代の話で、当時はタイタニック🚢、売春、ビデオカメラが流行っていたそうです。なので主人公と男性の会話で出る理由です。
ラストシーンの男性から手紙を貰い、手紙をみた主人公の笑顔が忘れられない。とても良かった。
人生って上手くいかないし思い通りにならないけど、良い人間関係がいれば良いよねっていうメッセージなのかな?
国境線
ロシアとフィンランドは国境を隔てているという事実 これを知らないと今作は全く以て心に届かない、邦画によくあるソフトストーリー的プロットに落とし込む帰着に思考を選択してしまいがちになろう 偶々寝台列車の4人個室の相席になったフィンランド人とロシア人の孤独感と共感と、そして距離を縮める淡い思慕 勿論、それだけでも旅情の中での心の変遷を感じる列車ロードムービーとして成立するのだろうが、前述にある、政治的問題が今作のベース足らしめていることを忘れてはいけないと思う・・・ ということを観賞後に考察サイトを調べて自分も初めて知ったことを恥を承知で記載する
"ペトログラフ"云々は、単なる社会階級のメタファーに過ぎない 上流階級に憧れと、しがみつく疲労感 方や一発逆転を夢見ながら今日の生活も儘ならぬ身上 二人とも理想と現実のアンバランスに苛まれる現実なのであり、そんな二人を乗せた列車が国境と並行しながら極北へ進んでいく地理的描写が見事である 個々人は国が違えど同じ悩みや境遇の中で、シンパシーを感じ合える しかしこれが国家同士となると・・・・ 途端に敵同士に変換と相成る この不条理を作劇として落とし込んだ制作陣の意図をきちんとカンヌは評価した結果であろう、グランプリ受賞である 『ハイスタ・ヴィットゥ』のフリオチは、政治を薄めるための制作陣の中和剤といったところだろう 今作プロット、多分世界中の隣り合わせの国の映画制作として活用できる内容なのではないのだろうか、そしてそれが毎年可能な限り作り続けることが、世界の緊張を解きほぐすことが可能な装置の一つだと期待するのは、自分の単なる幻想なのだろうか・・・?
寝台列車
1990年代のモスクワが舞台。
意志薄弱なフィンランド人留学生ラウラと粗悪でぶっきらぼうなロシア人リョーハの同室になった寝台列車の珍道中。
本当に同室の方がだらしなく、アル中っぽかったら、そりゃ部屋も交換したくなるよね。
匂い、音、盗難など長い旅には切実な問題。
特殊な空間により、不器用な二人は人との付き合いを次第に学んでいく。
リョーハの強引な不思議な力により、古代のペテグリフに着いた二人は楽しそうだった。
正に恋人風。
最後に似顔絵つきクソッタレと書かれた手紙を読んだ時の表情は微笑ましかった。会った当初に愛してるは何て言うのと聞かれ、クソッタレと教えたのだ。
二人は短期間で人との付き合いを成し遂げた。そして、心と身体という自分をさらけ出した瞬間であった。+ラブストーリー。
全92件中、21~40件目を表示