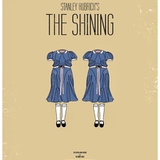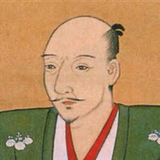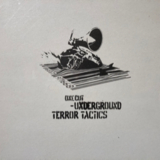こちらあみ子のレビュー・感想・評価
全116件中、21~40件目を表示
穏やかな家庭崩壊映画NO1
おそらく発達障害のようなものを持つ子どもの目線で送る映画
劇的ではなく穏やかに、時間をかけて蝕むように家庭崩壊していった
ところどころであみ子の周りの人が「うわ、こいつ、、、」みたいな目であみ子を見るのがしんどかった
無関心なお父さんなんて手を出す一歩手前までいってた
けど僕も小学生の頃はあみ子のようなクラスメイトをそういう目で見てた
後半の中学生パートからいよいよ周りから浮いてきて見ていられなかった
中学校は社会に出るロールプレイングみたいな場所だと思う
一人だけ制服のあっていないあみ子はまるで小学生のまま中学校に通ってるようなチグハグさがあった
冒頭の小学生の解像度が高くていい!
友達の名前呼んで「呼んだだけ」
道路で不恰好な側転をしだす とか
あみ子を中心に変わりゆく人たち
あみ子目線で見ると自由さや面白さでコミカルに描かれているように感じるが、別の角度から見ると凄く悲しくてもどかしいようなお話。
あみ子はいわゆる普通じゃない子なんだろうけど、あみ子にとってはそれが普通で、それを普通ではないと矯正するのは本人の良さまで消えてしまうような気もする
だがあみ子の行動や発言で学校では浮いているし家族も崩壊していく
自分が原因だなんて思っていないだろうし思っていたとしてもどこが問題なのかわかっていないだろう、それが悲しい、ひとりだけ取り残されているようで...
前半までは、あみ子にみんな向きあっていた、兄は「あの人はホクロか?それとも母ちゃんか?」などと言って、価値観を変えていこうと頑張っていたり、母親や父親も。
家族だからといえど、あみこと向きあうことに相当なエネルギーを使うだろうし、疲れてしまった。もどかしい。
最後、海で船に乗るお化けたちに波際から手を振る姿を見て、あみ子はそれでも元気に生きていくのだと決意のようなものが見えて、少しだけ救われたかなと思うような終わり方でした
幸せなときもあったのよ
家族だからなんでもうまく行くわけじゃない
自分の中に感じる純朴さに涙した
エンドロールに入った直後に涙があふれてきた。
理解できなかったあみ子の言動は、それを理解しようとしなかった私自身で間違いはない。
あみ子自身が誰にも理解されていないことを14歳くらいになってようやく気付き始めたときに、今までそれを理解しようとしかった自分に出会う。この物語は、私自身の物語かもしれない。
頭の中に流れ続けていた「お化けの歌」 父までもあみ子を放棄したことがあみ子のなかでゆっくりと理解されてゆく。
あみ子にとっての謎 それはその通り謎だが、この作品のテーマの象徴でもあるだろう。
このテーマを言葉でうまく説明できない。それは、あみ子にとっては純粋な興味だが、大人になるにつれその「謎」そのものへの興味が同世代たちと乖離していく。
最後にあみ子は朝方まで一睡もできずに、やがてはだしのままスキップしながら海辺まで行く。
目の前に何艘かののボート ボートをこぐ霊たちの姿 彼らはあみ子に手招きしている。
あみ子はただ手を振り返し続ける。
霊たちはやがて、再びボートを漕ぎ始めて去ってゆく。
誰かが道端から声を掛けた。
「おーい、まだ冷たいじゃろ?」
あみ子はその声に振り返りながら大きな声で返事をする。
「大丈夫じゃ!」
そう、あみ子は大丈夫なのだ。もう、何があっても大丈夫なのだ。
あみ子はあみ子のまま生きることをこの世界に向かって宣言したのだろう。
この瞬間、彼女の純朴な精神に打たれてしまった。
この作品は2000年ごろの広島を描いたのだろうか?
「はだしのゲン」という言葉と戦争当時や昭和40年代くらいまでいた元気な男の子の女の子バージョンがあみ子だろうか?
2000年以前まではあまり言われなかった発達障害。
今では何でもすぐに病名を付けられてしまう時代。
あみ子の義母は、最初はあみ子に対して温厚だったものの、死産したことと「弟の墓」なんてものを作ったことで完全にあみ子をシャットアウトしてしまう。
いまでいうネグレクトだろう。食事も作らず、家事もしない。
さて、
兄のコウタはなぜ不良グループの仲間になったのだろう?
コウタは義母がまだ臨月の時すでに10円玉ハゲを作っていた。彼は何らかのストレスを抱えていたと思われる。
その時コウタは「あまり母さんのほくろばかり見るな」という。母に人一倍気を使っているのが伺える。そのストレスがコウタのハゲだったのだろう。
「弟の墓」
これがすべての元凶だったのだろうか? 俯瞰している視聴者からは、あみ子がした行為はそこまで咎めることはできないように思うが、義母が泣き喚いたことでそれが「元凶」とされたのだろうか?
コウタもこれがきっかけであみ子に辛く当たるようになった。
コウタはなぜそこまで変化してしまったのだろう?
あみ子が作る墓には母の墓はないことから、離婚したと考える。
その原因を作ったのは、少なくともコウタの認識ではあみ子だったのかもしれない。
父は最後まであみ子の世話をしていたことから、最初にあみ子から手を引いたのが母だったのだろう。
母を初めて紹介されたときコウタは、「俺のハゲを見ろ。オレはハゲか兄か? お父ちゃんは眼鏡かお父ちゃんか? あの人は母かほくろか?」と尋ねる。
一般の人から見れば奇異に見えてしまうあみ子の言動を何とか修正しようと頑張っていたが、墓の件でコウタの心が折れてしまったのだろう。
あみ子は発達障害なのかもしれない。勝手気ままに学校に来たり来なかったり 勉強もしないし字も書けない。今この瞬間に興味惹かれることだけがあみ子を動かしている。
そして人々はすべてあみ子をおかしな子としてレッテルを貼っている。
兄が暴走族でなかったなら、いじめの対象だった。しかしこの作品のテーマはいじめではない。兄の変化はそのための伏線だったのだろう。
この作品の基本的な視点は「あみ子」 彼女そのものだ。元気で活発で、他人を傷つけたりはしない。
ただ人と同じことができないだけだ。枠に縛られていることができないだけだ。
また、この作品は教育システムや社会システムに問題を投げかけているのでもない。
母がいなくなり、また新しい母がやってきて、弟が生まれる期待。それが妹だったとずっと知らないままでいたのは、「みんな秘密にする いつも 毎日」
そうして、みんなから相手にされなくなってゆく。
「私、気持ち悪かったの? どこが? 教えて、全部」
みんなからそう思われていたことを男子から聞かされたとき、ほんの少しだけ周囲との齟齬があったことを感じ取る。
その男子が「それはワシだけの秘密じゃ」と言ったのは、それを口に出すことが自分自身に返って来ることを悟ったからだろうか。心の底では、誰もあみ子を裁くことなどできないことを知っていたのかもしれない。
男子から教えられた「鷲尾佳典」という漢字 ノリ君の本当の名前 それを忘れまいと心に刻むあみ子。
大切なものがひとつひとつ消えていくのを実感として心に降りてくる。
彼女の心にほんの一瞬触れた男子は、彼女を傷つけるような言葉は間違っても言えなくなってしまったのだろう。
引っ越し 転校 おばあちゃん宅 大きなカエルに大きな蛇 でも、同じ年頃の子供たちは誰もいない。
夜中にしたトランプゲーム やがて父から聞かされる「本当のこと」
あみ子には彼女なりに考えることがあったのだろう。
あの時、
引っ越し直前に兄がやってきて、突然「謎」だった霊の音の正体を暴いて見せた。
「ウォ~リャ~」
鳩の巣と1個の卵を外に放り投げた。
生まれなかった命 その卵はきっと「妹」だったのだ。
木に引っ掛かった卵にはどんな意味があるのだろう?
何かの可能性を示しているのだろうか?
明け方の浜辺で見えたボート
あみ子には霊になるという選択もあった。
でもあみ子は端からそんな選択肢は持たない。
その霊たちを見送るだけ。あみ子の些細な「謎」の根源がゆっくりと昇華されていった。
中学時代までの想い出たち
すべてに別れを告げて彼女は大きな声で言った。
「大丈夫じゃ!」
この訳の分からない作品に心打たれる自分がわからない。
言葉にならない「赦し」のようなものを感じるだけだ。
リアルでいい。
確かにホクロが気になります。
広島で暮らす四人家族。主人公のあみ子は発達障害、多動症なのか?他の子供達とは違う子供。母(尾野真千子)は家で書道を教えている。父も兄も優しく穏やかな家族。母は、妊娠中だったが子供が死産になってしまう。あみ子は思いつくと行動に出す為庭に亡くなった子供の墓を作り母に見せた事で母はおかしくなり徐々に家庭が良くない方向へと進むストーリー。
とてもセンシティブで、衝撃的、切なくて、残酷に描いた映画だが良く表現したなと感じます。
あみ子は、ただ思った事、感じた事を行動にしてしまい相手の気持ちが理解出来ないが故に、周囲の人間も恐怖や不快に感じる。あみ子は、確かに理解もしているし、会話も成立する所から普通の子供と一緒に学ばせるのも理解は出来るが!学校側もあみ子を見て手を差し伸べる事が出来なかったのか?なんて思ってしまう。先生も家庭訪問に来て、母親が病気になっている事は父と話している場面がある。
学校でも、唯一あみ子に一番自然に接する坊主の青年がいたのが、救いでしたね。
兄も、たぶん一番あみ子の理解者じゃないのかな?回想シーンで兄とあみ子が歩きながら、母の事をホクロと言うあみ子にきちんとお母さんで、ハゲは兄、メガネは父親と会話するシーンは心に残りましたね。しかし、不良に走ってしまう。状況を受け止めるには、無理だったんだろうと感じて切なくなってしまう。決して家族は誰一人悪くないのでは?と思う。
あみ子は、裸足が好きで感性が敏感すぎるのでは?きっと本当に霊的な存在も見えていてラストでのシーンであみ子が手を振っているのは、あみ子なりの選択で「大丈夫❗️」と言ったのなら、前向きなラストにもとれました。
全編通して、家族意外の関わりがあまり表現されていないので、社会から孤立している家族である様にも映り社会が冷たくも映ります。そこで手を差し伸べてくれたのが、祖母だった。
あみ子は、これが個性だから仕方ないと一言で片付けられない内容なだけに実際に悩んでいる家族もいるだろう。こういった子供もいると言う大人の理解が必要な社会が確立することなのか?なんて考えさせられる映画でした。
心をえぐられる名作
大沢一菜の演技力!
この映画を言葉で説明するのは簡単じゃない。 この小説を読んだり、 この映画を見たりしてほしいと思う。
動画配信で映画「こちらあみ子」を見た。
2022年製作/104分/G/日本
配給:アークエンタテインメント
劇場公開日:2022年7月8日
大沢一菜
井浦新
尾野真千子
奥村天晴
大関悠士
橘高亨牧
幡田美保
黒木詔子
一木良彦
映画「星の子」を見て原作者、今村夏子の别の作品も見たくなった。
見てみるとこれは「星の子」とはまったく違う映画だなと感じた。
しかし、よく考えてみると子供が主人公で、
舞台は学校と家庭という点は同じだなと思った。
広島県に住むあみ子は変わった子どもだった。
自分の感情にまっすぐで、
他人の気持ちを気にしない。
あみ子の同級生であるのり君が、
お母さんから「孝太君の妹は変な子じゃけどいじめたりしちゃいけんよって。なんか変なことしようとしたら注意してあげるんよ」と言われている。
父親と母親(井浦新、尾野真千子)とお兄ちゃんはあみ子に優しい。
あみ子の日常を淡々と描く。
ある時お兄ちゃんが唐突に不良化した。
タバコを吸う。
暴走族に入る。
家に帰らなくなる。
父親は全く注意しない。
母親も注意しない。
あみ子は小学校でも中学校でも変わらず同じような生活を続けていた。
ある日保健室で事件が起こる。
大好きなのり君に殴られてあみ子は鼻を骨折する大怪我を追う。
自宅に帰ると父親に言われる。
「あみ子、引っ越ししようか」
父親と一緒に祖母の家に引っ越しした。
数日たった日、父親に言われる、
「お父さんは家に帰らなければいけんのよ」
あみ子は祖母の家に置き去りにされた。
これは障害を持った子供の話だった。
あみ子の同級生の坊主頭(橘高亨牧)が毒舌ながらもあみ子に優しかったのは印象的だった。
この映画を言葉で説明するのは簡単じゃない。
この小説を読んだり、
この映画を見たりしてほしいと思う。
満足度は5点満点で4点☆☆☆☆です。
「おばけなんてないさ!おばけなんてうそさ!」あみ子にとっての“おばけ”とは…?
アマプラで無料鑑賞できる『アタック・オブ・ザ・キラートマト』とか『トリプルヘッド・ジョーズ』とか見つけたんで、そういうの観て駄文書こうかと思ってたんですよね、実は。このアホは。
ですが、ここのところ、レビュアーさんが極端に少ない作品のレビューしか書いてないませんでした。
それも寂しいので“普通の映画”を観ることにした次第です。
いつも女装で観に行く映画館でフライヤーをもらってきて以来、気にはなっていた作品だったし。(しれっと女装絡めてるし・笑)
写真のぽけーっとした表情の奇妙な印象の子が、なぜかツボだったんですよ。
課金制だったので、どうせならと思いTSUTAYAへGo!しました。
“ちなみに”同時に借りてきたのって、やっぱり『インプリント~ぼっけえきょうてえ~』だったりするの。レビュアーさん、わずか2名の作品(笑)の、3人目に名を連ねようかと思ったんですが(懲りてねぇ…)そこは初志貫徹です。
相変わらず、まくらが長いです。ごめんなさい。では行きます『こちらあみ子』レビューです。
この作品のテーマに関わるキーワードっぽい“おばけ”って一体何?と思い、そこを考えてみることにしました。
結論から述べると、それはあみ子が抱える「自分でもよくわからない、漠然とした寂しさという恐怖」であったように感じました。
喜怒哀楽の、最初と終わり以外の感情を持ち合わせていないように見える「普通の子とはちょっと違う」彼女でですが、あと二個を認めてしまうと、自分自身が壊れてしまうこと。それを彼女自身の本能が理解しているように思えましました。
誰もが本能的に感じている“死”への恐怖に通じるような。
あからさまに死の匂いが漂っていたラストシーンなんて、その最たるものだと思いました。
“おばけ”たちの手招きに応えてしまういこと=どうしようもない「寂しいという感情」に呑まれてしまうこと=自我の崩壊=死にたいという気持ちが芽生えてしまうこと。なのでは?と。えつ、考えすぎ?
あみ子自身に「自我が崩壊する」という観念はないにせよ、それこそが「漠然とした恐怖」=“おばけ”の正体だったに違いないと思って。
最後の台詞の「大丈夫じゃー!」は、彼女が“おばけ”=「恐怖」に真正面から向き合う、もしくは、言えば立ち向かいたいという決意の“バイバイ”ではなかったのでは?と解釈したかったです。そうでないと、彼女があまりにも不憫すぎます。救いがなさすぎます。えつ、考えすぎ?
そんな彼女だからこそ、のり君という“希望”にすがりたかったのだと思えて。希望を見つめている時だけ彼女は、幸せな時間を過ごせていたのだと思い。傍目には滑稽としか映らなかったとしても。
『ダンサー・イン・ザ・ダーク』でセルマが妄想の中でダンスを踊っていたかの如く。えつ、考えすぎ?
だから、鼻骨を折られるほど殴られても、彼女にとってのそれは、のり君と触れ合えるかけがいのない幸福な出来事だったのかな?と思えて。いつまでも剥がすことのない鼻の絆創膏は、あみ子にとっての“勲章”だったに違いないと思って。
“ちなみに”私、初見時にはあのシーンで笑ってしまったんですよ。
「好きじゃー!」→「殺ーす!」→「好きじゃー!」→「殺ーす!」→「好きじゃー!」→「殺ーす!」(笑)
ところが二度目に観ると、決して笑えない自分がいて。
先に述べたように、あみ子の、のり君への想いが、滑稽なまでに描かれている哀しいシーンだったと思うから。えつ、考えすぎ?
キーアイテムのトランシーバーは、言うまでもなく、彼女と他者とのコミュニケーションを表現しており。
決して応答のない一方通行の通話は「私はここにいますよ!」「私に気づいて!」のSOS信号だったのかなと思ったんですよ。えつ、考えすぎ?
そして、触れずにはいられないことが。銀幕初出演?(色々と調べたんですが、確たる資料が見つかりませんでした)の大沢一菜がとてもよかったの。
森井監督は、きっと一菜さんに演技をさせなかったのだと思いました。
あくまでも“素の”少女の姿を撮ることで、あみ子というキャラクターを創りたかったんだろうなぁと思って。
そのイメージにドンピシャとハマった少女が一菜さんだったと思って。
このあたり、先日観た『秘密の森の、その向こう』の少女の描き方と同じように感じました。
が…如何に?
アホの私にしては、珍しく真面目な考察系レビュー。
なのに、どうしてもわからなかったのは、劇中に登場する小動物の数々。エンドロールでもイラストが描かれていたので、きっと何かのサインだったと思うのですが。
やっぱりアホの私にはさっぱりでした。
言葉にできない心の声をきけ!
作品序盤のあみ子が家族の写真を撮る場面、ゆるゆるで大らかな家族だなという印象を受けた。
この段階では、あみ子に対して、ちょっと変わった子くらいの認識だったので、あみ子が変わっているところを家族がよく分かっていて、それを受け入れている優しい家族に見えた。
物語が進み、あみ子が発達障害であろうことが分かってくる。
同じころにあみ子が、家族が崩壊してしまうようなことをしでかす。
こうなると、序盤に感じていたゆるくて優しそうな家族像が間違っていたことに気づき始める。
タイトルの「こちらあみ子」はトランシーバーに向かって言うあみ子のセリフだが、要はあみ子からの呼びかけである。私はここにいる。誰か応えてという呼びかけだ。
裏を返せば、誰もあみ子の呼びかけに応えていないことを意味する。
「お化けなんてないさ」と歌うあみ子の、「だけどちょっと、だけどちょっと、ぼくだってこわいな」のところが「私だってさみしい」と言っているように見えた瞬間に、言葉にできないあみ子の心がガツンと流れ込んできた気がした。
観ていてあみ子の呼びかけに自分も応えていなかったのである。
私が小学生や中学生だったころ同級生にあみ子のような子がいた。今までに数人と関わりをもったことがある。
その時の自分は普通に接していた、つもりだった。バカにしたりしていない、つもりだった。
しかし今考えてみると、自分はあみ子のお父さんとあまりかわらないことに気付いた。
それは、話が複雑化したときや、理由など、言っても解らないだろうと言わなかったことだ。
「なんで?」に対して、真実を言わず、適当に流す。自分は無意識にバカにしていたのである。
つまり、大らかそうに見えた父は、最もあみ子に向き合っていなかったことがわかるのだ。
優しく振る舞っているように見えても、家族として最低限の接触だけをして、あみ子に対する真摯さが足りていないのだ。
序盤に感じていた優しそうな家族は、ある意味で虚構だったといえる。
あみ子が起こした事件によって、頑張って支えようとしていた兄は崩壊。母はもっと直接的なダメージにより崩壊。父はあみ子を更に突き離すようになる。
唯一、あみ子に対して対等で真摯に向き合っていたお調子者のクラスメイトは、あみ子の「ねえ、なんでなん?」という問いに、過去の私とは全く違う理由で「秘密」と答える。
しかしそれは、奇しくもあみ子の孤立を生み出してしまった。
エンディング、怖さを感じるシークエンスだったが、最悪は免れた。
しかし「大丈夫」と答えるあみ子が本当に大丈夫だとは思えない。
あみ子は自分の複雑な感情を言葉にできない。言葉にできない心の声をきけ!
普通だと描かれないけれど視点の特異な映画
この映画のテーマが、「タブー」ですね。
発達障害を持つ小学生の「あみ子」の存在が周囲の人々を
変えて行く。
それが良い方向へ・・・ではなくて悪い影響を与えて
悪い方へ悪い方へ転がっていくストーリーでした。
普通の小説家はこんな発達障害児童の家庭への悪影響。
そんなことをテーマにしませんし、書かないと思う。
タブーです。
障害児の暗い部分、負の側面、家族への悪影響・・・なんて、
書けないですよ。
原作者の今村夏子さんはこの作品などで太宰治文学賞」と
「三島由紀夫賞」を受賞した。
映画からはちょっと離れますが、「こちらあみ子」に作者は
この作品に強い思い入れがあります。
大学卒業後に清掃のアルバイトをしていた、など人付き合いが苦手。
もしかしたら「あみ子」は作者の分身なのかもしれない。
全部、あみこの存在と言動のせい・・・とは限らないけれど、
映画を観てれば、あみ子のせい・・・そう思えてきます。
義母(尾野真千子)が死産したのは、あみ子のせいではない。
しかし庭に「弟の墓」と札を立てて、わざわざお母さんを呼びに行って、
「弟のお墓だよ」と見せつけて、
結果的にお母さんは号泣して、そこから病気がちになり、
精神に不調をきたし、入退院を繰り返す。
優しかった兄は中学で喫煙しはじめて暴走族に入り学校へ行かなくなる。
両親は離婚して、
あみ子は引っ越しとの名目でおばあちゃんの家に連れて行かれ、
お父さんに置いてきぼりにされる。
そしてあみ子の憧れの同級生の「のり君」が、
病んできて、「好きじゃー」あみ子、「殺すー」と、のり君。
「好きじゃー」「殺すー」「好きじゃー」を繰り返して、
結果、のり君はあみ子に暴力を振るい、
それもあみ子に馬乗りになり鼻の骨を折り大出血!!
すごく怖い話です。
それって、あみ子が優しい「のり君」を変えたってこと!?
作家が病んでるのかな?
発達障害児やダウン症の子供が家族にいても、健やかな家庭も多いと
思います。
事実、多動性障害児で手に負えなかった男の子が、
大人になり凄く人の心の分かる中学校教師に成長した例を知っています。
確かに問題提起映画。
障害児が家庭の不幸の連鎖を引き起こす、みたいな視点は
ちょっと極端ですね。
あみ子は少しづつ成長して、空気を読める大人に成長するかもしれない。
もしかしたら、成長しないかもしれない。
だけど「生きたい」と心の底から思っている。
この映画が描いた世界は、パンドラの箱を開けた側面がある。
ホラーよりも怖い映画でした。
印象に残る映画
てんとう虫やカエルをアップしているシーンの意図を知りたい。
あみ子が怖がるベランダからの音の正体がわかって良かった。
わからないのは怖い。
広島弁で話す自然な雰囲気がとても良かった。
”秘密だらけの世の中”イコール”みんな何考えてるかわからない世の中”イコール”怖いオバケの世界”。
最後にオバケたちにサヨナラしたのは面白い描写だと思った。
今作では描かれていないが、ラストの後、おばあちゃんとどのように過ごし、どう成長していくのか楽しみだ。希望の持てる終わり方だった。
エンディングで流れた主題歌『もしもし』(作詞・作曲:青葉市子)が、とても素敵な曲で尾を引く。
あみ子からのメッセージ
しんど過ぎたのと、なぜ作ったのかが全く理解できなかった
予告やいろんな媒体の宣伝、ネタバレに警戒し高評価のレビュー内容は確認せずポイントだけを見て鑑賞したところ、予想外の作品だったので面食らいました
ADHDの方々とそのご家族・周囲の方々のご苦労は他人には理解できないほどの心底計り知れないものがあると思っていますので、容易く手をかけるべきではないテーマだと思いました
本作を高評価する寛容な気持ちにはとてもなれず、むしろこういうのをフィクションの映画で作る意図が全く理解できないな、という一言が私の感想です
昨年「福田村事件」「月」など実話の映像化作品を観て震える思いをし、その事を残す偉業に挑んだ作り手へ敬意を感じ素晴らしいと思いましたが、本作はそれらとは全く次元の違う事だと思いました
全116件中、21~40件目を表示