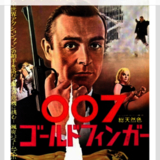エンドロールのつづきのレビュー・感想・評価
全103件中、21~40件目を表示
「映画」に対する想いを、個人的な熱情を超えた奥行きで描いた一作
映画監督が自らのキャリアの原点を振り返る作品は、もともと数多く作られてきたけど、『フェイブルマンズ』と同時期に本作が公開されたという偶然は興味深いです。
最初から最後まで、「映画」そのものだけでなく、映像芸術としての映画を築き上げてきた先達に対する敬意と愛情が全編に溢れた作品です。どの場面・挿話にも、パン・ナリ監督が影響を受けた監督の影響を入れ込んでいて、作中の少年(バビン・ラバリ)が本当にこの映画を作ったんだなー、と心動かされます。
キューブリックの影響は特に大きいようで、『フェイブルマンズ 』同様、この作品でも随所で光源を意図的に画面に入れ込む、プラクティカル・ライティングを用いた映像が随所に使われています。
貧困やカーストなど、インドの社会問題も物語に大きく影響してきますが、声高な告発調ではなく、少年たちが逆境の中でも映画に対する情熱を燃やし続ける姿に描写の焦点を絞り込んでいる点がとても印象的でした。
映画の光学的な原理を説明する場面は、『エンパイア・オブ・ライト』のある場面と奇妙に符合していますが、こちらの作品はユーモラスかつ皮肉が効いていて、あくまで物理現象として説明する『エンパイア』との対照性が面白いです。
まさにタイトル通り、エンドロールに到達した映画フィルムの行く先を通じて、時代が移り変わっても先達の魂は生き続けることを確信を持って提示した結末は非常に素晴らしいです。
英語が出来る人とそれ以外
インドの田舎町で暮らす9歳の少年サマイは、学校に通いながら父のチャイ売りを手伝っていた。バラモンの家系で、厳格な父は映画を低俗なものと考えているが、信仰するカーリー女神の映画だけは特別だと言い、家族で映画を見に行った。初めて経験する映画の世界に心を奪われたサマイは再び映画館に忍び込んだが、チケット代を払えず追い出された。それを見た映写技師ファザルは、料理上手なサマイの母が作る弁当と引き換えに映写室から映画を見せてくれた。サマイは映写窓から見る様々な映画に引き込まれ、自分も映画を作りたいと思うようになった、というインドの映画監督の実体験に基づく話。
カーストの頂点、バラモンの家系なのにチァイ売りに落ちぶれた家族が不憫だと感じたが、下からのし上がっていく人もいれば、上から落ちていく人もいる。家柄なんて現代では役に立たないものだとつくづく思わされる。インドで英語の出来る事を重要と考えられているのもよくわかった。
お母さんの作る料理はどれも美味しそうだった。
サマイ役のバビン・ラバリが魅力的だったし、お母さん役の女優は美しかった。
嘘が上手いやつは頭が良い
映画に愛をこめて
映画を通して失ったもの、得るもの
もう少し…
インド映画2本目にして、まさかの「RRR」越え!
うわー、いい映画、「ニューシネマパラダイス」を思い出す。
自分の運命に出合うって、こういうことなんだね。
小学生くらいの男の子が、親や友人や故郷を離れて、知らない人を頼って未知の街に行くことを即決できるくらいの、抗いがたい引力。
息子のまっすぐな情熱に触れて、息子の背中を押す父親。
見守り、抱きしめ、おいしいご飯を用意し、息子にとって最大の癒しである母親。
子どもが自分たちのもとから力強く羽ばたいていくなんて、最高。
日本に比べて、衣食住は十分でないが、遠くない未来世界の中心となるインド。
彼らの可能性は計り知れない。
子どもたちは、ハングリーさを抱えて、キラキラした瞳で生きている。
衣食住足りて、世界がすごいスピードで変化しているのに、変わらないことを選択している日本。
国としても、個人としても、未来予想図が描けない。
何がしたいか分からなくて、考えるのも面倒で、毎日何となく生きている。
住むのに楽なのは日本だけど、ワクワク生きるならインドかな。
今度は、アグラやバラナシ、リシュケシュ、バンガロール、観光地でない町にも行ってみたい!
インドのパワーに触れて、主人公のように自分の運命に気付きたいものです。
邦題いいですね
インドの逞しさ
映画への愛に溢れた作品
監督のほとんど実話という本作は、「ニューシネマパラダイス」を彷彿とさせる映画に魅せられた少年の物語。
かなり過酷で娯楽がない暮らしの中に、主人公サマイに差した光である映画。どれだけかけがえのないものなのかが、直向きなサマイの姿勢から伝わり、胸を打ちます。
インドの田舎町という閉鎖的な環境下にあり、家族や友人との関係も、日本でしか暮らしたことがない私から見るとかなり特殊。文化的にも理解し難いところもありましたが、映画に触れることで煌めく目の輝き、逆にクライマックスでの虚しさが主演バビン・ラバリくんの素晴らしい演技により体現されていて、じわーーっと心が熱くなっていきました。
ちょっとアート的な要素が思ったより強く、じーーっくり描くわりに意味を感じるのが難しい場面も多いため、観る人は選ぶかも。
とはいえ、監督の映画愛に溢れた温かく熱い作品でしたし、少年たちがとても可愛かったです。
「インド映画の新たな一面」
少年(監督)の映画への憧れが伝わってくる作品
まず・・・。
お母さんが作る料理が美味そう!!!
愛情たっぷりお弁当。そりゃ、タダ鑑賞と取引できまっせ!僕もいただきたーーーい!
料理の過程を見せてくれるのですが・・・空腹で見ると絶対にお腹鳴りますよww
さて、本作。
監督自身の映画愛がそのまんま形になったような印象を持ちました。とにかく全編キラッキラしてるのです。
☆七色キラキラ☆
きっと主人公の少年を通して監督自身の映画、過去の作品へのリスペクト、映画界への夢、期待などなどマルっと含んだワクワクする明日を描いているのではないでしょうか?ラスト、フィルムが形を変えて人々を豊かにする・・なんて描写も監督の映画愛を感じちゃいますね。
本作のキーワードは「光」なんじゃないかなぁ?って思います。
作中、光を使った印象的なシーンが数多く出てきます。光があるから映し出される色と景色。
「光を捕まえにいく」・・・素敵なセリフだったなぁ。映像って光がなければ見れないんですよね。ガラスの破片も光がなければ綺麗には見えない。未来が決まっているようなあの土地で心奪われた「映画」を作り出す「光」はサマイにとっての「夢」であり「未来」だったのかもしれないです。光が平凡な日常に色をつけてくれたってところでしょうか?その色は(映画も含めて)人々の心を豊かにする。そんな魔法のようなものに心奪われていくサマイを愛しく感じて仕方ない作品です。
そして彼を見守る家族、友達との温かいストレートなストーリーはすっと心に入ってきて爽やかな気持ちにさせてくれます。サマイのキラキラした熱情を映画館で楽しんで、さらに映画が好きになってしまいました。
ニュー・シネマ・パラダイスのインド版と思いきや…
全く違いますね。
むしろ、違っていてホッとしました。
これ、実話なんですよね。
凄いですよね。
今後のパン・ナリン作品に注目します。
親の反対を押し切ってでも、好きなことを貫き通す
どんなにお腹が空いても、好きなことに没頭する
どんな困難にも諦めずに好きなことだけに集中する
昔、林修先生が「好きなことを仕事にするのは、とてもリスクがあるから、出来ることを仕事にしなさい。好きなことを仕事にして成功しているのは、ほんの僅かか人たちだけだ」と。
ビートたけしさんも同じことを数十年前に言っていました。
だからこそ、男の憧れの物語なのです。
また、成功者と脱落者の違いを、主人公のサマイとその父を比べて分かりやすく描いていると思いきや、最後のシーンで父のサマイに対する愛情は、これも心豊かな生き方なんだろうと、ついウルっと来てしまいました。
インド映画は、好き嫌いが分かれますが、この作品はいわゆる「歌と踊りのインド映画」ではなく、映画好きはもちろん、多くの人が感動すると思います。
サマイの演技が上手い、そしてサマイが可愛い。
出てくる子供たちがみんな可愛い。
サマイのお母さんが、綺麗で優しくて、そして料理が上手で。
今日の夜はインド料理屋さんに行くことにしました(^^)
ボーイ・ミーツ・ムービー 芸術的な演出に引き込まれる
インドの貧しい家庭に生まれた少年は、学校に通いながら父親のチャイ売りを手伝う。
少年はある日「これきりだ」と一言付け加えられながら、家族で映画を観に行った。
映写機から伸びる光、映画を運ぶその光に少年は心を一瞬にして奪われる。
映写機の光に囚われた少年の心情は、言葉ではなく芸術的なカットで描かれているのがぐっとくる。
どことなく『ニュー・シネマ・パラダイス』に似た感じがするが、
この映画では親子関係や貧困についても、細かに描写されている。
暖かい暮らしの中にいる私から見たら、虐待や犯罪など完全にアウトな要素もたくさんあるんだけど、
社会の発展から取り残されたインドの貧しい地域では、当たり前で許容範囲の現実なんだと思うと、
改めて貧困問題について考えさせられる。
辛さがにじむ社会問題の部分はさておき、境遇は全く異なるのになぜか少年に共感を覚える。
それはきっと私たちの記憶の中にもこの少年のように映画に心を奪われた瞬間の煌めきが残っているからだと思う。
あぁ、映画好きになって良かった…
そう思わせてくれる素敵な作品だった。
インド映画なの?!素晴らし過ぎる!!
全103件中、21~40件目を表示