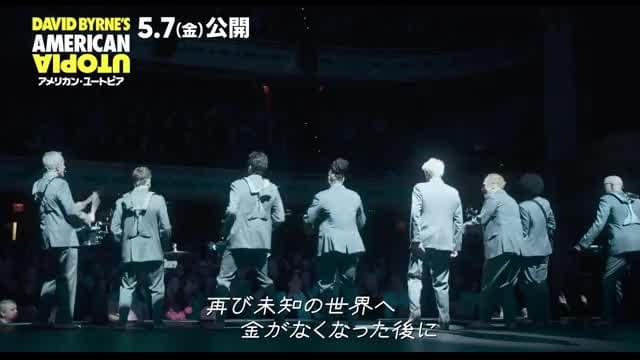アメリカン・ユートピアのレビュー・感想・評価
全126件中、101~120件目を表示
物理学の教授みたいな風貌
自分の中で昔からデヴィッド・バーンのイメージは相反する二面性がある。
ひとつは、ものすごくインテリで書斎でバッハや武満を聴いていそうなイメージ。
もうひとつは、ものすごくプリミティブで、南米やアフリカのリズムを積極的に取り入れる人。
その相反性は、フォーマルなスーツに裸足という本作の衣装にも表れているし、また、ミニマルで都会的な洗練を感じる舞台セットに対して、音楽はパーカッション中心の民族的エスニック性をも感じさせるものだったりする。
彼の身体性を示すダンスや政治的主張を見るに、インテリ色の方が強い人なのかなと、個人的には思っている。
久しぶりにトーキング・ヘッズのアルバムでも聴き直してみるかな。
映画館で観ないと後悔するじょ
裸足で鑑賞するのがベストか?
正直言って、トーキングヘッズの曲は「サイコキラー」しか知らない。無理やり参加させられたパンクバンドで演奏し、なんだか一番盛り上がっていたような記憶がある。多分、先輩にアルバムごと聴かされていたのですが、まったく覚えてません・・・というのがトーキングヘッズの思い出です。
コンサートなのかショーなのか、踊りメインだった気もするし、見事な撮影と音響編集によってあたかもコンサートの客席で鑑賞している気分になりました。デビッド・バーンを中心にパーカッション6人(最後は全員)の12人編成。みんな動けるようにケーブルなしの楽器とヘッドセットマイクによる演奏で、マーチングバンドのようだった。
21曲もあったのですが、逆に考えると一曲一曲が短くて聴きやすい。全体的にメッセージソングといった感じで、MCでは選挙の投票率について面白おかしく語るバーン氏。ただ、トーキングヘッズの曲よりもジャネール・モネイの曲「Hell You Talmbout」が最も感動的だった。泣いたよ・・・ネットでも動画を見ることができるけど、写真付きではない。
有色人種の差別や虐待に反旗を掲げたコンサート。バンドメンバーも出身地がバラバラ、多様性を象徴している。その中でもギターのアンジー・スワンが良かったな~女の子のギタリストって、どうも惹かれてしまう。『THIS IS IT』のオリアンティみたいに・・・
ライブのよさを再認識
トーキング・ヘッズは名前だけは覚えているが、当時自分の周りでは、デュラン・デュランやJapanが騒がれていて、誰もトーキング・ヘッズのレコードを持っていないからラジオで数曲聴いたくらい。
パフォーマンスは、素晴らしい。60才後半とは思えないデヴィッド・バーンの高音の伸び。パーカッションが6人もいて、いろいろな打楽器から響く音が重なりあって伝わってくる。爆音モードにしてほしい。
この作品を見ながらライブは、パフォーマーと観客で作りあげるものだと再認識した。ミュージシャンの調子がよくて、オーディエンスの熱気が最高に達すると、場内はゾーンに入る。そう何度もないが、この体験をすると一生忘れられない。
早くマスクなしでライブに行ける日がきますように。
本当に生演奏なの?
デビッド・バーンについて、何も知らずに鑑賞。
パッと見で、アメリカ人っぽくないなあと思ったら(偏見?)、スコットランド出身のようだ。
声域は広くないが、年のわりには、きれいで伸びやかな声だ。
冒頭の「脳」をめぐる知的な語りや、ソフトな物腰を見ると、いわゆる“ロックスター”とは肌合いの異なる、インテリなのだろうなと推測。
会場は“小型のオペラハウス”のようなところで、舞台はシックな青みがかったグレーで統一されている。
完全ワイヤレスで、ミニマムどころか、セットもスピーカーも大型モニターも、なんにもない。
とても、モダンな香りに満ちたステージだ。
後半のメンバー紹介のところで、「本当に生演奏なの?」と聞かれると語っていたが、自分もボーカル以外は、「本当に生演奏なの?」と最初から思っていた。
多くが「パーカッション」と「ベース」のリズムセクションで成り立っており、“生っぽい音”に極めて乏しいのだ。
「タンバリン」や「マラカス」や「ボンゴ」っぽい楽器なども出てきて、リズム系はめちゃくちゃ充実している。
その一方で、「キーボード」は控えめで、「ギター」でさえ基本的にリズムギターであって、ソロパートがほとんどない。
演奏者の手の動きと音が同期しているので生演奏と分かるが、音だけ聴けば生演奏っぽくないし、“打ち込み”でも何とかなりそうだ。
デジタルよりも、アナログ好きな自分には、好きなれそうにない音楽である。
そんな中で、唯一、“生っぽい音”で自分を楽しませてくれたのが、「ベース」のボビー・ウーテンだった。
自分は、“5弦ベース”なんて見たのは初めてだ。
歌って踊って大活躍なのであるが、そんな中でも正確に演奏しているし(あまりに正確なので、これまた録音かと思ってしまう(笑))、バンドリーダーの「キーボード」よりも、演奏の中心になっている気がする。
ステージが終わった後、カーテン裏でデビッド・バーンが、ボビーと固いハグをしていたが、なるほどそうだろう、と思った。
自分は正直なところ、音にもパフォーマンスにも慣れてきた開始30分で、すでに飽きてしまった。
「この後、まだ1時間もやるの?」という感じだった。
デビッド・バーンは、“詩”と“アレンジ”のミュージシャンであって、“メロディー”の人ではないと思う。
ユーモアもあるし、メッセージ性も高いし、本当に素晴らしいステージだった。
しかし、「音楽そのものが好きか?」となると、自分は「NO」だ。
グレーに際立つ真っ赤な口紅
インテリ好きを刺激する様な語りかけからはじまるショー。
トーキングヘッズよりラストエンペラーのイメージが強いから、このMCはしっくりと感じニヤニヤワクワクした。
しかし、シンプルな舞台と裸足の演出、パーカッションの軽快な響きに次第にイメージは一変して行く。
非常に距離が縮まり観客席と一体化した舞台の盛り上がり、そして強いメッセージに混ぜ込んだ皮肉なMCも痛快だ。
多種多様なミュージシャン達も魅力的で、特にコーラスとダンスで盛り上げる金髪の方が気になる。
グレーに際立つ真っ赤な口紅、目を惹くダンスに目が離せなくなるも、パーカッション勢の登場にも圧倒される。
もちろん打楽器の響きだから、リアルに体感するのが良いに決まっているが、映画でも十分に臨場感に満たされた。
自分史上最高に感動を覚えたコンサート映画
デビッドバーンすごいのね?見事なショウ!
日本にいながら海外のショウを観られるのは
大変ありがたいことです。
大画面で大音量で。
(そりゃ、現地で観られたら最高だけど)
とにかく、素晴らしかった。
トーキング・ヘッズもデヴィッド・バーンも
マトモに聴いてこなかった僕としては、
本作品をどこまで楽しめるか?は不安でした。
THE 杞憂 。関係ないっす。
めちゃくちゃ楽しかった。
この構成やステージングはデヴィッド・バーンが
考えたものでしょうかね?
本人が言ってたからきっとそうなのだと思い
ますが、まぁよくぞ考えましたね。
これを機会に「ストップ・メイキング・センス」の
動画をちょっと観てみました。なるほど、そうか。
そもそもアーティスティックなライブを
やる方なんですね。
さらにそこに「魅て楽しむ」をさらに強力にして
一貫した統一感を打ち出したものですよね、
このショウは。
しつこいようですみませんが、素晴らしい!
最近じゃ聞かなくなった「トータルアルバム」、
一つのテーマで統一されたアルバム。
ショーの元となってるアルバムは未聴ですが、
まさにこのショウはそれであると思います。
>これでいいんだっけ?
>これはおかしくないか?
>動かなくては!
なんとまぁメッセージが強いです。
スパイク・リー監督ということもあり、
スタイリッシュにえぐってきますよ。
ただメッセージソングが並んでいるって
いうことではありません。ショウとしての
曲構成は見事かつライブとしての
高揚感も十分にある形になってます。
さらにステージングの演出も一役買います。
観たことがある方は思うのではないでしょうか?
マーチングバンドみたいなんです。
<オレンジの悪魔 京都橘高校吹奏楽部>を
初めて観たときのワクワクにも似た高揚感で
満たされ、その素晴らしいパフォーマンスと演奏に
心奪われます。かっこいい、かっこいい!!!
楽曲の素晴らしさは言うに及ばず。
パフォーマー達の練り上げられた技量、
綿密に計算された演出が・・・つまり人間達の力が、
人種も出身もジェンダーも関係なく集まった
人間達の力や想いが結実したからこそ
派手は仕掛けも装飾も一切削ぎ落とした
ミニマルでシンプルなステージをめちゃくちゃ
豊かで至福な空間にしてくれるのです。
シンプルなのに幸せな時間を与えてくれる
このステージは現代社会のアンチテーゼなのかも
しれません。物質社会、無限の欲求社会への。
また、個の力をどうか肯定してほしいという
メッセージなのかもしれません。
できるよー!僕たちはできるんだよー!って。
と思ったことをぐちゃぐちゃ書きましたが
あれこれ考えずに楽しむべきです、本作品。
この不思議なステージングの魅力を余すところなく
映像化したスパイク・リーの手腕も見事です。
素晴らしいライヴパフォーマンス映画です。
必見!!!傑作です!!!
タイトルなし(ネタバレ)
2018年発表の、元トーキング・ヘッズのデイヴィッド・バーンによるアルバム『アメリカン・ユートピア』。
バーンはツアー後に、本アルバムをもとにしてブロードウェイ・ショウを行った。
シンプルな舞台。
「HERE」から始まる。
歌詞は、物事を理解するのは脳のここだ・・・
といったところからはじまるショウの様子をスパイク・リーが捉えたもの。
デイヴィッド・バーン(トーキング・ヘッズ)のステージを記録した映画といえば『ストップ・メイキング・センス』を思い出します。
それほどトーキング・ヘッズのことを知っていたわけではないが、観た当時、「カッコイイ」という言葉しか思いつかないほどのカッコよさだった。
あちらの監督はジュナサン・デミ。
『羊たちの沈黙』でアカデミー賞を取る前の作品だ。
あの作品はデミ的とでもいうのか、どちらかというと長めのワンショットでの撮影が多かったように思います。
対して、本作のスパイク・リーは、かなりの数のカメラを使って、細かくカットを割っていきます。
舞台のショウを捉えるのに、細かいカットはあまり好きじゃないなぁ・・・と思っているのも束の間、舞台を真上からの垂直俯瞰ショットが登場し、デイヴィッド・バーンのシンメトリカルな舞台構成、様式美のようなものが映し出され、なるほど、こういう舞台構成か、と見とれていきます。
そういえば、トーキング・ヘッズ時代のビッグスーツも様式美だったなぁ。
メンバー構成はパーカッションが中心で、それにキーボードとベースなどのギター類。
総勢十数名ほどでしょうか。
彼らはみな、楽器類を携えて、ほぼ裸足(バレリーナが履くトゥシューズのようなものを履いているメンバーもいたが)。
楽器にはコード類がない。
コード類がないことで、バンドメンバーは鼓笛隊のように自由に舞台を行き来することが出来、それゆえにダイナミックな舞台が構成されています。
楽曲は、米国の悲惨な現状を歌いながらも、それでも希望、変化はあるはず・・・と信じたくなるもので、楽曲にある種のストーリーを感じることが出来ます。
そういう意味では、リベラルな中年以上の白人向きなショウかもしれず、実際、客席の観客もそういった階層のひとびとが多かったように感じられました。
ここが実際にはいちばんの問題で、デイヴィッド・バーンが歌っている内容を届けたいひとびとは、バーンの歌を聴く余裕がないのかもしれないし、趣味嗜好が違うのかもしれません。
ま、それはそれ、「とにかくカッコイイとは、こういうことさ」ということを改めて認識した次第。
それにしてもデイヴィッド・バーン、どうみてもテレンス・スタンプにそっくりなんだけどなぁ。
世界を変えるために踊れ
究極の「バーン様式」完成
帰りはチャリンコで
ショーも後半、ジャネール・モネイの曲を披露する中で犠牲になった黒人の人々が映し出される演出描写、ここにスパイク・リーが関わる意味があったのかと。
デビッド・バーンの14年振りになるアルバム「AMERICANUTOPIA」を原案に"TalkingHeads"の曲を含めた様々な国籍を持つメンバーを従え、六十も後半とは思えないデビッド・バーンの素晴らしいショーを堪能出来る。
シュールでコミカルにも思える演出やダンス、合間に入るデビッド・バーンの小話など知らない曲でも飽きさせない舞台演出は映像としても映える、舞台監督の手腕かスパイク・リーの成せる技か?
社会問題を提起したショーである事は後半に連れて強くなり、さすがに「PsychoKiller」をやる雰囲気ではないか!?
TEDトーク調で始まり、祝祭的空間で宗教を感じて、最後やっぱりスパイク・リーだったのだと思う。
先入観、予備知識なしに見た。ライブそのものを、(おそらく全編)テンポよく、小気味良いカメラワークで魅せてくれる。シンプルな歌詞も字幕で確認できるので、ある意味日本の映画館で見られることの幸せを感じた。
今日的なポリティカルなメッセージあり(アメリカの田舎の方では大統領選挙の投票率が20%って、しかも平均年齢57歳って、不都合な真実だよね)、一方でデヴィット・バーンがネトフリのドラマに出てきそうな現代的新興宗教のクールな教祖に見えないこともなかった。
ともあれ、コロナ以前にこの密な空間をフィルムにできたのは本当にラッキーだったと思う。
ラストでやっとお外に出れて、NYの街に行きたくなるけど、そういえば多様性のある面々を集めたと紹介していたバンドメンバーにインド系もアジア系も一人もいなかったなあと思った。
【不完全で窮屈だけど、希望のある僕達の世界】
デイヴィッド・バーンや、トーキング・ヘッズのファンじゃなくても楽しめる圧巻のステージ。
これを映画として残そうと考えた、スパイク・リーにも拍手を送りたい。
トーキング・ヘッズが解散してから30年ぐらい経過すると思うが、まあ、インテリ感あふれる風貌を嫌う人もいるスノッブなバンドだった。
トーキング・ヘッズの音楽はずっと変化しっぱなしだったが、メンバーの方向性の違いが鮮明になり、僕の好きなヴィム・ヴェンダースの作品「夢の涯てまでも」に楽曲を提供して解散したことで、更に強烈に僕の記憶に残っている。
今回のステージは、メッセージ性が強い。
脳の神経細胞が成長するに従い減少していくのは、人間が大人になるとバカになってしまうということなのかというテーゼからスタートし、多くの楽曲を通じて、多様性の重要性や既成概念からの脱却の可能性を示唆し、余計なものを削ぎ落し、僕達は成長しているのだという方向性を、つまり、それがアメリカン・ユートピアではないかというメッセージに繋がっているように感じる。
人種や国籍、ジェンダーが異なる世界中から集まった多様なメンバー(多様性)。
そして、固定されず、ひとところに止まることのない楽器をもったままで歌い動くメンバー(既成概念からの脱却)。
目指すものはアメリカン・ユートピア。
僕達の住むこの世界は、実は、不完全で窮屈だけど希望のある世界なのだ。
それが、タイトルロゴの逆さになっているUTOPIAの文字に示されているのではないのか。
だから、これをひっくり返したら良いのではないのか。
選挙、投票率の話が出てくるが、アメリカでは、昨年の大統領選の後も、有色人種有権者(特に黒人有権者)の選挙登録をしにくくする試みが共和党の右派から行われている。
それが、最後のメッセージにもなっている......が、
それにしても、やっぱり、なんといっても、音楽とステージが素晴らしいのだ。
いつまでも若いし、成熟している。
デイヴィッド・バーンはトーキング・ヘッズやソロのアルバムを何枚か聴いた程度で、それほど強く好きだったわけでもないのだけれど、本当にセンスのある人だと思う。この映画はデイヴィッド・バーンによるブロードウェイのショーを、スパイク・リーが監督を務め映画化したものだが、69歳のデイヴィッド・バーンはすっかり白髪になっているけれど、声も若々しいし、舞台のパフォーマンスが活き活きとしている。コードやケーブルを舞台上から排除し、ワイヤレスの状態で、様々な国籍を持つ11人のミュージシャンやダンサーとともに、バーンは舞台上を縦横無尽に動き回り、様々な詩的な言葉を歌に盛り込んでいる。この言葉の一つ一つにセンスと熱量があり、同時に、彼の音楽同様、微妙な外し方の技法に満ちている。セットや衣装は地味なのに、11人のミュージシャンは縦横無尽な動き方に終始圧倒される。最後にかかったTalking Heads時代の名曲、”Road to Nowhere”は観客に混じっての演奏だったし、素晴らしかった。80年代に聴いていた頃の音楽とはまた違った、「成熟」を感じさせるものがある。じっと座って映画を観ていられる状態ではなく、体が自然とリズムをとってしまう映画。ジャネール・モネイのプロテストソング「Hell You Talmbout」でBLMを訴えたのも、厭味のない演出でよかったと思う。老若男女を問わず、是非多くの方に映画館で観てもらたいなと思った。
映画としては期待してなかったけど、最高の映画だった!
舞台的なコンサートを撮影した、よくある何かを映画というフォーマットにしたもの。だから、それほど期待せず、スパイク・リーだしデビッド・バーンだから見ておくか、という半端な気持ちで観賞。
出だしの音響に、少し期待が─。シンプルな美術・衣装、シンプルなマテリアル、シンプルな照明─、それらが自由自在に絡み合い、単純ならざる見事な演出に昇華。
これまで見たコンサート映画で自分史上最も感動した作品でした。
音楽的にも派手ではないし、決して斬新でも新しくもない。昔の音楽満載の半ば回顧的な様相も─。しかし、歌の構成、動きの構成、光の演出等々、様々な要素が緻密に計算しつくされていて(←勝手な妄想)一見シンプルで自由な舞台が、終わってみると、まさにユートピアという名の小宇宙と化していた。
トーキングヘッズをよく知っていればしびれるだろうなーという浅はかな思い、終いにはこれは普遍的なメッセージだと思うまでに─。
映像も素晴らしくて、会場全体の臨場感とともに、舞台上を(はたまたその裏側までも)詳細に切り取ってくれて、これは会場にいる以上の楽しみを味わえているのではと本気で思ったほど。
音響も終始素晴らしかったし、このレベルだから録音疑惑が生まれるのだろうという納得感。
これから音源を探ろう。恐らくBlu-rayは買っちゃいます。
デビッド・バーン好きなら満点になる
デビッド・バーンといえばトーキング・ヘッズだが、実はあまり聴いてきたバンドではない。ポップなのだが若干アーティスティックか感じがして馴染めなかったのだ。評論家や通が好む音楽という印象。
それでもこの映画を観ようと思ったのは予告編がよかったから。実際にブロードウェイで上演していた作品を映画にしたものなのにミュージカルというよりデビッド・バーンのライブに近い。でも普通のライブとはかなり異なる。
バンド?のメンバーは立ち位置が決まっていないし、マーチングバンドのようにフォーメーションを変えながら踊ったりするし、演奏する楽器はコードに繋がれていないし、ストーリーがあるわけではないのに流れがあったりするし。
デビッド・バーンの飄々とした感じで語るMCもジョークを交えながらきっちりメッセージを含んだものだったりする。そりゃスパイク・リーが監督するわな。
で、演奏する曲もトーキング・ヘッズ好きでない自分でも知ってる曲がちらほら。聴いたことあるなーと思い、後で調べたらBPA(ファットボーイスリムのノーマン・クックが作ったバンド)の曲だったりして。デビッド・バーンのボーカルもとてもよかった。こりゃトーキング・ヘッズやデビッド・バーン好きなら満点をつける映画だ。
全126件中、101~120件目を表示