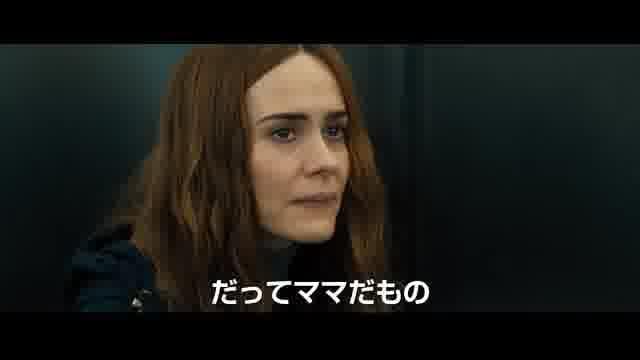RUN ランのレビュー・感想・評価
全190件中、1~20件目を表示
毒親はありのままでホラーになる
「search」の、ネット上の画面だけで展開される斬新な趣向が印象的だったチャガンティ監督。
前作のような奇をてらった制限付きの描写ではないものの、ネットを使えない、主人公は足が不自由という縛りあり。序盤は恐怖のボルテージ弱めだが、加速度的にサイコ指数が上がっていき、あの手この手でほぼラストまで緊張感を途切れさせない。
端的に言えば代理ミュンヒハウゼン症候群の母親の話だが、心理描写を見ていると、母ダイアンの恐ろしい行動とクロエの逃げ惑う姿がいわゆる「毒親」とその子供の心理の暗喩のように見えてくる。
ダイアンは、大学受験をしたクロエの家庭学習の段取りを指導しているところから、元々頭の良い女性のようだ。田舎の生活リズムにいらつきを見せる様子があり、かつては都会で生活していたのはと想像した。
出産にまつわる不幸な体験を機に、そんな彼女の心の歯車が狂い始めた。「自分がいないと生きていけない状態(とダイアンは思っている)の娘をかいがいしく世話する母親」という立ち位置に、自分の存在価値、女性としての尊厳のよりどころを全て委ねた。だからダイアンにとって、娘の自立は自我の崩壊に等しく、あってはならないことなのだ。
17歳まで母親を疑わずに育ったクロエは、毒親に心を支配された子供の象徴のようだ。序盤の、大学からの手紙を開封しないよう母親に釘を刺すくだりなどで、普段から母親の細かい管理があることを伺わせる。母親の行為が自分に害をなすものだと気付いても、そう簡単には逃げ出せない。クロエの場合は身体能力的なハードルが高いという設定だが、彼女の不自由な足は、毒親にはめられた心理的枷を暗示するもののようにも見えた。
ダイアンの異常性が徐々に明らかになってゆく展開は、あらかじめ予告などで分かっていることだ。話の運び方に細かい突っ込みどころもある(そもそも何故大学受験自体は許したのかとか)。
しかしそれでも、どこか生々しい緊張感と恐怖に晒されるのは、それが以前見聞きした代理ミュンヒハウゼン症候群の実例や、我が子を虐待した親のニュースに感じた恐怖と同じベクトルのもので、そのことがリアリティを補完しているのだろう。
日本でも、母親が健康な娘に抗てんかん剤を飲ませたとか、水中毒にさせた、腐敗した飲み物を点滴に入れたといった例がある。意外と誇張のない映画なのではという気さえした。
ラストは賛否が分かれそうだ。私は後味が悪くなって嫌だった。本当の意味でクロエが解放されたことにならないのでは、というモヤモヤ感が残った。いっそ終盤の急展開したところでばっさり終わって、結局どうなったかさえ分からずじまい、のパターンの方が好みに近い。
ただ、そもそも後味の悪い終わり方を狙った作りなので、監督の思う壺、という意味ではこれでいいのかも知れない。子が毒親の虐待と真に縁を切るのはこれほどに難しいということか。
極限状態の中に研ぎ澄まされたサスペンスの魅力が光る
チャガンティ監督の前作「search」で革命的なサスペンス構築力と新時代の映像文法に酔いしれた自分にとって、次なる「RUN」はことのほか意表をついた作品に思えた。きっと一般的な監督ならば最初に「RUN」のような作品で自らのシンプルながら強靭な感覚や才能を世に知らしめつつ、次の段階へ向かうのだろう。だがチャガンティの場合、第一歩で想像もつかない次元に足跡を残し、二歩目で極めてオーソドックスなところに着地した。よく言われるようにヒッチコックをはじめとする伝統的なサスペンスの語り口に則しつつ、それでいて主人公が受け身ではなく能動的に呪縛から解放されたいと願うとき、破格の意志の力が放出される。と同時に、行動の制約、視点の制限という意味では前作を踏襲する部分もあり、物語と状況がよりナチュラルに馴染んでいる進化ぶりが伺えたりも。できれば前情報をいっさい入れず、ニュートラルな視点で楽しみたい作品である。
ヒッチコック、スティーヴン・キングを継ぐサスペンスの語り手
2018年の「search サーチ」で鮮烈な長編監督デビューを果たしたアニーシュ・チャガンティによる第2作。前作はPCやスマホの画面上だけでドラマが進行するという映像スタイルが大いに注目を集めたが、ストーリー自体の面白さがあったからこそ映画もヒットした。そんなチャガンティ監督が、今回は映像的ギミックに頼らず、オーソドックスなストーリーテリングに徹して上質のサスペンスを楽しませてくれる。
冒頭、ダイアン(サラ・ポールソン)が病院で未熟児の娘を出産。画面が暗転して、テキストで不整脈、ぜんそく、糖尿病などの病状が順に説明される。最後の項目の麻痺では、「筋肉機能の不全により、体を動かせなくなる。走ることができない」と記される(英文のテキストでは文末の"run."だけが残って他が消え、これがタイトル表示にもなっている)。
これらの症例は、ダイアンの出産から17年後、現在のクロエ(キーラ・アレン)が抱える病状であることが、開始5分過ぎあたりでクロエの視点に切り替わってから明らかになる。クロエは車椅子生活を余儀なくされているが、ホームスクールの教師でもあるダイアンの指導により高校生レベルの学力を身につけ、受験した地元大学からの合格通知を心待ちにしている。
一見、生まれつき多くの病気と障害を抱えながらも明るく前向きに生きる十代の娘と、そんな娘の生活を献身的に支える愛情に満ちた母の美しい親子関係のようだ。だが、母親がキッチンに買い物袋を置いて離れたすきに、クロエが袋の中から見慣れない錠剤を見つけたことで、彼女の中にダイアンに対する疑念が芽生え、それが次第に大きくなっていく。
殺人犯や精神異常者といった映画の悪役に狙われる主人公に身体的なハンディキャップを持たせることは、サスペンスを盛り上げる手法としてたびたび使われてきた。ヒッチコックの「裏窓」(54)や英国の傑作サスペンス「恐怖」(61)などの主人公は本作同様車椅子を使っていたし、オードリー・ヘプバーン主演の「暗くなるまで待って」(67)以降は、盲目のヒロインが命を狙われるサスペンスも何本か作られた。
歪んだ愛情、監禁、身体的ダメージという要素でチャガンティ監督が手本にしたのは、スティーヴン・キング原作、ロブ・ライナー監督の「ミザリー」だ。クロエが緑のカプセル薬のことを尋ねた薬剤師の名前はキャシー・ベイツ。「ミザリー」の主演女優の名を拝借し、オマージュを表している。
さて、以降は本格的なネタバレになることをあらかじめ申し上げておく。
おそらく他のレビューで“毒親”や「代理ミュンヒハウゼン症候群」(これに代わる「他者に負わせる作為症=FDIA」という症名が近年米国などで推奨されている)という用語を目にすることも多いだろうが、微妙にずれている気がする。鑑賞済みの方ならおわかりのように、クロエはダイアンの実の娘ではない。真の娘は出生後すぐに死亡し、ダイアンが同じ産院にいた他人の乳児を誘拐して育ててきた。幼少期は健常者だったクロエは、ダイアンが与えてきた薬物によって下肢の麻痺をはじめとするさまざまな障害を持つようになった。FDIAの主な動機は、他人からの注目や評価、経済的な利得だという。これらもダイアンには当てはまらない。
ダイアンとクロエの歪んだ危険な関係の本質は、端的に言えば、虐待の連鎖だ。他人の子を誘拐したこと自体は、出産直後に娘を亡くした悲しみと喪失感を埋める代償行動だったろう。しかし我が子として育てていくうち、クロエが健常のまま大きくなったら、いずれ自立して手の届かないところへ行ってしまうことに気づく。それを防ぐには、クロエの体を薬物で弱らせて、庇護する親と庇護される娘の関係を永続させればいい。
ダイアンがシャワーを浴びるシーンで、背中に古い切り傷があった。また、YouTubeで視聴可能な削除されたシーンでは、ダイアンが7歳の時に目の前で母親が自殺したこと、母親もまたダイアンを虐待していたことが新聞記事で明かされる。つまり、ダイアンの背中の傷は幼少期に母親からつけられたもの。ダイアンがクロエをいつまでも手元に置いておきたいのは、虐待する対象を欲しているからだ。
そう考えると、ラストの30秒は、クロエの単なる復讐ではない可能性が高くなる。クロエもまた、虐待する対象を欲しているのだとしたら。いつかダイアンに薬を飲ませることができなくなったとき、その矛先は我が子に向かうのではないか――そんな恐ろしい未来を予感させる。虐待の連鎖はどこまでも続く。
人間が一番怖い
何も疑わずに母の言うままに薬を飲み続けてきた女の子がちょっとしたことから母親を疑い始める。
まさか母親が誘拐犯だったとは思わなかったから、怖かったです。
あと夜中に実は監視してた母親もめっちゃ怖がった。でも安っぽい、ジャンプスケア系ではないから落ち着いてみれるのか良かった。
歪んだ愛情はどこからきたのかとかまで知れたら良かったな、とは思います。
あとは娘がちゃんとrevenge を果たしていたのも怖かった…
面白かった!
けど、やっぱり人間が一番怖い。
この『物語』は 彼女が歩き出す物語だ。 〈肉体の檻〉という極限の制限下での戦いを見届けよっ!💉♿️
制限された環境で展開されるサイコスリラー『サーチ』シリーズの第2作。
生まれながらにして糖尿病や喘息など、複数の持病を患っており、下半身麻痺により車椅子で生活する少女クロエ。母ダイアンはそんな彼女を献身的にサポートしていた。
しかしある日、クロエは母親から手渡された薬に違和感を覚える。その薬が何なのか調べるうち、ある恐ろしい事実が浮上する…。
監督/脚本はアニーシュ・チャガンティ。
公開当時、映画評論家の町山智浩さんがラジオで紹介していて興味を持った作品。……おまっっ!ラジオで全部ネタバラししちゃってるじゃねーかこの野郎っ😡😡😡
…まぁそれは置いといて。
20代で監督した初長編映画『search/サーチ』(2018)が興行面/批評面で大成功を収め、時代を代表する映画人となったチャガンティの長編2作目。どうやら『サーチ』と世界観を共有しているらしいのだが、彼の前作を未鑑賞のため何処がどう繋がっているのかはわからず。本作は単体の映画として完全に成立しているので、そこはあまり気にしなくても良いのかも。まぁ機会があったら『サーチ』の方も鑑賞してみます。
内容としては、歪んだ愛情が狂気として顕現する『ミザリー』(1990)的なサイコパスもの。肉親が子供に襲い掛かるという意味では『シャイニング』(1980)にも近しいが、要するにスティーヴン・キングの流れを汲む正統派にして王道のスリラー映画に仕上がっている。
見どころはやはり主人公クロエの頑張り。車椅子かつ呼吸器系と心臓に持病を持っているという、肉体的制限がガンガンに掛けられている彼女が、如何にして文字通りの“毒親“から逃げる(Run)のか、この一点突破で本作は押し進む。清々しいまでに単純な映画なのだが、「病人」という持たざるものの象徴の様な主人公が己の頭脳と技術と体力を最大限まで活用して戦いに挑む、その姿勢は激アツ。絶望的な状況であるにも拘らず泣き言も言わずに即断即決で行動してゆく彼女は、どんな肉体派ヒーローよりもワイルドである。
クロエを演じるキーラ・アレンは本作が映画初出演の新人女優だが、そうとは感じさせない迫真の演技は見事👏実際に車椅子ユーザーである彼女だからこそ、クロエというキャラクターにリアリティが宿ったのであろう。
アレンさんは本作以降目立った活躍はない様なのだが、もっとバンバン映画に出演させるべき逸材だと思う。こういう役者に活躍の場を与えてこそのDEIだろハリウッドさんよぉ〜〜。
本作が面白いのは、普通のスリラー映画とはキラー側の勝利条件が違うという点。ダイアンの勝利条件はクロエを生かして捕える事であり、彼女の死はダイアンにとって最大の敗北条件となる。チャガンティはキラーがサバイバーを殺せば勝ちという、従来の「Dead by Daylight」(2016-)方式を逆転させる事で、絶対に逆転不可能に見える状況からの大どんでん返しを可能にしてみせた。命を捨てて命を拾う。クロエの機転とクソ度胸はほとんど「ジョジョ」の領域。チャガンティ!きさま!(ジョジョを)見ているなッ!
冷静に考えれば、お母ちゃんの監禁はかなりゆるい。『ルーム』(2015)くらいガチガチの環境に閉じ込めてしまえばそれでゲームセットだった訳だが、そこは親心が働いたと解釈する事にしましょ。
また、本物のクロエの死亡診断書とかクロエがまだ歩けた頃の写真をなぜあんな風に丁寧に保管していたのかも謎っちゃ謎。いや、それらは思い出の品として手元に残しておきたかったという気持ちもわからんでもないのだが、誘拐事件の新聞切り抜きまでセットでとっておく必要はねーだろっ!!まぁそのおかげで話がテンポ良く展開したんだけどね。
90分という短いランタイムできっちりと恐怖と勇気を描き切った、現代サイコスリラーのメルクマール的傑作!指の一本、あるいは足の先が少しでも動かせれば、勝負はまだわからないのだ!!
本作公開時、まだ監督は30歳かそこら。その若さでこんなん作られたら、同時代のホラー監督たちはたまったもんじゃないぞ💦スピルバーグが『JAWS/ジョーズ』(1975)を作ったのが27歳の時。チャガンティも順調にキャリアを歩めば、スピルバーグクラスの大監督になれるかも…?
『Search/サーチ』監督の新作ということで鑑賞。 下手なホラー...
母と娘の関係に潜む歪んだ愛情を描いたサイコスリラー。
毒親を通り越した母にドン引き
母親にも事情が、ということを差し引いても、「こいつ頭おかしい…」「そこまでやるのか…」とドン引きしてしまう毒親からの逃亡。
犬の薬を飲ませてまで手元に娘を置きたい毒母親だが、二言目にはあなたのため、と言っている姿が本当に「あ、こいつもうダメだ」と思わされる。
母親と同居している主人公だから、少しでも不審な動きを取ると勘づかれてしまうドキドキ感。何度でも追ってくる恐怖。家で電話するだけでも何度も母親の姿を確認してしまう。
下半身不随の主人公による、知恵と執念のこもった自宅逃亡劇にハラハラしてしまう、緊張感を保った良質なスリラー映画。
ーーーーーー以下ネタバレーーーーーー
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
あの配達員はやはり殺されてしまったのだろうか?シーン的にそんな描写だったが。殺人による刑罰を受けた上でのあのラストなのか。
これは怖い!!!
人間の狂気という最長不倒
もしかすれば見るのは2度目だったのかもしれない。
このサイコスリラーの型は素晴らしくよくできている。
以後の多くの物語でもこの型が使われている。
しかしおそらく最初だったのはあの「ミザリー」だろう。
さて、
この作品で最も難解な部分はタイトルだろうか。
RUN
冒頭に登場するこの子は「走ることができない」とする見通しの記述
生まれて割とすぐに死んでしまった「クロエ」の先天性疾患と見通し。
走ることができないことを「RUN」という一言で表現している。
サブタイトルには「筋肉機能の全不全により体を動かすことができなくなる。走ることができない」とあったが、英語表記には「to move,feel, walk,or run.」
しかしタイトルは単にRUN
つまりタイトルはクロエに対する応援のメッセージのように感じる。
クロエは母親に閉じ込められた部屋から脱出する際に自分のつま先が動くことを発見する。
危機的状況が本来の機能を呼び戻すのかもしれない。
物語の奇妙な部分が徐々に明らかになっていく表現は、スリラーとして申し分ない。
スマホを持たせてもらえないことは、潜在的にクロエが持つ母への違和感を助長させていったのだろう。
成長と共に考え方の幅も広がりを見せることもあったのだろう。
母の名前の薬「トリゴキシン」は犬用の筋弛緩剤だった。
おそらくそれは末期がんの犬に対する安楽死用のものという設定なのだろうが、ネット検索すると犬用の鎮痛剤、抗炎症薬とある。
クロエの母に対する違和感が確信となるが、助けを呼ぶのは難しい。
配達の運転手も始末された。
自殺覚悟で飲み込んだ劇薬
この手段の設定は上手だと思った。
サイコパスの母の娘に対する歪んだ愛情こそ、彼女の原動力だからだ。
物語はその後クロエがどうなったのかは描いていないが、7年後にクロエが収監施設を訪問するシーンが描かれている。
それこそがこの作品、サイコスリラーの真骨頂なのだろう。
なんとも恐ろしい物語だ。
人間の狂気に勝る怖さはないのかもしれない。
ミザリーみたいな監禁系が好きなので面白かった
ミザリーみたいな監禁系が好きなので面白かった。薬関連で展開は予想できたけど、重すぎる母(ダイアン)の愛の話?からの...まさか誘拐ものってのは気づけなかったなぁ。ダイアンが誘拐犯だと分かってからはまた別の恐怖を感じる。
ダイアンのバックボーンが薄いのが気になる。薬で足を麻痺させてまで、(クロエ)に執着する理由が分からなかった。「あなたのためにしたこと、いずれ分かる時が来る」ってのは何だったんだ。
最後クロエと生きてたダイアンの和解エンドかと思ったら...「ママ、お薬の時間よ」笑顔のクロエの仕返し怖いねー。
母性の妄執
怖かった映画でした。
脚本がよく練られていて、集中して見れました。
アニーシュ・チャガンティ監督のファンになりました。
母親役のサラ・ポールソンはなんともならない事をどうにかしようと動き周ります。
娘役のキーラ・アレンは根性据えて自由を求めます。
その時点で勝負決まっていました。
ラストも怖いです。
舞台化できそうな映画です。
全190件中、1~20件目を表示